明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
- 協調性とは
- 協調性がある人の特徴
- 協調性でアピールできるポイント
- 協調性をアピールする際のコツ
- 自己PRで協調性をアピールしたい人
- 協調性について知りたい人
- 自己PRを作ったことがない人
- 例文を見て参考にしたい人
目次[目次を全て表示する]
協調性診断で協調性を分析しよう!
チームでの働き方や人間関係の築き方を分析。
職場での協力姿勢やリーダーシップ発揮のバランスを評価します。
【自己PRでの協調性】協調性が評価される理由
協調性は、自己PRのアピールポイントとしてとても有効です。
しかし、なぜ有効なのかをきちんと理解してアピールしなければ、効果的な自己PRにはなりません。
ここでは、協調性がある人はなぜ評価されやすいのか、その理由を解説します。
職場に早く馴染んでくれそうだから
企業が協調性の高い人物を求める理由の1つとして、「職場に早く馴染んでくれそうだから」という理由が挙げられます。
協調性がある人は、周囲とのコミュニケーションを積極的に行い、チーム内での関係構築が非常に得意です。
新入社員が他の従業員と効果的に協力し、職場の文化や流れを早く理解することは、企業にとって非常に重要です。
また、企業においては他者の意見を尊重して異なる視点を受け入れる柔軟性も求められているため、高く評価されます。
プロジェクトやタスクの進行において、多様なアイディアが必要な場面において非常に重要な要素の1つです。
また、ストレスが多い状況下でもポジティブな姿勢を保ち、チーム全体の士気を支える役割を果たすことも期待されます。
組織で貢献してくれそうだから
協調性のある人物は、組織で貢献する可能性が高いため、多くの企業から歓迎されます。
他のメンバーとの連携を効果的に行い、共同で目標に向かって作業する能力が高い人物が多いからです。
この能力は本人だけでなく、チーム全体のパフォーマンスを向上させることに直結します。
組織に貢献できる人物を1人採用するだけで、プロジェクト全体がスムーズに運ぶ可能性もあるのです。
様々な意見やスキルを統合して、それを活用して問題解決やプロジェクトの成功に役立てられる人物は、どのような企業でも求められています。
また、困難な状況においてもチームを鼓舞し、メンバー内で意見が衝突した際も最小限に抑えられる人物は、多くの社員がストレスフリーに業務を進めるにあたっても重要です。
取引先ともいい関係構築ができそうだから
協調性の高い人物は、企業内での人間関係だけでなく、取引先とも良い関係構築ができる可能性が高いです。
特に、営業職などの取引先と関わることの多い仕事において重要な要素といえます。
さらに、柔軟性を持ち合わせていることも多いため、様々な考え方を受け入れることができ、相手の意見に同調しつつ、奥深くにあるニーズをとらえることも期待できます。
取引先が何を望んでいるのか、どうすれば取引先の望みを叶えつつ、自社にとって最高の結果をもたらせるのかについて考えられる人は、多くの企業に求められています。
【自己PRでの協調性】協調性がある人の特徴
協調性の高い人は理解力にたけています。 そのため、企業が掲げる理念やビジョンをスムーズに受け入れることができ、環境や文化の変化に柔軟に対応することができます。
また、どんな場所でも自分の力を発揮できるのが特徴です。
- 柔軟性がある
- 自分の意見を押し付けない
- 相手の気持ちを考えることができる
- 洞察力がある
- 社交的で明るい
柔軟性がある
協調性がある人は自分の意見と異なっていることでも否定することなく話を聞くことができます。
自身の意見も発信することができ、相手の意見も聞くことができるためリーダーなどに向いています。
自分の意見を押し付けない
意見が対立した場合など、会議の場で人と人との間に波風が立ちやすい状況でも協調性が役立ちます。
協調性がある人は、たとえ自分の意見が正しいと思っていても、まず相手の話に耳を傾けて理解しようとする姿勢を取ることができます。
そして、相手の話を聞く中で、相手の主張を受け止めながらも自分の意見を提案することで、ケンカなどに発展してしまいそうな場面でも話をまとめられるのです。
円滑なコミュニケーションを、主体的に作り出せる能力とも言い換えられます。
相手の気持ちを考えることができる
意見が食い違ったときに、つい感情が乗ってすぐに反論してしまう人は多くいます。
しかし、協調性がある人は、まず相手の考えていることやその結論に至った経緯を聞き出すなど、話を前に進めるための行動を取ります。
すぐさま行動に移せなくても、相手がなぜ自分とは異なる意見を主張するのか、背景を考え理解しようとする姿勢を示せるので、相手も落ち着いて会話ができますし、無駄な言い争いを避けて意見をまとめていけるのです。
洞察力がある
周囲の人の気持ちや考えを敏感に察知し、適切な対応を取ることができます。
たとえば、相手の表情や言葉の選び方から本音を読み取り、「この人はこういう言い方が合う」「こういう状況は苦手かもしれない」といったことを自然に考えます。
そのため、相手が無理をしていないか、あるいは困っているかを素早く察知し、フォローすることができるのです。
こうした細かな気配りができることが、協調性が高い人の大きな特徴の一つです。
社交的で明るい
周囲の雰囲気を大切にし、明るく前向きな態度で人と接することもできます。
そのため、初対面の人とも打ち解けやすく、周囲との関係を円滑に築くことができる傾向があります。
また、周囲の人と協力して物事を進めることを重視するので、自然と場の空気を和ませるような言動を取ることが多くなります。
たとえば、困っている人を気遣う一言をかけたり、会話の流れを良くする話題を提供したりするなど、周囲が快適に過ごせるよう工夫します。
【自己PRでの協調性】企業が求める協調性
採用担当者が評価する「協調性」とはどんなものか、その特徴を理解し、それに沿った自己PRを作成することが大切です。
採用担当の理想に沿ってアピールするためには、志望企業の求める人物像をしっかり把握しておきましょう。
チームワークの向上が期待できる
企業が協調性を求める理由の一つは、チームワークの向上が期待できるからです。
協調性がある人は、周囲のメンバーと円滑に連携し、チーム全体のパフォーマンスを引き上げることができます。
他のメンバーの意見を尊重しながら、自分の考えを的確に伝えることで、より良いアイデアや解決策を導き出すことが可能です。
また、協調性がある人は、困難な状況でも冷静に対応し、チームの士気を高める役割を果たします。
自己PRでこの特徴をアピールする際には、具体的なエピソードを通じて、チームの一員としてどのように貢献したかを示しましょう。
コミュニケーションの円滑化が図れる
協調性がある人は、コミュニケーションの円滑化が図れる点においても企業にとって重要です。
効果的なコミュニケーションは、誤解やトラブルを防ぎ、業務をスムーズに進行させるために不可欠です。
協調性がある人は、他者の意見や感情を理解し、それを踏まえた上で自分の意見を伝えることができます。
これにより、チーム内外の関係者との良好なコミュニケーションが実現し、組織全体の効率を向上させることができます。
自己PRでは、具体的な場面を挙げて、どのように円滑なコミュニケーションを実現したかを示すと良いでしょう。
取引先との関係構築ができる
協調性がある人は、取引先との関係構築が得意である点も企業にとって大きな魅力です。
ビジネスにおいては、社内だけでなく社外の関係者とも良好な関係を築くことが成功の鍵となります。
協調性がある人は、取引先のニーズや要望を的確に把握し、信頼関係を築くためのコミュニケーションを取ることができます。
このスキルは、長期的な取引関係の維持や、新たなビジネスチャンスに直結します。
自己PRでは、取引先との関係構築に関する具体的なエピソードを述べると効果的です。
【自己PRでの協調性】協調性をアピールする際のポイント
就活で協調性をアピールする際のコツにはどのようなものがあるでしょうか?
以下の点に注意することで、より効果的に協調性をアピールすることができます。
下記のコツを掴み、より良い印象を与えることができる協調性の自己PRを完成させましょう。
具体的なエピソードを選ぶ
協調性をアピールする際には、具体的なエピソードを選ぶことが重要です。
曖昧な表現や抽象的な話ではなく、実際に経験した出来事を基に話を組み立てましょう。
例えば、ゼミでの経験や部活動、アルバイトなどで他のメンバーと協力して達成した成果について述べると効果的です。
この際、エピソードはできるだけ詳細に説明し、聞き手がその場面をイメージしやすいようにすることがポイントです。
行動と結果を明確にする
エピソードを選んだら、その中で自分がどのような行動を取ったのかを具体的に述べましょう。
単に「協力しました」ではなく、「どのような役割を担い、どのように他のメンバーと協力したのか」を明確にすることが大切です。
さらに、その行動の結果としてどのような成果が得られたのかも説明しましょう。
例えば、「意見が対立していたメンバー間の調整役を務め、プロジェクトを期限内に成功させた」といった課題からの具体的な結果を示すと、協調性の効果がより伝わります。
学んだことをアピールする
最後に、その経験を通じて自分が何を学んだのかをアピールしましょう。
単に成功体験を語るだけでなく、その経験から得た教訓やスキルについて述べることが重要です。
例えば、「異なる意見をまとめることで、コミュニケーションスキルが向上した」「チーム全体の目標を意識することで、リーダーシップの重要性を学んだ」など、自分の成長につながった具体的な学びを伝えます。
このように、経験を通じて自分がどのように成長したかを強調することで、協調性を持つ人材としての魅力が増します。
どのように活かしていくかを述べる
協調性をアピールする際には、過去の経験や学びだけでなく、強みである協調性を活かして、今後どのように業務に活かしていくかを述べることが重要になります。
企業は、営利団体であるため、活躍してくれる人間を採用したいと考えています。
企業に貢献できる人物であることをアピールしましょう。
【自己PRでの協調性】就活で協調性をアピールする際の注意点
ここからは協調性を自己PRで使用する際の注意すべき点を解説します。
以下の点を意識するだけでも企業からマイナスの評価をつけられる可能性は低くなるので、是非チェックしておきましょう。
受け身な人と思われないように
協調性を強調しすぎると、主体性がないと判断される可能性があります。
特に「意見を言わずに周囲に合わせるだけ」という印象を与えると、社会人としての積極性が欠けていると思われかねません。
そのため、単に周囲と調和するのではなく、チームの一員として意見を述べ、建設的な議論に貢献できる姿勢をアピールすることが大切です。
「相手の考えを尊重しながら自分の意見を伝える力」を示せるエピソードを選び、協調性と主体性のバランスを意識しましょう。
優柔不断なイメージを与えないように
協調性を使用した自己PRは、面接官によっては「決断力がない」「周囲に流されやすい」と捉えられることがあります。
なので、エピソードの中で、周囲を思いやりながらも自ら考え、行動し、決断した経験を盛り込みましょう。
例えば、「異なる意見をまとめて最善の選択を導いた経験」や「チームのために自ら動いたエピソード」を交えることで、協調性と同時に決断力や主体性も伝えられます。
【自己PRでの協調性】協調性が長所の就活生と差別化するコツ
他の人と、自己PRでの協調性を差別化するためにはどのような方法をとると良いでしょうか?下記のポイントを抑えることで差別化を図った自己PRの作成を行いましょう。
独自のエピソードを掘り起こす
他の人と差別化するためには、独自のエピソードをアピールすることが重要になります。
多くの就活生が協調性をアピールする中で、一般的なエピソードでは埋もれてしまう可能性があります。
自分だけの特別な経験や、ユニークな状況での協調性の発揮を具体的に述べることで、印象に残る自己PRができます。
他の人があまり経験していないようなエピソードを探しましょう。
また、困難な状況を乗り越えた経験や、協力したことでチームに貢献したエピソードを振り返ってみましょう。
自己分析を深める
協調性を効果的にアピールするためには、自己分析が欠かせません。
自分がどのような状況で協調性を発揮できるのか、どのような強みがあるのかを理解することで、具体的かつ説得力のある自己PRを作成できます。
自己分析の方法としては、自分の過去の経験を振り返り、協調性を発揮した場面を洗い出すことが有効です。
また、他人からのフィードバックを参考にすることも重要です。
友人や同僚から見た自分の強みや協調性の特徴を聞き、自分自身では気づかなかった視点を取り入れましょう。
これにより、より深い自己理解が得られ、他の人とは一線を画す自己PRが可能になります。
具体的な成果を示す
協調性をアピールする際には、具体的な成果を示すことが大切です。
単に「協調性がある」と言うだけではなく、その協調性が実際にどのような成果をもたらしたのかを具体的に説明することで、信憑性と説得力が増します。
例えば、プロジェクトでの協調性がチーム全体の目標達成にどう寄与したのか、売上や顧客満足度の向上にどのように貢献したのかといった具体的な数字や結果を挙げると効果的です。
また、チームの雰囲気が改善されたり、困難な状況を乗り越えたりした経験を詳細に述べることも有効です。
これにより、あなたの協調性が実際に役立つスキルであることを強くアピールできます。
「主体性」も併せてアピールする
協調性をアピールする際、他の就活生と差別化するためには「主体性」も併せて強調することがおすすめです。
「協調性があります」アピールするだけでは、ただ周囲に合わせるだけの受け身な印象を与え、主体的に行動する力が不足しているように見られてしまうことすらあります。
そのため、協調性を発揮しながらも、自ら積極的に行動したり、課題に対して主体的な提案を行ったりした具体例を加えることで、他の就活生との差別化をしましょう。
例えば、目標達成のために自ら進んで役割を引き受けたり、チーム全体の利益を考えてアイディアを提案したりしたエピソードがあれば、その内容を加えることで主体性を同時にアピール可能です。
「他者に合わせるだけでなく、チームの方向性をリードできる」という印象を採用担当者に与えることができるでしょう。
「協調性」を言い換える
「協調性」という言葉は多くの就活生が使うため、採用担当者にとっては聞き慣れた表現です。
そのため、より具体的でオリジナルな言い回しに言い換えることが効果的と言えるでしょう。
例えば、「洞察力」「巻き込み力」「チームワーク」「サポート力」などの言葉を使うことで、協調性の中でも特に自分が得意とする部分を強調できます。
こうした言い換えによって、採用担当者に「この就活生は自分の強みを理解している」と感じさせることができるでしょう。
また、選んだ言葉に沿った具体的なエピソードを加えることで、より深い印象を与えることができます。
【自己PRでの協調性】協調性のおすすめの言い換え
協調性は、とても多くの就活生が自分の強みとしてアピールします。
そのため、差別化がとても大切です。
自己PRや長所を聞かれた時には、うまく言い換えて差別化することが必要です。
ここでは、協調性が強みの人はどのようにして言い換えてアピールすれば良いのかを解説します。
共感性
共感性を強調することで、相手の気持ちを理解し、相手の立場に立って考える力があることをアピールできます。
相手の気持ちに共感し、協調することができる人材は、チームワークを重宝する企業においてとても大きな強みになります。
私は常に相手の視点に立って物事を考え、チームメンバーが抱える悩みや問題を理解し、共感することができます。
その結果、チーム全体の士気を高めることに貢献してきました。
対応力
変化や予期せぬ事態に柔軟に対応できる力としてアピールします。
協調性と対応力を組み合わせて表現することで、臨機応変さを強調できます。
私は、メンバーのサポートに注力することで、チームの一体感を高めてきました。
特に、困難な状況に直面したメンバーを支え、全体のパフォーマンスを向上させることに成功しました。
私は、予想外の事態にも迅速に対応できる柔軟性を持っています。
例えば、チーム内で急なメンバー変更があった際にも、他のメンバーとのコミュニケーションを密にし、円滑な業務運営をサポートしました。
リーダーシップ
協調性を発揮しながら、リーダーシップを持ってチームを導くことができる、という人も多いのではないでしょうか。
協調性をリーダーシップと掛け合わせることで、チームメンバーに対して協調性を発揮しつつうまくまとめることができるリーダーシップがアピールできます。
私は、メンバーのサポートに注力することで、チームの一体感を高めてきました。
特に、困難な状況に直面したメンバーを支え、全体のパフォーマンスを向上させることに成功しました。
私は、チーム全員の意見を尊重し、共通の目標に向かって全員が一丸となれるようリーダーシップを発揮してきました。
結果、プロジェクトを成功に導き、メンバー全員から感謝の言葉をいただきました。
傾聴力
他者の意見や考えをしっかりと聞く力として協調性をアピールします。
傾聴力が協調性の源となっていることを伝えると、より細やかなコミュニケーション能力を示せます。
私は、相手の話に耳を傾け、真摯に意見を受け止めることを大切にしています。
これにより、チーム内での信頼関係を深め、円滑なコミュニケーションを図ることができています。
サポート力
協調性を他者を支える力としてアピールします。
過去にチームスポーツの経験がある方などは、チームの中でどのようにサポートしてきたかを具体的に伝えることで、協調性をより実践的に表現できます。
私は、メンバーのサポートに注力することで、チームの一体感を高めてきました。
特に、困難な状況に直面したメンバーを支え、全体のパフォーマンスを向上させることに成功しました。
ヒアリング力
ヒアリング力は、相手のニーズや課題を正確に把握し、それに応じた対応を行う能力を示します。
この力をアピールする際には、具体的な場面での活用事例を提示することが重要です。
例えば、顧客の要望を詳しく聞き出し、それを基に適切な提案を行った結果、成約に繋がった営業経験などは、ヒアリング力を強調する好例となります。
ヒアリング力は特に営業職や企画職で求められるスキルであり、コミュニケーション能力の高さを示すポイントとしても非常に有効です。
また、ヒアリングを通じて顧客や同僚の意見を尊重する姿勢をアピールすることで、協調性の高さも間接的に伝えられます。
臨機応変
臨機応変さをアピールすることで、予期せぬ状況や問題に対して柔軟に対応できる能力を示せます。
企業は、日々変化するビジネス環境の中で、状況に応じて最適な判断ができる人材を求めています。
この力をアピールするには、実際に困難な状況に直面し、それを解決に導いた具体的なエピソードを伝えることが効果的です。
例えば、プロジェクト進行中に発生したトラブルに冷静に対応し、代替案を提案してチームを危機から救った経験を語ることで、臨機応変な対応力を証明できます。
また、臨機応変な対応を行う際には、チーム全体の状況を考慮する必要があるため、協調性と同時にリーダーシップや判断力もアピールすることができます。
【自己PRでの協調性】エピソード別の例文12選
実際に協調性がアピールできる例文を6つ紹介します。
自分の希望する企業が求めているようなエピソードを選び、書き方を工夫する必要があります。
またエピソードは面接官から詳しく質問されることの多いポイントです。
記憶があいまいだったり例文をまねていたりしていては、信憑性を疑われてしまうこともあります。
ここでの例文はあくまでも参考程度にして、自分だけのPR文を作成しましょう。
例文①部活動
多様な意見を取り入れて、それらを1つにまとめ上げ、全員が納得するアイデアを提案できる協調力が私の強みです。
私は大学時代にサッカー部に所属しており、キャプテンを務めておりました。
そこでは、チームワークが良好と言えず、うまく点数が取れないという課題がありました。
どうすればチームワークが高まるかのアイデアを出し合った際、チームのみんなで出し合ったアイデアは、人によってさまざまでした。
主に「声出しをする」「さまざまな人とペアが組める練習を取り入れる」という、2つの意見に分かれたのです。
私は、それら2つを取り入れるために、「ペアを入れ替えながらできる練習」と「練習時にできるだけ相手の名前を呼ぶという声出し」を提案しました。
チームのみんなもそれに賛同し、監督からもチームとしての結束が高まったと評価をいただきました。
私はこの協調性を活かして、貴社でもチームの中心的な存在として活躍したいと考えております。
協調性×部活動のポイント
例文②アルバイト
私は協調性があり、どんな人ともすぐに良好な関係を構築することで、チームでのコミュニケーションを自然に促すことが得意です。
私は大学時代、コンビニエンスストアでアルバイトをしておりました。
そのアルバイト先は、私が入る前まで人間関係が良好とは言えず、各々があまりコミュニケーションを取っていない環境でした。
コミュニケーションが少ないため、業務にも支障をきたしている場面もありました。
私は仕事をスムーズに進めるためにも、まずはみんなとコミュニケーションを取り、他のアルバイトにどのように動くと楽かを聞き、全員で話し合う場を設けたのです。
全員で話し合うことで、少なかったコミュニケーションは増え、私が主体としなくとも各々でコミュニケーションを取るようになりました。
こまめなコミュニケーションにより、支障をきたしていた場面もなくなり、お客様に迷惑をかけることもなくなりました。
貴社ではこの協調性を活かして、グループの結束力を高め、大きな目標達成を目指して活躍したいと考えております。
協調性×アルバイトのポイント

監修者
ポイント
サポートタイプの協調性をアピールするためには、あなたがどのようなコミュニケーションを取り、どのような課題を解決したかを説明する必要があります。
あなたが主体でなくとも、あなたの影響で問題が改善したエピソードがあると、サポートタイプとしてのエピソードが成り立ちます。
例文③学校行事
私は傾聴力があり、チーム内で異なる意見が出たとしても、全員の納得・合意の得られる妥協点を探し出せる協調性が強みです。
大学時代、文化祭の実行委員で全体を取り仕切るリーダーを務めておりました。
文化祭の内容で委員会内の意見が分かれた際には、対立した意見のそれぞれの言い分を聞き、両者の意見が成り立つ折衷案を提案しました。
そこで、全員の納得・合意を得て、実施内容を取り決めることができたのです。
その結果、文化祭のプロジェクトの進行中も関係性がぎくしゃくせずに、無事に文化祭の成功をおさめることができました。
その後も、文化祭の実行委員だったチームメンバーのみんなとは強い結束力でつながっており、いつかまたこのチームでプロジェクトを成功させたいという夢があります。
貴社では、チームの意見をまとめ、全員の合意を得て業務に取り組めるように計らいながら、チームの関係性・意欲を高めて、利益に貢献したいと考えております。
協調性×学校行事のポイント

監修者
ポイント
リーダータイプの協調性をアピールするためには、分かれた意見から折衷案や妥協案を提案するという点が大切なポイントとなります。
また、対立していたチームの関係性を修復したという点も、伝えられると良いでしょう。
例文④ゼミ活動
思いついたことは率先して考えながらもすぐさま行動に移し、周りのメンバーを引率できるリーダーシップが私の強みです。
私は、所属しているゼミでゼミ長を担っていました。
人数の多いゼミだったこともあり、やる気のある学生とそうでない人とでゼミ内が2つにわかれている状態でした。
ゼミ全体の集まりのときに改善策を話し合ったのですが、積極的に意見を出す人がほとんどいなかったため、私自らやる気のある人とない人が混ざるようにペアを組み、研究内容の発表はペアで行うことにしようと提案しました。
この運用を続けて3ヶ月ほどで、積極的にゼミに参加していなかった人たちは研究内容を誤解していたことが原因で、学ぶ姿勢を取れなかったことが明らかになったのです。
誤解が解けた後はゼミ全体の雰囲気がよくなり、有意義な学びの時間を過ごせるようになりました。
この経験を活かし、全体の状況を見渡しながら自ら積極的に動いていけるリーダーになりたいと考えています。
協調性×ゼミ活動のポイント

監修者
ポイント
ゼミの中で全体の調和を図るだけでなく、自分が主体となって課題を解決した経験があると、話に説得力をもたせることができます。
ゼミの中で特筆すべき役割を担っていなくても、行動力を発揮したエピソードがあれば大丈夫です。
例文⑤ボランティア
初対面の人とでもすぐに打ち解け、スムーズな会話ができるコミュニケーション能力が私の強みです。
学生時代に行ったボランティアで、地域活性化プロジェクトの一貫として、昔ながらの商店街を盛り上げるイベントを運営した経験があります。
主に若者を集客し、幅広い年代層へ向けて商店街のあたたかさやその歴史を知ってもらうことを目的としたイベントでは、当日現場のリーダーを務めました。
本来であれば当日のみの役目ですが、イベントの準備期間から様々な人とコミュニケーションを取り、打ち解けておいたことで、イベント当日に起こったアクシデントにいち早く気づき、大ごとになる前に対処ができたのです。
また、当日初めて会った人ともすぐに打ち解けて情報交換を行い、無事にイベントを成功させることができました。
このように、年齢や立場を超えて様々な人と打ち解けるコミュニケーション能力は、入社後、会社の先輩や上司だけでなく、お客様との距離を縮める際に役立つと考えています。
協調性×ボランティアのポイント

監修者
ポイント
持ち前のコミュニケーション能力を活かし、ボランティア活動を通して活躍した経験は、面接官に訴えかけるものがあります。
年齢や立場などの垣根を超えて、相手から本音を引き出し理解することのできるタイプの協調性は、一言では説明しにくいのでエピソードを厳選することが大切です。
例文⑥サークル
仲のよい友達にとどまらず、いろいろな背景や考え方をもつ人の話を聞き、受け止められる傾聴力が私の強みです。
学生時代所属していたサークルは、大規模ではないものの人数は少なくないサークルで、サークル長や各リーダーたちは個性の強いサークルメンバーをまとめるのに日々奮闘していました。
その話を友人から聞いていたこともあり、普段から仲のよい友人だけではなく、いろいろな人と関わり、それぞれの人の考え方などを聞いていました。
年4回あるイベントでサークル内の派閥同士での衝突が起こった際、私は事前に得ていた個々人の考え方などを元にしながら、衝突の原因となった意見の食い違いとそれに対する各派閥の主張を受け止め、解決に導いた経験があります。
結果、イベントのリーダーやサークル長たちに感謝してもらった経験から、この傾聴力が人の役に立つと知りました。
この能力を活かし、顧客の些細な不満や商品に求めるものなどをヒアリングできる営業になりたいと考えています。
協調性×サークルのポイント

監修者
ポイント
過去に目立った成功談がなくても、傾聴力があることは、就活においては大きなポジティブポイントになります。
傾聴力を活かして、自分とはタイプの異なる人の意見も受け止めた経験があれば、自信をもって主張しましょう。
例文⑦インターン
自分は行動力のある人間です。
そして、その行動力をもって得た経験や知識を活かし、次の世代へつなげるサポートをすることが得意です。
学生時代に長期インターンに参加した経験があり、はじめは実際の仕事を体験するばかりで右も左もわからず、会社の方や同じインターン生から学ぶ機会が多くありました。
そのときに小さな失敗を多く経験したことから、新規インターン生に自分が先輩として教える立場になった際、後輩の立場に立って親身になって仕事のサポートをすることができました。
学ぶ際は、周囲から学べるものをとにかくすべて吸収したことで、後輩の気持ちに寄り添い、的確なアドバイスができたのです。
この能力を活かし、誰よりも多くのことを吸収し、次世代へつなげていく仕事がしたいと考えています。
協調性×インターンのポイント

監修者
ポイント
その場の空気を瞬時に察して、アウトプットする能力は多くのことを吸収できることのアピールにつながります。
自分が吸収したことを組織に還元できる、という訴え方以外にも、それを自分のものとし開発に活かせる、といった話のもっていき方もできます。
例文⑧友人関係
私の協調性を示す一例として、大学時代に友人との関係を築く中での経験があります。
特にサークル活動において、様々な性格や考え方を持つメンバーと一緒に活動する機会が多くありました。
例えば、イベントの企画時に意見が分かれた際には、双方の意見を尊重しながら、全員が納得できる形で解決策を提案するよう心掛けました。
この経験を通じて、相手の立場に立ち、柔軟に対応する力を身につけました。
この協調性を活かし、貴社でもチームでの仕事に積極的に取り組みたいと考えています。
協調性×友人関係のポイント

監修者
ポイント
友人関係を築く中で、柔軟に対応する力を身につけたことを伝えることで、貴社でのチームワークにも積極的に貢献できるという意欲を示しています。
このように、過去の経験を入社後の仕事にどう活かすかを説明することが大切です。
例文⑨人助けの経験
私は人助けを通じて協調性を培ってきました。
大学時代、アルバイト先で新人スタッフの指導を担当した際、仕事に慣れない新人が困っている場面に直面しました。
その時、私が心掛けたのは、一方的に教えるのではなく、相手のペースに合わせてサポートすることでした。
新人の意見を取り入れながら、一緒に問題を解決していくことで、新人の成長を促すとともに、チーム全体の雰囲気を良くすることができました。
こうした協調性を持って、貴社でも周囲と連携し、円滑な業務遂行に貢献したいと考えています。
協調性×人助けのポイント

監修者
ポイント
アルバイト先での新人スタッフの指導という、協調性が求められる具体的な場面を伝えられています。
人助けの経験を協調性を発揮したエピソードとして提示することで、説得力を高めることができます。
例文⑩家族関係
私の強みは他人の良いところを見つけ、それを伸ばすサポートができることです。
例えば、妹が自分の意見を周りに伝えることが苦手であると悩んでいた時、彼女のじっくりと考え抜く力に注目しました。
この長所を活かして、彼女に時間をかけて意見を練り、自分の考えを整理してから伝える方法をアドバイスしました。
その結果、妹は自分のペースで発言できる自信を持つようになり、少しずつ積極的に発言できるようになったのです。
この経験を通じて、相手の特徴を理解し、それに合わせた助言を行うことで、自分自身だけでなく周りの人々も成長できることに気付きました。
今後もこの強みを活かし、貴社の職場環境でも同僚やお客様の特性を理解し、それぞれの長所が活きるようなサポートを行い、全体のパフォーマンスを向上させるために貢献したいと考えています。
例文⑪留学
私の強みは自分と異なる価値観や文化を受け入れ、柔軟に対応できる点です。
大学3年次に1年間、留学に行った際には様々な国や文化を背景に持つ友人や教師と交流する機会がありました。
例えば、グループワークでは全員が満足する形でプロジェクトを進めるため、発言が控えめなメンバーに声をかけ、意見を聞き、皆が納得できる形にまとめるよう努めました。
その結果、多角的な解決策を導き出すことができ、プロジェクトも無事、成功しました。
この経験を通じて、価値観の違いを否定せず、多様な考えを積極的に受け入れることでチーム全体の成果を高められることを学びました。
貴社でも多様なお客様のニーズに柔軟に対応し、信頼を築く姿勢で業務に取り組むことで、円滑なコミュニケーションと高いサービス提供に貢献したいと考えています。
例文⑫趣味
私の強みは相手の意見を尊重しながら自分の考えを論理的に伝え、円滑なコミュニケーションを図れることです。
ある旅行の計画では友人Aが訪れたいという歴史的な観光地と、友人Bが行きたいというショッピングエリアのどちらに行くかで意見が分かれました。
そこで、まずはそれぞれが訪れたい理由や目的をじっくり聞き、何に一番価値を置いているのかを理解しようと努め、まずショッピングをして、夕方から歴史的な観光地を巡ることにしました。
この経験を通じて、相手の意見を尊重した上での調整力がコミュニケーションの円滑さに寄与することを実感しました。
貴社においても、顧客や同僚の意見をしっかりと受け止めつつ、自分の提案をわかりやすく伝えることで、相互理解のもとでの円滑な業務推進を目指したいと考えています。
【自己PRでの協調性】協調性が強みな人におすすめな職種
協調性がある人におすすめな職種を4つ紹介します。
どんな職業も、協調性は求められます。
しかし、特に協調性が求められる職種では、自己PRで協調性をアピールできるととても有利になります。
ここでは、営業職・事務職・技術職・専門職について解説します。
営業職
営業職は、クライアントとのコミュニケーションや社内の他部署との連携が求められる職種です。
顧客のニーズを的確に理解し、それに応じた提案を行うためには、協調性が欠かせません。
特に、チームで目標達成を目指すプロジェクトでは、同僚との連携が重要であり、協調性が発揮されます。
事務職
事務職では、日々の業務で他部署や外部の取引先との調整を行う場面が多くあります。
例えば、資料作成やスケジュール調整においては、相手の立場を考えた行動が必要です。
協調性がある人は、細かな配慮をしながら仕事を進めることで、円滑に業務を進めることができます。
技術職
技術職では、プロジェクトチームの一員として複数の専門分野のメンバーと協力して作業を進めることが求められます。
各メンバーの意見を尊重し、全体の調和を保ちながら成果を上げるためには、協調性が重要なスキルとなります。
協調性がある人は、技術的な議論や問題解決の場面で、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。
専門職
専門職においても、他の専門家や関係者との協力が不可欠です。
例えば、医療や法律などの分野では、複数の専門家がチームを組んで問題解決にあたることが一般的です。
このような場面では、相手の意見を尊重し、協力しながら最善の解決策を導き出す能力が求められます。
協調性がある人は、チーム内で信頼され、スムーズなコミュニケーションを図ることができるでしょう。
接客・販売職
接客や販売職は、協調性が必要な職種の代表格と言えます。
この職種ではお客様との対話を通じてニーズを的確に理解し、満足度の高いサービスを提供することが求められます。
協調性を活かすことでお客様への心配りや丁寧な対応ができるため、リピーターの獲得や信頼関係の構築にも大きく寄与できるのです。
また、他のスタッフと密に連携し、協力し合うことが業務の円滑な運営には欠かせません。
協調性がある人は周囲と協力してチーム全体で良い接客環境を作り上げられるため、接客・販売職において非常に適した能力と言えます。
協調性をアピールする際には「スタッフやお客様との信頼関係を築き、チームの一員として積極的に業務に貢献した」などのエピソードを伝えると、職場での活躍がイメージしやすく、好印象を与えられるでしょう。
企画職
企画職は、新しい商品やサービスを生み出し、顧客や世の中のニーズに合った価値を提供する役割を担います。
この職種では、相手がどのような課題を抱えているのかを正確に聞き出し、それを解決するアイデアを形にする力が求められます。
協調性は、他部署や取引先との連携をスムーズに進め、プロジェクト全体をまとめる上で欠かせない能力です。
さらに、他者の意見を尊重しながら、自らの考えを適切に伝える力も重要です。
企画職を志望する際には、自身が人の話を深く聞き取り、そこから具体的なアイデアを導き出す能力を備えていることをアピールすると、協調性と合わせた適性を効果的に示すことができます。
公務員
公務員は、国民や地域社会に対して直接的に貢献する役割を担います。
この職種では、社会が求めるニーズを的確に把握し、それに応じた施策を立案・実行する能力が求められます。
協調性は、多様な立場の人々と意見を交わしながら、最適な解決策を見つけるプロセスにおいて非常に重要な役割を果たします。
また、相手の意見を尊重しながらも全体の調和を保つ能力や、住民や他部署との連携を円滑に進める力も求められます。
公務員を目指す場合には、国民の幸福や地域の発展に対して思いやりを持ちながら尽力できる姿勢を強調することで、協調性が職務に直結する資質として説得力を持たせることができます。
【自己PRでの協調性】職種別の例文5選
ここからはここまで紹介してきた内容をもとに、職種別の例文を5つ紹介していきます。
いずれの職業においても協調性をアピールする自己PRの文章となっているため、協調性をアピールしたい方にぴったりの文章となっています。
例文①営業職
私の最大の強みは「協調性」であり、これによりクライアントとの信頼関係構築に大いに貢献できると確信しています。
協調性を身につけた経験は、大学時代のプロジェクトでのことです。
私たちは新しい学生イベントを企画し、成功させることを目指していました。
しかし、メンバーがそれぞれ自分のアイデアに固執し、意見が対立してしまい、進行が停滞してしまいました。
そこで私は各メンバーの意見を丁寧に聞き出し、共通の目標に向けての妥協点を見出すことにしました。
全員が納得できるアイデアの要素を組み合わせ、一つの企画案を作成するなど、さまざまな対策をしました。
これによりチームは一致団結し、イベントは大成功に終わりました。
この経験から、私は協調性がチームの成功に不可欠であることを学びました。
この能力を活かして社内外のチームと連携し、クライアントとの長期的な信頼関係を築くことで、貴社の売上向上に貢献します。
協調性×営業職のポイント

監修者
ポイント
協調性を営業職においてアピールする際には、社内の従業員と良好な関係を築くことができることもアピールした方が良いでしょう。
また、当然のことながら、クライアントと信頼関係が構築できるということも主張することが大切です。
例文②事務職
私の最大の強みは「協調性」です。
この協調性は大学のサークル活動で身につけました。
私たちのサークルでは、年に一度の大規模なイベントを企画していましたが、企画部門と広報部門の間で意見の食い違いが生じました。
企画部門はより独創的なイベントを望んでいましたが、広報部門は実現可能で予算内の案を提案したのです。
そこで私は双方の意見を聞くことにしました。
両部門の要望を丁寧に聞き出し、折衷案の提案に尽力し、両者が納得した上でイベントの実施が決まりました。
イベントは予算内で実施され、参加者からも高い評価を得ることができました。
この経験は、異なる立場の人々を理解し、効果的に協調する方法を学ぶ貴重な機会でした。
貴社に入社した暁にも、この協調性を通じて、目標達成に大きく貢献する所存です。
協調性×事務職のポイント

監修者
ポイント
事務職において、他の部署と連携するためには協調性が必須です。
よって、協調性を活かして他の部署とも円滑にコミュニケーションを取り、連携をすることができるという点をアピールするようにしましょう。
例文③技術職
私の最大の強みは「協調性」です。
大学のエンジニアリングプロジェクトでは特にこのスキルを発揮しました。
私たちのチームは、革新的かつ環境にやさしい車両を開発することを目標としていました。
しかし、プロジェクトの初期段階でメカニカルチームと電気チーム間の意見の不一致により、進行が困難になりました。
そこで私は両チーム間のコミュニケーションの架け橋となる役割を担いました。
定期的な合同会議の開催を提案し、各チームが抱える技術的な問題点や期待を共有し、相互理解を深める機会を設けました。
また、異なる専門分野の知識を持ち合わせたチームメンバーが協力し合えるように、目標とする成果物のビジョンを明確に定めました。
その結果、チームは一丸となって作業を進め、プロジェクトは成功を収めました。
私はこの協調性を活かし、貴社のチームに貢献します。
困難な案件に直面した際にもチームメンバー間の協力を促し、共通の目標に向けて効率的に取り組むことでプロジェクトの成功に導く所存です。
協調性×技術職のポイント

監修者
ポイント
技術職においては、開発や研究を行うチームメンバーと協力できるということをアピールしていきましょう。
また、クライアントと関わりがある業種の場合は、クライアントともうまくコミュニケーションを取るという姿勢も併せてアピールしましょう。
例文④専門職
私の最大の強みは「協調性」です。
大学時代のボランティア活動で身につけたものです。
私は地域の子供たちに読書の楽しさを伝えるプログラムを運営するチームの一員として参加しました。
しかし、プログラムの企画においてチーム内で意見が分かれてしまいました。
そこで私はチームメンバーと積極的に意見交換を行い、各々の提案の長所を組み合わせることで合意ができるよう取り計らいました。
また、子供たちと直接交流し、彼らの関心や好みを把握するためのアンケートを実施しました。
プログラムは大きな成功を収め、子供たちは読書を習慣化してくれました。
専門職として、私はこの協調性を活かし、社内の様々な部署やクライアントとの間において、信頼と共感を築きながら働きます。
また、顧客や生徒の本質的なニーズを理解し、それに応じた提案やサポートを行うことで、貴社の組織の目標達成に貢献する所存です。
協調性×専門職のポイント

監修者
ポイント
専門職においては顧客などと信頼関係を構築し、ニーズを汲み取れるといったことをアピールしていくと良いでしょう。
相手が何を求めているのか、どうすれば喜んでもらえるのかと常に思考を巡らせ、協調性を活かして発展的なことをできるということもアピールしていきましょう。
例文⑤接客・販売職
私の強みは協調性です。
アルバイト先の飲食店では忙しい時間帯に迅速かつ正確な対応が求められますが、スタッフとの円滑な連携を心がけ、情報の共有を積極的に行うよう努めました。
特に、料理の注文状況や何組並んでいるかなどをリアルタイムで確認し合うことが重要であると感じ、率先してコミュニケーションを図るようにしました。
これによりお客様から「繁盛しているのに、提供が早くてありがたい」というお言葉をいただくことも増え、サービス向上に繋がったと感じています。
この経験を通じて、協力して業務を進めることで個々の力を最大限に引き出し、より良いサービスを提供できることを学びました。
貴社においても、私の協調性を活かして他のスタッフと積極的にコミュニケーションを取りながら、お客様一人ひとりに満足していただけるサービスの提供を目指したいと考えています。
例文⑥ 企画職
私の強みは、他者の意見を尊重しながら、自分のアイデアを形にする協調性です。
この強みは、大学時代にゼミで新商品企画のプロジェクトを進めた経験で活かされました。
プロジェクトを進めるにあたり、メンバーの意見がまとまらず、全員が納得する方向性を見つけることが課題でした。
この課題を解決させるために、まず全員の意見を丁寧にヒアリングし、それぞれの意見の共通点や強みを整理しました。
その上で、話し合いを重ねながら最適な提案を形にすることに取り組みました。
結果、メンバー全員が納得できる企画を完成させ、コンペで最優秀賞を受賞することができました。
貴社に入社した際も、顧客やチームメンバーの意見を尊重しながら、新たな価値を提供する商品やサービスの企画を通じて貢献していきたいと考えています。
例文⑦ 公務員
私の強みは、多様な意見をまとめて合意形成を図る協調性です。
この強みは、地域ボランティア活動で住民からの要望をまとめ、具体的な改善案を提案した経験で活かされました。
活動を進めるにあたり、住民の要望が多岐にわたり、意見の方向性が一致しないという課題がありました。
この課題を解決させるために、住民一人ひとりの意見を丁寧に聞き、それらを整理して共通点を見つけ出す作業に取り組みました。
さらに、意見の調整を重ねながら全員が納得できる妥協点を探しました。
結果、住民全員が納得できる形で改善案をまとめ上げ、イベントを成功させることができました。
貴社に入社した際も、多様な立場の意見を調整し、地域社会の発展と住民の幸福に貢献していきたいと考えています。
【自己PRでの協調性】面接でも協調性をアピールしよう
面接では、あなたの協調性を効果的にアピールすることが重要です。
協調性をアピールする際のポイントを2つに絞って説明します。
1つの要点に絞って端的に述べる
協調性に関するエピソードを複数盛り込むのではなく、最もアピールしたい要点を1つに絞りましょう。
具体的なエピソードを1つ選び、その中であなたがどのように協調性を発揮したのかを明確に説明することが重要です。
話が長すぎると、面接官の集中力が途切れてしまう可能性があります。
簡潔かつ分かりやすく伝えることを心掛けましょう。
話の聞き方にも気を配る
面接は、あなたが一方的に話す場ではありません。
面接官の質問を注意して聞き、意図を正確に理解することが重要です。
質問の意図と異なる回答をしてしまうと、協調性がないと判断される可能性があります。
また、面接官の目を見て話す、相槌を打つなど、コミュニケーション能力も評価されています。
話の内容だけでなく、話し方や態度にも気を配りましょう。
【自己PRでの協調性】自己PRに困ったらエージェントに頼ろう
かなり詳しく紹介しているので、本記事を読み終わってもうまく自己PRが書けない人は「もう自分は良いものを書けないのではないか」と頭を抱えているかもしれません。
しかし、一つの記事を読んだだけで完璧な自己PRが書ける人はなかなかいません。
そこでおすすめなのは、ジョブコミットを利用することです。
毎年何人もの就活生を希望する企業に送り込んでいるベテランのエージェントが、自己PRをはじめとしたESを徹底的にサポートしてくれるサービスであり、面接対策なども行ってくれるので、就活をスムーズに進められます。
完全無料で利用できるので、気になる方は是非、下記のリンクから登録してみてください。
まとめ
今回は協調性をテーマとした自己PR文に焦点をあててご紹介しました。
協調性という言葉だけでは、魅力的な人柄は伝わりません。
具体的なエピソードとともに、主体的に動けることをアピールすることが非常に大切です。
希望する企業や職種においてどのような人材が求められているのかをしっかり理解したうえで、アピール方法を考えてみましょう。



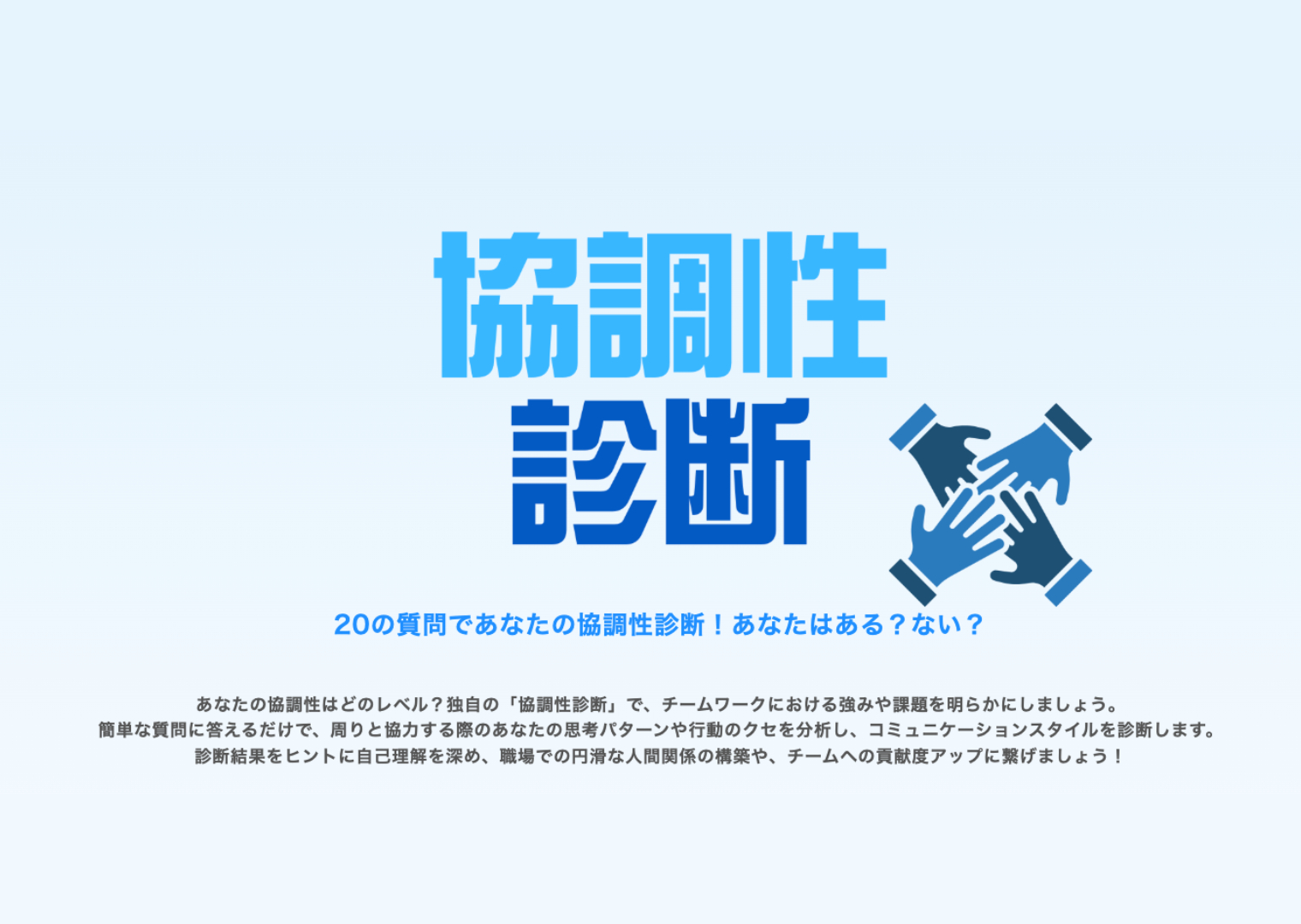











監修者
プロフィールポイント
リーダータイプの協調性をアピールするためにも、部活動内のチームをまとめ上げたという実績があると非常に好ましいです。
部長・キャプテンなどのリーダー的ポジションでなくとも、チームの意見をまとめ、課題を解決するという流れであれば大丈夫です。