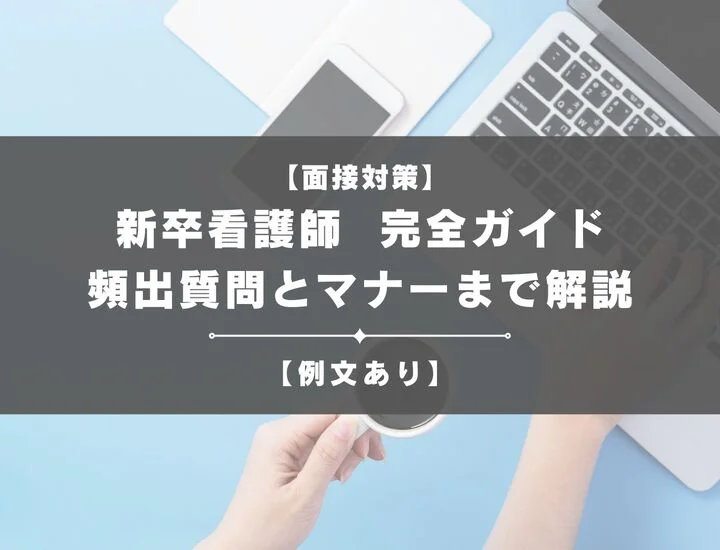明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・二次面接はほぼ内定なのか
・二次面接の特徴
・二次面接に向けた準備
・二次面接が控えてる人
・面接が不安な人
・二次面接に受かりたい人
はじめに
入社を希望する企業の書類選考や一次面接を通過すると、二次面接に入ります。
二次面接になると、内定がより現実味を帯びてくるため、より気合いを入れて臨むようになります。
そんな二次面接は、「通過すればほぼ内定」ということをよく耳にしますが、これは果たして本当なのでしょうか。
今回は、二次面接の位置づけやポイント、想定される質問や必要な事前準備についてご紹介します。
二次面接について理解を深め、第一志望の企業の内定を勝ち取りましょう。
【二次面接の通過率】二次面接の通過率とは
面接の中でも低い通過率である二次面接ですが、実際にどのくらい通過が難しいのでしょうか。
一次面接の後に二次面接、最終面接と続く選考フローの合格率は、一次面接が20~40%、二次面接が20~50%、最終面接が50%ほどと言われています。
一次面接は人数も多く、志望度やスキルの度合いの異なる就活生がライバルとなります。
一方の二次面接は、企業から一定の評価を受け一次面接を通過した人たちと競わなければなりません。
通過率の数値だけを見ると、一次面接も二次面接も同水準のように感じますが、二次面接は少数精鋭の中から面接通過者が決まるため、難易度は高いと言えます。
なお、企業や企業の選考フローによって通過率は大きく異なりますので、1つの目安として参考にしてみてください。
基本的は一次面接よりも高い
新卒採用における二次面接の通過率は、一次面接と比べて基本的に高くなる傾向があります。
一次面接では学生の数が多いため、大幅な選考が行われますが、二次面接に進む段階では企業も「より自社に合う人材」を見極めるフェーズに入ります。
そのため、一次面接を通過した時点で、企業が一定の評価をしていると考えられます。
ただし、油断は禁物です。
二次面接では志望度の高さや企業とのマッチ度がより重視され、深掘りした質問が増えます。
しっかりと企業研究を行い、具体的なエピソードを交えて話せるよう準備することが重要です。
二次面接の通過率は高いとはいえ、万全な対策をして次の最終面接に備えましょう。
実際の通過率は企業によって異なる
一般的に二次面接の通過率は一次面接よりも高い傾向にありますが、実際の通過率は企業によって大きく異なります。
例えば、大手企業や人気企業では学生が多いため、二次面接でも厳しい選考が行われ、通過率が低めになることがあります。
一方で、中小企業やベンチャー企業では、一次面接を通過した学生を前向きに評価し、比較的高い確率で二次面接を通過できるケースもあります。
そのため、志望企業の選考フローや過去の通過率の情報を調べることが大切です。
企業の採用ページや就活サイト、選考体験談などを活用し、どのような基準で評価されるのかを把握しておきましょう。
企業ごとの特徴を理解し、効果的な面接対策を行うことが重要です。
【二次面接の通過率】二次面接の通過率を予測するには
二次面接の通過率は企業によって異なりますが、事前にある程度の予測を立てることは可能です。
選考フローや過去の採用実績を分析することで、自分がどの程度通過できる可能性があるのかを把握できます。
志望企業の傾向を知ることで、より効果的な面接対策が可能になります。
ここでは、二次面接の通過率を予測する方法について解説します。
採用倍率から考える
二次面接の通過率を予測する方法の一つが、企業の採用倍率を参考にすることです。
採用倍率とは「応募者数÷採用人数」で算出される数値で、この倍率が高いほど競争が激しくなり、二次面接の通過率も低くなる傾向があります。
例えば、最終的に20名を採用する企業で応募者が2000人いた場合、採用倍率は100倍になります。
一次面接や二次面接で徐々に絞り込まれるため、このような企業では二次面接の通過率も低めになる可能性が高いです。
一方、倍率が低い企業では、二次面接を通過しやすくなることもあります。
企業の採用倍率は就活サイトや説明会で得られる場合があるので、事前に情報収集し、自分がどの程度の確率で通過できるのかを把握しておきましょう。
採用フローから考える
企業の採用フローを確認することで、二次面接の通過率を予測できることがあります。
例えば、面接が一次・二次・最終の計3回しかない企業と、四次・五次面接まである企業では、二次面接の位置づけが異なります。
面接の回数が少ない企業では、二次面接が重要な選考ステップとなり、厳しく評価される可能性があります。
そのため、通過率も比較的低めになることが予想されます。
一方、面接回数が多い企業では、二次面接は通過しやすく、最終面接で厳選されるケースが多いです。
企業の採用ページや口コミサイトで選考フローを事前に調べることで、どの面接が最も重要視されるのかを把握し、適切な対策を立てましょう。
二次面接の通過率が高い企業とは
企業の規模や採用方針によって、二次面接の通過率には違いがあります。
特にベンチャー企業や中小企業は、熱意や意欲をしっかりアピールすることで二次面接の通過率が高くなる傾向があります。
これらの企業は、大手企業と比べて「企業とのマッチ度」や「成長意欲」を重視するため、スキルや経験以上に「この会社で成長したい」「貢献したい」という熱意が評価されやすいです。
逆に、志望動機が曖昧だったり、受け身の姿勢が見られると、通過は難しくなる可能性があります。
企業研究をしっかり行い、なぜその企業で働きたいのかを具体的に伝えることが重要です。
熱意を持ってアピールし、二次面接を突破しましょう。
二次面接の通過率が低い企業とは
超一流企業や大手企業は、採用基準が高いため、二次面接の通過率が低くなる傾向があります。
一次面接では基本的なコミュニケーション能力や志望動機が評価されますが、二次面接ではさらに深掘りされ、より厳しい基準で選考が行われます。
特に、大手企業では応募する学生の数が多いため、最終面接に進める人数を絞り込む必要があります。
そのため、論理的な思考力や企業とのマッチ度、リーダーシップなどが厳しく評価され、少しでも基準に満たないと判断されると落とされてしまうこともあります。
こうした企業を志望する場合は、事前に企業研究を徹底し、求められる人物像に合った自己PRを準備することが重要です。
万全な対策をして、選考を突破しましょう。
▼ 人気企業の内定者の面接回答集を確認しよう!▼
学生が就活で最も不安を感じている面接対策。
どんなことが聞かれ、どう答えたら選考通過できるのか気になる方も多いはず。
そこで、今回無料でダウンロードできる「内定者の面接回答集50選」を用意しました。
この資料ではニトリやソニーグループ、味の素といった人気企業の面接でよく聞かれる質問とその回答例、ポイントをサクッと確認できます。
今すぐ、確認して内定獲得の一歩を踏み出しましょう!
ニトリ
・学業で最も力を入れたことはなんですか
・チームで何かを成し遂げた経験はありますか
ソニーグループ
・あなたの強みや長所を教えてください
・なぜこの業界を志望しているのですか
味の素
・最近感動したことはなんですか
・周りからどんな人と言われますか
【二次面接の通過率】二次面接の目的とは
企業によって、二次面接の目的や立ち位置、そして二次面接の通過がほぼ内定といえるかは異なります。
一般的に二次面接は、本当に採用したい人材かどうかを見極める意味合いがあります。
二次面接自体が最終選考である企業や、二次面接の次が最終面接である企業の場合、特に吟味して選考通過者を選ばなければなりません。
そして、その中からさらに最終面接で、企業が求める人材を選ぶフローになります。
一方で、二次面接が中間面接にあたるような企業では、二次面接の通過がほぼ内定を意味するわけではないので、注意しましょう。
ホームページや募集要項に、採用までの流れが記載されていることが多いため、志望する企業がどのような選考のステップを踏んでいるのか、事前に確認が必要です。
二次面接 → 中間選考
二次面接が中間選考にあたる企業において、二次面接は就活生をふるいにかける目的があります。
志望者の多い大手の企業であると、一次面接や二次面接だけで最終的な内定者を絞るのは厳しいので、その分面接の回数も多く設定されているのが一般的です。
そのため、二次面接が中間選考にあたり、仮に選考を通過したとしても、その後に三次面接や最終面接が控えています。
三次面接や最終面接に進む人数は、もちろん内定者の人数よりも多いため、内定を出すかどうかの判断は、三次面接や最終面接で行われます。
つまり、二次面接が中間選考にあたる企業では、二次面接の通過は「ほぼ内定」に該当しません。
二次面接の後に控えている選考で、内定を勝ち取れるかどうかが決まると覚えておきましょう。
二次面接 → 最終選考
二次面接を中間選考とする企業がある一方、二次面接を最終選考と捉えている企業もあります。
志望者がそこまで多くない中小企業や、採用を急いでいる企業などでは、面接の回数が少なく、二次面接が最終選考となっているケースも多いのです。
そういったケースでは、二次面接を最終的な内定者を絞る目的で行っているため、二次面接を通過すれば、ほぼ内定ともいえます。
「二次面接でほぼ内定が得られるのなら、面接回数の少ない企業を志望するほうが楽そう」と考える人もいるかもしれませんが、油断は禁物です。
面接の回数が少ない分、一つひとつの面接でのミスが命取りになります。
最初の選考から内定獲得を意識した成果が出せるよう、入念な事前準備が必要です。
【二次面接の通過率】二次面接の面接官の特徴
難易度の高い二次面接ですが、面接官として面接に参加するのはどのような人たちなのでしょうか。
一次面接の後に二次面接、最終面接と続く選考フローの場合は、二次面接では部長や課長といった管理職クラスの社員が出てくるケースが多いです。
一方、一次面接は人事担当者、最終面接は役員や社長といった経営層であることが多いと言われています。
面接が進むにつれて、より高い役職に就いている人が面接官となるのです。
また、二次面接では現場をよく知る人が面接官となるので、一次面接と比べてより踏み込んだ質問をされることが多くなります。
評価ポイントとしても、企業に利益をもたらすか、実際に現場で活躍できそうな素質があるかといった視点が強くなります。
一次面接と二次面接の違い
一次面接と二次面接では同じ面接のくくりでも、様々な違いがあります。
一次面接と二次面接の違いを把握して対策しましょう。
面接形式
一次面接では、集団面接(グループ面接)を行う企業が多い傾向にあります。
しかし、二次面接では個人面接、もしくは少人数での集団面接を実施するところが多いです。
もちろん全部がこのようになるわけではなく、企業によって内容が違います。
それを理解して対策していきましょう。
見られている事
一次面接では一般的なビジネスマナーが守れているか、ESの内容の相違がないかを確認します。
人物に関して深く突っ込むことはあまりない傾向にあります。
しかし、二次面接では人柄など見られるポイントが多くなります。
これはより選考の重要度が上がるということを意味します。
次で見られているポイントを詳しく見てみましょう。
より詳しい違いについては以下の記事をご覧ください。
【二次面接の通過率】二次面接で見られているポイント
ここまで、二次面接の位置づけや特徴をご紹介してきました。
より内定が現実味を帯びる二次面接は、企業にとっても就活生にとっても重要な面接となります。
しかし、通過率の低い二次面接は、一次面接と同じ対策をしていては突破することができません。
二次面接ではより入社後の具体的なイメージを伝え、企業に利益をもたらしたり現場で活躍したりする素質があるということを面接官に伝える必要があるのです。
ここからは、事前に押さえておいてほしい、二次面接で見られているポイントをご紹介します。
内容が一貫しているか
二次面接で見られるポイントの一つに、内容に一貫性があるかが挙げられます。
二次面接は書類選考や一次面接をもとに行われるため、これまで話してきた内容が一貫しているか、嘘をついていないかなどが見られているのです。
そのため、二次面接で突拍子もない話をしてしまうと、「矛盾している」「一次面接で話した内容は事実ではないのでは」などと判断され、信頼が大きく落ちてしまいます。
話に一貫性を持たせるには、綺麗事は避け、正直に自分の考えや強みをアピールしましょう。
志望度の高さ
まず、二次面接では志望度の高さが見られています。
企業としては、内定を出したのに結局入社してもらえなかったというのはできるだけ避けたいトラブルです。
そのため、二次面接においては、応募者が企業へ入社する意欲があるかどうかを確認する質問が想定されます。
面接官からは志望動機や志望度が確認できるような質問があるはずなので、そのための対策を練っておきましょう。
志望度の高さは、事業内容や企業理念をどれだけ調べているか、調べたうえでなぜ企業への入社を希望するのかといった話から見えてきます。
企業研究をしっかりと行い、事業内容や企業理念を理解したうえで、なぜその企業に入社したいのか、入社して何を成し遂げたいのかを伝えることが重要です。
自社とのマッチ度合い
次に、企業の事業内容や求める人材にどれだけマッチしているかどうかが見られます。
二次面接はより内定に近い面接であるため、実際に働いた後をイメージして面接が行われます。
採用した後に、一定期間意欲的に働くことのできる人材かを見ているのです。
企業の雰囲気や価値観と合わない環境で、その人が成果を出すのは難しいとされています。
また、新卒採用には時間と費用が必要で、採用した人に早期退職されてしまうと、企業にとっては大きな損失となります。
そのため、二次面接では入社した後のことをイメージし、より具体的に志望動機や入社後の展望を話せると良いでしょう。
企業研究から企業が求めている人物像をつかみ、そこに合う形で話ができるとなお良いです。
入社して活躍できそうか
最後に、入社後に企業で活躍できる人材かどうかが見られています。
二次面接を通過すると内定がぐっと近づき、実際に企業で働く可能性も高くなります。
そのため、業務で求められる能力や強みを持っているかどうかも、面接官が合格を出すかどうかの重要なポイントです。
二次面接では、自分の持っている強みやスキルを仕事にどう活かせるかを積極的にアピールしていきましょう。
うまくアピールするためには、企業研究などで実際の業務内容や求められるスキルを確認し、自分の持つスキルや強みと合致する点を探すと良いでしょう。
面接官に自分の能力や強みをしっかりとアピールし、入社後に活躍しているイメージを持ってもらうことができれば、ほかの就活生とも差別化され高評価が期待できます。
【二次面接の通過率】二次面接の合格フラグ
二次面接の結果が気になる学生も多いでしょう。
実は、面接中の企業側の反応や質問の内容から、合格の可能性をある程度判断することができます。
例えば、選考の具体的な流れを詳しく説明されたり、入社後の働き方について話が及ぶ場合は、企業が前向きに評価しているサインかもしれません。
ここでは、二次面接の合格フラグとなるポイントについて詳しく解説します。
メモ多く取っている場合
二次面接の際に、面接官が多くメモを取っている場合は学生の話に興味を持っているケースが多く、合格フラグの一つと考えられます。
企業側は、多くの応募者の中から自社に合う人材を見極めるため、特に印象に残ったポイントや評価したい部分を記録することがあります。
例えば、自己PRや志望動機について話している際に熱心にメモを取られている場合は、その内容が企業の評価基準に合致している可能性が高いです。
また、深掘り質問の際に詳細を記録している場合は、より具体的に検討したいと考えている証拠かもしれません。
ただし、メモを取られなかったからといって不合格とは限らないため、最後まで気を抜かずにしっかりアピールしましょう。
質問数が多い場合
面接中に質問数が多く、深掘りされる場合は、企業が学生に興味を持っている可能性が高いため、合格フラグの一つと考えられます。
企業は、優秀な人材を見極めるために、気になるポイントをさらに詳しく確認しようとすることがあります。
例えば、自己PRに対して「具体的なエピソードは?」「どのような工夫をした?」などと掘り下げた質問が続く場合、企業側が学生の強みに魅力を感じ、より深く知りたいと考えているサインかもしれません。
また、入社後の働き方やキャリアプランについて多く質問される場合も、前向きに評価されている可能性があります。
ただし、回答の一貫性が求められるため、しっかり準備し、説得力のある回答を心がけましょう。
次の選考のアドバイスがある場合
二次面接の終盤で、面接官から次の選考に関するアドバイスを受けた場合、通過する可能性が高いと考えられます。
企業側は基本的に、不合格と判断した応募者に対して具体的なアドバイスをすることは少なく、次の面接に進む前提でサポートしているケースが多いためです。
例えば、「次の面接ではより具体的な経験を話せるといいですね」や「最終面接では〇〇をしっかり伝えると良いですよ」といった助言があれば、それは企業が次のステップを見据えている証拠かもしれません。
ただし、アドバイスを受けたからといって確実に合格とは限らないため、気を抜かずに最終面接に向けた準備を進め、さらに完成度の高い受け答えができるようにしましょう。
採用を前提とした質問やアドバイスがある場合
面接官から採用を前提とした質問や入社後を想定したアドバイスを受けた場合、二次面接を通過する可能性が高いと考えられます。
企業側は、基本的に不合格の応募者に対して入社後の話をすることは少なく、具体的な業務内容や働き方について触れるのは、すでに採用を前向きに検討しているサインであることが多いです。
例えば、「入社後はどんな業務に興味がありますか?」や「〇〇の部署で活躍できそうですね」といった言葉が出た場合、企業がその学生を戦力として考えている可能性が高いです。
また、「入社後はこういうスキルを伸ばすといいですよ」などのアドバイスがある場合も、期待されている証拠かもしれません。
ただし、確実に合格とは限らないため、最後まで気を抜かずにしっかりと自己アピールをしましょう。
【二次面接の通過率】二次面接で想定される質問
ここまで、二次面接で見られるポイントについてご紹介しました。
二次面接は非常に重要な選考フローとなるため、面接官も就活生の入社意欲や入社後に活躍しているイメージをしっかりと見ているのです。
では、そういったポイントを確認するために、二次面接ではいったいどんな質問が出るのでしょうか。
以下で、二次面接で想定される質問の切り口をご紹介します。
これらを押さえておくと、ほかの質問にも応用ができるので、事前にしっかりと対策を練っておきましょう。
自己紹介について
二次面接でも、最初に「簡単に自己紹介をお願いします」と聞かれることが多いです。
ここでは、名前や大学名に加え、自分の強みや経験を簡潔に伝えることが重要です。
一次面接では基本的な情報を確認する目的が強いですが、二次面接では「この学生が自社に合うか」を見極めるための質問となります。
例えば、「〇〇大学の△△です。学生時代は◇◇に取り組み、△△な強みを身につけました。本日はそれを活かしたい理由をお伝えできればと思います。」のように、面接官が興味を持つような自己紹介を準備しておきましょう。
ガクチカについて
ガクチカは、学生時代に力を入れたことの略語で、面接では必須となる質問です。
二次面接でもこのガクチカを聞かれる可能性が高いのですが、書類選考や一次面接よりもよりシビアに内容を確認されます。
なぜ力を入れていたのかといった行動原理や、なぜ力を入れて取り組めたのかといった意欲の源泉など、より深く問われることがあります。
事前に話すネタを準備しておかないと、しどろもどろの回答になってしまうかもしれません。
以下に、ガクチカを深掘りするための3つの質問例を見ていきましょう。
ほかに考えていた施策はありますか?
ガクチカを話す際、学生時代に一番力を入れていたことを題材にする人がほとんどです。
しかし、なぜその施策に一番力を入れて取り組むことになったのかも、企業にとっては気になる点です。
仕事において、1つの結論を出すために考えられる選択肢を挙げ、その中から有効な結論を導き出すというプロセスが求められることが多々あります。
企業は、そういった思考ができる人材かを見極めるため、ガクチカを深掘りします。
「ほかに考えていた施策はありますか?」という質問からは、ガクチカの中で出てきた施策を選ぶにあたって、どのような思考プロセスを踏んだのかを見ようとしているのです。
質問に答える際には、単に思いつきの行動ではなく、いくつかの選択肢からより有効な施策だと考えたと説明できるよう準備をしておくと良いでしょう。
どうしてその取り組みをがんばれましたか?
ガクチカでは、どのようにがんばっていたかを話す就活生は多くいます。
二次面接ではそこからさらに一歩踏み込んで、何をモチベーションにその施策をがんばっていたのかを深掘りされるケースがあります。
企業は入社後、意欲的に仕事に取り組むことのできる人材を確保したいと思うのは当たり前のことです。
しかし、面接の様子から実際の仕事現場で意欲的に働くことができるかを見極めるのは、決して容易なことではありません。
そこでガクチカのエピソードを深掘りし、なぜその取り組みをがんばれたのかを聞くのです。
企業は、どのような状況なら応募者の意欲やモチベーションが高まるのかを見ています。
「仕事においても高い意欲で働くことができる」というイメージを持ってもらえるような回答を心がけましょう。
その課題はどうやって見つけましたか?
仕事は、顧客や自分が取り組む業務の課題を見つけ、解決するためにアクションを起こすことの繰り返しです。
学生時代にそういった経験をしているのか、課題発見や解決のスキルがあるのかは、企業が面接で確認しておきたい点となります。
そのため、ガクチカでは「その課題はどうやって見つけましたか?」という質問がよく出ます。
この質問では、自分自身で課題を発見する力があるのか、発見するためにどのような工夫ができるのかが見られます。
回答では、単に「友人から言われたから」といった受動的な内容は控えるようにしましょう。
人から言われないと気づけないという印象を与えてしまうと、評価が下がる可能性もあります。
もし人から言われて気がついた場合でも、「漠然とした課題をより具体化するために周りの人に意見を求めた」など、自発的に行動を起こしたエピソードを話せると良いでしょう。
志望動機について
先述したように、二次面接は一次面接以上に志望度の高さを見られています。
その人に内定を出した場合に、「本当に入社する意欲があるのか」を確認する必要があるのです。
面接官からは、志望動機や志望度が確認できるような質問をされます。
そのため、入社意欲がしっかりと伝わる回答ができるように準備しておくと良いでしょう。
以下で、志望動機に関係する質問の例を紹介します。
想定される質問をもとに、志望度の高さが伝わる回答ができるよう、事前準備をしておきましょう。
競合他社と比べた際の自社の志望度とその理由は?
どのくらい志望度が高いのかを確認するために、競合他社に関する質問がよく出されます。
たとえば、「競合他社と比べた際の自社の志望度とその理由は?」という質問では、競合他社の中でもあなたの企業が第一志望であると話せると良いでしょう。
さらに、他社と比較したうえでなぜその企業を強く志望しているのかを伝えることが大切です。
評価の近い就活生がいたときには、どのくらい自社を強く志望しているかも評価の重要なポイントとなります。
競合他社と比べた際の志望度の高さを伝えるには、企業研究や業界研究が欠かせませんので、事前に対策を練っておきましょう。
なお、就活において、1つの企業のみの選考を受けているということは稀です。
競合他社の選考を同時並行で受けていることは、マイナスの評価につながることではないので安心してください。
他社の選考状況を教えてください
企業としては、競合他社に良い人材を取られたくないという考えがあります。
そして、自社で働いてほしいと思った就活生がいた場合に、競合他社よりも早く次の選考に案内して内定を出したいと考えます。
「他社の選考状況を教えてください」という質問では、以降の選考のペースを検討するための材料を集めているのです。
先ほどもご説明したとおり、競合他社の選考を同時並行で受けていることはマイナスの評価にはなりませんので、聞かれた場合は素直に答えるようにしましょう。
また、他社の選考状況を聞かれるもう1つの理由として、本当に自社が第一志望なのかを見ることが挙げられます。
ほかにどのような企業を受けているのか、具体的な選考状況を話す際には、自身の志望度を見られているという意識を持っておくと良いでしょう。
企業選び・業界選びの軸は何ですか?
企業とのマッチ度が見られる二次面接では、就活生の価値観と企業の特徴が合っているかどうかを問う質問もよく出されます。
企業選びの軸や業界選びの軸を聞くことで、仕事に対する就活生の価値観を確認するのです。
軸と企業の特徴が一致していない場合は、入社した後の早期退職やモチベーション低下のリスクがあるため、面接での評価が下がる可能性もあります。
さらに、この質問では、志望動機の内容が本当なのかをたしかめている場合もあります。
企業や業界選びの軸と企業の特徴が一致していない場合、「本当に入りたい企業ではなく、とりあえず受けてみただけなのではないか?」と判断されてしまうかもしれません。
企業や業界選びの軸から志望動機まで一貫した話ができるよう、あらかじめ準備しておくようにしましょう。
入社してやりたいことはありますか?
就活生がどのような展望を持って志望しているのかは、企業にとって気になる点のひとつです。
「入社してやりたいことはありますか?」という質問は、一見、就活生の自分らしさが問われているようにも聞こえますが、実際は企業への理解度が問われています。
入社後、具体的に何をしたいかを考えるには、企業の事業内容や展望を理解しておく必要があります。
企業が行っている事業や目指す方向性と違った目標を掲げられてしまうと、入社後に活躍しているイメージが湧きません。
企業研究を十分に行い、事業内容や展望を理解したうえで、自分の想いやスキルを活かして何をしたいのか伝えるようにしましょう。
面接官に「一緒に働きたい」と思ってもらえるような話ができると、高評価の可能性が高いです。
自己PRについて
ガクチカに加え、自己PRも二次面接ではさらに深掘りして聞かれることがあります。
複数のエピソードや複数の強みから、企業で活躍できそうな人材かを確認しようとしているのです。
二次面接は、内定を出した場合に企業で活躍できる人材かが見られています。
さらに、実際の業務で求められる能力や強みを持っているかどうかも、合格を出すかどうかの重要な視点です。
自分の持っている強みやスキルを、入社後の仕事にどう活かせるかを積極的にアピールしていきましょう。
以下で、想定される質問を3点ご紹介します。
その強みを発揮したほかのエピソードはありますか?
自己PRを考える際、印象的なエピソードから自分の強みを紹介するという就活生も多いのではないでしょうか。
しかし、印象的なエピソードがどんなに良い話だったとしても、その人の強みがそこだけでしか発揮されないものだと意味がありません。
二次面接では、強みを発揮した状況についてさらに詳しく聞かれることがあります。
企業は、その強みが入社後にどのように仕事に活かされるのかを知りたいのです。
「その強みを発揮したほかのエピソードはありますか?」という質問があった場合には、できるだけ具体的に強みが発揮された場面がイメージできるように話してください。
印象的なエピソードとは違った状況や場面で発揮された話ができると、強みの説得力が増して高評価につながる可能性が高くなります。
ほかに強みはありますか?
二次面接では、企業もより深く就活生のことを理解したいと考えており、そのため自己PRで話される強み以外の要素を聞く質問もよく出されます。
その人の得意とすることや人間性を理解することで、自社とのマッチ度をチェックするのです。
そのため、自己PRのときに述べた強み以外にも、自分のアピールポイントとなるような要素を考えておくと良いでしょう。
さらに、それらの強みを活かして企業にどう貢献できるのかまで深掘りしておくと、想定外の質問にも対応しやすくなります。
また実際の仕事は、1つの強みやスキルだけでは乗り越えることのできないトラブルが起こるものです。
仕事に活きるような強みを多く持っている就活生は高評価が期待できますので、自分の強みを事前に整理しておくようにしましょう。
その強みは今後どう活かしていけると考えていますか?
繰り返しになりますが、企業で活躍できる人材であるかは、二次面接の重要な評価基準となります。
自分の持っている強みやスキルを、入社後の仕事にどう活かせるかを積極的にアピールしていきましょう。
「その強みは今後どう活かしていけると考えていますか?」といった質問へも、強みを仕事にどう活かしていくかを関連させながら回答できるとベストです。
また、企業での仕事にどう活かせるかを明確に話せる就活生は、企業への理解が深いと判断されやすいです。
企業研究をしっかりと行い、企業の求める人材や働き方への理解を深め、自分の強みの活用方法を考えておきましょう。
企業研究や事前準備を行っていることが面接官に伝わると、それだけ志望度の高さのアピールにもつながります。
二次面接におけるより具体的な質問について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
成功体験・挫折経験について
二次面接では、「これまでの成功体験を教えてください」や「挫折を経験したことはありますか?」といった質問がよくあります。
企業はこの質問を通じて、学生の価値観や課題解決能力、成長意欲を見極めようとしています。
成功体験を話す際は、単に成果を述べるのではなく、どのように努力したか、どんな工夫をしたかを伝えることが重要です。
一方、挫折経験については、失敗したこと自体よりも、そこから何を学び、どう改善したかが評価されます。
例えば、「アルバイトでリーダーを務めた際、最初はチームがまとまらず苦労しましたが、◯◯の工夫をして改善しました」のように、具体的なエピソードを交えて話せるよう準備しておきましょう。
キャリアビジョンについて
キャリアビジョンについても、企業からよく聞かれる質問の一つです。
二次面接では、「入社後にどのようなキャリアを築きたいか」「将来的にどのような役割を担いたいか」といった質問を通じて、学生の長期的な成長意欲や企業とのマッチ度を確認します。
企業は、短期間で辞めてしまう人材ではなく、長く活躍できる人材を求めています。
そのため、漠然と「成長したい」ではなく、具体的にどんなスキルを身につけ、どのような仕事に携わりたいのかを明確に伝えることが重要です。
例えば、「◯◯の業務を通じて専門知識を深め、将来的には△△の分野でリーダーシップを発揮したいです」といった形で、自分のキャリアプランをしっかり説明できるよう準備しましょう。
【二次面接の通過率】二次面接に向けて行うべき準備
これまでの説明から、二次面接の位置づけや想定される質問について理解いただけたかと思います。
二次面接は、多くの就活生の中から選ばれた人たちと競う面接であるため、書類選考や一次面接とは違った対策が必要になります。
また、企業が見ているポイントや想定される質問に答えるためには、事前準備が欠かせません。
では、二次面接に向けて具体的にどのような準備をするのが良いのでしょうか。
二次面接を通過するために、ぜひ実践してほしいことをご紹介しますので、ぜひ取り組んでみてください。
自己分析を再度行う
二次面接では、一次面接よりも深掘りした質問が増えるため、自己分析を再度行い、自分の強みや弱みを確認しておくことが重要です。
企業は、学生の人柄や価値観が自社と合うかどうかをより詳しく見極めようとします。
そのため、表面的な回答ではなく、具体的なエピソードを交えて説明できるよう準備する必要があります。
例えば、「自分の強みは何か?」「その強みをどのように発揮してきたか?」を再確認し、過去の経験を整理しましょう。
また、弱みについても「どのように克服しようとしているか」を話せるようにしておくと、より説得力が増します。
自己分析を深めることで、自信を持って面接に臨むことができ、企業に好印象を与えることができます。
志望度が伝わる話し方
面接官からの質問に対する回答を考えておくことも大切ですが、回答の話し方にも意識を向けてみましょう。
どのような話し方をするかによって、二次面接で大切な企業への志望度や入社への熱意の伝わり方も変わります。
志望度や熱意の伝わる話し方のポイントは、抑揚をつけることです。
面接で緊張をしていると、つい覚えてきた回答を単調に読み上げるような話し方になってしまいがちです。
しかし、これでは自分の気持ちが伝わらず、面接官の印象にも残りません。
単調なトーンにならないよう、自分が伝えたい単語や内容を話すときにゆっくりと大きく話すといった工夫をしてみましょう。
特にベンチャー企業では、志望度をより重要視しているケースが多くあります。
志望度や熱意が伝わる話し方ができているか、意識して準備することが大切です。
企業理解を深める
二次面接では、企業理解を深めることも重要です。
二次面接では、「入社したら企業で活躍できる人材であるか?」が見られます。
また、企業研究を踏まえた発言からは、志望度も見られています。
書類選考や一次面接の対策の際に企業研究をしているはずだとは思いますが、より深く理解を深めるようにしましょう。
その企業の事業の強みや弱み、事業の特徴や社風における他社との違いなどを再度確認しましょう。
そのうえで、なぜ自分がその企業で働きたいのかを伝えることが大切です。
さらに、企業で求められるスキルを確認し、自分の持つスキルやアピールポイントと合致することを探します。
自分の能力や強みをしっかりとアピールできると、ほかの就活生とも差別化され高評価が期待できます。
入社後に活躍できる人材であることをしっかりと伝えられるよう、回答に個性を持たせるようにしてください。
言葉遣いのミスをなくす
二次面接に向けて行うべき準備として見落としがちなのが、言葉遣いのミスをなくすことです。
話す内容の要点を決めていても、話し言葉にした際に、言葉を正しく使えていないケースもあります。
エントリーシートなどの書類選考では、書き言葉で文章を作成しているため、面接では話し言葉に変えて読まなければなりません。
その際に、正しく話し言葉に変換できていないと「正しい言葉遣いができていない」「準備不足」など、マイナスな印象につながる可能性があります。
たとえば、謙譲語や尊敬語、敬語が正しく使い分けられているかなどは、間違えやすいポイントです。
言葉遣いのミスをなくすためには、実際に話す内容を文字に起こしてみると良いでしょう。
話しながら文字に起こすのが難しい場合は、録音してから文字に起こす方法もおすすめです。
一次面接の振り返りをする
一次面接の振り返りも、二次面接に向けて行うべき準備として大切です。
一次面接を通過できた場合には、一次面接をベースにして二次面接の質問が行われます。
一次面接での反省点を洗い出し、二次面接までに再確認すると、よりクオリティの高い面接対応ができるはずです。
また、一次面接で話した内容と違った話をしてしまうと「一貫性がない」「一次面接で話した内容は事実ではないのでは」などの印象を持たれてしまう恐れもあります。
一次面接と二次面接で一貫性のある話をするためにも、振り返りは重要です。
一次面接が無事に終わると、開放感から振り返りを疎かにしてしまう人もいるかもしれませんが、二次面接に向けて振り返りを忘れずに行いましょう。
逆質問を用意しておく
逆質問を聞かれた場合に何を質問するかの用意も、二次面接に向けて重要な準備です。
面接では最後に「何か聞きたいことはありますか?」と逆質問を求められるケースが多くあるため、とっさに「特にありません」と答えてしまう人もいるでしょう。
しかし、何もないと答えてしまうと、入社への意欲が低いと捉えられ、場合によってはマイナス評価につながる可能性もあります。
逆質問は、就活生が抱えている不安や疑問点を解消する目的のほかに、志望度や意欲を測る目的もあります。
面接の残り時間が少ないようなケースでは、必ず逆質問があるとは限りませんが、用意しておくに越したことはありません。
志望度や意欲の高さをアピールする意味でも、逆質問で何を聞くのか、事前にしっかりと疑問点をピックアップしておきましょう。
二次面接の逆質問について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
選考後にお礼状を出す
一次面接や二次面接後に、メールや手紙などでお礼の連絡ができると、好印象を残せる可能性が高まります。
面接後に一から文章を考えるのは時間がかかるので、事前にある程度準備を進めておき、面接後になるべく早くお礼ができると良いでしょう。
お礼の連絡は絶対に必要なわけではありませんが、意欲が高さや志望度の高さのアピールに少なからずつながります。
また、きちんとした人柄や、丁寧な人柄が伝わる可能性もあります。
志望度の高い企業であるほど、お礼状を出す準備をしておくと良いでしょう。
二次面接の対策方法について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
スキルや経験をまとめておく
二次面接では、これまでのスキルや経験について深く掘り下げられるため、具体的に説明できるように整理しておくことが大切です。
一次面接では基本的な内容が問われますが、二次面接では「どのようにそのスキルを身につけたのか」「どのような状況で活かしたのか」といった詳細な質問が増えます。
例えば、「リーダーシップがある」とアピールする場合は、単に「サークルで部長を務めた」ではなく、「チームの課題をどう分析し、どのような行動を取ったか」を具体的に伝えることが重要です。
また、スキルを裏付ける成功体験や成果も整理しておくと、より説得力が増します。
事前に経験を振り返り、論理的かつ明確に伝えられるよう準備しておきましょう。
入社後のイメージをする
入社後の働き方をしっかりイメージできている学生と、そうでない学生の間には大きな差が生まれます。
企業は「この学生が入社後に活躍できるか」を見極めるため、二次面接では「入社後にどのような業務をしたいか」「どのように成長したいか」といった質問をすることがよくあります。
例えば、「営業職を志望しています」と伝えるだけではなく、「新規開拓に力を入れ、顧客の課題を解決できる営業を目指したい」といった具体的なビジョンを話せると、企業側も採用後の姿をイメージしやすくなります。
企業研究を深め、仕事内容やキャリアパスについて理解を深めることで、より説得力のある受け答えができるようになります。
入社後のビジョンを明確にし、面接官に好印象を与えましょう。
【二次面接の通過率】二次面接で落ちてしまう人の特徴
二次面接で落ちてしまう人には何か共通点が何かあるのでしょうか。
ここでは、その共通点を解説します。
ESと一次面接と内容が違う
「見られているポイント」の所でも記したように二次面接では、一次面接を元に就活生の人柄などを深堀りしていきます。
そこと内容が違ったら一貫性がなく、伝えたいことがわからない状況になってしまいます。
ESなどとの内容には一貫性を持たせましょう。
志望動機が曖昧
志望動機の内容が薄い場合、落ちてしまう可能性が高くなってしまいます。
それはここの会社でなければならない理由がなく、志望度が低いとみられてしまいます。
その企業でなければならない理由を話してアピールしましょう。
自社とのマッチ度が低い
落ちる要因として企業とのマッチ度が低いというケースがあります。
企業は入社後にどのように貢献してくれるかを見ています。
例えば、チームでやる仕事が多い会社で、コミュニケーションが苦手な子を採用することは考えにくいでしょう。
「マッチ度が低い」と思われることがないように、企業研究をしっかり行いましょう。
自分の強みをアピール出来ていない
二次面接では、当然人が減っているのでレベルは上がります。
面接官は、その中であなたの強みは、「仕事の中でどのように活かせるのか」という部分を見て判断します。
面接官が入社後の自分の姿をイメージできるような内容にしましょう。
二次面接で落ちる人の特徴をより詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
意欲が伝わらない
二次面接では、学生のスキルや経験だけでなく、「本当にこの企業で働きたいのか」という意欲が重視されます。
そのため、面接官に対して意欲を十分に伝えられなければ、通過が難しくなる可能性が高いです。
例えば、志望動機が曖昧だったり、他の企業でも通用するような一般的な回答ばかりしていると、「本当に自社を志望しているのか?」と疑問を持たれてしまいます。
また、受け身な姿勢や消極的な態度もマイナスに働きます。
企業研究をしっかり行い、「なぜこの企業で働きたいのか」「入社後にどのように貢献したいのか」を具体的に話せるよう準備することが重要です。
熱意をしっかり伝え、面接官に好印象を残しましょう。
深掘りの質問に対応できない
二次面接では、一次面接よりも踏み込んだ質問が増え、自己PRや志望動機に対する深掘りが行われます。
ここで適切に回答できない場合、不合格となることが多いです。
例えば、「なぜそう考えたのか?」「具体的にどんな行動をしたのか?」「その経験から何を学んだのか?」といった質問に対して曖昧な答えしか返せないと、説得力が欠けてしまいます。
また、表面的な回答ばかりでは、「本当にその経験を活かせるのか?」と面接官に疑問を持たれることもあります。
深掘り質問に備えるためには、過去の経験を振り返り、「なぜ?」「どのように?」を意識して具体的なエピソードを準備することが重要です。
しっかりと準備し、自信を持って答えられるようにしましょう。
入社後のビジョンが考えられていない
二次面接では、「この企業でどのように成長し、どのように貢献していきたいか」という入社後のビジョンが問われることが多くなります。
入社後のビジョンが考えられていないと、企業はその学生の将来性や活躍のイメージを持ちにくくなり、不合格につながる可能性が高いです。
例えば、「入社後に挑戦したいことは?」と聞かれても具体的な回答ができなかったり、仕事内容を十分に理解していないと、「この学生は本当にうちで働きたいのか?」と疑問を持たれてしまいます。
企業研究をしっかり行い、「なぜこの企業で働きたいのか」「どのようにキャリアを積みたいのか」を明確に伝えられるよう準備しましょう。
具体的な目標を話せることで、企業からの評価も高まります。
【二次面接の通過率】 二次面接の通過率を上げる回答のポイント
二次面接では、一次面接よりも深掘りした質問が多くなり、回答の質が合否を左右します。
自分の経験やスキルが企業でどのように活かせるのかを明確に伝えることで、評価が高まります。
ここでは、二次面接の通過率を上げるために意識すべき回答のポイントについて解説します。
志望動機は熱意を伝える
二次面接では、志望動機をどれだけ熱意を持って伝えられるかが重要になります。
一次面接では基本的な志望理由を確認されることが多いですが、二次面接では「なぜこの企業なのか」「他社ではなくこの会社でなければならない理由」を深掘りされます。
熱意を伝えるためには、具体的なエピソードを交えて話すことが大切です。
例えば、「貴社の〇〇という事業に魅力を感じています」と述べるだけでなく、「実際に〇〇を利用し、その価値を実感したため、自分もその成長に貢献したいと考えました」といったように、自分の経験と絡めて話すことで説得力が増します。
企業研究をしっかり行い、熱意が伝わる志望動機を準備しましょう。
入社後のビジョンは具体的に伝える
入社後のビジョンを具体的に伝えることで、面接官の印象に残りやすくなります。
企業は、学生が自社でどのように成長し、貢献できるかを重視しているため、将来のキャリアプランを明確に話せることが重要です。
例えば、「営業職として活躍したいです」と伝えるだけでは抽象的ですが、「〇〇業界に特化した営業を担当し、顧客の課題解決に貢献できる提案力を身につけたい」と話すと、具体的な成長イメージが伝わります。
また、「3年後には〇〇のプロジェクトを担当し、リーダーとして活躍したい」といった目標を示すことで、意欲や計画性がアピールできます。
入社後の働き方をしっかりイメージし、説得力のある回答を準備しましょう。
逆質問は実際に働くことを考えた内容にする
逆質問は、実際に働くことをイメージして質問することが大切です。
企業は、学生の質問内容から「どれだけ入社後を具体的に考えているか」を判断します。
そのため、表面的な質問ではなく、働くことを前提とした質問をすることで、より意欲をアピールできます。
例えば、「御社の研修制度について詳しく教えてください」よりも、「〇〇のスキルを高めるために、入社後に活用できる研修制度はありますか?」と聞くと、自分の成長を意識していることが伝わります。
また、「配属後の評価基準や成長のために意識すべきポイント」などを質問するのも効果的です。
実際に働く姿を想像しながら、面接官に響く逆質問を準備しましょう。
【二次面接の通過率】二次面接で聞くべき逆質問とNGな質問
二次面接の最後には「何か質問はありますか?」と聞かれることがほとんどです。
逆質問は、企業への理解を深めるだけでなく、意欲や入社後のビジョンをアピールするチャンスにもなります。
しかし、質問の内容によっては印象を悪くしてしまうこともあるため注意が必要です。
ここでは、二次面接で聞くべき逆質問と、避けるべきNGな質問をご紹介します。
入社意欲をアピールする質問
逆質問は、単なる情報収集ではなく、入社意欲をアピールする場でもあります。
企業側は「この学生は本当にうちで働きたいのか?」を見極めているため、入社後の働き方を意識した質問をすると好印象を与えられます。
例えば、「入社までに身につけておくべきスキルや知識はありますか?」と質問すれば、成長意欲をアピールできます。
また、「御社で活躍している社員の共通点を教えてください」と聞けば、自分がどのように貢献できるかを考えている姿勢を示せます。
逆に、給与や福利厚生ばかりを気にする質問は印象が悪くなりがちです。
企業の魅力を理解し、自分がどう活躍できるかを意識した質問を準備しましょう。
逆質問のNG例
逆質問は入社意欲をアピールするチャンスですが、内容によっては印象を悪くしてしまうこともあるため注意が必要です。
特に、調べれば分かるような基本的な質問や、待遇面ばかりを気にする質問は避けるべきです。
例えば、「御社の事業内容を教えてください」といった質問は、企業研究をしていないと判断される可能性があり、マイナスの印象を与えます。
また、「残業はどれくらいありますか?」「昇給のペースは?」など、待遇面ばかりを気にする質問は、「この学生は働く意欲よりも条件重視なのでは?」と思われることがあります。
逆質問では、企業や業務に対する関心を示し、「自分がどう貢献できるか」を意識した質問をすることが大切です。
【二次面接の通過率】二次面接が不安な人はエージェントの利用がおすすめ
二次面接のポイントや注意点がわかっても、「面接対策を自分一人で行うのは不安だ…」と感じる就活生も多いのではないでしょうか。
そういった人は、就活エージェントを活用してプロのアドバイザーのサポートを受けるのもおすすめです。
専属のアドバイザーが、内定獲得までの自己分析から面接対策など手厚いサポートをしてくれます。
面接対策では、模擬面接に加え、業界ごとの対策についてもアドバイスを受けることができます。
さらに、大手から中小、ベンチャー企業まで対応したアドバイスを受けることもできるので、エントリーを検討している多くの企業について相談ができるのもうれしいポイントです。
また、模擬面接についてはこちらの記事で紹介しているのでぜひご覧ください。
まとめ
内定を勝ち取るために重要な位置づけとなる二次面接は、何よりも事前準備が重要です。
二次面接を通過したからといって内定が確実になるということはそこまで多くありませんが、内定に大きく一歩近づくことのできる面接であることは間違いありません。
企業側も、就活生のことをより深く理解し、入社して活躍できる人材かどうかを見極めるため、より鋭い質問をするようになります。
しかし、志望度の高さや熱意、仕事に活きる強みをアピールすれば、ほかの就活生と差をつけることができます。
十分な事前準備をして二次面接に臨み、志望企業の内定を手に入れましょう。