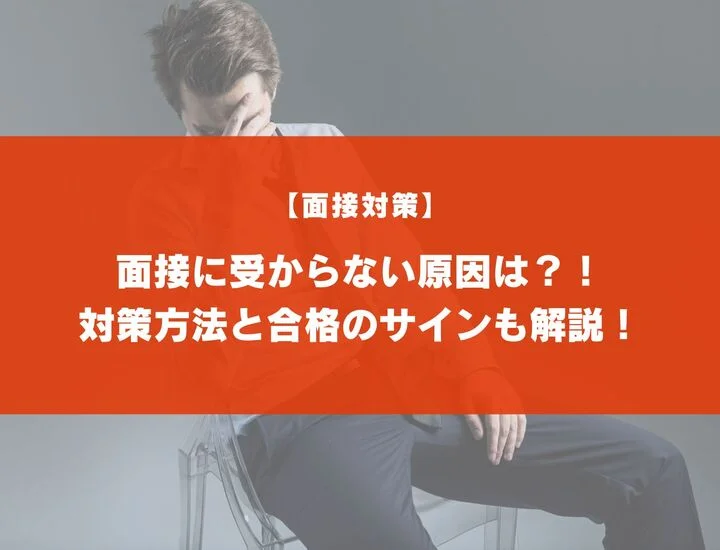明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・公務員のインターンに向けた準備の方法
・面接本番で好印象を残すポイント
・インターン面接でおすすめの逆質問
・インターンに確実に参加したい人
・面接対策をまだ始めていない人
・インターンを本選考につなげたい人
はじめに
公務員のインターンの面接において、どのような対策をすれば良いのか知っている人と、そうでない人とでは本番でのパフォーマンスが大きく異なってきます。
インターンに参加できれば、業務内容への理解が深まるだけでなく、本選考でアピールできる経験や能力が身につけられます。
ぜひこの記事を参考に、まずは公務員のインターンを突破できるよう、しっかりと面接対策を行ってみてください。
公務員インターンとは
- 公務員インターンの基本概要
- 参加するメリットと就職活動への効果
- 面接で参加理由が問われる背景
まずは公務員のインターンとは何なのかについて詳しく紹介します。
基本的な概要と、参加するメリットや就職活動への影響、そして面接で参加理由が問われる背景などについて紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
公務員インターンの基本概要
公務員のインターンは自治体や官公庁が主催する学生向けの短期プログラムで、数日から数週間の期間にわたり職員の業務を体験できます。
多くの場合、大学の夏季・春季休暇に合わせて実施され、対象は大学生・大学院生です。
参加者は政策企画や住民対応、庁内会議への参加、施設見学などを通じて、日常では見えにくい公務員の仕事に触れられます。
こうした体験を通じて、参加者は「公務員の仕事とは何か」を具体的にイメージできるようになり、将来的な進路選択に大きなヒントを得られます。
参加するメリットと就職活動への効果
公務員インターンの参加はただ職場を知るだけでなく、就職活動全体に良い影響を与える手段です。
まず、自分の適性や価値観を職場と照らし合わせることができる点が大きなメリットです。
職員と会話をしたり、仕事の流れを見聞きしたりすれば、公務員としての働き方や課題も明確になります。
また、こうした体験があると、志望動機や自己PRの説得力も格段に増すでしょう。
インターンの中で感じた疑問や学んだことを言語化することで、自分の言葉で説明する力も養われます。
さらに、面接で「なぜその自治体なのか」「公務員のどこに魅力を感じるのか」と問われた時に、実体験に基づいて話せることは、印象を強く残すうえでも非常に有効です。
面接で参加理由が問われる背景
インターン面接では「なぜそのプログラムに参加したいのか」が問われます。
この質問が重視される背景には学生の関心度や目的意識を図る意図があると考えられます。
インターンはただの職場見学ではなく、限られた時間の中で業務に触れ、公務員として働くイメージを持つための機会です。
したがって「何を学びたいのか」「自分の将来にどう結び付けたいのか」といった視点が欠けていると、志望度が低いとみなされる可能性があります。
面接官は応募者の回答からその自治体に対する理解の深さや、自分なりに課題意識を持っているかどうかを見極めています。
目的が明確であればあるほど、インターン中の行動や姿勢も前向きになりやすく、職員に好印象を与えられるでしょう。
面接に向けた事前準備
- 志望動機は公共性や地域貢献を意識して作る
- よくある質問と回答のパターンを押さえる
- 面接で評価されるポイントを理解しておく
- インターンの合否が本選考に影響するケース
- 自治体や官庁の情報を事前にリサーチする
もちろん、インターンだからといって、面接に向けて何も準備をしていないと、選考を突破できません。
以下の5つの対策はいずれも、入念に行っておくべきであると言えるでしょう。
また、本選考の対策にもそのまま繋がるものであるため、ぜひ取り組んでみてください。
志望動機は公共性や地域貢献を意識して作る
公務員のインターンの面接において、志望動機の中核となるのが、公共性と地域貢献の観点です。
民間企業の利益追求型の志望動機とは異なり、住民の生活や社会課題、社会全体の課題に関する関心と行動意欲が問われます。
そのため、自分自身の経験と照らし合わせながら、どのような価値観から公務に携わりたいと思うようになったのかを言語化する必要があります。
また「ただ困っている人の役に立ちたい」などの言葉では不十分です。
地域が抱える課題や、その中で自分が貢献できると思った理由などを含めることで、より説得力のある内容になるでしょう。
よくある質問と回答のパターンを押さえる
インターン面接では定番とされる質問が複数あります。
代表的なものに、志望動機、自己PR、学生時代に力を入れたこと、インターンで得たいことなどが挙げられます。
これは事前準備の有無が明確に現れる質問であり、流れ作業のように受け答えしてしまうと、志望度が低く見えてしまう可能性が高いです。
質問の意図を汲み取って、自分の経験と関連付けて話せるようにしましょう。
「学生時代に力を入れたこと」を例に挙げるならば「行動」だけでなく、その経験から得た「学び」が重要です。
面接で評価されるポイントを理解しておく
インターン面接は表面的な言葉よりもその人の姿勢や考え方に注目が集まります。
特に公務員を目指す場合は誠実性や協調性、責任感といった人格面が重視される傾向にあります。
話す内容そのものよりも、それをどのように語るか、言葉にどのような思考の深さがあるかが見られているのです。
したがって、模範解答のような内容を一方的に話すのではなく、自分の体験に根ざしたエピソードをもとに、率直かつ一貫した説明ができるよう心がけることが大切です。
準備した内容をただ丸暗記するのではなく、自分の価値観や経験と照らし合わせながら話しましょう。
インターンの合否が本選考に影響するケース
一部の自治体や官公庁ではインターンの参加者に対して面接評価を行い、その結果が後の本選考に反映される場合もあります。
表向きは「選考」と明示していなくても、参加中の姿勢などが職員の記憶には残るため、インターンを通じた印象が後々の選考に影響を及ぼすことは少なくありません。
つまり、インターンだからといって気を抜くのではなく、本選考と同等の意識で臨むことが必要です。
受け答えや振る舞いだけでなく、報連相などの基本的な行動が問われることがあります。
限られた期間の中で、自分がどれだけ主体的に取り組もうとしているか、また吸収しようとしているかを示すことが評価に直結します。
自治体や官庁の情報を事前にリサーチする
面接に向けた準備として欠かせないのが、応募先の自治体や官庁に対する情報収集です。
公式サイトに掲載されている施策、政策方針や組織図、重点施策、過去の事業実績などについて、しっかり目を通し、面接の際にそれを踏まえた受け答えができるようにしておく必要があります。
ただ名称や概要を把握するだけでなく、自分がどの部分に関心を持ったのか、どのような問題意識を感じたのかを言葉にできるようにしておくと、面接官に対して高い関心と理解度をアピールできます。
面接本番で好印象を残すポイント
- 重視されるのは誠実さと基本的なマナー
- 内容よりも考え方や伝え方の一貫性が重要
- 逆質問で主体性と関心をアピールする
続いて、面接の本番で好印象を残すにあたって意識しておきたいポイントについて紹介します。
以下の3点を本番前に思い出せば、面接官に好印象を与えられる可能性が高まることでしょう。
ぜひ忘れないように、読んだ後はどこかにメモしておいてください。
重視されるのは誠実さと基本的なマナー
公務員の面接において、特に重視されるのは受け答えの内容以上に受験者の人柄や姿勢です。
特に誠実さや丁寧な態度は自治体の職員としてふさわしいかどうかを判断する基準として強く意識されます。
また、入退室の仕方、座り方、アイコンタクトなど基本的なマナーも、日常の態度や協調性を推し量る材料とされています。
マナーに自信がない場合は、事前に面接練習を何度も行い、適切な振る舞いができるように準備しておくと安心です。
内容よりも考え方や伝え方の一貫性が重要
インターンの面接では話の中身以上に、どのような価値観や考え方を持っているかが重視されます。
用意されたエピソードがどれだけ印象的であっても、思考の筋道が曖昧であれば評価は上がりにくいでしょう。
重要なのは「経験を通して何を学び、どう行動に移したのか」という一連の流れを矛盾なく説明できることです。
形式的なエピソードを並べるだけでなく、自分らしい言葉で経験を語り、それらを通じてどのような人物であるかを伝えることが、面接官にあなたの人柄を伝え、信頼感を与えるポイントです。
逆質問で主体性と関心をアピールする
面接の最後に設けられることが多い逆質問の時間は、受験者の関心や姿勢が最もよく現れる場面です。
この時にどのような質問をするかによって、その自治体や職務にどれほどの理解と関心を持っているかが明確になります。
組織の取り組みや方針について質問したり、職員として大切にしている価値観について尋ねたりすると、主体的な姿勢をアピールできます。
ここで気をつけたいのが「調べればすぐわかる情報を質問しないこと」です。
自治体の公式サイトや募集要項に載っているような基本情報を確認するような質問だと、準備不足の印象を与えてしまいます。
事前に調べた内容を踏まえて、自分の考えや疑問をさらに深掘りするような質問が望ましいです。
インターン当日の服装と身だしなみ
- スーツか私服かの判断基準と注意点
- 男女別のおすすめ服装と避けるべきアイテム
- 髪型や持ち物など細かい部分の印象管理
インターン当日の服装と身だしなみについても、いくつか覚えておいていただきたいポイントが存在します。
人は見た目が9割とも言われるように、服装と身だしなみは第一印象を大きく左右するものであるため、ぜひ覚えておいてください。
スーツか私服かの判断基準と注意点
インターン当日の服装について最初に確認すべきなのは、自治体からの案内文や事前メールに服装に関する規定があるかどうかです。
「服装自由」や「私服で構いません」と記載されることもありますが、その言葉をそのまま受け取り、カジュアルすぎる格好で参加してしまうと、印象を損ねる可能性があります。
したがって、たとえ「私服可」とされていたとしても「ビジネスカジュアル」程度の、かっちりとした服装を意識しておいた方が無難です。
また、服装指定がない場合はスーツを着用するのが基本です。
男女別のおすすめ服装と避けるべきアイテム
インターンの服装では、性別に関係なく清潔感と整った印象を与えられるかどうかが重要となります。
男性の場合はワイシャツにスラックス、必要であればネクタイとジャケットを合わせて、落ち着いた印象を与えることが大切です。
シャツのしわや汚れ、サイズ感には特に注意し、靴やベルトも派手すぎないものを選びましょう。
一方、女性の場合はブラウスに膝丈のスカートやスラックスを合わせた、上品で動きやすいスタイルが好まれます。
ヒールの高すぎる靴や露出の多い服装は避け、メイクも濃くなりすぎないように控えめに整えることが重要です。
また、大きすぎるアクセサリーなども外して行った方が良いでしょう。
どちらの性別でも、カジュアルすぎる格好だと、公的な場にふさわしくないと判断されてしまいます。
インターンは「職場の一員として迎えられる場面」でもあるため、服装によって自分の社会性や常識が問われていることを意識して準備しましょう。
髪型や持ち物など細かい部分の印象管理
服装と同じくらい重要なのが、髪型や持ち物といった細部にわたる身だしなみです。
髪型は男女ともに顔がしっかり見えるように整えることが基本であり、乱れや寝癖がないかは当日の朝に必ずチェックしてください。
男性は清潔感のある短髪が望ましく、女性は髪をまとめ、降ろす場合でも巻き髪など、華やかすぎる髪型は避けましょう。
爪の長さや手の清潔さにも注意が必要で、見られている部分であることを忘れないようにしてください。
また、靴やカバンなどの小物にも気を配る必要があります。
汚れたスニーカーや装飾の多いバッグではなく、シンプルで機能的なものを選びましょう。
インターン当日のマナーと行動
- 時間厳守とあいさつで社会人としての基本を示す
- メモを取る姿勢やリアクションで積極性を見せる
- 終了後はお礼メールと振り返りで好印象をキープ
続いて、インターンに参加が決まった際に、当日押さえておきたいマナーや行動について紹介します。
以下の点を知っている人と、そうでない人とでは与えられる印象が大きく異なりますから、ぜひ参考にしてみてください。
時間厳守とあいさつで社会人としての基本を示す
インターン当日は公務員という職業の特性を考えても、時間に対する意識が非常に重要になります。
遅刻はもちろん、ギリギリの到着も印象を下げる要因になります。
最近は「就業時間までに到着していれば良い」という企業も多いですが、公務員のインターンの時は少なくとも、10分前程度には到着しておいた方が良いでしょう。
また、訪問時や面会時には、明るくはっきりとしたあいさつを行うことが大切です。
「よろしくお願いしまーす」などと語尾を伸ばしてしまう人も多いですが、失礼であると捉えられることが多いため、気をつけましょう。
メモを取る姿勢やリアクションで積極性を見せる
インターン中はどのような業務内容であっても「学ぶ姿勢を持つ」ことが大前提となります。
その姿勢を外から見てわかる形で示す手段の1つが、メモを取ることです。
重要だと思った点を記録したり、わからなかった用語を書き留めたりすることで、やる気を持って参加していることが相手にも伝わります。
また、アイコンタクトを取り、うなずきなどのリアクションをすれば、話している側も気持ちよいです。
「理解しよう」と努めていることを態度で示すことが、評価を左右する要因になるでしょう。
大げさにアピールする必要はありませんが、無反応で、ただぼーっと聞いているよりは確実に印象が良いです。
終了後はお礼メールと振り返りで好印象をキープ
インターンが終了した後も、丁寧な対応をし続けることが大切です。
当日中、できるだけ早い時間に担当者にお礼のメールを送りましょう。
その際はただ「ありがとうございました」と述べるだけでなく、印象に残った出来事などを一文添えることで、誠実さと感謝の気持ちを伝えることができます。
また、その日のうちにインターンの内容を振り返り、どのようなことを学んだか、何が課題として残ったかをメモにまとめておくと、今後の本選考にもつなげやすくなります。
その場限りで終わらせるのではなく、自分の中に落とし込んで言語化しておくことで、志望動機や自己PRの説得力を高められます。
インターン面接でおすすめの逆質問15選
ここからはインターンの面接でおすすめの逆質問を15個紹介します。
いずれの質問も意欲の高さが伝わりつつ、インターンに参加するうえであなたが知りたいと思うことを明確にできる、おすすめの質問です。
自分が何を知りたいか、どのような印象を与えたいか、考えながら読んでみてください。
業務や働き方に関する質問
業務や働き方に関する質問は配属後の自分の姿を具体的に想像するうえで有益です。
面接時にこのような質問をすることで、業務への関心や理解しようとする姿勢が伝わります。
また、公務員の仕事は職種や部署によって幅があるため、実際の業務内容を知ろうとする態度は志望度の高さの表明にもつながります。
1日のスケジュールについて
実際に働く現場の1日のスケジュールを聞くことで、職員の働き方やリズムを把握できます。
公務員の仕事は定時で帰れるイメージを持たれがちですが、業務内容や部署によって異なります。
そのギャップを面接時に確認しておくことで、入庁後のミスマッチを防げるでしょう。
また、職員がどのようなタイムスケジュールで仕事をしているのかを具体的に聞くことで「自分が働くとしたらどんな1日を過ごすのか」をより現実的に想像できるようになります。
【質問例】
若手職員の方は1日のなかでどのようなスケジュールで業務に取り組まれていることが多いですか。
繁忙期や仕事の山場はいつか
繁忙期や仕事の山場を把握することで、1年間の業務の流れや、職場がどのように忙しさを乗り越えているのかが見えてきます。
「繁忙期=避けたいもの」という意識を持つのではなく、組織にとって大事な時期であることを理解し、そこにどう向き合うかを知ろうとする姿勢が評価されます。
この質問は業務理解の深さを示すとともに、自分の働き方のイメージを描くヒントにもなるでしょう。
【質問例】
年間を通して特に業務が集中する時期や、職場全体が忙しくなるタイミングについて教えていただけますか?
若手職員の主な担当業務について
若手職員の仕事内容はみなさんにとって最も関心の高いテーマの1つでしょう。
面接時にこの質問をすることで「実際に自分が最初に何を担当するのか」「どのような立場からキャリアが始まるのか」がイメージできます。
また、若手の成長を支える環境や、早い段階から任される業務のレベルを知ることもでき、組織の雰囲気や教育体制の特徴を探る手がかりにもなります。
志望動機に深みを持たせる材料にもなるため、非常に有効です。
【質問例】
若手職員の方は入庁後どのような業務を任されることが多いですか?
また、そのなかで責任の大きさや工夫が求められる場面があれば教えてください。
やりがいや大変さに関する質問
やりがいと大変さの両方を聞くことで、職場の魅力と現実をバランスよく把握できます。
どちらか一方だけに偏った質問は「志望動機が弱い」と見なされる可能性があるため、正直な姿勢で双方に関心を持っていることを示すのが効果的です。
特に公務員の仕事は「人の役に立つことがやりがい」などと抽象的に語られがちな分野です。
そこで「大変な時にどう工夫したか」なども聞くことで、その人自身の価値観や組織の体制も見えてきます。
この仕事のやりがいは何か
やりがいについて質問することで、その職場の仕事が社会にどう貢献しているかや、職員がどのような価値を感じながら働いているかが見えてきます。
特に公務員の仕事は数値化しづらい成果や地域貢献などを扱うことが多いため、やりがいの内容は人によって異なります。
そのため、実際に働く方がやりがいを感じる具体的な瞬間を知ることで、仕事への理解を深め、自分が共感できる職場かどうかを見極めることが大切です。
【質問例】
日々の業務のなかで、やりがいを感じるのはどのような場面ですか?
また、そのやりがいは入庁前のイメージと比べてどのような違いがありましたか?
大変だった経験とその乗り越え方
仕事の大変さや困難な経験を聞くことは、職場のリアルな姿を知るうえで欠かせません。
さらに、その困難をどのように乗り越えたのかまで聞くことで、組織としてのサポート体制や個人の工夫を知ることができます。
この質問には「苦労に対してどう向き合う姿勢が求められるか」を理解しようとする意図が込められているため「楽な職場を求めているだけだな」という印象にはなりません。
【質問例】
これまでの業務で特に大変だったことや、苦労された経験があれば教えていただけますか?
また、その場面をどう乗り越えたのかも知りたいです。
職場の雰囲気や人間関係に関する質問
職場の雰囲気や人間関係は業務内容と並んで、就職先選びで重要な要素です。
仕事内容が魅力的であっても、職場の人間関係が合わなければ長く働き続けるのは難しいため、あらかじめ雰囲気を確認することはとても有意義です。
「チームの距離感」「上下関係」「声のかけやすさ」などを掘り下げることで、組織文化を知ることができます。
また、逆質問でこのテーマを選ぶと「働く環境や人間関係を重視している」といった堅実な志望姿勢が伝わるでしょう。
チームの雰囲気や関係性について
チームの雰囲気や職員同士の関係性を尋ねることは、組織の働きやすさや相互理解の深さを知る重要なきっかけになります。
公務員の仕事は協力体制が求められることが多いため「どのように情報共有しているか」「困ったときに助け合える雰囲気があるか」といった点は重要な判断材料になります。
このような質問は雰囲気を知るだけでなく、入庁後の働き方や人間関係の形成の仕方を具体的にイメージする材料になるでしょう。
【質問例】
チーム内での雰囲気や、若手職員とベテラン職員との関係性について教えていただけますか?
日常的なやりとりや雰囲気がどのようなものか知りたいと考えています。
相談のしやすさや風通しの良さについて
「相談のしやすさ」や「風通しの良さ」は安心して長く働ける職場かどうかを見極めるためのポイントになります。
特に公務員の組織は縦割りや年功序列の制度が色濃い現場も多いため、現場の職員が相談しやすいと感じているかを確認することで、入庁後の不安を減らせます。
また「ミスをしたときにどのような対応がされるか」や「困ったときに誰に相談できるか」といった実情を聞くことで、その組織の信頼関係のあり方が見えてくるでしょう。
【質問例】
新人の方が悩んだときや業務で困った場面で、先輩や上司の方に相談しやすい雰囲気はありますか?
どのようにフォローされるのかもお聞きしたいです。
キャリアや制度に関する質問
キャリア制度に関する質問は将来の働き方や成長のイメージを具体的に持っていることを示すのに役立ちます。
特に公務員の場合、民間と違って異動や研修の制度が組織全体で整備されており、異動によって担当業務が大きく変わる可能性もあります。
そのため、異動の頻度やキャリアの積み上げ方について質問して、自分がその組織でどう成長できるかを考えている姿勢を伝えましょう。
異動の頻度や範囲について
異動の頻度や範囲を知ることで、自分がどのような環境で働き続けるのか、将来的にどのような経験ができるのかが推測できます。
特に公務員は複数の部署を経験する前提でキャリアが設計されているケースが多く、配属後も長期的に働くことを前提とするなら、異動制度への理解は不可欠です。
また、異動にどのようなメリットがあるのかや、不安に感じることへのサポート体制について聞くことで、制度面だけでなく組織の柔軟性も確認できます。
【質問例】
異動の頻度や、担当する業務や所属先の範囲について教えていただけますか?
研修制度やキャリア支援の仕組み
研修制度やキャリア支援について質問することで、組織が人材をどのように育成しているかや、成長のチャンスがどのように与えられているかを知ることができます。
特に新人職員向けの研修や年次別・階層別の研修制度の有無などを確認することで、初期の不安が和らぐだけでなく、将来的なスキルアップの道筋も見えてきます。
また「職員一人ひとりのキャリアを大切にしているかどうか」という組織の方針を知るうえでも重要な観点です。
学生時代にやっておくと良いこと
この質問は「学生として今の自分に何ができるか」を真剣に考えている姿勢を示せるテーマです。
公務員として働くうえで求められる素養や考え方は必ずしも学業だけで身につくものとは限りません。
そのため、社会人として働くために役立つ経験や、学生時代に積んでおくと良かったと職員が感じていることを尋ねることで、自分の行動指針を具体化できます。
【質問例】
学生時代にやっておいて良かったと感じている経験や、今の自分にも活かせると感じた取り組みがあれば教えていただきたいです。
この仕事に向いている人の特徴
この質問をすることで、自分がその仕事に合っているかを判断するだけでなく「職員として何が求められるのか」を知ろうとする前向きな姿勢が伝わります。
表面的な適性だけでなく、どのような価値観や態度が日々の業務で活きているかを職員の視点から聞くことで、より具体的な職務理解につながります。
また、このテーマは自分自身の自己分析ともつながっているため、逆質問として活用することで、面接中の自己PRや志望動機にも一貫性を持たせられるでしょう。
【質問例】
日々の業務を通して、どのような性格や考え方を持つ方が活躍していると感じますか?
周囲の職員の方々の共通点などもあれば教えてください。
インターンで避けたいNG質問
- 調べればわかる情報をそのまま聞く
- 給与や休暇など待遇ばかりを深掘りする
- プライベートに踏み込む質問をする
- 否定的または上から目線に聞こえる質問をする
続いて、インターンにおいて避けるべきNGな質問の特徴について紹介します。
以下のような質問をしてしまうと悪い印象を与え、インターンで仕事を任せてもらえないこともあるかもしれませんし、その後の本選考に響くこともあるでしょう。
ぜひ以下の4点は注意点として覚えておいてください。
調べればわかる情報をそのまま聞く
インターン中の逆質問では基本的な情報は事前に調べておくことが大切です。
自治体や官公庁の公式サイトには事業概要や組織の取り組み、方針など基本的な情報が網羅されています。
そうした内容を確認せずに質問してしまうと、準備を怠った印象を与えてしまう可能性が高いです。
面接官は学生の関心や質問内容から意欲を読み取ろうとしますが、基礎的な情報ばかり尋ねると「調べる意欲がない」「関心が薄い」と思われてしまいます。
【質問例】
〇〇市では子育て支援として〇〇制度を導入されていると拝見しましたが、運用する中で工夫されている点があれば教えていただけますか。
給与や休暇など待遇ばかりを深掘りする
待遇に関する質問はタイミングや聞き方によって印象が大きく分かれます。
公務員のインターンでは仕事内容や社会的な役割への関心を示すことが大切です。
ところが、給与や休暇制度など待遇ばかりに関心を示す質問ばかりだと「働く意義」や「責任感」については興味がないと受け止められてしまいます。
もちろん、働くうえで条件面を確認すること自体は問題ではありませんが、それが質問の中心になると目的意識が見えにくくなります。
「安定性だけを重視していて、仕事にやる気がない人だ」と思われないように注意しましょう。
【質問例】
残業時間の平均について伺ってもよろしいでしょうか。
プライベートに踏み込む質問をする
インターンはあくまで職場体験の一環であり、ビジネス上の関係性を意識して行動することが大切です。
担当職員との距離感を誤ると、思わぬところで印象を損ねてしまう可能性があります。
特に注意したいのが、相手の私生活に関する質問です。
プライベートな情報に対しては答えづらいこともあり、軽い気持ちで聞いた内容が失礼に当たることもあります。
質問の焦点は常に業務や施策、組織の取り組みに置くべきであり、個人的な話題への言及は避けるべきです。
親しみのつもりでも、社会人の視点から見ればマナー違反と判断されることもあります。
【質問例】
〇〇さんは休みの日、何をされていますか?
否定的または上から目線に聞こえる質問をする
自分の考えを持つことは大切ですが、その伝え方が否定的だったり、自分の方が優れていると示唆するような表現になったりしてしまうと、非常に悪い印象を与えてしまいます。
公務員の業務は住民の意見など、様々な制約の中で行われることが多く、外部の立場では想像しにくい事情も存在します。
そうした背景を無視して一方的な意見を述べたり「なぜこうしないのか」と否定的な質問をしたりすると、相手の取り組みを軽視しているように受け取られます。
もちろん、公務員の業務の中には誰が見ても非効率に思えるものもありますが「そんなことを言われても、私の一存で改善できるわけではないんだよ」と相手をイライラさせてしまうでしょう。
【質問例】
〇〇の制度は非効率に思えるのですが、変えようとはされないのですか?
インターン経験を本選考に活かす方法
- インターン体験を志望動機や自己PRに反映する
- 実際に見た職場の様子や学びを具体化する
- 落ちた場合も経験として次に活かす考え方
続いて、インターンの経験を本選考に活かす方法について紹介します。
ただインターンに参加して満足するだけでは、せっかくの貴重な体験をフル活用できません。
以下の3つの取り組みを行い、インターン経験を本選考に還元してください。
インターン体験を志望動機や自己PRに反映する
インターンシップを通じて得た経験は、本選考で志望動機や自己PRを語る際に非常に重要な要素となります。
現場での体験を通じて、自分の関心がどのように深まったのか、どのような場面で自分の強みを活かせるのかを振り返りながら、自分の言葉で表現することが求められます。
ただ参加したという事実だけでなく、何を感じ、何を学び、自分にとってどのような意味があったのかを明確にすることで、説得力あるアピールが可能になります。
また、その経験を通じて志望先の業務内容や職場環境が自分に合っていると感じた根拠を言語化しておくと、より一貫性のある志望動機になります。
実際に見た職場の様子や学びを具体化する
インターン中に見聞きした職場の雰囲気や業務の流れ、職員の姿勢などは志望動機や自己PRを組み立てるうえで大きなヒントになります。
ただし、それを表面的に語るだけでは不十分です。
重要なのはその光景や出来事が自分にどのような影響を与え、どのような考えや価値観につながったのかという点です。
住民の声に耳を傾ける職員の姿を見たならば、その様子から自分が何を学び、どのような行動への意識の変化があったのかを深掘りしましょう。
さらに、その学びが今後どのように自分の働き方に反映されるのかまで伝えられると、具体的な志望動機の根拠として機能します。
落ちた場合も経験として次に活かす考え方
インターンの選考や参加後の評価で思うような結果が得られなかったとしても、その経験は決して無駄にはなりません。
不合格という結果に直面した時こそ、自分の課題や強化すべき点を見直す絶好の機会です。
大切なのは、その過程で何に気づき、次にどうつなげようとしているのかを明確にすることです。
うまくいかなかった理由を分析し、その反省を具体的な行動に移せば、次の選考でより強いアピールが可能になります。
「反省」をただの「後悔」に終わらせるのではなく、自分を客観的に見つめ直す機会として前向きに捉えることで、成長できるでしょう。
まとめ
今回は公務員のインターンを受ける方が面接においてどのような振る舞いをすべきか、どのような質問をすれば良い印象を与えられるかなどについて詳しく紹介しました。
インターンといえど、面接は選考において非常に重要な役割を果たすものです。
ぜひこの記事を参考に、印象の良い振る舞いや質問の回答を行い、インターンへの参加を勝ち取ってください。





_720x550.webp)