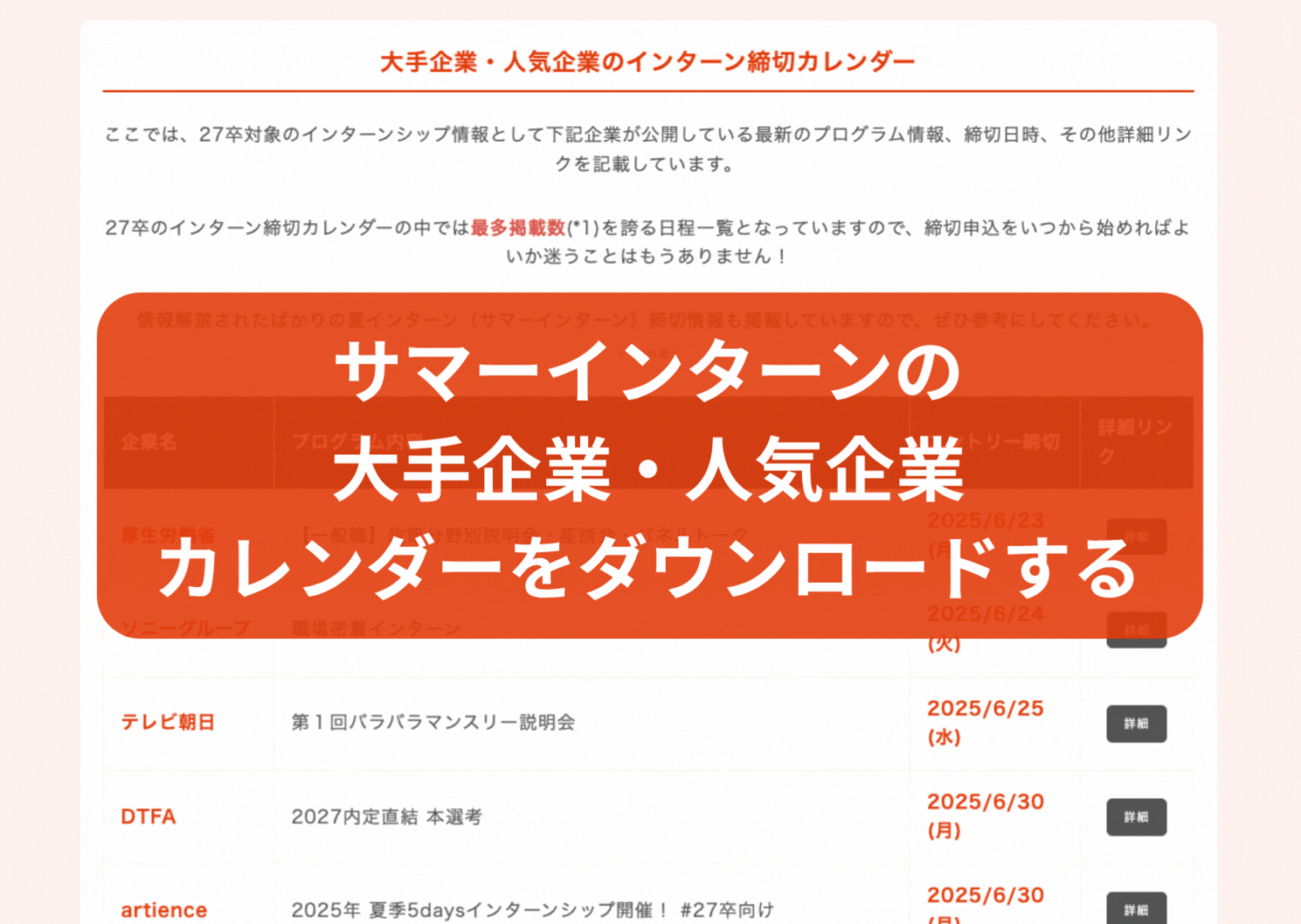目次[目次を全て表示する]
ファーストリテイリングのサマーインターンで自己PRが求められる場面とは
ファーストリテイリングのサマーインターンは、単なる職業体験にとどまらず、将来のグローバルリーダー候補を発掘・育成する位置づけで実施されており、選考における「自己PR」の重みも非常に大きくなっています。
ユニクロやGUといったブランドを展開する同社は、「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」という理念のもと、変革者としてのマインドセットを持つ学生を求めています。
そのため、インターンの選考過程では、受け身の学生や表面的な自己紹介しかできない学生よりも、自分の言葉でなぜその行動を取ったのかを語れる人物が高く評価される傾向にあります。
自己PRは単なる通過要素ではなく、その人の「意思決定力」「行動力」「価値観」といったファーストリテイリングの根幹と通じる部分を見抜くための最重要材料とされているのです。
ES(エントリーシート)での自由記述が基本形式
まず選考の入口となるエントリーシート(ES)では、自由記述形式の自己PRが課されます。
典型的な設問としては、「学生時代に最も力を入れたこと」「あなたが周囲に良い影響を与えた経験」などが見られ、文字数は300~400字程度で構成されるのが一般的です。
中には、日本語と英語の併記を求められる年もあるため、語学面の準備があると安心です。
重要なのは、このES段階で「行動の背景にある意志」まで丁寧に書き込めているかどうかです。
ファーストリテイリングでは、結果そのものよりも「自分で考え、自分で動いたか」という行動の主体性を強く評価します。
また、「売上を上げた」「リーダーを務めた」といった実績を並べるだけでは不十分であり、「なぜそれに取り組もうと思ったのか」「どんな価値観がそこにあったのか」といった深層部分まで踏み込んだ記述が求められます。
さらに、企業理念やブランド精神との接続を意識することも大切です。
例えば、ユニクロが重視するLifeWearのように、「誰かの生活をより良くするために行動した経験」などを織り交ぜることで、企業との親和性をより強く印象づけることができます。
面接やグループディスカッションでも一貫性が見られている
ESを通過した後の個別面接やグループディスカッション(GD)では、ESで提出した自己PRの内容が再び問われます。
ただし、それは単なる確認ではありません。
面接官や評価者は、ESに書かれた内容と、実際の言動や思考に一貫性があるかを非常に細かく見ています。
面接では「その行動を選んだ理由」「実行時に迷いはなかったのか」「結果に対してどう感じたか」といった深掘りがされ、自分自身の価値観や判断基準を明確に語れるかが問われます。
自己PRで「挑戦した」と記載していても、面接で「周囲に言われたのでやってみただけです」と答えてしまえば、すぐに矛盾が露見してしまいます。
グループディスカッションでは、自己PRの内容が直接話題になることは少ないものの、自己PRに紐づく「自分らしさ」が発言や行動に現れるかどうかが見られています。
たとえば、ESで「主体的に物事を進めた経験」を語った学生が、GDの場で周囲の発言をただ聞いているだけで終わってしまえば、「発言内容と行動が一致していない」と判断される可能性があります。
自己PRは選考全体を通じた判断軸になる
ファーストリテイリングのインターン選考では、自己PRが単なるエントリーポイントではなく、選考の最初から最後まで「人材評価の軸」として機能します。
面接官や選考担当者は、ESに書かれたPRと、面接での態度、GDでのふるまい、さらにはインターン参加後の行動までを一貫して観察し、「この学生はファーストリテイリングの価値観と親和性があるか」「将来、同社の変革を担う人材になり得るか」を見極めようとしています。
このため、自己PRは一貫性と深さが重要です。
選考を通じて何度も問われる可能性があるからこそ、自分の核となる価値観を中心に据え、どの場面でもブレずに語れるストーリーを構築する必要があります。
「自分は何者なのか」「なぜこの行動を取ったのか」「どんな未来を描いているのか」といった問いに対して、自分の言葉で語れるよう準備しておくことが、インターン通過への鍵となります。
自己PRの設問形式と文字数の傾向|サマーインターン選考での実例
ファーストリテイリングのサマーインターン選考では、応募者の人となりや価値観、そして「行動の背景にある意志力」を見極めるために、毎年一定の傾向に沿った自己PR設問が課されます。
設問自体はオーソドックスなテーマでありながら、評価の観点は極めて企業独自のものとなっており、単なる経験談の羅列では通用しない設計になっています。
ESでの自己PRは、数百字という限られた文字数の中に「行動の理由」「挑戦のプロセス」「結果から得た学び」までをバランス良く含める必要があり、完成度の高さが問われるパートです。
また、場合によっては英語での記述を求められることもあり、ファーストリテイリングのグローバル志向を体現できるかも見られています。
過去のESでは「学生時代に力を入れたこと(400字)」が頻出
ファーストリテイリングの過去のサマーインターンESでは、「学生時代に最も力を入れたこと」あるいは「自分の強みが発揮された経験」などの王道テーマが出題されるケースが多くあります。
文字数の指定は概ね400字前後で、与えられた分量の中に論理的な構成と明確な結論を含めなければならず、非常に高度な文章力と構成力が求められます。
この設問で重視されているのは、何をやったかではなく、なぜその挑戦を選び、どのように行動したかです。
つまり、行動の背景にある「意思決定の質」が問われており、表面的な成果よりも、その成果に至るまでの思考や努力の痕跡にファーストリテイリングの評価軸が置かれているのです。
また、具体性が欠けている文章や、抽象的なアピールで埋め尽くされた内容は「再現性がない」と見なされ、通過率が下がる傾向があります。
英語力を見られるケースもあり「英語PR」欄が設けられることも
一部の年度やグローバル志向が強いコースでは、自己PRを「英語で記述せよ」といった設問が設けられるケースも報告されています。
これは同社が「世界中の店舗と人材を動かすグローバル企業」であることを強く意識しているためであり、言語能力の有無を測る目的というよりは、「伝える力」「構造的に考える力」「文化を越えて価値を届ける力」を見ていると考えられます。
このような英語設問では、完璧な英語表現よりも、「自分の経験を簡潔に、筋道立てて説明するスキル」が評価の対象となります。
文法の正確さよりも、行動と価値観のつながりが明瞭か、同社の求める変革力や主体性が英語でも表現されているかどうかが鍵となります。
また、こうした英語設問は事前に周知されるとは限らず、応募段階や選考ステップの途中で突然提示されることもあります。
あらかじめ、自分のPRを英語でも整理しておくと安心です。
回答内容に数字や具体的行動があるかがカギ
自己PRの記述において、ファーストリテイリングでは「どれだけ行動を具体的に描写できているか」が合否を分ける重要なポイントになります。
特に、曖昧な形容詞や抽象的な評価ではなく、数字・実績・変化などの具体的な証拠があると、評価が高まりやすくなります。
たとえば、「売上が上がった」ではなく「前年比で120%の売上を達成した」、「部活動で努力した」ではなく「週5日3時間、年間を通じて新メニューの開発に取り組んだ」といったように、行動の量や質を明確に伝えることが重要です。
これにより、読んだ側が「その行動にどれだけ本気だったか」「どれほど主体性があったか」を具体的にイメージできるようになります。
また、数値だけでなく、状況の変化や周囲への影響といった文脈のある描写も重視されます。
「何をしたのか」だけでなく、「なぜそれをしたのか」「その結果、どう環境が変わったか」というストーリーの流れを明確に伝えることで、読み手に強い納得感を与えることができます。
ファーストリテイリングに響く自己PRの共通点とは?
ファーストリテイリングのサマーインターンにおいて、高く評価される自己PRには、いくつかの明確な共通点があります。
それは、単に経験を語るだけでなく、「なぜそう動いたのか」「どのような価値観で行動を選んだのか」といった、行動の動機と主体性に深く根ざした内容であることです。
同社は企業理念として、「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」という変革志向を掲げており、それに共鳴する個人の意志を非常に重視します。
したがって、他者に依存した協調性よりも、自分の頭で考え、意志を持って行動した経験の方が評価される傾向にあります。
ここでは、通過者に共通して見られる自己PRの特徴を掘り下げて紹介します。
「やると決めたらやり抜く」姿勢が伝わるエピソードが強い
ファーストリテイリングの選考では、一度決めた目標に対して、どれだけ本気でやり抜いたかという「意思の強さ」が見られています。
これは、単に頑張ったという話ではなく、困難や壁に直面しても「諦めずに続けた」「試行錯誤を重ねて乗り越えた」といった、粘り強さと継続力に裏付けられたストーリーが求められているということです。
例えば、「メンバーが途中で辞めてしまった中で、最後までプロジェクトを完遂した」「初めての営業で何度も失敗したが、自ら改善点を見つけて契約に繋げた」といったように、行動の継続と改善努力が伝わる内容は非常に好印象を与えます。
企業としても、スピード感と実行力を武器に世界展開してきたファーストリテイリングにとって、「決めたことを、必ずやり切る人材」は極めて重要です。
その姿勢を言葉や経験で伝えられるかが、選考突破の大きなカギになります。
自分で課題を見つけ、即行動・即実行した体験が評価される
ファーストリテイリングのインターン選考では、誰かに指示されて動いたエピソードよりも、「自分で課題を見つけ、自発的に解決に向けて動いた経験」が強く評価されます。
これは、同社が自ら考えて動く人材を中心に組織を構築しているためであり、受け身で指示待ちの人材とは文化的に相性が良くないためです。
高評価されるのは、たとえばアルバイト先での「在庫の動きに課題を感じ、自ら発注の仕組みを改善した」といった、現場で課題に気づき、即行動に移したようなエピソードです。
行動のスピードや決断力も評価の対象になるため、「まずやってみる」「やりながら修正する」といったアプローチが伝わる内容だと、よりファーストリテイリングらしさが表現できます。
この企業では、「考える前にまず一歩踏み出す」くらいの行動力が推奨されており、自己PRでも行動の先手を打った経験があるかが問われていると考えるとよいでしょう。
チームではなく「自分がどう動いたか」にフォーカスする
チーム活動のエピソードを語ること自体は悪くありませんが、ファーストリテイリングにおいては、チーム全体の動きよりも「自分自身がどう行動したか」が重要視されます。
つまり、リーダーであっても、フォロワーであっても、「自分の意志と判断でどう価値を出したか」が明確に語られていないと評価に繋がりません。
例えば、「チームでの目標達成に向けて、意見が対立する中、自分がファシリテーター役を担い、方向性をまとめた」といったように、自分の果たした役割を具体的に描写することで、個の価値が伝わる構成になります。
「皆で協力しました」「チームで工夫しました」といった抽象的な表現では、個人の判断力や行動力が見えず、企業が求める自律的な挑戦者像とはギャップが生じます。
むしろ、少人数の活動や、個人の挑戦でも「自分が選び、動き、変化を起こした」経験であれば、十分に選考を突破できる可能性があります。
ファーストリテイリングは、主体性のないチームワークよりも、意志を持った個人の行動から始まる変革を重視する企業です。
そのため、自己PRでも「私はどう考え、どう行動したか」という私軸を明確に打ち出すことが何より重要です。
通過者の実例|ファーストリテイリングの評価ポイントを押さえた自己PR
ファーストリテイリングのサマーインターンでは、単なる成功体験ではなく、「なぜその行動を選び、どうやって結果を出したのか」を深く掘り下げた自己PRが高く評価されます。
以下は、実際の通過者に見られる特徴を押さえた3つの例です。
それぞれに共通するのは、主体的な意思と行動力、そして周囲を巻き込む影響力です。
例①:アルバイトで売場改善を提案し、実際に成果を出した話
私の強みは、現場で課題を見つけて改善策を即行動に移せる実行力です。
アパレルショップでのアルバイト中、来店者数は多いのに売上が伸びないという状況に違和感を持ちました。
観察とヒアリングを繰り返す中で、お客様が「試着室の順番待ちで購入を諦めている」ことに気づき、スタッフ動線とレイアウトに課題があると分析しました。
店長に対して、売場動線の再設計とPOP表示の見直しを提案し、自ら改善案の設計と陳列変更を主導しました。
結果、レジ通過率が前年比20%以上改善され、売上にも目に見える効果が現れました。
この経験から、現場で課題を自分事として捉え、周囲を巻き込みながら形にしていくことの重要性を学びました。
御社の店舗運営でも、顧客目線とスピード感を武器に貢献できると考えています。
例②:ゼミで新しい研究テーマを提案し、成果に導いた経験
私は、自分の興味だけでなく、社会的な意味を意識してテーマを提案する力に自信があります。
大学のゼミでは既存の研究テーマが固定化しており、学生の関心が薄れていることに課題を感じていました。
そこで、世代間の消費行動の変化を定量的に捉えるという新たなテーマを自ら提案しました。
教授への交渉や先行研究の調査に加え、アンケート設計とデータ分析も自分が主導し、半年後には学内論文発表会で優秀賞を受賞する成果を挙げました。
この経験では、問題意識を起点に周囲の納得を得ながら物事を動かす難しさと、それを乗り越えたときの達成感を知りました。
企業であっても、慣例にとらわれずに課題提起できる姿勢は、御社のような変革志向の強い企業でこそ生きると感じています。
例③:学生団体の中で、メンバーの行動変容を促したリーダーシップ
学生団体での広報責任者として活動した際、私が直面したのは「やらされ感」で動くメンバーの多さでした。
活動の質を高めるには、一人ひとりが主体性を持つことが不可欠だと考え、私はまず役割の再定義から始めました。
全体ミーティングでは、自分が感じた違和感と改善案を共有し、各メンバーに裁量を持たせた担当業務の再設計を提案しました。
すると徐々にメンバーの提案数が増え、自発的な行動が生まれるようになりました。
最終的に、半年後には参加イベント数が2倍に増加し、SNSのフォロワー数も大幅に伸びるなど、成果としても現れました。
この経験を通じて、「人の行動は環境と役割の設計で変わる」ことを実感しました。
御社のように、人・チーム・ブランド全体をデザインしていく組織では、この視点と働きかけ力を活かせると考えています。
自己PRを書くときのコツ|ファーストリテイリングの価値観を踏まえて
ファーストリテイリングのインターン選考における自己PRでは、企業側が求めている価値観との一致をどれだけ明確に表現できるかが重要です。
単に経験や成果を語るだけでは、他の応募者との差別化にはなりません。
自分自身の行動の背景にある「思考」や「意志」を、同社の理念と重ねながら言語化することで、初めて評価に値する自己PRとなります。
この章では、ファーストリテイリングで高く評価される自己PRに共通する3つの観点を紹介します。
いずれも、経験そのものよりも考え方や姿勢に重きを置いた構成が求められるという点で共通しており、表面的な実績よりも深く自分自身を掘り下げることが不可欠です。
企業理念「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」に沿う視点を持つ
ファーストリテイリングが掲げる「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」という企業理念は、単なる衣料品の提供にとどまらず、社会の価値観や生活スタイルそのものにポジティブな変化をもたらすことを目指すものです。
この理念に共鳴するかどうかは、インターン選考でも重要な判断基準になっています。
自己PRを書く際には、この理念と自分の経験をどう接続するかが問われます。
たとえば、「誰かの課題を自分ごととして捉え、解決に向けて行動した経験」や、「既存のルールや当たり前を疑い、新しいやり方を提案・実行した経験」などは、まさにファーストリテイリングが求める人材像に直結します。
自分の行動が変化の起点となったという視点で振り返ることが、企業との価値観の一致を自然に伝える近道です。
「なぜそう行動したのか」の思考を丁寧に説明する
ファーストリテイリングでは、「自分で考え、意志を持って行動する人」を高く評価します。
そのため、自己PRにおいても「なぜそう行動したのか」という意思決定のプロセスが非常に重視されます。
どれだけ立派な成果を上げたとしても、「上司に言われたから」「流れでそうなった」といった受動的な理由では、同社の選考には通用しません。
評価されるのは、課題を見つけたときに「何を考え、どう判断し、なぜその選択をしたのか」を自分の言葉で語れる自己PRです。
たとえば、売上を伸ばしたという結果よりも、「どうしてその方法を選んだのか」「どんな失敗や反省があったのか」など、背景の思考を丁寧に描くことで、自立した行動者としての資質を印象づけることができます。
思考の深さを見せることで、表面的な行動だけでは測れない人間性を伝えることができるのです。
成果よりも「動機とプロセス」の一貫性が重視される
ファーストリテイリングの選考では、結果としての成果よりも、行動に至るまでの「動機」と「プロセス」に一貫性があるかどうかが重要視されます。
これは、同社が「やり抜く力」や「自律性」を重んじる文化を持っているからです。
たとえば、「新商品を企画してヒットさせた」という話であっても、「なぜその商品を生み出そうと思ったのか」「どういったステップで形にしていったのか」という一連の流れに説得力がなければ、単なる偶然や棚ぼたのように見えてしまいます。
逆に、最終的な成果が大きくなかったとしても、「課題を発見→仮説立て→行動→失敗→改善」というプロセスを粘り強く繰り返したエピソードであれば、同社の求める変革力と実行力を示す材料になります。
重要なのは、「自分がなぜその行動を起こしたのか」と「どのように考え、乗り越えたのか」という因果関係を明確にし、読み手に納得感を与えることです。
一貫性がある自己PRは、読み手に信頼を与えると同時に、ファーストリテイリングの現場でも活躍するイメージを持たせる効果があります。
よくあるNGパターンと改善アドバイス
ファーストリテイリングのサマーインターンにおいては、自己PRの内容が選考突破の成否を左右する重要な要素になります。
しかし、優秀な学生であっても、伝え方を誤ることでチャンスを逃してしまうケースが少なくありません。
特に、他の就活生と似たようなアピールに埋もれてしまう表現や、行動の背景が浅く見えてしまう構成は要注意です。
この章では、ファーストリテイリングの評価基準に照らして「通過が難しくなる自己PRの特徴」と「どう改善すべきか」について、具体的な視点から解説していきます。
文章の表面的な印象ではなく、本質的なアプローチの違いに気づくことが、合格レベルへの第一歩です。
「頑張った話」だけでは差がつかない
多くの学生が陥りがちなのが、「とにかく頑張りました」という努力の過程を中心に語ってしまうパターンです。
努力をしたこと自体は悪いことではありませんが、ファーストリテイリングの選考では、何を考え、なぜその行動を選んだのかといった内面の思考と判断が重視されます。
たとえば、「文化祭の準備を誰よりも頑張った」「サークル活動で毎日遅くまで練習した」といったエピソードは、一見熱意が伝わるように思えても、なぜその挑戦に価値があったのかという視点が抜けていると、自己PRとしての深みが足りず、他の応募者との差がつきません。
このような場合は、「努力を始めるに至ったきっかけ」「その中で見出した課題」「結果的にどのような変化を起こせたか」といった視点を追加し、行動の前後にあるストーリーを補うことで、自己PRの説得力を高めることができます。
「チームで協力した」だけのエピソードは印象が弱い
「チームで協力して成果を出した」というエピソードも就活では定番ですが、ファーストリテイリングでは「その中であなたは何を考え、どう行動したのか」が明確でないと評価に繋がりにくくなります。
同社が重視しているのは、集団の中で埋もれず、個人としてどれだけ価値を発揮できるかという視点です。
たとえば、「みんなで協力してイベントを成功させた」という話も、その中で自分がどのようにメンバーに働きかけたのか、課題に対してどんな改善策を提案したのかが不明瞭だと、読み手の印象に残りません。
集団成果の裏にある自分の主導性が見えてこそ、ファーストリテイリングが求める「個の力」に近づきます。
改善のためには、チーム活動を語る中でも、「自分の判断で何を選んだか」「その行動によって何が変わったか」を具体的に言語化することが必要です。
たとえ目立つ役割でなくても、そこに主体性が宿っていれば、十分に評価の対象になります。
決意や意思の弱い文章は行動力不足と見なされる
ファーストリテイリングのインターン選考では、意思を持って動ける人を重視するという特性上、「なんとなく始めた」「周囲に言われてやった」といった動機に基づいた自己PRは、行動力や自律性に欠けると判断される恐れがあります。
たとえば、「友人に誘われてボランティアに参加した」「部活動で上級生に言われたことを続けただけ」というような表現は、本人の意志よりも受動的な要素が前面に出てしまい、この人が自分で行動を起こしたのかという点に疑問を抱かれかねません。
こうしたケースでは、たとえきっかけが受動的だったとしても、「自分がその中で感じた課題」や「そこからどう主体的に関わるようになったか」を丁寧に描写することで、自分の中にある変化と意思を際立たせることができます。
動機の明確化と、行動への転換点を示すことが、説得力あるPRをつくるポイントです。
まとめ|サマーインターンの自己PRでファーストリテイリングに刺さるには?
ファーストリテイリングのサマーインターンにおける自己PRでは、表面的な成果や肩書きよりも、「その行動を選んだ理由」と「自分の意志でどれだけ行動できたか」が核心的な評価ポイントとなります。
企業としても、主体性を持って挑戦し、現場に変化を起こす“自律型人材”を求めているため、その視点に沿って自分のエピソードを深掘りする必要があります。
さらに、企業理念への共感だけではなく、それを自分の経験の中でどのように体現してきたかを語れることが、他の応募者との差別化につながります。
インターン参加は単なる職業体験ではなく、将来の採用候補者としての資質を見極められる場でもあるため、自己PRの質が選考通過に直結することを意識しましょう。
「意思を持って動いた経験」を軸にストーリーを組み立てる
評価される自己PRの特徴は、自分の中にある「強い意思」と、それを実行に移した「行動力」にあります。
何をしたかだけでなく、なぜその行動を選び、どうやってやり切ったのかというプロセスを中心に語ることで、ファーストリテイリングが重視する“変革を起こす人材像”に近づけることができます。
また、行動に至るまでの背景を丁寧に描写し、苦悩や葛藤を含めたリアルなストーリーに仕立てることで、単なる成功談ではなく“信頼感のある人物像”を形成することができます。
「自分で考え、責任を持って動いた経験」があれば、それがどのようなテーマであっても、十分に評価される可能性があります。
企業理解と自己分析を融合させ、ロジカルに語ることが重要
ファーストリテイリングに刺さる自己PRをつくるには、「自分はこういう人間である」という内省に基づいた自己理解と、「この企業はこういう人材を求めている」という企業理解の両方が不可欠です。
どちらか一方では説得力に欠け、選考の現場では埋もれてしまいます。
自分の過去の経験を棚卸しし、「その経験が、ファーストリテイリングでどう活かせるのか」を論理的に結びつけることで、ESや面接での印象は格段に高まります。
特に同社の選考では、一貫性と納得感が求められるため、自己PRの構成は感情に流されず、冷静に“理由と結果”で語る姿勢が効果的です。
自分という素材を最大限に活かしながら、ファーストリテイリングというフィールドでなぜ挑戦したいのかを明確に言語化する。
それが、サマーインターン選考を突破するための最も重要な鍵となります。