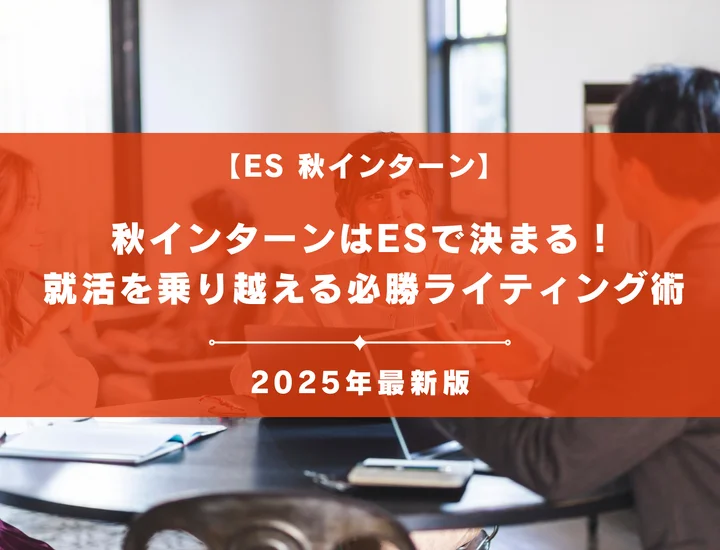明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・就活の軸の定め方
・就活の軸を「将来性」にする際のコツ
・就活の軸の例文
・例文を読んで参考にしたい人
・就活の軸を決められない人
・就活の軸について基本から学びたい人
はじめに
将来性のある企業に就職することは、将来に不安を覚える人が多い現代においては非常に重要視されることです。
将来性を就活の軸に定めている人が、面接でどのように回答すれば良いかや、業界・企業の将来性をどのように調べれば良いかについて詳しく紹介します。
将来性を就活の軸にするのはあり?
将来性を就活の軸にすることは全く問題ありません。
安定した企業に入ることで安心できますし、面接でも「長期的な視点でキャリアを考えている」と判断され、長く働くつもりがある人物と思ってもらえるでしょう。
ただし「将来性がありそうだから志望した」といった表面的な回答をしてしまうと、マイナスな印象を与えてしまうため、表現には注意が必要です。
「成長している企業に入って安定を得たい」「今後も仕事がありそうだから」といった動機ではなく、将来性に魅力を感じた背景を自分の経験や価値観と結びつけて語りましょう。
何に興味を持ち、どのような視点で業界や企業の動向を調べたのか、その結果として「この企業なら長く働いていける」と思った理由を明確に述べることが大切です。
就活の軸とは?
「就活の軸」とは自分が企業を選ぶ際に最も大切にしたい価値観や、働くうえで「これだけは譲れない」と感じる条件のことです。
職種や年収といった条件面だけでなく、どのような環境で働きたいか、どのような姿勢で社会と関わりたいかといった、より根本的な考え方も含んだものです。
就活の軸があることで、大量にある選択肢の中から自分に合った会社を見つけやすくなり、選考の際にも一貫性のある受け答えができるようになるでしょう。
軸が少なすぎると選択肢が多くなりすぎてしまいますし、軸が多すぎると当てはまる企業がかなり少なくなってしまうため、おすすめは3個程度設けておくことです。
就活の軸はなぜ必要?
就活の軸が必要であると、先輩やキャリアセンターのスタッフから耳にタコができるほど言われた人もいるでしょう。
しかし、なぜ必要なのか、明確に言語化して教えてくれない人も多くいます。
そこで、就活の軸がなぜ必要なのか、その理由を3つに分けて紹介するため、参考にしてみてください。
企業を絞るための基準になる
就活の軸を持つことは自分に合った企業を見極めるための明確な判断基準となります。
軸が定まっていない状態で企業選びを始めると、企業の知名度や福利厚生など表面的な条件にばかり目がいってしまうでしょう。
その結果、自分の価値観と合わない企業にも手を広げてしまい、エントリー数だけが増えてしまうという非効率な状況に陥りやすくなります。
軸があることで、自分に必要な条件が明確になるため、初期段階で志望先をスムーズに絞り込めるのです。
応募する企業数が減ったとしても、その分準備に時間を使えるため、選考に向けた精度の高い対策が可能になります。
無駄なエントリーを減らし、本当に目指す企業にだけ集中できるという意味で、就活の軸は非常に重要な役割を果たすでしょう。
将来のビジョンを立てられる
就活の軸を意識することは自分自身のキャリアや将来の姿を具体的に描くきっかけになります。
「自分は何のために働くのか」「どのような環境で、どのような価値を発揮したいのか」といった問いに向き合う中で、自分が働くことに何を求めているのかが明らかになっていきます。
ただ企業を選ぶだけでなく、長期的にどのような社会人になりたいのかという「在り方」について考えるうえでも非常に有益です。
将来のビジョンがあれば、働くうえでも就職後も主体的にキャリアを築いていけるようになります。
また、ビジョンが明確になると、話に一貫性を出せるため、企業側からも信頼感を持ってもらいやすくなります。
自分の軸を掘り下げていくことは「自分の人生そのものと向き合うこと」でもあり、就活を有意義な時間にするための大切な土台です。
ESや面接などの選考対策になる
就活の軸が明確であれば、ESや面接での説得力も大きく変わってきます。
志望動機や自己PRを作成する際、軸に基づいて話を組み立てることで、内容に一貫性と深みを持たせられます。
「なぜこの企業なのか」「なぜこの業界を選んだのか」といった問いにも、自分の軸を元に説明ができるため、論理的な構成で伝えられるようになるのです。
特に企業側は志望度の高さや企業理解を重視しているため、軸を明確にして「この人はなぜうちで働きたいのか」を納得できる形で示すると印象が良くなります。
また、自分自身もブレない軸を持っていることで、自信を持って臨めるようになるでしょう。
業界・企業の将来性を調べるための方法
就活の軸に将来性を含めることは全く問題ないと分かりましたが、実際に業界や企業の将来性を調べるためにはどのような方法をとれば良いのでしょうか。
様々な調べ方がありますが、以下の5つの方法ならば確実に業界や企業の将来性を調べられるでしょう。
ぜひ一つひとつ入念に取り組んでみてください。
市場の成長性を調べる
業界の将来性を判断する際には、まずその市場自体が成長しているかどうかを確認することが大切です。
市場が拡大している分野では新たなニーズが生まれやすく、企業の成長余地も大きくなります。
市場の成長性は経済産業省や総務省などの公的機関が発表している統計データ、民間の調査会社がまとめた市場レポートなどから、過去の推移や将来の予測を確認できます。
また、グローバルな視点で見れば、国内で頭打ちの市場でも、海外では成長の兆しがある場合もあり、それが企業の海外展開戦略と直結していることも少なくありません。
こうした市場規模の変化や成長率に目を向けることで、業界全体の今後の方向性を読み取ることができ、どの業界が将来性のあるフィールドかを見極める判断材料になるでしょう。
企業の新規事業について調べる
企業の将来性を判断するには、新規事業や今後の成長分野への挑戦状況を確認することも欠かせません。
成熟した事業だけでなく、新たな事業にどれだけ力を入れているかを調べることで、その企業が変化に対応しながら成長していく姿勢を持っていることが見えてきます。
新規事業の内容や新しいプロジェクトの規模や連携している外部企業、ターゲットとしている顧客層などを読み解くことで、収益の柱になる可能性や社会の変化に対応できる柔軟性を評価できます。
特に技術革新や消費行動の変化が早い分野では新規事業への取り組みが企業の将来像を左右するため、注視する価値があると言えるでしょう。
企業の財務状況を確認する
企業の将来性を見極めるためには財務状況の確認も欠かせません。
収益性や自己資本比率、営業利益率などの指標を見ることで、企業が健全に経営されているかどうかを判断できます。
また、売上や利益の推移を見れば、事業の成長性や収益の安定性も読み取れます。
上場企業であれば有価証券報告書や決算短信などがIRページに公開されており、そこから詳細な財務データを確認できるでしょう。
財務基盤が安定している企業は将来的な投資や人材採用にも積極的に取り組むことができるため、長期的に成長する可能性が高いです。
ビジネスモデル・成長戦略を理解する
企業の将来性を判断するうえで欠かせないのが、その企業がどのような仕組みで価値を提供し、どこから収益を得ているのかを把握することです。
これがいわゆる「ビジネスモデルの理解」にあたります。
どれだけ業界全体が成長していても、その中で企業が持つ独自性や差別化のポイントが不明瞭であれば、競合に埋もれるリスクも高まります。
そのため「その会社の強みがどこにあるのか」「顧客にどのような価値を届け、どのような課題を解決しているのか」を見極めることが大切です。
また、企業が掲げる成長戦略にも注目しましょう。
新しいターゲット層への展開、商品・サービスの拡充、海外市場への進出など、将来の成長を支える明確な戦略があるかどうかを見れば、企業の伸びしろを見極められます。
IR情報・中期経営計画を調べる
企業のIR情報や中期経営計画は将来性を見極めるために非常に信頼性の高い資料です。
「IR情報」は株主や投資家に向けて発信されるため、経営陣の考えや今後のビジョン、業績予測などが比較的客観的かつ具体的に示されています。
また「中期経営計画」には3年から5年のスパンで企業が目指す方向性や重点事業、投資予定、新規事業の方針、数値目標などが盛り込まれており、企業の長期的な成長ビジョンが語られています。
特に注目すべきなのは「どの分野にリソースを集中しているか」「社会課題や市場の変化にどう対応しようとしているか」という点です。
これらは企業の方向性を知る手がかりとして非常に有効であり、自分の志望先が本当に将来性のある企業かどうかを判断する有力な材料となるでしょう。
また、IR資料は言葉選びが慎重である分、誇張が少なく、内容に信頼性があるのも特徴です。
将来性を使った就活の軸の注意点
将来性を就活の軸に据えること自体は全く問題ありません。
それは冒頭で紹介した通りなのですが、いくつかの注意点を理解しておかないと就活がうまく進まない可能性があります。
以下の6つの注意点はしっかりと頭の隅に置いたうえで、将来性を軸にした企業選びをしましょう。
「絶対」はないと理解する
将来性を就活の軸に据えること自体は全く問題ありませんが、その判断に「絶対」を求めてしまうと判断を見誤る可能性があります。
企業の成長性や業界の動向を読み解くには複数の要素を冷静に見極める必要がありますが、未来を100%予測することは誰にもできません。
急激な経済の変動や社会構造の変化、新技術の登場など、企業を取り巻く環境は常に流動的であり、どれほど情報を集めていても、確実な答えが得られるとは限らないのです。
今注目を集めている事業が数年後にはまったく需要がなくなってしまっている可能性すらあります。
そのため、ブームや評判といった聞こえの良い情報だけに流されるのでなく「不確実性がある」という前提のもとで情報を扱い、自分自身の視点で価値を見極める姿勢が重要です。
「将来性」だけで決めない
どれほど将来性のある企業であっても、自分の価値観や働き方に合っていなければ、入社後に違和感を覚えやすくなりますし、やりがいも感じられません。
将来性だけを重視して企業を選ぶと、自分が本当にやりたいこと、向いている仕事を見失い、仕事そのものに満足できなくなってしまうでしょう。
「企業が成長すること」と「自分が長くやりがいを持って働けるか」は別問題であり、自分にとってのやりがいや挑戦したいことと照らし合わせて判断することが重要です。
また、企業が将来性を持つ領域に進出していたとしても、その事業に自分が関われるかどうかは部署やタイミングによって異なる場合もあります。
労働環境や社風も理解する
企業の成長性や将来のビジョンを調べることは就活において有益ではありますが、それだけに偏ってしまうと入社後にギャップを感じる可能性があります。
将来性があるという理由で入社しても、普段の働く環境が自分に合っていなければ、働き続けることは難しいです。
教育制度が整っていない、上司とのコミュニケーションが取りづらいなどの場合、自分の成長どころか心身に負担がかかる可能性すらあります。
就活では企業の説明会やOBOG訪問、口コミサイトなどを活用して、職場の雰囲気や制度の運用情報などにも目を向けることが大切です。
理想の未来だけに目を奪われるのではなく「自分はこの会社でやっていけるのか」という現実的な視点で捉えることで、自分に合った環境を選ぶ力が養われていきます。
自分が将来性のある環境で働かないといけない理由を述べる
将来性を就活の軸として話す際は、なぜ自分が将来性のある企業で働く必要があるのかを明確に伝えなければなりません。
企業の将来性に魅力を感じるだけでは、ただ「伸びている会社に入りたいだけ」という受け身の印象になってしまいがちです。
したがって、自分の中にある具体的な目標や将来の理想の姿と将来性のある環境がどのように結びついているかを丁寧に説明する必要があります。
自分が将来性のある環境に身を置くことで何を実現したいのか、どのような成長を目指すのかという視点を持って話すことが、説得力のある面接での回答につながります。
数値を理解する
将来性があるから志望したと伝える時に、その裏付けとなるデータや根拠が乏しいと、表面的な志望動機と思われてしまいます。
成長性を語るならば、業界の市場規模や今後の拡大の見通し、企業の売上推移、利益率、経営指標など具体的な数値を理解することが大切です。
企業のIR資料や中期経営計画などを読み込むことで、その企業が実際にどのような成長を遂げてきたのか、今後どのようなビジョンを持っているのかを把握できます。
数字を用いて語ることによって「自分で分析したうえで、〇〇な点に魅力を感じている」という、一歩踏み込んだ説得力のあるアピールが可能です。
また、自分のキャリアプランと照らし合わせて「成長している貴社のこの事業の中で、自分はこう貢献したい」といった構成で話せば、ただ情報を引用しているだけでなく、自己理解と企業理解の両方が深い人材だということも伝えられます。
受け身や他力本願な印象を与えないようにする
将来性を軸に企業を目指す場合、その伝え方によっては「伸びているから乗っかりたいだけ」「成長している会社に入って楽をしたいだけ」といった受け身な印象を与えてしまう可能性があります。
それを避けるには「将来性があるから選んだ」というだけで話を終わらせず、自分がその環境に飛び込み、どのような価値を生み出したいのかを主体的に語ることが欠かせません。
企業の成長にどう関わりたいのか、自分の経験がどのように活かせるのかを踏まえた話の流れを意識することで、他力本願ではない姿勢が伝わります。
就活の軸で将来性を魅力的に伝えるためのポイント
将来性を大切にしていることを面接で魅力的に伝えるためにはどのようなポイントがあるのでしょうか。
以下の3点を意識しておけば、面接で「就活の軸は何ですか」と聞かれた際も、より分かりやすくあなたの魅力が伝わりやすい回答を作成できます。
ぜひ以下のポイントは覚えておいてください。
将来性のある環境で成し遂げたいことを伝える
企業の将来性を就活の軸としてアピールする際には、ただ「成長している企業で働きたい」と述べるだけでは説得力に欠けます。
その環境に身を置いて自分がどのようなことを成し遂げたいのか、具体的に語ることが良い印象を与えるために重要です。
将来性のある企業は挑戦や変化が求められる場面が多く、そこで主体的に行動できる人材が歓迎されます。
したがって、自分が企業の発展や社会への価値提供にどう関わりたいと考えているのかを明確にすることが大切です。
環境や制度を「与えられる」のではなく「自分がどのように関与して、価値を生み出すか」という視点を持って話すことで、主体的な姿勢をアピールできます。
自分の将来性も伝える
企業の将来性に魅力を感じているだけでなく、自分自身にも成長の余地があること、そしてそのポテンシャルをどのように発揮していきたいのかを伝えることで、他の就活生との差別化ができます。
将来性を軸とするならば、自分がその企業とどのように歩んでいきたいのか、どのような人材になりたいのかを示すことも不可欠です。
採用担当者は企業の将来を担う人材を求めているため、自分の能力や学びに対する姿勢などを話して「この人は会社と共に成長し、長く活躍してくれそうだ」と思ってもらえるような表現が重要です。
自己理解を深めたうえで、自分の強みや課題に向き合い、どのような力を伸ばし、どのように課題を解決していきたいのかという視点を持って話すと、自分の将来像と企業の方向性をうまく重ねられます。
業界・企業研究をしてつけた知識を基に伝える
将来性を軸に企業を選ぶならば、その企業がなぜ将来性があると判断できたのかについて、根拠を持って話さなければなりません。
自分なりに業界や企業について深く調べ、成長性を感じた理由を、自分なりの視点で明確にしましょう。
多くの就活生は「この業界は今後伸びる」といった漠然とした印象で話を進めてしまうため「なんとなく選んだのかな」と思われてしまいがちです。
だからこそ、業界構造、社会課題との関係性、企業の中期経営計画などを自分なりに調べた知識を踏まえて話しましょう。
こうして準備した内容はESや面接の際に内容の深みとして現れますし、採用担当者も「この人は本当にしっかりと調べたうえで弊社を志望しているのだな」と思ってくれます。
情報をただ「暗記する」だけでなく「自分なりに解釈」して、それを自分の軸とどう結びつけたのかまで言語化することが、魅力的な伝え方のコツです。
将来性を使った就活の軸の例文
ここまで紹介してきた内容を踏まえたうえで、将来性を就活の軸とした回答の例文を3つ作成しました。
この記事で紹介した構成やポイント、注意点などを踏まえたうえで作成したため、いずれも記事のおさらいとして参考になるはずです。
自分ならばどのように答えるか考えながら、ぜひ読んでみてください。
例文①
大学時代、ドローンを活用した地域物流の研究プロジェクトに参加し、過疎地におけるインフラ代替手段としての可能性を探ってきました。
中山間地域の住民にヒアリングを行い、安全性や採算性を検証し、自治体へのプレゼンも行いました。
この活動を通じて、今は小規模であっても社会課題に根ざしたテクノロジーが、数年後には大きな変革をもたらす可能性があると実感しました。
貴社は先進技術を活用した物流の再構築に取り組んでおり、私が関わった研究と完全に方向性が一致しています。
入社後は技術の社会実装に関わる業務に携わり、現場の課題を丁寧に拾いながら実現可能性の高いサービスを形にしていく所存です。
例文②
大学ではデータサイエンスを専攻し、分析コンペへの参加や統計モデルの構築を通じて、実践的なスキルを磨いてきました。
中でも印象に残っているのは大学主催の企業連携プロジェクトで、小売企業の購買履歴をもとに売上予測モデルを開発したことです。
精度の高い予測を出すためには技術だけでなく、事業の構造や顧客行動を深く理解する必要があり、将来的に高度な専門性が競争力になることを実感しました。
貴社はデータを軸に新しいビジネスを創出する姿勢を貫いており、自らの成長と企業の発展が同じベクトルを向いていると確信しています。
入社後は分析力と事業理解の両方を磨きながら、データを通じて意思決定を支える人材として貢献する所存です。
例文③
大学で都市開発に関する行政ワークショップに参加し、自治体や住民との意見交換を通じて、再開発が街の暮らしに与える影響や企業の役割を体感しました。
貴社は都市開発とITを融合させ、スマートシティ構想における交通やエネルギーのインフラ整備にも取り組まれており、再開発によって生まれる街の未来を支える事業に力を入れられています。
私の経験や関心のある領域とも共通点が多く、これまでの学びや興味を活かして社会基盤の進化に貢献できると感じたため、貴社を志望しています。
入社後は行政や地域と連携しながら、持続的に成長できる街づくりに関わる仕事を通じて、貴社のさらなる業績向上に貢献したいと考えています。
就活エージェントを利用しよう!
就活の軸を将来性にすることについてこの記事で詳しく紹介しましたが、たった1つの記事を読んだだけで悩みがすべて解決するならば、就活生の皆さんはここまで困っていないことでしょう。
就活の軸の回答にまだ不安がある方や、志望動機や自己PRなどに自信がない方も多いでしょう。
そこでおすすめなのが就活エージェントを利用することです。
弊社が提供している「ジョブコミット」では、志望動機、自己PR、ガクチカ、就活の軸といった代表的な質問の回答の添削にES・面接両方で対応できますし、あなたがどのような就活の軸を定めるべきか、一緒に考えることもできます。
完全無料でプロに相談できる弊社自慢のサービスですから、気になる方はぜひ下のリンクから登録してみてください。
まとめ
今回は就活の軸を将来性にしようと考えている方のために、意識しておきたいポイントや注意点、回答の構成などについて紹介しました。
将来性が高いことは特に近年、多くの就活生の方が大切にしているポイントです。
同じような題材を話すライバルは数多くいるでしょうが、この記事を参考に回答を作成すれば、自ずと差別化できるはずです。
ぜひ入念に対策を行い、面接本番でも自信を持って答えて、内定を掴み取ってください。