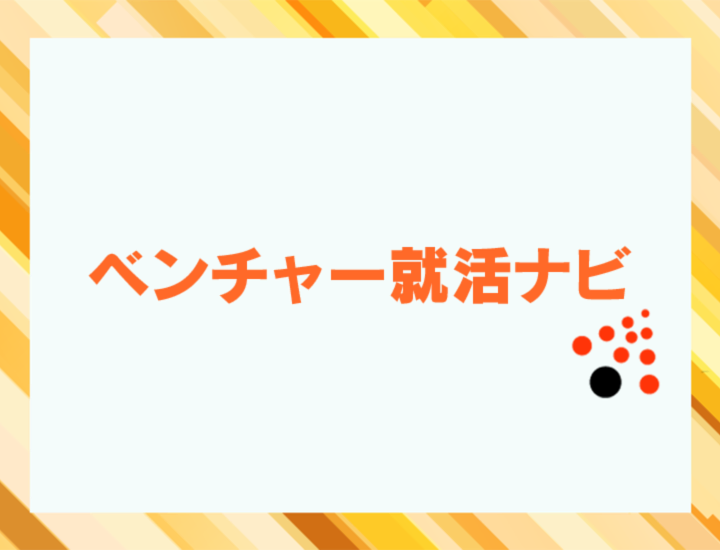明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
- 地方創生とは
- 地方創生に力を入れているベンチャー企業とは
- 地方創生に力を入れているベンチャー企業の特徴
- 地方創生に力を入れているベンチャー企業に興味がある人
- ベンチャー企業から内定をもらいたい人
- 選考対策をしたい人
目次[目次を全て表示する]
地方創生ベンチャーは何するの?
まずは地方創生ベンチャーが何をするのかを確認してみましょう。
名前からわかる通り、地方創生をテーマに、地方ならではの課題解決に向けてビジネスを展開していきます。
自治体と協力して、連携することもあるでしょう。
実は、地方創生というのは、わが国の課題でもあり、急務でもあります。
そして、これまでは難しかった地方創生を、IT技術などを活用することによって、新しい視野でチャレンジする企業が増えているのです。
そうした企業はベンチャーであることも多く、非常に魅力的な分野だと言えるでしょう。
そのため、地方創生にチャレンジするようなベンチャーで働くことができれば、普通のベンチャーでは得られないような経験を得られる可能性があります。
地方創生ベンチャーが増えている理由
・行政の地方支援が拡充してきている
・地方の良い資源がうまく活用されていない
・地方経済に課題を感じる人が増えている
なぜ地方創生ベンチャーが増えているのでしょうか。
ここでは、地方創生ベンチャーが増えている理由を紹介します。
リモートワークの浸透
新型コロナウイルスの影響もあり、リモートワークやオンラインでの業務遂行が社会全体で浸透しました。
これにより、物理的な拠点に縛られずにビジネスを行うことが可能になり、ベンチャー企業が都市部にオフィスを構える必要性が低下しました。
結果として、都市部の高コストな家賃や人件費を避け、地方に本社やサテライトオフィスを設置する選択肢が現実的になりました。
また、地方在住の人材をリモートで雇用したり、都市部にいた人材が生活の質を求めて地方に移住しながら仕事を続けたりするケースも増加しています。
この働き方の多様化が、地方を活動拠点とするベンチャーの立ち上げを後押ししています。
行政の地方支援が拡充してきている
近年、政府や自治体は地方創生を重要課題として位置づけ、そのための支援策を大幅に拡充しています。
具体的には、地方での起業や事業拡大を促すための補助金や助成金制度が整備され、特にデジタル技術を活用した事業には手厚いサポートが提供されています。
また、地方創生に特化したファンドの設立や、地域金融機関と連携した融資支援、さらにはインキュベーション施設の提供など、事業者が成長しやすい環境が整えられています。
行政側が積極的にベンチャー企業との連携を模索し、地域課題の解決を外部の力に求める姿勢が強まっていることも、地方での起業を後押しする大きな要因となっています。
地方の良い資源がうまく活用されていない
地方には、豊かな自然資源、伝統文化、歴史的な建造物、高品質な農林水産物など、都市部にはない魅力的な資源が豊富に存在します。
しかし、これらの多くは従来の枠組みや販路、プロモーション手法では十分に価値が発揮されず、未だ潜在的な資源として残されていました。
地方創生ベンチャーは、このような「埋もれた資源」に対し、最新のIT技術や斬新なビジネスモデルを適用することで、新たな付加価値を生み出します。
例えば、地域の特産品をD2Cで世界に販売したり、古民家をリモートワーク対応の宿泊施設として再生したりする事業など、地域の資源を現代のニーズに合わせて再構築する試みが増えています。
地方経済に課題を感じる人が増えている
少子高齢化や人口流出の進行により、地方では経済の停滞、雇用機会の減少、地域の活力低下といった深刻な課題が顕在化しています。
このような状況に対し、「自分たちの地域をなんとかしたい」という強い課題意識と使命感を持つ人が、都市部出身者やUターン・Iターン層を中心に増えています。
特に、社会貢献とビジネスの両立を目指すソーシャルビジネスへの関心の高まりも背景にあります。
これらの人々は、既存の組織や行政では難しいスピード感と革新性をもって課題解決に取り組むために、自らベンチャーを立ち上げる道を選んでいます。
地域の未来への危機感と、それを解決したいという情熱が、地方創生ベンチャー増加の根源的なエネルギーとなっています。
地方創生の社会的意義
・多様な働き方
・結婚・出産・子育て支援を通じた少子化対策
・地域の独自資源を活用した新たな価値創造
・地域コミュニティ機能の維持・再生
地方創生の社会的意義は、どのような部分にあるのでしょうか。
ここでは、地方創生の社会的意義を紹介します。
国土の均衡ある発展
都市部への人口・機能の過度な集中は、大災害発生時の国家的なリスクを増大させます。
例えば、首都圏直下型地震が発生した場合、経済機能の麻痺、生活インフラの崩壊など、国全体に甚大な被害が及ぶ可能性があります。
地方創生は、人や企業の活動拠点を分散させることで、このリスクを低減する役割を担います。
また、各地域がそれぞれの特性を活かし、自立的に発展していくことで、国土全体が多極分散型となり、地域間の経済格差の是正にもつながります。
これにより、特定の地域に依存しない、より強靭で安定した国づくりが実現します。
多様な働き方
都市部での過密な生活や長時間労働といった課題に対し、地方創生は新たな選択肢を提供します。
リモートワークやワーケーションの普及、地方への企業誘致や起業支援などを通じて、地方でも専門性の高い仕事や、地域に根ざした新しい仕事を生み出すことが可能になります。
これにより、個々人が仕事と生活のバランスを重視し、豊かな自然環境や子育てしやすい環境など、自分の価値観に合った場所で生活する自由が得られます。
これは、都市集中による閉塞感を打破し、国民一人ひとりの幸福度を高めることに貢献します。
結婚・出産・子育て支援を通じた少子化対策
地方の多くでは、若年層の流出や地域の経済活動の縮小により、安心して結婚や出産、子育てができる環境の維持が困難になっています。
地方創生は、医療・教育・子育て支援などの生活サービスを充実させ、魅力的な職場とコミュニティを創出することで、子育て世代が定着・流入する流れをつくります。
具体的には、待機児童解消のための施設整備や、地域ぐるみでの見守り体制の強化などが挙げられます。
こうした取り組みは、若者が将来に希望を持ち、結婚・出産への意欲を高めることに直結し、結果として国全体の少子化対策の一翼を担う、極めて重要な社会的意義を持ちます。
地域の独自資源を活用した新たな価値創造
日本の地方には、豊かな自然環境、歴史的な文化財、伝統的な技術、高品質な農林水産物など、都市部にはない多様な独自資源が豊富に存在します。
地方創生は、これらの資源を単に維持するだけでなく、観光、食産業、芸術文化、エコツーリズムといった分野で高付加価値化し、新たな産業や雇用を生み出すことを目指します。
例えば、使われていなかった古民家を再生して宿泊施設やオフィスにするなど、地域資源を創造的に再解釈することで、その地域の経済的自立を促し、地域ブランドの向上に貢献します。
これは、日本全体の文化的な多様性を保全し、国際競争力を高める基盤にもなります。
地域コミュニティ機能の維持・再生
人口減少と高齢化が深刻化する地方では、地域の担い手不足により、消防・防災、祭りや伝統の継承、日常の相互扶助といったコミュニティの機能が低下し、社会的孤立が広がる懸念があります。
地方創生は、移住者や関係人口(観光客や交流を通じて地域と関わる人々)を増やすことで、コミュニティに新たな活力を注入し、その維持と再生を目的とします。
特に、デジタル技術を活用した見守りサービスや地域交通の再構築は、高齢者が安心して暮らせる環境を整備します。
これにより、人と人とのつながりが守られ、誰もが孤立せずに暮らせる、温かく強靭な地域社会の実現を目指します。
地方創生のベンチャーがやっている仕事とは
・地方メディア
・不動産関連
・コンサル
・DX支援
地方創生のベンチャーがやっている仕事には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、地方創生のベンチャーがやっている仕事を詳しく解説します。
商品開発
地方創生ベンチャーにおける商品開発は、地域の埋もれた資源や特産品に新たな価値を付与し、市場に送り出す仕事です。
単に既存の農産物や工芸品を販売するのではなく、最新のトレンドや都市部の消費者のニーズを捉えたブランディングやデザイン、加工を行います。
例えば、地域の未利用な果物を活用したクラフトビールを開発したり、伝統工芸の技術を用いて現代のライフスタイルに合うプロダクトを制作したりします。
この仕事は、地域の一次産業や伝統産業の担い手と密接に連携し、持続可能な収益源を生み出すことを目指します。
地域に新たな雇用と誇りをもたらし、域外からの外貨獲得に貢献する重要な役割を担います。
地方メディア
地方メディア事業は、地域の魅力や情報を発掘・編集し、効果的に地域内外に発信する仕事です。
従来の情報発信源が届きにくい若年層や都市部の人々に対し、Webサイト、SNS、動画などのデジタルチャネルを駆使します。
地域に根ざしたライフスタイル、ローカルなグルメ、移住者の体験談、ベンチャー企業の取り組みなど、「人」や「物語」に焦点を当てたコンテンツを制作することが特徴です。
これにより、地域への関心人口や関係人口を増やし、観光客の誘致や移住・定住の促進を目的としています。
情報発信力を高めることで、地域ブランドの向上と経済の活性化に貢献します。
不動産関連
地方創生における不動産関連の仕事は、空き家や遊休不動産を再生し、地域の新たな経済拠点や交流拠点として活用することです。
単なる仲介や管理ではなく、地域課題の解決に繋がる用途へのコンバージョンを企画・実行します。
具体的には、古民家を改装して観光客向けの宿泊施設(分散型ホテル)にしたり、使われていない店舗をリモートワーカー向けのコワーキングスペースや地域住民が集うカフェにしたりします。
これにより、地域の景観維持に貢献しつつ、交流人口や新しい事業者を呼び込みます。
不動産の価値を再定義し、地域経済の循環を促す重要なインフラ整備としての側面を持つ仕事です。
コンサル
地方創生ベンチャーのコンサルティング事業は、自治体や地域の中小企業、団体に対し、外部の視点と専門知識を提供して事業や組織の変革を支援する仕事です。
特に、マーケティング戦略、IT導入、新規事業開発、人材育成など、都市部の最新の知見や手法を地域に持ち込みます。
例えば、地域特有のデータを分析し、それに基づいた観光戦略を策定したり、後継者不足に悩む企業に対しM&Aや事業承継の支援を行ったりします。
この仕事の鍵は、地域のニーズを深く理解しつつも、現状に囚われない革新的な提案を行うことです。
地域の自立的な成長を促すため、短期的な支援に留まらず、長期的な伴走を担うことも多くあります。
DX支援
DX支援は、地方の中小企業や自治体の業務効率化、および新たな価値創造をデジタル技術の導入を通じて実現する仕事です。
地方の企業や組織はデジタル化の遅れが課題となっていることが多く、ベンチャーはそこに特化したサポートを提供します。
具体的には、クラウド会計やSaaSツールの導入支援、WebサイトやECサイトの構築、AIを活用したデータ分析基盤の整備などを行います。
これにより、人手不足の解消や生産性の向上を図り、競争力を高めます。
地域の事業者がデジタル化の波に乗り遅れないよう、専門知識と実行力を提供することで、地方経済全体の底上げに貢献します。
地方創生ベンチャーのやりがいは?
・地域との密接な連携ができる
・幅広い経験ができる
・新たな商機へのチャレンジができる
・大きな自己成長につながる
地方創生ベンチャーで働くことは、地域社会の活性化という大きな目的に直結し、一般的なビジネスでは得難い独特のやりがいをもたらします。
社会貢献性が高い
地方創生ベンチャーの仕事は、地域が抱える社会課題の解決に直結しています。
少子高齢化、過疎化、産業の衰退、空き家問題など、地域社会の存続に関わる深刻な課題に取り組むため、その成果が住民の生活の質向上や地域の未来に明確に反映されます。
都市部の大規模なビジネスでは成果が見えにくいこともありますが、地方創生では、雇用を生み出す、特産品に新たな価値を付加する、観光客を呼び込むといった活動が、すぐに地域経済の活性化につながるのを肌で感じられます。
この高い社会貢献性は、「誰かの役に立っている」という強い仕事の意義や誇りにつながり、大きなやりがいとなります。
地域との密接な連携ができる
地方創生事業の成功には、地域に根差した住民、自治体、地元企業との密な協力体制が不可欠です。
ベンチャー企業は、外部からの視点と柔軟な発想を持ち込みつつ、地域の歴史や文化を尊重し、深い対話を重ねることで信頼関係を築きます。
この過程で、地域社会の一員として受け入れられ、課題を「自分事」として捉えることができます。
単なる取引先ではなく、「同志」として、共に汗を流し、喜びを分かち合う経験は、深い人間的なつながりをもたらします。
この「顔の見える関係性」の中で進める事業は、成果が出た際の感動もひとしおで、地域と共に歩むという確かな手応えを感じられます。
幅広い経験ができる
地方創生ベンチャーでは、少数精鋭で事業を推進することが多く、一人ひとりが多岐にわたる業務を担当します。
企画立案、市場調査、営業、マーケティング、資金調達、時にはプロジェクトの現場作業まで、一気通貫で関わることが求められます。
特に地方では、都市部のように細分化された役割分担が難しいため、ジェネラリストとしての能力が磨かれます。
この環境は、特定の専門性を深めたい人だけでなく、事業全体を俯瞰する視点や、様々なスキルを身につけたい人にとって理想的です。
多様な役割を通じて、ビジネスの全体像を深く理解し、自身の職務領域を広げることができるのは、大きな魅力です。
新たな商機へのチャレンジができる
地方には、既存の市場では満たされていない独自のニーズや、未活用なまま眠っている地域資源が豊富に存在します。
地方創生ベンチャーは、これらの「課題の裏側にある商機」を発見し、これまでにないビジネスモデルやプロダクトを創造することに挑戦できます。
大手企業や行政では難しい、スピード感と柔軟性をもって、ニッチな市場や地域特有の文化を活かした事業を展開できるのが強みです。
競争が少ない分野で、アイデアと熱意次第で大きなインパクトを生み出すことが可能であり、パイオニアとして「新しい価値」を生み出すことへの刺激的なチャレンジは、尽きることのないやりがいとなります。
大きな自己成長につながる
地方創生ベンチャーという環境は、「不確実性」と「多様な関係者」の中で事業を進めるため、極めて高い問題解決能力と調整力が求められます。
前例のない課題に対して、自ら考え、行動し、結果を出すというPDCAサイクルを高速で回す中で、起業家精神やリーダーシップが自然と養われます。
また、事業を通じて自治体の首長や地元の有力者、多分野の専門家と対話し、連携する機会も多く、コミュニケーション能力やネットワーク構築力も飛躍的に向上します。
ビジネススキルだけでなく、人間的な成長も含め、「どこでも通用する力」を短期間で身につけられる点が、大きな自己成長につながるやりがいと言えます。
地方創生ベンチャーで向いている人の特徴
・地域との深いつながりが生まれる
・多様なスキルと経験が得られる
・自由な発想を活かしやすい
・地域の魅力に触れながら働ける
地方創生に向いている人は、どのような人でしょうか。
ここでは、5つのポイントに絞って、地方創生ベンチャーに向いている人の特徴を紹介します。
地域への強い想いがある人
地方創生は、人口減少や高齢化、産業衰退など、根深く複雑な課題に取り組む活動です。
成果がすぐに見えにくかったり、地道な努力が必要だったりする場面も多くあります。
そのため、特定の地域に対する愛着や、社会課題を解決したいという強い使命感が、困難な状況を乗り越えるための原動力となります。
この想いは、地域住民や関係者との信頼関係を築く上での基盤にもなります。
損得勘定だけでは測れない地域への貢献意欲や、課題解決に対する当事者意識を持っている人は、モチベーション高く活動を続け、周囲を巻き込みながら前進していくことができるでしょう。
ゼロからイチを生み出せる人
地方創生には「決まった正解」はありません。
多くの場合、既存の仕組みが通用しない、あるいはそもそも仕組み自体が存在しない中で、新しい価値を創造していく必要があります。
そのため、誰かの指示を待つのではなく、自ら地域に入り込み、課題を発見し、解決策を考え、仮説検証を繰り返しながら事業を形にしていく主体性と行動力が不可欠です。
限られたリソースの中で創意工夫し、時には周囲を巻き込んでリーダーシップを発揮することも求められます。
前例のないことに挑戦し、失敗から学びながら、ゼロからイチを生み出すプロセスを楽しめる人が活躍できる環境です。
コミュニケーション力が高い人
地方創生の現場では、地域住民(特に高齢者)、行政職員、地元の経営者、NPO、移住者、他のベンチャー企業など、非常に多様な立場や価値観を持つ人々と関わることになります。
それぞれの意見や利害が異なる中で、プロジェクトを前に進めるためには、相手の話を丁寧に聞き(傾聴力)、自分の考えを分かりやすく伝え(説明力)、時には粘り強く交渉し、合意形成を図っていく(調整力)高度なコミュニケーション能力が求められます。
地域コミュニティに積極的に溶け込み、様々な人々と良好な人間関係を築ける力は、事業成功の鍵を握ると言っても過言ではありません。
柔軟性がある人
地方創生ベンチャーを取り巻く環境は常に変化しており、計画通りに進むことの方が稀です。
市場の変化、競合の出現、自然災害、地域特有の人間関係による影響など、予期せぬ問題が次々と発生する可能性があります。
そのため、当初の計画に固執せず、状況に応じて目標やアプローチを柔軟に変更できる対応力が重要になります。
また、都市部とは異なる独自の文化や慣習、ルールに適応することも求められます。
こうした不確実性の高い状況をストレスと感じるのではなく、むしろ変化を楽しみ、困難な状況でも前向きに解決策を探し続けられるタフさが求められます。
地域資源を活かすアイデアとビジネス感覚がある人
地方創生の取り組みを持続可能なものにするためには、社会的な意義だけでなく、経済的な合理性、つまりビジネスとして成立させる視点が不可欠です。
そのためには、地域に埋もれている魅力的な資源(豊かな自然、伝統文化、特産品、空き家、地域の人材や技術など)を発見し、それらを活用した新しい商品やサービス、事業を生み出すアイデア力が求められます。
さらに、そのアイデアを具体的な事業計画に落とし込み、収益を上げ、継続的に運営していくためのマーケティング、財務、マネジメントといったビジネススキルも重要になります。
社会貢献と事業性のバランス感覚が大切です。
地方創生ベンチャーで向いていない人の特徴
・保守的な風土や人間関係の難しさ
・リソースの不足
・成果が見えにくい
・プライベートとの境界が曖昧になりやすい
地方創生に向いていない人は、どのような人でしょうか。
ここでは、5つのポイントに絞って、地方創生ベンチャーに向いていない人の特徴を紹介します。
地域や社会課題への関心が薄い人
地方創生ベンチャーの仕事は、その根底に地域を良くしたい、社会課題を解決したいという想いがあります。
もし、こうしたテーマ自体に関心が薄く、共感できない場合、日々の業務の中にやりがいや意義を見出すことが難しくなります。
特に、地道な活動や泥臭い作業、成果が出るまでに時間がかかるプロセスに対して、モチベーションを維持するのが困難になるでしょう。
地域住民とのコミュニケーションにおいても、表面的な関心しか示せないと、信頼関係を築くのは難しく、結果として事業推進の妨げにもなりかねません。
情熱を持って取り組める分野でないと、長続きしない可能性が高いです。
受動的な人
ベンチャー企業、特に地方創生という新しい領域では、明確な業務マニュアルや確立された業務プロセス、手厚い研修制度などが整っていないことが一般的です。
役割や責任範囲も流動的で、自ら仕事を見つけ、考え、判断し、行動することが日常的に求められます。
常に上司からの具体的な指示がないと動けない、あるいは細かく管理された環境でないと不安を感じるというタイプの人は、このような環境ではパフォーマンスを発揮しにくいでしょう。
自律的に学び、能動的に動く姿勢がないと、活躍の場が限られてしまい、本人にとっても組織にとっても不幸な結果になりかねません。
多様な価値観を受け入れるのが苦手な人
地方には、都市部とは異なる独自の文化、長年続いてきた慣習、特有の人間関係が存在します。
また、関わる人々(高齢者、若者、移住者、行政職員など)の価値観も様々です。
自分の考え方ややり方が絶対だと考え、異なる意見や文化に対して非寛容であったり、拒否反応を示したりする人は、地域コミュニティに溶け込むのが難しく、円滑なコミュニケーションの障害となります。
多様なステークホルダーと協力して事業を進める必要がある地方創生において、異文化理解や多様な価値観の受容性が低いことは、致命的な欠点となり得ます。
安定志向な人
地方創生ベンチャーは、事業モデルが確立されていなかったり、資金調達に依存していたりと、経営基盤が不安定な場合があります。
また、外部環境の変化に応じて事業方針が大きく変わることも珍しくありません。
常に安定した雇用や予測可能な業務内容、確立されたキャリアパスを求める人にとっては、こうした不確実性の高い環境は大きな精神的ストレスとなるでしょう。
変化を恐れ、リスクを取ることを極端に避けようとする姿勢は、新しい挑戦が求められるベンチャーの風土とは相容れません。
安定を第一に考える人には不向きな環境と言えます。
給料や福利厚生を重視する人
地方創生のプロジェクトは、地域に根差した活動が多く、成果が目に見える形になるまでには長い年月を要することが少なくありません。
また、必ずしも大きな経済的利益に直結するとは限らず、給与や福利厚生といった待遇面でも、大手企業や都市部の企業に見劣りする可能性があります。
自身のキャリアアップや収入増といった短期的なリターンを何よりも重視し、社会的な意義や地域への貢献といった要素への関心が薄い人は、仕事に対する満足感を得にくいでしょう。
長期的な視点で地域と向き合い、コミットする覚悟がないと、ミスマッチを感じやすい環境です。
地方創生ベンチャーに向いている人
・主体性を発揮できる人
・結果と地域貢献のバランスを取れる人
・地域の資源に新たな価値を見出す人
・DX推進力を持つ人
地方創生ベンチャーに向いている人は、どのような特徴を持った方なのでしょうか。
ここでは、地方創生ベンチャーに向いている人の特徴を紹介します。
共感力がある人
地方創生事業の成功は、地域住民、自治体、地元企業、そして金融機関など、多様なステークホルダーとの信頼関係構築にかかっています。
都市型のベンチャーのように、プロダクトの力だけで事業を進めることは困難です。
そのため、高い傾聴力と共感力を持ち、地域の課題やニーズ、人々の想いを深く理解しようと努められる人が向いています。
具体的には、地域住民の「雑談」から本質的な課題を見つけ出し、異なる意見を持つ人々の間を取り持ちながら、共通の目標へと合意形成を導ける力が必要です。
一時的な成果よりも、地域に根差した持続的な関係性を築くことにやりがいを感じる「コミュニティ・ビルダー」としての資質が求められます。
主体性を発揮できる人
地方のビジネス環境は、情報や人材、インフラの面で都市部に比べて未整備な部分が多く、前例やマニュアルが存在しない状況に常に直面します。
そのため、誰かの指示を待つのではなく、自ら課題を発見し、解決策を企画・実行できる主体性とオーナーシップが不可欠です。
地方創生ベンチャーでは、営業、企画、マーケティング、財務、行政連携など、多岐にわたる役割を一人で担うことが多く、高いセルフスターター能力が求められます。
変化を恐れず、不確実な状況をむしろ楽しむことができ、限られた資源の中で最大の効果を出す創意工夫ができる人が、この分野で活躍できます。
結果と地域貢献のバランスを取れる人
地方創生ベンチャーは、社会的なミッションと経済的な持続可能性の二つの軸を同時に追求する必要があります。
単なるボランティア活動ではなく、ビジネスとして利益を生み出し、その利益を地域に再投資することで、初めて事業が持続します。
このため、社会貢献への強い情熱を持ちながらも、同時に収益性や生産性を厳しく追求するビジネス感覚を持つ人が求められます。
理想論だけでなく、スピード感を持って実行に移し、目に見える成果を出すことにコミットできる、ミッションと利益のバランス感覚に優れた人が向いています。
地域の資源に新たな価値を見出す人
地方には、埋もれた資源や見過ごされている魅力が豊富に存在します。
地方創生ベンチャーの重要な役割の一つは、これらの地域資源を、現代の市場や消費者のニーズに合わせて再解釈し、新たなビジネスモデルへと昇華させることです。
そのため、地域の「当たり前」を「魅力」として捉え直す好奇心と創造性を持つ人が向いています。
デジタル技術やデザイン思考といった新しいツールを柔軟に取り入れながら、地域の資産に高付加価値をつけ、地域ブランドとして国内外に発信できる着眼点と実行力が求められます。
DX推進力を持つ人
多くの地方が抱える課題の一つに、IT化・デジタル化の遅れがあります。
行政手続き、地域産業、商店街の活性化など、あらゆる分野でデジタル技術の活用が急務です。
したがって、基礎的なITスキルに加え、ITコンサルティング能力やプロジェクトマネジメント能力を持つ人が非常に重宝されます。
地域の関係者に対して、専門用語を使わず分かりやすい言葉でデジタル化のメリットと手順を伝え、抵抗感を乗り越えて変革を主導できる推進力を持つデジタル・チェンジメーカーが、地方創生ベンチャーの成功に不可欠な存在となります。
代表的企業20社を紹介
・シタテル株式会社
・株式会社ホープ
・ライフイズテック株式会社
・リノベる株式会社
・地域ブランディング研究所
・株式会社ジモティー
・FANTAS technology 株式会社
・株式会社ネクストビート
・株式会社Creema
・株式会社トラストバンク
・READYFOR 株式会社
・株式会社 trippiece
・株式会社skyer
・株式会社47PLANNING
・株式会社グローバル・デイリー
・エスビージャパン株式会社
・株式会社MeltingPot
・フラー株式会社
・LGBreakthrough
ここでは、地方創生ベンチャーを紹介しています。
代表的な6社を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
アソビュー株式会社
アソビをテーマにして地方での遊びを顧客に提供する企業になっています。
各地の観光業に地方創生を促すような事業を扱っています。
この企業については、今後大きく伸びる可能性があるでしょう。
なぜならば、今のトレンドに見事に合致する企業だからで、最近の観光業は、インバウンドに頼らない新たな道を模索している最中です。
これはコロナウイルスによるインバウンドの激減が教訓となっていて、いかに国内の旅行者に振り向いてもらうかという観点から観光業を見直しているところが増えています。
各地方行政も観光業に注目しているところは多いので、そういった観光資源が豊富な地域で地方創生に携わりたいという人にはとてもおすすめでしょう。
また、アソビがテーマなので、働いている社員としても、かなり楽しみながら仕事をすることができるのではないでしょうか。
楽しいことを考えるのが大好きというような人にもおすすめできます。
シタテル株式会社
インターネットを利用した衣服生産を手掛けている企業になっています。
オリジナルブランドを手掛ける企業でもありますので、価値の創造に非常に強い企業とも言えるでしょう。
そして、そういったブランドを確立するのが得意な企業は、地方創生にも向いていると言えます。
地方創生をするためには、地方のブランドを高める必要があるのです。
そういったノウハウを持っている企業なので、こちらの会社で地方創生に携わるのもおもしろいでしょう。
また、衣類生産を手掛ける企業になっていますので、ファッションやアパレル関係で働きたいと思っているような人にもおすすめです。
こういった業界とは、少し違った視点を持った会社になっていますが、だからこそ楽しく働ける可能性があるのではないでしょうか。
株式会社ホープ
これまでに紹介した企業とは、また違った観点から地方創生に携わる企業だと言えるでしょう。
自治体に対して広告、メディアを提供するサービスになっています。
自治体の財源確保に動くことによって、地方創生の金庫番としての立ち位置を確立しているのです。
地方創生に絶対に必要になってくるのが、お金です。
どこの自治体もお金さえあれば、地方創生をできるところは多いでしょう。
しかし、そのお金が厄介で、資源のないところにはなかなかお金が集まってこないのです。
だからこそ、こういった企業が重要であって、地方創生の中核を担うことになるといっても過言ではないでしょう。
広告やメディアを提供するベンチャー企業は多いですが、そういった企業で働くといまいちやりがいにかけるという人もいます。
しかし、この会社の場合は地方創生という大義名分がありますので、やりがいを獲得しやすいというメリットもあるでしょう。
ライフイズテック株式会社
ライフイズテックが提供しているサービスも、ある意味で地方創生を担っていると言えるでしょう。
なぜならば、地方にオンラインのIT、プログラミングの教育を提供するサービスだからです。
今後の地方創生には、ITと何かの連動が必要不可欠になってきます。
そして、地方にはこういったIT技術者が足りない状態が続いています。
技術者も首都圏や主要都市に集中していますので、どうしても地方で必要な開発ができないのです。
そこで、こういった企業のように、ITやプログラミングの教育を提供することによって、地方の技術者育成をサポートすることができます。
かなり間接的な地方創生ではありますが、こちらもとても大切なポジションであると言えるのではないでしょうか。
リノベる株式会社
個人向け住宅のリノベーションプラットフォームを展開している企業です。
空き家問題にコミットしています。
地方創生に、住居問題は密接に関係していきます。
住みたいと思える住居や通いたいと思えるお店があれば、地方も活性化する可能性があるのです。
だからこそ、こういったリノベーションプラットフォームは重要になってきます。
https://www.renoveru.jp/corporate/about/
地域ブランディング研究所
現場に赴いて、魅力を見つけてマーケティングやブラッシュアップを行う企業になっています。
最終的に型化をして自走できる仕組みづくりをするのが目的です。
自社で手掛けるだけではなく、その仕組みを地域に確立するというとても高度な取り組みを行っている企業だと言えるでしょう。
そのため、やりがいという意味ではかなりのものがあるでしょう。
株式会社ジモティー
株式会社ジモティーは地域密着型の情報掲示板サイト「ジモティー」を企画・開発・運営しています。
ジモティーは都道府県や市区町村ごとに情報を分類して掲載できるサービスで「売ります・あげます」「求人」「中古車」「不動産」「友達募集」など多彩なカテゴリの地域情報をユーザーが無料で投稿・閲覧できる点が魅力です。
また、ジモティーは「地域の今を可視化して、人と人の未来をつなぐ」というミッションを掲げています。
ユーザーファーストでサービスを育てる社風があり、自分自身も地域課題の当事者として主体的に動ける人材を求めているのです。
よって、知見のない領域にも「まずやってみる」姿勢で飛び込み、自らサービスとともに成長していきたい方におすすめできる企業と言えます。
FANTAS technology 株式会社
FANTAS technology株式会社は不動産テックの力で誰もが気軽に資産運用や物件取引に参加できるプラットフォーム「FANTAS」を提供しています。
主軸の「FANTAS platform」事業では不動産の売り手・買い手・投資家をオンラインでマッチングし、首都圏・関西・福岡のワンルームマンションを中心に豊富な物件情報を扱っています。
「不動産業界をテクノロジーで開かれたものにする」というビジョンを掲げており、新しい領域に挑戦したい方に向いている企業です。
金融・不動産・ITが交差する事業のため、いずれかの分野に知見がある人はもちろん、未経験でも学習意欲が高く柔軟に知識を吸収できる人は活躍できるでしょう。
株式会社ネクストビート
株式会社ネクストビートはライフイベント・地方創生・グローバルの3領域で幅広いサービスを展開しています。
日本最大級の保育士専門求人支援サイト「保育士バンク!」を運営しており、転職・就職支援だけでなく、保育施設向けの業務支援システムや人材定着支援、業界データの調査研究など、保育業界の採用から経営まで包括的にサポートしています。
社会貢献性の高い事業に情熱を持ち、ベンチャーマインド旺盛な学生に向いていると言えるでしょう。
急成長する環境下で常に新規事業が立ち上がるため、未知の課題に対して100%の準備がなくとも、まず実行に移すフットワークや、他社の10年分を1年で成し遂げるようなスピード感についていける行動力が求められます。
株式会社Creema
株式会社Creemaは日本およびアジア最大級のハンドメイドマーケットプレイス「Creema」を運営する企業です。
Creema全国の約19万人を超えるクリエイターによる1,000万点以上のオリジナル作品が出品されており、日本最大級の規模を誇ります。
1点から気軽に出品・購入が可能で、決済手段も豊富に用意されていることから、初心者でも安心して利用できます。
ハンドメイドマーケットプレイス事業では競合の少ない創成期から参入し、minneと並んで国内シェアの約80%を占める先駆者としてブランドを確立しました。
少数精鋭のベンチャー企業ですが、上場企業としての基盤もあるため、裁量を持って新規サービス開発に挑戦したい人、安定した経営環境で腰を据えて事業を育てたい人の双方に向いています。
株式会社トラストバンク
株式会社トラストバンクは自治体と都市住民をつなぐ日本最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を運営しています。
ふるさとチョイスは全国1,788ある自治体の約8割にあたる1,400以上の自治体が参加しており、地域の特産品や名産品など6万点以上の返礼品情報を掲載しています。
サイトの月間PVは約1億9,500万にも上り、SEOにも強いため寄付を検討する多くのユーザーがまず訪れるプラットフォームとなっています。
新卒採用の募集要項には「ビジョンに共感し、技術の力で社会課題を解決したい方」「月間2億PVを超えるサービスを支えることに意欲のある方」といったポイントが明示されています。
READYFOR 株式会社
READYFOR 株式会社日本初のクラウドファンディングサービス「READYFOR」を立ち上げたリーディング企業です。
国内最大級のクラウドファンディング・プラットフォームであり、これまでに2万件以上のプロジェクトに対して資金調達の機会を提供してきました。
READYFORの強みは「想いを集め、お金の流れを変える」という社会的意義の高い事業ドメインで確固たる実績と信頼を築いている点です。
クラウドファンディング市場ではソーシャル分野における支援案件数で圧倒的No.1の地位を誇り、難病の子どもの支援や災害復興、文化保存など多くの社会課題解決プロジェクトを成功に導いてきました。
金融と社会貢献を融合させた事業のため、金融業界やNPO業界に関心がある人「資金面から世の中を支えたい」という意志を持つ人に向いていると言えるでしょう。
株式会社 trippiece
株式会社 trippiece「みんなで旅を作る」をコンセプトに、旅行者同士をインターネット上でつなぐコミュニティ型旅行プラットフォームを運営していました。
2023年10月末をもってtrippieceの旅行コミュニティサービスは終了となり、株式会社くふうAIスタジオ(現株式会社くふうカンパニーホールディングス)に吸収合併されました。
現在、RETRIP系の事業としては、国内最大級の旅行・おでかけメディア「RETRIP」を運営しています。
メンバーは様々なバックグラウンドがあり、多様性を重視しているとのことで、色々な方と関わりたい人に向いていると言えるでしょう。
特に旅行好きな方やインターネット好きな方、幸せを届けるプロダクトを作りたいと考えている方におすすめできる企業です。
https://netsui.or.jp/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEtrippiece/
株式会社skyer
株式会社skyerは、ドローン技術の活用を通じて地方創生を推進しています。
主要な事業として、JUIDA認定のドローンスクール運営、空撮による映像制作、そして赤外線カメラを活用したインフラ点検など、多角的なドローン関連ソリューションを提供しています。
これらの技術を地方に導入することで、地域産業のDXと業務の効率化に貢献しています。
特にドローンスクールは、地域の人材育成と新規雇用に直結しています。
さらに、同社が運営する鳥取県初のプロバスケットボールチーム「鳥取ブルーバーズ」は、スポーツを通じて地域住民の一体感を醸成し、地域のにぎわい創出という文化的な側面からも地方創生を支えています。
株式会社47PLANNING
株式会社47PLANNINGは、日本の47都道府県の魅力を発信することに特化したイベントプロデュースとPR、そしてホテル事業を展開しています。
地方自治体と連携し、地域に根差した食や文化をテーマにしたイベントやPRブースを企画・運営することで、都市部の消費者に地方の魅力を届け、交流人口の増加を図っています。
特筆すべきは、分散型宿泊施設ブランド「BYAKU」の展開です。
これは、古民家などの地域資源を改修・活用することで、文化財の保全と観光客誘致を両立させ、地域経済に深く根差した持続可能な観光モデルの創出に貢献しています。
株式会社グローバル・デイリー
株式会社グローバル・デイリーは、訪日外国人をターゲットとした広告・PRを専門としています。
世界各国のメディアネットワークを活用し、地方自治体や観光施設、企業に対して、海外向けの戦略立案、広告、プロモーションを一貫して提供しています。
その最大の貢献は、大都市圏に集中しがちな外国人観光客の関心を地方の観光資源や特産品に向けることです。
このインバウンド誘致の強化は、外貨獲得を通じた地方経済の活性化に直結します。
また、アジア市場を中心としたクロスバウンド型施策も展開しており、地方の企業やブランドがグローバル市場へ進出する足がかりを作る役割も担っています。
エスビージャパン株式会社
エスビージャパン株式会社は、地域活性化とグローカル(グローバル+ローカル)な事業展開に焦点を当てたコンサルティングサービスを提供しています。
地方創生事業として、地域ブランドの価値を高めるための多言語対応の動画制作や、海外ネットワークを活用した特産品の販路拡大・輸出支援を行っています。
これにより、地方の資源に新たな市場を開拓し、生産者の所得向上をサポートしています。
さらに、地方自治体の行政事務局運営支援や、中小企業の事業承継サポートを通じて、地域経済の基盤強化にも貢献しています。
同社の活動は、地方の魅力を世界に発信し、地域経済の自立を促すことを目指しています。
株式会社MeltingPot
株式会社MeltingPotは、アートの力を活用して地方創生を推進している点が特徴です。
主要事業として、地域芸術祭の企画・運営や、アーティストと地域を繋ぐアーティスト・イン・レジデンスの委託運営を行っています。
アートイベントを通じて、地域外からの訪問者を呼び込み、地域のにぎわい創出に貢献しています。
また、空き家などの遊休施設をアートスタジオとして活用するなど、地域資源の有効利用にも繋げています。
アートを媒介とした住民とアーティストの交流は、住民が自身の地域の歴史や文化を再評価し、愛着を深めるという、文化的な側面からの地方活性化を促しています。
フラー株式会社
フラー株式会社は、デジタルパートナー事業として、主にアプリ開発とIT活用支援を通じて地方創生に貢献しています。
同社の強みであるスマホアプリの企画・開発や分析サービス「App Ape」の知見を活かし、自治体や地域企業に対してデジタルトランスフォーメーションを推進しています。
具体的には、観光、プロスポーツ、地域イベントなどのアプリ開発を通じて、住民の利便性向上と外部への情報発信力強化を実現しています。
また、地方に拠点を設置し、地方企業へのDX支援を行うことで、地域におけるデジタル人材の育成や雇用創出にも取り組み、地方の持続的な成長のためのデジタル基盤構築を支援しています。
LGBreakthrough
株式会社LGBreakthroughは、地方自治体との連携を目指す民間企業を支援するコンサルティングファームです。
元公務員や官民連携の経験豊富なコンサルタントが、民間企業の自治体ビジネス参入をサポートし、地方創生、観光振興、DXといった分野でのプロジェクト立ち上げから拡大までを伴走しています。
同社の貢献は、企業の持つ革新的な技術やアイデアを、自治体のニーズや行政のプロセスに合わせて最適化することにあります。
これにより、官民連携による先進的な地域課題解決や、新たな公共サービスの実現を促進し、自治体単独では難しかった地域の活性化と効率化に貢献する橋渡し役を果たしています。
地方創生ベンチャーに評価される人の特徴
・行動力がある人
・主体性がある人
・コミュニケーション能力がある人
・柔軟性がある人
・熱意を持って取り組める人
地方創生ベンチャーで評価される人の特徴として、どのような特徴が挙げられるでしょうか。
ここでは、複数のポイントに沿って、地方創生ベンチャーで評価される人の特徴を解説します。
地域への深い関心がある人
地方創生に携わるベンチャー企業は、地域社会への貢献を重視しています。
そのため、就活生には地域への深い関心と理解が求められます。
単に「地方が好き」という表面的な感情ではなく、地域の歴史、文化、産業、課題などについて具体的な知識を持ち、自身の言葉で語れることが重要です。
例えば、特定の地域が抱える過疎化、高齢化、産業衰退などの課題を理解し、その解決に向けた具体的なアイデアや提案ができる人材は高く評価されます。
また、地域独自の魅力や可能性を見抜き、それを最大限に活かす方法を考えられることも重要です。
地域の人々との交流を通して得た経験や、地域活性化に関する活動への参加経験などは、自身の関心と理解を具体的に示す上で有効なアピール材料となります。
地域への愛情と熱意を持ち、地域社会の一員として貢献したいという強い意志を示すことが重要です。
行動力がある人
ベンチャー企業は、変化の激しい環境の中で、自ら考え行動できる人材を求めています。
与えられた仕事をこなすだけでなく、自ら課題を発見し、解決策を提案し、実行に移せる能力が求められます。
例えば、学生時代に地域活性化プロジェクトを企画・運営した経験や、困難な状況下でも粘り強く目標を達成した経験などは、行動力と主体性を示す上で有効なアピール材料となります。
また、失敗を恐れずに新しいことに挑戦する姿勢や、常に改善を求める向上心も評価されます。
地域の未来を切り拓くという強い意志を持ち、自ら道を切り拓いていく開拓精神を持つ人材が求められます。
主体性がある人
地方創生ベンチャー企業が求める「主体性」は、ただ言われたことをこなすだけでは足りず、多層的な能力と姿勢を包括する概念です。
まず、彼らは課題発見と問題提起の主体性を重視します。
地方創生においては、目に見える問題だけでなく、潜在的なリスクや将来的な課題を察知する力が必要です。
地域住民との密なコミュニケーションや、現場の丁寧な観察を通じて、表面的なデータだけでは見えてこない、地域の本質的な課題を捉え、それを関係者に提起できる人材が求められます。
また、解決策の提案と実行における主体性も問われます。
既存の枠組みにとらわれず、柔軟な発想で革新的な解決策を生み出す力、そしてそれを具体的に実行に移すための計画性と行動力が重要です。
アイデアを出すだけでなく、関係者を巻き込みながらプロジェクトを推進し、実際に成果を出せる人材が評価されます。
コミュニケーション能力がある人
地方創生は、地域住民、企業、行政など、多様なステークホルダーとの連携が不可欠です。
そのため、高いコミュニケーション能力と協調性は、地方創生ベンチャーで働く上で重要な資質となります。
相手の意見を丁寧に聞き取り、自分の意見を分かりやすく伝える能力はもちろん、異なる価値観を持つ人々とも円滑な関係を築き、協力して目標を達成できる能力が求められます。
例えば、学生時代のチーム活動やボランティア活動などで、多様な人々と協力して成果を上げた経験などは、コミュニケーション能力と協調性を示す上で有効なアピール材料となります。
また、地域の課題解決には、地域住民との信頼関係構築が不可欠です。
地域の人々と積極的に交流し、彼らのニーズや想いを丁寧に聞き取り、共感する力も重要です。
柔軟性がある人
ベンチャー企業は、常に変化し続ける環境に置かれています。
特に地方創生ベンチャーでは、地域の状況やニーズに合わせて、事業内容や働き方を柔軟に変えていく必要があります。
そのため、固定観念にとらわれず、変化に対応できる柔軟性と適応力が求められます。
新しい知識やスキルを積極的に学び、変化を恐れずに挑戦できる人材が評価されます。
また、地方での生活や働き方は、都市部とは異なる側面も多く、それに適応できる能力も必要です。
例えば、学生時代に予期せぬトラブルにも冷静に対応し、状況に応じて柔軟に計画を変更した経験などは、柔軟性と適応力を示す上で有効なアピール材料となります。
熱意を持って取り組める人
地方創生は、決して簡単な仕事ではありません。
地域の課題は複雑で、解決には時間と労力がかかります。
そのため、高い熱意と情熱を持ち続けられる人材が求められます。
地域への強い愛情や、地域社会に貢献したいという強い意志は、困難な状況を乗り越える原動力となります。
自身の経験や価値観に基づいた具体的な言葉で、地方創生への熱意を語ることが重要です。
例えば、「将来は地域に根差した事業を立ち上げ、雇用を創出したい」「地域の伝統文化を継承し、観光資源として活用したい」など、具体的な目標やビジョンを示すことで、熱意と情熱が伝わります。
地方創生ベンチャーから内定をもらうためには
・他己分析
・企業研究
・インターンシップへ参加する
・OB・OG訪問をする
・説明会に参加する
地方創生に力を入れているベンチャー企業から内定を貰うためには、どのように対策をしていけばいいのでしょうか。
基本的には、選考を進めていく中で、具体的に何がしたいかやどのように貢献することができるかを伝えることが重要になってきます。
そのため、まずは自分自身についてもっと詳しくなり事や志望している企業に関して詳しくなる必要があります。
自己分析
ベンチャー企業は、大企業とは異なり、即戦力となる人材や、企業の成長に貢献できる人材を求めています。
そのため、自身の強みやスキル、価値観を明確に把握し、企業に対して「私は貴社でこのように貢献できます」と具体的に示す必要があります。
自己分析を通じて、過去の経験や実績を深く掘り下げ、どのような状況でどのような成果を出したのかを分析することが重要です。
単に「頑張りました」という抽象的な表現ではなく、「〇〇という課題に対して、〇〇という方法で取り組み、結果として〇〇という成果を達成しました」というように、具体的なエピソードと成果を結びつけて語れるように準備しましょう。
他己分析
他己分析は、自己分析を補完し、より客観的な自己理解を深めるための重要なプロセスです。
自己分析だけでは、どうしても主観的な視点に偏ってしまう可能性があります。
他者からの評価や意見を取り入れることで、自分では気づかなかった強みや改善点を発見し、自己理解を深めることができます。
ベンチャー企業の面接では、自己PRや質疑応答において、客観的な視点から自己分析の結果を補強することが求められます。
他己分析の方法としては、友人、家族、大学のキャリアセンター、OB・OGなど、様々な人に自分の長所や短所、印象などを聞いてみることが有効です。
特に、過去に一緒に仕事をした経験のある人や、自分をよく知っている人からの意見は、非常に参考になります。
企業研究
ベンチャー企業は、企業のビジョンや価値観に共感できる人材を求めています。
そのため、企業のウェブサイトや採用情報だけでなく、ニュース記事や社員インタビューなども参考に、企業文化や事業内容を深く理解することが不可欠です。
ベンチャー企業は、大企業と比べて規模が小さく、組織体制や企業文化が大きく異なる場合があります。
そのため、企業のウェブサイトやパンフレットだけでなく、社員インタビューやOB・OG訪問などを通して、企業のリアルな情報を収集することが重要です。
企業研究を通じて、企業の成長性や将来性、業界における立ち位置などを把握することで、入社後にどのようなキャリアを築けるかをイメージすることができます。
ベンチャー企業は、成長スピードが速く、変化も大きいため、企業の将来性を見極めることは、非常に重要です。
インターンシップへ参加する
インターンシップを通じて、企業の雰囲気や働き方を体験し、自分との相性を確認することができます。
ベンチャー企業は、企業文化や働き方が多様であるため、インターンシップで実際に働いてみることで、自分に合った企業かどうかを見極めることができます。
また、インターンシップは、社員とのネットワークを構築する絶好の機会でもあります。
インターンシップ中に積極的に社員とコミュニケーションを取り、自分の能力や熱意をアピールすることで、採用担当者の目に留まる可能性が高まります。
インターンシップに参加するためには、企業のウェブサイトや就職情報サイトで、インターンシップ情報を収集する必要があります。
ベンチャー企業のインターンシップは、募集人数が少ない場合や、選考倍率が高い場合もあるため、早めに情報収集を行い、応募準備をすることが重要です。
OB・OG訪問をする
OB・OG訪問は、企業のリアルな情報を得るための貴重な機会です。
ベンチャー企業は、企業文化や働き方が多様であるため、OB・OGから直接話を聞くことで、企業の雰囲気をより深く理解することができます。
OB・OG訪問を通じて、企業の強みや弱み、働きがい、キャリアパスなどを聞くことができます。
企業のウェブサイトや説明会では得られない、現場の社員ならではの情報を得ることができるため、企業選びの参考になります。
また、OB・OGとのネットワークを構築することで、選考に関するアドバイスや情報が得られることもあります。
OB・OGは、選考を経験した先輩として、面接対策や自己PRのポイントなど、具体的なアドバイスをくれることがあります。
説明会に参加する
企業説明会は、企業の担当者から直接話を聞くことができる貴重な機会です。
ベンチャー企業は、企業のビジョンや価値観に共感できる人材を求めているため、説明会で企業の担当者の話を聞くことで、企業の魅力をより深く理解することができます。
説明会を通じて、企業の事業内容や企業文化、採用情報などを詳しく知ることができます。
企業のウェブサイトやパンフレットだけでは分からない、企業のリアルな情報を得ることができるため、企業選びの参考になります。
また、説明会では、企業の担当者に直接質問する機会があります。
自分が知りたい情報を積極的に質問することで、企業への理解を深めることができます。
就活エージェントに相談する
ベンチャー企業の選考を進めていく際に、自分だけで行うとうまくいかないことがあります。
そのようなときは、自分以外の人に志望動機について相談すると良いでしょう。
専門の人に頼みたいのであれば、就活エージェントを活用してみてください。
専門的で高度なことを行っている企業への志望動機は不安になりがちですが、プロのアドバイザーがサポートしてくれるため、不安なく選考に臨むことができます。
無料で利用できるので、興味をお持ちの方はこちらのサイトをご覧ください。
まとめ
地方創生ベンチャーについて、かなり理解が深まったのではないでしょうか。
これからの時代を考えれば、かなりやりがいのある仕事になり、もしかするとこういった企業での成功が、国を救うことになるかもしれません。
これは決して大事ではなく、地方再生や地方創生というのは、今後の日本にとって、とても重要な課題になっているということを覚えておくと良いでしょう。