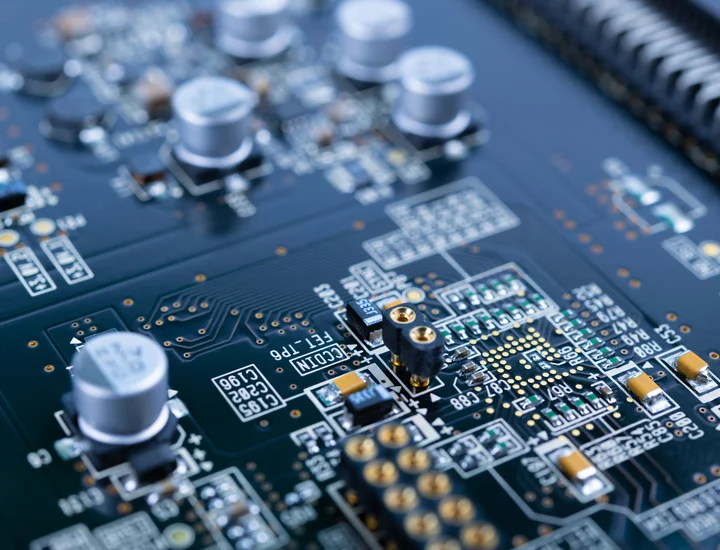- ベンチャー企業向けの志望動機の書き方
- 志望動機のおすすめ構成
- 厳選例文
- ベンチャー企業向けの志望動機の書き方を知りたい人
- 自分の志望動機に不安がある人
- 例文を参考にして志望動機を作成したい人
みなさんは、面接前に必要な志望動機をどのように書いているでしょうか。
就職活動を進めるうえで、志望動機は内定を得るためにとても重要なものです。
志望動機1つで、採用担当者が感じる第一印象は全然違うものになるでしょう。
今回は、志望動機をどのような観点で採用側は見ているのか、
また職種によってどのような書き方の違いがあるのかを詳しくご紹介します。
また、それらのポイントをふまえたうえで、実際に例文つきで各業種における志望動機の書き方もご紹介します。
業種によって志望動機に対する見方はバラバラです。
それに伴い、書き方は変化していきます。
まずこの記事を読んで、どのように志望動機を書けばいいのか、コツをつかんでください。
そして、第一希望の会社に就職できるよう努力していきましょう。
目次[目次を全て表示する]
【ベンチャー企業の志望動機】そもそもベンチャー企業とは
- 中小企業との違い
- スタートアップ企業との違い
ベンチャー企業は既存の業界において新しいサービスや商品を提供し、市場に新たな価値を生み出そうとする新興企業を指します。
ベンチャー企業は従来のビジネスモデルや技術に挑戦し、革新的なアプローチを通じて業界の構造の変革を目指しているのです。
また、スタートアップ企業とベンチャー企業はしばしば混同されますが、微妙な違いがあります。
スタートアップ企業は「設立されてから間もない段階の会社」で、ビジネスモデルの検証や市場での立ち位置の確立を目指していることが一般的です。
一方で、ベンチャー企業は「成長段階にあること」が多く、革新的な技術やサービスを用いて「既存の市場に」挑戦しています。
どちらの用語も高い成長ポテンシャルを持ち、革新的なアイデアを追求する企業の特徴を捉えていますが、スタートアップは「設立初期のフェーズ」に焦点を当て、ベンチャーは「成長途中の企業」というニュアンスが含まれることが多いです。
中小企業との違い
ベンチャー企業と中小企業には似たような特徴があるものの、根本的に異なる点があります。
まず、両者の定義について明確に理解することが重要です。
中小企業は従業員数が300人以下の企業を指し、その規模に関する基準が設定されています。
これに対して、ベンチャー企業は企業の規模ではなく、企業の性格や経営スタイルを示すものです。
また、ベンチャー企業と中小企業の違いは企業の規模や運営スタイルだけでなく、その企業が目指す成長戦略や文化にも表れます。
ベンチャー企業は常に新しい挑戦を追い求め、革新的な方法で市場に影響を与えようとする企業であるのに対して、中小企業は既存の市場において安定した成長を求める傾向があります。
以下の記事ではベンチャー企業と中小企業の違いについてさらに詳しく紹介しています。
スタートアップ企業との違い
ベンチャー企業とスタートアップ企業は似たような特徴を持つものの、ビジネスモデルや企業の成長段階において大きな違いがあります。
まず、ベンチャー企業は基本的に既存のビジネスモデルを基盤にしており、その上で事業のスケールを拡大し、収益性を高める工夫をすることに集中しています。
一方、スタートアップ企業はまだ新しいビジネスモデルを手探りで構築している段階であることが多いです。
スタートアップは革新的なアイデアを基に従来の市場にない新しい価値を提供しようとする企業であり、ビジネスモデル自体が未成熟な場合があります。
そのため、スタートアップは急速な成長を求めると同時に、実験的なアプローチを取ることが多いです。
【ベンチャー企業の志望動機】ベンチャー企業が求める人物像
- 自分で考えて動くことができる人
- 社長や企業の理念に共感できる人
- 変化に順応でき変化することを嫌がらない人
- 成長する意欲が高く、チャレンジ精神がある人
志望動機を書く際には、その企業がどんな人材を求めているのかを把握しておきましょう。
求める人材を理解しておくことで、担当者に刺さる志望動機が書きやすくなるからです。
自己分析を行う際にも、どんなエピソードを取り上げればいいのかわかりやすくなります。
これ以外にも企業によっては期待される能力や人材があるので、志望動機を書く前に必ずチェックしましょう。
自分で考えて動くことができる人
ベンチャー企業では業務が曖昧であったり、明確なマニュアルや指示がなかったりする場合が多いため、自分で考えて動ける人材が求められます。
急成長を目指しているため、従来の企業のように細かい指示に基づいて業務を遂行することは少なく、自己主導的な行動が重視されるのです。
そのため、与えられた業務に対して自分なりのアプローチを見つけ、柔軟に対応することが求められます。
多くのベンチャー企業は業務においては実験的な試みが多く、失敗を恐れずに改善を重ねていく姿勢が重要視されるため、何も指示がない中で、自分で目標を設定し行動することができる人材は貴重です。
社長や企業の理念に共感できる人
社長や経営者のビジョンや企業の理念に共感できることは志望動機において非常に大きなポイントとなります。
ベンチャー企業は企業の規模が小さいため、企業の方向性が経営者や創業者の考え方に大きく影響されます。
経営者が掲げる理念やビジョンが、企業文化に深く根ざしており、社員一人ひとりがその理念に共感し、実現に向けて努力することが重要です。
したがって、企業の理念に対する共感がないと、職場でのモチベーションの維持が難しくなり、企業にとっても不利となる可能性があります。
企業理念に共感できるかどうかを判断するには、まずその企業がどのような価値観を持ち、どのような目標を設定しているのかを理解することが大切です。
その理念に共感し、自分がどのようにその理念に基づいた行動を取れるかを示しましょう。
変化に順応でき変化することを嫌がらない人
ベンチャー企業では急速に成長を目指す中で、状況が変化することが頻繁にあります。
そのため、変化に柔軟に順応できる人材が求められるのです。
特に企業の成長段階においては事業戦略や方針が急激に変わることがあり、社内の構造や業務の進め方も変化します。
こうした環境においては、変化を恐れず積極的に取り組む姿勢が重要です。
また、ベンチャー企業は意思決定が迅速であり、経営陣が素早く方針を変更する場合もあります。
そのため、臨機応変に対応し、短期間で新しい方針や仕事の進め方に適応できる柔軟性が不可欠と言えるでしょう。
成長する意欲が高く、チャレンジ精神がある人
ベンチャー企業は新しい市場や未開拓の分野に挑戦することが多く、そのためには新しいことに挑戦できる人材が必要です。
ベンチャー企業ではまだ成熟していない市場をターゲットにすることが多く、未知の領域に対して積極的にチャレンジする姿勢が重要です。
このような環境で働くためには、自らが成長し続ける意欲を持ち、新しい課題に取り組みながら自分を高めていく姿勢が求められます。
成功するためにはリスクを取る覚悟と、そのリスクに対して前向きに挑戦し続ける心構えが必要でしょう。
【ベンチャー企業の志望動機】ベンチャー企業の志望動機を考えるポイント
- なぜその企業を選んだか
- 企業の魅力を伝える
- どのように企業に貢献するか
ベンチャー企業の志望動機を考えるときのポイントは「なぜその企業を選んだか」「企業の魅力を伝える」の2つです。
この2つは、大企業を志望するときにも押さえておくべきポイントですが、とくにベンチャー企業では重視される傾向にあります。
大企業と比べれば知名度が低く、待遇も良いわけではないベンチャー企業を選んだ理由を説明する必要があるからです。
自己分析や企業研究の時点で、このポイントを意識して志望動機が書けるように取り組みましょう。
なぜその企業を選んだか
志望動機を考えるときの1つ目のポイントとして、なぜその企業を選んだかの理由を必ず述べましょう。
ベンチャー企業では、応募者が企業を選択した理由を重視する傾向にあるからです。
大手企業と比較すれば、ベンチャー企業は知名度も安定性も低くなっています。
例えば、説明会などで大きなブースを設置できるわけではないため、誰もが知っているわけではありません。
また、多くのベンチャー企業は経営基盤が安定していないため、不景気では失業のリスクも高まります。
そんな中でも、なぜベンチャー企業で働きたいと考え、志望したのかを明確に書く必要があります。
とくに学生時代の経験などを踏まえた理由があると説得力が高まるので、自己分析を徹底して行いましょう。
企業の魅力を伝える
志望動機を考える2つ目のポイントは、企業の魅力を志望動機で伝えることになります。
ベンチャー企業は企業を成長させるため、仕事に対するモチベーションが高い人材を求めているからです。
新事業・新領域に取り組むベンチャー企業は、ビジネスを成功させないと生き残れません。
そのためには、ときには業務量が多くなったり、不本意な業務を与えられたりすることもあるでしょう。
それでも働きたいと思えるためには、経営方針への共感や経営者への信頼が求められます。
このため、志望動機においては待遇面ではなく、企業の理念や経営ビジョンなど仕事面での魅力を伝えましょう。
ベンチャー企業は公開情報が少ないこともあるので、非公開情報を入手するために、就活エージェントの活用も検討してみてください。
どのように企業に貢献するか
企業は自社に利益をもたらすと判断した人を採用します。
人を一人雇うだけでも、企業側は100万円近く、あるいはそれ以上のコストを支払うことになります。
利益を求めている以上、それ以上のリターンを期待しているのです。
つまり、自分がその企業にとってどのように貢献できるかをアピールするのは企業側のメリットに直結するものであり、非常に重要なファクターとなるといえるでしょう。
また、採用活動に大きなコストがかかる以上、企業はなるべく長く働いてもらいたいと考えています。
志望理由は、それを見極める判断材料にもなり得ます。
雇った人に長く働いてもらうというのはコスト面以外にもさまざまなメリットがあるため、その点をうまくアピールするようにしましょう。
【ベンチャー企業の志望動機】志望動機を書く前にやること
- 自己分析をする
- 業界・企業研究をする
- 企業の情報収集をする
続いて、志望動機を作成する前に取り組んでおきたいことについて紹介します。
以下の3つの対策をあらかじめ行った人と、そうでない人では志望動機のクオリティが大きく異なりますし、最終的に作成にかかる時間も大きく異なります。
一見遠回りに思えるかもしれませんが、まずは以下の3つの準備を行ってから志望動機作成に取り組んでみてください。
自己分析をする
志望動機を作成する前にはまず自己分析を徹底して行うことが大切です。
自己分析を通じて自分の特徴や価値観を整理し、過去の経験から強みを発見すれば、より説得力のある志望動機を作成できます。
自分のこれまでの取り組みや成果などについて振り返り、自分がどのような場面で力を発揮したか、どのようなことが苦手だったのかについて思い出してみてください。
学生時代の経験、アルバイト、プロジェクトなど、様々な場面で発揮した力や印象に残っている出来事を棚卸ししましょう。
自分が大切にしたい価値観や、どのようなキャリアを目指しているのかといったことを明確にすることで、志望動機に一貫性が生まれます。
業界・企業研究をする
ベンチャー企業の志望動機を作成するにあたっては業界と企業の研究を入念に行う必要があります。
業界全体の動向や成長性を理解すれば、志望する企業が業界内でどのような立ち位置になるかを把握できるでしょう。
急成長している分野や、新たなビジネスモデルが登場している業界においてはその流れをつかむことが特に大切です。
業界研究を通じて得た知識は志望動機に具体性を持たせるための根拠となります。
その企業が特定の技術やサービスに強みがあるならば、その背景を理解しておくことで企業のビジョンとの共通点まで確認できるでしょう。
企業が掲げる目標や価値観が自分のキャリアビジョンと一致していることを示すことで、入社意欲の高さが伝わります。
業界の中でその企業が直面している課題や今後の展望まで理解できていれば、さらに差別化された志望動機が作成できるでしょう。
また、深掘り質問などをされた時にも、自信を持って回答できるようになります。
企業の情報収集をする
企業の情報収集を徹底的に行うことも欠かせません。
ベンチャー企業はそれぞれ異なるビジョンや事業展開を持っていることが多いため、表面的な理解では説得力のある志望動機が作れないことが多いです。
公式サイトやSNSなど、様々なツールを駆使して、企業が掲げる価値観や今後の方向性を把握しておきましょう。
また、企業の経営層の考え方を知るために社長や経営者のインタビュー記事を読むこともおすすめです。
創業者の思いや事業に対する情熱を理解すれば、企業文化や働く環境をより深く理解できるでしょう。
また、可能であれば就活イベントや説明会、インターンなどに参加することを推奨します。
直接社員の方々から話を聞けば、現場の雰囲気や求められる人物像をさらに具体的に理解できるからです。
【ベンチャー企業の志望動機】志望動機の構成
- 結論:志望理由
- 理由:その結論至った理由
- 具体例:なぜその理由になったのかエピソードと背景
- 結論:入社後に活躍できる
志望動機を構成していくうえで、ビジネスシーンでもよく使われる「PREP法」に基づいて完成させていくと、
よりスムーズで好印象を与えられる文章になるでしょう。
この方法を簡単に説明すると、
「結論→理由→例→結論」
の順で文章を構成します。
そうすることで、伝えたいことを簡潔に伝えられ、例を途中に挟むことで具体的な考えも伝わりやすいです。
そこで、どのような形でそれぞれの部分を書いていけば良いか、具体的にご紹介していきます。
結論:志望理由
まず志望理由を短く簡潔にまとめて、ストレートに一番伝えたいことを伝えてみましょう。
導入に1番伝えたい部分をもってくることで、後々その理由や例の部分で、より相手へ自分の考えが伝わりやすくなります。
ただ簡潔にまとめるといっても、簡潔すぎて伝わらなくなってしまっては意味がありません。
自分が伝えたいことをあとの部分で補足する想定をしながらまとめ、
なおかつ採用担当者の印象に残るようなインパクトのある理由にできれば完璧です。
とにかく短くても、印象に残るような文章が作れるように考えましょう。
そうすることで、のちの文章でどんなことを語ってくれるのかと引き付けられ、さらにどんな人材なのかと興味をもってくれるはずです。
理由:その結論至った理由
志望理由を導入部分で伝えたあとは、その理由に至るまでの背景や、具体的なエピソードを盛り込みながら文章を作成しましょう。
この部分でいかにオリジナリティを出して、ほかの就活生と差別化をはかるかが採用への大きな近道となります。
言い換えれば、この部分はほとんどの就活生が汎用的な内容になりがちなのです。
つまり、採用担当者の印象を悪くしてしまう一因となりやすいといえるでしょう。
なぜ汎用的な内容が悪印象かというと、決して就活生全員が、同じような出来事を体験しているわけがないからです。
一人ひとりにそれぞれの物語があり、採用担当者はその物語を通じて、その人のことを知りたいのです。
そのことを理解し、より具体的なエピソードを盛り込んで自分のことを理解してもらえるよう、努力しましょう。
具体例:なぜその理由になったのかエピソードと背景
なぜそのような志望動機を抱くに至ったのかについて、エピソードと背景を分かりやすく説明することが重要です。
この具体例の部分が最も差別化できるポイントであるため、特に力を入れて書く必要があります。
基本的に志望動機や自己PR、ガクチカなどにおいては、常に具体例の部分を特に強調して書くようにしましょう。
これは、自分の価値観を伝えられる部分であるだけでなく、企業側が最も重視しているポイントです。
可能な限り、誰が読んでも理解できるようなわかりやすい表現を用い、あなたの志望動機や熱意が分かりやすく伝わるような回答を心がけましょう。
結論:入社後に活躍できる
ここまでは自分自身の会社に対する思いや、その思いに至るまでの過程など、感情的な部分について詳しく書くことを述べてきました。
それらの部分を十分伝えられたら、つぎは「どのように会社に貢献できるような力があるか」という点を伝えましょう。
熱意だけで入社しても、いざ働き始めると、自分の力と企業がマッチしなかったということもよくあります。
そうすると早期退職を余儀なくされ、会社側も就職した側もマイナス面しか残りません。
したがって、入社後に成長して力を発揮してくれる人材であると、入社前の段階で思わせることが重要になってきます。
自分は何ができて何ができないのかを明確にし、そのうえで貢献できることについて具体例を交えながらわかりやすく伝えましょう。
【ベンチャー企業の志望動機】アピール時のポイント
- 熱意や志望度の高さをアピール
- ビジョンや方向性に共感したことをアピール
- 待遇以外で魅力に感じたことを伝える
ベンチャー企業が志望動機を伝えるポイントや、ベンチャー企業が求める人材について分かってきたところで、続いては志望動機でアピールする際のポイントについて詳しく紹介していきます。
下記の3つを念頭に置いた上で文章を作成することで、より企業の採用担当者に良い印象を持ってもらえる文章が作成できることでしょう。
熱意や志望度の高さをアピール
熱意や志望度の高さをアピールすることは、一般企業を受けるにも重要なことではありますが、ベンチャー企業の場合、さらに重要であると言えます。
ベンチャー企業の多くは新しい事業を展開し、どんどん会社を大きくしていこうと高いモチベーションで業務に取り組んでいます。
同じように熱意のある人材が入ってくることは、企業にとって非常に望ましいことです。
また、ベンチャー企業は規模が大きいわけではないので、せっかく採用しようと思った人材が内定を蹴って、他のところに行ってしまった場合、かなり損失が大きいです。
そこで、内定を出した場合はきちんと就職してくれそうな、熱意のある人材を重視して作業する傾向にあります。
ビジョンや方向性に共感したことをアピール
ビジョンや方向性に共感したことを強くアピールすることができれば、企業の採用担当者に強い印象を与えることができます。
ベンチャー企業は能力の高さや経歴、学歴などを重視しないわけではありませんが、どちらかというと、モチベーションの高さや同じ方向を向いて働けるかどうかを重視しています。
いくら能力が高い就活生であったとしても、ビジョンに共感していない、もしくはやる気がないと感じられる場合は、採用をためらわれることが少なくありません。
しかし、現時点で即戦力として活躍できる可能性が低かったとしても、ビジョンや方向性に強く共感し、モチベーションが高いと感じられる人物は、採用される可能性が高いです。
したがって、企業に対して深い理解があり、ビジョンや方向性に強く共感していることを力強くアピールすることを推奨します。
待遇以外で魅力に感じたことを伝える
待遇の話ばかりをしてしまうのは、どの企業の面接を受ける際にもよくありませんが、特にベンチャー企業の場合は「待遇以外で」魅力に感じたことを積極的に伝えることが重要です。
なぜならば、ベンチャー企業は社員のモチベーションの高さや、新しい業務に取り組むというやりがいにおいては素晴らしいものがありますが、大手の企業と比べると待遇が良くない場合が多いからです。
よって、待遇を重視している人材であることを知られてしまうと、「他の企業に内定した場合、うちの内定を蹴られてしまうかもしれない」と採用の優先順位を下げられる可能性があります。
魅力に感じた点は企業のビジョンや目標、取り組んでいる事業などの、モチベーションが伝わる、待遇以外の内容にすると非常に良いでしょう。
【ベンチャー企業の志望動機】差別化するには
- 情報量で差別化
- エピソードを変えて差別化
続いて、ベンチャー企業を受ける際の志望動機を作成する際に、他の就活生と差別化するポイントについて詳しく紹介していきます。
下記の2点を重視して志望動機を作成することで、他の就活生よりもあなたが魅力的に映る可能性が高まります。
情報量で差別化
志望動機において、企業のどのような点に魅力を感じたのか述べるのは非常に重要なことではあります。
しかし、企業の話ばかりしてしまうと、他の就活生と同じような内容になってしまいます。
そこで、自分の情報量を増やして、独自性のある志望動機を作成するようにしましょう。
企業に対してなぜ自分が魅力を感じたのか、どのような経験を通じて、今受けているベンチャー企業に魅力を覚えるようになったのか、自分の話を含めて話すことで、相手にもあなたの魅力が伝わりやすくなり、あなたの人となりが理解しやすいでしょう。
エピソードを変えて差別化
最終的に伝えることが同じであろうが、エピソードを交えるか交えないかでは大きな違いがあります。
どのような経緯で今受けている企業に魅力を感じるようになったのか、印象に残りやすいエピソードを用いると良いでしょう。
例えば、実際にその企業のサービスを利用したエピソードでも良いですし、その企業が取り組んでいる事業に対して魅力を覚えた経緯などでも良いです。
もしインターンシップに参加したならば、そのエピソードは必ず交えるようにすると良いでしょう。
このように、志望動機のエピソードに印象に残りやすいものを用いることで、他の就活生と差別化を図ることができます。
【ベンチャー企業の志望動機】作成時の注意点
- 文字数指定の8割は埋める
- 書き言葉に気をつける
- 誤字脱字
ここからは志望動機を作成するにあたっての注意点について詳しく紹介していきます。
これはベンチャー企業を受ける場合に限らず、大手企業でも受ける場合でも非常に重要なポイントなので、注意した上で作成するようにしましょう。
就活においてはプラスのイメージを与えることも重要ですが、マイナスなイメージを避けることも重要です。
なぜならば、就活は総合点で判断されるからです。
よって、マイナスなイメージを与えないような工夫もしっかりと行っていきましょう。
文字数指定の8割は埋める
どれだけ文字数の指定が多かろうが、指定の8割は必ず埋めるようにしましょう。
なぜならば、文字数が少ないと「やる気がない」と思われてしまうからです。
基本的に志望動機においても自己PRにおいても、本当に行きたい企業ならば自分の魅力を最大限に伝えるために、文字数いっぱい使って必死にアピールする人が多いはずです。
しかし、そんな中で文字数の8割も満たしていない人物は「そもそもあまり入社したいと思っていない」と判断されてしまう可能性があります。
よって、文字数指定が800字や1,000字など、あまりにも一般より多い場合は埋めることが難しい場合もあるかもしれませんが、400字、600字など一般的な数字の場合はなんとか工夫をして文字数を埋めることが大切です。
書き言葉に気をつける
これまであまり長い文章を書いてきたことのない人の場合、書き言葉と話し言葉を間違えてしまうこともあるのでしっかりと注意しましょう。
一般的なビジネスの場面ですらある程度の話し言葉は許容されることはありますが、書き言葉となると異なります。
「やっぱり」と「やはり」「やっと」と「ようやく」「いつも」と「常に」「どうして」と「なぜ」など、さまざまな書き言葉と話し言葉の違いがありますが、文章で書き言葉を使ってしまうと、国語能力が低い、常識があまりない人材とみなされてしまう可能性が高いです。
よって、志望動機を作成し終わった後は、誰かに確認してもらうのはもちろんのこと、自分でも話し言葉と書き言葉に着目して、間違った表現をしていないか確認することが非常に重要です。
誤字脱字
これは当然のことと言えますが、誤字脱字が多いとやる気のない人物、注意力散漫な人物であるという印象を与えてしまいます。
就職したいと強く思っている、志望度の高い企業においては特に、何度も何度も文章が間違っていないか、誤字・脱字がないか確認しましょう。
たった数百字の中に何度も誤字脱字が入っている人物は、「きちんと対策していない」「そもそもやる気がない人物」であると思われてしまう可能性が高いでしょう。
ビジネスの現場で誤字脱字はNGです。
誤字脱字の多い人を採用して、取引先へのメール連絡で、ミスを繰り返されると、企業自体のイメージを下げてしまう可能性もあるので、採用したいと思ってもらえないでしょう。
【ベンチャー企業の志望動機】志望動機の例文
ここからは今までのポイントをもとにベンチャー企業に刺さりやすい志望動機の例文を5つ紹介します。
ぜひ参考にしてください。
将来成し遂げたいことをテーマにした例文
大手企業向けの志望動機の場合、その会社に入社して、将来何を成し遂げたいかを盛り込みながら作成すると良いでしょう。
たとえば、食品系の大手企業の場合は
「この会社に就職し、社会全体のフードロスを限りなく減らせるような商品の開発をし、貧困で困ってる人々を少しでも助けられるような人材になりたいです。」
などと具体的な目標を盛り込むと、どのような志のある人間なのか伝わりやすいです。
最終的にどのようなゴールを見据えているのかを明確にして文章を作りましょう。
また、別の手段として
「その会社の魅力と自分の魅力がマッチし、その結果何を生み出せるか」
を提示できると強みになるでしょう。
「貴社の環境保全に対する姿勢にとても魅力を感じています。
そして、私は大学時代に自然に対する有害物質の研究に力を入れてきました。
この私の強みは貴社とマッチしていると感じ、入社し力を発揮できれば、生態系へプラスの影響を及ぼすような開発ができます。」
このように、将来のビジョンが見えるような文章を目指すことが大切です。
自分自身の成長をテーマにした例文
ベンチャー企業向けの志望動機は、自身の成長を軸に考えて、
成長することでその企業にどう貢献できるかというポイントを志望動機に盛り込むと良いでしょう。
ベンチャー企業は現段階でまだ成長段階にある、発展途中な企業であることが多いため、
バイタリティーにあふれた人材を求める傾向にあります。
日々目まぐるしいスピードでIT化が進む世の中において、
海外に対抗できるような新たなシステムを将来開発したいと学生時代に思い、就職活動をしていたところ、貴社に出会いました。
入社後は学生時代に培ったチャレンジ精神やハングリー精神を軸に仕事へ取り組みたいと思っています。
また自身が成長することで、新たな社会の基盤となるシステムを作り上げ、社会と貴社に貢献することが目標です。
このように、将来の具体的な高い目標を掲げながら、その目標に対して仕事に取り組み、
自分自身も同時に成長するという明確なビジョンを見据えた内容にしましょう。
営業職で自分のスキルをテーマにした例文
営業職向けの志望動機では、営業という職業にはどんなスキルが必要か、というポイントを押さえておく必要があります。
特に、営業職は「コミュニケーション能力」と「提案力」がとても大切です。
この2つの能力を持ち合わせているとわかるエピソードを盛り込みながら、自身の人柄もわかりやすい文章にできれば良いでしょう。
貴社の魅力である、地域の企業と密接な関係を築きながら仕事をするという点にとても惹かれました。
私自身、学生時代に地域の発展のために祭りのボランティアに参加し、人と人とをつなぐことに幸せを感じる機会に恵まれておりました。
そのため貴社に入社して、よりほかの企業との結びつきを強める、架け橋となるような営業マンに成長できると確信しています。
このように、自分をアピールするために伝えたいことを強調しながら書いていくと、より印象に残りやすいでしょう。
強い印象を残すことで、入社後にもライバルより一歩リードした状態で選考をスタートすることもできます。
マーケティング職で自分のスキルをテーマにした例文
マーケティング職の志望動機では、情報を収集する能力に長けているというポイントを明確に伝えられれば、
採用への道は一気に開かれるでしょう。
常にトレンドを肌に感じながら、アンテナを張って敏感に情報を察知することが大切です。
したがって、人に対しての気づかいができる方や、
身の回りの流行をいち早くとらえているというエピソードを盛り込みながら志望動機を書いていくと良いでしょう。
貴社の一番の魅力である、トレンドを常にいち早く発信しているという点で入社後に自分が輝ける会社だと思っております。
なぜなら私も学生時代にSNSやブログを通じて、
人々が日常で新鮮に感じ、楽しめるような物事はないかと常に考えながら、トレンド情報を発信してきました。
この経験や自身の発信力を貴社で発揮することで、
学生からお年寄りまで楽しめるような新たなトレンドを常に開発・発信できると思っております。
この文章のように、実際に実績があることをアピールポイントの軸として考えることができれば、採用に近づくでしょう。
そのような実績がなくても、常にどう努力をし、自分自身はどのような感性があるのかを意識しながら伝えてみましょう。
事務職で自分のスキルをテーマにした例文
事務職への志望動機では、具体的なパソコンスキルや事務スキルがあることを前面にアピールしながら、
そのスキルを活かして、その企業にどう貢献できるかを伝える必要があります。
ExcelやWordをいかに使いこなせるか、前の職場でそれらのツールを使いこなして、どのように仕事の効率化をはかったかなど、
過去に行ってきた具体例を交えながらアピールしましょう。
貴社に入社できたならば、○○株式会社で〜年間事務員として勤務してきた経験を活かし、
社員全員の立場や仕事内容を考えつつ、作業の効率化を大幅に改善できます。
常に効率化を考えることで、自身のスキルをより高めていく必要もあるかもしれません。
しかしそうすることで、会社と社員が共に成長していくという、理想形を実現させていくことも可能になると考えております。
常に成長と周りに気配りを心がけ、周りの方々にも影響を与えられる人材として、入社後は成長していきたいと思います。
事務職は常に周りの社員に対する心遣いと作業の効率化を考えなくてはいけない職種です。
それらを実現するためのビジョンをどうもっているかを伝えましょう。
【ベンチャー企業の志望動機】業界別例文
ここからは業界別に志望動機の例文を紹介していきます。
多岐にわたる業界に関する志望動機の例文を紹介してはいますが、全て構成はここまで紹介してきたものを参考にして構いません。
どこを受けるに当たって、志望動機の構成というものはフォーマットが存在するのでそれに沿ったものを作成することで、企業に読みやすく、良い印象を与えられる文章を提出できることでしょう。
コンサルティング
大学時代に経営学の授業で学んだケーススタディを通じて特に興味を持ちました。
ある多国籍企業が直面していた市場進出の課題を解決するプロジェクトに取り組んだ際、その複雑さと解決に向けた戦略立案の過程に魅了されました。
この経験から、企業の課題に対する洞察を深め、具体的な解決策を提案する能力を身につけたいと強く感じるようになりました。
貴社に興味を持ったのは、その実績豊富なコンサルティングサービスと、クライアント企業の持続可能な成長を実現するための独自のアプローチに惹かれたためです。
入社後は貴社のネットワークとリソースを活用し、クライアント企業のビジョン達成に貢献することを目指します。
特にデータ分析と戦略立案のスキルを活かして、革新的な解決策を提案し、実行に移すことで、クライアント企業だけでなく、貴社の成長にも貢献したいと考えています。
商社
留学中に多様な文化背景を持つ人々と交流し、異文化間のコミュニケーションの重要性と魅力を実感し、現地での市場調査プロジェクトに参加し、地域特有の商習慣や消費者行動を理解することの業務への直接的な影響を学びました。
貴社が持つグローバルなネットワークに魅力を感じ、商社業界への興味が一層深まりました。
貴社の事業は、私が学んできた国際関係や異文化間交流の知識を活かし、より大きなスケールでの貢献が可能であると感じています。
入社後は貴社のグローバル事業の一員として、国際市場でのビジネス展開を支援したいと考えています。
特に、新興市場におけるビジネスチャンスの発掘や、持続可能なビジネスモデルの構築に貢献することで、貴社のさらなる成長と、その市場における社会経済発展に寄与したいと思っています。
IT
大学でコンピュータサイエンスを学び、プログラミングとアプリケーション開発に没頭した際に興味を持ちました。
特に、限られた時間の中でチームと協力して実用的なソフトウェアソリューションを開発した際、技術がいかに迅速に社会的課題を解決できるかを実感しました。
貴社が展開している革新的な製品とサービス、特にAIとデータ解析を活用したプロジェクトに大きな興味を抱きました。
貴社の技術が業界に与える影響力と常に進化し続ける企業文化は、私が目指すキャリアパスと完全に一致しています。
入社後は、私のプログラミングスキルと問題解決能力を活かし、貴社の製品開発チームの一員として貢献したいと考えています。
特に、AIや機械学習のプロジェクトに関わり、革新的なアイデアを実現し、貴社の技術的リードをさらに前進させる所存です。
金融
経済学の講義で金融市場の影響力とそのメカニズムについて学んだことがきっかけで、この夢を抱きました。大学でのインターンシップで金融機関に関わる機会があり、現実のビジネスシーンで金融が果たす役割の大きさと、そのダイナミズムに深く魅了されました。
特に、貴社が持つ幅広い金融サービスと、革新的な取り組みに対する強いコミットメントに大きな魅力を感じています。
入社後は、私の分析力と市場に対する洞察を活かし、貴社の金融コンサルティング部門で活躍したいと考えています。
また、新しい金融技術の導入によるイノベーションにも関わり、貴社のサービスをさらに進化させ、顧客に新たな価値を提供することに貢献したいと思っています。
海運
この関心は、大学でのサステナビリティに関するプロジェクトに取り組んだ経験によって深まりました。
特に、あるプロジェクトで海運業界がグローバルな貿易と環境に与える影響について研究した際、この分野で働くことの意義と、改革の可能性を強く感じました。
貴社が取り組んでいる環境保護への取り組みと、効率的な物流サービスの提供に対する強いコミットメントに大きな魅力を感じています。
貴社の持続的な事業運営と、革新的な技術を取り入れた物流ソリューションの展開は、私が目指すキャリアパスと完全に一致しています。
入社後は、私の分析力と問題解決能力を活かして、貴社の運航効率化や環境負荷の低減に貢献したいと考えています。
特に、最新のテクノロジーを利用した物流管理に携わり、貴社のサービス品質の向上と環境保護への取り組みに貢献することを強く望んでいます。
人材
大学でのボランティア活動を通じて、多様な背景を持つ人々の潜在能力を引き出し、彼らが直面するキャリアの障壁を乗り越える手伝いをした際にこの夢を抱きました。
キャリアカウンセリングのイベントを企画し、参加者が自己実現に向けた一歩を踏み出すきっかけを作ることができた時、人の可能性を引き出し支援する仕事の価値を実感しました。
貴社が提供する多様な人材サービスと、個人のキャリア成長を促進するための独自のプログラムに魅力を感じました。
貴社のビジョンである「人々の働き方と生き方を豊かにする」は、私の価値観と完全に一致しており、この業界で働くことへの意欲を更に高めてくれました。入社後は、私のコミュニケーション能力と人を理解する力を活かし、一人ひとりに最適なキャリアサポートを提供したいと考えています。
不動産
都市計画に関する授業を受けたことがきっかけで、この夢を抱きました。
不動産が個人の生活質や地域社会に与える影響は大きく、地域コミュニティの再開発プロジェクトに参加した際、効果的な不動産開発が地域の活性化にどれほど寄与するかを目の当たりにし、この分野でのキャリアを強く望むようになりました。
貴社が手掛ける先進的な不動産プロジェクトと、持続可能性を重視した開発方針に大きな魅力を感じています。
貴社のプロジェクトは、ただ建物を建設するだけでなく、環境や地域社会に配慮した価値ある空間を創出しており、私が目指す価値観と完全に一致しています。
入社後は、私の計画能力と創造性を活かし、貴社の一員として貢献したいと考えています。
食品メーカー
大学の栄養学の授業で健康的な食生活が人々の生活品質に与える影響を学んだことがきっかけでした。
特に、大学でのフィールドワークで地域の食文化を調査し、その地域に根ざした食品がコミュニティの結びつきを強固にする様子を目の当たりにした経験は、食品業界でのキャリアを強く望むようになる大きな要因となりました。
貴社が展開する健康志向の製品ラインと、持続可能な製造プロセスに対する取り組みに大きな魅力を感じています。
貴社の製品は、消費者の健康を第一に考えた開発姿勢が感じられ、私が食品業界で実現したい価値観と完全に一致しています。
入社後は、私の栄養学の知識と製品開発に対する情熱を活かして、貴社の研究開発部門で活躍したいと考えています。
教育
大学時代も個別指導のアルバイトをしており、学習面はもちろん、モチベーションを引き出すサポートが重要であると実感しました。
勉強に苦手意識がある生徒が1つずつ自信をつけて成績を向上させた経験から、生徒の成長を支えることのやりがいを強く感じました。
貴社が掲げる個別最適化教育の理念に共感し、教育に対する丁寧なアプローチはまさに私の考えと一致します。
入社後は学生時代に個別指導のアルバイトを通じて培ったコミュニケーション能力や指導力を活かし、生徒一人ひとりの個性や目標、苦手に沿った指導を心掛けます。
【ベンチャー企業の志望動機】NGな志望動機の特徴
- 勉強したい
- ITの時代だと思ったから
- ワークライフバランスを重視したい
- 安定志向が強すぎる
多くの志望動機においてマイナスなイメージを与えてしまう特徴というものも存在します。
下記のような特徴が当てはまってしまう志望動機の場合、企業の採用担当者はマイナスなイメージを覚えてしまうことでしょう。
そこで、下記の4点が自分の志望動機に含まれていないか再度確認し、企業の採用担当者に総合的に良い印象を与えられるような工夫をすることが大切です。
勉強したい
特にベンチャー企業において、企業採用担当者が悪い印象を抱く志望動機として「勉強したい」というものが挙げられます。
「勉強したい」ということは「その企業を踏み台にして成長したい」と言っていることとほとんど変わりません。
ベンチャー企業の中には企業によっては社員の成長を促し、「独立する場合も応援する」といった姿勢を持っているところもあります。
しかし、全ての企業がそういった考えを持っているわけではありません。
可能な限り長く働いてくれる人材を求めていますし、そもそも踏み台として扱うという暗黙の了解があったとしても、それをわざわざ口にするということはデリカシーのない、常識のない人物であると思われてしまう可能性が高いです。
よって、もしあなたが3年や5年、その企業で修行を積んで、大企業への転職や独立を目指している場合でも「勉強したい」という言い方はしない方が良いでしょう。
ITの時代だと思ったから
少し前までならば「時代の流れをしっかりと把握している」というプラスの印象を与えることもできた志望動機ですが、今の時代に「ITの時代だと思ったから」と言うと、あまりにもありきたりすぎてマイナスなイメージを与えてしまいます。
「ITの時代」とひとくちに言っても、ITという業界にもさまざまなものがありますし、IT企業は最近どんどん増え続けているので、わざわざその企業を選んだ理由がよくわかりません。
「ITの時代だと思ったと」いうのが最初の志望動機であったとしても「なぜITの中でもその企業なのか」「なぜその分野を選んだのか」が分かりやすい文章を作成していなければ、プラスの印象を与えることは到底できません。
よって、「ITの時代だと思ったからその企業を志望していたとしても、より深掘りした内容を提供できるようにしましょう。
ワークライフバランスを重視したい
ワークライフバランスを重視したいという志望動機は、ベンチャー企業を目指す上で最も悪い印象を与える可能性が高いものの1つです。
ベンチャー企業は基本的にチームの人数が少ないため、時には残業や休日出勤をしてでも業務に取り組まなければならない場面が少なくありません。
したがって、ワークライフバランスを重視する志望動機はベンチャー企業には全く適していません。
また、ワークライフバランスを重視したいと考えている人は、ベンチャー企業を目指すこと自体が間違いである可能性が高いため、他の企業を目指すことも選択肢に入れておいてください。
安定志向が強すぎる
安定志向が強すぎる志望動機は避けた方が良いでしょう。
安定を求める姿勢が前面に出ていると、挑戦心や成長意欲が乏しいと判断され、マイナスな印象を与えてしまいます。
ベンチャー企業では変化が激しい環境で柔軟に対応しながら成果を上げることが求められます。
よって、安定だけを重視する人は企業の風土にそぐわないと思われてしまいがちです。
「安定して働きたい」「長く働ける、安定した職場環境を求めている」といった表現には気をつけましょう。
「リスクを取らず現状維持だけを望んでいる、ぬるま湯に浸かりたい人だ」と思われてしまいます。
【ベンチャー企業の志望動機】ベンチャー企業の就活に関連するよくある質問
続いて、ベンチャー企業の就活に関連するよくある質問について紹介します。
以下の質問は就活エージェントを運営する中で、多くの就活生の方々からいただくものです。
この記事を読んでくれているあなたも気になっている項目があるでしょうから、ぜひ疑問点を解消するためにも参考にしてみてください。
「新卒でベンチャー企業は危ない」と言われる理由は?
新卒でベンチャー企業を選ぶことに対して「危ない」と言われる理由の1つは「不安定な企業が多い」というイメージがあるからです。
経営基盤がまだ確立されていない企業や、急成長を目指している段階の企業は経営方針が変わることがあり、安定性が懸念されることもあります。
また「残業が多い」「業務が過酷」といった先入観もあり、リスクが高いとみられがちです。
しかし、必ずしも大企業が安定しているというわけでもありません。
業界不振やリストラといった問題が発生するケースもあり、つまりどの企業でもリスクは存在します。
重要なのは、自分の適性や価値観を踏まえて、ベンチャー企業と大手企業の違いを理解することです。
よほど不安定な業界で、かつチャレンジングなことをしており、さらに評判や口コミが悪くなければ、特に心配する必要はありません。
ベンチャー企業で働くメリットは?
ベンチャー企業で働くメリットは様々なものがありますが、特に代表的なものは、社員一人ひとりの裁量権が大きく、チャンスを掴みやすいことでしょう。
少人数体制の企業が多いため、若手がいきなり大きなプロジェクトを任せてもらえることもあり、早い段階から責任ある業務に携わることができます。
実務経験を豊富に積めるため、スキルアップのスピードも早いです。
また、経営者や役職のある上司との距離も近いため、自分の意見を直接伝えやすく、企業全体の意思決定プロセスに関与できる機会が多いのも魅力です。
努力や成果が見えやすいため、評価基準も明確で、実績次第で昇給や昇進のチャンスも増えます。
風通しが良く、社員とリーダー層が日常的に意見交換できる環境はまさにベンチャー企業ならではの魅力であると言えるでしょう。
出世は早い?
一概に早いとは言えませんが、ベンチャー企業は他の一般的な企業と比べると、出世が早いこともあります。
裁量権が大きく、仕事に対して積極的に取り組む姿勢が評価されやすいからです。
企業全体が成長段階にあるため、ポジションが増加しやすく、新規プロジェクトが立ち上がることも多いため、責任ある立場に急に抜擢されることは珍しくありません。
ただし、出世が早いかどうかは個人の努力や成果による部分も大きいです。
結果を出すために行動し続ける姿勢が求められ、受け身でいるだけではなかなか昇進はできません。
ベンチャー企業はブラック企業が多い?
結論として「ベンチャー企業にはブラック企業が多い」という認識は誤解です。
急成長を目指すために忙しい環境が多いケースもありますが、これはベンチャー企業に限ったことではありません。
長時間残業や休日出勤は、大手企業や中小企業にもあります。
むしろ、ベンチャー企業の中には人材確保に苦労する分、働きやすさを重視して良い社風を築こうと努力しているところも多々あります。
企業によってはフレックスタイム制を導入したり、在宅勤務を積極的に取り入れたりして、ワークライフバランスを整えているところもあります。
結局、最大の指針は「ベンチャーかそうでないか」ではなく「社員からの口コミが良いか」です。
「ベンチャーだから、ブラックかもしれない」と懸念している時間があるならば、口コミサイトを確認する方がよほど有意義でしょう。
【ベンチャー企業の志望動機】志望動機が思いつかない時は
ここまで、志望動機について例文はもちろんのこと、ポイントや注意点、構成方法などについても紹介してきました。
しかし、この記事を読んだだけで簡単に志望動機が思いつくならば、誰も就活で苦労しません。
そこで志望動機や自己PRが作成できずに思い悩んでいる人におすすめしたいサービスがあります。
ジョブコミットはESの作成はもちろんのこと、面接対策や企業の選び方など、就活のプロが無料でサポートしてくれます。
友人や大学の教授に相談するのはもちろん効果的な方法ではあるのですが、無料で利用できるならば、これまで何人もの就活生を就職に導いてきたプロに相談するのももっとも手っ取り早く、より良いESを作成できることでしょう。
簡単に利用できるので、興味のある方はぜひ利用してみてください。
まとめ
どんな業種でも、志望動機は採用への第一歩です。
ここをおろそかにすると、採用担当者から興味をもってもらえません。
興味をもってもらうためには、まず相手の求めていることを感じ、相手が理解して欲しいことも感じとる必要があります。
自身をアピールすることも大事ですが、相手のこともちゃんとわかっているという部分も強調していくと、
「この就活生はこの会社に対する理解度が高い」と好印象を与えられるでしょう。
また、それらをアピールするなかで、自分自身は何ができるかを盛り込みながらアピールしましょう。
伝えたいことだけを伝えるのではなく、結論→理由→例→結論の順番を頭に入れておき、どの順序で構成を組めばより相手に伝わりやすいのかを考えることが大切です。