明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・「人の役に立つ」を就活の軸にできるのか
・就活の軸がブレる際の決め方
・「人の役に立つ」の言い換え
・就活の軸を「人の役に立つ」にしたい人
・「人の役に立つ」の言い換えを知りたい人
・就活の軸の例文を参考にしたい人
はじめに
面接では、就活の軸を問う質問をされることは珍しくありません。
そのため、就活の軸としてなんと答えるのが正解か悩む方は多いです。
今回は、就活の軸としてよく耳にする、「人の役に立つ」という例について、差別化のポイントや伝える際の注意点をご紹介します。
人の役に立つことを就活の軸として挙げても良いのか、実際に面接で答える時にどのようなことに注意するのかまで詳しく解説しますので、悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
就活の軸を「人の役に立つ」にするのはあり?
そもそも、就活の軸として人の役に立つことを挙げるのはありなのでしょうか。
結論から言うと、就活の軸として「人の役に立つこと」を話すのはありです。
しかし、人の役に立ちたいという就活の軸は多くの就活生に用いられており、埋もれてしまう可能性が高くなるというデメリットがあります。
差別化を図らないと企業に印象を残すことができないので、注意しましょう。
さらに、人の役に立ちたいというだけでは、非常に抽象的な表現になってしまいます。
人の役に立つ仕事というのは、どの業界・企業にも当てはまる抽象度の高い軸であるため、業界研究が不足していると感じられる恐れがあり、注意が必要になります。
就活の軸を「人の役に立つ」にする際の注意点
- 他の就活生との差別化が必要
- 抽象的な表現は避ける
- どの会社にも当てはまりやすい
人の役に立ちたい気持ちは、社会人になるうえで必要な感情ですので、この軸を伝えることは、決して悪印象を与えるわけではありません。
では、実際に人の役に立つことを軸として伝える際には、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。
就活の軸をうまく話して効果的にアピールができるように、以下の内容をよく読んで事前にしっかりと対策しましょう。
ほかの就活生と差別化が必要
1つ目は、他の就活生との差別化を図ることが挙げられます。
先ほどもご紹介したように、人の役に立つことは多くの就活生が軸として使う傾向があるため、ただ役に立ちたいとだけ伝えても、埋もれてしまう可能性が非常に高いです。
面接官はエントリーシートの段階から、応募者を何人も見てきており、同じような内容を何度も聞くと、どうしても飽きてしまうのです。
そこで、面接官に興味を持たれないという事態は絶対に避けるために、他の就活生との差別化が必要になるのです。
誰に対して、どんな形で役に立ちたいか、そのために自分がやりたいことは何かを具体的に伝え、自分らしさをアピールすることが効果的です。
抽象的な表現はNG
2つ目は、抽象的な表現を避けることが挙げられます。
どのような業界・業種の志望動機でも、抽象化していくと誰かの役に立つことに集約されます。
そのため、ただ役に立ちたいというだけでは、その業界・業種でなくてはいけない理由や、企業への熱意・志望度が伝わりません。
そこで、どのような形で、どのような層に貢献したいかや、人の役に立ちたいと思った経緯を考え、志望企業との関連性を持たせることで、志望度の高さを伝えることができます。
その際には、その企業を選んだ理由とつなげるようにすると効果的です。
企業理念にマッチさせて具体的に伝えると、より好印象を与えることができます。
そのために活かすことができる能力や経験があれば、それもあわせて伝えるようにしましょう。
どの会社にも当てはまりやすい
3つ目は、どの企業にも当てはまりやすいことです。
人の役に立つという理由だけでは、どの企業・業界にも当てはまってしまうので、なぜその企業でないといけないのかを説明できるようにしておきましょう。
そのためには、自分がどんなことに役立ちたいと考えているのかを、再度分析する必要があります。
事業展開やサービス、社風などの企業研究を深め、入社後に実現したい自分のキャリアプランや目標をイメージすることで、この企業でなければいけない理由を見つけましょう。
特にベンチャー企業では、面接官は、安定感のある大企業ではなくベンチャーを選んだ理由を知りたいと思っているため、その会社でないといけない理由を明確にした方が良いです。
志望先の企業でしかできないことを深掘りすることで、具体的で説得力のある就活の軸が完成するでしょう。
企業が就活の軸を聞く理由
- 自社とのマッチ度を確認するため
- 志望度の高さを測るため
ESや面接において、企業が就活の軸を聞く理由について解説します。
企業側が持っている意図を理解しておくことで、より相手の求める情報に合わせた効果的なアピールができるようになるので、ぜひ覚えておきましょう。
自社とのマッチ度を確認するため
「就活の軸」には、応募者が働くうえで大切にしたい価値観や、企業に求める条件が色濃く表れます。
そのため、企業はそれを通して、自社の風土や事業内容、理念とどれほどマッチしているかを確認しています。
企業側の目的として、入社後に早期離職することなく、自社で長期的に活躍してくれる人材を採用したいと考えています。
そのため、就活の軸を問うことで、応募者が自社に適性のある人物かどうか、働くうえでのミスマッチが起こらないかを慎重に見極めようとしているのです。
応募者としても、自身の価値観と企業の方向性が一致しているかを確認する機会と捉え、しっかりと志望企業の特徴は押さえつつも、自分の素直な想いを伝えることが重要です。
志望度の高さを測るため
就活の軸が企業理念やビジョン、求める人物像と合致しているほど、企業は「自社への志望度が高い」と受け取ります。
特に、「人の役に立つ」という軸が具体的にどのようにその企業の活動とつながるのかを語ることができれば、志望動機に説得力が生まれます。
また、企業側は、理念に共感している人材は入社後の定着率やパフォーマンスが高いと考えており、その点を重視しています。
単なる表面的な条件や希望ではなく、自身の就活の軸と企業の目指す方向性がしっかり重なっていることを伝えることが、選考を突破するうえでも非常に効果的です。
そのため、自分の想いと企業の想いの重なりを言語化することを意識しましょう。
就活の軸「人の役に立つ」を魅力的に伝えるポイント
- 自己分析で自身の価値観を洗い出す
- 深掘りで軸に具体性を持たせる
- 企業とのマッチ度をアピールする
次に、人の役に立つことを就活の軸とする際の伝え方のポイントを解説します。
より説得力のある就活の軸を持っていると、面接官に好印象を持たれやすいため、以下のポイントを押さえて他の就活生との差別化を図りましょう。
自己分析で自身の価値観を洗い出す
1つ目は、自己分析を行い、自分の価値観や仕事への向き合い方について理解を深めることです。
人の役に立つことを就活の軸にする際には、具体的にどう役に立ちたいかを伝えることが大切です。
その際に、この業界・企業でなくてはいけない理由などを具体的に伝える必要があります。
自分を掘り下げていくことで就活の軸がより明確になり、他の就活生との差別化できる、自分ならではの軸を見つけることにつながります。
また、具体的で自分らしさが伝わる就活の軸を話せると、自己分析や企業研究などの事前準備がしっかりできていると感じてもらうことができ、面接官に良い印象を残すことができます。
深掘りで軸に具体性を持たせる
2つ目は、就活の軸に具体性を持たせることが挙げられます。
具体的になぜ人の役に立ちたいのか、そう思ったきっかけを話すようにしましょう。
就活の軸の根拠となる理由を伝えられると、志望度の高さを伝えることができ、長く自社で働いてくれそうな人物として面接官に印象づけられます。
さらに、どのようにして役に立ちたいのかを具体的に説明しましょう。
面接官は、どうしてこの業界・業種なのか、それがこの企業でできることなのかを見ているため、志望企業に合ったキャリアプランを持っているとなお良いです。
具体性を持たせることで、志望度やマッチング度合いの高さを伝えられるでしょう。
企業とのマッチ度をアピールする
3つ目は、企業への適性をアピールし、採用するメリットを伝えることです。
企業は応募者の志望度を測っているという話を、よく耳にすると思います。
それは、内定を出した時に本当に入社してくれるのか、早期退職の心配がないかを判断するためです。
企業の方針と応募者の目的が同じなら、それらの可能性が低くなると考えられているため、なるべく企業の方針にマッチしている就活生を採用したいと考えているのです。
エピソードと企業の方針をマッチさせて、就活の軸を伝えると良いでしょう。
マッチ度合いの高さだけでなく、事前準備としてしっかり企業のことを調べてきていることで志望度の高さを感じてもらえる可能性が高いです。
就活の軸「人の役に立つ」を深掘りする3ステップ
- 役に立ちたいと思う対象を明確にする
- 役に立つための手段・方法を考える
- 相手に与えたい影響を具体化する
「人の役に立つ」という就活の軸をより深掘りすることで、内容が深く、そして企業の採用担当者の胸に響く、質の高い回答を提供できるようになります。
ぜひ以下のポイントを意識して、あなたの就活の軸をより深掘りしていきましょう。
1.役に立ちたいと思う対象を明確にする
「人の役に立つ」という就活の軸を深掘りする上で重要なのは、まず自分が誰の役に立ちたいのかを考えて確認することです。
多くの人がこのような言葉を口にしますが、対象が曖昧なままでは、自分の志望動機や将来像も曖昧なままです。
そこで、自分が過去にどのような場面で人の役に立てたと感じたかを振り返ってみましょう。
アルバイトでお客様から感謝された経験や、サークル活動で貢献できた経験など、小さな成功の中にヒントが隠れていることは少なくありません。
社会全体の役に立ちたいのか、目の前の個人を支えたいのか、あるいは企業や地域の課題に関わりたいのか、自分の価値観を整理して対象を明確にしましょう。
2.役に立つための手段・方法を考える
「人の役に立ちたい」という思いを就活で語る際には、その目的を実現するための手段やアプローチについても考えなければなりません。
自分がどのような立場やスキルを通じて貢献したいのかを掘り下げていくことで、志望企業や職種との接続点が見えてきます。
IT業界を志望する人に「地域課題の解決に貢献したい」思いがあるならば、地元の商店街に対してDX化を支援するような業務に関心を持つでしょう。
また、エンジニアとして新しい技術を生み出し、暮らしの利便性を高める方法もあります。
同じ「人の役に立ちたい」という気持ちでも、その手段は人によって大きく異なるのです。
自分の強みや得意分野を軸にしながら、どのような手段で、誰に貢献できるのかを具体的に考えておくことで、志望動機にも一貫性と説得力が生まれます。
3.相手に与えたい影響を具体化する
人の役に立つことを軸に据えるなら、単に「人助けをしたい」という漠然とした気持ちだけでなく、相手にどのような影響を与えたいのかまで具体的に考えることが重要です。
「支援を通じて相手に前向きな気持ちになってほしい」「困っていることを解決して、日常に余裕をもたらしたい」といったように、関わりの結果としてどのような変化が起きてほしいのかを描いてみましょう。
この作業はつまり「最終的に、自分がどのような社会的意義を感じながら働きたいのか」を明確にする作業でもあります。
イメージができれば、自分がその企業で実現したい目標も自ずと見えてくるでしょう。
就活の軸「人の役に立つ」の言い換えの具体例
- 人を喜ばせる
- 人の生活を豊かにする・支える
- 他者をサポートする
先ほど注意点について紹介した際にも話したように、「人の役に立つ」という就活の軸はあまりにも抽象的であり、曖昧な印象を与えてしまうことが多いです。
そこで、他の言い換え表現を活用してエピソードを話す方がより適切であると判断される場合は、それを活用した方が良いこともあります。
人の役に立つことを言い換える表現には以下の2つが存在するため、ぜひ確認してみてください。
人を喜ばせる
「人を喜ばせる」という表現は人の役に立つことよりも解像度が高く、より良い印象を与えられる可能性が高い就活の軸であるといえます。
特に営業職やエンタメ系の仕事においては、人の役に立つよりもこの言い換えの方が適切であることが多いです。
よりクライアントやお客様と直接接する機会が多く、目の前で喜んでいる姿を見れる仕事を目指す場合はこの表現の方が適切であるといえます。
この就活の軸について話す際は、エピソードにも「実際に誰かに働きかけ、喜ばせた経験があり、それに強いやりがいを感じた」という種類の話をすることをおすすめします。
人の生活を支える・人の生活を豊かにする
「人の生活を支える」という表現も人の役に立つよりも分かりやすく、企業の採用担当者がイメージしやすい就活の軸です。
この話をする際はどのような方法で人の生活を支えるのかについて明確にするようにしましょう。
インフラ業界のような人々の生活に欠かせない部分で当たり前を支えたいのか、小売業や商社のような人々の生活を豊かにする面で価値提供を支えたいのかによってアプローチの方法は多少異なります。
就活の軸は自分がどのような考え方を持っているのかについて話すことはもちろん、その考えをどのように活かして仕事に還元するのかについても話す必要があります。
したがって、「どのように」の部分は特に分かりやすく話すようにしましょう。
人をサポートする
「人をサポートする」という表現は、人の役に立つ方法として、相手を直接サポートすることで、貢献したいと考えている人におすすめの軸です。
実際に、金融や人材、教育業界などの顧客と直接関わり、深い信頼関係を構築することで、相手の課題解決をサポートしたいと考えている人や、事務職やコーポレート部門などの管理系職種を志望していて、他の社員や会社全体の運営サポート・支援に貢献したいと考えている人は、この軸がマッチしているでしょう。
ここでは、志望する業界や職種に合わせて、自分が誰に対して・どのようにサポートしたいかを明確にしておくことで、より効果的に適性をアピールすることができるでしょう。
就活の軸がブレてしまう際の決め方
- 志望企業を比較して分析する
- 業界・企業研究を深める
「人の役に立つ」を就活の軸にしても、就活を進める中でより重視したい軸が見えてきたり、深掘りを通じて変化してくることもあるでしょう。
そんなときの判断材料として役立つ、軸の決め方のポイントを2点紹介します。
志望企業を比較して分析する
最初から「自分は何を重視して働きたいのか」を明確にし、しっかりと自分の価値観に合った就活の軸にするのは難しく、それによって就活の軸のブレに繋がってしまいます。
そこで有効なのが、志望企業を複数比較し、そこから逆算して自分の価値観を見つけ出す方法です。
例えば、「この企業のどの部分に惹かれたのか」「志望企業にあって他の企業にはない魅力は何か」といった視点で情報を整理すると、自分が重視している点が見えてきます。
それが働くうえで譲れない条件や、やりがいを感じる場面といった、自分だけの就活の軸につながるので、この方法を通じて「人の役に立つ」という軸をより具体化し、納得感のある軸を形成していきましょう。
業界・企業研究を深める
就活の軸がブレてしまうときは、自身の強みや興味関心に合った業界・職種・企業を見つけられていない場合が多いです。
そこで、業界・企業について深く知ることで、自分の価値観に合致した、より具体性と説得力のある就活の軸を見つけやすくなります。
以下の3点のポイントを意識して業界・企業研究を深めていきましょう。
「人の役に立ちたい」という想いを実現するうえで、「誰に役立ちたいのか」という対象を明確にすると、自然と進むべき業界も絞れてきます。
たとえば、「病気で苦しむ人の役に立ちたい」と考えるのであれば、医師や看護師といった医療従事者だけでなく、製薬会社で医薬品を届けるMR(医薬情報担当者)、医療機器メーカー、あるいは食品・化学メーカーの医療分野など、さまざまな業界が該当します。
このように、抽象的な軸を「誰の役に立ちたいか」という視点で深掘りすることで、自分に合った業界を選ぶ手助けになります。
職種は「どのように人の役に立ちたいか」という手段に関わってきます。
営業職や事務職などが代表的ですが、その他にも企業や業界によって多種多様な職種が存在します。
「病気で苦しむ人の役に立ちたい」場合は、看護師や薬剤師として直接患者を支援する方法もあれば、製薬メーカーの営業職として質の高い医薬品を届ける、研究職として新しい治療薬を開発する、といった間接的な支援もできます。
ここでは、「どのような役割を担い、どんな方法で相手のためになりたいか」を軸に、自身の興味関心や強みを活かせる職種選びを進めることが効果的です。それにより、働くうえでの納得感やモチベーションも高まるでしょう。
企業理念は、企業がどんな社会的役割を持ち、どんな考え方・価値観を大切にしているのかを表しています。
そこで、人の役に立つことで与えたい影響と、企業理念の方向性が一致しているか、共感できるかを確認することが大切です。
たとえば、「癌患者を減らしたい」という思いがある場合は、それにマッチした事業・製品展開や顧客第一主義を掲げている企業と重なり合う可能性があります。
この部分が一致していることは、入社後の仕事に対するモチベーションややりがいにも直結します。
理念に共感できる企業を選ぶことで、長く働き続ける意味を見出しやすくなり、組織への貢献度も高まるでしょう。
就活の軸を答える際におすすめの構成
就活の軸を面接やESで答える際に、分かりやすく伝えるうえでおすすめの構成を紹介します。
以下の構成に沿って、採用担当者に効果的にアピールできる就活の軸を作りましょう。
結論
まず、結論ファーストであなたが持っている就活の軸を簡潔に伝えましょう。
「私の就活の軸は、困っている人の役に立つことです」など、結論を最初にハッキリと言うことで、話の全体像をイメージしやすくなり、相手の理解も深まります。
加えて、企業側はあなたがこれから話す内容の流れを予測して聞くことができ、円滑なコミュニケーションに繋がります。
具体的なエピソード
次に、就活の軸を設定するに至った具体的なエピソードを説明しましょう。
特に、「人の役に立つ」という就活の軸を使う際には、原体験を用いることで他の就活生と差別化し、自分らしさや入社後の再現性をアピールすることが非常に重要です。
例えば、「学生時代のボランティア活動を通じて、自分の行動が誰かの笑顔に変わる瞬間に喜びを感じ、人の役に立つ仕事がしたいと思うようになった」などが考えられます。
過去の経験から得た気付きを織り交ぜることで、自身が大切にしている価値観への説得力が高まり、あなたらしさの伝わる就活の軸になります。
軸と志望企業の共通点
そして、この就活の軸が志望企業の特徴とどのようにマッチしているのかを明確に示しましょう。
企業理念や具体的な取り組みなどの事例を用いて共通点を提示することで、「人の役に立つ」という就活の軸を実現するために「志望企業でなければならない理由」に説得力を持たせられます。
例えば、「御社は生活に欠かせない交通インフラを整備・運営している点で、人の役に立ちたいという思いを実現できると考えた」など、企業に合わせてアピールがすることができます。
このように、志望企業と就活の軸の関連性を持たせ、企業への適性と志望度の高さを伝えましょう。
入社後の貢献
最後に、入社後に志望企業でどのように貢献できるかを伝えましょう。
その就活の軸を満たす環境の中で、どのように業務に取り組んでいきたいかを考え、企業で活躍するイメージを持たせましょう。
そのためには、単に人の役に立ちたいという思いを話すだけでなく、企業でどのように活躍したいか、どんな影響を与えたいかを明確にすることが必要です。
「○○という課題を解決するために、御社の○○事業に携わり、人々の豊かな生活に貢献したい」など、具体的なビジョンや展望を述べましょう。
これにより、再現性の高い就活の軸を作ることができます。
「人の役に立つ」を就活の軸にする場合の例文
続いて「人の役に立つ」を就活の軸にする際の例文について紹介します。
以下の5つの例文を参考にしながら、自分はどのように回答するかについて考えてみてください。
ぜひ自分が目指している業界以外の例文も読み、どのような点が回答のポイントなのかも意識してみましょう。
「人の役に立つ」×「メーカー業界」の例文
大学時代、地域の小学生を対象にした科学教室の企画運営に参加しました。
実験を通して理科が面白いと感じてもらえるよう、道具の準備や説明の順番まで細かく工夫し、分かりやすさを大切にして取り組みました。
「もっと知りたくなった」と言ってくれたことが嬉しく、この経験を通して、誰かの視野を広げたり、行動を変えるきっかけを作ることに大きなやりがいを感じたことが印象に残っています。
将来的には、製品やサービスの提供を通じて人々の生活の中に安心や便利を届けられる存在を目指します。
特に、社会的なインフラや暮らしに直結する御社のような企業であれば、幅広い層の人々の生活を支える仕事ができると感じています。
「人の役に立つ」×「IT業界」の例文
大学のゼミで地域の高齢者向けにスマートフォンの使い方を教えるボランティアに取り組みました。
一つひとつの説明を丁寧に行い、カタカナ語を避けるなど、わかりやすい言葉を選ぶことを心がけた結果「これで孫にメッセージが送れるようになった」「病院の予約が楽になった」と、嬉しいフィードバックをいただきました。
この経験から、技術を通して誰かの不安を取り除いたり、可能性を広げる手助けができる仕事に魅力を感じるようになりました。
入社後はシステム開発やサービス設計に携わりながら、ユーザー目線での価値提供を追求していく所存です。
「人の役に立つ」×「金融業界」の例文
大学時代、家計の都合で奨学金制度を利用しながら生活しました。
契約内容や返済シミュレーションを自分で考え、金融機関に問い合わせるなど工夫した結果、仕組みを理解できました。
少しずつ金融の知識が増えていくことで不安が解消されていき「正しく知ることが、安心につながる」と実感しました。
この経験をきっかけに、将来は同じようにお金に不安を感じる人の力になれる仕事がしたいと考えるようになりました。
御社のような企業であれば、人生の選択に関わる資金計画やライフプランの設計を通じて、前向きな選択を支えることができると感じています。
丁寧な対応と正確な知識をもとに一人ひとりに合った提案を行い、信頼される存在として活躍する所存です。
「人の役に立つ」×「教育業界」の例文
教育学部で学ぶ中で、近隣の中学校で学習支援ボランティアに参加することがありました。
自信をなくしていた生徒に寄り添いながら学習内容を丁寧に説明した結果、少しずつ前向きな言葉が増えていき、自分から質問してくれるようにもなりました。
「先生と話すことが楽しい」などと笑顔で言ってくれた時は自分の言動が人の気持ちを変えられるのだと強く感じました。
御社のような生徒の気持ちを大切にしている塾であれば、人の成長を支えるやりがいを感じながら業務に取り組めると感じています。
一人ひとりの背景や悩みに向き合いながら、学びの機会やサポートを提供して、より多くの生徒が自分の力を信じて前進できる環境づくりに貢献する所存です。
「人の役に立つ」×「地域密着」の例文
自分が生まれ育った地域を少しでも盛り上げたいという気持ちから、このアルバイトを始めました。
調理から接客までを行うのはとても大変ですが、どうしたらお客様に喜んでいただけるかを考えながら、工夫して仕事に取り組んでいます。
地域のお客様と直接関わっていく中で、「ありがとう」と言っていただけた時に、地域の役に立てたという嬉しさを感じました。
そのため、地域を活性化していくために事業展開をしている企業に就職したいという気持ちが非常に強いです。
御社が特化されている地域振興の取り組みは、まさに地域の人々の役に立ち、喜ばれるサービスであると感じています。
また、御社は実際に地域の方々とお話をしながら課題を解決されています。
直接地域の方と関わることのできる取り組みに、非常に魅力を感じました。
さらに、長期にわたって地域を盛り上げてきた御社は、多くの方々との信頼関係をお持ちです。
そんな御社でより多くの方々の役に立ちたいと考え、志望いたしました。
「人の役に立つ」を就活の軸にした時のNG例文
続いて、人の役に立つことを就活の軸にしたNG例文を2つ紹介します。
「なぜこのような回答をしてはいけないのか」という解説も添えて説明するため、自分は以下のような回答を面接で話してしまわないよう、反面教師として活用してください。
具体的なエピソードが含まれていない
常に母親から「人の役に立つように、人のために生きなさい」と言われ続け、人の役に立つことが非常に重要なことであると、自分の軸として生きてきました。
御社のようなユーザー最優先で、常に「give」の精神を持って業務に取り組んでいる企業ならば、私のこの信念がまさに活かせるのではないかと考えています。
入社後は営業職として、企業の利益だけでなく、取引先の担当者のQOLや取引先企業の利益にも貢献できるような人物として貢献する所存です。
どの企業にも当てはまる抽象的な内容
特に御社のようなお客様第一の精神で営業を行っている飲食店でならば、この目標を実現できると考えています。
御社は常にお客様最優先で接客に力を入れており、クレーム数が非常に少ないと伺いました。
週末や仕事終わりのリラックスした時間を、おいしい食事と丁寧なサービスで彩るような企業こそ、私の目標です。
キャリアアドバイザー 木下恵利

この文章は、どの企業にも当てはまる、あまりにも抽象的な内容と言えるでしょう。
良い接客を提供している飲食店などいくらでもありますから「他の企業で良かったのではないですか?」と聞かれる可能性が高いです。
接客に焦点を当てるならば「どのようにその企業が接客のクオリティを担保しているのか」などについて触れる必要があります。
まとめ
人の役に立つことを就活の軸とすることについて、詳しくご紹介しました。
注意点やポイントなどを知ったことで、しっかりと軸を伝えられるようになったかと思います。
また、役に立ちたいという気持ちを深掘りして、具体的な就活の軸を見つけられた方もいらっしゃるかも知れません。
自分なりの就活の軸を持っていることで、面接官に好印象を持たれやすくなりますので、自己分析や企業研究を深めていきましょう。

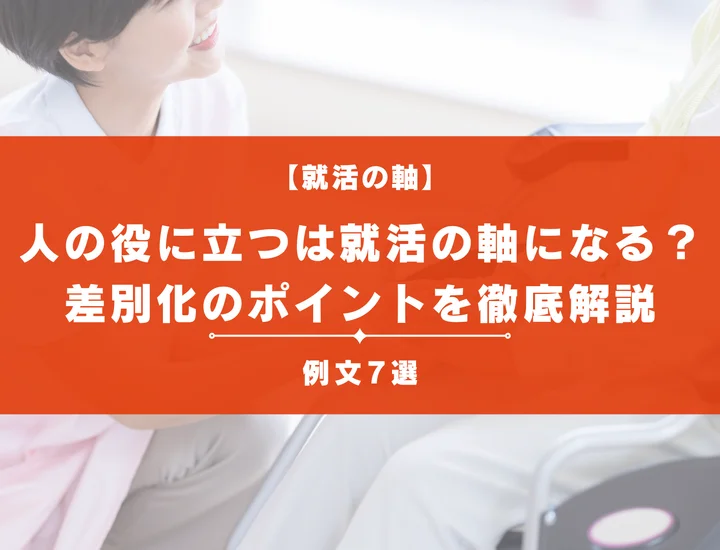





_720x550.webp)
_720x550.webp)









キャリアアドバイザー 木下恵利
この文章には、自身の具体的なエピソードが全く含まれておらず、なぜ人の役に立つことを大切にしているのかよく分かりません。
一応、母親から「人のために生きなさい」と言われたことは添えられていますが、これだけではあまりにも不十分です。
どのような経験をして、なぜ人の役に立ちたいという強い思いを持つに至ったのかまで説明できなければ、内定は到底獲得できないでしょう。