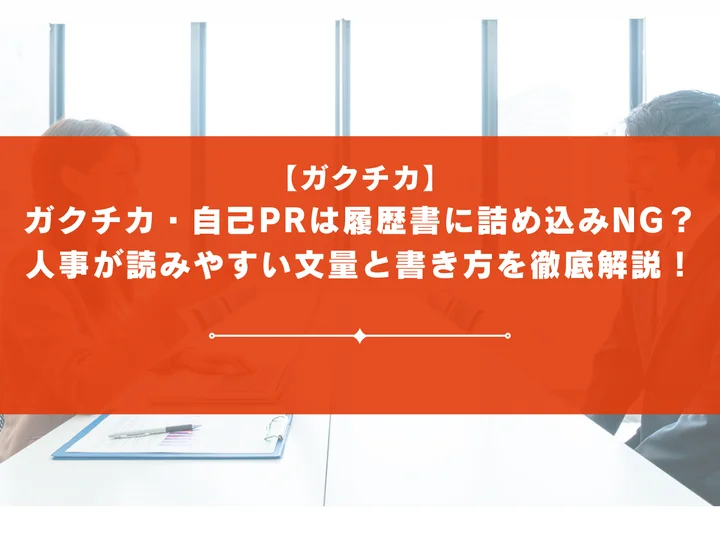明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・アルバイト経験をガクチカにする方法
・塾講師アルバイトの経験でアピールできること
・塾講師アルバイトのガクチカ例文
・アルバイト経験をガクチカにしたい人
・ガクチカの構成が不安な人
・例文を参考にアルバイト経験でガクチカを作りたい人
【塾講師のガクチカ】はじめに
塾講師のアルバイトをしている人の中には、ガクチカとしてアピールをしたいと思っている人も多いと思います。
そこで今回は、塾講師をガクチカとしてアピールするためのコツや注意点、参考になる例文などをご紹介いたします。
この記事を読んで、他の就活生とガクチカを差別化して印象に残る最強のガクチカを作成しましょう!
また以下の記事では、作成ツールを使ったガクチカの作り方について詳しく解説していますので、ガクチカ作成に苦戦している方や今からガクチカを作成しようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
【塾講師のガクチカ】塾講師の経験をガクチカにするのはありきたり?
結論から言うと、塾講師の経験をガクチカとしてアピールするのは最適です。
ガクチカはありきたりなエピソードではなく、変わっているエピソードを使用した方がいいと思われがちですが、ガクチカに必要なのはその経験での行動や経験のため、生徒や保護者と関わっていく中で、様々なスキルが身につく塾講師は最適であると言えます。
そして大学生が勤務時間を増やせる長期休暇期間は、塾に通う生徒の休みと重なり、必然と受講する生徒が増えるため、大学生と相性の良く人気のあるアルバイトです。
しかし、人気が高いということは、同様の経験をしている就活生のライバルが沢山いるためエピソードは似たものになってしまいがちでしょう。
そのため塾講師でのガクチカをアピールするコツを掴んで、他の就活生と差別化をはかる必要があります。
ガクチカとは
多くの就職活動で聞かれる質問の1つに「学生時代、力を入れたもの」、通称ガクチカがあります。
「ガクチカ」とは「学生時代に力を入れたこと」の略です。
就職活動で、面接やエントリーシートにおいてアピールするポイントです。
ガクチカとして書けるものは勉強、部活、サークル、趣味などさまざまです。
それらの経験を就職活動で効果的に活かすためには、ガクチカについて質問される目的を理解し、自身の経験の強みを把握しておかなくてはいけません。
【塾講師のガクチカ】塾講師の経験に対して企業が持つ印象
ESや面接で使用されるガクチカは企業が求めている人物像のイメージにギャップが起きないようにしましょう。
そのためにも、企業が塾講師の経験に対してどのような印象を与えるか知っておく必要があります。
- マナーが備わっている
- 真面目である
- 責任感がある
- 人と関わることが好きである
マナーが備わっている
生徒の多くは子供である場合が多いため、保護者との関わりも頻繁にあったことでしょう。
子供の将来に関わるため保護者の要求は高く、たとえアルバイトの講師であったとしても、保護者や受講生からは同じ先生として見られています。
そのため、授業の内容に加えて、子供の模範となる言動や振る舞いも求められます。
そのような環境で講師を務めてきた経験は、身だしなみや言葉遣いのマナーが備わっているものと高く評価されます。
真面目である
生徒に勉強を教えるには、自分自身が真面目に学習してきた実績が重要です。
他人に説明し理解させるには、一人ひとりの理解度に合わせて噛み砕いて説明できるほど深く知っていることが不可欠だからです。
また、生徒の理解を助け成績を向上させるには、様々な指導方法を考えて粘り強く取り組む真面目さが大切と言えます。
このように生徒に親身になり取り組んだ実績は、真面目な性格であることを表しています。
責任感がある
塾講師の経験がある人は企業から強い責任感を持つ人物として評価されることが多いです。
教育という分野は生徒の学習成果や進学に直接影響を与える重要な役割を担っているため、塾講師は一人ひとりの生徒に対して責任を持って指導しなければなりません。
授業の準備や生徒の進捗管理、個別の対応など様々な業務を行うため、高い責任感が求められます。
さらに、塾講師は生徒や保護者からの信頼を得るために誠実な対応を心がける必要があります。
このような理由から、塾講師の経験がある人は仕事に対して真摯に取り組み、与えられた任務を最後まで遂行する責任感が強い人物だとみなされるのです。
また、塾講師は生徒の成長を見守る中で失敗を経験しながらも忍耐強く指導を続けることが求められるため、粘り強さや忍耐力も備えていると評価されることが多いです。
このように、塾講師の経験を通じて培われた責任感は企業にとって非常に価値のある特性とされています。
人と関わることが好きである
塾講師の経験がある人は「人と関わることが好きである」という印象を企業に与えられます。
塾講師の仕事は単に授業を行うだけでなく、生徒一人ひとりと向き合い、その理解度や個別のニーズに応じて指導方法を調整することだからです。
生徒とのコミュニケーションを通じて、強みや弱み、苦手な分野や好きなものを把握し、それに基づいて適切なサポートを行いながら授業を提供することで、生徒の成長をサポートします。
このような仕事をこなすためには、高いコミュニケーション能力と人間関係を構築する能力が必要です。
また、保護者とのやり取りや同僚の講師との協力も必要不可欠であるため、対人スキルが自然と磨かれます。
これらの経験を持つ人は人と接することが得意であり、人間関係を大切にする性質を持っているとみなされます。
ベンチャー企業は特にこのような対人スキルやコミュニケーション能力を持つ人材を高く評価する場合が多いため、積極的にアピールするようにしましょう。
【塾講師のガクチカ】企業がガクチカを通して知りたいこと
企業が就活でガクチカについて質問する目的は、学生の個性や考え方を知るためです。
自身の経験をどのようにとらえ、何を頑張ったと考えているかを知ることで、モチベーションの源泉が見えてきます。
また、目標に対してどのように努力できるか、壁に直面した際はどのような対策が立てられるかといった点も知ることができるでしょう。
これらの点を見ることで、企業はその人物が自社で活躍できる人材かどうか、自社の社風やカルチャーとマッチしているかをはかることが可能です。
そしてポテンシャルや成長性を重視する新卒採用において、企業とマッチしているか否かは重要な判断基準となります。
なぜならコストをかけて採用した新卒社員が、ミスマッチにより退社してしまうことは、企業にとって大きな痛手となるからです。
働き方や仕事に対するスタンスが多様化している現代において、ガクチカはより大切になってくるでしょう。
学生が自身の個性や強みをアピールし、企業がリスクを減らして採用をするために、ガクチカは重要な役割を果たしているのです。
【塾講師のガクチカ】塾講師のガクチカでアピールできる能力5選
つぎは塾講師のガクチカでアピールできる能力を見ていきましょう。
アルバイトはガクチカに活用される経験としては定番の1つです。
それゆえにどんなアルバイトでも共通するような経験を書いては印象に残りにくく、自身の強みも伝わりません。
そのため、塾講師として働くうえでどういった能力を必要とされていたか、どんな考え方が身についたかを考えておく必要があります。
自身のアルバイト経験を就活に有効活用するためにも、塾講師として働いた経験の強みを改めて確認してみてください。
- 課題解決力
- 周囲を巻き込む力
- 傾聴力
- 相手の立場に立って考える能力
- プレゼンテーション能力
課題解決力
塾講師は生徒を相手にして、成績の向上や受験を突破するために働く職業です。
その仕事では、異なった個性をもつ生徒の相手をすることになります。
成績向上という同じゴールを見据えた場合でも、それぞれの学習能力や抱えている問題は異なります。
勉強を教えていくなかで何が課題かを考え、それを解決する試みが必要になるでしょう。
この一連のプロセスで身につけられる課題解決力は、ガクチカとして十分にアピールできるものです。
生徒の成績が伸び悩んでいる原因をどのようにして突き止めたのか、それを解決するためにどのような対策をおこなったのかを具体的にアピールしましょう。
課題を見つける観察力や分析力、独自の解決策を見るける思考力は就職したあともさまざまな点で役立てられます。
周囲を巻き込む力
塾講師のガクチカでアピールしやすいもう1つの強みとして、周囲を巻き込む力があげられます。
働くなかで周囲と共同して、何かを成し遂げた経験があるのであれば、それも大切なアピールポイントです。
勉強を教える過程で全体に共通した課題が見つかった場合、自分の力だけでは解決が難しい場合もあります。
そういったケースでは社員やほかのアルバイトなどを巻き込んで、よりよい学習環境の構築や、カリキュラムの改善を進めていく必要もあるでしょう。
人事担当者は、周囲を巻き込んで変化を促した経験からリーダーとしての素質や、協調性の高さなどを見出すことが可能です。
どのようにして周囲に改善の必要性を伝えたか、共同して成果を出すために苦労した点はどこかなど、具体的なエピソードを通して自身の強みと成長の結果を伝えましょう。
傾聴力
塾講師の面接では、学力以外に人柄も重視します。
生徒や保護者と信頼関係を築くために、親しみやすい雰囲気であることが求められるからです。
塾では生徒がわからないところを質問したり、保護者が進路の相談をしたりしやすいような環境を作ることが大切です。
そのうえで、相手が本当に話したいことを引き出し、理解しようと努めます。
このように塾講師として働いた経験は、生徒からの質問や保護者との面談における傾聴力をアピールできます。
傾聴力とは、ただ受動的に話を聞いていることではありません。
相手をより深く理解するために、注意深く耳を傾け、積極的に話を聞くことです。
どのような態度や考え方で、相手の話を能動的に聞いていたのかをアピールしましょう。
相手の立場に立って考える能力
塾講師の経験を通じてアピールできる能力の1つとして、相手の立場に立って考える能力が挙げられます。
塾講師は生徒一人ひとりの学習状況や理解度、それぞれの課題に対してきめ細かく対応することも求められます。
生徒がどの部分がわからずにつまづいているのか、どのようなサポートが必要かを的確に把握するためには、常に生徒の視点に立って考える必要があります。
例えば、生徒に苦手科目がある場合、その原因を探り、理解を深めるための方法を考えることが重要です。
これには生徒とのコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、相手の気持ちや考えを理解する努力が欠かせません。
このような経験を通じて培われた、相手の立場に立って考える能力は企業においても非常に有用です。
顧客対応やチーム内でのコミュニケーションにおいて、相手のニーズや状況を理解し、それに基づいた対応ができるため、職場での人間関係を円滑にし、信頼を得られます。
プレゼンテーション能力
塾講師は授業を通じて生徒にわかりやすく情報を伝えることが求められるため、プレゼンテーション能力もおのずと磨かれている可能性が高いです。
生徒が興味を持ち、理解しやすい形で情報を構成し伝える技術が求められます。
板書やスライドを用いて視覚的に情報を伝え、時には質問を促して生徒の理解度を確認するなど、多様な方法を駆使してわかりやすいプレゼンテーションを行わなければなりません。
このような経験は企業でのプレゼンテーションや報告業務にも直結します。
特に、複雑な情報を簡潔かつ明確に伝える能力は社内外のコミュニケーションを円滑にし、プロジェクトの進行や意思決定をスムーズにするために非常に有効です。
また、プレゼンテーション能力は説得力のある話し方や聴衆の興味を惹き付けるスキルとも関連し、営業やマーケティングなどの分野でも高く評価されます。
【塾講師のガクチカ】塾講師経験のガクチカを作成する流れ
塾講師の経験を活かしたガクチカを効果的に伝えるためには、順序立てて準備を進めることが重要です。
以下では、3つのステップを通じて、魅力的なガクチカを作成する方法を詳しく解説します。
- 自分の強みを絞る
- アピールする塾講師経験のエピソードを決める
- 構成に沿ってガクチカを作成する
① 自分の強みを絞り込む
まず初めに、自分の経験を通じて伝えたい「強み」を明確にします。
塾講師として得た経験はさまざまですが、その中でも自分が最もアピールしたいポイントを1つに絞り込むことが重要です。
たとえば、課題解決能力やプレゼンテーション能力、協調性、責任感などが代表的な強みとして挙げられます。
この段階では、単なる「できること」ではなく、企業にとって魅力的に映る「価値」を意識して強みを選ぶことが肝心です。
企業は単なる経験ではなく、そこから得た能力や価値観に注目しています。
そのため、自分の強みが企業の求める人物像にどうマッチするかを考えながら、アピールの核を決めましょう。
② アピールする塾講師経験のエピソードを選ぶ
次に、自分の強みを裏付ける具体的なエピソードを選びます。
このステップでは、ガクチカ全体を通じて最も重要なパートとなる「具体例」を明確にする必要があります。
ここで選ぶエピソードは、1つに絞ることが大切です。複数のエピソードを取り上げると焦点がぼやけ、アピールポイントが伝わりにくくなるからです。
例えば、「生徒の成績を向上させたエピソード」や「保護者とのコミュニケーションを通じて信頼関係を築いた経験」など、あなたが塾講師として特に力を入れた活動を選びます。
具体的な成果を示すことで、エピソードに説得力が生まれます。
たとえば、「生徒の定期テストの点数を10点向上させた」「教え子5人全員を志望校合格に導いた」といった数字や結果があると、より魅力的な内容になります。
また、選ぶエピソードは必ず「なぜその取り組みを行ったのか」「どんな課題があったのか」「その結果どうなったのか」といったストーリーを持つものにしましょう。
③ 構成に沿ってガクチカを作成する
エピソードが決まったら、それをもとに文章を作成します。
文章は以下の基本構成に沿ってまとめると、分かりやすく論理的な内容になります。
まず、冒頭で結論を述べます。この段階では、ガクチカ全体の概要を簡潔に伝えることがポイントです。
「塾講師として生徒の成績向上を目指し、独自の指導方法を工夫しました」といった一文で、どのような経験をアピールするのかを明確に示します。
次に、その結論を裏付ける具体的なエピソードを展開します。
この部分では、エピソードをより詳細に描写し、「どのような課題に直面したのか」「それを解決するためにどんな取り組みをしたのか」「結果としてどのような成果を上げたのか」を順序立てて説明します。
たとえば、「学習意欲の低い生徒に対して、毎授業の冒頭にミニテストを導入し、達成感を感じてもらうことでモチベーションを向上させました。その結果、生徒の平均点が10点向上し、志望校への合格率が上がりました」といった具合です。
最後に、その経験から得た学びと、それをどう活かすかを述べます。「この経験を通じて、個々のニーズに応じた柔軟な対応力を学びました。この力を活かして、貴社のプロジェクトでも、チームメンバー一人ひとりの能力を最大限引き出せるよう貢献したいと考えています」といった具合に締めくくることで、企業にとってあなたが魅力的な人材であることを示しましょう。
【塾講師のガクチカ】塾講師経験のガクチカを魅力的にアピールするコツ
次に、塾講師経験のガクチカをアピールするコツについて紹介していきます。
塾講師のアルバイトで学んだことは、アピールの仕方によって、自分らしさを印象づけられます。
自分だけが語ることのできるエピソードを明確に伝え、これまでの経験と企業に活かせることを結びつけましょう。
似たようなエピソードにも、魅力的に見えるものとそうではないものがあります。
それではガクチカをうまく伝えるために、押さえるべきポイントを確認していきましょう。
- 塾講師のアルバイトを始めた理由を話す
- 業務中に工夫したことを述べる
- 具体的な数字をアピールする
- 客観的評価を挙げる
- なるべく具体的に書く
- 企業に活かせる学びを述べる
- 企業が求める人物像を意識して書く
- ガクチカを第三者に添削してもらう
塾講師のアルバイトを始めた理由を話す
塾講師のアルバイトを始めた理由をわかりやすく説明することで、自分の価値観や考え方をアピールしやすくなります。
なぜ塾講師という仕事を選んだのか、その背景には自分の教育に対する熱意や人を助けたいという思いがあるかもしれません。
例えば「学びの楽しさを伝えたいと考えたから」あるいは「過去に自分が受けた教育が人生に大きな影響を与えたから」など、具体的なエピソードを交えて話すことでより説得力が増します。
また、塾講師という職業を選ぶに至った動機を説明することで、自分の行動原理や価値観を明確に伝えられます。
これにより、企業はあなたがどのような考え方を持っており、そしてどのような状況でモチベーションが高まるのかを想像できるのです。
業務中に工夫したことを述べる
業務中にどのようなことを工夫したのかについても詳しく説明することで、より良い印象を与えられる可能性が高まります。
業務中に自分なりに工夫したことを具体的に説明しましょう。
単に「塾講師として働いていた」という説明だけではインパクトが弱いです。
例えば、生徒一人ひとりの理解度に合わせた個別指導方法で工夫したり、難しい問題をわかりやすく説明するために独自のテキストを作ったりしたことなどが挙げられます。
このような工夫を通じて、どのようにして生徒の学習意欲を高め、成果をあげたのかを具体的に説明することで、自分の創意工夫と実行力を強調できます。
また、問題解決能力やコミュニケーション能力など、業務を通じて培ったスキルを具体的なエピソードを交えて伝えることで、企業に対して自分の能力をよりわかりやすくアピールできます。
具体的な数字をアピールする
具体的な数字をアピールすることも、塾講師の経験をより魅力的に伝えるためにおすすめの対策の1つです。
例えば「生徒の成績を平均で20点向上させた」「生徒の約80%が志望校に合格した」など、具体的な成果を示す数字を述べることで実績の裏付けとなり、信憑性が高まります。
数字は客観的な指標として非常に高く評価されやすく、面接官に対してあなたの能力を具体的かつ明確に伝える手段として有効です。
また、数字を用いることで自分がどれだけ貢献したのか、どのような成果をあげたのかを明確に示せます。
具体的な数字を用いてアピールすることで、企業に対して自分の実績をわかりやすく伝えることができ、将来的に活躍できる人物であるという期待を持たせることができます。
客観的評価を挙げる
塾講師としての経験をアピールするためには、自分の意見を話すだけでなく他の人からの客観的な評価を説明することも重要です。
例えば、保護者からの感謝の言葉や上司や同僚から褒められた経験など、第三者からの評価を交えることで自分の能力や努力が他者にどのように認識されているかを示せます。
保護者から「先生のおかげで子供の成績が上がりました。
前は勉強が嫌いだったのに今は塾に行くのを毎週楽しみにしている」などと感謝されたエピソードや、上司から「君の授業はいつ聞いてもわかりやすい」と評価された経験など、具体的に述べることで自分の努力や成果が客観的に評価されていることを強調できます。
なるべく具体的に書く
冒頭にも述べたように、塾講師は多くの学生がガクチカとして利用するため、差別化が必要です。
ガクチカでは成果と、その成果に至るまでの問題や課題に対して、どのように取り組んだかをくわしく書きます。
その際、問題と解決策には矛盾がないように注意してください。
解決策が根本的な改善になっていない場合、アピールにはなりません。
そこで数字を使って書くと、自分できちんと把握することにつながり、また相手にもエピソードが明確に伝わります。
定量的に成果を伝えると、エピソードに説得力をもたせられます。
したがって、エピソードにおける物事の様子や変化について、数値や数量にも着目して捉えられると良いでしょう。
相手に印象を残すために、具体的な数字を用いるなどして差別化をはかってください。
企業に活かせる学びを述べる
塾講師で得た学びを志望する企業に活かせないと、再現性がなく、アピールにつなげられません。
それを防ぐために、あらかじめ企業が求めている人材についてきちんと理解しておくと良いでしょう。
塾講師のアルバイトでは、社会に出てから必要とされるスキルが身につきやすいです。
自分の人柄やスキルが、企業に活かせるとわかるようなエピソードを探してみてください。
経験から何を学び、企業でそれをどのように活かしたいのかを考えてみましょう。
そのようにして自分の強みや価値観を整理し、企業が求める人物像と関連させて述べられれば理想的です。
企業に貢献する意思を積極的にアピールし、採用したくなるような一貫性のあるエピソードを目指しましょう。
企業が求める人物像を意識して書く
企業が求める人物像を意識して作成することも非常に重要なポイントです。
企業ごとに求める人物像は異なるため、企業の公式サイトはもちろん、採用情報や企業理念をよく調査し、余裕があれば企業の説明会に参加した上で、その企業がどのようなスキルや特性を重視しているのかを把握するようにしましょう。
例えば、リーダーシップを重視する企業ならば、生徒を指導する過程でリーダーシップを発揮したエピソードを強調することが重要です。
また、チームワークを重視する企業であれば、他の講師やスタッフと協力して円滑に授業を進めた経験などを具体的に説明することで、企業が求める人物像に合致することをアピールできます。
ガクチカを第三者に添削してもらう
ガクチカが完成したら、そのまま提出するのではなく、ぜひ一度第三者に添削してもらうようにしましょう。
自分では気づけない誤字脱字やわかりにくい表現、論理が破綻している部分などを指摘してもらえる可能性があります。
特に就活の経験が豊富な人や国語が得意な人に添削を依頼することで、よりガクチカが洗練されます。
第三者からのフィードバックを受けることで、自分の強みやアピールポイントについても再確認し、よりわかりやすく伝えるための工夫も可能です。
ぜひ、家族や友人、就活がすでに終わった先輩、キャリアセンターのスタッフなどに相談してみましょう。
【塾講師のガクチカ】ガクチカの構成
ガクチカの内容を企業に正しく伝えるのには、適切な文章構成にする必要があります。
塾講師の経験での学びをしっかりとアピールできるように、文章の組み立て方を見ていきましょう。
詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。
- 結論
- 理由
- 行動(塾講師のアルバイトのエピソード)
- 貢献(入社後の抱負を述べる)
結論
最初に「私が学生時代に力を入れたことは〇〇です」のように結論を簡潔に述べるようにしましょう。
結論を冒頭で伝えることで、人事担当者は学生が何を伝えようとしているのかを理解してこの後の内容を読むことができるからです。
また、結論を先に提示することで、結論を推測しながら読み進める必要がなくなります。
そのため、アピールしたいポイントが明確に効果的に伝わる効果があります。
理由
次に、「〇〇をしたいと思い〇〇に取り組みました」や「〇〇という目標を立て、〇〇に取り組みました」のように理由を説明しましょう。
ここで、結論で述べた内容をなぜ行ったのか動機を説明します。
これにより、どのようなことに関心があり価値を感じるのかや、行動を起こすモチベーションになるのかを伝えることができます。
どのような課題を感じ目標を立て、行動のきっかけになったのかを明確にするようにしましょう。
行動(塾講師のアルバイトのエピソード)
次は具体的なエピソードを用いて行動した内容を述べます。
ここでは、目標設定から課題の明示、解決の状況までを数字を用いて、客観的な判断ができるようにします。
塾の授業で使うような専門用語はなるべく避けて、一般的な言葉を使うように注意します。
行動した内容は詳しく具体的にして、人事担当者が状況をイメージできるようになります。
こうすることで、伝えたい内容が正確に理解され、適切に評価される可能性が高まります。
貢献(入社後の抱負を述べる)
最後にエピソードを通じて何を学びをまとめ、その経験が企業でどのように貢献できるのかを伝えます。
その際、企業研究の結果にもとづいて、企業が求めている学生の資質に合わせることが大切です。
ガクチカからの学びが素晴らしいことであったとしても、企業の求める内容とギャップがあると就活では評価されないです。
逆に志望企業が重視している分野に適した学びを伝えられると、熱意と志望度の高さをアピールできるでしょう。
【塾講師のガクチカ】塾講師をエピソードにしたガクチカの例文15選
つぎは上記の構成を活かした塾講師の経験に関するガクチカの例文を紹介します。
塾講師は生徒の成績を上げるという明確な目標が存在しています。
そこを課題として、エピソードの軸にすれば動機や成長が伝わりやすいガクチカを書けるでしょう。
また、生徒や保護者、社員や同僚など立場が異なる人々との関係をもつ点も塾講師の特徴です。
塾講師という仕事について、単に勉強を教えるだけの職業として見るのではなく、広い視野で自分の経験を俯瞰してみましょう。
それまで意識していなかった課題や取り組みを発見できるかもしれません。
新人研修制度をつくりあげた
例文
私が学生時代に力を入れたのは、塾講師アルバイトにおける新人研修プランの立案です。自身がアルバイトとして働き始めた際、塾のシステムやカリキュラムに関する説明が少なく、そのために初期のころは仕事につらさを感じていました。当時、塾ではアルバイト講師の早期離職率の高さが問題となっており、私は自身の経験からその理由は新人への指導が不十分なためだと考えました。そこで、私が取り組んだのは社員や先輩に対する新人指導の重要性の説明と、研修プランの提案です。勤務初期にしっかりと研修期間を設けることで、アルバイト講師の離職率が減り、同時に授業の理解度に関するアンケート結果も向上しました。
この経験を通して、自身が辛いと感じた際はただそれを我慢するのではなく、きちんと問題に向き合って原因を考えることが重要なのだと学びました。
生徒と保護者からのフィードバックの活用をした
例文
自分は塾講師として働くなかで尽力していたことは、保護者と密に連携を取れる体制の構築です。働いていた塾は進学校の受験対策をメインにした指導をおこなっており、実際に成果はあげていました。しかし保護者の評判はあまり良くありませんでした。自身の仕事や実績が理由もわからないまま、評価されない状況は放置できないため、保護者と直接面談し聞き取りをすることにしました。その結果、講師と教師のコミュニケーションが不足しており、お互いの想定している勉強のペースにずれが生じているとわかりました。そこで保護者に向けた説明資料にも力を入れ、不満点や疑問点のヒアリングも積極的に行うことにしました。
その結果、今の生徒数はこの取り組みをする前の1.5倍ほどに増えています。
塾は生徒と講師の問題という視点に固執せず、広い視点で俯瞰することの大切さを学んだ経験です。
生徒一人ひとりに合わせた勉強法を考え成績をあげた
例文
私は学生時代に塾講師として働き、生徒それぞれの個性にあった指導プランの作成に力を入れてきました。この活動の起点となったのは、同じ指導を受けている生徒でも成績の差があるにもかかわらず、特に対策をおこなっていない指導カリキュラムです。画一的な指導しかできていない点が成績に差が生じる原因だと考えました。そこで、通常のテストに加えてそれぞれの適性や、得意分野を判断するテストの実施を社員さんに提案し、承認されました。その結果をもとに生徒ごとの指導プランを制作したことにより、成績が伸び悩んでいた子どもを中心に全体的な平均点の底上げに成功したのです。
現状の問題を仕方ないこととして放置するのではなく、改善できるのではないかと考え始めること、その気づきの重要性を学べた点で、塾講師は自分を変えてくれた大切な経験です。
生徒のモチベーション管理と向上をした
例文
私が学生時代に特に力を入れたのは、塾講師として生徒の学習意欲を高めることです。これは、教育への深い関心と、生徒たちが知識を身につける過程に積極的に関わりたいという思いからでした。私は生徒一人ひとりの関心事を把握し、それを授業内容に結びつける方法を行いました。例えば、理科が苦手な生徒には日常生活での科学の例を挙げ、教材の内容が実生活にどのように適用されるかを示しました。このアプローチにより生徒たちは授業内容に対する関心を深め、学習意欲が顕著に向上しました。
この経験から私は一人ひとりのニーズに対応し、個々の関心に基づいて動機付けを行うことの重要性を学びました。
新しい授業をつくりだした
例文
私がアルバイト先の塾講師として最も力を入れたのは、参加型の学習環境を提供することです。この取り組みを始めた理由は、生徒の積極的な関与が学習効果を高めるという思いからです。実際に生徒が関心を持ちやすい新しい教材とアクティビティの導入を提案し実行に移しました。相互的な参加型のゲームやディスカッションを取り入れることで、生徒たちの学習意欲を高め授業への参加を促すなどです。科学の授業で実験を通じて理論を実践的に学ぶ活動や、数学でのパズルゲームを通して問題解決能力を養うことで消極的だった生徒の理解力が高まりました。
この経験から、新たな取り組みにチャレンジすることの重要さを学びました。
複雑な問題をわかりやすくまとめていた
例文
私が学生時代に働いた塾講師として最も力を入れ取り組んだのは、いかに簡単な言葉で解説するかということです。同じクラスでも解説の理解度が生徒により開きがあり、それが原因になり成績の向上を妨げていると感じていたからです。そのため、難しい理論や概念を説明する際も、生徒全員が理解できるように工夫しました。例えば、複雑な数学の公式を日常生活の例を用いて説明することで、生徒たちが概念をより簡単に理解できるようになりました。この取り組みにより生徒たちの理解度が向上し、その結果学業成績も改善しました。
この経験から聞き手の理解度に合わせて、内容を分かりやすく伝えることの重要性を学びました。
教室内の学習環境の維持
例文
私が学生時代に最も力を入れたのは、塾の講師として生徒の積極的な学習姿勢を育てることです。授業の内容を一方的に聞いているだけでは知識が定着せず成績は低迷していました。そこで私は学習は受動的なものではなく、生徒自身の積極的な参加が必要だと提案をおこないました。そして、授業中には生徒が自発的に参加し、質問や議論に積極的に関わるよう促しました。例えば、生徒に授業内容についての短い発表を行わせることで、彼らの自発的な学習と発言の機会を設けました。このアプローチにより生徒たちは自信を持ち、主体的に学ぶ姿勢が育ちました。
この経験から、私は自主性とコミュニケーション力の大切さを学びました。
チームワークを促す授業の展開
例文
私がアルバイトをしていた塾で講師として特に力を入れたのは、生徒同士の協力とチームワークの大切さを伝えることでした。大学の研究室の活動を通じて、個々の学習能力だけではなく他者と効果的に協力し共同で問題を解決する能力が重要になっていると感じたからです。生徒たちに相互に協力することとチームワークのスキルを実践してもらおうと簡易的なプロジェクトやグループディスカッションを行い発表を行いました。最初は話し合いや発表がうまく進みませんでしたが、回数を重ねるごとに改善されました。
この経験から単に知識を得るだけでなく、他者との協働の重要性とチームワークの大切さを学びました。
行動量で生徒の成績を上げた
例文
私は学生時代にアルバイトをしていた塾で、個別に苦手克服の対策をすることに力を入れていました。塾の通常のカリキュラムでは補えていない、生徒たちの苦手を克服することでさらなる学力向上が望めると考えたからです。そのため、授業の時間外でも質問を受け付けるという行動を起こしました。そして、生徒一人ひとりの個別のニーズや理解度の把握に取り組み、各生徒の苦手な部分に特化した問題を作成し対策しました。この取り組みにより生徒たちは自分の弱点を克服し、成績の向上につながりました。
この経験から、一人ひとりのニーズを汲み取り柔軟性を持って細やかに対応する重要性と行動力の大切さを学びました。
課題解決力をアピール
例文
私は学生時代に塾講師のアルバイトに力を入れて取り組みました。担当していたのは高校生の英語クラスで、生徒の成績向上が主な目標でした。しかし、生徒たちの多くは勉強に対するモチベーションが低く、特に英語に苦手意識を持つ生徒が多かったため、授業に集中してもらうのに苦労しました。 この問題を解決するために、私は生徒一人ひとりの理解度や興味に合わせたカスタマイズした授業計画を立案しました。まず、生徒と個別に面談し、彼らがなぜ英語に苦手意識を持っているのかをヒアリングしました。その結果、多くの生徒が基礎的な文法に自信がないことがわかり、授業内容を基礎に立ち返りつつ、実生活で使える例を取り入れたものに変更しました。また、授業の最後には簡単な英語ゲームを導入することで、楽しみながら学べる環境を作りました。 その結果、クラス全体の平均点は2か月で15点上がり、生徒たちのやる気も向上しました。さらに、生徒自身が自発的に勉強に取り組む姿勢が見られるようになり、最終的には全員が志望校に合格するという結果を残すことができました。
この経験を通じて、問題の根本原因を見つけ、解決策を立案・実行する力を身につけました。また、コミュニケーションを通じて相手のニーズを理解する力も強化されました。今後もこの経験を活かし、目標達成に向けて主体的に行動する姿勢を大切にしていきたいです。
協調性をアピール
例文
私が学生時代に最も力を入れたのは、塾講師のアルバイトです。大学1年生の頃から3年間、主に中学生を対象に数学と英語を教えていました。当初、教え子の多くは勉強への苦手意識が強く、特にテスト前になると不安が募り、勉強に身が入らない様子が見受けられました。 私は、単に知識を教えるだけでなく、生徒一人ひとりの悩みや苦手意識に寄り添い、勉強を楽しんでもらえる工夫をしました。例えば、数学の授業では、難しい公式を使う前にその意味や日常生活での応用例を一緒に考えることで、生徒が興味を持てるように工夫しました。また、生徒の理解度に応じた個別の学習プランを提案し、小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に自信をつけてもらうことを目指しました。 この取り組みの結果、成績の伸び悩んでいた生徒たちが次第に積極的に授業に取り組むようになり、クラス全体の平均点が一学期で15点向上しました。また、保護者からも「子どもが自主的に勉強するようになった」と感謝の声をいただきました。
この経験を通じて、目標達成には「相手に寄り添い、個々のニーズに合わせたアプローチ」が大切だということを学びました。また、粘り強く努力することで、成果が出ることの喜びを感じました。この経験を活かし、今後もどんな課題に対しても前向きに取り組み、周囲の人と協力しながら成果を出していきたいと考えています。
教室運営の効率化を実現
例文
私が学生時代力を入れたことは、塾講師として教室運営の効率化を実現したことです。授業準備や片付けに時間がかかり、講師が指導に集中できないという課題を感じました。そこで、教材を科目別・学年別に整理し、QRコードを活用した貸出管理システムを導入しました。
この取り組みにより、準備時間が半分に短縮され、授業の質を向上させる環境を整えることができました。この経験を通じて、問題を発見し解決に導く力を養いました。
生徒同士の教え合い制度を導入
例文
私が学生時代力を入れたことは、生徒同士で教え合う制度の導入です。個々の学力差が大きいクラスで、生徒同士が互いに学び合える仕組みを考えました。理解度の高い生徒をティーチャー役に指名し、質問や解説をしてもらう場を設けたところ、教える側も教わる側も理解が深まりました。
その結果、クラス全体の平均点が向上し、生徒たちの学ぶ意欲も高まりました。この経験から、人の強みを活かし、全体の成長を促す方法を学びました。
オンライン授業の導入と質の向上
例文
私が学生時代力を入れたことは、塾でオンライン授業を導入し、その質を向上させる取り組みです。対面授業が難しい状況下で、生徒の集中力が持続せず、理解が進まないという課題がありました。私は授業内容を動画にまとめたオンデマンド教材を作成し、好きな時間に復習できる仕組みを整えました。また、オンラインホワイトボードやリアルタイムクイズ機能を活用して、インタラクティブな授業を実現しました。その結果、授業後の確認テストで生徒の平均点が15%向上しました。
この経験を通じて、柔軟な対応力と技術を活用した問題解決能力を磨きました。
定期テスト前の特別対策授業を企画・実施
例文
私が学生時代力を入れたことは、塾で定期テスト前の特別対策授業を企画・実施したことです。生徒一人ひとりの弱点を分析し、頻出分野を中心にしたオリジナルプリントを作成しました。また、集中して学習できるよう土日に特別講習を開講し、生徒のモチベーションを高めました。その結果、クラスの平均点が約20点向上し、多くの生徒が志望校に合格しました。
この経験から、目標達成に向けた計画力と行動力を身につけました。
400文字のガクチカは下記の記事に詳しく解説しています。こちらもあわせてご覧ください。
【塾講師のガクチカ】ガクチカを作る際の注意点
塾講師のガクチカでどのような強みがアピールできるのかはすでに説明した通りです。
しかし、アピールできる経験があったとしても書き方を間違えれば、それは相手にうまく伝わりません。
つぎは塾講師のガクチカを書く際の注意点を見ていきましょう。
ガクチカで要求される相手にわかりやすい文章を書く、相手に自身の経験や考えを伝えるという技法は就活以外でも多くの場面で役に立ちます。
ガクチカを書きながら新しいスキルを身につけるつもりで、適切な書き方を試行錯誤してみるとよいかもしれません。
- 動機を明確にする
- わかりやすい表現を用いる
- 成果だけを述べない
- アピールにならない話題は避けるようにする
動機を明確にする
先述したように、企業がガクチカを通して知りたいことの1つは、学生が何をモチベーションの源泉としているかです。
ガクチカでそれを伝えるためには、動機を明確に記述する必要があります。
ただ課題と行動や結果を記述するだけでなく、自身がなぜそれを問題と考え、対策をすることになったのか、そのスタート地点の感情をしっかりと描写しましょう。
自身の感情や考えを抜きにしてガクチカを書いてしまうと、それは単なるアルバイト先の説明や仕事先の記録になってしまいます。
また動機を明確に描写することは、成果が出たあとの変化や成長を強く印象づけるためにも有効な手法です。
一方、動機や感情だけを全面に出しすぎてもガクチカとして十分ではありません。
具体的な事実と自身の内面をバランスよく描写しましょう。
わかりやすい表現を用いる
ガクチカでアルバイト経験について書く際は、相手に伝わりやすい文章を意識することも重用です。
専門用語や固有名詞は極力使わないことを意識し、わかりやすい表現へ言い換えましょう。
また、一口に塾講師と言っても、生徒の年齢層や指導環境、一度に相手にする人数などは仕事先によって異なります。
そういった事前情報を十分に把握できていなければ、ガクチカを読んでも頑張りや苦労を十分に理解できません。
そのため、塾講師の経験でガクチカを書く際には具体的な数字やエピソードを盛り込みましょう。
自身の労働環境や、行動による変化をイメージしやすい形で伝えることが大切です。
わかりやすくイメージしやすいガクチカを書くためには、事前に仕事内容を知らない人に試し読みをしてもらい、わかりにくい点の聞き取りをするのも有効でしょう。
成果だけを述べない
塾講師として何を成し遂げたのかを考えた際に、生徒の学力を伸ばしたことについてあげる人が多いのではないでしょうか。
しかし、この成果だけを述べることは、アピールポイントにはなりません。
不十分であり、ただの自慢になってしまうかもしれません。
実際に生徒の学力を向上させるために、どんな工夫をしたのか、要因を深掘りすることが大切なのです。
具体性がなければ、説得力に欠けてしまいます。
成果が出るまでの課題や、問題に対するアプローチの仕方に工夫が見えると良いでしょう。
なぜその問題点に目をつけたのかということにも、就活生の特性はあらわれます。
したがって成果を述べる際は、それまでにどのような取り組みを行ったのか、はっきり指し示すように意識してみてください。
アピールにならない話題は避けるようにする
塾講師の経験に関するものなら、なんでも話して良いというわけではありません。
塾講師経験について話すならば、授業の工夫や生徒との関わり方、保護者から信頼を勝ち取ったことなどを話すのが一般的です。
例えば「仲良くなった同僚と一緒に資格試験を頑張った」という話をするなら、主題は塾ではなく、資格勉強にしましょう。
また、アピールになりにくい「一度も遅刻せずに出勤した」「苦手な生徒が居たけれど、頑張って指導した」なども避けた方が良いです。
遅刻しないことは当然ですし、アルバイトをするなら、1人くらい苦手な人は居るものです。
必ずしも、卓越した実績を残した必要はありませんが「他に話すことはなかったのか?」と思われてしまうようなエピソードは避けましょう。
【塾講師のガクチカ】塾講師のガクチカはベンチャー企業にも刺さる
塾講師で得られる力として、課題解決力・周囲を巻き込む力・傾聴力などをあげました。
これらの力は、日々変化が目まぐるしく、比較的少人数であるベンチャー企業にも求められるものです。
一人ひとりの生徒と向き合う塾講師は、過去に例のない課題に向き合わなければならないときがあります。
すべての生徒に当てはまる解決策は存在しません。
ベンチャー企業において、こうした状況に応じた対応ができるのは大切なことです。
周囲と協力し、人の話にしっかりと耳を傾け、相手の立場に合わせて物事を変えられた経験は、ベンチャー企業で活かせる力と言えるでしょう。
また、ベンチャー企業は経験や実績を重視します。
塾講師としての経験には、わかりやすい成果があります。
その成果と、それに至るまでの道を明確に述べられる塾講師のガクチカは、ベンチャー企業へのアピールに向いているのです。
まとめ
塾講師経験で就活に受かるガクチカを書くコツは、自身の問題解決力や周囲を巻き込む力のアピールをするとともに、モチベーションや個性をしっかり伝えることです。
こういった点を意識すれば企業とのミスマッチも少なくなり、企業にとっても、学生にとっても効率的に就活を進められるでしょう。
一方で行動を開始する動機が不明瞭であったり、わかりにくい表現を多用していたりすると、努力や成長が十分に伝わらない可能性もあります。
自信の経験から動機や学びをしっかりとくみ取り、わかりやすい構成になるよう意識したガクチカを作ることが大切です。
以下の記事では塾講師以外にもアルバイト経験をアピールする方法を紹介をしています。こちらもご覧ください。
▼▼▼▼ この記事の要約動画はこちら ▼▼▼▼