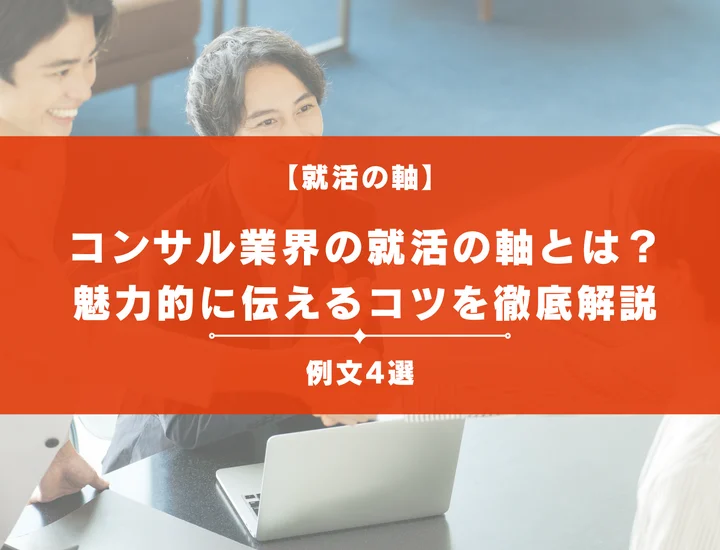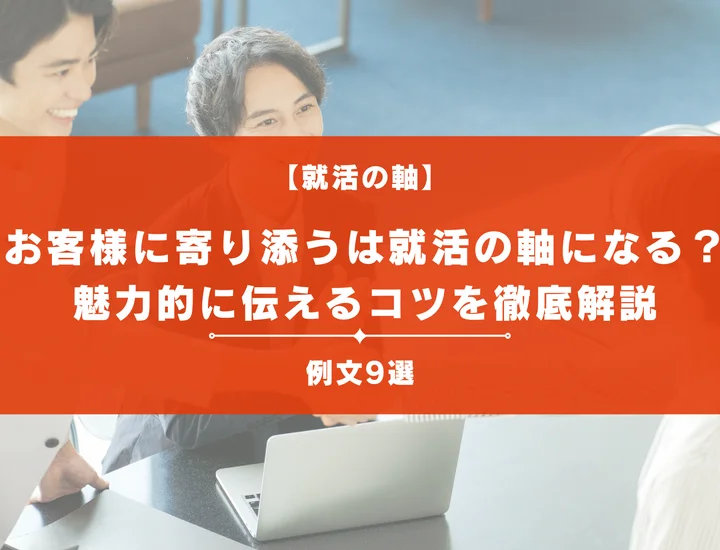明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・評価される就活の軸の作り方
・就活の軸を作るときの注意点
・面接で聞かれた時の回答例文5選
・就活の軸の作り方が分からない人
・自分に合った就活の軸を作りたい人
・就活の軸の例文を参考にしたい人
はじめに
就活をする際に、自身の基準がない状態で就活を行うと、企業選定やES・面接対策のタイミングで悩むことになり、就活を効率的に進めることが難しくなります。
そこで、まずは自身の大切にしたい価値観を見極めて就活の軸を作り、就活に挑むことが大切です。
しかし、就活の軸を実際にどう作れば良いかわからないと不安な就活生もいると思いますので、本記事では「就活の軸の作り方」について、事前準備を含めて詳しく解説します。
就活の軸を作る際の注意点やポイントもあわせてご紹介しますので、就活の軸に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
【就活の軸の作り方】就活の軸とは
世の中には様々な業界と企業が存在するため、就活の際に何も考えずに膨大な数の企業の中から自分にあった企業を選ぶのは簡単ではありません。
そこで、企業選びでは、就活の軸を事前に作っておき、それに合わせた企業を絞ることが大切になってきます。
就活の軸とは、自身が働くうえで最も譲れない条件や基準のことです。
自身の就活の軸から見て企業ごとの社風や事業が一致していると、自分に合った企業を選択しやすくなります。
また、企業側も学生が就活の軸を持っていることを前提に選考を行っており、面接の時に学生の価値観や考えを見るために、就活の軸を尋ねる企業も多いです。
就活の軸は、就活を効果的に進めるうえで非常に重要ですので、作る際には過去の経験や自分が入社後やりたいことなどの自己分析を行うことがおすすめです。
【就活の軸の作り方】就活の軸を作るメリット
就活を進める際に、就活の軸があるとさまざまなメリットがあります。
就活の軸を作ることで、自身の何を重点的にしたいかを明確にでき、企業選びが円滑に行えるようになります。
また、就活の軸は自身のやりたいことから、どのような企業や業界を選べば良いのかの指標になるため、就活の軸として自身の基準を具体的に作ることで、企業とのミスマッチが減ります。
しかし、就活の軸がないままに就活を行うと、選択の幅が広がって企業とのミスマッチの可能性も高くなるでしょう。
企業選びが円滑に行える
就活の軸を作る1つ目のメリットは、企業選びが円滑に行えるようになることです。
企業ごとに、社風や得意とする業務は様々ですので、就活の軸を決めてから企業選びをすると、自分の性格や価値観に近い社風ややりたいことを実現できる企業を選びやすくなります。
就活の軸が定まっていないと企業選択だけでなく、その前の業界選びから簡単ではありません。
また、就活の軸ではなく、志望動機で決めて就活を行うこともできますが、志望動機は就活中に変わってくることがあるでしょう。
理由が変わると今まで探していた企業とまったく違う社風や業界の企業も選びかねません。
そのため、就活の軸を定めてから企業選びを行ったほうが良いです。
基本の就活の軸を決めた後に、それを軸に妥協点やこだわりたいポイントなどを増やしていきましょう。
志望動機に活かせる
2つ目のメリットは、就活の軸をESや面接の際に志望動機としても活かすことができることです。
就活の軸には、自身の大事にしたい企業を選ぶ際の譲れない条件と企業の魅力を感じたポイントが入っているためです。
また、就活の軸を決める際に、さまざまな自己分析や他己分析を行う必要がありますので、その際に出てきた価値観ややりがいを企業への志望動機の中に応用することもできます。
ただし、志望動機と就活の軸をまったく同じものにしてはいけません。
志望動機はさまざまな企業ごとの理由ですが、就活の軸は企業に関係なく自分の就活をするうえでの譲れない一つのものだからです。
就活の軸から企業への志望動機ができると考えましょう。
入社後のミスマッチを減らせる
3つ目のメリットは、就活の軸を持つことで入社後のミスマッチを減らせることです。
なぜなら、就活の軸は自身の譲れない条件のため、一番避けたい条件の企業などを省くことができるからです。
一方で、就活の軸がないと、企業の選択が広くなり自身が譲れない条件から企業を絞ることができません。
また、企業選びの基準となる就活の軸でなく、自身の志望動機から企業を選択すると就活の途中で志望するポイントがブレやすくなります。
基準が変わると、その時は自身にあった企業と思っていても働くにつれてミスマッチを感じる場合があります。
また、入社後もし企業で何かあった時に就活の軸を決めておくと、軸から何を基準にして選んだか振り返ることができるでしょう。
面接で一貫した回答ができる
就活の軸を設定することは就職活動全体を通じて自分の意志や目標を明確にするために不可欠です。
明確にしておくことで、志望動機や自己PRといった面接での回答が一貫性を持ちます。
一貫性がある回答は採用担当者に対して信頼感や誠実さを伝える上で非常に重要です。
自分の就活の軸が「成長できる環境で働く」ことだと明確にしておけば、企業研究や自己分析の際に、その軸を基にしたエピソードを探しやすくなります。
これにより、志望動機では「成長を支援する環境があるため御社を志望しました」など具体的な説明が可能となり、自己PRでは「自分が成長を求めて挑戦した経験」を述べることで自然な流れを作れます。
軸を中心に据えることで、採用担当者に対して説得力のあるメッセージを届けることができるでしょう。
【就活の軸の作り方】就活の軸を聞く理由
企業がわかるなぜ就活の軸を聞いてくるのかについても理解を深めておく必要があります。
この部分を深く理解できれば、相手が求めている回答に沿ったものを提供できるからです。
ぜひ企業側がなぜ就活の軸について聞いてくるのかについて、理解を深めた上で文章を作成しましょう。
企業側もミスマッチを防ぐため
就活生は就職した後に「想像以上にマッチしていなかった」「業務が辛い」などの理由でミスマッチを感じることもあります。
これらの対策をすることは就活生にとって非常に重要である一方で、企業側もミスマッチを避けたいと考えているのは同様です。
すぐに離職されてしまっては、採用に費やしたコストや新人教育に充てた時間が無駄になってしまいます。
そこで、企業の理念にマッチしないような人材を採用しないためにも、就活の軸がどのようなものであるのかについて詳しく聞こうとしているのです。
企業は、自社で長期的に活躍できる人材を求めているため、その姿勢をアピールしましょう。
志望動機と照らし合わせるため
志望動機と照らし合わせるためというのも、就活の軸を企業が聞いてくる理由の1つとして挙げられます。
就活の軸は、その学生が就活に望む態度がどのようなものであるかを確認できるものの1つです。
よって、その軸に矛盾が生じていたり、その企業に本当にマッチしているのかどうか怪しい場合は、採用を見送られる可能性が高いです。
しっかりとした返答ができるか、志望動機と矛盾していないかなどについて確認することで、あなたが企業に合っている人材かどうか、就活に対してのモチベーションが高い人材かどうかを確認しているのです。
【就活の軸の作り方】就活の軸の主な分類
就活の軸の主な分類についても紹介します。
大きく分けて4つの分類があるため、それぞれ確認して自分が何を大切にして就活を進めていくのかについて考えてみてください。
労働条件・待遇
労働条件や待遇を軸として就活を進めることは現代の多様な働き方を考える上で非常に重要です。
特にフレックスタイム制やリモートワークといった柔軟な働き方が増えている中、自分がどのような働き方を望んでいるのかを明確にしておくことで、入社後の不満やストレスを軽減できます。
この軸を考える際には給与体系や勤務地、勤務時間、休日制度など具体的な条件をしっかりと確認することが必要です。
ライフワークバランスを重視するならば、残業時間の少ない企業や有給休暇の取得率が高い企業は魅力的に映るでしょう。
また、リモートワークが可能な企業であれば、通勤の負担を減らしながら自宅で効率的に働ける環境を得られる可能性があります。
一方、通勤が必要な場合でも勤務地が自宅から近い、もしくは勤務地が選べる企業であれば、働きやすいでしょう。
業務内容
業務内容を就活の軸とすることは仕事を通じて自分の目標を実現する上で非常に有効です。
自分が興味を持つ分野や得意とするスキルを活かせる業務内容を選ぶことで、やりがいや達成感を得やすくなります。
また、業務内容の軸が明確であれば、入社後に起こりがちなミスマッチを防ぐことにもつながります。
プログラミングが得意な人であれば、開発業務に力を入れている企業を選ぶのが良いでしょう。
また、マーケティングに興味がある場合は企画や広報といった業務に携われる企業を優先するべきです。
このように、自分の興味やスキルと一致する業務内容を選ぶことで、スムーズに仕事に取り組める環境を見つけられます。
職場の雰囲気
職場の雰囲気を軸として考えることは自分が働きやすい環境を見つけるための重要な要素です。
職場の雰囲気には社員同士の人間関係やコミュニケーションの取り方、働き方のスタイルなどが含まれます。
自分がチームで協力し合う環境を好むのか、それとも個人で集中して作業する方が得意なのかを明確にすることで、適切な職場を選べます。
アットホームな雰囲気の職場では社員同士の距離が近く、相談しやすい環境が整っている場合が多いです。
一方で、成果主義を重視する職場では個人の能力が尊重されるため、自分の実力を試したいと考える人には適しているでしょう。
企業理念
企業理念を就活の軸にすることは仕事に対するやりがいや満足感を得るための重要なポイントです。
企業理念に共感できるかどうかは自分の価値観や目標と企業の方向性が一致しているかを判断する基準となります。
この軸を基に企業を選ぶことで、自分の価値観に合った環境で働ける可能性が高まります。
社会貢献を重視する企業の理念に共感するならば、その企業の活動内容や方針が自分の目標に合っているかを確認することが必要です。
一方で、革新的なアイデアを追求する企業に魅力を感じる場合はその企業が取り組んでいるプロジェクトやビジョンを深く理解することが大切です。
【就活の軸の作り方】就活の軸を作るための事前準備
さまざまな事前準備を行うと就活の軸が作りやすくなります。
まず業界研究を行うことで、自身のイメージだけで業界を考えず具体的に志望の理由も書きやすくなるでしょう。
そして、業界で働いているOBOGの訪問を利用することによって、先輩からの働いて感じた業界のイメージなどを知ることができます。
実際に就活の軸の具体例を見て、何を重点としているのか見てみることで、就活の軸が作りやすくなります。
業界研究をする
就活を始める前は、業界のイメージは自身の想像のことが多いでしょう。
そのため、就活の軸を作るうえでは、業界の研究をすることが必要です。
志望する業界が決まっていなければ、就活の軸は作りにくいため、業界研究によって自身の興味のある業界を探していくことも有効です。
そのほかにも、業界研究の目的として、志望する業界について詳しく知っておく必要があります。
業界研究の仕方は、業界の事業内容や種類などを含めて、業界ごとに特徴を調べていきましょう。
業界ごとの深堀りを行う際には、まずその業界全体がどのようなことを行っているか全体図を見ます。
その後に、業界の中での専門性についてどのようなものがあるか調べて、より志望業界に対する理解を深めていくのがおすすめです。
OBOG訪問をする
OBOG訪問を利用して、実際に企業で働いている人から話を聞くことができます。
OBOG訪問をする際には、先輩から実際の企業の現場の話を聞いて、自分のイメージとズレがないかを確認していきましょう。
また、先輩は直接企業の社員でもあります。
そのため、自身の意欲を見せることで企業への内定につながる可能性もあるのです。
実際にOBOG訪問を行う際には、まず企業に自身の大学の先輩がいるか確認することから始めます。
大学のキャリアセンターや就職課で卒業生を探したり、自身のサークルやゼミの卒業した先輩から頼む方法もあるでしょう。
どの方法を使っても、先輩は自分のために時間を割いてくれているので、実際にOBOG訪問で話を聞く際には、事前準備をして時間を無駄にしないようにしましょう。
就活の軸の具体例を知る
就活の軸を自身の力だけで作るのは難しいと感じる場合は、実際の具体例を知ることも効果的です。
就活の軸の具体例を見る時は、何を理由にどうしていきたいかを実際にどのように記載されているかを見ていきます。
就活の軸の理由は業界、人、社風、働き方など様々であり、何を軸にするかによって、未来の目標も変わってきます。
逆に何を企業でしたいか、どの業界や企業ならそれを叶えられるかの視点で見ることも大事です。
ただし、自分で就活の軸を作る際には、具体例と同じものを使うのではなく、具体例を見て、アピールできる就活の軸について学んでいきましょう。
それを踏まえたうえで、自身の就活の軸をイメージしていくと作りやすくなります。
【就活の軸の作り方】就活の軸の一覧
続いて、就活の軸にはどのようなものがあるのかについても確認してみましょう。
大きく分けて「自分の適正に合わせた軸」「自分のやりがいに関係する軸」「自分の働き方に関する軸」の3つが当てはまるため、自分がどれを重視していきたいかについて考えた後で、何を軸にするか考えてみてください。
自分の適性に合わせた軸
自分の適正に合わせた軸、つまり自分のスキルや長所、経験などを活かせる環境であるかを重視している人は、以下のような就活の軸を活用することをおすすめします。
就活の軸において自分の適性を中心にアピールするということは、即戦力として活躍する可能性が高い能力のある人材であるということをアピールすることにつながります。
よって、ベンチャー企業のような、即戦力を求めている可能性の高い企業には特に効果を発揮する就活の軸であると言えます。
- 自分の長所を活かしたい
- 自分の専門分野を活かしたい
- 自分の経験を活かしたい
- 語学力を活かしたい
自分のやりがいに関する軸
自分のやりがいに関する内容も就活の軸に据えることをおすすめするものの1つです。
これはモチベーションを重視する企業において特に高く評価されやすい傾向があり、ベンチャー企業など、やる気がある人材を特に採用したいと考えている企業において特に好印象を与える可能性が高いと言えます。
よって、自分のモチベーションも積極的にアピールしたい人は、ぜひ以下の就活の軸を参考にしてみてください。
- 顧客に直接感謝される仕事をしたい
- 理念に共感できる仕事をしたい
- チャレンジできる企業で働きたい
- 若いうちからリーダーとして働きたい
- 世界情勢に基づいた仕事をしたい
- 自分の成長を実感できる仕事をしたい
自分の働き方に関する軸
これはどちらかというと、企業に対して積極的にアピールする「建前の軸」というよりは自分が求めている「本音の軸」に当てはまるものです。
もちろん、場合によっては企業に対してアピールして良いものではありますが、自分の待遇に関することであるため、基本的には「前面に押し出す」というよりは、自分が企業を選ぶ際に重要にするものであり、面接で話す必要はそこまでないものです。
「面接で話す」というよりは自分の中に留めるようにしましょう。
ただし、就活で企業を絞り込むに当たってはぜひ検討したいポイントの1つです。
- 転勤のない職場で働きたい
- 都会で働きたい
- 地元で働きたい
- 海外で働きたい
- リモートワークで働きたい
- 福利厚生が充実している企業で働きたい
- 仲間と競い合って働きたい
【就活の軸の作り方】就活の軸の作り方
就活の軸を作る際にはいくつかポイントがあります。
まず就活の軸となるスキルや能力について何を持っているか自身を知るために自己分析を行うことが大事です。
現在の自分を知った後に、将来のビジョンをイメージしてどのように自身が働いているかを想像しましょう。
そのイメージを元にすると就活の軸の内容が見えてきます。
就活の軸として、自身の就活するうえでの譲れない条件を決めることで、企業とのミスマッチを減らすことにつながります。
自己分析をして今の自分を知る
就活の軸を作る際には、自分を知ることが大事です。
自己分析は自身の能力や強みを理解することができるでしょう。
また、自身の強みや考えなどは過去の経験から現在につながっています。
自己分析をすると過去の経験から強みや考え方になった理由がわかるため、具体例が出せるようにもなるでしょう。
さらに、自己分析の際には、自身の得意なことだけでなく苦手なことや欠点も合わせて理解するようにしましょう。
苦手なことも理解することで、就活の軸を客観的評価の視点でも作ることができます。
また、自身で自分を分析するだけではなく、他者から自身の評価を見てもらう他己分析もしましょう。
分析をする際に、相手がいなければ就活エージェントなどを利用するのも方法としてあります。
自己分析や他己分析の方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
将来のビジョンを考える
就活の軸を考える際に現在だけでなく、自身の将来も合わせて考えることが必要です。
就活生が将来のビジョンを考えると大きな目標になりやすいです。
ですが、就活の軸としては実現可能なことを目標として定めることが大事でしょう。
また、最初から大きな目標を立てるのではなく、その大きな目標から何をすればそれが実現できるか考えます。
一つずつ過程を逆算することによって、大きな目標も実現できる可能性が高くなるのです。
将来のビジョンを考える際に、まず未来の自分がどうなっているか想像します。
区切りをつけて年齢ごとに分けて決めると、将来のビジョンが浮かびやすいでしょう。
ただし、将来のビジョンを考える時は、普段の生活のことではなく仕事に対しての将来的なビジョンを持つことが大事です。
将来のビジョンをイメージしておくと、面接で質問があった時も答えやすくなります。
志望企業を比較して共通点を探す
就活の軸を作るためには、まず自分が志望している企業や業界を深く理解し、その共通点を探すことが効果的です。
複数の企業や業界に興味がある場合、それぞれの特徴や理念、事業内容、働き方、企業文化などを比較しておきましょう。
その中で、共通して自分が魅力を感じるポイントや希望する条件が浮かび上がってくることが多いです。
例えば「挑戦を奨励する文化」「グローバルに展開している」「社員の自主性を尊重する」など、志望企業に共通する価値観や方向性が見つかるでしょう。
それがあなたにとっての重要な軸になるかもしれません。
志望企業の共通点を見つければ、あなた自身がどのような働き方や企業文化を求めているのか、またどのようなキャリアパスを目指しているのかが明確になることでしょう。
就活において譲れない条件を決める
就活の軸を作る際に、就活において自身の譲れない条件を決めることは大事です。
譲れない条件を作らず、企業を受ける都度条件を変えると内定を獲得しても入社後に後悔することでしょう。
就活の軸がブレないようにするためにも、自分なりの譲れない就活の条件は決めるべきです。
条件を決めるためには、まず将来のビジョンから見て今の自分に足りないものを考えていきます。
そして、その足りないものに優先順位を付けます。
その中から就活の中で何が一番譲れない条件かを考えましょう。
自身の就活に対して譲れない条件が、他の就活生とまったく同じになることは少ないです。
ただし、就活の中で譲れない条件を作る時に、いくつも譲れない条件を作ってしまうと、その条件が増えれば増えるほど企業の選択の幅が狭くなります。
そのため、譲れない条件は1~3つにしましょう。
【就活の軸の作り方】就活の軸を作る際のポイント
続いて、就活の軸を作る際のポイントについても紹介します。
以下のポイントを踏まえた上で作成することで、スムーズかつ企業に良い印象を与えられる質の高い就活の軸が出来上がるはずです。
ぜひ、それぞれのポイントを参考にしてみてください。
軸を考えることに時間をかけすぎない
就職活動において、就活の軸を作ることは重要なステップですが、軸を考えることにあまりにも多くの時間を費やすのは避けるべきです。
自己分析や業界研究を通じて、自分の価値観や希望する働き方を明確にすることは大切ですが、深く考えすぎて行動が遅れると、選考や面接のタイミングを逃してしまうこともあります。
就活の軸は、一度設定した後、実際に企業説明会に参加したり、エントリーシートを書いたり、面接を受けたりする過程でさらに洗練されていくものです。
最初から完璧な軸を作る必要はなく、ある程度の方向性が見えたら、すぐに行動に移すことが大切です。
就活の軸を作る際におすすめの対策は以下の2つです。
それぞれ取り組んでみてください。
1. 説明会やOB訪問で話を聞く
就活の軸を作る際には、企業説明会やOB訪問を利用して、実際にその企業で働いている人の話を聞くことが非常に有効です。
会社の公式サイトや求人情報だけでは分からない、現場での具体的な仕事内容や職場の雰囲気、職場文化などを知ることで、自分の軸がその企業や業界に合っているかを判断する材料が増えます。
特に、OB訪問では自分と同じ大学出身者や同じ経歴を持つ先輩から直接体験談を聞くことができるため、リアルな視点で企業を評価することができます。
説明会での企業プレゼンテーションやOBとの対話を通じて「自分はこの会社で何をしたいのか」「この会社の価値観に共感できるか」といった点が明確になるでしょう。
また、実際に働いている人の意見を聞くことで、企業に対する疑問や不安も解消でき、自分にとっての就活の軸がしっかりと固まるはずです。
2. インターンに参加する
インターンに参加することも、就活の軸を作る上で非常に有効な手段です。
実際に企業で働く体験をすることで、その職場でどのように働くのか、企業の社風や業界の雰囲気が自分に合っているかを体感できます。
こうしたリアルな経験を積むことで、単なるイメージや噂ではなく、実際の業務を通じて自分の就活の軸を固めていくことができます。
例えば、インターンシップで営業職を体験して、顧客とのコミュニケーションにやりがいを感じたり、逆にデスクワークが自分に向いていると気づいたりできます。
また、インターンシップでは社員と直接触れ合う機会が多いため、その会社の人間関係や働き方のスタイルをより深く知ることができ、自分がその企業で働くイメージがより具体化されます。
このような経験は自分の就活軸を確立するための非常に有益な情報源となり、自己分析の精度を高める上でも重要です。
職種から考えてみる
就活の軸を作る際には、業界だけでなく職種に注目して考えることも有効な方法の1つです。
同じ業界内でも、職種によって求められるスキルや業務内容は大きく異なります。
例えば、IT業界を見てみると、エンジニアと営業職では仕事内容が全く異なり、求められる能力や働き方も異なります。
業界だけでなく、自分がどの職種に興味を持っているかを考え、それが自分の強みやキャリアビジョンに合っているかを検討することがより具体的な軸づくりにつながります。
職種を中心に考えることで、自分が何にやりがいを感じ、どのようなスキルを磨きたいかが明確になり、企業選びもスムーズになるでしょう。
さらに、職種にフォーカスすることでキャリアパスを具体的に描くことができ「将来どのように成長していきたいか」を考えながら企業を選ぶこともできます。
【就活の軸の作り方】就活の軸を作る際の注意点
就活の軸を作る時には、さまざまな注意点があります。
まず、就活の大きな根元の軸はブレないようにしましょう。
次に就活の軸を書く際には、自身の待遇面などを書くことは控える必要があります。
なぜなら、待遇面を就活の軸にすると企業から自分のことしか考えていないと思われるからです。
また、就活の軸の内容は、曖昧なものではなく具体的に作る必要があります。
就活の軸を具体的にすることで、企業選びが行いやすくなるでしょう。
これらの注意点についてそれぞれ説明していきます。
軸はブレないようにする
就活を続けていくにつれて自身の思っている就活の軸の条件ではなく、ほかの条件に目移りすることもあるでしょう。
ですが、就活の軸をブレて内容を変えてはいけません。
就活の軸を作る際には、その就活の軸はブレないようにすることが大事です。
就活の軸がブレていると信頼性が薄くなるでしょう。
企業から見ても就活の軸がブレている就活生は信頼性が薄くなり、悪い印象を与えることになります。
そのため一度決めた就活の軸は就活が終わるまでは変えてはいけません。
また、一つの就活の軸では幅が狭く選べる企業の範囲が少ない時もあるでしょう。
その場合はもともと決めている就活の軸に、条件を追加して範囲を広げることをおすすめします。
最初に決めた就活の軸の根本が、ブレていないか確認することが大事です。
待遇面は控える
就活の軸を作る時に仕事について考えると、自身の待遇面も気になるでしょう。
ですが、就活の軸では待遇面の内容は控えたほうが良いです。
面接で聞かれた際に待遇面のことを話すと企業から自分のことしか考えていないと思われるでしょう。
そのため、就活の軸として待遇面を含めるのはおすすめしません。
そのほかにも、待遇面を就活の軸として優先すると、企業から業務や業界はどこでも良いのかと思われやすくなります。
待遇面でも妥協したくないという場合は、就活の軸以外で条件に入れましょう。
企業選びをする際に待遇面を確認すること自体は、忌避されていません。
就活の軸ではなく、あくまで自分の志望動機の一つとして心に留めておきましょう。
多くの業界に当てはまる軸は避ける
就活の軸を作る際、多くの業界や企業に当てはまってしまうような、広い軸を設定することは避けるべきです。
汎用性が高すぎる軸はどの企業にも通用する反面、志望度や企業への特別な熱意が伝わりにくくなってしまいます。
「成長できる環境」「チームワークを重視する職場」といった軸は、多くの企業で実現可能な条件であり、特定の業界や企業を選ぶ理由としては非常に弱いです。
このような軸では、選考において「なぜこの企業を受けているのか」という問いに対する説得力が非常に薄くなってしまうことでしょう。
企業側は応募者が自社に対して強い関心や理解を持っているか、またその企業でしか実現できない具体的な目標があるかを見ています。
そのため、志望企業や業界の特性に密接に関連した軸を設定することが求められるのです。
なるべく具体的にしておく
就活の軸を作る際には、内容を曖昧にしてはいけません。
なるべく具体的に就活の軸を作りましょう。
たとえば、やりがいがある仕事をしたいという就活の軸ならば、やりがいという言葉だけでは抽象的になります。
就活の軸が抽象的だと条件も曖昧になるため、企業の選択が難しくなるでしょう。
物事を一つずつ具体的にしてくと、就活の軸が抽象的になりづらいです。
たとえば、仕事へのやりがいを就活の軸にしたいのであれば、何をした時にやりがいを感じるのか理由を考えましょう。
物事に対して理由を作ることで具体的になりやすいです。
そのほかにも、就活の軸を具体的にするためには、自己分析や他己分析などの自身の評価ややりたいことの見直しをしましょう。
抽象的にならないように、物事に優先順位をつけていくことも大事です。
【就活の軸の作り方】面接で就活の軸を聞かれた際の回答例文12選
実際に面接で就活の軸について聞かれた場合にはどのように回答すれば良い印象を与えられるのでしょうか。
代表的な業界における例文を作成したため、ぜひ参考にしてみてください。
本記事で紹介した内容を踏まえた上で作成されている例文であるため、自分が目指していない業界のものについても、時間があるならばぜひ確認し、本記事のおさらいとしてください。
金融業界の例
私はこれまでの学生生活で経済学を専攻し、金融市場の社会経済への影響について深く学んできました。
具体的には、大学での論文研究を通じて、金融政策が国内外の経済に与える影響を分析し、この分野における専門知識を深めてきました。
また、学外でのインターンシップでは実際の金融業務に関わり、理論だけでなく実務における問題解決能力も磨きました。
このような経験を通じて、私は金融の仕事がただ数字を扱うだけではなく、それによって企業や個人、さらには国の経済が大きく左右されることを実感しました。
したがって、私は金融業界でのキャリアを通じて、重要な決定を行い、多くの人々の生活や社会全体にポジティブな影響を与えることを目指しています。
私は自分の専門知識とスキルを活かして、責任ある立場で貢献したいと考えており、貴社でその夢を実現させたいと思っています。
メーカー業界の例
学生時代、工学部で学んだ知識を活かし、さまざまなプロジェクトで技術的な課題に取り組む中で、創造力がいかにして新しい解決策を生み出すかを実感しました。
特に4年次に取り組んだプロジェクトでは、環境に優しい新素材を用いた製品開発を行いました。
新しい素材を用いた開発は難航しましたが、想像力を活かして検証を繰り返し、最終的には学内コンペティションで最優秀賞を獲得しました。
この経験から、創造的な思考、そして社会に価値を提供するという強い意志がどれほど重要かを学びました。
貴社では常に革新が求められており、私のような創造力を持つ者には絶好の舞台であると考えています。
私は貴社で創造力を最大限に活かし、市場に新たな価値を提供する製品を創出することで貢献し、活躍していきたいと考えています。
商社業界の例
大学時代にアメリカでの1年間の留学を経験し、様々な文化背景を持つ人々とのコミュニケーションや、多様な考え方に触れる中で、国際的な視野と柔軟性を身につけました。
留学中、現地の大学で行われたビジネスプランコンテストに参加し、チームの中で唯一の非ネイティブスピーカーでしたが、プレゼンテーションを担当しました。
私たちのチームは15チーム中2番目に高い評価を受け、この経験は私にとって大きな自信となりました。
このような国際経験を活かし、商社で働くことで世界各国との架け橋となり、国境を越えたビジネスの成功に貢献したいと思っています。
異文化間の交渉やプロジェクトマネジメントのスキルを活かし、グローバルな市場での新たなビジネスチャンスを探求し、企業の国際競争力を高めるために尽力します。
私は貴社において、留学で培ったスキルと知識を存分に発揮し、世界的に活躍したいと考えています。
IT業界の例
私はコンピュータサイエンスを専攻しており、プログラミングスキルとともに、ユーザー中心のソフトウェア開発に関する深い知識を身につけてきました。
大学でのプロジェクトやインターンシップを通じて、使いやすさを重視したアプリ開発に携わった際は、特に高齢者や障がいを持つユーザーが使いやすいデザインを考慮しました。
このプロセスで、ITの力がどれほど多くの人々の日常生活に直接的な影響を与えるかを実感しました。
私はこの経験を活かし、社会的な課題に対応するためのソリューションを開発したいと考えています。
例えば、日本は教員の数が足りず、現場で働く方々は長時間に及ぶ時間外勤務を強いられています。
そこで教員の方々が効率的に業務を行えるアプリを開発し、ワークライフバランスを改善することに貢献したいと考えています。
このようなビジョンを持ち、貴社の一員として、革新的で人々の役に立つ技術を創出し続ける所存です。
官公庁・公社・団体の例
私は大学で社会学を専攻し、地域社会の問題解決に焦点を当てた数多くのプロジェクトに取り組みました。
そして、公共政策が地域コミュニティに与える影響に深い関心を持つようになりました。
特に地域の高齢者向けサービスの改善に関するプロジェクトでは直接住民の声を聞き、ニーズに応える提案をしました。
この経験は私にとって大きなやりがいとなり、公共の場で働くやりがいを改めて実感しました。
私は市民一人ひとりの問題に耳を傾け、それに対応することで、具体的な感謝の声を直接聞きたいと考えています。
私は、市民からの「ありがとう」を力に変え、より良い社会を築くために、日々業務に取り組み、感謝とやりがいを日々の業務に反映させながら、地域社会に寄与し続けたいと強く願っています。
広告業界の例
大学時代、私は学園祭の広告プロモーションを一任されました。
当初、来場者数が例年より減少しており、その原因は従来の紙媒体を中心とした広告手法にあると考えました。
そこで、SNSを活用したデジタルマーケティングを導入し、ターゲット層を10代から20代の若者に設定して、彼らの興味を惹くコンテンツを制作しました。
その結果、来場者数が前年比で30%増加し、学園祭運営チームからも高い評価を受けました。
この経験を通じて、広告の持つ力やアイデア次第で社会に大きな影響を与えられる可能性を強く感じました。
入社後は貴社が手掛けるプロジェクトにおいて新しい発想を持ち込み、多様な手法でクライアントの課題を解決する所存です。
インフラ業界の例
大学時代、私は地方自治体が主導する災害復興プロジェクトに学生ボランティアとして参加しました。
豪雨被害を受けた地域のインフラ復旧が急務であり、私は地元住民の方と連携しながら復旧作業を支援し、被害を受けた橋の設計案を検討する際には建築学科で学んだ知識を活かし、耐久性とコストのバランスを考慮した提案を行いました。
プロジェクトは予定より早く進み、住民の方々から「安心して生活できるようになった」との感謝の言葉をいただきました。
この経験を通じて、インフラ整備が地域の安心と繁栄を支える重要な仕事であることを実感しました。
入社後は貴社が手掛ける社会基盤の整備プロジェクトに積極的に携わり、自分の専門性を活かして貢献する所存です。
小売業界の例
私は大学時代、地元商店街の活性化プロジェクトに参加しました。
商店街の客足が減少している原因を分析したところ、周辺に大規模なショッピングモールが建設されたことが影響しているとわかり、地域の特産品をテーマにしたフェアを開催し、地域住民との交流を促進するアイデアを提案しました。
その結果、イベント当日は多くの来場者が訪れ、商店街の売上が一時的に倍増し、継続的な交流のきっかけを作ることができました。
この経験を通じて、地域と密接に関わる小売業の可能性を強く感じました。
入社後は貴社が展開する店舗運営に携わり、地域に密着したサービスを通じて新たな価値を提供する所存です。
コンサル業界の例
大学時代、私はゼミ活動の一環として中小企業の経営改善プロジェクトに参加しました。
売上が減少している地元の小規模飲食店を対象に、課題の特定と改善策の提案を行った結果、広告戦略が不十分であることが判明しました。
そこで、SNSを活用したキャンペーンを企画し、新規顧客層をターゲットにした広告を展開しました。
その結果、売上が15%増加し、店主から感謝の言葉をいただきました。
この経験を通じて、課題解決のプロセスにやりがいを感じ、より多くの企業に貢献したいと考えるようになりました。
入社後は貴社が手掛けるコンサルティング案件において、クライアントの課題を的確に把握し、実現可能な解決策を提案する所存です。
サービス業界の例
私は大学時代、ホテルでのアルバイトを通じて接客業務を経験しました。
ある時、体調を崩したお客様に近隣の病院を紹介し、送迎を手配したことがありました。
その後、そのお客様から丁寧な感謝の手紙をいただき、自分の行動が人の役に立つ喜びを実感しました。
この経験を通じて、直接人と関わり、人のために尽力する仕事にやりがいを感じました。
入社後は貴社のサービスを通じて多くの方に満足を届ける所存です。具体的には現場での接客業務に携わりながら、顧客満足度を向上させる取り組みを行いたいと考えています。
また、現場の経験を重ねる中で、サービスの品質向上に寄与し、会社全体の成長に貢献する所存です。
食品業界の例
大学時代、食品衛生に関する研究室に所属し、食品の保存方法や衛生管理について学びました。
その中で、研究の一環として、地元の食品工場と連携し、保存技術を応用した加工品の開発や、地域イベントでの低価格販売を実施し、廃棄量を大幅に削減しました。
この取り組みを通じて、安全で持続的な食品の提供が社会に与える影響の大きさを学びました。
入社後は貴社の製品開発に携わり、食品の安全性と美味しさを両立させた商品を生み出す所存です。
また、食品ロスの削減や持続可能な生産方法を提案することで、社会に貢献する製品を提供したいと考えています。
不動産業界の例
大学時代、地方都市の空き家問題に着目したフィールドワークを行いました。
空き家の増加により地域が活気を失っている現状を知り、地元自治体や不動産業者と協力して解決策を模索しました。
特に空き家をリノベーションし、若者や子育て世代向けの住居として活用するプロジェクトを企画したことが印象に残っています。
空き家が賃貸物件として生まれ変わり、新しい住民を迎えることができた際には大きな達成感を得ました。
この経験から、不動産業界が持つ社会貢献の可能性を強く感じました。
入社後は貴社の事業を通じて、安心して暮らせる住環境を提供できる人物として長岐に渡り、貴社と消費者に貢献する所存です。
【就活の軸の作り方】ベンチャー企業で評価される就活の軸
ベンチャー企業への就職における就活の軸については、一般の企業とは別の視点で評価されます。
ベンチャー企業では受動的な内容の就活の軸ではなく、能動的な内容の就活の軸が好まれやすいでしょう。
なぜなら、ベンチャー企業では一人ひとりの裁量が大きく社員が成長しやすい環境であるため、挑戦的な姿勢を求められます。
そのため、自己成長ややりがい、実力主義を元とした就活の軸を作ると評価もされやすいでしょう。
ただし、成長や仕事のやりがいなど言葉だけを使うと抽象的になりやすいです。
将来のビジョンと合わせて事業的に自分はどうしていきたいか、具体性を含ませて作ると良くなります。
また、自身の中でも成長の定義は何かについて考えておくと良いでしょう。
実力主義などを就活の軸にする際には、もし実力が足りない時どうすれば良いかの対策も求められます。
まとめ
就活を進めていくうえで、就活の軸は自身の企業選択につながる必要な考え方になるでしょう。
そのためには、就活の軸を具体的に決めておくことが必要です。
企業からも面接で聞かれることの多い就活の軸は、就活における自身の譲れない条件にもなります。
インターンや企業研究から業界、企業のことを理解したうえで将来のビジョンを元に実現したい目標を意識します。
自分なりの就活の軸を作って、企業選択のミスマッチを減らしていきましょう。







_720x550.webp)


_720x550.webp)