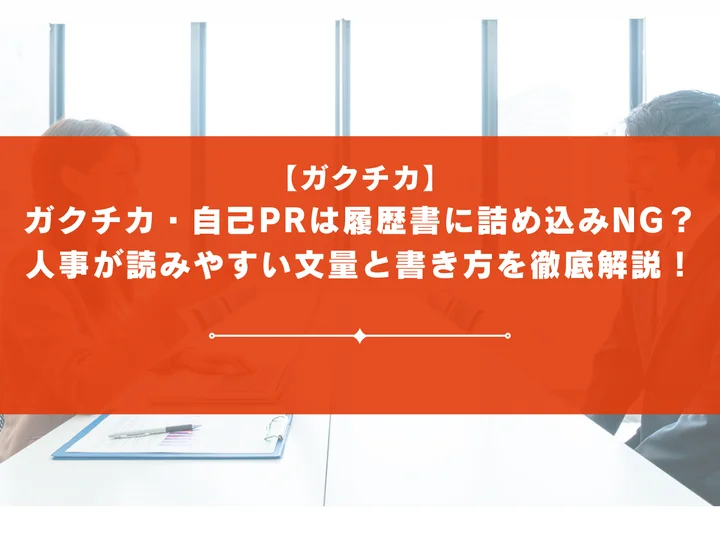明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・ガクチカとは
・企業がガクチカを聞く理由
・高評価を得る具体的なテーマの選び方
・企業が求めるポイントを押さえた伝え方
・ガクチカで話すエピソードに悩んでいる大学生
・自分の経験が面接で評価されるか不安な就活生
・ガクチカを効果的に構成する方法を知りたい人
・例文を見て作成時に参考にしたい人
【ガクチカの強いエピソード】はじめに
ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」の略であり、自己PRや志望動機の次に聞かれる可能性が高い非常に重要な質問です。
この質問を通じて、あなたが学生時代にどのようなことに力を入れてきたのか、どのような価値観を持ち、どのように成長してきたのかを伝えることが求められます。
しかし、ガクチカを作成する際「自分のエピソードが弱い」と感じており、より強いエピソードを作る方法を探して悩む方も多いでしょう。
そこで今回は強いエピソードを作る方法や、これまでの経験をどのように表現すれば強い印象を与えられるのかについて紹介します。
【ガクチカの強いエピソード】ガクチカに強いエピソードは必要?
結論として、ガクチカを作成するにあたって、強いエピソードは必ずしも必要ではありません。
「全国大会で優勝した」「英検1級を取得していた」「全国模試で常に1位だった」などの素晴らしい実績は悪いわけではありませんが、それをただ話すだけではアピールにならないこともあります。
むしろ重要なのは経験をどのように伝え、そこから学んだことを具体的に説明できるかです。
そのため、自分のエピソードが弱いと感じても、悩む必要はありません。
【ガクチカの強いエピソード】企業がガクチカを聞く理由
企業はガクチカを通じて、どのようなことが知りたいのでしょうか。
もちろん、企業によっては別の要素を確認している場合もありますが、ほとんどの企業は下記の3つを確認している場合が多いでしょう。
ここではその理由について紹介していきます。
- 人柄や価値観を知るため
- 求めている人物像とマッチしているかをみるため
- 学生時代の経験と今後の活かし方を知るため
- モチベーションの源泉を知るため
- 問題解決能力をみるため
- 分かりやすく伝える力を測るため
人柄や価値観を知るため
企業がガクチカを聞く最大の目的は、応募者の人間性や価値観を理解することです。
どのようなことに興味を持ち、どのような困難に直面し、それをどう乗り越えたか。
その過程を通じて、応募者の本質的な性格や思考パターンが見えてきます。
例えば、挑戦心や協調性、責任感といった社会人として重要な資質が浮き彫りになります。
日本企業は特に「人柄重視」の採用方針をとる場合が多く、自社の雰囲気や価値観と一致する人物であるかを確かめるために、ガクチカの内容をチェックしています。
求めている人物像とマッチしているかをみるため
企業はそれぞれ独自の理念や方針を持っており、求める人物像も多様です。
そのため、採用では自社が理想とする人材に合致しているかを重要視します。
ガクチカを通じて応募者の特性が伝わるため、企業は「この人物がチームや職場の中でどのように活躍するのか」を具体的にイメージします。
逆に、求める人物像と一致しない応募者を採用すると、ミスマッチによる早期離職のリスクが生じるため、慎重な判断が求められます。
学生時代の経験と今後の活かし方を知るため
企業は、応募者の学生時代の経験を通じて、具体的なスキルや知識のほか、それをどのように応用してきたのかを知りたいと考えています。
例えば、アルバイトや部活動、留学経験などで得たスキルが、入社後の業務で活かされる可能性を重視します。
また、問題解決力やチームでの働き方、リーダーシップといったビジネスで重要な能力を測る基準にもなります。
さらに、具体的なエピソードの中で、学んだことや困難を乗り越えた方法が語られることで、「入社後の活躍が期待できるか」を判断する材料になるのです。
モチベーションの源泉を知るため
企業はガクチカを通じてモチベーションの源泉も確認しようとしています。
応募者が何に対して強い関心を持ち、どのような状況でやる気を感じるのかを知れば、自社に合っているかを判断できますし、どのような職種を任せるかについても判断できるからです。
好奇心旺盛であると伺える人は、積極的に新しい知識を吸収し、変化が多い環境に順応できると想像できますし、数字にこだわる人や達成感を求める人は、営業職やコンサルのような、自分の仕事の成果が数値化される仕事を好むでしょう。
ガクチカはその人の価値観や行動の原動力を反映させているものであるため、何をモチベーションに努力を続けられるのかが、非常にわかりやすいのです。
問題解決能力をみるため
どのような企業においても問題解決能力は非常に重要視されているため、ガクチカを通じて確認されている場合も多いです。
ただし、ガクチカを通じて確認されているのは「問題解決ができたかどうか」ではなく「再現性のある解決能力を持っているか」です。
論理的な思考力を有しているか、柔軟な発想を持っているかなど、就職した後にも問題解決に携われるかについて確認されています。
そこで「根性で何とかしました」「毎日努力を続けた結果解決できました」などといった根性論とも言える、工夫のないアピールではなく、どのような取り組みをして問題を解決させたのかについて触れられると良いでしょう。
分かりやすく伝える力を測るため
ガクチカは自分を売り込む場です。
よって、簡潔に分かりやすく、自分の能力や経験をアピールしなければなりませんが、裏を返せば、分かりやすく伝える能力があるかを企業が測る絶好のチャンスでもあります。
分かりやすい構成で、起承転結がはっきりとしていれば「分かりやすく伝える力を有しており、論理性も高い人物である」と判断されますし、ガクチカですら分かりにくい文章を書いているということは「伝える力が足りず、あまり優秀な人物ではない」と判断される可能性があります。
そこで、自分の経験を構造化して「何に取り組んだのか」「どのような課題があったのか」「どのように解決したのか」「そこから何を学んだのか」という流れで伝えましょう。
【ガクチカの強いエピソード】強いガクチカのテーマと例文
続いて、ガクチカによく使われるテーマとその例文について紹介します。
それぞれの経験や活動がなぜよく使われるのか、なぜ高く評価されやすいのかについて紹介した後に、それぞれの例文を1つずつ紹介するため、参考にしてみてください。
ガクチカの例文については下記記事で詳しく紹介をしています。参考にしてみてください!
アルバイト経験
アルバイト経験は就職活動において社会に近い環境で自身の能力を発揮した具体的な事例として高く評価されます。
アルバイトをテーマに選ぶ際には、労働の事実を述べるだけでなく、自身がどのように貢献したのかを具体的に伝えることが重要です。
特に、リーダーとして新人教育を行った経験や、売上向上に寄与したエピソードは強力なアピールポイントになります。
飲食店でのアルバイト経験を題材にするならば「効率的な作業分担を提案し、平均待ち時間を30%短縮した」といった成果を数字で示すと説得力が増します。
また、自らが主体的に問題を見つけ、それを解決するために具体的な行動を起こしたプロセスを伝えることも有効です。
こうした「行動を通じて得た学びやスキル」を明確にすることで、採用担当者に強い印象を与えられます。
例文:アルバイト
私が学生時代に力を入れたことは飲食店でのアルバイトです。
私の役割はホールスタッフとしての接客対応でしたが、売上向上を目指して店舗全体の業務改善にも関わりました。
ランチタイムにおける顧客回転率の低下が課題となっていたため、オーダーのスムーズな受け取りと配膳の効率化を図るための新しい動線を提案しました。
この取り組みにより、平均回転率が20%向上し、売上が前年同月比で15%増加しました。
この経験を通じて、課題を見つけ出し解決策を提案する力や、チーム全体を動かすためのコミュニケーションスキルを学びました。
貴社に就職後はこの課題解決能力とコミュニケーションスキルを活かし、顧客やチームメンバーとの信頼関係を築きながら業務に貢献する所存です。
部活動・サークル活動
部活動やサークル活動はチームワークやリーダーシップを具体的にアピールするテーマとして非常に適しています。
特に、キャプテンやリーダーとしてメンバーをまとめた経験や、大会での成果を語る際には自分の役割を明確にし、どのようにチームに貢献したのかを伝えることが重要です。
体育会系の部活動でキャプテンを務めたならば、チームが直面した困難をどのように克服したかをエピソードとして述べると良いでしょう。
一方、文化系のサークル活動でも、自分の役割や達成した成果を具体的に述べることが大切です。
「文化祭でサークルの展示を成功させるために、予算管理や役割分担を徹底し、例年よりも多くの来場者を集めた」といった経験を語ることで、計画力や実行力を伝えられます。
また、チームメンバーの意見をまとめる際に注意した点や、困難を乗り越えた際のプロセスを加えることで、協調性や問題解決能力もアピールできます。
例文:部活動
私が学生時代に力を入れたことは大学の陸上競技部での活動です。
私は主将として部全体のトレーニング内容の見直しにも携わりました。
練習中の怪我が多発していることが課題であったため、過去のデータを分析し、けがを予防するためのウォーミングアップ方法を提案しました。
さらに、部員全員が共有できるスケジュール管理システムを導入することで、個々の練習計画が明確化されるようにした結果、部員のけがの件数が前年よりも30%減少し、全体の練習効率が向上しました。
この経験から、課題を分析し、具体的な改善策を実行に移す力を養いました。
貴社に就職後はこの経験を活かし、チームの一員として業務に取り組むだけでなく、必要に応じて改善提案を行う姿勢で貢献する所存です。
例文:サークル活動
私が学生時代に力を入れたことはイベント企画サークルで文化祭でのライブイベントの企画責任者を務めたことです。
集客率が低迷しているという課題があったため、ターゲット層を明確化し、SNSを活用した広報戦略を展開しました。
また、出演者のブッキングから当日の運営まで全体のスケジュールを管理し、チームメンバーと協力して準備を進めました。
その結果、過去最高の来場者数を記録し、来場者アンケートでは満足度が90%を超える結果となりました。
この活動を通じて、限られたリソースを活用しながら成果を最大化する力や、周囲と連携して目標を達成するスキルを学びました。
貴社に就職後は企画力と実行力を活かし、新しいプロジェクトの立案や運営に積極的に関わりたいと考えています。
ゼミ・研究活動
ゼミや研究活動も、学問に対する探究心や問題解決能力を示すテーマとして非常に適しています。
特に、研究の過程で直面した課題をどのように克服したのか、またその成果がどのように評価されたのかを具体的に述べることが重要です。
「ゼミで地域経済の活性化をテーマに研究を行った際、データ収集が難航したため、地方自治体との連携を提案し、協力を得た」というエピソードは説得力があります。
研究活動をガクチカとして選ぶ際には学問的な側面だけでなく、その経験を通じて得たスキルや知識が将来の仕事にどのように活かせるのかを述べることも重要です。
「データ分析を通じて論理的な考え方を養うことができ、それを活かして貴社の業務で精度の高い提案を行いたい」といった形で述べると、適応が伝わりやすいでしょう。
例文:ゼミ
私が学生時代に力を入れたことはゼミでのマーケティング研究です。
ゼミでは消費者行動の分析をテーマに研究を行い、チームでアンケートを作成し、約300名の回答を収集しました。
その後、収集したデータを基に統計ソフトを用いて分析を行い、購買行動に影響を与える要因を明確化しました。
これにより、大学の学内コンテストでは10チームの中で最優秀賞を受賞できました。
この活動を通じて、データを基にした論理的な考え方や、チームで成果を上げるための協力貴社に就職後はこの分析力やプレゼンテーションスキルを活かし、データを活用した戦略的な提案を行うことで、事業の成長に貢献する所存です。
例文:研究活動
私が学生時代に力を入れたことは卒業研究におけるAI技術の活用に関する研究で、AIを用いた画像認識システムの開発を選びました。
まず、関連する論文や資料を調査し、既存技術の理解を深め、実際にプログラミング言語を用いてアルゴリズムを構築し、データセットを基に精度を向上させる試行錯誤を繰り返しました。
最終的に、精度90%を超える認識モデルを完成させ、学会で成果を発表した際は好評を得ることもできました。
この研究を通じて、新しい技術を学ぶための継続的な努力や、問題解決に向けた粘り強さを身につけました。
貴社に就職後はこの技術的な知識と問題解決能力を活かし、新しいプロジェクトで成果を上げることに貢献する所存です。
ボランティア活動
ボランティア活動は社会貢献意識や他者との協力性を示すテーマとして非常に有効です。
ただし、参加した事実を述べるだけではなく、どのような背景や目的で活動を行い、そこから得た学びや成果を具体的に伝えることが重要です。
「地域の清掃活動に参加した」といった内容を挙げる場合、その活動を始めた理由や背景を述べると説得力が増します。
「地域住民の間で清掃の必要性が高まっていたが、リーダーシップを取る人がいなかったため、自分が企画を提案した」という形で、自身の主体性を強調しましょう。
例文:ボランティア活動
私が学生時代に力を入れたことは地域の清掃活動を中心としたボランティア活動です。
毎月1回開催される清掃活動では、活動の運営にも携わりました。
当初は参加者数が減少傾向にあったため、新たな参加者を募るためのポスターやSNSを使った広報活動を実施しました。
また、活動後には地域住民との交流会を企画し、地域全体での一体感を高める取り組みを行いました。
これにより、参加者数が以前の倍以上に増加し、活動が地域での認知を得る結果となりました。
この活動を通じて、他者との協力の重要性や、課題に対して柔軟に対応する力を学びました。
貴社に就職後はこの経験を基に、周囲と連携しながら課題を解決し、プロジェクトを円滑に進行させる所存です。
留学・インターンシップ
留学やインターンシップはチャレンジ精神や国際感覚、実務経験をアピールするテーマとしておすすめです。
特に、異文化に適応する過程や、現地で達成した成果を具体的に伝えることで、採用担当者に強い印象を与えられます。
留学をテーマにする場合には「海外で生活した」という事実を述べるだけではなく、具体的な目標や課題に取り組んだエピソードを挙げることが重要です。
「現地の学生と共同でプロジェクトを行い、文化の違いから生じる意見の対立を調整した」などのエピソードを述べると、異文化適応能力や調整力を具体的に示せます。
一方、インターンシップをテーマに選ぶ場合には業務内容や貢献度を具体的に述べることが大切です。
「インターン先で新商品のプロモーション企画を担当し、その結果としてSNSのフォロワー数を20%増加させた」というエピソードは行動力や提案力をアピールする材料になります。
また、その経験を通じて得たスキルや学びを応募企業の業務にどう活かせるのかを述べることで、志望動機とも結びつけられます。
例文:留学
私が学生時代に力を入れたことは半年間の海外留学です。
留学先では現地の大学に通いながら、現地学生と共同でプロジェクトを行いました。
地域の観光資源を活用したマーケティングプランを作成し、地元企業に提案する活動を行いました。
文化の違いから意見の衝突もありましたが、その都度話し合いを重ね、互いの考えを尊重しながら解決した結果、提案が採用され、観光客数の20%増加に貢献したと報告を受けました。
この留学経験を通じて、異なる価値観を受け入れる姿勢や、柔軟な対応力を身につけました。
貴社に就職後はこの経験を活かし、グローバルな視点で業務に取り組むとともに、柔軟な対応力を発揮して貴社の発展に貢献する所存です。
例文:インターンシップ
私が学生時代に力を入れたことはIT企業でのインターンシップです。
私はシステム開発部門に配属され、チームの一員として新しいウェブアプリケーションの開発に携わりました。
主な役割はユーザーインターフェースのデザインと、バックエンドとフロントエンドの連携部分のコード実装で、特に、UI/UXデザインを改善することでユーザビリティを向上させる提案を行い、実際にユーザーからの評価が高まりました。
この経験を通じて、現場での課題解決能力やチームでの連携力を磨くことができました。
貴社に就職後はこの実務経験を活かし、プロジェクトに積極的に貢献する所存です。
特に、課題を分析し、迅速に解決策を提案する姿勢で貴社の業務効率化に寄与したいと考えています。
資格取得
資格取得は自己成長や努力を示すテーマとして非常におすすめです。
このテーマを選ぶ際にはどのような背景や目的で資格取得を目指したのか、そしてその過程でどのように努力を重ねたのかを具体的に述べることが重要です。
また、資格取得に向けてどのような工夫や努力を行ったのかを具体的に述べると、採用担当者に取り組みのプロセスが伝わりやすくなります。
最後に、資格取得を通じて得たスキルや知識を応募企業でどのように活かせるのかを述べることも大切です。
「簿記資格を通じて身につけた数字に強い基盤を活かし、貴社の財務分析業務に貢献する所存です」といった形で締めくくると、あなたを採用するメリットが明確になります。
例文:資格取得
私が学生時代に力を入れたことは簿記2級資格の取得で、特に過去問の分析や模擬試験の繰り返しに力を入れました。
また、理解を深めるために会計実務の基礎について独自に調査し、参考書とオンライン教材を活用しました。
試験直前には毎日3時間以上の集中学習を行い、試験当日には模試を含め、過去最高の得点で合格を果たしました。
この経験を通じて、目標に向けて計画的に行動する力や、継続的な努力を続ける重要性を学び、実際に会計の知識を活用する場面での応用力も身につけました。
貴社に就職後はこの経験から得た知識を活かし、財務管理やコスト削減などの分野で貢献する所存です。
その他
ガクチカのテーマは必ずしも学業やアルバイト、サークルなどよく使われるものである必要はありません。
旅行、読書、筋トレ、料理、人間関係など、あなたの経験の概要と、その経験を通じて何を身につけ、入社後どのように貢献してくれるかが理解できれば良いからです。
よほど奇抜なものでなければ、テーマはなんでも良いのです。
趣味
私が学生時代に力を入れたことは趣味の映画鑑賞です。
映画は歴史や文化、心理学など幅広い知識を得られる機会だと考え、週末に最低でも2本、常にノートを取りながら映画を見ることを心がけました。
構成や登場人物の心理、社会的背景など様々な要素を分析し、映画に関する考察をブログにまとめました。
この積み重ねにより、論理的思考力や物事を多角的に捉える力を身につけることができ、映画の内容を端的に伝える力も養うことができました。
貴社に入社した際には、この経験を活かし、膨大なデータや市場の動向を的確に読み取りながら、クライアントに分かりやすく施策を提案し、多くの契約を勝ち取りたいと思っています。
旅行
私が学生時代に力を入れたことは、旅行の計画を徹底的に練ることです。
1年生の時に一人旅に出た際、お店の臨時休業や急な悪天候で旅行が台無しになってしまったため、移動手段、予算、食事の好みなど徹底的に考慮し、3つのプランを用意することにしました。
その結果、どのようなハプニングに襲われても柔軟にプランを組み合わせて旅行を楽しむことができ、回数を重ねるごとに多くの友人が旅行に参加してくれるようになり、私の友人間では半年に一度の旅行が一大イベントとなっています。
この経験から、計画力と柔軟な対応力を身につけることができました。
貴社に入社した際には、プロジェクトを進めるにあたって常に代替案を考えておき、エラーが発生した際や納期が短くなった時にも即座に対応できるよう、リスクヘッジを大切にして仕事に取り組みたいと考えています。
一人暮らし
私が学生時代に力を入れたことは、一人暮らしを始めるにあたって自己管理を徹底することです。
大学入学を機に一人暮らしを始め、自己管理能力を高めるために毎朝5時に起床し、ジョギングとストレッチを習慣化し、早めに大学に登校して、授業開始まで予習や読書をする習慣を続けました。
その結果、時間を効率的に使う力が身につき、集中力や忍耐力が鍛えられただけでなく、4年間で250冊以上の本を読破でき、ビジネス全般に関する知識や営業、マーケティング、ライティング、自己啓発、哲学など、多様な知識とスキルを身につけることもできました。
貴社に入社してからもこの習慣を続け、健康を徹底的に管理するとともに、知識を磨き続け、常に最新の情報をキャッチアップし、業務に取り入れられるエンジニアとして貢献する所存です。
【ガクチカの強いエピソード】成功するテーマの選び方
続いて、ガクチカのテーマの選び方についても紹介します。
以下の2つのポイントを押さえた上でテーマ選びをしておけば、企業の採用担当者に良い印象を与えられるだけでなく、内定を獲得しやすくなります。
先ほど紹介した「高評価を得るガクチカに共通する3つのポイント」と併せて確認しておいてください。
- 志望企業の価値観や求めるスキルに関連するものを選ぶ
- 自分の強みや成果をアピールできる内容に絞る
志望企業の価値観や求めるスキルに関連するものを選ぶ
ガクチカで高い評価を得るためには、志望企業の価値観や求めるスキルに関連するエピソードを選ぶことが非常に重要です。
企業ごとに求める人物像や大切にしている価値観が異なるため、それらに沿ったエピソードを提示することで、自分が企業文化や業務に適応できる人材であることをアピールできます。
まず、志望企業の求めるスキルや価値観を調査することが不可欠です。
企業の採用ページや公式SNS、またはインターンシップでの経験を通じて、どのような能力や姿勢を求めているのかを把握しましょう。
顧客対応力を重視する企業であれば、アルバイトやインターンシップで顧客対応に取り組んだ経験をテーマに選ぶと良いでしょう。
このように、志望企業の価値観や求めるスキルに関連するエピソードを選ぶことで、自分と企業との相性をアピールできます。
自分の強みや成果をアピールできる内容に絞る
ガクチカでは自分の強みや成果を明確にアピールできるエピソードを選ぶことが大切です。
採用担当者は応募者がどのような強みを持ち、それをどのように発揮してきたのかを知りたがっています。
そのため、自分のスキルや性格的な特徴が際立つエピソードを選び、それを具体的に説明することが評価につながります。
エピソードを選ぶ際には自分がどのように課題を認識し、行動を起こし、成果を出したのかを明確にすることがポイントです。
アルバイト経験をテーマにする場合「働いていた」という事実だけでは不十分です。
「新しいキャンペーンを提案し、実施した結果、売上が20%向上した」といった具体的な成果を示して、自分の行動の影響を伝えましょう。
【ガクチカの強いエピソード】ガクチカを作成する際のポイント
続いて、高い評価を得られるガクチカに共通する5つのポイントについて紹介します。
以下の5つのポイントが全て当てはまっているガクチカは高確率で企業の採用担当者から高い評価を得られます。
ぜひ作成時に念頭に置いて作成し、完成した後も以下の5つが当てはまっているかチェックポイントのように活用してみてください。
- 明確な課題を解決したエピソード
- チームワークやリーダーシップが発揮された場面
- 具体的な数字やデータを用いる
- 論理的な説明をする
- 他者に添削をしてもらっている
明確な課題を解決したエピソード
ガクチカにおいて、エピソードに明確な課題が含まれることは非常に重要です。
課題がはっきりしていることで、採用担当者は応募者が問題をどのように認識し、それに対してどのように取り組んだのかを具体的にイメージしやすくなります。
課題があいまいなエピソードでは行動や成果が評価されにくくなるため、まず最初にどのような問題があったのかを明確に伝えることが求められます。
エピソードに含まれる課題は個人的なものでもチーム全体のものでも構いません。
その課題に対して自分がどのように解決策を見出し、行動を起こしたのかを具体的に述べることがポイントです。
この際、自分の行動がどのように課題解決につながったのかを説明すると、説得力が増します。
チームワークやリーダーシップが発揮された場面
チームワークやリーダーシップを発揮した場面をエピソードに含めることで、協調性や主体性をアピールできます。
現代の企業では個人の成果だけでなく、チームでの成果を重視する傾向が強いため、チーム内でどのように貢献したのかを具体的に伝えることが評価につながります。
エピソードではまずチームの目的や目標を明確にすることが重要です。
サークル活動で文化祭のイベントを成功させることを目標にしていたならば、その目標に向けて自分が果たした役割を具体的に述べましょう。
リーダーとしてチーム全体をまとめた経験や、サポート役としてメンバーの意見を反映させた経験など、自分がどのように貢献したかを詳しく説明することが大切です。
具体的な数字やデータを用いる
ガクチカにおいて、エピソードに数字や具体的な結果を含めることは説得力を大きく高める要素です。
採用担当者は応募者の行動や成果を具体的にイメージしやすくなるため、エピソードがより印象的に映ります。
そのため、エピソード内では可能な限り数値を用いて結果を明確に示すことが求められます。
数字を含める際にはエピソード全体の流れと関連づけることが重要です。
「アルバイト先で接客の効率化を図る提案を行い、月間売上が15%向上した」といった具体例を挙げると、成果の大きさが分かりやすく伝わります。
また、結果に至るまでのプロセスを詳しく説明することも大切です。
「売上を向上させた」だけではなく「売上向上のために新しい販売手法を提案し、スタッフ全員と共有した」といった行動を具体的に述べることで、結果がどのように生まれたのかを採用担当者に伝えられます。
論理的な説明をする
ガクチカは論理的に説明することが重要です。
採用担当者が短時間で内容を理解し、あなたの強みや魅力をイメージできるように、エピソードを順序立てて整理しましょう。
その際には「PREP法」と呼ばれるフレームワークを活用するのがおすすめです。
PREP法とは、結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Point)の順で説明を展開する方法です。
たとえば、「私はアルバイトで売上管理を担当し、月間売上目標を達成しました」という結論から始め、「その理由は、売上データを分析して効果的な施策を導入したからです」と続けます。
そして「具体的には、商品の陳列を改善し、SNSを活用した集客を行いました」と詳細を述べ、最後に「この経験から、分析力と行動力を身につけました」と締めくくる形です。
このように構造化された説明を心がけることで、内容の理解度と説得力が大幅に向上します。
他者に添削をしてもらっている
また、ガクチカを作成する際には、他者に添削をしてもらうことが効果的です。
自分一人で完成させようとすると、主観的な表現や不明瞭な箇所に気づきにくくなるため、第三者の視点を取り入れることで文章の完成度が高まります。
添削を依頼する相手としては、キャリアセンターのアドバイザーや就職活動を経験した先輩、あるいは信頼できる友人が適しています。
さらに、最近ではAIを活用した添削ツールも登場しており、手軽に具体的なフィードバックを得られるため、忙しい就活生にとっては便利な選択肢となるでしょう。
添削では、表現の具体性や論理の一貫性、読みやすさを重点的に見直すことがポイントです。
論理的な説明と他者からのフィードバックを組み合わせることで、ガクチカの完成度を大幅に向上させることができます。
これらのポイントを押さえたうえで、自分の経験を魅力的に伝えられるガクチカを作成し、企業にしっかりとアピールしましょう。
【ガクチカの強いエピソード】ガクチカの構成
続いて、おすすめのガクチカの構成についても紹介します。
この構成を活用すれば、どのような業界・企業を受ける際でも、どのような経験を主題とする際でも起承転結がしっかりとしている、分かりやすい文章が出来上がります。
また、この構成を読んで、いまいち納得できない部分があれば、先ほど紹介した例文の部分に戻ってみてください。
どのようなことを言っているのかが、より深く理解できるはずです。
- 結論
- エピソード
- 得られた学び
- どう貢献できるか
結論
最初に結論として「私が学生時代に打ち込んだことは〇〇です。」と述べることで、採用担当者に話のテーマを明確に伝えることが重要です。
この部分は簡潔であるほど良く、話の全体像が一目でわかるように工夫する必要があります。
結論を明確に述べることで、聞き手にテーマの方向性を伝え、その後の説明にスムーズにつなげられます。
「私は学生時代にサークル活動を通じて大規模なイベントの企画運営に打ち込みました。」といった形で、具体的な内容に触れつつ、短く話しましょう。
エピソード
次に、具体的なエピソードを詳しく述べ、結論の根拠を示しましょう。
この段階では実際に取り組んだ活動や、それを通じて直面した課題や出来事について具体的に説明することが求められます。
数字やデータ、他人からの評価を活用すると、話に説得力が加わります。
サークル活動でイベントの企画運営を行った場合「100人規模の参加者を目指したイベントで、広報活動を強化するためにSNS広告を活用した」といった具体的な取り組みを述べると良いでしょう。
さらに、その結果として「予定を上回る150人の参加者を集められた」といった成果を数値で示すと、行動の結果が明確になります。
得られた学び
エピソードを通じて得た学びを述べることで、自分の成長や変化を伝えられます。
活動の結果だけを述べるのではなく、それを通じて自分がどのようなスキルや知識を身につけたのかを明確にすることが大切です。
「チームをまとめる経験を通じて、リーダーシップを発揮する際にはメンバー全員の意見を尊重しながら調整を図ることが重要だと学びました」といった形で、自分の成長を具体的に述べましょう。
さらに、その学びが今後のキャリアにどのように活かされるのかを説明することで、聞き手に自身の成長過程を理解してもらうことができます。
どう貢献できるか
最後に、得た学びや強みを入社後にどう活かせるかを述べ、話を締めくくりましょう。
ここでは自分が企業に対してどのように貢献できるかを具体的に述べることで、採用担当者に自分の価値をアピールすることが重要です。
「学生時代に培ったリーダーシップを活かし、貴社のチームプロジェクトでも円滑なコミュニケーションを図りながら成果を上げたいと考えています」といった形で、具体的なイメージを示しましょう。
さらに、企業が求めるスキルや価値観と自分の経験を結びつけることで、説得力が増します。
この部分では応募企業の事業内容や業務についてしっかりと理解し、それに沿ったアピールを行うことが大切です。
しっかり企業研究を行い、モチベーションの高さをアピールすることが、内定を得る近道です。
【ガクチカの強いエピソード】ガクチカで避けるべき注意点
続いて、ガクチカを作成する上で当てはまってしまうとマイナスな印象を与える可能性が高い例を紹介します。
もちろん、ガクチカを作成する上でも覚えておいて欲しいのですが、どちらかというと「完成した後に、当てはまってしまっていないか確認するため」に使って欲しい例です。
もし忘れそうならば、この記事をブックマークしておくか、以下の2つの項目だけでも自分のWordなどのメモにコピペして残しておいてください。
- 主観的で自己満足的な内容
- チームの成果を自分の成果として話す
- 結果だけをアピールしてしまう
- 専門用語を使用してしまう
- 嘘をついてしまう
主観的で自己満足的な内容
主観的かつ自己満足的な内容を述べると、採用担当者に対して自分の実力や成果を正確に伝えられません。
「頑張った」「努力した」といった抽象的な表現だけではどのような行動を取ったのか、どんな成果を出したのかが分かりません。
「アルバイトでとても頑張りました」と述べるだけでは具体的に何をしたのか、どのような状況で努力したのかが全く伝わりません。
そこで、実際に取り組んだ行動や課題を明確に示すことが必要です。
「売上向上を目指して顧客対応を改善し、月間売上を前年同月比で20%増加させました」というように、数字や具体的な結果を加えることで説得力が生まれます。
また、内容が自己満足に留まると、自分中心の視点しか持っていないと感じさせてしまいます。
エピソードを話す際には取り組んだ活動がどのように他者に影響を与えたのか、また自分がどう成長したのかを示すことが重要です。
チームの成果を自分の成果として話す
チーム全体の成果をあたかも自分1人の成果のように話すことも、避けるべき行動の1つです。
自分の具体的な貢献が見えないため、評価に結びつきにくくなります。
「サークルでの文化祭企画が大成功しました」と述べるだけでは、自分がその企画でどのような役割を果たしたのかが伝わりません。
企業はあなたを採用するのであり、サークル全員を採用するわけではないため、採用担当者が知りたいのはチームの成果そのものではなく、その中で自分がどのような貢献をしたのかという点です。
「文化祭企画でリーダーとして全体のスケジュール管理を担当し、メンバーの意見をまとめる役割を果たしました」というように、自分の役割や行動を具体的に述べることが必要です。
結果だけをアピールしてしまう
ガクチカでは、結果のみを強調してしまうと、取り組みの過程や自分の役割が十分に伝わらず、評価を下げる可能性があります。
どれだけ成果が優れていても、「具体的にどのように貢献したのか」「どんな課題を乗り越えたのか」が伝わらなければ、自己PRとしての説得力は弱まります。
例えば、部活動で「全国大会に出場した」と述べるだけでは、表面的な成果の紹介に留まってしまいます。
それに対して、「全国大会に出場するために、練習メニューを改善し、メンバーのモチベーションを高める工夫をした」と具体的な行動を加えれば、プロセスの中で得たスキルや人間性が伝わり、面接官にも印象深く残るでしょう。
結果ではなく、過程とその意義を丁寧に説明することが大切です。
専門用語を使用してしまう
ガクチカを説明する際、専門用語や業界用語を多用することは避けるべきです。
特に、志望先の業界に関連する内容であっても、採用担当者全員がその用語を理解しているとは限りません。
難解な言葉を使うことで、伝えたい内容が正確に伝わらず、論理性が損なわれる可能性があります。
例えば、「ゼミで○○法を活用してデータ分析を行いました」と述べる際も、具体的な内容や成果を説明することでわかりやすさを保つことが重要です。
「○○法を使い、消費者行動を分析しました。その結果、販売戦略の改善点を提案しました」というように、専門用語を補足しながら具体的な成果を伝えることで、相手の理解度が高まります。
ガクチカでは、誰にでもわかりやすい言葉選びを心がけましょう。
嘘をついてしまう
ガクチカを作成する際に、実際には経験していないことや誇張されたエピソードを盛り込むのは絶対に避けるべきです。
面接では、採用担当者が詳しく掘り下げて質問をしてくるため、嘘が露呈するリスクがあります。
一度でも嘘を疑われると信頼を失い、採用の可能性が大幅に下がります。
また、たとえ嘘がバレなかったとしても、入社後に求められるスキルや知識が不足していると、職場での活躍に支障が出る可能性があります。
本当に経験したことや学んだことを基にガクチカを作成し、自分自身の成長や成果を正直にアピールすることが、信頼を得る最善の方法です。
【ガクチカの強いエピソード】就活エージェントに相談しよう
この記事をここまで読んでくれた方のほとんどは、自分のガクチカがエピソードとして弱く「どうすればより強くできるか」「より良い印象を与えるには」どうすれば良いか、と悩みながら読んでくれたはずです。
そして、この記事を読んで悩みが解決した人もいれば、まだ解決しきっていない人も居るでしょう。
前者の方はESの添削の相手役として、後者の方は、まずは相談をするために就活エージェントに登録することを推奨します。
弊社が提供している「ジョブコミット」というサービスは、完全無料で就活の基本的な相談からESの添削、面接の相手役まで様々なサービスを提供しています。
就活のプロに徹底的に相談し、より質の高いガクチカを提出して内定を勝ち取るためにも、ぜひ以下のリンクから登録してみてください。
【ガクチカの強いエピソード】まとめ
この記事では「ガクチカで話せる、強いエピソードがない」と悩んでいる方のために、まず強いエピソードは必要なのか、エピソードを伝える際にはどのような工夫を凝らせば良いのかなどについて紹介しました。
記事中に伝えたように、ガクチカを作成するにあたっては、卓越した、輝かしい経験がなければならないわけではありません。
平凡に思えるガクチカしかなくても、工夫次第で十分あなたの魅力が伝わる回答を作成することはできるため、本記事を参考に質の高い回答を作成し、内定を勝ち取ってください。















_720x550.webp)