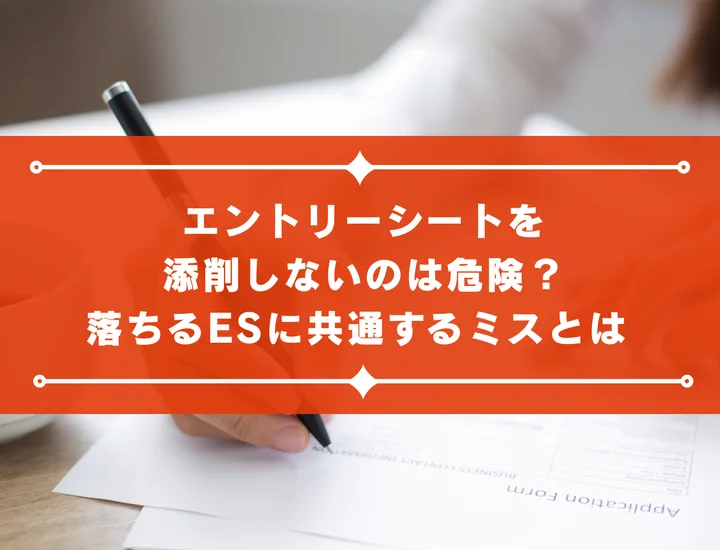明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
- 小売業界とは
- 小売業界の仕事内容
- 小売業界の課題
- 小売業界に向いている人/向いていない人
- 小売業界に興味のある人
- 小売業界の課題を知りたい人
- 自分が小売業界に向いているか知りたい人
- 業界研究中の人
はじめに
就活の成功には業界の特徴や強みだけでなく、課題を理解する必要もあります。
そこで、今回は小売業界全体について紹介しつつ、どのような課題が存在するのかに焦点を当てて詳しく紹介します。
小売業界に興味を持ち始めた段階の方はもちろんのこと、小売業界の研究を進めている方の参考にもなる記事であるため、ぜひ活用してみてください。
小売業界とは
小売業界は皆さんご存知の通り、商品を消費者に直接販売する業界であり、日常生活に密接に関わる重要な産業です。
スーパーマーケットやコンビニ、百貨店、アパレルショップ、家電量販店など、多種多様な業態が存在します。
また、特に最近ではECの拡大により、オンラインと実店舗を組み合わせた新しい販売戦略が進められているのも特徴の1つです。
消費者のニーズに迅速に対応しながら商品を効率的に提供することが、小売業界の役割であると言えるでしょう。
以下の記事では小売業界についてさらに詳しく紹介しているため、企業研究がまだ進んでいない方や、より小売業界について掘り下げたいと考えている方は確認してみてください。

【小売業界】代表的な企業
続いて、小売業界における代表的な企業を3つ紹介します。
日本の小売業界には様々な企業が存在しますが、特に業界を代表するのはニトリ、イオン、そしてセブン&アイ・ホールディングスであると言えるでしょう。
これらの企業はいずれもデジタル技術の活用やサステナビリティへの取り組みを強化し、時代の変化に適応しながら成長を続けています。
ぜひ、それぞれどのような特徴があるのか、どのような取り組みをしているのかについて、確認してみてください。
- ニトリ
- イオン
- セブン&アイ・ホールディングス
ニトリ
マイナビによる調査によると、2023年・2024年と2年連続でニトリが文系の就職人気ランキング1位に選ばれました。
2位のみずほファイナンシャルグループに2倍近い大差をつけており、安定していることや業界で上位であること、将来性が高いことを挙げる人が多く、働きやすさや安定性が評価されたと言えるでしょう。
また、総合職社員が転勤を伴わず働ける新たな勤務制度を採用しており、2024年の春には新卒の基本給を大卒で1万5,000円引き上げ、月給を最大31万円とするなど、社員の待遇改善に力を入れたのが要因であると考えられます。
イオン
イオンも日本最大級の企業の1つであり、スーパーマーケットやショッピングモールなど多様な業態を展開しています。
また、最新技術の活用に積極的で、国や自治体と連携しながら先進的なサービスを導入していることに、魅力を感じる就活生が多いです。
レジの自動化やAIを活用した品揃えの最適化など、デジタル技術を取り入れることで、働く側にとってもお客様側にとっても便利なサービスを提供しています。
また、千葉市と協力し、ドローンを活用した配送の実証実験に参加するなど、さらなる技術革新に力を入れている点が将来性の高さを感じさせ、多くの就活生から人気を獲得している理由と言えるでしょう。
セブン&アイ・ホールディングス
ングスはセブン&アイ・ホールディ日本を代表する総合流通企業であり、コンビニ業界ナンバーワンのシェアを誇るセブン-イレブンを中心に事業展開しています。
最近ではプライベートブランド商品の開発に力を入れており「セブンプレミアム」シリーズは高品質でありながら手頃な価格で、多くの消費者に支持されています。
また、コンビニ事業だけでなく、イトーヨーカドーやそごう・西武などの百貨店事業も手掛けており、幅広い業態で展開していることも魅力です。
また、技術を活用したサービスやキャッシュレス決済の導入も進めているのも、利便性を高め、多くの消費者から指示を得ている理由であると考えられます。
【小売業界】小売業界の仕事内容
続いて、小売業界の仕事内容について紹介します。
小売業界と言っても様々な職種があり、代表的なものは以下の7つです。
自分にはどの職種が向いているのか、新卒として企業に応募する際はどの職種を担当したいかを考えながら読んでみてください。
・販売
・店舗経営
・バイヤー
・店舗開発
・商品開発
・マーケティング
・物流管理
販売
販売の仕事は店頭でお客様に直接商品を提供する、つまり小売業界の最前線で消費者と接する重要な業務です。
接客、レジ対応、品出し、売り場の整理などがあり、皆さんが想像する小売店の店員の仕事そのものと考えて良いでしょう。
また、商品を販売するだけでなく、お客様の要望を聞きながら適切な商品を提案して満足度を高めることも重要な仕事の1つです。
多くの企業では新入社員の方はまず販売業務からスタートします。
現場での経験を積むことで、商品知識や顧客対応のスキルを身につけ、消費者のニーズを深く理解できるようになるからです。
店舗経営
店舗運営の仕事は店舗全体の運営を管理し、売上向上やスタッフのマネジメントを行うことが主な業務になります。
店長やマネージャーなどと呼ばれることが多く、販売業務だけでなく、売上の管理、在庫管理、シフト作成、スタッフの教育など、様々な業務を任されます。
また、店舗の売上目標を達成するために販売促進策を考えたり、顧客満足度を高める施策を実施したりすることも役割の1つです。
実績を積むことで、より大きな店舗の運営を任されたり、エリアマネージャーとして複数の店舗を統括する立場に昇進したりすることも可能です。
近年ではECサイトと実店舗を連携させる「オムニチャネル戦略」が進んでおり、データを活用した店舗運営が求められるようにもなっています。
バイヤー
バイヤーは消費者のニーズや市場の動向を入念に分析した上で、店頭に並ぶ商品を選定し、仕入れる役割を担います。
メーカーや卸売業者と交渉を行い、価格や納期を決定するため、交渉力や市場分析力が求められる職種と言えます。
また、自社ブランドやターゲット層に合わせた商品を選ぶことが重要であり、消費者のトレンドを常に把握しながら、最適な商品ラインナップを構築することが必須です。
売上に直結する非常に重要な職種であり、仕入れた商品の売れ行きによって企業の業績を左右することもあります。
そのため、価格交渉や在庫管理はもちろん、市場の変化に柔軟に対応することが求められます。
責任重大ではありますが、その分やりがいも大きい仕事であると言えるでしょう。
店舗開発
店舗開発の仕事はどこにどのような店舗を建てるのかを企画・実行することが主な業務です。
新規出店の際には立地選定が非常に重要であり、候補地の周辺環境や競合情報、ターゲットとする顧客のニーズを分析した上で、最適な場所を決定しなければなりません。
ファミリー層向けのスーパーであれば住宅街の近くが良いですし、ビジネスパーソン向けのコンビニであればオフィス街の中心部など、それぞれの業態に適した立地戦略が求められます。
また、店舗開発は場所を選ぶだけでなく、出店後の収益を最大化するための計画も重要です。
家賃や建築コスト、集客効果などを考慮し、費用対効果を見極めながら経営視点で戦略を立てる必要があります。
商品開発
商品開発は消費者のニーズを理解した上で売れる商品を企画・開発する仕事です。
特に近年では多くの企業がプライベートブランドを立ち上げています。
イオンの「トップバリュ」商品などはその代表格と言えるでしょう。
プライベートブランド商品はメーカー品に比べてコストを抑えつつ、自社のブランド価値を高めることができるため、特に力を入れて開発されています。
商品開発においては市場調査や消費者アンケートを基にニーズを分析し、コンセプトを設定することが大切です。
その後、試作品を作成し、価格やパッケージデザインを決定しながら最終的な商品を完成させます。
また、トレンドを取り入れることも重要であり、健康志向やエコ志向など、社会的な動向を反映させた商品開発が求められます。
マーケティング
マーケティングの仕事は商品の売上を最大化するための広告やイベントの企画を行い、消費者に質の高いアプローチを行うことが主な役割です。
競合他社の動向や市場トレンドを分析し、ターゲットに適した販売戦略を立案することも求められます。
SNSを活用したプロモーション、ポイントキャンペーンの実施、季節ごとの特別セールなど、様々な手法を駆使して売上を伸ばします。
また、店舗の売り場レイアウトやポップ広告の工夫もマーケティングの1つです。
消費者の購買行動を分析し、より魅力的な売り場を作ることで購買意欲を高めることが求められます。
最近では特にデジタルマーケティングの重要性が高まっており、オンラインとオフラインを組み合わせた戦略も増えています。
物流管理
物流管理は商品の流通を円滑にするための在庫管理や配送計画を担当する仕事です。
小売業界では適切なタイミングで必要な商品を供給することが重要であり、売上データを基に最適な仕入れ量を決定する必要があります。
在庫が足りないと機会損失につながりますし、反対に、余らせてしまうとロスにつながってしまいます。
需要が高まる季節商品や新商品は多めに在庫を確保し、売上が不透明なものは過剰在庫にならないように調整するなど、工夫が必須です。
また、商品の配送効率を上げることも重要な課題の1つです。
倉庫から店舗への配送ルートを最適化し、無駄なコストを削減することで経営の効率化にもつながります。
小売業界の課題
続いて、小売業界にはどのような課題が存在するのかについても紹介します。
この課題は将来、小売業界に就職した後に直面する可能性が高いため、覚えておきたいところです。
また、下記のような話題は、将来直面した際はどのように対策・解決するのか、面接で聞かれることもあります。
しっかりと答えられるようになっておくためにも、確認しておいてください。
・人手不足
・消費者ニーズへの対応
・実店舗の価値低下
人材不足
想像がつく方も多いでしょうが、小売業界では特に店舗スタッフや物流に従事するスタッフの確保が深刻な課題となっています。
コンビニやスーパーマーケットの業態では長時間労働や低賃金が理由で求職者が集まりにくく、人手不足が慢性化しているのです。
また、EC市場の拡大に伴い、倉庫作業員や配送ドライバーの需要も急増していますが、人材の確保が追いついていない状況です。
この問題を解決するために、セルフレジや自動発注システム、ロボットを活用した店舗運営など、デジタル技術を活用した人件費削減の取り組みも進められていますが、それでもやはり人手が追いついていないのが現状と言えます。
消費者ニーズへの対応
消費者の購買行動が多様化し、小売業界ではただ良い商品を提供するだけでは競争に勝てなくなっています。
ECの拡大により、オンライン注文と店舗受け取りサービスを導入する企業が増えており、実店舗とデジタルを融合させた新しい販売手法が求められているのです。
また、エコ意識の高まりを受け、オーガニック商品やフェアトレード商品など、環境や社会に配慮した商品を展開する動きも加速しています。
さらに、高齢化社会の進行により、高齢者の利便性を考慮したサービスが重要です。
移動販売や宅配サービスの拡充、キャッシュレス決済の導入など、高齢者でも利用しやすい購買環境を整えることが求められています。
実店舗の価値低下
インターネットの普及により、消費者が実店舗で商品を確認し、オンラインで購入する「ショールーミング化」が進んでいます。
特に家電量販店やアパレル業界では価格比較が容易なネット通販に顧客が流れやすく、実店舗の売上が減少する傾向にあります。
「せっかく接客をして、購入してもらえると思ったのに、最終的にはオンラインで買われてしまう」というケースも珍しくありません。
そこで、リアル店舗の価値を高める工夫が求められています。
一部の家電量販店では商品の実演や使用体験ができるスペースを設け、来店のメリットを強調しています。
試着後にオンラインで購入できるサービスを導入し、実店舗とECの相互送客を図る企業も多いです。
小売業界に向いている人の特徴
続いて、小売業界に向いている人の特徴について紹介します。
いくら小売業界に魅力を感じ、就職を熱望していても、向いていなければ仕事を続けるのは難しくなります。
自分が以下の3つの特徴に当てはまるか、確認してみてください。
・人と関わることが好きな人
・トレンドに敏感な人
・商品の知識を活かしたい人
人と関わることが好きな人
小売業界で働くにあたっては、どの職種でも人との関わりが重要になります。
販売職であれば顧客対応はメインの仕事ですし、店舗経営ではスタッフとのコミュニケーションが欠かせません。
バイヤーやマーケティング担当者も、メーカーや物流業者とやり取りしながら業務を進めるため、円滑な意思疎通が必要です。
特に顧客対応においてはただ商品を販売して終わりではなく、相手のニーズを引き出し、最適な提案をするスキルが求められます。
また、クレーム対応などの場面では冷静かつ丁寧な対応をすることで、お客様を落ち着かせ、円満に解決する力も重要です。
トレンドに敏感な人
消費者のニーズは目まぐるしく変化しており、小売業界では新しいトレンドをいち早くキャッチし、それに対応した商品やサービスを提供することが欠かせません。
特にアパレル、食品、家電などの分野は流行を取り入れた商品展開が売上に大きな影響を与えるため、業界の最新情報にアンテナを張ることが重要です。
SNSや口コミの影響力が非常に強い時代においては、消費者がどのような情報に関心を持っているか分析し、それを販売戦略に活かすことも求められています。
小売業界で活躍するためには日頃からニュースやSNSをチェックする習慣を持ち、消費者の動向を敏感に把握する人こそ、求められていると言えるでしょう。
商品の知識を活かしたい人
小売業界では自分が扱う商品への深い知識が大きな強みになります。
例えば、家電量販店であれば製品のスペックを理解すること、アパレル業界であれば素材やコーディネートの知識が接客に役立ちます。
商品に対する深い理解があれば顧客の質問にも自信を持って対応でき、より良い提案ができるようになるでしょう。
また、バイヤーや商品開発職においても、商品知識があれば市場のニーズに合った商品を選定・企画できます。
特定の分野に興味があり、商品について学ぶことが好きな人ならば、小売業界に向いている可能性は高いと言えるでしょう。
小売業界に向いていない人の特徴
一方で、小売業界に向いていない人の特徴についても紹介します。
このような「〇〇業界に向いていない人の特徴」は多くの場合「向いている特徴」の裏を返せば判断できることが多いです。
しかし、小売業界の場合は、先ほど紹介した「向いている人の特徴3つ」が当てはまっていたとしても、向いていない可能性があります。
向いていない人の特徴についても、しっかり確認しておいてください。
・土日祝日は休みたい人
・定時で帰りたい人
・様々な業界を経験してみたい人
土日祝日は休みたい人
小売業界では土日祝日や年末年始、ゴールデンウィークの繁忙期にこそ多くの顧客が訪れるため、休みを取ることが基本的にできません。
販売職や店舗運営に関わる仕事はシフト制での勤務が基本となるため、平日に休みを取ることが多いです。
企業によってはシフトの調整や有給休暇の取得を推奨するところもありますし、繁忙期に休みを取ることができる場合もありますが、基本的には難しいと考えておいた方が良いでしょう。
よって、週末の予定を優先したい方や家族との時間を優先したい方は、別の業界を目指した方が良いかもしれません。
定時で帰りたい人
小売業界では営業時間が長いことに加え、閉店後の売上集計や翌日の準備、在庫管理などの業務が発生するため、定時で帰るのはなかなか難しいです。
特に店舗勤務の場合、接客業務だけでなく、発注作業やレジ締め、棚卸しなどの業務があり、残業が発生しやすい傾向にあります。
特に閉店間際に店舗が混んでしまった場合は長時間の残業が発生することも少なくありません。
また、繁忙期やセール期間中は通常業務に加えて品出しや販促活動も増え、業務量が増大します。
もちろん、近年は労働環境の改善が進み、残業を減らすための施策を導入する企業は増えています。
しかし、業界の特性上、突発的な業務が発生することがあることは覚えておきましょう。
様々な業界を経験してみたい人
小売業界は他の業界と比べて転職がしにくい傾向にあるため、いつかは他の業種へ転職しようと考えている人には向いていない可能性が高いです。
販売や店舗運営の経験は小売業界内でのキャリアアップには有利ですが、専門性が限定されやすく、異業種への転職ではアピールポイントになりにくいのです。
営業職やマーケティング職ならば転職は可能ですが、販売職や店舗運営の経験が中心の場合、異業界への転職を目指す際には、相当な努力が必要とされるでしょう。
また、小売業界ではキャリアを積みながらマネジメント職への昇進を目指すケースが多く、短期間での転職を繰り返すと評価が下がる可能性が高いです。
小売業界で求められるスキル
続いて、小売業界で求められるスキルについて紹介します。
もちろん、職種別に紹介するならば、他に求められるスキルがあるのですが、小売業界で働くにあたって、どのような職種でも必須のスキルは以下の2つです。
それぞれ、自分に当てはまっているか確認してみてください。
・柔軟性
・コミュニケーションスキル
柔軟性
小売業界では季節ごとのイベント、セール、曜日ごとの来客数の変動などに応じて、販売戦略や業務内容が変化するため、柔軟に対応する能力が必須です。
年末年始、クリスマス、夏のバーゲンシーズン、ブラックフライデーなどの繁忙期には通常時とは異なる売り場作りや接客対応が必要になります。
また、天候や社会情勢によって消費者の購買行動が大きく変わるため、状況に応じた適切な判断を下せるかどうかも重要です。
さらに、ECの普及やキャッシュレス決済の導入など、小売業界全体の環境も急速に変化しています。
最近はデジタル技術の進化により実店舗とオンラインを組み合わせた販売手法なども増えており、新たなツールやシステムに順応できる能力も欠かせません。
コミュニケーションスキル
小売業界で最も重要なスキルの1つが、コミュニケーションスキルです。
販売職であれば、お客様に対して商品の魅力を伝え、購入を後押しすることはもちろん、クレーム対応や問い合わせ対応の際にも適切な対応が必要です。
また、小売業界では社内外の様々な関係者とやり取りをする機会が多く、接客以外の場面でも円滑な意思疎通が求められます。
店舗スタッフ同士で業務を分担する際やメーカーや卸売業者と商品の仕入れ交渉を行う際にも、相手の意向を正しく理解し、的確に伝える能力が欠かせません。
マーケティング担当者であれば、多くの取引先と関わる機会が多く、論理的に説明し交渉を進める能力が必要不可欠です。
このように、どの職種においてもコミュニケーションスキルは必須であると言えます。
小売業界で実際に働くには
小売業界への内定を獲得するためにはどのような対策を行うべきかについても紹介します。
以下の手順でしっかりと準備を進めれば、自分に足りていない点を把握し、エントリーシートや面接での回答の質を向上させられます。
ぜひ、この順番で取り組んでみてください。
・自己分析
・業界分析
・企業分析
自己分析
小売業界への内定を得るためにはまず自己分析を行い、自分の強みや適性を明確にすることが重要です。
自己分析が不十分なまま就職活動を進めると、自分に合わない企業を選んでしまう可能性もあります。
特に、小売業界には接客業務が中心となる企業もあれば、バイヤーやマーケティング職など、裏方の業務に力を入れている企業もあります。
自分がどのような環境で働きたいのか、どの職種に興味があるのかを明確にしてから、企業を選ぶことが大切です。
また、小売業界は消費者と直接関わる機会が多いため、「人と接することが好きか」「流行に敏感か」「柔軟に対応できるか」といった要素も重要になります。
自己分析の方法については以下の記事で詳しく紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
業界分析
自己分析が終わったら、続いて業界を分析することが大切です。
小売業界は実店舗とECの融合、キャッシュレス決済の普及、人材不足への対応など、大きな変化の中にあります。
実店舗の売上が伸び悩む中、OMO(オンラインとオフラインの融合)戦略を取り入れる企業が増えており、オンラインとオフラインの連携が重要視されているのです。
また、消費者のニーズが多様化しているため、個別対応型のサービスや、サブスクリプション型ビジネスの導入も進んでいる点もポイントです。
こうした業界の動向を把握することで、企業ごとの戦略を比較しやすくなり、選考の際に説得力のある志望動機を作成することが可能になります。
以下の記事では業界研究ノートの活用方法やメリット、おすすめのテンプレートについても紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
企業分析
業界分析が終わったら、次に自分が志望する企業を詳しく分析しましょう。
企業ごとに扱う商品やビジネスモデルは大きく異なるため、自分に合った企業を見つけるには丁寧な企業分析が欠かせません。
同じアパレル業界でも、ユニクロのようなファストファッションを展開する企業と、高級ブランドを扱う企業では働き方や求められるスキルが違います。
企業ごとの社風や働き方を考慮し、自分の価値観に合う企業を選びましょう。
また、企業が求める人物像を理解することで、志望動機や自己PRをより魅力的に作成できるようにもなります。
以下の記事では企業分析の詳しい方法や、企業研究ノートの作り方、テンプレートの配布も行っているため、気になる方は参考にしてみてください。
小売業界についてもっと詳しく知りたい時は
ここまで小売業界について詳しく紹介しつつ、どのような課題があるのかについても解説しましたが、より深く業界研究を行いたい方は就活エージェントを利用することを推奨します。
忙しい大学生の方は1人でES作成、面接対策、業界研究をすべて完璧に行うことは難しいです。
そこで、就活のプロに相談しながらスムーズに進めることを推奨します。
弊社の「ジョブコミット」というサービスは完全無料で利用でき、おすすめ企業や非公開求人などの紹介も行っているため、気になる方は以下のリンクから登録してみてください。
まとめ
今回は小売業界について詳しく紹介しつつ、小売業界にはどのような課題があるのか、解決するためにはどのような対策が必要なのかについて紹介しました。
小売業界は日々変化する消費者のニーズに対応しながら、より良い商品とサービスを提供することを目指す、やりがいのある業界です。
働くためには接客スキルや販売スキル、マーケティングスキルなどを身につけ、エントリーシートや面接で的確にアピールすることが重要になります。
ぜひ、本記事で紹介した求められるスキルや対策を理解した上で、自分の魅力を最大限にアピールし、内定を勝ち取ってください。