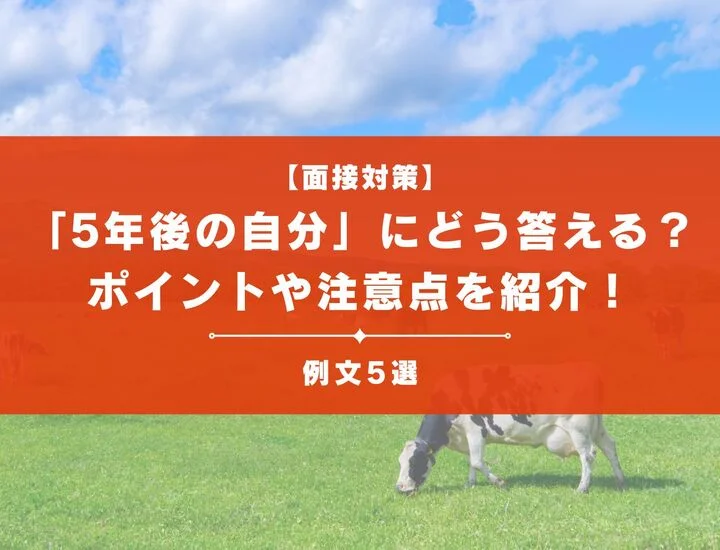明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・アルバイト経験をガクチカにする方法
・アルバイト経験でアピールできる力
・アルバイト経験のガクチカの参考例文
・アルバイト経験をガクチカにしたい人
・ガクチカの構成が不安な人
・例文を参考にアルバイト経験でガクチカを作りたい人
【グループディスカッション役割診断】向いている役割を理解することはとても大切
グループディスカッションは、学生の普段の人柄や、コミュニケーション能力をみることができるので、選考に利用している企業が多いです。
グループディスカッションでは、自分に向いている役割で挑むことが何よりも大切です。
自分に向いていない役割でグループディスカッションを行ってしまうと、本領発揮できずに、選考で落とされる可能性が非常に高いです。
自分の性格に向いている役割と絶対にやらない方がいい役割を把握して、グループディスカッションに臨みましょう。
【グループディスカッション役割診断】グループディスカッションの役割診断とは?
性格診断を利用してグループディスカッションの向いている役割や、立ち回りのポイントが診断できるツールが存在します。
役割診断は学生が慣れ親しんだもので診断できるのでおすすめです。
グループディスカッションの対策はまず役割診断を行って、自分の適正を把握することから始めましょう。
【グループディスカッション役割診断】おすすめの役割診断ツール
- グルディスの役割診断
- GD役割診断
グループディスカッションの役割診断ツールはいくつか存在しますが、ここでは特におすすめの役割診断ツールを2つご紹介します。
グルディスの役割診断
ベンチャー就活ナビ監修の「グルディスの役割診断」では、20問の質問に答えるだけで自分の性格タイプがわかり、グループディスカッションで向いている役割と向いていない役割、立ち回りのポイントが診断できます。
下のボタンから利用できます。
GD役割診断
digmediaが運営する「GD役割診断」は、LINEでグループディスカッションの役割診断ができます。
グループディスカッションの役割だけでなく、おすすめの業界や職種など、就活系の診断が同時にできることもポイントです。
下のボタンから利用できます。
【グループディスカッション役割診断】性格別!おすすめの役割
- リーダー
- タイムキーパー
- 書記
- アイデアマン
グループディスカッションでは、それぞれの性格や得意分野に応じた役割を担うことで、より効果的に議論へ貢献できます。
自分に合ったポジションを見つけ、無理のない形で参加することが重要です。
ここでは、代表的な役割ごとに向いている人の特徴と、その役割を上手にこなすためのポイントを紹介します。
リーダー
グループディスカッションのリーダーは、議論の進行をまとめる役割です。
全員が議論に参加できているか、議論がまとまった方向に進んでいるかを適宜確認することが大切です。
向いている人
リーダーに向いているのは、周囲に気を配りながら議論を前に進めることができる人です。
自分の意見を押しつけるのではなく、チーム全体をまとめ、円滑に議論を進める力が求められます。
判断力があり、必要な場面では決断できる人が適任です。
ポイント
リーダーとして議論を進めるためには、まずは自分から率先して行動することが大切です。
最初に自己紹介を行い、メンバーにも紹介を促すことで、場を和ませつつ自然に主導権を握ることができます。
また、議論の前提条件を明確にすることも重要です。
テーマが曖昧なまま進行すると、意見が散漫になりやすいため、最初にチーム内で共通認識を持つようにしましょう。
議論の中で出た意見に対しては、否定ではなく前向きな形で対応することを意識します。
タイムキーパー
グループディスカッションのタイムキーパーは、議論が決まった時間配分で進んでいるかを確認し、チームに経過時間を伝える役割です。
経過時間を見逃してしまうと致命傷になってしまう大切な役割です。
向いている人
タイムキーパーは、議論の流れを把握しながら適切に時間配分ができる人に向いています。
話すのが得意でなくても、全体の進行を管理し、的確なタイミングで声をかけられる人に適した役割です。
ポイント
タイムキーパーの役割は単に残り時間を伝えるだけではありません。
議論が円滑に進むように、最初に全体の時間配分を決め、適宜メンバーにリマインドを行うことが重要です。
また、時間には必ず余裕を持たせ、議論がまとまらない場合のために調整できる時間を確保しておくことが大切です。
最後に焦って結論を急ぐことがないよう、タイムキーパーとして柔軟に時間を管理しましょう。
書記
グループディスカッションの書記は、議論ででた意見やまとまった意見を記録しておく係です。
最後のまとめや発表では書記の記録をもとに進めるのでポイントを押さえて記録することが大切です。
向いている人
書記に向いているのは、情報を整理するのが得意で、話の流れを把握する力がある人です。
発言が得意でなくても、冷静に議論を記録し、要所で意見を整理できる人に適しています。
ポイント
ただメモを取るだけでなく、議論が進む中で要点を明確にし、必要に応じて参加者へフィードバックを行うことが求められます。
「今の話はこういう理解で合っていますか?」と確認することで、議論の方向性を整理し、チーム全体が共通認識を持てるようにしましょう。
また、記録は発表の際に使われることが多いので、誰が見ても分かりやすい形でまとめることが重要です。
要点を簡潔に整理し、発表者がスムーズに話せるように工夫しましょう。
アイデアマン
グループディスカッションのアイデアマンは、名前の通りアイデアをどんどん出していく役割です。
様々な視点からアイデアを出すことがポイントです。
向いている人
アイデアマンに向いているのは、発言することに抵抗がなく、新しい視点を持っている人です。
論理的な整合性よりも、まずは自由に発想し、多様な意見を出すことが求められます。
ポイント
アイデアを出す際には、単に思いついたことを言うのではなく、他のメンバーの意見を踏まえた上で発言することが大切です。
また、意見を出すことに躊躇しない姿勢も大切です。
最初の段階では、間違いを恐れずに多くのアイデアを出し、議論を活性化させることが役割となります。
話が進むにつれて、現実的な視点を加えながら意見を整理していくことで、より深みのある議論につなげることができます。
【グループディスカッション役割診断】グループディスカッションの基本的な流れ
- 自己紹介をする
- 役割を決める
- グループディスカッションを始める
スムーズにグループディスカッションを進めるためには、自己紹介、役割決め、議論の開始という基本的な流れを理解し、適切に対応することが大切です。
ここでは、それぞれのステップについて詳しく解説していきます。
自己紹介をする
グループディスカッションは、初対面のメンバーと協力して進めるため、最初の自己紹介が重要な役割を果たします。
この段階で、自分の性格や得意分野を簡潔に伝えることで、後の役割決めがスムーズになります。
自己紹介では、名前、大学・学部、得意分野、グループディスカッションへの意気込みなどを簡潔に伝えます。
また、他のメンバーの自己紹介にも注意を払い、それぞれの得意分野を把握することが重要です。
誰がどのような役割に向いていそうかを意識しながら聞くことで、役割決めの際に適切な提案がしやすくなります。
役割を決める
自己紹介が終わったら、次にグループ内での役割を決める段階に入ります。
役割を明確にすることで、議論がスムーズに進み、全員が効果的に貢献しやすくなります。
人気のある役割に希望者が集中した場合は、話し合いで決めるか、公平性を保つためにじゃんけんや多数決を活用するのも一つの方法です。
一方で、希望者がいない役割がある場合は、チームのために積極的に引き受ける姿勢を見せることが評価につながります。
無理にリーダーシップを取ろうとせず、自分の強みを活かせるポジションを選ぶことが重要です。
役割について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
グループディスカッションを始める
役割が決まったら、いよいよグループディスカッションが始まります。
まず、議論の方向性を決めるために、与えられたテーマについて全員で認識を統一することが大切です。
議論中は、ただ発言するだけでなく、他のメンバーの意見をよく聞き、それを踏まえた発言をすることが評価につながります。
最終的に、チームの結論がまとまったら、発表者がそれを整理し、発表の準備を進めます。
発表者は、単に結論を述べるだけでなく、議論の流れや根拠を分かりやすく伝えることが求められます。
質疑応答にも対応できるように、発表前にチーム全員で補足情報を確認することも重要です。
【グループディスカッション役割診断】役割決めで起こるトラブル
- 役割が決まらない
- 苦手な役割にされた
役割決めの段階で意見がまとまらず、議論が停滞することもあります。
また、自分が希望しない役割を任されてしまい、戸惑うこともあるでしょう。
こうしたトラブルが発生した場合でも、冷静に対処することで、チームの雰囲気を壊さずに進行することが可能です。
ここでは、役割決めでよくある二つのトラブルとその対処法について解説します。
役割が決まらない
役割がなかなか決まらない原因としては、メンバーが遠慮して立候補をためらったり、全員が同じ役割を希望して譲らなかったりするケースが挙げられます。
こうした状況が続くと、貴重な議論の時間が削られ、チームとしての印象が悪くなってしまいます。
このような場合、誰かが率先して話を進めることが必要です。
また、どうしても決まらない場合は、じゃんけんや多数決など公平な方法を取り入れるのも一つの手段です。
役割を巡る争いが長引くよりも、迅速に決定し、本来の目的である議論に集中することが何よりも重要です。
役割そのものに優劣はなく、それぞれの役割がチームの成功に貢献するものであることを理解し、柔軟に対応する姿勢を持ちましょう。
苦手な役割にされた
自分が希望していなかった役割を任されることも、グループディスカッションではよくあるトラブルの一つです。
特に、発言が苦手な人がファシリテーターを任されたり、人前で話すのが得意でない人が発表者になったりすると、不安を感じることがあるでしょう。
こうした場合、最も重要なのは、まず前向きに取り組む姿勢を見せることです。
「得意ではないですが、挑戦してみます」と意欲的な態度を示すことで、成長意欲や柔軟性を評価される可能性があります。
また、苦手な部分を補うために、チームメンバーに助けを求めるのも良い方法です。
【グループディスカッション役割診断】役割に関係なく意識したいポイント
- 発言と傾聴のバランスを意識する
- 協調性とリーダーシップを両立する
- 非言語のコミュニケーションを意識する
グループディスカッションでは、それぞれの役割が重要ですが、役割にとらわれすぎるのは逆効果です。
自分の役割を果たすだけでなく、議論全体にどのように貢献できるかを意識することが、評価を高めるポイントになります。
どのポジションであっても、発言の仕方や態度、コミュニケーションの取り方が評価につながります。
ここでは、どの役割を担っていても意識すべき3つのポイントを紹介します。
発言と傾聴のバランスを意識する
グループディスカッションでは、自分の意見をしっかり述べることが大切ですが、一方的に話すだけでは高評価にはつながりません。
他のメンバーの意見に耳を傾け、内容を理解した上で発言することで、議論の質が高まります。
また、ただ頷くだけでなく、「なるほど、それは面白い視点ですね」「〇〇さんの意見をもう少し詳しく聞かせてもらえますか?」といった言葉を添えると、相手の発言を尊重していることが伝わり、良好なコミュニケーションが生まれます。
発言の機会を作りつつ、傾聴の姿勢を示すことで、グループ全体の雰囲気を良くし、評価を高めることができるでしょう。
協調性とリーダーシップを両立する
グループディスカッションでは、チームワークが重視されるため、協調性は不可欠です。
しかし、ただ周囲に合わせるだけでは、自分の意見を持っていないと判断される可能性があります。
そこで重要なのが、協調性を保ちつつ、必要な場面ではリーダーシップを発揮することです。
リーダーシップは、必ずしもファシリテーターや発表者だけが発揮するものではありません。
どの役割でも、チームのために積極的に動き、適切な発言をすることで、協調性とリーダーシップのバランスを取ることができるでしょう。
非言語のコミュニケーションを意識する
グループディスカッションでは、発言内容だけでなく、態度や表情も評価の対象となります。
適切な非言語コミュニケーションを意識することで、チームの雰囲気を良くし、議論を円滑に進めることができます。
例えば、発言者の方をしっかり向き、頷きながら聞くことで、話を真剣に受け止めていることを示すことができます。
逆に、腕を組んだり、無表情でいたりすると、消極的な印象を与えてしまう可能性があります。
また、発言の際には相手の目を見て話し、ジェスチャーを交えながら説明すると、説得力が増します。
非言語のコミュニケーションは、意識するだけで大きな違いを生みます。
細かい部分まで気を配り、良い印象を残せるように心がけましょう。
まとめ
この記事では、グループディスカッションの役割診断の方法や、おすすめのツール、各役割の意識すべきポイントについて解説しました。
グループディスカッションに挑む前には必ず役割診断を行って、自分に向いている役割を把握しておきましょう。



.webp)