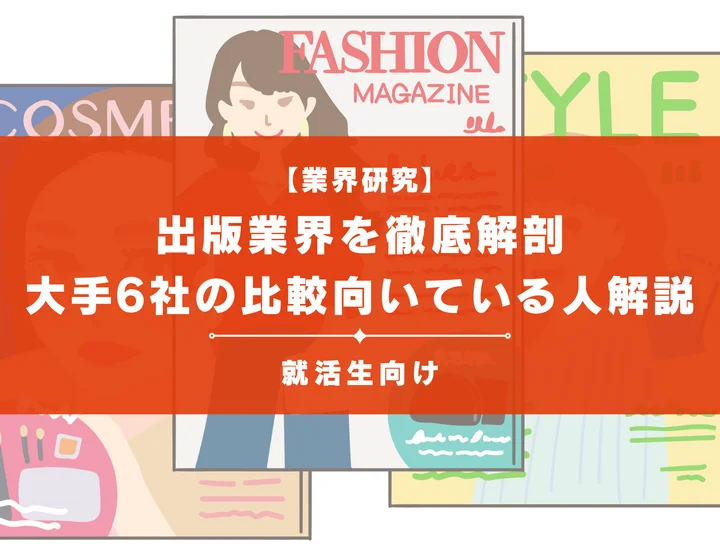はじめに
新卒で早速、経理職として働きたいと考えている方は多いでしょうが、検索してみると「難しい」とサジェストに出てくることが多いです。
そこで今回は新卒で経理職を目指している方のために、なぜ難しいのか、どうすれば新卒からいきなり経理職として働ける可能性を高められるのかについて詳しく紹介するので、参考にしてみてください。
【新卒に経理は難しい】経理ってどんな仕事?簡単解説
まずは経理はどのような仕事なのかについて、簡単に紹介します。
主に以下の5つの業務を担当することになり、また、その他諸々細かい業務を任されることもあります。
業務の全体像を把握するために、それぞれ確認しておいてください。
①仕訳業務
仕訳業務とは業務で発生する様々な勘定を仕分けする仕事です。
商品を売った時の売り上げや従業員に給料を支払った時の支出、備品を購入した際の費用など、お金が動く出来事を全て記録します。
取引の内容を「勘定科目」と呼ばれる分類で整理するため、正確さと注意深さが求められます。
この作業が正確であることが企業の経営状況を把握する上で非常に重要な土台となるため、注意深く行う必要があります。
②請求書・支払い管理
企業間のやり取りでは商品の購入やサービスの提供に伴い、入金や支払いのやり取りが必ず発生します。
経理は取引の請求書を正しく作成し、相手に送付することも仕事の1つです。
また、取引先から受け取った請求書に対しても、内容を確認し、支払い期日までに支払う処理を進めなければなりません。
金額や日付の確認はもちろん、支払い漏れや二重払いを防ぐ管理能力が求められます。
企業の信用に直結する業務の1つです。
③経費精算
経費精算は社員が仕事のために一時的に立て替えた交通費や接待費などを後日、会社が支払う仕組みのことです。
この業務は社員と経理担当者の両方が関与するため、申請内容の確認や問い合わせ対応など、コミュニケーションが発生する場面が多くなります。
金額の整合性をチェックしながら、正確かつ迅速に処理を進めるスキルが必要です。
間違いがあると社員の不満にもつながってしまうため、丁寧な対応が欠かせません。
④月次・年次決算
月次決算は月に一度の頻度で行われる業務で、企業がその月の経営状況を把握するために必要です。
取引先からの入金状況や請求書の発行、給与計算など、日々の経営業務がしっかりと整理されることで、翌月以降の計画に役立つデータが得られます。
年次決算は1年に一度、全ての取引が完了した後に行われ、決算表にまとめられます。
月次決算を毎月実施して、年末の年次決算をスムーズに行うことが大切です。
⑤税務申告
税務申告は法人が毎年行わなければならない重要な業務で、法人税や消費税、所得税などの税金を申告することが必要不可欠です。
申告期限に遅れたり、誤った申告をしてしまったりすると、企業に対しペナルティが課される可能性があります。
そのため、正確な税務申告を行うために、経理担当者は税法をしっかりと理解しておかなければなりません。
多くの企業では税理士にまとめて代理申告を行いますが、経理部門がデータを整え、税理士と連携して申告作業を進めることが多いです。
その他
申告だけでなく、他にも様々な業務が存在します。
銀行との調整では企業の資金繰りや融資の管理、入出金の確認を行い、予算管理では企業の支出を予測して収支を予測し、適切な予算配分を行わなければなりません。
内部監査では企業内の経理処理が正確であるか、内部規定に従っているかどうかを確認し、問題があれば提案します。
いずれの業務も、企業がスムーズに運営されるために必要不可欠であるため、経理職は非常に重要な役割を担っていると言えるのです。
【新卒に経理は難しい】新卒に経理が難しい理由
結論として、新卒の方が経理を担当するのはやや難しいと言われています。
それぞれの理由を理解した上で、適切な対策を行うことで、新卒の方でも経理として採用される可能性が高まるので、確認してみてください。
実務経験を要する仕事だから
経理は会社のお金の流れを正確に管理する役割を担っているため、専門的な知識だけでなく、実務に基づいた判断力が必要です。
伝票の1つをとっても、取引の背景や会社全体の業務フローを理解しなければ、正確に処理することはできません。
また、数字のミスが直接企業の信用や経営に影響を及ぼすことがあるため、初歩的なミスでも許されない環境と言えます。
したがって、現場では即戦力として動ける人材が求められる傾向が強く、実務経験が2〜3年ある人が優先されることが多くなっています。
新卒の方はどうしても「実際の業務で応用する」レベルまで力をつけるには時間がかかるため、いきなり任せられることがあまり多くないのです。
採用枠が少なく競争率が高い
経理は一度職に就くと長く働く人が多く、離職率の低い職種です。
その理由の1つとして、経理業務は毎月・毎年のルーティンが決まっており、残業も比較的少なく、働きやすい環境が整っている点が挙げられます。
あなたもおそらく、このような点に魅力を感じて経理職を目指していることでしょう。
つまり、新しく人を採用する必要性があまりなく、新卒向けの募集がどうしても限られてしまうのです。
また、中途採用ですでに他社での実務経験を積んだ即戦力が応募してくることも多いため、新卒はそうした経験者と同じ土俵で比較されてしまい、不利なのです。
【新卒に経理は難しい】経理職に就くメリット
AIの普及により、定型的な事務作業が自動化される時代ではあるのですが、経理の仕事はその全てが機械に置き換えられるわけではありません。
というのも、経理には取引先との調整や社内とのやり取りの処理など、人の判断や対応が必要な業務が多く含まれているからです。
こうした背景から、経理職は今後も安定したニーズが見込まれる仕事であると言えます。
また、経験の積み重ねが評価される職種で、一度この職に就けば、長く働き続けることができる点も魅力です。
また、業務に繁忙期と閑散期がある程度決まっており、計画的に仕事を進めることができるため、ワークライフバランスを大切にしたい人に向いている職種であると言えるでしょう。
【新卒に経理は難しい】経理職に就くデメリット
経理の仕事は会社の数字を扱う責任ある業務で、1つのミスが大きな損失や信頼の低下につながる可能性があります。
したがって、常に正確さと緊張感が求められる、プレッシャーのかかる環境で働くことになります。
また、売上のように目に見える成果を出すことが難しく、他者と比べて成果を数値で評価されにくいという側面もデメリットの1つです。
昇進や評価に結びつきにくい職場も多いでしょう。
また、経理業務はルーティン化されている部分が多く、日々同じような処理を繰り返すことになるため、仕事に刺激や変化を求める人は飽きてしまう可能性もあるでしょう。
したがって「刺激的な環境で働きたい」「毎日違う仕事がしたい」という方は別の仕事を目指すことを推奨します。
【新卒に経理は難しい】経理職に求められるスキル
続いて、経理職に求められるスキルについて紹介します。
以下の7つのスキルが当てはまっている人は自信を持って経理職を目指しても良いでしょう。
もし当てはまるものが少ない場合は、別の仕事を目指すか、就活が本格化する前に1つでも該当項目を増やせるように取り組んでみてください。
注意力
経理の仕事では取引先への請求金額や社内の経費精算など、1つのミスが大きな損失や信頼の低下につながる恐れがあります。
したがって、細かな数値や日付、金額などの確認を怠らず、どのような場面でも正確さを保てる注意力が必要なのです。
特に経理業務はルーティン化されていることが多く、慣れが油断につながるケースもあります。
「ミスが許されない仕事である」という自覚を常に持ち、細部まで気を配れる姿勢が重要です。
経理職では日々の積み重ねが信頼につながるため、些細な内容でも丁寧に取り組む意識が欠かせません。
分析力
経理業務では日々集まってくる数字の裏側にある企業の状況を読み解く力が求められます。
ただデータを入力するだけでなく、どのような傾向があるのか、資金繰りが順調か、どこに改善点があるのかを把握しなければなりません。
さらに、分析を元に経営陣に報告を行うことが求められる場合も多いため、経理は経営の意思決定の状況を整理して、客観的に企業全体を捉える視点を持つことが求められています。
根気強さ
経理は毎日似たような作業を繰り返す仕事であるため「新しい刺激に満ちた仕事」とは言いづらい側面があります。
同じような書類の確認や仕分け作業が続く中でも、集中力を切らさず、丁寧に取り組む姿勢が欠かせません。
また、決算期や月末などの繁忙期には業務量が一気に増え、残業が発生することもあります。
そのような時でも一定のクオリティを保って作業をやり遂げるためには根気強く粘り強い性格が必要です。
すぐに飽きてしまう人や、短時間で結果が出ないタイプの人には難しく感じられることもあるでしょう。
パソコンスキル
Excel、Word、PowerPointといった基本的なオフィスソフトを使いこなす力も欠かせません。
特にExcelを使ってデータを整えたり分析したりは、毎日の業務とも言えるほどです。
パソコン操作がスムーズであればルーティン業務も効率的に進めることができ、業務のスピードや正確性も高まるでしょう。
また、データの視覚化や報告書作成などでも役立つため、パソコンスキルは経理における必須の基礎力と言えます。
コミュニケーションスキル
経理というと「黙々とパソコンと向き合う」というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、他部署や社員とのやり取りも頻繁に発生する仕事です。
経費の申請内容について確認したり、支払いや請求について調整したりするやりとりは毎日のように発生します。
また、同じ経理部のメンバーと連携しながら業務を進めることも求められるため、報連相ができることは必要不可欠です。
数字だけでなく、人とかかわる力も同時に求められる職種であるということを、必ず覚えておいてください。
数字や計算が好き
経理は毎日数字と向き合う仕事です。
そのため、日頃から数字を見るのが苦にならない人や、家計簿をつける習慣がある、計算を楽しめる人には向いていると言えるでしょう。
細かな数値を扱う場面が多く、正確な計算が求められるため、数字に対して苦手意識があるとつまずきやすい可能性が高いと言えます。
反対に「数字を見ることに全く苦痛を感じない」「整理されている方が落ち着く」というタイプの人にとっては、経理の仕事はまさに相性が最高であると言えるでしょう。
タイムマネジメントを徹底している人
経理業務は月末や年末に締め切りが集中するため、時間内に業務を終える力が求められます。
日々の業務も定められたスケジュールの中で効率よく進める必要があるため、自己管理ができる人に向いていると言えるでしょう。
時間にルーズな人や、スケジュールを後回しにしがちな人は業務が滞り、チーム全体に迷惑をかける可能性が高いです。
一方、普段から課題や予定を計画的に進めている人であれば、経理の業務でも、問題なく、安定したパフォーマンスを発揮できることでしょう。
【新卒に経理は難しい】新卒で経理職に就くためにやるべきこと
続いて、新卒の方が経理職として就職するためにはどのような対策をしなければならないのかについて紹介します。
以下の7つの対策を入念に行えば、新卒でいきなり経理になれる可能性があるため、できるものから取り組んでみてください。
①会計の基礎知識を学ぶ
経理の業務を正しく理解し、実際に活躍するためには会計の基本的な考え方やルールをしっかりと身につけておく必要があります。
法人会計では売上や仕入れ、経費の処理など、日常的な取引がどのように数値として記録されているのかを把握する力が必要不可欠です。
この知識がないまま現場に入ると、業務の流れがつかめず、ミスや混乱を招く恐れがあります。
まずは書籍や入門講座、YouTubeなどを活用して、簿記の基本や貸借対照表、損益計算書の構造などを理解することが大切です。
こうした知識があることで、面接時や実践の仕事でも自信を持って取り組むことができます。
本格的に学びたい人は「udemy」がおすすめです。
その道のプロが作成した体系的なコースで学べますし、普段は2〜3万円するコースも、年に何度もあるセール中は90%程度安くなります。
②経済・税務の知識を学ぶ
学生時代にはあまり触れる経験がなかったかもしれませんが、経理の業務では税金やお金の流れについての知識が欠かせません。
企業が納める法人税や消費税、源泉徴収税など、日常的に扱う金額の中は、税金処理が発生するものばかりです。
これを正しく理解していないと、業務の中で見落としや処理ミスが発生する可能性が高まってしまいます。
また、経済全体の動きや制度の変更が企業活動にどう影響するのかを知っておくことも、経理職としての視野を広げる上で重要です。
新聞や経済誌に目を通したり、税務に関する基本的な書籍を読んだりすることから始めてみましょう。
③簿記資格の取得
必須ではありませんが、簿記の資格を持っておけば経理に関する関心、そして学習意欲の高さを示せます。
特に日商簿記2級以上は実務でも通用するレベルとされており、経理職を志望するなら取得しておきたい資格です。
簿記2級以上を持っていることで、仕分けの理解や財務諸表の読み方など、実践的なスキルを証明できます。
また、ステップアップを目指すならば、日商簿記1級や公認会計士、税理士などの上位資格に挑戦することで、専門性の高さを強く打ち出すことができます。
特に公認会計士や税理士などは非常にレベルが高いですが、独立もできるため「将来は起業したい」という方はぜひ、今から少しずつでも勉強を始めてみましょう。
その他経理職を目指すなら欲しい資格紹介
経理職を本格的に目指すならば、簿記以外にも多様な資格を取得しておくことで自身の専門性を高めることができ、ライバルに圧倒的な差をつけられます。
ビジネス会計検定は財務諸表の読み取りや経営分析の力を測る検定で、分析力や会計的思考をアピールするときに有効です。
また、財務諸表スキル検定(FASS検定)は実務レベルの処理能力を客観的に示す資格として知られています。
加えて、経理事務パスポート検定や給与計算実務能力検定なども、日常業務に関する知識が問われるため、現場で即戦力として働きたい方におすすめです。
また、有名なFP検定は資産管理の知識を身につける上で役立ちます。
より高度な専門職を目指す場合は公認会計士や税理士試験といった国家試験にも挑戦しましょう。
④Excel・会計ソフトの使い方を学ぶ
経理職ではExcelや会計ソフトの操作が業務の中心と言えます。
日々の仕訳入力やデータ集計、帳票の作成など、ほとんどの業務をパソコン上で行うため、最低限のスキルは身につけておかなければなりません。
Excelでは表計算や関数、グラフ作成に加えて、ピボットテーブルやVLOOKUPなどの関数操作が求められる場面も日常茶飯事です。
また、MOSなどの資格を取得しておけばスキルの証明にもなるため、ぜひ資格取得を目指してみると良いでしょう。
実際の会計ソフトを体験できる講習やセミナーを利用してみるのも選択肢の1つです。
⑤インターンやアルバイトで実務経験を積む
新卒で経理職として働く上で最大のハードルは実務経験が無いことです。
これを克服する手段として、会計事務所や企業の経理部門でのインターンやアルバイトを経験しておくことが挙げられます。
実際の職場で、伝票の処理や書類作成、データ入力などを行うことで、座学だけでは得られない実務の業務感覚が身についていきます。
また、職場での報連相など、社会人としての基本も学べるため、面接時に具体的な経験として話すことができ、他のライバルに差をつけることができるでしょう。
⑥会計系のゼミに入る
経済学部以外では難しいかもしれませんが、会計系のゼミに入れるならば、ぜひ選択してください。
会計や財務に関するゼミに所属すれば、授業以上に深い知識を身につけるきっかけになります。
実際の企業データを使った分析や模擬決算を行うプログラムを導入しているゼミも少なくありません。
実務に近い経験を豊富に積めることでしょう。
また、指導教員に質問を行えば、専門的なアドバイスを受けられる点も魅力です。
「自分が経理になるにあたって何が足りていないか?」などと聞いてみると良いでしょう。
ゼミで学んだ内容を就活でしっかりと話せば、志望動機や自己PRにさらなる説得力が生まれます。
⑦OB・OG訪問で直接話を聞く
実際に経理職として働いている先輩から話を聞くことも、非常におすすめの選択肢の1つです。
OB・OG訪問を活用すれば、就職活動において非常に貴重な情報源を得られることでしょう。
「どのスキルが必要だったか」「学生時代にやっておいて良かったことは何だったか」「入社後に苦労した点は何だったか」など、具体的な話を直接聞けます。
また、就活の面接で何を聞かれたかといった質問もできるため、面接対策にも役立ちます。
さらに、現場で求められる人物像や企業ごとの違いについても把握できるため、選考のピンポイントな対策を立てられるでしょう。
OB・OG訪問を通じて得た具体的な話は、面接での発言にも説得力を加える材料になり得るものです。
【新卒に経理は難しい】新卒が経理職に採用されるポイント
以下の3つのポイントを意識した上で就活に取り組めば、新卒の方でも経理職として採用される確率が高まります。
就職後、初日から経理として働きたいと考えている方は、ぜひそれぞれのポイントを念頭に置いた上で、就活を進めてください。
自分のスキルや資格に応じて応募する
経理職を目指す新卒の方にとって重要なこととして、自分の持っているスキルや資格、経験に見合った企業を選んで応募することが挙げられます。
大手の企業は即戦力となる人材を重視する傾向にあり、インターンやアルバイトなど、実務経験を積んだ人や、簿記の資格を保有している人にとっては有利な環境です。
一方、まだスキルや実績に自信がない方は、若手の育成に力を入れている中小企業やベンチャー企業を選ぶ選択肢も有効と言えるでしょう。
中小・ベンチャー企業では「将来の中核を担う存在」として丁寧に指導してもらえる可能性が高く、成長の機会も豊富にあります。
職種別採用を行っている企業に応募する
経理職での採用を目指す場合は職種別の採用を行っている企業を狙って応募することがおすすめです。
新卒向けの企業サイトや企業の公式サイトを見ていると、職種ごとに募集を行っているケースも多く、あらかじめ経理職での配属が確定している募集枠を選べば、希望と異なる部署に配属されるリスクを回避できます。
ただし、業界と職種の両方で志望先を絞ることになるため、選択肢が少なくなってしまうことには注意が必要です。
会計を専門職としている業種に応募する
経理職にこだわりたい方は企業の経理部門に限らず、会計を専門とする業種に目を向けてみるのも選択肢の1つです。
税理士事務所や会計事務所、あるいは金融機関などで、お金の流れを扱う業務に日常的に触れることが可能です。
こうした環境に身を置くことで、実務経験を積みながら専門的な知識を深めることができ、将来的に企業経理や財務職にキャリアを広げていく上でも大きな土台になります。
また、一般企業と比べて専門性が高いため、入社後の学びも多く、スキルアップの速度も速いのが特徴です。
「会計を軸に置きたい」という意欲がある方にとっては魅力的なキャリアのスタートになることでしょう。
【新卒に経理は難しい】もし経理職に就けなかったら
当然、全ての人が新卒でいきなり経理になれるわけではありません。
どれほど熱い思いを持っていたとしても、企業の求める項目にまだ該当できていない場合など、別の仕事を任されることもあるでしょう。
そこで、ここからは経理職になれなかった場合、どのように対応するべきかについて紹介します。
ジョブローテーション・異動を活用する
新卒で希望通り経理職に就けなかった場合でも、配属後のジョブローテーションや社内異動制度を利用することで、経理職へキャリアチェンジできる可能性は大いにあります。
特に大きな企業では数年ごとに部署を異動するジョブローテーション制度を設けていることが多く、入社後に実績を積んだ上で異動を希望すれば、経理部門に配属されるチャンスはあります。
その際に重要なのは「なぜ経理を目指しているのか」という明確な意思と、資格取得や関連業務での成果など、アピール材料の有無です。
自分の熱意が伝わるように、上司や人事部門に働きかけることが必要であり、異動希望を出すまでにしっかりと準備を進めておくことが求められます。
第二新卒・中途採用で再チャレンジ
新卒で経理職に就けなかった場合でも、キャリアの初期段階で再チャレンジする道は十分残されています。
特に第二新卒の枠は入社後3年以内の若手層を対象とした中途採用であり、実務経験こそ、ある程度問われるものの、ポテンシャルや成長意欲が評価されやすいタイミングです。
3年程度、他の職種で社会人としての基本的なスキルやビジネスマナーを習得しつつ、並行して簿記資格の取得や経理に関する勉強を進めておくと、転職活動でもライバルを蹴散らせるでしょう。
特に、簿記2級やFASS検定などの資格があると、実務未経験でも「知識面での準備はできている」とみなされやすくなります。
学生時代から長期的に計画を立てておけば、たとえ新卒では経理職を逃してしまったとしても、数年後には再び目指すことが可能です。
まとめ
今回は経理職を目指している方向けに、具体的な対策や難しい理由、心がけておくべきポイントなどについて詳しく紹介しました。
新卒の方がいきなり経理になることは記事中で説明したように簡単ではありません。
特に、実務経験がある人がライバルとして応募してきた場合は、なかなか難しいでしょう。
しかし、本記事で紹介した知識を蓄え、資格取得などに取り組めば勝てる可能性もありますし、もし失敗しても数年後に再チャレンジできるので、ぜひ取り組んでみてください。