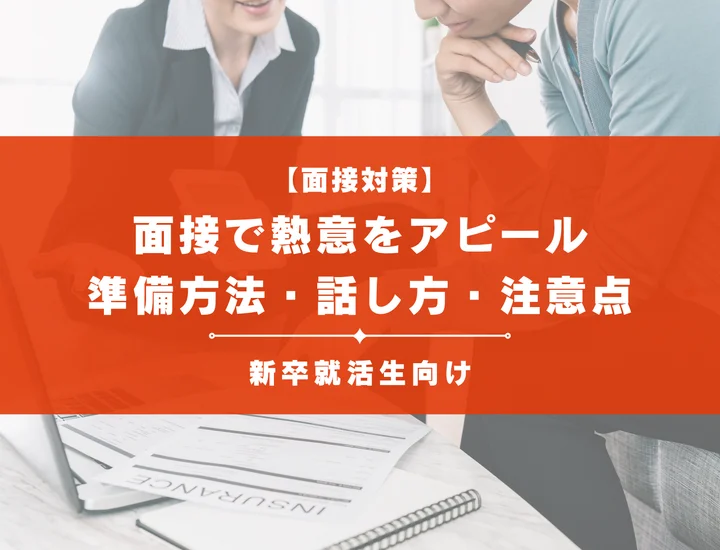明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・苦手なことを聞く理由
・苦手なことの答え方
・苦手なことの注意点
・苦手なことを伝える時の注意点を知りたい人
・苦手なことの答え方を知りたい人
・苦手なことを話している例文を参考にしたい人
はじめに
面接でよく聞かれる質問の中に、得意なことや興味のあることに関する質問があります。
しかし、その一方で、苦手なことを聞かれることもあります。
おそらく、いきなり苦手なことを聞かれたときにネガティブな印象を残さず、率直に答えることは難しいでしょう。
この記事では、そのような場合に面接官に好印象を与えることができる回答方法を紹介します。
ぜひ、面接の事前準備に活用し、自信をもって面接を受けることができるようにしましょう。
【面接で苦手なことを伝える時】面接で苦手なことを聞かれる意図
面接で「苦手なことは何ですか?」と聞かれたとき、多くの人はどう答えるべきか迷うでしょう。
しかし、面接官の意図を理解し、事前にどのように答えるか対策しておけば、自分の人間性を理解してもらうきっかけにすることができます。
面接官は、この質問を通してあなたのことを深く理解しようとしているのです。
具体的にどのような意図があるのか、以下で解説します。
自己認識の確認
面接官はあなたが自分のことをどれだけ客観的に見つめられているかを知りたいと思っています。
自分の強みだけでなく、弱みや課題をしっかりと認識できているか、それは自己分析の深さを示すバロメーターとなるからです。
「特にありません」といった回答は、自己認識が甘い、または自己開示に抵抗があるという印象を与えかねません。
誰でも得意なことや好きなことについてアピールすることはできるでしょう。
しかし、面接という自分を企業に売り込む場において、自分の苦手なことをどのように語れるかにこそ、真の人間性が現れるとも言えます。
苦手なことを率直に語ることは、あなた自身の成熟度を示すとともに、課題と向き合う誠実さを伝えるチャンスなのです。
成長意欲や学びの姿勢のチェック
面接官はあなたが苦手なことに対してどのような姿勢で臨んでいるのかを知りたいと考えています。
単に「苦手です」と述べるだけでなく、その苦手なことを克服するためにどのような努力をしているのか、あるいはどのように工夫して業務に取り組んでいきたいのかといった具体的な行動を知りたいのです。
これは、あなたの成長意欲や学び続ける姿勢を測る上で非常に重要なポイントとなります。
過去の経験を踏まえ、どのように課題を認識し、改善に向けて行動してきたのかを具体的に説明することで、面接官にあなたの成長への意欲を強く印象づけることができるでしょう。
ストレス耐性や自己管理能力の確認
面接官はあなたがストレスにどのように対処し、自己管理をどのように行っているのかを知りたいと思っています。
仕事をする上で、予期せぬ困難や苦手な業務に直面することは避けられません。
そうした状況において、あなたがどのように冷静さを保ち、どのように問題解決に向けて取り組むのかを見ています。
苦手なことに対する感情的な反応だけでなく、それを客観的に分析し、建設的な解決策を見出そうとする姿勢を示すことが大切です。
また、必要に応じて周囲に助けを求めたり、効率的に業務を進めるための工夫をしたりする能力も、自己管理能力として評価されるでしょう。
【面接で苦手なことを伝える時】面接で苦手なことを答える時の注意点
面接で苦手なことを正直に伝えることは、自己認識の深さを示す上で重要です。
しかし、伝え方を間違えてしまうと、ネガティブな印象を与えてしまう可能性もあります。
苦手なことについて質問されたとしても、あくまで面接では自分の強みをアピールすることが重要です。
苦手なことの印象が強くなりすぎないように気を付けましょう。
ここでは、面接官にあなたの成長意欲や自己改善への意識を効果的に伝えるための注意点について、詳しく紹介していきます。
過度にネガティブにならない
大切なのは、苦手なことを率直に認めつつも、過度にネガティブな表現を避けることです。
「どうしても〜が苦手で…」「〜は全くできません」といった強調しすぎる言い方や、暗い表情で話すのは避けましょう。
話し方や自信は、面接において印象を大きく左右します。
苦手なことを認識している事実は伝えつつも、声のトーンや表情は明るく、前向きな印象を保つように心がけてください。
以下の3つを心がけることで、ネガティブな印象が強くならない伝え方になります。
苦手なことを素直に認める方法
苦手なことを素直に認める際には、謙虚さと自己改善への意欲を同時に示すことが重要です。
「〇〇については、まだ経験が浅く、至らない点があると感じています」のように、現状を冷静に分析し、課題として捉えていることを伝えましょう。
「苦手」や「できない」というような直接的な言葉を避け、「改善の余地がある」のような遠回しな表現を意識してください。
決して卑屈になるのではなく、苦手なことを克服していきたいという前向きな姿勢を明確にすることが大切です。
改善策を盛り込んだポジティブな表現
苦手なことを伝える上で最も重要なことの一つが、その改善に向けてどのような努力をしているかを具体的に説明することです。
何が苦手なのか伝えるだけで終わらせるのではなく、その改善策や実際に苦手を克服するために行っていることといった具体的な行動を示すことで、あなたの成長意欲を強くアピールすることができます。
改善のために取り組んでいることがない場合も、今後どのように改善していくか意気込みを伝えましょう。
フィードバックを受け入れる姿勢を見せる
面接官からのフィードバックを素直に受け入れる姿勢を見せることも、成長意欲を伝える上で非常に効果的です。
面接官があなたの回答に対して何か意見やアドバイスをしてくれた際には、真摯に耳を傾け、「ありがとうございます。参考にさせていただきます」といった言葉で、学ぶ姿勢を示すことが大切です。
フィードバックを聞いている最中も、うなずいたり、積極的に聞き入れようとしている姿勢を見せたりすることで、真っすぐで周囲から学びを得ようとする人間性を印象付けることができます。
ポジティブな結果を強調する
改善に向けた取り組みの結果として、どのようなポジティブな成果があったかを具体的に話すことも、面接官に良い印象を与えるための重要なポイントです。
大学での経験やアルバイトでの経験をもとに、苦手なことが改善されていった例のように、努力が具体的な成果に繋がっていることを伝えることで、成長力と問題解決能力をアピールすることができます。
実際に苦手なことを克服した経緯などがあれば、企業側は、入社後に課題や苦手とする分野の業務を担当することになったときにどのように切り抜けるのか想定することもできます。
職務に関連しない苦手なことを挙げる
面接で話す苦手なこととして、職務に直接関連しない事柄を選ぶのも一つの有効な手段です。
例えば、「大人数の前で話すことにまだ慣れていませんが、積極的に機会を作って克服したいと思っています」といった内容は、自己開示をしつつも、業務遂行能力への懸念を最小限に抑えることができます。
ただし、あまりにも業務と無関係なことを挙げすぎても、面接での意図を理解していないと捉えられてしまうかもしれないためバランスを考慮しましょう。
過度に自己弁護しない
自分の弱点について説明する際に、言い訳がましくならないように注意することも大切です。
「〜のせいで」「〜だったから」といった自己弁護の言葉は避け、うまくいかなかった経験を例に出しながらも、そこから得た学びを伝えるなど、過去の経験を成長の糧として捉えていることを示すようにしましょう。
「でも」や「しかし」といった逆説の接続詞を多用するのも、自己弁護しているような印象を与えかねませんので注意が必要です。
過去の経験から学んだことを話す
苦手なことを最終的にどのように乗り越えたのか、あるいは乗り越えようと努力する過程でどのような学びや気づきがあったのかを話すことは、自分の成長を示す上で非常に効果的です。
単に苦手なことを克服したという結果だけでなく、その過程で得た経験や教訓を伝えることで、困難を乗り越える力や、自己成長への意識を持っていることを面接官に印象づけることができるでしょう。
【面接で苦手なことを伝える時】面接で苦手なことを聞かれた時の答え方
面接で「苦手なことは何ですか?」と尋ねられた際、どのように答えるかは、あなたの印象を大きく左右します。
単に弱点を伝えるだけでなく、それをどのように克服し、仕事に活かしていくのかを示すことが重要です。
長々と話さず、いくつかの内容を意識して回答することによって、苦手なことを話しつつも自分の成長力と仕事への意欲を効果的に伝えることができるでしょう。
自分の苦手なことを伝える
大切なのは自分の苦手なことを率直に伝えることです。
完璧な人間はいません。
誰にでも得意なこととそうでないことがあります。
面接官もそのことを理解しています。
飾らずに自分の弱点を認めることは、自己認識の高さを示すとともに、正直で信頼できる人物であるという印象を面接官に与えます。
まずはじめに、何が苦手なのかを明確に伝えましょう。
その際に、具体的な例や改善にとりくんでいることなどから話さずに、端的かつわかりやすく苦手なことを示すことによって、面接官もその後の内容を理解しやすくなります。
改善に向けた具体的な取り組みを示す
苦手なことに対して、あなたがどのように改善に取り組んできたのか、あるいは現在取り組んでいるのかを具体的に説明することが重要です。
単に「苦手です」と言うだけでは、成長意欲があるかどうかを判断できません。
「以前から大人数の前で話すことに苦手意識がありましたが、克服するために、社内外のプレゼンテーション研修に積極的に参加したり、少人数の会議で率先して発言する機会を増やしたりしています」のように、具体的な行動を示すことで、あなたが課題に対して主体的に向き合い、改善しようと努力している姿勢を伝えることができます。
改善に向けた取り組みは、特別大きなことでなくて構いません。
日頃から少し意識していることや、その苦手なことをやらなければいけない場合にどのように対処しているのか、その過程が重要です。
結果や改善の進捗を伝える
改善に向けた取り組みによって、どのような結果が得られたのか、あるいはどの程度改善が進んでいるのかを伝えることで、あなたの成長を具体的にアピールすることができます。
どのような行動を起こし、それによって苦手なことはどのように改善されたかのように、具体的な変化や進捗を伝えることで、あなたの努力が実を結びつつあることを示すことができます。
もし、あまり改善することができていない場合でも、その原因について触れ、次はどのように克服していくかなど、意欲的な姿勢を貫きましょう。
仕事で活かす方法を伝える
苦手なことの克服や改善の過程で得られた学びや経験を、今後の仕事でどのように活かしていくのかを面接官に伝えることで、入社意欲と貢献意欲を示すことができます。
「大人数の前でのプレゼンテーションの練習を通して、相手に分かりやすく伝えるためには、事前の準備がいかに重要かを学びました。入社後も、常に相手の視点を意識し、丁寧なコミュニケーションを心がけていきたいと考えています」のように、具体的な学びを仕事への意欲と結びつけることで、面接官はあなたが単に弱点を克服するだけでなく、その経験を活かして成長し、会社に貢献してくれる人材であると期待感を持つでしょう。
【面接で苦手なことを伝える時】苦手なことの代表例10選
面接で「苦手なことは何ですか?」と聞かれた際に、どのようなことを挙げれば良いか悩むこともあるかもしれません。
ここでは、一般的な苦手なことの例を10個挙げ、それぞれについて、なぜそれが苦手と感じられるのか、そしてどのように改善していけるのかを掘り下げて解説します。
これらの例を参考に、自分の状況に合った苦手なことを見つけ、具体的な改善策と共に面接官に伝える準備をしましょう。
プレゼンテーション
人前で話すことは、多くの人が苦手意識を持つものです。
緊張してしまったり、何を話せば良いか分からなくなったりすることが原因かもしれません。
しかし、プレゼンテーション能力は、情報を効果的に伝え、相手を説得するために、社会人として非常に重要なスキルです。
練習を重ねることで、自信を持って話せるようになります。
例えば、家族や友人の前で練習したり、オンラインのプレゼンテーション講座を受講したりするなどの具体的な行動を示すと良いでしょう。
また、大学などの経験を例に出すとしたら、講義での発表やサークルの新歓でのサークル活動についての説明などの経験がわかりやすく、効果的です。
時間管理
複数のタスクを効率よくこなすのが難しいと感じる人もいます。
これは、タスクの優先順位付けが曖昧だったり、スケジュール管理がうまくいっていなかったりすることが原因として考えられます。
しかし、時間管理は業務効率を高める上で不可欠なスキルです。
スケジュール帳やタスク管理ツールを活用したり、 Eisenhower Matrix のようにタスクを緊急度と重要度で分類する方法を学んだりすることで、改善が可能です。
また、作業が早い人がどのように行動しているのかを参考にし、自分の行動とどう違うのか比較することで、時間管理が苦手な原因に気づくことができるかもしれません。
細かい作業
データ入力や書類のチェックなど、注意力を要する細かい作業に苦手意識を持つ人もいます。
集中力が続かなかったり、見落としをしてしまったりすることが原因かもしれません。
細かい作業において不可欠な集中力は、生活習慣や睡眠によっても大きく変わります。
自分の生活習慣から見直すことも解決方法の一つになる可能性があります。
細かな作業での正確性は仕事の質を左右する重要な要素です。
タイマーを使って作業時間を区切ったり、チェックリストを作成して確認したりするなど、ミスを防ぐための工夫を意識することで改善できます。
チームワーク
チームで協力して仕事を進める際に、自分の役割をうまく果たせなかったり、他のメンバーとの連携に苦労したりする場合です。
コミュニケーション不足や、自分の意見をうまく伝えられないことが原因として考えられます。
しかし、チームワークは組織で成果を出すために不可欠です。
積極的にチーム内の会議に参加し、メンバーの意見に耳を傾け、自分の考えを分かりやすく伝える努力をすることで、改善することができます。
具体的に苦手に感じた経緯、改善のための行動の例としては、アルバイトでの他の従業員との連携や、委員会活動での他のメンバーとの協力が挙げられます。
マルチタスク
複数のタスクを同時にこなすことに難しさを感じる人もいます。
注意が散漫になったり、どのタスクから手をつければ良いか迷ったりすることが原因かもしれません。
しかし、多くの仕事は複数のタスクを同時並行で進めることが求められます。
タスクをリスト化し、優先順位をつけて一つずつ確実に片付けていく、シングルタスクの意識を持つことで、効率的にこなせるようになります。
一つひとつの仕事をいかに早く、正確にこなすことができるかを意識し続けることで、だんだんと自分が一度にできることの量を増やすことができるでしょう。
迅速な決断
状況を素早く判断し、決断を下すことに苦手意識がある場合です。
情報が不足していると感じたり、決断によって生じる責任に不安を感じたりすることが原因かもしれません。
しかし、ビジネスの現場では迅速な判断が求められる場面が多くあります。
迅速な決断は、機会損失を防ぎ、変化に柔軟に対応することを可能にし、チームやプロジェクトを前に進める原動力となります。
事前に必要な情報を集める習慣をつけたり、小さな決断から意識的に行う練習をしたりすることで、徐々に素早く判断できるようになります。
日常生活における些細な選択、例えばランチのメニューや休憩時間の過ごし方など、リスクの低い場面で積極的に自分で決断を下す練習をすることで、すぐに決める癖をつけることができるでしょう。
自己主張
自分の意見や考えをしっかりと主張することに抵抗がある人もいます。
周りの意見に流されやすかったり、自分の意見に自信が持てなかったりすることが原因かもしれません。
しかし、チームで仕事を進める上で、それぞれのメンバーが持つ異なる視点やアイデアを共有することは、より良い結論を導き出すために不可欠です。
発言する前に自分の考えを整理したり、小さな会議で意識的に発言する練習をしたりすることで、自信を持って意見を言えるようになります。
また、自分の意見に根拠を持つことも重要です。
そう考える理由や、それを裏付けるデータや事例などを準備しておくことで、発言に説得力が増し、自信を持って主張できるようになります。
ストレス管理
現代社会において、仕事や人間関係など、様々な要因からストレスを感じることは避けられません。
特に、完璧主義な傾向を持つ人は、目標を高く設定しすぎるあまり、達成できない場合に強いストレスを感じやすい傾向があります。
完璧主義の他にも、休息を取るのが苦手な場合もストレスをため込む原因になります。
しかし、心身の健康を保ち、長く活躍するためには、ストレスを適切に管理することが重要です。
リラックスできる趣味を見つけたり、適度な運動を取り入れたり、十分な睡眠時間を確保するなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。
対人関係(特に初対面の人との交流)
初対面の人と何を話せば良いか分からず、ぎこちなくなってしまうという人もいます。
相手にどう思われるか不安になったり、共通の話題を見つけるのが苦手だったりすることが原因かもしれません。
しかし、仕事を進める上で、同僚、取引先、顧客など、様々な立場の人と円滑なコミュニケーションを取ることは非常に重要です。
良好な対人関係は、チームワークを高め、仕事の効率を向上させ、信頼関係を築く上で不可欠な要素となります。
積極的に挨拶をしたり、共通の話題を探すように心がけたりすることで、徐々に対人スキルを向上させることができます。
また、相手に質問をすることも、会話を続けるための有効な手段です。
質問をする際は、相手が答えやすいオープンな質問を心がけることで、相手も心を開きやすくなったり、会話が広がりやすくなったりします。
論理的思考
物事を筋道立てて考えたり、感情ではなく根拠に基づいて判断したりすることが苦手だと感じる場合です。
情報が整理できていなかったり、先入観で判断してしまったりすることが原因かもしれません。
しかし、論理的思考は問題解決や意思決定において重要なスキルです。
論理的に考える力があれば、感情に左右されることなく、客観的な根拠に基づいて判断を下すことができ、より合理的な意思決定に繋がります。
情報を整理するフレームワークを学んだり、Why思考を意識的に行ったりすることで、論理的に考える力を養うことができます。
何か問題に直面した際に、「なぜそうなるのか?」と問い続けることで、表面的な事象だけでなく、その根本的な原因を探る習慣を身につけることができます。
【面接で苦手なことを伝える時】例文10選
ここでは、面接で苦手なことを伝える例文を、苦手なことの内容ごとに紹介しています。
それぞれ、先の項目で解説したポイントを押さえた例文になっているので、自分の苦手なことに置き換えて参考にしてみましょう。
どのように答えるか想定しておくことで、実際に質問されたときに慌てずに、好印象につながる回答ができます。
プレゼンテーション
時間管理
細かい作業
チームワーク
マルチタスク
迅速な決断
自己主張
ストレス管理
対人関係(特に初対面の人との交流)
論理的思考
【面接で苦手なことを伝える時】面接練習で大切なこと3選
面接本番で力を発揮するためには、事前の準備が不可欠です。
ここでは、面接練習において特に重要な3つのポイントを掘り下げて解説します。
これらの点を意識して練習に取り組むことで、自信を持って面接に臨み、あなたの魅力を最大限に伝えることができるでしょう。
面接は経験が一番大切です。
知人や就活エージェントに協力してもらいながら、何度もシミュレーションしてみましょう。
1. 自己分析
最も重要なのは、自己分析を深く掘り下げ、自身の強みや弱み、これまでの経験をしっかりと理解することです。
面接では、過去の経験に基づいて、あなたの能力や人となりが評価されます。
そのため、「学生時代に力を入れたことは何か」「困難だった経験をどう乗り越えたか」といった質問に対して、具体的なエピソードを交えながら明確に答えられるように準備しておく必要があります。
単に経験を思い出すだけでなく、その経験を通して何を学び、どのように成長したのかを言語化しておくことが重要です。
さらに、面接官はあなたの回答に対して、具体的になぜ、どのように行動したのかといった深掘りの質問をすることがあります。
これらの質問にスムーズに答えられるように、事前に様々な角度から自己分析を行い、回答を準備しておくことが、面接官に深い理解と論理的な思考力があるという印象を与えることに繋がります。
自分自身のことを深く理解し、それを面接官に分かりやすく伝える準備を徹底的に行いましょう。
2. 模擬面接で実践的に練習
どれだけ頭の中で完璧に回答を準備しても、本番の緊張感の中でそれをうまく表現できるとは限りません。
そのため、実際の面接を想定した模擬面接を繰り返すことが非常に重要になります。
模擬面接を行うことで、本番特有の雰囲気に慣れ、緊張感をコントロールする練習になります。
また、話すスピードや声の大きさ、表情や姿勢など、言葉以外の要素も意識しながら練習することができます。
事前に面接でよく聞かれる質問を模擬面接に協力してくれる相手に共有しておき、本番さながらの雰囲気で質問をしてもらいます。
可能であれば、複数回異なる相手と行うことで、様々な質問の仕方やフィードバックに対応する練習になります。
模擬面接を通して、自分がどのような時に詰まってしまうのか、どのように話すと相手に伝わりやすいのかなど、具体的な課題が見えてくるはずです。
3. フィードバックを受け入れて改善
模擬面接が終わった後が、最も重要な時間です。
自分の回答や態度を客観的に振り返り、改善点を見つけ出す必要があります。
録画した映像を見返したり、模擬面接の相手からのフィードバックを参考にしたりしながら、より効果的な伝え方や改善すべき点を具体的に洗い出しましょう。
もし可能であれば、大学のキャリアセンターの職員や就職活動のプロにフィードバックをお願いすることも非常に有益です。
客観的な視点から、あなたの強みや改善点について的確なアドバイスをもらうことができます。
プロの視点からのフィードバックは、自分では気づかなかった改善点や、より効果的なアピール方法を発見するきっかけになるでしょう。
自己分析、模擬面接、そしてフィードバックの活用という3つの要素をしっかりと意識して練習に取り組むことで、あなたは必ず面接で最高のパフォーマンスを発揮できるはずです。
まとめ
ただでさえ、緊張する面接で自分の苦手なことを話すのは抵抗感があるかもしれません。
しかし、その質問にどのように答えるかによって、入社後にどのような姿勢で、仕事上でぶつかる困難を乗り越えるのか見られていると考えてみましょう。
自分の強みを感じさせるチャンスになります。
この記事で解説したポイントを参考に、徹底した事前準備を進めましょう。



_720x550.webp)