はじめに
「もし答えられない質問が来たらどうしよう…」と不安に感じる就活生の方も多いのではないでしょうか。
準備不足を感じていたり、実際に面接で言葉に詰まってしまった経験があると、なおさらその不安は大きくなるかもしれません。
でも、安心してください。
この記事では、面接で答えられない質問をされた時の上手な対処法や、そもそもなぜ答えられなくなってしまうのか、その原因と具体的な対策について、新卒の皆さんにも分かりやすく解説します。
この記事を読めば、面接への不安が軽減され、自信を持って本番に臨めるようになるはずです。
面接で答えられなくても落ちるとは限らない
まず知っておいてほしいのは、「面接で質問に完璧に答えられなかったからといって、必ずしも不合格になるわけではない」ということです。
もちろん、スムーズに回答できるに越したことはありませんが、面接官はあなたの全てをその一瞬だけで判断しているわけではありません。
大切なのは、答えられない状況にどう対応するか、そしてあなたの持つ潜在的な可能性や人柄です。
少し肩の力を抜いて、面接官が何を見ているのかを理解しましょう。
面接官が完璧を求めてない
多くの面接官は、学生に対して完璧な回答を求めているわけではありません。
特に新卒採用の場合、社会人経験がないことは当然理解しています。
面接官が見ているのは、むしろあなたが困難な状況や予期せぬ質問に対して、どのように考え、対応しようとするかというプロセスや、その誠実な姿勢です。
ですから、少し言葉に詰まったとしても、正直に自分の考えを伝えようと努力する姿は、むしろ好印象を与えることさえあります。
大切なのは、完璧な模範解答ではなく、あなた自身の言葉で、一生懸命伝えようとする気持ちです。
答え方より人間性を評価している
面接官は、あなたが質問にどう答えるかという「内容」だけでなく、その答え方や態度から、あなたの「人間性」を評価しようとしています。
例えば、落ち着いて対応できるか、誠実さがあるか、困難な状況でも前向きに取り組もうとする姿勢があるか、といった点です。
答えに詰まってしまったとしても、正直にその旨を伝え、少し考える時間をもらうなど、真摯に対応することで、むしろコミュニケーション能力や素直さ、成長の可能性をアピールできるチャンスにもなり得ます。
面接は、あなたの知識やスキルを試す場であると同時に、あなたという人間を知ってもらうための対話の場なのです。
面接で答えられない時の言い方は?
面接中に予期せぬ質問や難しい質問をされて、頭が真っ白になってしまうことは誰にでも起こり得ます。
そんな時、パニックにならずに落ち着いて対応するための「言い方」を知っておくことは非常に重要です。
沈黙が続いて気まずい雰囲気になるのを避けるためにも、いくつかのフレーズを覚えておきましょう。
ここでは、具体的な言い方の例と、その際のポイントを解説します。
これらのフレーズを上手に活用することで、ピンチを乗り切り、むしろ誠実な印象を与えることができるかもしれません。
「少し考える時間をください」と伝える
最も基本的かつ有効な対処法の一つが、正直に「少し考える時間をいただけますでしょうか」と面接官にお願いすることです。
何も言わずに黙り込んでしまうと、面接官はあなたが質問を理解できなかったのか、あるいは答える気がないのか判断できず、不安にさせてしまいます。
この一言を添えるだけで、あなたは質問に対して真摯に向き合おうとしているという意思表示になります。
通常、面接官は数秒から数十秒程度の時間であれば快く待ってくれます。
ただし、あまりにも長い時間をもらおうとしたり、何度も繰り返したりするのは避けましょう。
時間をもらったら、焦らずに頭の中で考えを整理し、落ち着いてから話し始めることが大切です。
嘘はつかず答えられる範囲で答える
答えられない質問に対して、その場しのぎで嘘をついたり、知ったかぶりをしたりするのは絶対に避けましょう。
面接官は多くの学生を見ているプロです。
見抜かれる可能性が高いですし、もし嘘が発覚すれば、あなたの信頼性は大きく損なわれてしまいます。
それよりも、正直に「その点については深く考えたことがありませんでした」と伝えた上で、「現時点でお答えできる範囲では〜」と、自分の知っていることや関連する経験、考えを述べる方が誠実な印象を与えます。
完璧な答えでなくても、一生懸命考え、答えようとする姿勢が重要です。
質問の意図を正確に理解し、少しでも関連する情報を提供できないか考えてみましょう。
分からなければ正直に
どうしても質問の答えが分からない、あるいは的確な回答が思いつかない場合は、正直に「申し訳ございません、勉強不足でその質問にはお答えすることができません」と伝える勇気も必要です。
ただし、単に「分かりません」とだけ言うのではなく、例えば「差し支えなければ、後日調べて改めてご報告させていただいてもよろしいでしょうか」といったように、学ぶ意欲や誠実な姿勢を示す一言を添えると、より良い印象につながります。
もちろん、企業の理念や事業内容といった基本的な質問に対して「分かりません」を連発するのは準備不足と見なされる可能性が高いので注意が必要です。
正直に伝えることと、事前の準備を怠らないことは両立させましょう。
面接で答えられない原因と対策
面接で言葉に詰まってしまうのには、必ず何かしらの原因があります。
その原因を事前に理解し、適切な対策を講じておくことで、本番で焦るリスクを大幅に減らすことができます。
ここでは、就活生が面接で答えられなくなってしまう主な原因と、それぞれの具体的な対策について解説します。
自分に当てはまるものがないか確認し、今日からできる対策を始めてみましょう。
しっかり準備をすれば、自信を持って面接に臨めるようになります。
緊張しすぎてしまう
多くの就活生が面接で答えられなくなる最大の原因の一つが、「過度な緊張」です。
適度な緊張は集中力を高めますが、緊張しすぎると頭が真っ白になり、普段なら答えられるはずの質問にも言葉が出てこなくなってしまいます。
この原因としては、準備不足への不安、完璧を求めすぎる気持ち、失敗への恐れなどが挙げられます。
対策としては、まず模擬面接を繰り返し行い、面接の雰囲気に慣れることが非常に重要です。
家族や友人、大学のキャリアセンターなどを活用しましょう。
また、面接前に深呼吸をする、自分なりのリラックス方法を見つけておくのも効果的です。
「自分は大丈夫」と自己肯定感を高めることも大切です。
質問内容が理解できない
面接官の質問の意図が正確に理解できなかったり、専門用語や抽象的な表現が含まれていて戸惑ってしまったりすることも、答えられない原因となります。
また、面接官の声が小さかったり早口だったりして、単純に聞き取れないケースもあるでしょう。
このような場合は、決して恥ずかしがらずに、正直に聞き返すことが大切です。
「恐れ入りますが、もう一度ご質問いただけますでしょうか」や、「〇〇というご質問でよろしいでしょうか」といったように、丁寧に確認しましょう。
質問を理解しないまま見当違いの回答をしてしまうより、正確に意図を把握しようとする姿勢の方が評価されます。
聞き返すことは、決して失礼なことではありません。
答えを丸暗記して臨んだ
自己PRや志望動機など、よく聞かれる質問に対して回答を準備しておくことは非常に大切ですが、その内容を一字一句丸暗記してしまうのは逆効果になることがあります。
丸暗記した答えは、どうしても棒読みになりがちで、あなたの熱意や個性が伝わりにくくなります。
また、少しでも質問の角度が変わったり、深掘りされたりすると、途端に言葉に詰まってしまう危険性があります。
対策としては、話したい内容のキーワードやエピソードの骨子だけを覚え、あとは自分の言葉で柔軟に話せるように練習することです。
エピソードを構造的に理解し、なぜそう考えたのか、何を感じたのかを自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。
面接で落ちてしまう原因と対策
面接で思うように受け答えができなかったとしても、それが直接的な不合格の理由とは限りません。
実は、面接で評価が下がってしまう原因は他にも様々あります。
ここでは、答えられないこと以外で面接に落ちてしまう可能性のある主な原因と、それぞれの対策について解説します。
面接全体の質を高め、合格を勝ち取るために、これらのポイントもしっかりと押さえておきましょう。
マナーや立ち振る舞いが悪い
面接では、話す内容だけでなく、あなたのマナーや立ち振る舞いも厳しくチェックされています。
基本的なビジネスマナーが身についていないと、社会人としての適性がないと判断されてしまう可能性があります。
例えば、挨拶の声が小さい、言葉遣いが不適切、身だしなみが整っていない、時間に遅れるといったことは大きなマイナスポイントです。
対策としては、事前に就職活動向けのマナー本やウェブサイトで基本的な知識を身につけ、模擬面接などを通じて実践的な練習を積むことが重要です。
オンライン面接の場合でも、背景の整理やカメラ目線、適切な服装など、対面とは異なるマナーがあるので注意しましょう。
要点が伝わらない
一生懸命話しているつもりでも、話が長すぎたり、結論がなかなか見えなかったりすると、面接官に「結局何が言いたいのだろう?」と思われてしまいます。
また、話の内容に具体性が欠けていると、あなたの経験や考えが十分に伝わりません。
対策としては、まず話の結論から先に述べる「PREP法(Point:結論、Reason:理由、Example:具体例、Point:再度結論)」を意識して話す練習をしましょう。
話す前に頭の中で伝えたい要点を整理し、簡潔かつ分かりやすく伝えることを心がけることが大切です。
自己PRや学生時代に力を入れたことなど、主要なエピソードは事前にPREP法でまとめる練習をしておくと良いでしょう。
志望度合いが伝わらない
企業は、自社に対して強い入社意欲を持っている学生を採用したいと考えています。
そのため、あなたの志望度合いが面接官に十分に伝わらないと、内定を得るのは難しくなります。
ありがちなのは、企業研究が不足しており、どの企業にも当てはまるような一般的な志望動機を話してしまうケースです。
対策としては、その企業ならではの強みや理念、事業内容を深く理解し、なぜ自分がその企業で働きたいのか、どのように貢献できるのかを具体的に伝えることが重要です。
企業のウェブサイトだけでなく、ニュース記事や業界情報なども積極的に収集し、自分なりの言葉で熱意を表現できるように準備しましょう。
逆質問の機会を活かして、企業の事業や働き方について積極的に質問することも、志望度合いを示す有効な手段です。
企業との相性が悪い
どれだけ優秀な学生であっても、企業の社風や価値観、求める人物像と合わなければ、残念ながら不合格となってしまうことがあります。
これは能力の問題ではなく、あくまで「相性」の問題です。
企業側も、入社後にミスマッチが生じて早期離職につながることを避けたいと考えています。
対策としては、まず自己分析を徹底し、自分がどのような環境で能力を発揮できるのか、何を大切にして働きたいのかを明確にすることが重要です。
その上で、企業のウェブサイトや説明会、OB・OG訪問などを通じて、企業の文化や雰囲気、社員の方々の働きぶりなどをできるだけ具体的に把握し、自分との相性を見極めるようにしましょう。
もし相性が合わないと感じた場合は、無理に合わせようとするのではなく、より自分に合う企業を探す方が双方にとって良い結果につながることもあります。
面接で答えられない時の言い方を対策しよう
ここまで、面接で答えられない時の具体的な言い方や、その原因と対策について解説してきました。
面接で言葉に詰まることは誰にでも起こりうることですが、事前に対策を練っておくことで、そのリスクを大幅に減らすことができます。
大切なのは、正直に、誠実に対応する姿勢です。
そして、万が一答えられない状況に陥ってもパニックにならず、今回ご紹介したような言い方を活用して落ち着いて対処しましょう。
模擬面接を重ね、自己分析や企業研究を深めることが、自信を持って面接に臨むための最大の武器となります。
おわりに
就職活動中の皆さん、面接対策は順調でしょうか。
面接で答えられない質問をされると、誰でも焦ってしまうものです。
しかし、この記事で紹介したように、対処法を知っていれば、ピンチをチャンスに変えることだって可能です。
大切なのは、完璧な回答をすることではなく、あなたらしさを伝え、企業への熱意を示すことです。
面接は、企業があなたを選ぶ場であると同時に、あなたが企業を選ぶ場でもあります。
準備をしっかり行い、自信を持って自分をアピールしてください。
この記事が、皆さんの就職活動の一助となり、面接への不安を少しでも和らげることができれば幸いです。

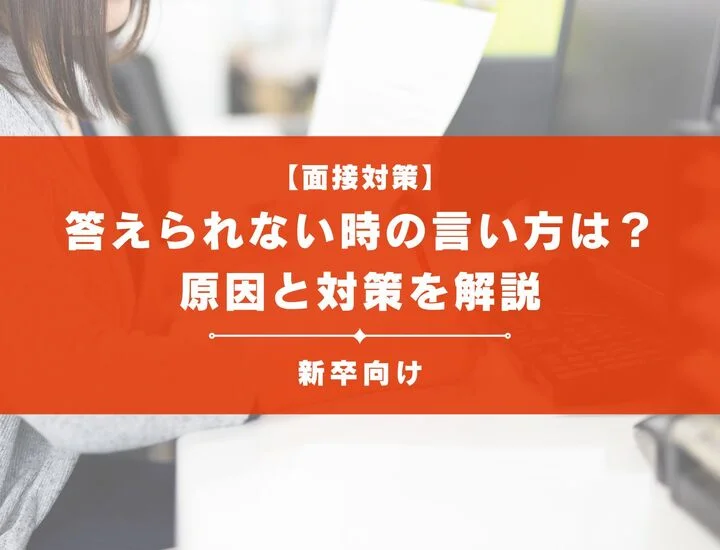



_720x550.webp)




