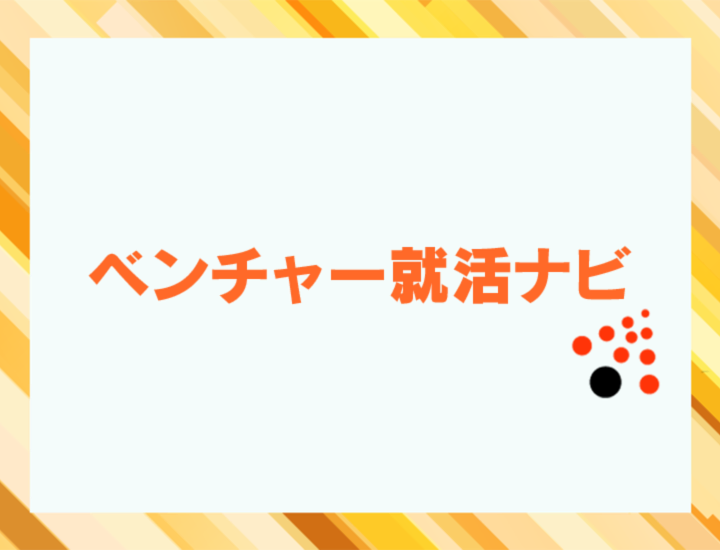明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・公務員インターンの志望動機の書き方
・自治体や官公庁がインターンで学生に期待していること
・志望動機で押さえるべきアピールポイント
・志望動機を説得力のある文章にするコツ
・公務員インターンに応募を検討している学生
・志望動機の書き方に悩んでいる人
・民間企業との違いを意識した志望動機を作りたい人
・他の学生と差をつけたい人
はじめに
インターンと聞くと一般企業が開催するものが多いと思われがちですが、市役所や県庁などの地方自治体が開催するものもあります。
必ず参加しなければならないというわけではないものの、公務員を目指す方ならばぜひ参加しておきたいところです。
そこで今回は公務員のインターンを目指す方のために、志望動機の作成方法について構成や例文などを詳しく紹介します。
なんとなく公務員に興味があるという方から、積極的にインターンに参加したいという方まで、ぜひ参考にしてみてください。
公務員はインターンに参加した方が有利?
結論として、公務員でも一般企業でもインターンに参加した方が有利になることは間違いありません。
仕事への理解が深まり、志望動機や自己PRの練度が高まりますし、面接対策にもつながることでしょう。
選考に影響を与えるかは、その自治体の採用担当者の考え方やインターンの内容、期間などにもよりますが、よほどインターン中に傍若無人な振る舞いをしない限り、マイナスに働くことはないでしょう。
「インターンに参加したから採用確率が30%上がる」など、確実かつ大幅に有利になるとは断定できませんが、参加して損になることはよほどありません。
公務員インターンの種類
- 地方公務員のインターン
- 国家公務員のインターン
公務員のインターンには大きく分けて地方公務員のものと国家公務員のものが存在します。
あなたがどちらのタイプの公務員を目指すかによって、参加すべきタイプは異なってきます。
具体的な学びや取り組みの内容などについて詳しく紹介するため、どちらに参加したいか考えながら読んでみてください。
地方公務員のインターン
地方公務員のインターンは市役所や県庁といった地方自治体で実施されるもので、地域に密着した行政の取り組みを身近に体験できる貴重な機会です。
参加することで住民の生活にどのような形で行政が関わっているのかを理解でき、行政サービスがどのように構想され実行に移されているかを具体的に知ることができます。
地域の課題をテーマにしたグループワークや窓口業務の見学、若手職員との座談会などが行われており、自治体職員としてのやりがいが何か、自分に足りないものは何か明確になるでしょう。
また、地域住民との距離が近い分、生活支援、教育、福祉、産業復興など幅広い分野の業務に触れる機会があり、自分の関心と自治体業務との接点を見つけやすいのも特徴です。
国家公務員のインターン
国家公務員のインターンは各省庁や出先機関において実施されるもので、政策の企画立案や制度設計、法令の運用といった国家規模の課題に取り組む行政の現場を体感できます。
これらのプログラムでは担当職員から業務内容の説明を受けたり、政策テーマに関するディスカッションや書類作成を行ったりすることが多く、法律、経済、国際関係などの幅広い知識を応用する力が求められます。
国家公務員のインターンでは職場ごとの専門性が非常に高く、配属される部局によって体験する内容も異なることになります。
したがって、参加前に各省庁のミッションや重点政策について理解を深めておくことが重要です。
【公務員のインターン】2025年度のインターン情報まとめ
2025年度に開催される主な公務員インターン・職場体験プログラムを、国家・自治体別に網羅しました。
※インターンの実施内容・締切・日程は変更になる可能性があります。必ず各機関の公式サイトで最新情報をご確認ください。
| プログラム名/内容 | 機関 | 締切 | 実施期間 |
|---|---|---|---|
| 総務省インターンシップ2025 | 総務省 | 5/13 | 7/22~9/12 |
| 羽田空港見学プログラム(スプリング) | 出入国在留管理庁 | 5/15正午 | 5/23・5/27 |
| 体験プログラムA〜D | 法務省 | 5/30 | 8~9月(4〜5日間) |
| 学生実務研修 | 北海道庁 | 5/31 | 8/18~9/5のうち約1週間 |
| 夏期インターン(厚生労働省) | 厚生労働省 | 6/2正午 | 7/28~9/26 |
| サマープログラム/データ分析 | 金融庁 | 一次締切6/9、最終7/7 | 8/4~9/10 他 |
| 女子学生霞が関体験プログラム | 内閣官房・人事局 | 6/12 | 9/1~12(2クール×5日) |
| 都庁インターンシップ2025 | 東京都庁 | 6/18正午 | 7/31~9/10 |
| 3daysサマープログラム | 警察庁 | 一次6/25、二次7/16 | 7/30~9/10(コース別3日間) |
| 1day捜査/政策立案プログラム | 警察庁 | 一次6/25、二次7/16 | 8月開催 |
| サマープログラム2025 | 公正取引委員会 | 7/11 | 8/21~22 |
| 入管庁サマープログラム2025 | 出入国在留管理庁 | 7月中(予定) | 8/26~28 |
| 政策立案ワークショップ | 財務省 | 7月中旬(予定)、締切7/14まで | 7/30~8/27 各回3日間 |
| インターンシップ・キャリア実習 | 千葉県庁 | 受付中(大学経由) | 7/1~9/30のうち約1週間 |
| 1week Summer School(政策立案) | 経済産業省 | 6/26 | 7/24~9/3(3期) |
| METI 1DAY仕事体験 | 経済産業省 | 6/17 | 6/24 |
| 参議院法案作成実習 | 参議院法制局 | 7/4 | 夏期(詳細未公開) |
| 県庁インターン(愛知県) | 愛知県庁 | 6/10 | 7月中(部署配属/1週間程度) |
| 県庁キャリア実習(兵庫県) | 兵庫県庁 | 6/13 | 8/18~22 |
| 福岡県夏季インターン | 福岡県庁 | 6/30 | 8月中旬~9月中旬 |
| 原子力規制委員会体験 | 原子力規制委員会 | 7/11 | 8/18~29(1〜2週間) |
| 防衛省事務・技術ワークショップ | 防衛省 | 7/31 | 7/15~9/3 各期3日間 |
| 防衛装備庁ワークショップ | 防衛装備庁 | 7/31 | 8月下旬 |
| 会計検査院体験プログラム | 会計検査院 | ~8/8 | 8/20~21 |
| 環境省本省/地方プログラム | 環境省 | 本省6/16、地方7/14 | 8/18~9/19 |
| サマープログラム/データ分析 | 金融庁 | 一次締切6/9、最終(二次)締切7/18 | 8/4~9/10 他 |
| インターンシップ(佐賀県庁) | 佐賀県庁 | 7/3 | 8~9月 |
| インターンシップ(岡山県庁) | 岡山県庁 | 7/11 | 8月~9月 |
| インターンシップ(鳥取県庁) | 鳥取県庁 | 7/9 | 8月~9月 |
| インターンシップ(茨城県庁) | 茨城県庁 | 7/10 17:00 | 8月~9月 |
| インターンシップ(徳島県庁) | 徳島県庁 | 7/25 17:15 | 8/25~8/29 |
| インターンシップ(和歌山県庁) | 和歌山県庁 | 7/14 | 8/1~9/30 |
| インターンシップ(青森県庁) | 青森県庁 | 7/7 | 8月~9月 |
公務員インターンに参加するメリット
- 実際の業務を体験し、公務員の働き方を知れる
- 現場職員との交流でリアルな情報が得られる
- インターン経験が志望動機・面接対策につながる
続いて、公務員のインターンに参加すると得られる可能性が高いメリットについて紹介します。
インターンに参加して良い印象を与えられれば、本選考にも、多少かもしれませんが良い影響を与える可能性はあります。
しかしそれ以外にも3つのメリットが存在するため、ぜひ以下の3点を確認しておいてください。
実際の業務を体験し、公務員の働き方を知れる
公務員のインターンに参加する最大のメリットの1つは行政機関における業務の実態を自分の目で見て体験できることです。
配属された部署で職員と同じ空間に身を置きながら、日々の業務の流れや取り組んでいる内容について知ることができるため、具体的な理解を深められます。
公務員の仕事と聞くと漠然としたイメージしか描けない人も多いですが、インターンに参加することでどのような立場で市民や社会と関わっているのか、どのような判断を下し、どのように行政が機能しているのかが明確になるでしょう。
現場職員との交流でリアルな情報が得られる
インターン期間中には現場で働く職員との交流の場が設けられることが多く、説明会やパンフレットだけでは得られない現場ならではの「生きた情報」に触れられます。
また、若手社員や中堅の方から直接話を聞くことで、入庁の決め手となった要因や配属後のギャップ、仕事のやりがい、働き方の実態など、採用活動ではなかなか知ることができない情報にも踏み込むこともできます。
職場の雰囲気や人間関係、残業の実情など、職員との対話を通して具体的に把握でき、進路選択の参考にもなるでしょう。
インターン経験が志望動機・面接対策につながる
インターンに参加することで得た経験は志望動機や面接での受け答えに説得力を与える要素ともなります。
具体的にどのような業務に触れ、どのような印象を受けたのか、またその中で自分が何を感じ、どう行動したかを言語化することで、他の受験者との差別化が可能です。
自分の言葉で語られた体験は書類上の志望動機や抽象的な説明以上に面接官に伝わりやすく、志望度の高さや職務理解の深さをアピールできます。
また、インターンでの経験を通じて自分の適性を確かめることもでき、本当に公務員として働きたいのかを再確認する機会にもなるでしょう。
ただ参加するだけでなく、振り返りをしっかり行い、自分の言葉でまとめておくことが、その後の選考において重要です。
公務員インターンの志望動機を作成するポイント
- なぜそのインターンに参加したいのか明確にする
- 自分の公務員としての適性を具体的に伝える
- インターン先での経験をどう活かすかを考える
続いて、公務員を目指す人がインターンの志望動機を作成するにあたって意識しておいてほしいポイントについて紹介します。
以下の3点を意識できている方とそうでない方とではインターンの選考通過率は大きく異なってくることでしょう。
重要な項目であるため、読むだけではなく、就活ノートなどを持っているならば、そちらに簡単にまとめておいてください。
なぜそのインターンに参加したいのか明確にする
志望動機を作成する際に最も重要なのは、なぜそのインターンに参加したいのかという動機を明確にすることです。
ただ漠然と「興味があるから」では説得力がありません。
自分がその自治体や省庁のどのような取り組みに関心を持ち、どのような経験を積みたいと考えているのかを言語化しましょう。
インターンを通じて何をやりたいのか、どのような視点で行政を見たいのかといった指針を持つことで、ただの情報収集ではなく、明確な目的意識があることを示せます。
自分の公務員としての適性を具体的に伝える
公務員インターンの志望動機では自分が公務員としてどのような適性を持っているのかを伝えることも重要な要素となります。
性格的な特性をただ述べるだけでなく、過去の具体的な経験をもとに説明することで、説得力を高められます。
継続的に取り組むことが得意である、ルールを守りながら柔軟に対応できる能力があるなどの場合、公務員としての資質が高いと評価されるでしょう。
このように、自分の特性と公務員の職務内容との関連性を説明し、自分がなぜ公務員の仕事に向いているのかを考えることが、相手が納得できる説明をする上で大切です。
インターン先での経験をどう活かすかを考える
インターンに参加すること自体が目的ではありません。
その経験を通して何を得たいのか、将来にどうつなげていくのかを考えることが重要です。
そのためにはインターン先である自治体や省庁の業務内容や方針を事前に調べておき、自分の関心や学びたいテーマとどのような接点があるかを把握しておく必要があります。
ただ業務内容を知るだけでなく、現場の雰囲気や職員の姿勢にも目を向けることで、インターンを通じて得た気づきや学びを将来の進路選択や公務員試験の準備にどう活かしていきたいかがより明確になるでしょう。
そして、その明確になった目標を志望動機に含めることで、将来をしっかり考えている人物であることが伝わります。
公務員のインターンの選考通過率を上げるコツ
- 結論ファーストで伝える
- インターンでの目的を明確にする
- 企業独自の要素を述べる
公務員のインターン選考に通過するためには、基本を押さえながらも志望動機や自己PRに明確な目的意識と独自性を持たせることが重要です。
以下の3つのポイントを意識することで、通過率を高めることができます。
結論ファーストで伝える
最初に結論を述べることで、論理的で説得力のある印象を与えることができます。
志望動機や自己PRでは、何を考えているのかを最初に簡潔に伝え、その後に理由や具体的なエピソードを続ける構成が効果的です。
面接でも質問に対して、結論、根拠、補足の順に答えることで、話の筋が通り、信頼感が増します。
インターンでの目的を明確にする
そのインターンに応募する理由をはっきりさせましょう。
行政の防災政策に関心がある、地域課題の現場での対応を体験したいなど、自分が学びたいことや成し遂げたいことを具体的にすることで、相手に熱意と意欲が伝わります。
目的が明確であれば、行動にも一貫性が出て、評価にもつながります。
企業独自の要素を述べる
応募先の自治体や省庁の特徴を事前に調べて、それに沿った志望理由を述べましょう。
全国どこでも通じるような一般的な志望動機だけでは印象に残りません。
特定の地域が推進している育児支援や観光政策に関心があるなど、その機関独自の取り組みに触れることで、志望度の高さや調査の丁寧さが伝わります。
よくある公務員インターンの志望理由例
- 市民や住民の支援を通して社会貢献したい
- 地域活性化に関心がある
- 都市開発・まちづくりに携わりたい
続いて、公務員のインターンに参加する人がどのような志望動機を述べるのかについて、具体的な例を紹介します。
以下のような志望理由は言ってしまえば少し「ありがち」ではありますが、悪い印象を与えるものではありません。
内容や表現、エピソードに工夫を加えればいくらでも差別化はできますから、志望動機が思いつかない方はぜひ参考にしてください。
市民や住民の支援を通して社会貢献したい
住民や市民の支援を通して社会に貢献したいという人は非常に多いです。
地方自治体の仕事は教育、福祉、防災、保健など住民の生活に密接に関わる業務が中心となります。
したがって、自分が誰かの暮らしを直接支えられる仕事に携わりたいという価値観を持っている場合は、その思いを根拠ある形で伝えると高く評価されます。
この動機を述べる際はこれまでに人を支える活動に取り組んだ経験や、困っている人を目の当たりにしたことを通じて意識した思いをもとに記述することがおすすめです。
また「インターンを通して現場でどのような支援が行われているのかを学びたい」「自身の将来像と重ね合わせて考えたい」という視点を加えると、現実味のある目標として受け取られやすくなります。
地域活性化に関心がある
地域活性化への関心も、非常に使いやすい志望理由の1つです。
過疎化や少子高齢化といった地域特有の課題を背景に、まちづくりや観光資源の活用、商店街の復興など、地域に根ざした取り組みを進める自治体が増えてきています。
こうした流れの中で、その地域に対する愛着や地域イベントの運営に携わった経験などがある人は、その経験と公務員の業務との接点を意識しながら志望理由を構築すると良いでしょう。
重要なのは「その地域が好きだから頑張る」など曖昧な表現ではなく「地域社会が抱える課題を具体的に理解し、その上で自分がどう関わっていきたいか」という「展望」を語ることです。
都市開発・まちづくりに携わりたい
都市開発やまちづくりへの関心も、公務員を志望する方の間でよく見られる動機です。
道路や公園の整備、交通インフラの計画、防災対策を含む全体の構想など、都市計画に関わる仕事は自治体の中でも大きな役割を担っています。
この分野に関心がある場合は自分が都市空間に対してどのような関心を持っているか、どのような問題意識を持っているかを具体的に示すことが大切です。
建築や地理、都市政策などを学んだ経験や、それに基づくフィールドワーク、また都市環境に興味を持つようになったきっかけがあれば、それらを組み込むことで動機に深みが出るでしょう。
公務員インターンの志望動機の構成テンプレート
- 最初に結論(なぜ参加したいか)を述べる
- きっかけ・背景・エピソードで動機を補強
- インターンを通してどんな学び・将来像を描くか
- 最後にもう一度結論で締める
続いて、志望動機を作成するにあたって覚えておいていただきたい構成のテンプレートを紹介します。
これはインターンに限ったものではなく、本選考を受けるにあたっても活用できるものであり、また、公務員だけでなく一般企業を目指す方でも活用できます。
つまり、覚えてしまえば様々な場面で応用できるものであるため、ぜひこの記事で頭の中に叩き込んでしまってください。
最初に結論(なぜ参加したいか)を述べる
まず文章の冒頭でなぜこのインターンに参加したいのかという結論を明確に伝えることが重要です。
相手は限られた時間の中で多くの応募書類を読む、または就活生と面接をする必要があるため、最初の一言で志望の方向性が伝わる構成にすることが大切です。
また、結論を先に示すことで内容全体の理解もスムーズになり、その後に続くエピソードや将来像とのつながりも掴みやすくなるでしょう。
なぜそのインターンに興味を持ったのか、どのような目的意識を持っているのかといった根幹の部分を冒頭で端的に表現することが大切です。
きっかけ・背景・エピソードで動機を補強
志望動機の核心を述べた後には、その考えに至った背景やきっかけとなる出来事を記述することで、動機に説得力を加えると良いです。
地域の課題に触れた経験や学業・ボランティア活動の中で行政の重要性を実感した体験などがある場合は、それらを言語化することで自分自身の内面に根ざした動機であることが伝わります。
動機の裏づけとして使うエピソードはできるだけ1つに絞り、状況下で自分の考えや、そこから得た学びを丁寧に述べて、読みやすく整理された文章を意識しましょう。
インターンを通してどんな学び・将来像を描くか
次に記述すべきはそのインターンで得たい学び、そして自分がどのような将来を描いているかについての展望です。
ただ「インターンに参加したい」だけでなく、その経験が自身のキャリアや価値観の形成にどうつながるかまで言及することで、あなたのビジョンが伝わります。
事前にインターン先の業務内容や自治体・官庁が取り組んでいる課題を調べておき、どのような観点から学びたいと考えているか示すと、志望動機の具体性が増します。
また、インターンで得た知識や経験を今後の学業、あるいは将来の公務員としての職務にどう活かしたいかを考えているならば、その点も含めると良いでしょう。
最後にもう一度結論で締める
最初に述べた結論を再度確認するような形で締めくくると、構成としてのまとまりが生まれ、印象付けることが可能です。
大量の就活生が応募する公務員のインターンのような場面では特に、一言だけでも構わないので、結論を述べておくとまとまりやすく、相手も忙しい中で内容を理解しやすくなります。
ただし、エピソードや将来像の部分の方が重要であるため、文字数の指定が少ない場合は、必ずしも最後にもう一度結論を述べる必要はありません。
公務員のインターンの志望動機の例文
続いて、ここまで紹介した内容を踏まえた上で、公務員を目指す方の志望動機の例文を地方公務員向けを3つ、国家公務員向けを2つ、技術職と福祉職の公務員向けのものをそれぞれ1つずつ作成しました。
時間に余裕がない方は自分の状況に近いものだけを、余裕がある方はぜひ全ての例文をじっくり読んでみて、ここまでの復習をしてください。
例文①:地方公務員(市民の支援がしたい)
大学時代に市役所主催の高齢者向けスマートフォン講座にボランティアとして参加し、機械の操作に不安を抱える方々に寄り添いながら説明を重ねる中で、少しずつ笑顔や安心を引き出せたことに大きなやりがいを感じました。講座終了後、職員の方が「一つひとつの支援が、このまちの支えになる」と語っていた言葉が心に残っており、その姿勢に深く共感しました。
今回のインターンでは窓口業務などを通じて市民との接し方や対応の工夫を学び、どのように安心感のある行政サービスが提供されているのかを体験したいと考えています。
例文②:地方公務員(地域活性化に関わりたい)
大学では地域社会学を専攻し、過疎地域の商店街を活性化するフィールドワークに参加しました。地域の魅力を発信するイベントを企画・運営し、徐々に住民同士の会話や協力が生まれ、地域全体が活気を取り戻していく様子に触れました。この経験から、まちの持つ力と、それを支える行政の働きに強い関心を抱くようになりました。
貴市が推進されている地域コミュニティ再生の取り組みは私が学んできた内容とも合致sているため、ぜひ現場でより深く学びたいと考えています。
例文③:地方公務員(都市開発・まちづくりに関心がある)
私は大学で都市計画に関するゼミに所属し、再開発事業の住民説明会に参加した経験があります。利便性を高める計画であっても、住民の声を丁寧に拾い上げることが重要であることを実感し、計画と生活者の視点の両立が求められる分野だと感じました。貴市は人口減少を見据えた持続的な都市づくりを進めておられ、住民参加型の取り組みにも力を入れている点に共感しています。
今回のインターンでは都市整備や住環境の改善に関する業務を体験し、現場でどのように市民の声を取り入れて計画が進められているのかを学びたいと考えています。
例文④:国家公務員(法律や制度の仕組みに興味がある)
大学のゼミで生活困窮者自立支援制度を取り上げ、自治体や支援団体への聞き取りを通して、制度が現場でどのように活用されているかを調査しました。その経験から、机上の政策だけでなく、運用面まで見通した制度設計の重要性を感じるようになりました。貴庁は国民生活に深く関わる政策の立案と執行を担っており、現場で何が求められているのかを理解したうえで制度を構築している点に魅力を感じています。
インターンでは実際の政策形成プロセスを間近で学び、法制度と生活との接点についてより実践的な知見を得たいと考えております。
例文⑤:国家公務員(国際的な視点で行政に関わりたい)
大学で国際関係学を専攻し、日本と北欧の福祉制度の比較研究を進める中で、北欧の自治体が取り組む移民支援の実態を知る機会がありました。現地では多文化共生を実現するための丁寧な制度設計や住民への支援体制に触れ、行政が果たす役割の大きさを実感しました。貴庁ではODAや国内の外国人施策にも力を入れておられ、私が学んできた内容を実地で学べる貴重な機会だと考えています。
今回のインターンでは異文化に配慮した政策の立案や運用の考え方を学び、将来に向けて実践的な視点を養いたいと考えています。
例文⑥:技術職公務員(理系の知識を行政に活かしたい)
大学では河川の氾濫リスクを評価するプロジェクトに参加し、地域の安全を守る防災対策の重要性を実感しました。住民や自治体とのやりとりを通じて、技術的な正確さに加え、生活者の立場に立った判断力が必要だと強く感じました。貴庁は防災インフラの整備や老朽施設の再整備といった長期的な課題に取り組まれており、私が目指す分野と一致しています。
今回のインターンでは施設整備や計画策定の現場に触れ、行政における技術系職員の具体的な業務や考え方を学びたいと考えています。
例文⑦:福祉職公務員(子どもや高齢者支援に関心がある)
大学で社会福祉を学び、実習では児童相談所で支援が必要な家庭と接する中で、制度の存在が支援の土台となることを実感しました。また、支援の継続や関係機関との連携が欠かせず、現場では制度の枠組みを超えた柔軟な対応力も求められるとも感じました。貴庁では子育て支援や高齢者の地域福祉に注力されており、現場と制度がつながる支援体制を学ぶには最適な環境だと感じています。
インターンでは福祉分野の行政職員がどのように制度を運用し、生活者に寄り添う支援を行っているのかを体感し、将来の進路を考えるうえでの学びを深めたいと考えています。
公務員インターンの志望動機を書く際の注意点
- 配属希望が叶うとは限らない点を理解しておく
- 募集要件や対象学年に合っているかを確認する
公務員のインターンの志望動機を書くにあたって、覚えておいていただきたい注意点を紹介します。
先ほど紹介したポイントは良い印象を与えるために重要なことですが、以下の2点は「マイナスな印象を与えないために」注意すべきポイントです。
就活は総合点で判断されますから、良い印象を与えるだけでなく、マイナスの印象を与えないためにもぜひ確認しておいてください。
配属希望が叶うとは限らない点を理解しておく
「この部署で、この業務を体験したい」という明確な希望を持っている人も多いでしょうが、全ての希望が通るとは限りません。
インターンの配属先は自治体や官庁側の受け入れ体制、業務量、受け入れ枠などによって決定されるため、事前に希望を出すことはできても、必ずしもその通りに配属されるわけではないのが実情です。
したがって、志望動機を書く際には、あまりにも特定の部署や業務に固執した内容に偏りすぎないようにしましょう。
募集要件や対象学年に合っているかを確認する
これは当然と言えるかもしれませんが、各自治体や官庁によって対象となる学年や学部、専攻、あるいは応募条件に違いがあります。
「大学3年生以上」「法学部、または経済学部に所属している学生」などの制限が設けられている場合もあり、こうした条件に該当しない場合は書類を提出しても選考対象にならず、準備する時間が無駄になってしまいます。
要件を読み飛ばしたまま応募すると、基本的な能力すら欠けていると思われてしまいます。
応募先ごとの募集要項を読み、自分の学年、専攻、希望時期など、条件に合致しているかをしっかり確認することが大切です。
志望動機が思いつかないときの対処法
- 自己分析で「やりたいこと」を深掘りする
- 他己分析で第三者視点の強みを知る
- 志望動機作成に悩んだら就活支援サービスを活用
志望動機の代表例や作成のポイント、注意点などについて紹介しましたが、志望動機自体が思いつかないという方も多いでしょう。
そこでおすすめなのは以下の3つの対策に入念に取り組むことです。
自己PRやガクチカ作成にも役立つものですから、多少時間はかけてでもしっかりと取り組むことをおすすめします。
自己分析で「やりたいこと」を深掘りする
志望動機が思いつかない時は、まず自己分析を丁寧に行うことが重要です。
「何を書けば良いのかわからない」という悩みの多くは「自分が本当に何を望んでいるのかが明確になっていない」ことに起因しています。
自分がどのような価値観を持ち、どのような経験に充実感を覚えたかを振り返れば、目指したい進路や関心のある分野が浮かび上がってくるでしょう。
高校時代、大学生活、アルバイトや部活などで夢中になった経験や、やりがいを感じた場面を具体的に思い出し、そこに共通するテーマを見つけることで、公務員という職業に対する自分なりの意味付けができるようになります。
他己分析で第三者視点の強みを知る
自己分析をしてもあまり納得ができていない、もしくは話すことが思いつかない方には他己分析がおすすめです。
他己分析は家族や友人、信頼できる先輩などに自分について率直な意見をもらう方法で、自分では気づいていない長所や適性を知ることができる点が魅力です。
「なぜその分野が向いていると思うか」「自分の長所は何か」などを質問してみると、意外な視点から自分の特性を言語化してもらえることがあります。
そこから得られたキーワードを手がかりに、なぜ公務員インターンに惹かれるのか、どのように活かせるのかを検討すれば、自分だけでは思いつかなかった視点から志望動機を組み立てられるでしょう。
志望動機作成に悩んだら就活支援サービスを活用
どうしても志望動機が思い浮かばない場合は就活支援サービスや大学のキャリアセンターを活用するのもおすすめです。
キャリアアドバイザーが個別に相談に乗ってくれたり、志望動機の書き方についてアドバイスをもらえたりする環境が整っています。
第三者の専門的な視点を取り入れることで、自分では気づけなかった切り口を提案してもらえることもあるでしょう。
また、就活本番の時期に差し掛かるとキャリアセンターは混み合っていることもあるため、無料で利用できる就活エージェントなどを利用しても良いでしょう。
弊社も就活エージェントを運営しているため、プロに無料で相談したい方はぜひ利用してみてください。
まとめ
今回は公務員のインターンを受けようと考えている方のために、志望動機の作成方法やコツ、注意点、例文などを紹介しました。
インターンに参加することで将来の職場について具体的なイメージができるだけでなく、選考対策に役立つ情報なども得られます。
参加した方が有利なことは間違いありませんから、ぜひこの記事を参考に、インターンの選考を通過できるような質の高い志望動機作成に取り組んでください。
県庁のインターン志望動機はこちらの記事をあわせてご覧ください!