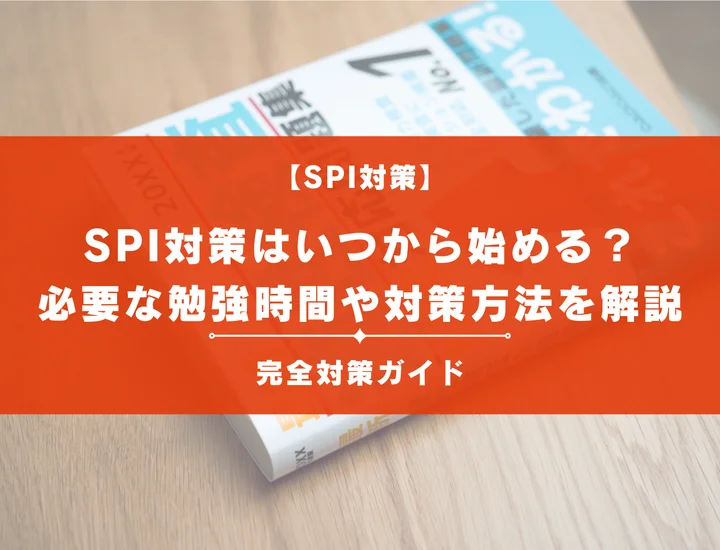明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・SPI対策を始める時期
・SPIの勉強時間
・SPI対策方法
・就活を始めた人
・SPI対策に悩んでいる人
・SPIが選考にある人
目次[目次を全て表示する]
はじめに
就職活動において、多くの企業が初期選考の一つとして導入しているSPI(Synthetic Personality Inventory)。
このSPIの結果次第で、面接に進めるかどうかが決まることも少なくありません。
だからこそ、しっかりとした対策が不可欠です。
しかし、「いつから始めればいいの?」「どんな対策が効果的なの?」と悩む就活生も多いのではないでしょうか。
この記事では、SPI対策の開始時期から具体的な勉強法、さらには性格検査のポイントまで、網羅的に解説していきます。
効率的な対策で、自信を持ってSPIに臨みましょう。
SPIの対策はいつから始める?必要な勉強時間は?
SPI対策をいつから始め、どのくらいの時間をかければ良いのかは、多くの就活生が気になるところでしょう。
ここでは、おすすめの開始時期と必要な勉強時間の目安について解説します。
SPI対策は大学3年生の12月までに始めるのがおすすめ
SPI対策を始める理想的なタイミングは、大学3年生の12月までです。
多くの企業で3年生の3月から本格的にエントリーが始まり、説明会やエントリーシートの作成、面接対策などで忙しくなります。
そのため、比較的余裕のある3年生の秋から冬にかけて対策をスタートすることで、他の就職活動準備と並行しながら、焦らずじっくりと取り組むことができます。
早期に準備を始めることで、SPIへの苦手意識を克服し、自信を持って選考に臨めるようになるでしょう。
SPI対策は最低でも30時間はやっておきたい
SPI対策に必要な勉強時間は、個人の学力や得意・不得意によって異なりますが、一般的には最低でも30時間程度は確保したいところです。
これは、問題の傾向を掴み、一通り解法をマスターするための目安の時間です。
もちろん、より高得点を目指す場合や、苦手分野が多い場合は、50時間以上かかることもあります。
大切なのは、まとまった時間を一度に確保するよりも、毎日少しずつでも継続して学習することです。
「言語問題」「非言語問題」の苦手なほうを重点的に対策したい
SPIは大きく分けて、国語力を測る「言語問題」と、算数・数学的な思考力を測る「非言語問題」があります。
効率的に対策を進めるためには、まず自分の得意・不得意を把握し、苦手な分野を重点的に学習することが重要です。
得意な分野で確実に点を稼ぎつつ、苦手分野の底上げを図ることで、全体のスコアアップを目指しましょう。
問題集を解いてみて、正答率の低い分野や、解答に時間のかかる分野を特定し、集中的に取り組むのがおすすめです。
早期スタートのメリット
SPI対策を早く始める最大のメリットは、基礎から応用まで段階的に学習できる余裕が持てることです。
大学3年の夏から秋頃に学習を始めれば、授業やインターンと両立しながら少しずつ演習を積み重ねることができます。
早めに過去問や模擬試験を解くことで、自分の苦手分野や時間配分の課題を早期に発見でき、改善する時間を十分に確保できます。
また長期的に学習できることで、語彙や計算スピードといった基礎力が自然に身につき、本番に近い環境で繰り返し練習する余裕も生まれます。
精神面でも試験直前に焦ることがなく、安定した状態で本番に臨めるため、得点力だけでなく自信にもつながります。
遅めスタートのリスクと対応策
SPI対策を遅めに始めた場合、短期間で得点を伸ばさなければならず、時間不足が最大のリスクとなります。
特に言語や非言語の計算問題は、解法を理解した後に繰り返し練習してスピードを上げる必要があるため、学習時間が足りないと基礎固めが不十分になりやすいです。
模擬試験を受ける前に本番を迎えてしまうと、自分の弱点を把握できないまま受験することになり、予想外の難問に対応できない可能性が高くなります。
もし学習開始が選考直前になった場合は、まず模擬テストを1セット解き、出題形式を理解したうえで苦手分野を優先して集中的に練習することが効果的です。
短期集中で勉強する際は毎日の学習時間を明確に決め、過去問を繰り返し解いて時間配分を体に覚えさせることで、限られた期間でも合格ラインを狙うことが可能です。
周囲の就活生はいつから始めている?
SPIは多くの企業で導入されているため、就活生にとって避けて通れない試験です。
しかし学業やインターンなどと並行しながら対策を進める必要があるため、いつから始めるべきか迷う人も少なくありません。
周囲がどの時期から準備を始めているのかを知ることで、自分の学習計画を立てる参考になります。
先輩たちの平均開始時期データ
多くの調査やキャリアセンターの聞き取りによると、SPI対策を始める平均的な時期は大学3年の夏から秋にかけてが最も多いとされています。
夏のインターン選考が一段落する7月から9月にかけて学習を開始する学生が多く、この時期に始めることで本選考が始まる翌年春までに十分な時間を確保できます。
早い学生では大学2年の冬や3年の春から基礎問題に取り組むケースもあり、時間に余裕を持って段階的にレベルを上げることが可能です。
一方で冬まで学習を始められなかった学生も一定数おり、その場合は短期集中で過去問や模擬試験を繰り返し解いて合格ラインを目指す傾向があります。
全体としては3年の夏から秋に着手する学生が全体のほとんどを占め、早く取り組んだ学生ほど安定した得点を取りやすいという結果が見られます。
文系・理系で異なる開始傾向
文系学生は夏から秋にかけて早めに対策を始める傾向が強く見られます。
これは文系就活が総合職を中心に早期選考が進む企業が多く、SPIが本選考の初期段階で課されることが多いためです。
一方理系学生は研究や実験が忙しいことから、秋以降や冬休み頃に本格的に学習を始めるケースが目立ちます。
理系は推薦や大学院進学を検討する学生も多く、SPIが必要となる時期が人によって異なるため、開始時期に幅があります。
ただし理系でも一般選考を受ける場合は、遅くとも冬前には基礎演習を始めておくことで安心して試験に臨むことができます。
文系理系にかかわらず、早めに模擬試験を受けて弱点を把握しておくことが安定した得点につながります。
インターン経験者と未経験者の差
インターンに参加した経験がある学生は、選考でSPIを早く受験する機会があるため、対策を始める時期も早くなる傾向があります。
夏の早期インターンではSPIを課す企業も多く、参加した学生は3年の春から初夏にかけて基礎学習を始めるケースが多く見られます。
早期に実際の試験を体験することで自分の課題を把握でき、その後の本選考に向けた対策を計画的に進めやすくなります。
一方でインターン未経験者はSPIを本選考で初めて受験することが多く、対策を始めるのが秋以降に集中する傾向があります。
その場合は短期間で得点を伸ばす必要があるため、無料教材を活用した集中学習や模擬試験を使った時間配分の練習を優先的に行うことが効果的です。
選考まであと1週間!SPI対策は間に合う?
選考まで1週間という限られた期間でSPIの対策を始める場合、全ての分野を完璧に仕上げることは難しいですが、出題形式を理解して得点源を優先的に押さえれば合格ラインに届く可能性は十分にあります。
短期間で成果を出すためには、学習範囲を絞り、時間配分を意識した演習を集中的に行うことが大切です。
短期集中で最低限押さえるべき範囲
残り1週間で取り組む場合は、出題数が多く比較的得点しやすい基礎分野を優先します。
言語分野では二語関係、語句の意味、長文読解など基本的な語彙力と読解力を問う問題を中心に演習します。
非言語分野では四則計算、割合、表の読み取り、確率など計算スピードを重視した問題が重要です。
これらは出題頻度が高く、解法パターンを覚えれば短期間でも得点を伸ばしやすい分野です。
性格検査は事前練習で形式に慣れることが大切ですが、時間をかけるよりも素直に回答する姿勢が基本となります。
複雑な推論問題や難易度の高い長文は時間がかかりやすいため、余裕があれば触れる程度にとどめ、基礎問題で確実に得点する方針が効果的です。
模試やアプリを使った学習スケジュール
残り1週間は毎日2時間から3時間を目安に学習時間を確保し、初日は模試形式で全体を体験して出題傾向を把握します。
2日目以降は模試の結果をもとに苦手分野を集中的に演習します。
午前や通学時間にはスマートフォンの無料アプリを使って短文問題や計算問題を解き、夜は1時間から1時間半を使って過去問や模擬試験を行うと効果的です。
3日目と5日目に再び模試を実施し、時間配分と正答率を確認して進捗を測ります。
6日目はこれまでに間違えた問題を総復習し、計算の解法や語彙の理解を確実に定着させます。
試験前日の7日目は新しい問題には手を出さず、模試の解き直しと時間配分の最終確認だけに集中し、体調を整えて本番に備えましょう。
このサイクルを守れば、短期間でも出題形式に慣れ、基礎問題を確実に得点できる状態に仕上げることができるはずです。
SPI対策の流れ
SPI対策を効果的に進めるためには、計画的な学習が不可欠です。
ここでは、具体的な対策の流れを5つのステップに分けて解説します。
Step1.志望企業の出題形式を確認する
まず最初に行うべきことは、志望する企業がSPIをどの形式で実施するのかを確認することです。
SPIには、企業が用意した会場で受験する「テストセンター」、自宅などのパソコンで受験する「Webテスティング」、企業内でペーパーテスト形式で行われる「インハウスCBT」、そしてマークシート式の「ペーパテスティング」といった形式があります。
出題形式によって、問題の傾向や試験時間、電卓の使用可否などが異なるため、事前に企業の採用ホームページや就職情報サイトで確認しておきましょう。
先輩社員に尋ねてみるのも有効な手段です。
Step2.ひと通り問題を解いてみる
次に取り組むのは、市販のSPI対策問題集を一通り解いてみることです。
この段階では、点数に一喜一憂するのではなく、SPIの問題形式や難易度、出題範囲を肌で感じることが目的です。
時間を計って解くことで、現時点での自分の実力や時間配分の感覚を掴むことができます。
Step3.得意・苦手を把握する
問題集を解き終えたら、必ず答え合わせを行い、自分の得意な分野と苦手な分野を明確に把握しましょう。
言語問題では語彙力、読解力、文章構成力など、どの部分で点数を落としやすいのか。
非言語問題では計算問題、確率、推論など、どの単元に課題があるのかを具体的に分析します。
この自己分析が、今後の学習計画を立てる上で非常に重要になります。
Step4.模試を受ける
ある程度学習が進んだ段階で、SPIの模試を受けてみることをおすすめします。
模試は、本番に近い環境で実力を試す絶好の機会です。
時間配分や問題への対応力を確認できるだけでなく、現在の自分の立ち位置を客観的に把握することができます。
多くの模試では、詳細な成績分析や弱点補強のためのアドバイスも提供されるため、その後の学習に活かすことができます。
Step5.隙間時間を有効活用する
SPI対策は、まとまった勉強時間だけでなく、日々の隙間時間を有効活用することも大切です。
通学中の電車の中や、授業の合間、寝る前のちょっとした時間など、10分でも15分でも良いので、SPIの問題に触れる習慣をつけましょう。
スマートフォンのアプリや単語帳などを活用すれば、手軽に学習を進めることができます。
コツコツとした積み重ねが、着実な実力アップに繋がります。
SPIの性格検査の対策は必要?
SPIには能力検査の他に、個人の特性や行動傾向を把握するための「性格検査」があります。
この性格検査について、特別な対策が必要なのかどうか、気になっている方も多いでしょう。
特別な対策は不要!
結論から言うと、SPIの性格検査に特別な対策は基本的に不要です。
性格検査は、個人のありのままの姿を知るためのものであり、企業が求める人物像に無理に合わせようとして嘘の回答をすると、かえって矛盾が生じたり、入社後のミスマッチに繋がったりする可能性があります。
自分を偽ることなく、正直に直感で回答することが最も重要です。
自己分析を振り返るのは必要
特別な対策は不要ですが、事前に自己分析をしっかりと行い、自分自身の価値観や強み、弱み、行動特性などを深く理解しておくことは有効です。
自己理解が深まっていると、質問に対して一貫性のある回答がしやすくなり、より正確に自分の特性を伝えることができます。
エントリーシートや面接対策として行った自己分析を、性格検査の前に一度振り返っておくと良いでしょう。
選考まであと1週間!SPI対策は間に合う?
「気づけば選考まであと1週間しかない!」そんな状況に陥ってしまった場合でも、諦めるのはまだ早いです。
短期間でも効果を上げるための対策は可能です。
まず、全てを完璧にこなそうとするのは避けましょう。
残された時間で最も効率的なのは、頻出分野に絞って集中的に学習することです。
特に、非言語問題の「推論」や言語問題の「語句の意味」など、短期間での対策でも比較的得点に繋がりやすい分野から優先的に取り組みましょう。
次に、問題集の解説を熟読し、解き方のパターンを理解することに重点を置きます。
新しい問題をたくさん解くよりも、1問1問を確実に理解し、類似問題に対応できる力を養うことが大切です。
そして、最も重要なのが時間配分の練習です。
本番と同じように時間を計って問題を解き、どの問題にどれくらいの時間をかけるべきか、見切るべき問題は何か、といった感覚を掴んでおきましょう。
性格検査については、正直にスピーディーに回答することを心がけてください。
残り1週間でも、優先順位をつけ、集中して取り組むことで、SPIのスコアアップは十分に可能です。
最後まで諦めずに、できる限りの対策を行いましょう。
おすすめのSPI対策方法
SPI対策を効果的に進めるためには、自分に合った方法を見つけることが大切です。
ここでは、おすすめのSPI対策方法をいくつかご紹介します。
問題集を繰り返し解く
SPI対策の王道は、やはり問題集を繰り返し解くことです。
1冊の問題集を最低でも3周は解き、全ての問題を完璧に理解することを目指しましょう。
1周目はまず全体像を掴み、2周目で間違えた問題や理解が曖昧だった部分を重点的に復習し、3周目で時間内に確実に解けるように仕上げていきます。
繰り返し解くことで、問題のパターンや解法が自然と身につき、応用力も養われます。
苦手分野は時間をかけて徹底的に対策をする
誰にでも苦手な分野はあるものです。
しかし、苦手分野を放置してしまうと、それが得点の伸び悩みに繋がります。
SPI対策においては、自分の苦手分野を特定し、そこに時間をかけて徹底的に取り組むことが重要です。
なぜ間違えたのか、どうすれば解けるようになるのかを深く分析し、類似問題を数多くこなすことで克服していきましょう。
苦手を得意に変えることができれば、大幅なスコアアップが期待できます。
解説から解法を掴む
問題を解いて答え合わせをする際、単に正誤を確認するだけでなく、解説をじっくりと読み込み、解法を理解することが非常に大切です。
なぜその答えになるのか、どのような手順で解けば効率的なのかを把握することで、他の問題にも応用できる力が身につきます。
特に非言語問題では、公式や定理だけでなく、問題文の読み解き方や立式のポイントを理解することが重要です。
新聞やニュースをチェックする
意外かもしれませんが、新聞やニュースを日常的にチェックすることも、間接的なSPI対策に繋がります。
特に言語問題では、長文読解や語彙力が問われるため、日頃から活字に触れておくことで、文章を読むスピードや理解度が向上します。
また、時事問題に関する知識は、直接的にSPIで問われることは少ないものの、社会人としての一般常識を養う上で役立ちますし、面接対策にも繋がります。
アプリを使って時間を有効活用
近年では、SPI対策用のスマートフォンアプリも数多くリリースされています。
これらのアプリは、移動中や休憩時間などの隙間時間を活用して手軽に学習できるのが大きなメリットです。
一問一答形式でテンポよく問題を解けるものや、苦手分野を重点的に学習できる機能がついたものなど、様々な種類があります。
自分の学習スタイルや目的に合ったアプリを見つけて、有効活用しましょう。
本番前は実戦形式の対策を
試験本番が近づいてきたら、実際の試験と同じように時間を計って問題を解く、実戦形式の対策を取り入れましょう。
テストセンターやWebテスティングなど、自分が受験する形式に合わせて練習することで、時間配分の感覚や、緊張感のある中での問題解決能力を高めることができます。
模擬試験を受けたり、時間を区切って問題集の特定範囲を解いたりするのも効果的です。
まとめ
SPIは、多くの企業で採用されている重要な選考ステップです。
しかし、適切な時期に、正しい方法で対策を行えば、決して乗り越えられない壁ではありません。
本記事で解説したように、大学3年生の12月までを目安に学習を開始し、最低でも30時間以上の勉強時間を確保することをおすすめします。
選考まで時間がない場合でも、諦めずに頻出分野に絞った対策や、時間配分の練習を行うことで、少しでもスコアを伸ばすことは可能です。
問題集の繰り返し、解説の熟読、隙間時間の活用など、自分に合った方法でコツコツと努力を重ねることが、SPI突破への一番の近道です。
この記事が、皆さんのSPI対策の一助となり、自信を持って就職活動に臨めることを心から願っています。