- 志望動機の締めくくりが重要な理由
- 志望同期の最後の締め方
- 志望動機の締めくくりのポイント
- 志望動機の締めくくりのテンプレート
- 志望動機をこれから作成する人
- 志望動機の書き方を知りたい人
- 志望動機の締め方を知りたい人
- 志望動機の例文を知りたい人
志望動機を書き始めた就活生の皆さんは構成や文字数、志望動機の書き始めや締めくくり多くのことに頭を悩ませている人もいるでしょう。
志望動機は、ESや面接において必ず質問されるため、なぜその企業や業界に興味をもったのかを、あらかじめまとめておかなければなりません。
意欲や熱意だけではなく、将来のキャリアプランまで具体的にしておく必要があります。
それらの志望理由をどのようにまとめ、人事に伝わりやすくするために伝え締めくくればいいのでしょうか。
今回は、志望動機の書き方の中でも魅力的な締めくくりについてお伝えします。
目次[目次を全て表示する]
【志望動機の締めくくり】志望動機で人事が見ているポイント
面接において、志望動機は特に重要な評価項目の一つです。
単に「この会社に入りたい」という気持ちを伝えるだけではなく、企業が求める視点を意識した回答をすることが求められます。
面接官は、応募者の志望動機を通じて「志望度の高さ」「人柄」「企業とのマッチ度」を判断します。
- 志望度の高さ
- 人柄
- 企業とのマッチ度
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
志望度の高さ
企業は、最終的に「本当にこの会社に入りたいのか」を確認したいと考えています。
そのため、面接官は応募者の話し方や熱意、企業研究の完成度から志望度の高さを判断します。
単に「第一志望です」と伝えるだけではなく、「なぜこの企業でなければならないのか」を明確に説明することが重要です。
例えば、「貴社の○○という事業に魅力を感じ、△△の分野で貢献したいと考えています」といった具体的な理由を述べることで、企業への関心の深さを伝えることができます。
さらに、「入社後にどのように活躍したいか」という視点も重要です。
志望度の高さを示すためには、「入社後の具体的な目標」や「自分がどのように貢献できるのか」を考え、それを志望動機の中に組み込むことで、より説得力のある回答になります。
人柄
企業は、応募者のスキルや経歴だけでなく、「一緒に働きたいと思える人かどうか」も重要な判断基準としています。
そのため、面接官は志望動機を通じて、応募者の人柄や職場への適応性を見極めようとします。
例えば、「この人と一緒に働くことで、職場に良い影響がありそうか」「チームの一員として円滑にコミュニケーションが取れるか」といった点が評価されます。
そのため、志望動機を述べる際には、自分の価値観や考え方を交えながら、どのような姿勢で働きたいのかを伝えることが大切です。
また、「協調性」「誠実さ」「積極性」などの要素を意識して話すことで、より好印象を与えることができます。
加えて、表情や声のトーンも人柄を判断する要素になります。
企業とマッチしているか
企業は、応募者の人柄やスキルが、自社の文化や働き方に合っているかを確認したいと考えています。
そのため、志望動機を通じて「自社で長く活躍できるか」「応募者の強みが業務で活かせるか」といった点を判断します。
例えば、「応募者の価値観が企業の理念と合致しているか」「仕事への取り組み方が自社のスタイルに合っているか」が評価の対象となります。
そのため、企業研究をしっかりと行い、「自分の考えと企業の方針がどのように一致しているのか」を具体的に伝えることが重要です。
また、「企業が求める人材像」と「自分の強み」を結びつけることで、より説得力のある志望動機になります。
【志望動機の締めくくり】志望動機の締めくくりの役割
- 志望動機の要約
- 企業への熱意を伝える
- 入社後にどう貢献できるかのアピール
志望動機において締めくくりが重要であることはこの後詳しく紹介するのですが、締めくくり自体にどのような役割があるのかについて理解しておけば、より納得できるはずです。
志望動機において締めくくりがどのような役割を果たすのか覚えておきましょう。
志望動機の要約
志望動機の締めくくりはこれまでの説明を簡潔にまとめ、何を伝えたかったのかを明確にする役割を果たします。
面接の中で志望動機を述べる際、面接官は学生がどのような理由でその企業を選んだのか、また自分がその企業にどのように貢献できるのかを知りたいと考えています。
そのため、志望動機の締めくくりではこれまで伝えてきた内容を簡潔にまとめ、面接官が自分の意図を理解しやすくすることが大切です。
特に、締めくくり部分で何を最も強調したいのかを明確に示しましょう。
企業の特長や自分がその企業で実現したいことなどを再度強調することで、面接官に自分の熱意や確固たる意志を伝えることができます。
また、冗長になってしまうと、面接官が伝えたい要点を見失い、印象が薄くなる可能性があるため、要点は簡潔に伝えましょう。
企業への熱意を伝える
志望動機の締めくくりは面接官に自分の熱意を伝える絶好のチャンスでもあります。
志望動機で企業の魅力を説明し、自分がその企業で働く理由を述べてきたわけですが、締めくくりでその熱意を強く伝えることで、面接官に自分の意欲を印象づけられます。
企業に対する熱意を最後に強調することで、面接官に「この人は本当にうちで働きたいのだな」と感じさせることが重要です。
熱意が伝わる締めくくりは面接官に好印象を与え、その後の選考にもプラスに働きます。
入社後にどう貢献できるかのアピール
あなたのスキルや経験が、企業の目標達成や課題解決にどのように貢献できるのかを具体的に示すことで、採用担当者の心を掴むことができます。
単に「頑張ります」と意気込むだけでなく、過去の実績や経験に基づき、「〇〇のスキルを活かし、△△の課題解決に貢献したい」のように、具体的な行動と成果を結びつけてアピールしましょう。
これにより、あなたが企業にとって採用する価値のある人材であるという強い印象を与えることができます。
【志望動機の締めくくり】志望動機の締めくくりが重要な理由
何事においても、理由について納得していた方が取り組みやすいものです。
そこでまずは志望動機において、締め方が重要な理由について紹介していきます。
大きく分けて理由は3つあるので、それぞれ自分の中で納得してから取り組むようにしましょう。
・志望度の高さを印象付けできるため
・人事の記憶に残りやすいため
・志望動機の一貫性を出すため
志望度の高さを印象付けできるため
基本的な構成の所でも触れたとおり、入社後に貢献できることを伝えるのが一般的です。
そのため、締めくくりの部分から「この子を採用してうちのメリットは何なのか」「どんな働き方をするのか」と就活生が働くイメージをします。
したがって、締めくくりの部分で志望度の高さを印象付けよう。
人事の記憶に残りやすいため
志望動機において最後の締め方が重要な理由の一つとして、人事の記憶に残りやすいということが挙げられます。
よほど応募が少なくない限り、または人事に割いている人数が多い企業でない限り、学生のESを全て隈なく読むことはありません。
そこで最初の書き出しと最後の締めの部分が非常に重要になってくるのです。
「企業の印象に残ればそれで良い」というわけではありませんが、就活において合否を左右するのは人事からの印象なので、しっかりと締めの部分はこだわって書きたいところです。
また、基本的には書類審査の後に面接が行われるという流れがほとんどなので、志望動機において印象に残るようなことを書ければ、面接の際に話題に上ることもあります。
よって、さまざまな側面から考えて、人事の評価に残るため最後の締めは非常に重要であると言えるのです。
志望動機の一貫性を出すため
志望動機だけでなく、自己PRやガクチカにおいても当てはまるものではあるのですが、主張が途中でズレている、バラバラなものよりも、一貫しているものの方が印象が良いことは間違いありません。
そこで冒頭の結論部分とエピソードの一貫性を最後の締めの部分で伝え、志望動機にまとまりを作ることが重要になってきます。
まとまりのある文章は読みやすく、人事も他の文章よりしっかりと読み込んでくれることでしょう。
途中に入れるエピソードや問題解決のための工夫は、ただ文字数を埋めるためのものではなく、あなたの魅力を伝えるために重要なものです。
最初は冒頭と最後の部分だけを読むつもりだった人でも、最後の締めが魅力的な場合、一度戻って途中の文章も読んでくれるかもしれません。
【志望動機の締めくくり】最後の締めくくりでアピールできること
最後の締め方によってアピールしたいのは、心からの熱い情熱であり、ゆくゆくは貢献したいといった自分自身の意欲です。
どのようなビジョンに共感し、成長や発展に役立てると思ったのか、また終わりには感謝の言葉を添えると、好印象につながりやすいでしょう。
- 志望度・熱意の高さ
- 意欲の高さ
- どう貢献できるか
- ポテンシャル
志望度・熱意の高さ
志望する企業についてしっかりとリサーチしたうえで、企業に魅力を感じたなら、志望度や熱意の高さを最後にアピールするのが有効です。
その際には具体的な業績などに触れながら、自分が勉強してきたことによる知識や経験が、どう活かせそうかを示しましょう。
これまでの事例だけではなく、将来の課題や新たに取り組もうとしている事業に対しての強い関心や、一員として成し遂げたいという意欲を伝えるのも効果的です。
いずれにしても自身の能力ばかりをアピールするのではなく、その企業にしかないような魅力に触れつつ、適合性をアピールすることが重要です。
ここでこそ自分の夢が叶う場所であるということを上手に伝えられれば、担当者によい印象を与えられます。
意欲の高さ
入社してから自分が達成したいと思っている目標や成果を、具体的に示さなければ意欲の高さはなかなかアピールできません。
業務を通じて成長に貢献したいという漠然としたものではなく、いつまでに成し遂げたいといった時期を明確にしながら目標設定を述べると、強い意欲が伝わります。
さらに自身の行動力をアピールできるエピソードがあれば、それを話題に盛り込むと、目標を達成して貢献できそうな人物であるとの印象を与えられるでしょう。
将来のことだけではなく現在取り組んでいること、例えば貢献するために学校で学んでいる分野などがあれば、それもアピールしてみましょう。
そうすると意欲の高さにぐっと説得力が増して、ライバルと大きく差をつけるきっかけになります。
どう貢献できるか
あなたのスキルや経験が、入社後に企業の具体的なプロジェクトやチームにおいて、どのような付加価値を生み出すのかを明確に示すことが重要です。
あなたがどのようにして企業の成長に直接的に貢献できるかを具体的に述べると良いでしょう。
単なる意欲表明ではなく、過去の成功体験や身につけたスキルを具体的な業務と結びつけ、即戦力として、あるいは長期的に企業に貢献できる人材であることを印象づけることができます。
ポテンシャル
ポテンシャルの高さをアピールするには、熱意を伝えるのと同じように、具体的な実現目標をしっかり示さなければなりません。
さらに、自分がその企業に入社してからどのような価値を提供できるのか、これまでの経験なども踏まえて伝わるように述べましょう。
しかしここで注意しなければならないのは、自分が身につけている能力や他にはない強みを並べるだけでは、効果的ではないということです。
なぜならば企業が求めているのはただ優秀な人材というわけではなく、組織にしっかり貢献できるかどうかを見極めているからです。
どのような分野において自身の能力が発揮できるのか、学校で学んできたことがどの事業で活かせるかを、企業研究を通じて具体的にしておき、自身の価値をしっかりアピールできるようにしておきましょう。
【志望動機の締めくくり】志望動機の締めくくりで伝えるべき内容
- 企業に貢献できること
- 入社後に実現したいこと
- 志望度の高さ
志望動機の締めくくりは、単に文章を終わらせるための部分ではなく、自分がその企業にとってどのような価値を持つのか、どれほど強い志望意欲を持っているのかを示す大切なポイントです。
では、志望動機の締めくくりではどのような内容を盛り込むべきなのでしょうか。
特に重要な3つのポイントについて詳しく解説します。
企業に貢献できること
採用担当者が最も気にするのは、応募者が自社にどのような形で貢献できるかという点です。
企業は利益を生み出し、成長を続けていくために新しい人材を採用します。
そのため、「この人を採用することで、会社にどんなメリットがあるのか?」をイメージしやすく伝えることが、締めくくりの重要な役割となります。
「どのように貢献できるか」を明確にするためには、企業の特徴や事業内容をしっかりと理解し、自分の強みと結びつけることも重要です。
自分がどのような強みを持ち、それを企業の成長にどう活かせるのかを、具体的に伝えることが求められます。
入社後に実現したいこと
企業への貢献を伝えるだけでなく、入社後にどのようなキャリアを築きたいのか、どのように成長していきたいのかを明確に示すことも重要です。
企業は、新入社員が短期的に戦力となるだけでなく、長期的に活躍し続けることを期待しています。
そのため、自分の将来像を具体的に語ることで、成長意欲が高く、企業とともに歩んでいく意思があることをアピールできます。
入社後の目標を述べる際には、「短期的な目標」と「長期的な目標」をセットで伝えると、より説得力が増します。
企業ごとに求める人材像は異なるため、事業内容や企業の方針をしっかりと理解し、それに即したキャリアビジョンを示すことが重要です。
単なる「頑張りたい」という意気込みだけではなく、「何をどう頑張るのか」を具体的に伝えることで、より説得力のある締めくくりとなります。
志望度の高さ
企業は、できるだけ志望度の高い人材を採用したいと考えています。
志望度が高い人ほど、入社後も意欲的に働き、企業の成長に貢献してくれる可能性が高いからです。
そのため、「なぜこの企業でなければならないのか」を明確にし、企業の理念や事業内容と自分の価値観が一致していることを伝えることが大切です。
「企業のどの部分に魅力を感じたのか」「どのような点に共感し、自分の価値観と合致しているのか」を明確に伝えることが重要です。
また、他の企業ではなく、その企業だからこそ志望している理由を述べることも重要です。
【志望動機の締めくくり】志望動機の締めくくりの5つの基本ルール
- 断定の形で前向きな表現をする
- 意味のない定型分は避ける
- それまでの内容から飛躍しないようにする
- 入社後のイメージがしやすいようにする
- 自分らしさが出せるように具体性を持たせる
志望動機の締めくくりは、その内容全体の印象を決定づける重要な要素です。
どれだけ魅力的な志望理由を述べたとしても、最後の締め方が曖昧だったり、説得力に欠けたりすると、採用担当者に十分な熱意が伝わらない可能性があります。
また、人は話や文章の最後の部分が強く印象に残る傾向があります。
ここでは、志望動機の締めくくりをより効果的にするための5つの基本ルールについて詳しく解説します。
断定の形で前向きな表現をする
志望動機の締めくくりでは、自分の意志を明確にし、前向きな姿勢を示すことが重要です。
「〜したいと思っています」「〜できればと考えています」といった曖昧な表現では、意欲が弱く感じられ、採用担当者に「本当にこの会社で働きたいのか?」「覚悟が足りないのでは?」という印象を与えてしまう可能性があります。
さらに、前向きな表現を加えることで、採用担当者に「この学生は主体的に行動できる」「意欲的に成長しようとしている」と感じてもらえます。
断定の形を意識しながら、よりポジティブな表現を使うことで、入社後の活躍が具体的にイメージできる志望動機の締めくくりにすることができます。
意味のない定型文は避ける
「頑張ります」「よろしくお願いします」といった定型文は、採用担当者にとって印象に残りにくいだけでなく、「この学生は特に考えていないのでは?」という疑念を生む可能性があります。
志望動機の締めくくりでは、単なる決意表明ではなく、「自分がどう貢献できるのか」「どのように成長していきたいのか」を明確に伝えることが重要です。
特に面接では、短い時間で自己PRを行う必要があるため、無駄な定型文を省き、できるだけ具体的な内容を盛り込むことを意識しましょう。
それまでの内容から飛躍しないようにする
志望動機の締めくくりでは、それまでに述べた内容と一貫性を持たせることが大切です。
採用担当者は、志望動機を通じて「この学生は本当に自社とマッチしているのか?」を見極めようとしています。
そのため、一貫性のある志望動機を作成し、締めくくりで違和感を与えないように注意しましょう。
自分の志望動機を振り返りながら、「なぜその企業を選んだのか」「どのように貢献できるのか」をしっかりとつなげることを意識することが大切です。
入社後のイメージがしやすいようにする
採用担当者が「この学生が入社したら、こういう風に活躍してくれそうだ」と具体的にイメージできるように締めくくることが重要です。
例えば、「まずは営業の基礎を徹底的に学び、3年以内にチームリーダーとして部下を育成できるような存在を目指します」と具体的な目標を述べることで、明確なビジョンを持っていることが伝わります。
入社後のキャリアプランをしっかりと考え、それを端的に伝えることで、採用担当者に「この学生は成長意欲が高い」と評価してもらえる可能性が高まります。
自分らしさが出せるように具体性を持たせる
志望動機の締めくくりは、できるだけ具体的に書くことで、自分らしさを伝えることができます。
ありきたりな志望動機の締めくくりでは、大量のESを読む人事には印象に残らない志望動機になってしまいます。
具体性を持たせることで、自分の強みや個性をアピールしやすくなり、他の応募者との差別化が可能になります。
志望動機の基本的な構成
①就活の軸
②企業に共感した点
③志望動機につながる体験やエピソード
④これまでの体験やエピソードから学んだこと
⑤入社後の貢献の仕方
⑥目指す将来像
といった6つの要素を入れることが重要です。
そして、6つの要素は、企業の特徴に合わせて考えるようにしましょう。
就活の軸は「企業選びにおいて、自分の中で絶対に外せない条件」のことで、企業に共感した点はそのままの意味で、企業の目標やビジョンなどに共感したことについて触れます。
「体験やエピソード」では、志望動機を抱くに至った経緯、「学んだこと」や、どのようなスキルや長所を身につけたのかについて話します。
また、「入社後の貢献の仕方」の部分では、エピソードから学んだことをどのように就職後活かすのかについて説明し、あなたを採用するメリットについて伝えます。
最後の「目指す将来像」の部分でさらに細かいキャリアの展望について話せれば、さらにその企業で長く働いてキャリアを築いていく意思も伝わります。
志望動機のテンプレについては、こちらの記事で紹介しているため、ぜひ併せて確認してください。
【志望動機の締めくくり】志望動機の締めくくりのポイント
ここまでみてきたように、志望動機の締め方は、自分がアピールしたいことを強調できる最後のチャンスです。
意欲でもポテンシャルでも、どのような内容にしようかある程度定まってきたら、次に相応しい言葉遣いなど、細かい部分に意識を向けるようにしましょう。
- 企業の求めている人材を把握する
- 自分の資質やスキルを業務内容につなげる
- ポジティブな内容で熱意を伝える
企業の求めている人材を把握する
志望動機の締めくくりを効果的に作るためには、企業がどのような人材を求めているのかを深く理解することが欠かせません。
まずは、企業の採用ページや公式サイト、求人情報、企業説明会の資料などをしっかりと確認し、「この企業はどんな人材を必要としているのか?」を把握することが重要です。
さらに、企業の過去の採用実績や、実際に働いている社員のインタビュー記事などを読むことで、より具体的なイメージをつかむことができます。
自分の資質やスキルを業務内容につなげる
自分の資質やスキルがどのように業務内容に活かせるのかを明確に伝えることも非常に重要です。
これにより、面接官は自分が企業にどのように貢献できるかを具体的にイメージしやすくなります。
あなたがプロジェクト管理やチームワークを得意としているならば、それがどのように日常の業務で役立つのかを示すことで、志望動機に説得力を持たせることができます。
自分のスキルが企業が抱える課題やニーズにどのように結びついているのかを示すことがポイントです。
「私の強みは計画性とリーダーシップであり、これを活かして貴社のプロジェクトを円滑に進行させます」といった具体的な表現を使うことで、スキルの実用性が伝わりやすくなるでしょう。
ポジティブな内容で熱意を伝える
ポジティブな内容を伝えることで、自分の熱意を強くアピールできます。
企業が求めるのは、仕事に対して前向きでエネルギッシュな姿勢を持った人材です。
したがって、締めくくりでは自分の熱意や意欲をポジティブに伝えることが非常に重要です。
「これまでの経験を活かしながら、更に成長し、貴社に貢献する所存です」といった表現を使うことで、企業に対する前向きな姿勢を強調できます。
自分が企業でどのように成長したいのか、どのように貢献できるのかをポジティブに述べ、面接官に対して良い印象を与えることが大切です。
また、困難な状況でも前向きに挑戦し、課題に取り組む姿勢を見せることで、ポジティブな印象をさらに強化することもできます。
「どのような課題にも積極的に取り組み、貴社の発展に貢献する所存です」というように、困難を前向きに捉え、解決に向けて努力する意欲を伝えることで、面接官はあなたの強い熱意を感じ取ってくれるでしょう。
【志望動機の締めくくり】志望動機で避けたい内容
志望動機の締めくくりを書く際には、いくつかの注意点が存在します。
以下の2つを意識した上で、企業の採用担当者にマイナスな印象を与えないような締めくくりを書きましょう。
- ネガティブで消極的な言葉
- 抽象的な表現
- 根拠のない誇張
ネガティブで消極的な言葉
ネガティブな表現を避けることは非常に重要です。
面接の際に消極的な言葉を使ってしまうと、面接官に不安や疑念を与えてしまう可能性があります。
企業は前向きで積極的に仕事に取り組む姿勢を持った人材を求めています。
そこで、志望動機で自分をアピールする際にはネガティブな言葉を使わず、どのように企業に貢献したいか、どのような目標を持っているのかをポジティブに伝えることが大切です。
「まだ経験が浅いので、仕事を覚えるのに時間がかかるかもしれませんが、精一杯努力します」といった表現はNGです。
代わりに「新卒で経験が少ない分、学ぶ意欲は誰にも負けません」「早期に業務を習得し、貢献できるよう努力します」といったポジティブな表現を使い、前向きな印象を与えましょう。
抽象的な表現
志望動機の締めくくりでよく見られる失敗のひとつに、抽象的な表現を多用してしまうことがあります。
「御社で自分の強みを活かして活躍したい」「会社の成長に貢献したい」など、一見すると前向きな言葉のように思えますが、具体性が欠けているため、採用担当者には伝わりにくくなってしまいます。
また、「成長したい」「スキルを磨きたい」といった表現も、漠然としすぎているため注意が必要です。
具体的にどのようなスキルを伸ばしたいのか、どのような業務に挑戦したいのかを述べることで、企業が求める人物像とのマッチ度を示すことができます。
締めくくりの部分では、抽象的な表現を避け、できるだけ具体的に「自分がどのように活躍できるのか」「どのような形で企業に貢献できるのか」を伝えることを意識しましょう。
根拠のない誇張
志望動機の締めくくりで、意気込みを強くアピールしようとするあまり、過度な誇張表現を使ってしまうケースがあります。
例えば、「必ず御社のトップ営業マンになります」「世界に通用するエンジニアとして御社をリードします」といった表現は、熱意を伝えたい気持ちから出る言葉かもしれませんが、具体的な根拠がないと逆効果になることがあります。
企業は新卒採用において、応募者の「ポテンシャル」や「成長意欲」を評価しますが、過度に自信を示すだけでは「本当にそれを実現できるのか?」という疑念を抱かれてしまう可能性があります。
大切なのは、「どのような努力をして、それを実現しようとしているのか」を伝えることです。
【志望動機の締めくくり】志望動機の締めくくりテンプレート8パターン
志望動機を聞かれた際にどのように締めればよいのか、よい印象を与えるためのコツを知りたい学生に向けていくつか注意点をみてきました。
ここからは、具体的な文章例を紹介しますので、志望動機を作成するうえでの参考にしてみてください。
貴社の経営理念である〇〇を大切に、私の〇〇の経験を活かして貴社の発展に貢献したいと考えております。
貴社の経営理念である〇〇に共感し、その理念を大切にしながら〇〇の分野で貴社に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。
貴社の経営理念である〇〇を大切にし、〇〇の分野で長期的に貴社の発展に貢献してまいります。
貴社の経営理念である〇〇を大切に、私の〇〇の経験を活かして貴社の発展に貢献したいと考えております。
貴社の経営理念である〇〇に共感し、その理念を大切にしながら〇〇の分野で貴社に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。
貴社の経営理念である〇〇を尊重し、〇〇を通じて貴社の成功に貢献できるよう努めてまいります。
貴社の経営理念である〇〇を大切にし、〇〇の分野で長期的に貴社の発展に貢献してまいります。
貴社の経営理念である〇〇を尊重し、〇〇を通じて貴社の成功に貢献できるよう努めてまいります。
【志望動機の締めくくり】志望動機の締めくくり例文6選
ここからはここまで紹介してきた内容をもとに志望動機の最後の締め方についての例文を紹介していきます。
この記事のおさらいとしても重要なポイントであり、「志望動機の書き出しから何も思いつかない」という方の参考にもなるはずです。
成し遂げたいことを伝える例文
入社後の貢献をアピールする例文
入社への熱意をアピールする例文
個性を印象付ける例文
社風から志望理由をアピールする例文
私自身、これまでの経験の中でチームワークの重要性を深く理解してきました。
特に印象的なエピソードが、大学時代の部活動での経験です。
私は野球部に所属していましたが、ある同級生が授業についていけず、自主勉強のために野球の練習にも参加できていませんでした。
そこで部員一同が力を合わせ、それぞれの得意分野を活かして彼をサポートしました。
この結果、彼は単位を取得でき、野球の練習にも復帰でき、最終的には無事に大学を卒業しました。
この経験から、一人ひとりが互いを支え、共に成長することの価値を強く感じました。
貴社で働く際も、これまで培ってきたチームワークのスキルを活かし、困っている同僚がいれば積極的にサポートし、また自分自身が困難に直面した時は仲間に助けを求めることで、プロジェクトの成功に貢献していきたいと考えています。
事業展開から志望理由をアピールする例文
私は大学で建築を専攻し、その中で特にバリアフリー設計の重要性について深く学びました。
バリアフリーの重要性を学ぶため、私は介護施設でアルバイトをしました。
実際に施設を利用される方々の日常を近くで見る中で、どのような設計が実際に役立つのか、またどこに改善点があるのかを学びました。
貴社は建築と介護の両方に事業を展開しているため、私の学んだ知識と実体験が活かせる絶好の場だと感じています。
大学で培った建築の専門知識とバリアフリー設計への深い理解を用いて、全ての人が安心して生活できる空間を創造し、貴社のさらなる発展に貢献したいと考えています。
【志望動機の締めくくり】業界別志望動機の締めくくり例文6選
業界別の志望動機を解説します。
自分の志望している業界の志望動機を参考にして、志望動機の作成に取り掛かりましょう。
IT業界
広告業界
不動産業界
物流業界
航空業界
化粧品業界
【志望動機の締めくくり】締めくくりでやりがちなNG例文
以下では志望動機の締めくくりでありがちなNG例文をいくつか紹介します。
自分の志望動機文章と比較して問題ないかチェックしてみましょう。
具体性がない
これまでアルバイトでお客様と接する機会が多く、相手の立場に立って考えることを意識してきました。
この経験を活かし、貴社で多くの人に喜んでもらえる仕事をしたいと考えています。
貴社の事業に携わることで、自分の強みを発揮し、会社の成長に貢献していきたいです。
誇張しすぎている
大学時代にデータを基に改善策を考える活動を続けてきたため、課題解決に対する意識が高まりました。
入社後はこの経験を活かし、業界に革新をもたらすような仕事をしたいです。
貴社で新たなビジネスモデルを生み出し、業界のリーダーとして成長することを目指します。
木下恵利

「業界に革新をもたらす」「リーダーとして成長」など、誇張しすぎていて現実味がありません。
面接官に「本当に実現できるのか」と疑問を持たせてしまうため、実現可能な目標を示すことが大切です。
前の内容とつながりがない
この経験を通じて、多くの人と協力しながら目標を達成する大切さを学びました。
そのため、貴社のマーケティング職に興味を持ち、消費者のニーズを把握しながら事業に貢献したいです。
入社後は、新規事業の開発に携わり、グローバルな視点で市場拡大に貢献できるよう努めます。
木下恵利

締めくくりの「新規事業の開発」と、それまでの「地域活性化の経験」に関連性がありません。
面接官に「なぜそうなるのか」と疑問を持たせてしまうため、一貫性のある流れを意識する必要があります。
【志望動機の締めくくり】締めくくりは面接でも重要?
結論として面接でも志望動機を行った後の締めくくりは非常に大切です。
そこで以下の2つのポイントを踏まえた上で、面接において志望動機を話した後うまく締めるための対策について紹介します。
面接でも重要!
「終わりよければ全て良し」といわれるように、最後が良いと全体がよく見えるのは面接でも同じことです。
反対に面接全体の内容が良かったとしても、締めくくりがしっかりしていないと全体の印象が悪くなりかねません。
話の中に重要な話を盛り込むことは重要ではありますが、最初や最後に重要な内容を含めることが最も大切です。
締めくくりが曖昧であったり、ありきたりな表現であったりした場合、曖昧なことしか言わない人物という印象を最後に与えてしまい終わってしまうからです。
全体の印象を良くするためにも、締めくくりの部分を徹底して準備し、具体的かつ前向きな言葉で終わらせるようにしましょう。
逆質問対策も欠かさずに
帰ってくるであろう質問を考えて対策することも、志望動機を締めくくる上で非常に大切です。
最後に将来的に貢献することや将来の展望などについて話した際は、「それを達成するためにはどのようなことをすれば良いですか」と質問されることが非常に多いです。
したがって、あらかじめどのような質問が飛んでくるのかについて考えてから面接に挑むようにしましょう。
これにより質問の内容をある程度想定することができ、スムーズに回答できるようになります。
【志望動機の締めくくり】志望動機を添削してもらおう!
ここまで志望動機の書き方や、志望動機の締め方のコツについて具体的に確認してきました。
読み終わりによい印象を残せるように、具体的なアピールだけではなく、言葉遣いも気にしなければなりません。
活用できるテンプレートを紹介しましたが、いざ書こうとすればなかなかうまくいかないこともあるでしょう。
はたしてこの内容で難関を突破できるのか不安になることもあるはずで、そのようなときには就活エージェントを活用することを検討してみてはいかがでしょうか。
就活エージェントでは志望動機やガクチカの添削に加え、自分に合った企業の紹介を受けることもでき、よい印象を与えるコツなども教えてもらえます。
まとめ
就職活動においては志望動機を仕上げる以外にも、エントリーシートを作成したり面接対策をしたりと、やらなければならないことが盛り沢山です。
それと平行して企業研究を重ねなければならず、限られた時間を効率的につかわなければなりません。
そこで心強い存在となるのが就活エージェントで、まだ活動をはじめたばかりのころから情報収集をサポートしてくれます。
活動に出遅れたと感じる場合などはとくに、積極的に活用してアドバイスをもらうといいでしょう。



_720x550.webp)



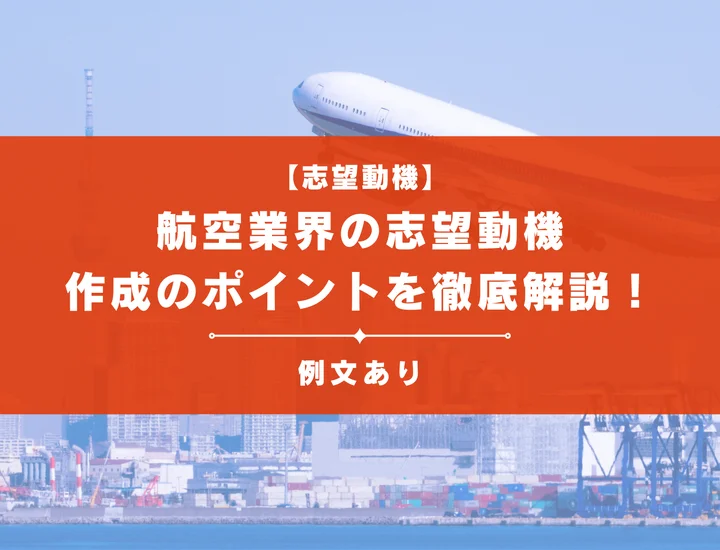
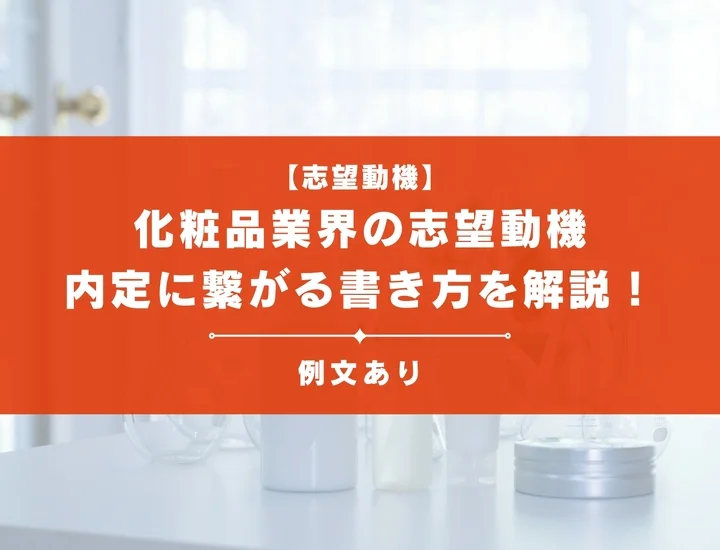


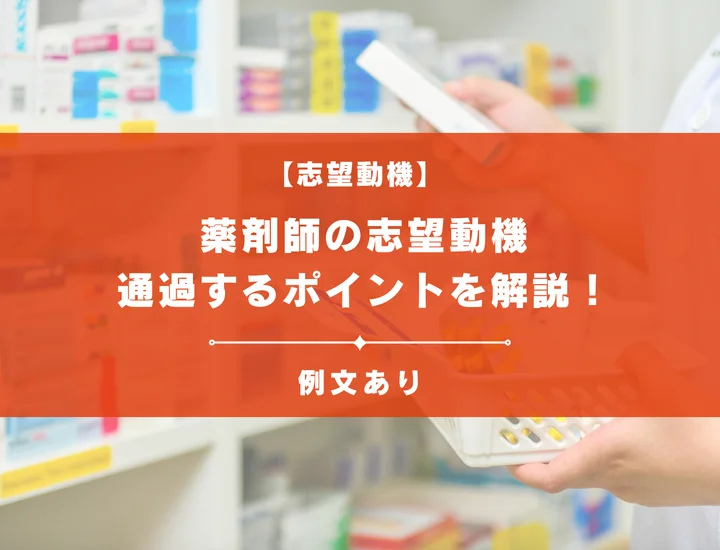
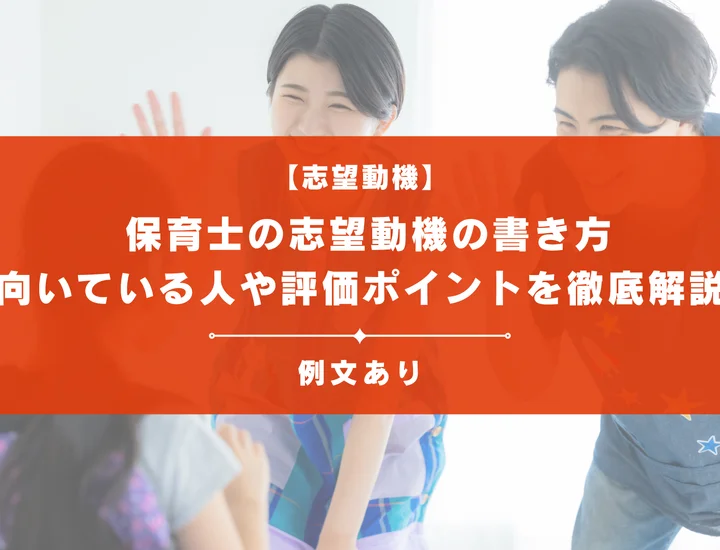





木下恵利
締めくくりの「貢献していきたいです」が抽象的であり、具体的にどのような形で貢献したいのかが分かりません。
「どの業務でどう活かすのか」や「どのような目標を持っているのか」を示すことで、説得力が増します。