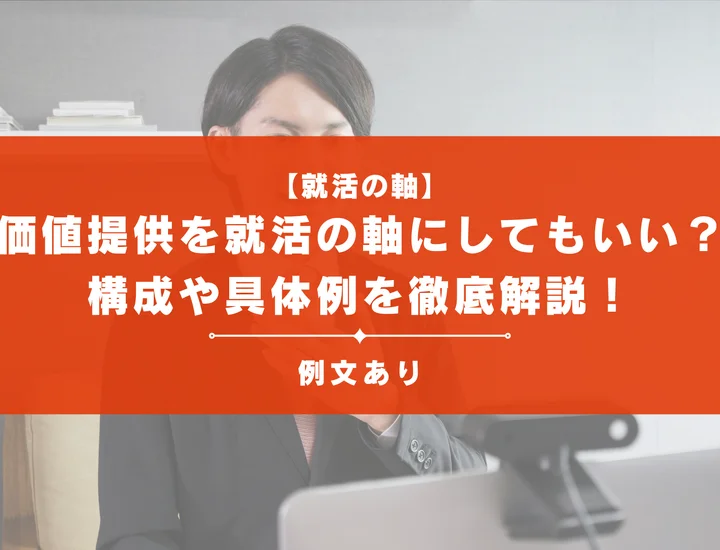明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・デザイン思考テストとは
・デザイン思考テストが就活で重視される理由
・デザイン思考テストの流れ
・デザイン思考テスト対策のコツ
・デザイン思考テストを受けようと思っている人
・デザイン思考テストの対策に悩んでいる人
・デザイン思考テストで高得点を取りたい人
・デザイン思考テストを就活で利用する人
はじめに
「デザイン思考テストってそもそも何?」 「デザイン思考テストのコツは?」
デザイン思考テストとは、ビジネスの課題を解決する「創造的問題解決」の思考法である、デザイン思考力を計測するテストです。
デザイン思考テストでは、固定観念にとらわれず、柔軟な発想力を持つことが求められます。
通常のテストとは特徴が異なるため、学生の中には対策に苦労している方もいるのではないでしょうか。
デザイン思考テストの対策に悩んでいる人は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考とは
デザイン思考とは、デザイナーがデザインを行う際に用いる思考プロセスを、ビジネスや社会の問題解決に応用する方法論です。
ユーザーの視点に立ち、ニーズを深く理解した上で、創造的なアイデアを生み出し、革新的な解決策を導き出すことを目的としています。
直感と論理を組み合わせ、試行錯誤を重ねながら最適な答えを探るアプローチが特徴です。
ビジネスや教育、行政など幅広い分野で活用され、「Design Thinking」とも呼ばれています。
デザイン思考の基本概念
デザイン思考は、利用する人の立場に立って問題を見つけ、より良い解決方法を考えるための考え方です。
進め方は大きく5つの流れがあります。
利用者の気持ちや行動を観察して理解する共感、集めた情報を整理して本当の課題を決める課題定義、自由に多くの案を出すアイデア創出、作った案を形にする試作、実際に試して改良する検証です。
このように何度も試しながら改善していくことを重視し、失敗を恐れずに行動する姿勢が大切です。
論理だけで考えるのではなく、使う人が喜ぶかどうかを想像しながら工夫する点に特徴があります。
またデザイン思考では、最初から完璧な答えを作るよりも、まず小さく形にして試すことを大切にします。
試作を繰り返すことで、利用者が本当に求めていることや自分では気づけなかった課題が見えてきます。
就活課題における特徴と一般的なデザイン思考の違い
就職活動で出されるデザイン思考の課題は、基本の考え方は同じでも進め方に特徴があります。
通常の開発では時間をかけて調査や試作をしますが、就活課題では短い時間の中で結果を出す必要があります。
利用者への共感や課題の整理は短時間でまとめ、限られた情報から素早く方向を決める力が求められます。
チームで話し合いながらアイデアを出すことが多く、提案の完成度よりも発想の広さや論理的な説明力、周囲と協力する姿勢が評価されます。
そのため学生は柔軟に考える力だけでなく、短時間で要点を整理し、分かりやすく発表する力を意識して取り組むことが重要です。
また就活課題では、面接官や審査員が限られた時間で発表内容を理解できるように、簡潔で分かりやすい言葉を使うことが求められます。
長い説明よりも、課題の背景や提案のポイントを一目で伝えられる資料や話し方が評価を左右します。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テスト概要
デザイン思考テストは、デザイン思考のプロセスを応用し、受験者の創造力や問題解決能力を評価するテストです。
ユーザー視点で課題を捉え、革新的なアイデアを生み出す力が求められるため、単なる知識ではなく、柔軟な発想や論理的思考が重視されます。
近年、企業の採用選考や人材育成に取り入れられるケースが増えており、特にイノベーションを推進する企業では、このテストを通じて創造的な人材の発掘や育成が行われています。
実施形式(オンライン/対面)
デザイン思考テストは企業によってオンライン形式と対面形式の2つに分かれます。
オンライン形式は自宅や大学などからパソコンを使って参加する方法で、事前に案内された時間にアクセスして課題に取り組みます。
カメラやマイクを通して面接官が進行を確認する場合もあり、通信環境を安定させる準備が重要です。
画面上で資料を共有したり、チャットを使ってチームメンバーと意見交換をすることもあります。
一方で対面形式は企業や会場に集まり、同じ空間で課題を進める方法です。
その場でメンバーと直接話し合いながら進めるため、相手の表情や反応を見ながら意見を調整できる利点があります。
ただし会場の雰囲気や緊張感が強く、即興で発言する場面が多いため落ち着いて対応する力が試されます。
受験者数や試験時間の目安
デザイン思考テストは企業によって規模や時間が異なりますが、一般的には1回の試験に数人から10人前後が参加します。
個人単位で受験する場合もありますが、多くは3人から5人程度のチームで課題に取り組む形が多く見られます。
試験時間はおおよそ1時間から2時間程度が目安で、課題説明、チームでの話し合い、アイデアまとめ、発表という流れで進みます。
短い時間で問題を整理し、資料を作成して発表まで行う必要があるため、時間配分を意識した練習が欠かせません。
中には半日かけて実施する長時間型の試験もあり、午前中に調査や課題整理、午後に発表という構成を取る企業もあります。
どの形式でも評価されるのは完成度だけではなく、課題を理解する力、論理的に説明する力、メンバーとの協力姿勢など多面的な要素です。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストの目的
デザイン思考テストの目的について紹介します。
このテストは、受験者の創造的思考力や問題解決能力を測ることを目的としています。
単なる知識の有無ではなく、ユーザー視点に立ち、柔軟な発想で課題を解決する力が問われます。
企業では、イノベーションを推進できる人材の発掘や育成のために活用されており、実践的な思考力を評価する手法として注目されています。
創造性
現代のビジネス環境では、常に新しい価値を生み出すことが求められています。
市場の変化が激しく、従来の方法では解決できない課題が増えている中で、創造性の高い人材の存在が重要視されています。
デザイン思考テストでは、単なる知識や論理的思考だけでなく、柔軟な発想や斬新なアイデアを生み出す力が問われます。
創造的な人材は、革新的な製品やサービスを開発し、企業の競争力を高めるだけでなく、社会全体の発展にも貢献することが期待されます。
そのため、多くの企業が採用選考や人材育成の一環としてデザイン思考テストを導入し、創造的な思考ができる人材の発掘や育成に取り組んでいます。
問題解決能力
デザイン思考テストでは、創造性に加えて問題解決能力も重要な評価基準となります。
現代のビジネス環境では、複雑な課題に直面する場面が多く、迅速かつ的確に解決策を見出す力が求められます。
問題解決能力の高い人材は、困難な状況でも冷静に対応し、組織の目標達成に貢献できるため、多くの企業がその能力を重視しています。
このテストでは、受験者が課題の本質を正しく理解し、論理的かつ柔軟な思考で解決策を導き出せるかが問われます。
従来の知識や経験に頼るだけでなく、新しい視点を取り入れ、革新的な方法で課題を解決する力が評価されます。
そのため、問題解決力を高めることが、デザイン思考テスト対策の重要なポイントとなります。
ユーザー視点
デザイン思考テストでは、創造性や問題解決能力だけでなく、ユーザー視点も重要な評価ポイントとなります。
現代のビジネスにおいて、単に製品やサービスを提供するだけではなく、顧客の期待を超える価値を生み出すことが求められています。
そのため、ユーザーの視点に立ち、彼らが何を求めているのか、どのような課題を抱えているのかを深く理解することが不可欠です。
特に、ユーザー自身がまだ気づいていない潜在的なニーズを発見し、それに応じた革新的な解決策を提案できるかが評価のポイントとなります。
デザイン思考テストでは、このようなユーザー視点を持ち、共感を基にした課題解決ができるかどうかが問われるため、受験者には高度な観察力と分析力が求められます。
柔軟性
デザイン思考テストでは、創造性や問題解決能力に加え、柔軟性も重要な評価ポイントとなります。
現代のビジネス環境は変化が激しく、従来の手法では対応できない課題が次々と生まれています。
そのため、変化を恐れず、状況に応じて最適な行動を選択できる柔軟な思考力が求められます。
特に、固定観念にとらわれず、新たな視点を取り入れながら解決策を見出す力が重要視されます。
デザイン思考テストでは、従来の枠組みにとらわれずに発想を転換できるか、変化する状況に適応しながら課題に対応できるかが評価のポイントとなります。
こうした柔軟な思考を持つ人材は、組織の持続的な成長に貢献できるため、多くの企業で注目されています。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストを採用している企業
デザイン思考テストは、多くの優れた企業で採用されています。
このテストを採用している一部の企業には、以下のような名前が挙げられます。
- パナソニック
- 住友商事
- 電通
- 日清食品
- 三井不動産
- 東急不動産
- 味の素
これらの企業は、デザイン思考力や問題解決能力を重視し、それを評価するためにデザイン思考テストを採用しています。
就職活動をする際に、これらの企業に応募する場合は、デザイン思考テストに備えることが重要です。
デザイン思考テストを通じて、自分の創造力やアイデア力を発揮し、企業にアピールしましょう。
総合商社
総合商社はエネルギー、食品、インフラ、デジタル分野など多様な事業を扱い、国内外の幅広い取引先と関わります。
そのため未知の課題を素早く整理し、新しい価値を生み出す力を持つ人材が求められます。
デザイン思考テストでは限られた時間の中で利用者や取引先のニーズを見つけ、実現可能かつ革新的な提案を作る力が試されます。
チームで話し合いながら市場分析やアイデア出しを行い、最後にプレゼンテーションを行う流れが多く、国際的なビジネスを意識した課題が設定されることもあります。
海外事業が多い商社では異なる価値観を持つ人との協力姿勢や、文化の違いを踏まえた柔軟な発想が高く評価されます。
語学力や専門知識よりも、問題の本質を素早く捉え論理的に整理する力が重視されるため、日頃からニュースや国際情勢に触れて視野を広げておくことが有効です。
実際の業務に近い課題が出されることもあり、受験者には実務に近い思考スピードと協調性が求められます。
コンサル
コンサルティング業界は企業や行政の課題を分析し、最適な解決策を提案することが仕事の中心です。
そのためデザイン思考テストでは、論理的な分析力と同時に新しい視点から提案を組み立てる柔軟さが重視されます。
課題の背景を短時間で整理し、数値や具体例を交えながら説得力のある計画を作る力が試されます。
実際の試験では数名のチームでディスカッションを行い、限られた情報から最適な提案を導き出して発表します。
コンサル業務ではクライアントに分かりやすく説明する力が欠かせないため、論理的な構成と簡潔な表現が評価の決め手となります。
面接官はアイデアの独創性よりも、課題の本質をつかみ筋道を立てて解決策を示す力や、他人の意見を引き出しながら議論をまとめる姿勢を見ています。
そのため受験前から新聞記事や企業分析に触れ、短時間で要点を整理する練習をしておくことが有効です。
IT
IT業界は新しいサービスやアプリを次々と生み出す分野であり、利用者目線で課題を見つけ改善する力が不可欠です。
デザイン思考テストでは、ユーザーの行動を想定して課題を整理し、短時間で具体的なサービス案をまとめる能力が求められます。
オンライン形式での実施が多く、画面共有やチャットを活用したディスカッションが中心となる場合があります。
試験課題では新しいアプリの改善案や既存サービスの新機能提案など、実際の業務に近いテーマが出されることが多いです。
短い時間で利用者の体験を想像しながら構想をまとめ、発表まで行うため、論理性と創造性を同時に発揮する力が必要です。
最新の技術や社会の動きを理解しているかも評価の一部となるため、日頃からITニュースや新サービスの情報に触れておくと有利です。
ベンチャー
成長中のベンチャー企業は、新しい市場を切り開く柔軟さとスピード感を重視します。
デザイン思考テストでは既成概念にとらわれない発想や、限られた資源を活かして実現可能な提案を作る力が評価されます。
少人数でのグループワーク形式が多く、一人ひとりの発言量が多くなるため積極的に意見を出す姿勢が必要です。
試験では短時間で課題を理解し、独創性と実行力を両立させた計画を示すことが求められます。
ベンチャーは変化の速い環境に対応できる人材を求めるため、提案内容よりも議論の進め方や思考の柔軟さを重視する傾向があります。
またリーダーシップや挑戦を恐れない姿勢も評価されやすく、チームの議論を活性化させる役割を担える人が高く評価されます。
広告代理店
広告代理店は消費者の心を動かす企画を短時間で形にする力を必要とする業界です。
デザイン思考テストではターゲットの気持ちを読み取り、魅力的な企画をまとめて発表する力が問われます。
課題には新商品の宣伝方法や地域イベントの集客施策など、多様なテーマが出されます。
発想の独自性だけでなく、誰にでも分かりやすく伝える表現力やプレゼンテーションの完成度が評価のポイントとなります。
試験では限られた時間でチームの意見を整理し、印象に残る発表資料を作成する必要があるため、デザインや構成を素早く決める練習が効果的です。
広告業界はトレンドの変化が早く、話題性や人々の感情に訴える提案が好まれるため、日頃からニュースや人気広告に触れて感性を磨いておくと役立ちます。
チーム内での役割分担や意見調整も重要で、他人の意見を尊重しながら自分の考えを分かりやすく発信する力が評価されます。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストが注目されている理由
ここからはデザイン思考テストがなぜ今注目されているのかということについて、その理由を解説していきます。
「なぜ世間から注目されているのか」という背景や理由を詳しく知り、理解することによって漠然とテストを受けるよりもその後に活かしやすくなるでしょう。
就活はあくまで企業に入社するまでの通過点であって、重要なのは企業に入社してからです。
周囲と差別化をし社会人になっても即戦力になれるよう、少しでも興味のある方はぜひチェックしておきましょう。
AI技術が進歩しているから
デザイン思考テストが注目される主な理由は、AIの普及と技術の進化が、労働市場におけるスキル要求を変えているからです。
AIが単純な作業やデータ処理を自動化する中で、人間に求められるのは、機械では代替できない創造性や、複雑な問題解決能力です。
デザイン思考は、ユーザー中心のアプローチを基に、問題を特定し、創造的な解決策を体系的に導き出すプロセスです。
このプロセスは、単に既存の解決策を実行するのではなく、新たな課題を見出し、独自の解決策を創造する能力を測るものです。
そして、今日の高度に変化するビジネス環境において非常に価値があります。
企業は、このような革新的かつ戦略的思考能力を持つ人材を求めており、デザイン思考テストを通じて、これらの能力を持つ候補者を見分けることができます。
VUCAの時代に対応するため
今後のVUCAの世の中に対応していくためという側面もあります。
VUCAは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を組み合わせた言葉です。
これは、現代社会やビジネスの不安定で予測が困難な状況を表します。
このようなVUCA時代においては、確定的で単純な解答やアプローチが通用しないため、目の前の課題に対して柔軟かつ適応的に対応する思考力が強く求められています。
これは、単に既存の知識や技術を適用するのではなく、状況の変化を敏感に感じ取り、新たな課題を迅速に特定し、創造的な解決策を構築する能力を指します。
VUCA時代の企業や個人にとっては、不確実性を受け入れ、複雑な問題を分析し、曖昧な情報から有意義な答えを導くことが求められます。
DX人材ニーズの高まり
多くの企業ではデジタル技術を活用した新規事業や業務改善が急速に進んでいます。
市場環境の変化に素早く対応するため、デジタルとビジネスをつなぐDX人材の需要は年々高まっています。
このような人材には技術知識だけでなく、利用者の視点から課題を見つけ新しい解決策を考える力が求められます。
デザイン思考は利用者の体験を重視して発想を広げる方法であり、DX人材が持つべき姿勢と重なる部分が多いです。
そのためIT企業だけでなく総合商社や金融、メーカーなど幅広い業界が、デザイン思考を理解している人を積極的に評価するようになっています。
就活生にとってデザイン思考を学び実践できることは、DX時代に対応できる人材であることを示す強力なアピール材料となります。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストの特徴
AIを筆頭とするテクノロジーの進化が著しい昨今、私たち人間に求められる価値も大きく変化しています。
これからの時代はAIには代替されない人間の創造性が最も重要になってきます。
デザイン思考テストには受験し、スコアがわかることで創造力をはじめとする目に見えない能力を数値かすることで様々なことがわかります。
そこでデザイン思考テストの特徴について紹介します。
課題発見・解決型人材、DX人材の発掘
現代のビジネス環境は、常に変化し、複雑化しています。
企業が持続的な成長を遂げるためには、従来の枠にとらわれず、新たな視点から課題を発見し、解決策を生み出すことができる人材が不可欠です。
特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためには、テクノロジーを活用するだけでなく、ユーザー視点を持ち、柔軟な発想でイノベーションを創出できる人材が求められています。
デザイン思考テストは、このような時代に求められる人材の潜在能力を評価するために開発されました。
創造性、問題解決能力、ユーザー視点、柔軟性といった、従来の選考方法では見えにくい能力を測定することで、企業は自社のニーズに合致した人材を発掘することができます。
例えば、デザイン思考テストでは、具体的な課題に対して、アイデアを創出し、評価するプロセスを体験します。
この過程で、受験者は自身の創造性や問題解決能力を発揮し、潜在的な能力を明らかにします。
企業は、テストの結果を参考に、従来の選考方法では見落としていた優秀な人材を発掘し、採用することができます。
デザイン思考テストは、企業が競争優位性を確立するために不可欠な、課題発見・解決型人材、DX人材の発掘を強力にサポートします。
客観的なデータに沿った採用・育成が可能
従来の採用選考では、書類選考や面接など、定性的な評価が中心となることが多く、評価者の主観や経験に左右される可能性があります。
また、採用後の育成においても、個々の能力や課題を客観的に把握することが難しく、画一的な研修プログラムになりがちです。
デザイン思考テストは、受検者の能力を定量的に評価し、客観的なデータを提供することで、これらの課題を解決します。
テストの結果は、創造力スコアや評価力スコアなど、具体的な数値で示されるため、企業は採用基準を明確化し、客観的なデータに基づいて人材を選考することができます。
また、テストの結果は、個々の受検者の強みや弱みを把握するための貴重な情報源となります。
企業は、この情報を活用して、個別の育成プランを作成し、より効果的な人材育成を行うことができます。
さらに、組織全体の課題分析にも役立てることができ、組織全体の能力向上に繋げることができます。
デザイン思考テストは、客観的なデータに基づいた採用・育成を可能にし、企業の成長を加速させるための強力なツールとなります。
短時間・低コストで実施が可能
従来の採用選考では、多くの時間とコストがかかることが課題でした。
書類選考、面接、筆記試験など、複数の選考プロセスを経る必要があり、採用担当者の負担も大きくなります。
また、地方や海外からの応募者に対しては、交通費や宿泊費などのコストも発生します。
デザイン思考テストは、オンラインで実施されるため、時間や場所の制約が少なく、多くの受検者を短時間で評価することができます。
受験者は、自宅やオフィスなど、好きな場所でテストを受けることができ、企業は会場の準備や運営にかかるコストを削減することができます。
また、オンライン実施により、人的・時間的なコストを大幅に削減することができ、採用活動の効率化に大きく貢献します。
特に、大規模な採用活動を行う企業にとっては、デザイン思考テストの導入は、コスト削減と効率化の両立を実現するための有効な手段となります。
デザイン思考テストは、短時間・低コストで実施可能であり、企業の採用活動における効率化とコスト削減に大きく貢献します。
評価項目の具体例
デザイン思考を取り入れた選考では、単なるアイデアの独自性よりも課題を理解して形にする過程が重視されます。
評価項目としては、まず利用者の立場に立って情報を整理し本当の課題を見つける力があります。
次にチームで協力して多くの案を出し、限られた時間で優先順位を決める判断力が見られます。
発表の際には自分の考えを分かりやすく伝える表現力や、相手を納得させる論理性も重要です。
また議論の中で他人の意見を尊重しつつ自分の考えを出せる姿勢や、意見が分かれた時に冷静に調整する力も評価対象となります。
試験官は最終的な成果物よりも、課題をどう分析しどのようにチームを動かしたかという行動全体を見ています。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストで高スコアをとるメリット
デザイン思考テストについて「難しそうだから対策も大変そう」と感じている学生もいるでしょう。
しかしデザイン思考テストで高スコアを取ると、学生にとってさまざまなメリットがあります。
ここからはデザイン思考テストで高スコアをとるメリットを紹介します。
特別な企業座談会に招待される
デザイン思考テストで高いスコアを獲得すると、特別な企業座談会に招待されることがあります。
この座談会では、一般的な説明会では得られない貴重な情報が得られるだけでなく、参加者同士での情報交換や交流も行われます。
自身のスキルアップはもちろん、就職活動の優位性にもつながるため、高スコアをとっておいて損はないでしょう。
インターンの参加条件をクリアできる
大手企業の中には、デザイン思考テストをインターンの参加条件としている企業もあります。
このテストで高スコアを獲得することで、企業の要求する課題解決力やアイデア力を証明することができます。
そのため、デザイン思考テストで高いスコアを取ることは、インターン参加のチャンスを手に入れる一歩となるでしょう。
課題解決力を定量的に測定できる
デザイン思考テストは、アイデア力や課題解決力を客観的に測定することができるため、自身の成長を客観的に判断しやすくなります。
就活生として、自身の能力を数字で客観的に把握することは非常に重要です。
またデザイン思考テストを通じて、自分自身の成長度合いを確認できるだけでなく、他の受験者との差を見極めることも可能です。
高いスコアは、自信にもなるでしょう。
本選考への加点・早期選考パスの可能性
デザイン思考テストは本選考に直結することも多く、優れた結果を出した受験者には加点や早期選考への招待が与えられる場合があります。
企業は短時間で課題を解決する姿勢やチームでの働き方を直接確認できるため、他の筆記試験や書類よりも信頼度の高い評価が可能です。
優秀な成績を残すと一次面接が免除されたり、特別ルートで次の選考に進める案内を受けるケースもあります。
また本番での高評価は選考全体においてプラス材料となり、面接官が応募者の発想力や協調性を事前に理解している状態で面接が進むため有利に働きます。
結果を左右するのは得点だけではなく、課題に取り組む姿勢やチームへの貢献度であり、積極的に参加して自分の役割を示すことが大切です。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考のプロセス
デザイン思考のプロセスは、ハーバード大学デザイン研究所のハッソ・プラットナー教授が提唱した5つのステップに分けられます。
このプロセスは、ユーザーのニーズを深く理解し、創造的な解決策を導き出すための枠組みとして広く活用されています。
具体的には、「共感」「問題定義」「創造」「プロトタイプ」「テスト」の5つのステップを順に進めることで、効果的な課題解決を目指します。
共感
デザイン思考のプロセスは「共感」から始まります。
これは、ターゲットユーザーの真のニーズを深く理解することが、その後のすべてのステップの基礎となるためです。
共感のプロセスでは、単にユーザーの表面的な意見を聞くだけでなく、彼らの行動や感情、潜在的な課題に目を向けることが重要になります。
観察やインタビューを通じて、ユーザーの視点に立ち、何が本当に求められているのかを把握することで、より的確な課題設定が可能になります。
この段階で得たインサイトが、革新的なアイデアを生み出すための出発点となるため、共感のプロセスを丁寧に行うことが成功の鍵となります。
デザイン思考では、ユーザーの立場を理解することが最も重要なステップの一つとされています。
定義
デザイン思考のプロセスにおいて、「定義」のステップは、共感のフェーズで得たユーザーインタビューや観察の結果を整理し、課題を明確化する重要な段階です。
このステップでは、収集した情報をもとにユーザーの本当のニーズを深く掘り下げ、解決すべき核心的な課題を特定します。
単なる問題の表面を捉えるのではなく、「なぜこの課題が発生しているのか?」という根本原因を追求することが求められます。
また、必要に応じて再度ユーザー調査を行い、課題の定義が適切かどうかを検証することも重要です。
このプロセスを丁寧に行うことで、次のアイデア創出(創造)のステップがより効果的になり、実用的かつ革新的な解決策を導き出す基盤が築かれます。
概念化
デザイン思考のプロセスにおける「概念化」のステップでは、創造的なアイデアを生み出すことが求められます。
この段階では、課題の定義をもとに、解決策の可能性を広げるために多様なアイデアを出し合います。
特に、質よりも量を重視し、自由な発想でブレーンストーミングを行うことが重要です。
既存の枠組みにとらわれず、斬新な視点や異なる業界の手法を取り入れることで、より革新的な解決策を見つけることができます。
出されたアイデアの中から、実現可能性や影響力を考慮し、最適な解決策を選定するプロセスも含まれます。
概念化のステップを丁寧に行うことで、ユーザーのニーズに寄り添った、実用的で革新的なプロトタイプの開発につなげることができます。
試作
デザイン思考のプロセスにおける「試作」のステップでは、概念化で生み出したアイデアを具体的な形にすることが求められます。
この段階では、完璧なものを作ることよりも、素早くプロトタイプを作成し、アイデアの検証や改良を重ねることが重要です。
簡易的な模型やスケッチ、デジタルツールを活用した試作品を作ることで、アイデアの実現可能性やユーザーへの適合性を確認することができます。
試作を繰り返すことで、新たな発見が生まれ、より効果的な解決策へと発展させることが可能になります。
また、ユーザーや関係者からフィードバックを受けながら改良を加えることで、より実用的で革新的なデザインへと磨き上げることができるのです。
テスト
デザイン思考のプロセスにおける「テスト」のステップでは、試作品を実際にユーザーに試してもらい、フィードバックを収集することが重要になります。
この段階では、試作品がユーザーのニーズに適しているかを検証し、課題が適切に解決されているかを確認します。
ユーザーテストを繰り返し行うことで、予想外の問題点や改善点を発見し、より優れたプロダクトへとブラッシュアップすることが可能になります。
特に、ユーザーのリアルな反応を分析し、試作段階で気づかなかったニーズや不便さを把握することが求められます。
このフィードバックをもとに改善を重ねることで、より高品質で実用的なプロダクトやサービスを生み出し、最終的にユーザーにとって価値のある成果へとつなげることができます。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストの構成
デザイン思考テストは、新しいアイデアを生み出すための有力なツールとして広く活用されています。
このテストは、大まかに「創造セッション」と「評価セッション」の2つのフェーズで構成されており、それぞれにコツがあります。
ここからはデザイン思考テストにおいて成功するための構成を詳しく見ていきましょう。
創造セッション
「創造セッション」は、デザイン思考テストの最初のステップで、与えられた選択肢から選んだシチュエーションにおけるニーズを考えるセッションです。
このセッションは通常、30分の制限時間内で行われ、計200点で採点されます。
具体的な解説を以下に示します。
Who/Where/When
このフェーズでは、いよいよセッションのタイトル通りの創造的な作業が始まります。
まず、あなたは「誰が」「どこで」「どんな時」に関するワードを一つずつ選択し、シチュエーションを構築します。
例えば、「忙しい営業マンが近所の工場で熱心に仕事をしている時」というような具体的なシチュエーションを作り出します。
この際、注意が必要なのは、選択したワードが自然な文脈に組み込まれるように気を付けることです。
これにより、後の段階でアイデアを考える際に、具体的なイメージが容易に浮かび上がるでしょう。
Why
次に、「Why」のフェーズでは、作成したシチュエーションから、ターゲットとなる人々が叶えたいであろう願望を記入します。
ここでは、20字以上120字以内で願望を簡潔に記述します。
例えば、「効率的に相手のニーズを汲み取った提案を行いたい」といった具体的な願望を記述します。
ここではターゲットの願望を簡潔に表現し、アイデアの方向性を明確にします。
What
次に、「What(ワット)」フェーズに進みます。
このフェーズでは、あなたが「Why(なぜ)」で記述した願望を具体的なアイデアや提案に変えるためのステップです。
提案されたワードから「〇〇を」「〇〇する〇〇」を選択し、アイデアを具現化します。
例えば、「提案を」「自動で生成する技術」といった形で具体的なアイデアを考えます。
この際、前段階で考えた願望と一致するアイデアを選ぶことが大切です。
願望とアイデアが一致することで、後のフェーズでの具体的なプランを練りやすくなります。
How
最後に、「How(ハウ)」フェーズでは、具体的な解決策を記入します。
このステップでは、アイデアの実現方法や具体的なプランを簡潔に記述します。
文字数は20字以上120字以内で記述しなければなりません。
例えば、「工場の情報を入力するだけでその企業が抱えていそうなニーズを推測し、それに対応した提案スクリプトを自動生成してくれるAIツールを利用する」といった具体的な解決策を考えます。
評価基準として、アイデアが新しさを持っているか、実現可能性が高いかが考慮されます。
評価セッション
デザイン思考テストは「評価セッション」と「創造セッション」の2つのフェーズで構成されますが、ここからは「評価セッション」に焦点を当てます。
評価セッションでは、他の受験者のアイデアを評価するセッションです。
これも30分の時間が設けられ、計200点で評価を行います。評価は「全くそう思わない」から「非常にそう思う」までの4段階で行います。
前半
前半の評価セッションでは、「Who/Where/When」に基づくアイデアに焦点を当てます。具体的には、アイデアが「Why」すなわち「なぜ」の部分に説得力があり、他の方法では難しい問題に対処するアプローチを持っているかどうかを評価することが求められます。
他の受験者の視点からアイデアを評価し、他の方法との客観的な比較を行うパートです。
後半
後半の評価セッションでは、他の受験者が提案した「What」および「How」のアイデアに焦点を当てます。
独自性のあるアイデアや、他の人が思いつかないような斬新なアプローチは高評価を受けやすいでしょう。
また、アイデアに現実的な実行可能性があるかも判断されます。
このフェーズは、他の参加者から受けた刺激によって、自分のアイデアをより洗練させる機会でもあります。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストのランク一覧
デザイン思考テストにおける評価方法とスコアリングについてどのようなものがあるのか一覧で紹介します。
このテストでは、創造力と評価力の2つの主要な側面に焦点を当てています。
創造力スコアは200点満点、評価力スコアも200点満点で、合計すると400点満点のテストとなっています。
テスト結果に基づいて、参加者のスコアは以下のようにランク別に分類されることが一般的です。
Sランク :受検者の上位5%以内に相当する
Aランク:受検者の上位20%以内に相当する
Bランク: 受検者の上位40%以内に相当する
Cランク :受検者の上位60%以内に相当する
Dランク :受検者の上位80%以内に相当する
Eランク :受検者の下位20%以内に相当する
ただスコアよりも重要なのは、このテストは参加者のデザイン思考能力の現状を把握することに役立つということです。
自分の現在地を把握し、改善に取り組むようにしましょう。
どのくらいのスコアを取ればいい?
デザイン思考テストのスコアに基づくランク分けには、特定のメリットや機会が伴うことがあるので高いほどいいでしょう。
Sランクに位置するスコアは、非常に高いレベルのデザイン思考能力を示しており、多くの企業の採用基準をクリアする可能性が高いと見なされます。
一方、Aランクのスコアを持つ候補者も高い能力を有しており、多くの企業ではこれを高く評価します。
特定の企業の特別座談会やネットワーキングイベントに招待されることもあるでしょう。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストの例題と回答例3選
ここからはデザイン思考テストで実際にどのような問題が出題されるのか気になる方向けに、いくつか例題を紹介していきます。
あくまでここで紹介していく例題は一部ですが、是非これを参考にしてまずは感覚を掴む練習をしおきましょう。
興味がわいてもっと問題を解きたいと思ったら参考書等を買って早速勉強を始めることをおすすめします。
初見では結構難しく見えてしまうかもしれないですが、次第に慣れていくので安心してください。
① 創造セッション
【問題】以下の選択肢から「Who(誰が)」「Where(どこで)」「When(いつ)」を1つずつ選び、シチュエーションを作成してください。
選択肢
Who(誰が)
- 高校生
- ビジネスパーソン
- スポーツ選手
- おじいさん
- 秘書
Where(どこで)
- 駅
- オフィス
- 自宅
- スポーツジム
- 近所
When(いつ)
- 仕事をしているとき
- 掃除をしているとき
- 買い物をしているとき
- 休憩しているとき
- 走っているとき
【ステップ 1】シチュエーションの作成
- Who → ビジネスパーソン
- Where → 駅
- When → 仕事をしているとき
【ステップ 2】願望(Why)の記述
この状況における願望を、「〜したい」「〜が欲しい」という形で表現してください。(20〜120字)
例:「移動中に効率的に仕事をしたいが、満員電車ではパソコンを開けないため、作業スペースが欲しい。」
【ステップ 3】解決策の考案(What & How)
What(技術やデータ):
- AI音声入力技術
- ARデスクスペース
- ノイズキャンセリングシステム
- 作業支援ロボット
- バーチャルミーティングツール
- How(解決策の説明)(20〜120字)
- 「AI音声入力技術を活用し、スマートフォンに話しかけるだけでメモやメール作成ができるシステムを導入する。」
①評価セッション
【問題】以下の解答を4つの評価基準に基づいて評価してください。
創造セッションで提出されたアイデア
- Who(誰が):ビジネスパーソン
- Where(どこで):駅
- When(いつ):仕事をしているとき
- Why(願望):「移動中に効率的に仕事をしたいが、満員電車ではパソコンを開けないため、作業スペースが欲しい。」
- What(技術・データ):AI音声入力技術
- How(解決策):「AI音声入力技術を活用し、スマートフォンに話しかけるだけでメモやメール作成ができるシステムを導入する。」
【評価基準】(4段階評価:非常にそう思う / そう思う / そう思わない / まったくそう思わない)
1. Whoの立場になったときに共感できる内容か?
- 評価例:「非常にそう思う」
- 理由:「満員電車での作業効率化は、多くのビジネスパーソンが抱える課題だから。」
2. 現状、他の方法では実現できていないニーズか?
- 評価例:「そう思う」
- 理由:「スマートフォンのメモ機能はあるが、音声入力の精度や利便性には改善の余地がある。」
3. 新規性が高い解決方法か?
- 評価例:「そう思う」
- 理由:「既存技術の応用だが、満員電車の中での仕事環境に特化した提案は新しい。」
4. ニーズを実現するために有効な解決策か?(技術的な実現可能性を含む)
- 評価例:「非常にそう思う」
- 理由:「既存の音声認識技術を活用すれば、実用化が可能であり、導入コストも抑えられるため。」
②創造セッション
【問題】以下の選択肢から「Who(誰が)」「Where(どこで)」「When(いつ)」を1つずつ選び、シチュエーションを作成してください。
Who(誰が)
- 大学生
- 忙しいワーキングマザー
- 配送ドライバー
- 高齢者
- フリーランス
Where(どこで)
- カフェ
- 自宅
- 公園
- スーパー
- 駅のホーム
When(いつ)
- 勉強しているとき
- 買い物をしているとき
- 子どもを迎えに行くとき
- 配達中
- 待ち時間が長いとき
【ステップ 1】シチュエーションの作成
- Who → 忙しいワーキングマザー
- Where → スーパー
- When → 買い物をしているとき
【ステップ 2】願望(Why)の記述
- 「子どもを迎えに行く前に買い物を済ませたいが、商品選びや会計に時間がかかり、スムーズに終わらない。」(20〜120字)
【ステップ 3】解決策(What & How)
What(技術やデータ)
- AIショッピングアシスタント
- 自動レコメンドカート
- モバイル決済システム
- 画像認識商品スキャン
- 音声入力買い物リスト
How(解決策の説明)(20〜120字)
- 「AIショッピングアシスタントを活用し、買い物リストに基づいて最短ルートを案内し、商品を自動でスキャン・決済できるカートを導入する。」
② 評価セッション
創造セッションで提出されたアイデア
- Who(誰が):忙しいワーキングマザー
- Where(どこで):スーパー
- When(いつ):買い物をしているとき
- Why(願望):「子どもを迎えに行く前に買い物を済ませたいが、商品選びや会計に時間がかかり、スムーズに終わらない。」
- What(技術・データ):AIショッピングアシスタント
- How(解決策):「AIショッピングアシスタントを活用し、買い物リストに基づいて最短ルートを案内し、商品を自動でスキャン・決済できるカートを導入する。」
【評価基準】
1. Whoの立場になったときに共感できる内容か?
- 評価:「非常にそう思う」
- 理由:「子どもを迎えに行く前に時間が限られているワーキングマザーにとって、買い物の時短は大きなニーズだから。」
2. 現状、他の方法では実現できていないニーズか?
- 評価:「そう思う」
- 理由:「セルフレジはあるが、買い物自体の時間短縮には十分ではない。」
3. 新規性が高い解決方法か?
- 評価:「非常にそう思う」
- 理由:「AIを活用し、買い物のルート最適化と決済のスムーズ化を同時に行う発想は新しい。」
4. ニーズを実現するために有効な解決策か?
- 評価:「そう思う」
- 理由:「技術的には可能であり、実装すれば利便性が大幅に向上する可能性がある。」
③創造セッション
【ステップ 1】シチュエーションの作成
- Who → 配送ドライバー
- Where → 住宅街
- When → 配達中
【ステップ 2】願望(Why)の記述
- 「宅配の荷物をスムーズに配達したいが、不在の家が多く、再配達の手間がかかる。」(20〜120字)
【ステップ 3】解決策(What & How)
What(技術やデータ)
- スマートロック連携システム
- AI配達ルート最適化
- 事前通知ボット
- 無人配達ボックス
- QRコード認証受け取り
How(解決策の説明)(20〜120字)
- 「スマートロック連携システムを活用し、許可を得た家の玄関に直接荷物を置ける仕組みを導入する。」
③評価セッション
創造セッションで提出されたアイデア
- Who(誰が):配送ドライバー
- Where(どこで):住宅街
- When(いつ):配達中
- Why(願望):「宅配の荷物をスムーズに配達したいが、不在の家が多く、再配達の手間がかかる。」
- What(技術・データ):スマートロック連携システム
- How(解決策):「スマートロック連携システムを活用し、許可を得た家の玄関に直接荷物を置ける仕組みを導入する。」
【評価基準】
1. Whoの立場になったときに共感できる内容か?
- 評価:「非常にそう思う」
- 理由:「再配達の負担は大きな社会課題であり、配送ドライバーの悩みを解決する。」
2. 現状、他の方法では実現できていないニーズか?
- 評価:「そう思う」
- 理由:「宅配ボックスはあるが、すべての家庭に設置されているわけではない。」
3. 新規性が高い解決方法か?
- 評価:「そう思う」
- 理由:「既存の技術を組み合わせる発想だが、実装されれば新しい宅配の形となる。」
4. ニーズを実現するために有効な解決策か?
- 評価:「非常にそう思う」
- 理由:「スマートロックの技術は確立されており、実用化が期待できる。」
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストの創造セッションで高スコアをとるコツ
デザイン思考テストにおいて、高得点を獲得するためにはいくつかのコツがあります。
以下にそのコツをご紹介します。
デザイン思考のやり方を学ぶ
高いスコアを取るためには、作成の手順やフレームワークを身につけておくことが重要です。
デザイン思考は一見シンプルで方法が無数にある行為を伴うため、より良いアイデアをデザインするための手順を身につけておくことが大切です。
クオリティが高く、そして効率よくデザイン思考を行うことができるでしょう。
今回はデザイン思考で使える一般的な手順を紹介するため、自分に合う形で取り入れてみてください。
1.ペルソナの設定
まずはユーザーの思考を理解し、ニーズを探る必要があります。
ペルソナ、つまりターゲットを設定しましょう。
デザイン思考におけるペルソナは、居住地や職業、家族構成や趣味、悩み、生活スタイルなど、実際に実在する人物であるかのように詳細な部分まで設定する必要があります。
これにより、マーケティングに関わるメンバーの中で共通認識が生まれ、方向性が定まります。
2.コンセプトの定義化
続いてコンセプトを定義化しましょう。
その人物の潜在的な課題やニーズを探ります。
おすすめの手段はカスタマージャーニーマップを作成することです。
これは顧客がある商品やサービスの購入に至るまでの行動や感情の変化、何を考えるのかなどを時系列順に可視化するものです。
ペルソナの情報をもとに、カスタマージャーニーマップを作成していきましょう。
3.アイデア出し
続いてアイデア出しを行います。
ペルソナの持つ課題やニーズを定義した後に、それを解決するための案やアプローチを導き出すのです。
ここで案を出す際はいったん、質にこだわるのではなく量を重視しましょう。
考えつくアイデアは次々と形にし、まずは書き出してみることが大切です。
その後、それぞれのアイデアをまとめて精査していくことで、より適切なアプローチを考えられます。
4.デザインを形づくる
続いてデザインを形作りましょう。
出てきたアイデアを元に、そのアイデアを組み込んだ仮のデザインを作るのです。
実際にプロトタイプを作成することでアイデアを具現化でき、イメージが分かりやすくなります。
ここで重要なのは、長時間かけて細部まで徹底的に作り込むのではなく、まずは一度形作ることです。
これにより完成図を確認し、どのような課題があるのかについて洗い出すことができます。
5.テスト・試算をする
デザインは作成してそこで終わりではありません。
テストや試算を行い、レビュー、改善のサイクルを繰り返していきましょう。
フィードバックをもとに改善することで、より質の高いものを作成できます。
また、テストをする際は施策だけでなく、定義したニーズの方向性があっているのか、アイデアを再び練り直す必要はないかなどについても確認し、より精度の高い製品やサービスを作ることが大切です。
基本的にデザイン思考の実践プロセスは1回実施したら終わりではなく、何度も行うことでより精度の高いものを作り上げることが求められるのです。
誤字脱字に気をつける
デザイン思考テストにおいては、評価をするのは同じ学生です。
そのため、誤字の多い文章は低評価を受けやすい傾向があります。
文章を作成する際には、丁寧に確認し、誤字や脱字がないように注意しましょう。
文章の正確性は評価に影響しますので、文字のミスは意識的になくしましょう。
語尾に気をつける
デザイン思考テストでは、願望についての回答が求められます。
その際には、Why(願望)は、「〜したい。」で終わらせるように注意しましょう。
願望を表現する際には、直接的かつ明確な表現を心がけることがポイントです。
これにより、自身の意図を相手に伝えやすくなります。
自分に近いシチュエーションを選ぶ
デザイン思考テストでは、自分が経験や知識を活かせるシチュエーションを選ぶことが重要です。
自身の得意な分野や興味を持っているテーマを選ぶことで、具体的で実践的な提案がしやすくなります。
また自分の経験や知識を活かすことで、より自信を持って解答することができるでしょう。
タイピングの速度を上げる
デザイン思考テストでは、時間内に多くの質の高い回答を生み出すことが求められます。
回答数が多いほどスコアが高くなるため、タイピングの速度を上げることも重要です。
タイピングの速度を上げるためには、事前にタイピング練習を行ったり、キーボード操作に慣れるための練習をすることが効果的です。
タイピング速度を高めることで、より多くの回答を作成できます。
シチュエーションを設定
デザイン思考テストの創造セッションで高スコアを獲得するためには、アイデアの具体性と独自性を高めることが重要です。
そのためには、単に課題を捉えるだけでなく、具体的なシチュエーションを設定することが不可欠です。
例えば、「買い物が大変」という課題に対して、漠然と解決策を考えるのではなく、「一人暮らしで足腰が弱り、週一度の買い物に苦労する80歳女性」というように、詳細なペルソナを設定します。
年齢、性別、生活環境、抱えている課題などを具体的にイメージすることで、より深くユーザーのニーズを理解することができます。
さらに、課題を多角的に分析することも重要です。
「買い物が大変」という表面的な課題だけでなく、「地域交流の減少による寂しさ」「重い荷物への不安」など、心理面も含めた課題を掘り下げることで、より本質的な解決策を見出すことができます。
具体的なシチュエーションとユーザー願望を明確にすることで、アイデアの具体性と独自性が高まり、評価者にアイデアの必要性を強く印象付けることができます。
創造セッションでは、ユーザーの視点に立ち、共感力を持って課題を捉えることが、高スコア獲得への鍵となります。
適切な技術やデータを選ぶ
デザイン思考テストの創造セッションで高スコアを獲得するためには、設定したシチュエーションとユーザー願望に基づき、最適な技術やデータを選定することが重要です。
アイデアの実現可能性を高めるだけでなく、使いやすさや安全性、倫理面への配慮も求められます。
技術選定においては、最新技術だけでなく、既存技術の組み合わせや地域特性に合わせたローテクな解決策も有効です。
例えば、高齢者向けの買い物支援サービスを考える場合、ドローン配送のような最先端技術だけでなく、地域の商店と連携した宅配サービスや、近隣住民によるサポートシステムなど、現実的で持続可能な解決策も検討する価値があります。
また、技術選定では、実現可能性だけでなく、使いやすさや安全性、倫理面への配慮も重要です。
特に、個人情報を扱う場合には、プライバシー保護に十分な対策を講じる必要があります。
データ選定においては、収集・分析・活用方法を具体的に説明することが求められます。
オープンデータやセンサーデータなど、多様なデータを組み合わせることで、より精度の高い解決策を生み出すことができます。
創造セッションでは、技術やデータの選定において、実現可能性と倫理的配慮を両立させることが、高スコア獲得のために不可欠です。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストの評価セッションで高スコアをとるコツ
続いて、デザイン思考テストの評価セッションで高スコアを取るためのコツについても理解を深めておきましょう。
以下の2点を意識しながら作成することで、より質の高い回答を作成でき、より良い印象を与えられます。
迷ったら直感で回答しよう
迷ったら直感で回答することもデザイン思考テストにおいては非常に重要なことです。
評価セッションにおいては考えてる時間が多くありません。
したがって、迷ったら直感で回答することを意識しましょう。
その際、他の学生も同じように迷っている可能性が高いため、無難に「そう思う」もしくは「そう思わない」など、簡潔に回答することをおすすめします。
回答のバランスを大事にしよう
回答のバランスを大事にすることも意識しましょう。
基本的に「非常にそう思う」を多く、「全くそう思わない」を少なくするのがベストです。
共感が大事であるため、良いアイデアに対しては共感力をアピールするために「そう思う」を選択するようにしましょう。
迷ったら真ん中の2つのいずれかを選択し、誤字脱字がある場合などは低評価を選択することをおすすめします。
評価セッションも手を抜かない
繰り返しになりますが、デザイン思考テストには、創造セッションと評価セッションの2つのセッションがあります。
評価セッションでは、同じ時間帯にテストを受けた他の受験者の提案を評価することが求められます。
評価セッションでは、他の受験者との類似性が高いかどうかで評価されます。
真剣に他の受験者の提案内容を見定め、手を抜かずに客観的な視点で評価しましょう。
複数の基準に基づいてアイデアを評価
デザイン思考テストの評価セッションは、アイデアの価値を多角的に評価し、本質的な価値を深く理解するための重要な機会です。
単にアイデアの良し悪しを判断するだけでなく、評価基準を理解し、客観的な視点を持つことが求められます。
評価セッションでは、アイデアの共感性、新規性、実現可能性、有効性など、複数の基準に基づいて価値を評価します。
共感性は、アイデアがユーザーニーズにどれだけ寄り添っているかを評価する基準です。
ユーザーの課題や願望を深く理解し、共感に基づいたアイデアであるかを判断します。
新規性は、アイデアの独自性や革新性を評価する基準です。
既存のアイデアとの差別化や、新たな視点からのアプローチがなされているかを評価します。
実現可能性は、アイデアが技術的、経済的、社会的に実現可能であるかを評価する基準です。
アイデアの実現に向けた具体的な計画や、課題解決のための実行可能性を判断します。
有効性は、アイデアが課題解決にどれだけ貢献できるかを評価する基準です。
アイデアの導入によって、ユーザーや社会にどのような影響を与えるかを予測し、その効果を判断します。
これらの基準を総合的に判断し、アイデアの本質的な価値を深く理解することが重要です。
客観的なデータや根拠に基づき、論理的に思考することが求められます。
評価セッションを通じて、アイデアの価値を見抜く力を養い、自身の評価能力を高めることができます。
他の受検者の視点を理解する
デザイン思考テストの評価セッションは、多様なアイデアに触れることができる貴重な機会です。
他者の視点を理解することで、自身の視野を広げ、多角的な視点を養うことができます。
評価セッションでは、他の参加者が考案した様々なアイデアに触れることができます。
それぞれのアイデアには、考案者の個性や発想力が反映されており、多様な視点からのアプローチを学ぶことができます。
他者のアイデアを評価する過程で、優れたアイデアを見抜く力や、改善点を見つける力を鍛えることができます。
アイデアの背景にある思考プロセスや意図を理解することで、自身のアイデアをより洗練させるためのヒントを得ることができます。
評価セッションは、単に優劣をつける場ではありません。
建設的な議論を通じて、自身の評価能力を高めることが重要です。
他者のアイデアの良い点を見つけ、積極的に評価することで、自身の視野を広げることができます。
また、他者のアイデアに対する質問や意見交換を通じて、自身の理解を深めることができます。
評価セッションは、多様な視点から学び、自身の成長に繋げるための貴重な機会です。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストのおすすめの対策方法
デザイン思考テストにおいては、豊かなアイデアを出すことが求められます。
デザイン思考力は、日常生活でも、アイデアの蓄え方を工夫することで鍛えることができます。
ここからはデザイン思考テストのおすすめの練習方法を解説します。
日常的な習慣の確立
デザイン思考テストの対策として、日常的な習慣の確立が効果的です。
デザイン思考力は、特別なスキルではなく、日々の生活の中で養うことができます。
そのため、普段から「なぜ?」と疑問を持ち、物事の背景や本質を探る習慣をつけることが重要です。
また、「もし~だったら?」と仮説を立てて考えることで、創造的な発想力を鍛えることができます。
さらに、周囲の人々の行動や会話を観察し、彼らのニーズや課題を推測することで、共感力を高めることも有効です。
これらの習慣を意識的に取り入れることで、柔軟な思考や新しい視点を持つ力が養われ、デザイン思考テストにおいてもより実践的な解答ができるようになります。
アウトプットと評価の反復
デザイン思考テストでは、単にアイデアを出すだけでなく、それを具体的に表現する力も求められます。
そのため、日常的にアイデアを絵や図で表現する習慣を身につけることが重要です。
言葉だけでは伝わりにくい概念も、視覚的に表現することで分かりやすくなり、より効果的にアイデアを伝えることができます。
また、作成した図やスケッチを客観的に評価し、改善点を見つける練習をすることで、論理的な思考力やプレゼンテーション能力も向上します。
ノートに日々アイデアを描き出したり、簡単なプロトタイプを作ることで、表現力が磨かれます。
こうした習慣を継続することで、デザイン思考テストにおいてもより実践的で魅力的な解答ができるようになります。
思考力の向上
デザイン思考テストでは、創造力だけでなく論理的な思考力も重要な評価ポイントとなります。
そのため、日常的に思考力を鍛えることが効果的です。
例えば、パズルや論理クイズを解くことで、筋道を立てて考える力を養うことができます。
また、さまざまな情報に批判的に触れ、自分の意見を持つ習慣をつけることで、柔軟な発想力を高めることが可能です。
一つの視点に偏らず、異なる立場や背景を持つ意見を比較検討することで、思考の幅を広げることができます。
さらに、課題に対して「他にどんな解決策があるか?」と自問し、複数のアプローチを考える訓練をすることで、デザイン思考テストに求められる柔軟な発想力と論理的思考力を同時に強化することができます。
デザイン思考の実践
デザイン思考テストの対策として、学んだ知識を実践に移すことが重要です。
デザイン思考は理論だけでなく、実際に使いながら体得することで、より深く理解できます。
例えば、日常生活の中で不便に感じることや身近な課題をテーマに、デザイン思考のプロセスを試してみるのも効果的です。
「共感」「定義」「概念化」「試作」「テスト」のステップを意識しながら解決策を考えることで、実践的な思考力が養われます。
また、ワークショップやデザイン思考に関するイベントに参加し、他者と協力しながらアイデアを形にする経験を積むことも有効です。
こうした実践を重ねることで、テスト本番でも柔軟で論理的な発想を発揮しやすくなります。
事前練習に使える無料ツール・模擬問題集
デザイン思考の練習には無料で利用できるオンラインツールや模擬問題集が役立ちます。
オンラインホワイトボードサービスでは複数人で同時に意見を書き込みながら整理でき、実際の試験に近い形で発想を広げる練習ができます。
大学や就活支援サイトが公開している模擬問題集を活用すれば、課題定義から発表までの一連の流れを体験できます。
また企業のインターンシップや学生向けイベントでは、デザイン思考をテーマにしたワークショップが無料で開催されることもあります。
これらを積極的に活用し、短時間で情報を整理して意見をまとめる経験を積んでおくと、本番でも落ち着いて対応できます。
友人や同級生と練習することで、他人の意見を取り入れる力やチームでの役割分担を体感できる点も大きなメリットです。
【デザイン思考テストのコツとは??】デザイン思考テストのよくある失敗とその対処法
デザイン思考テストでは、いくつか学生がやりがちな失敗があります。
失敗とその対処法について考えながら、デザイン思考テストのコツを身につけていきましょう。
アイデアが思い浮かびません
アイデアが浮かばないと感じた場合、まずは練習を重ねることが大切です。
前述したように、5dなどのツールを使ってデザイン思考をトレーニングし、異なる視点からアプローチできるようになります。
また、評価セッションの際に他の学生のアイデアを注意深く見て学ぶことも効果的です。
他の人のアイデアからのインスピレーションは、新しいアイデアを生み出す手助けになるでしょう。
評価セッションが時間内に終わりません
評価セッションが時間内に終わらない場合、事前に1問にかける時間を設定しておくことが重要です。
制限時間内に評価が行われた内容のみがスコア算出の対象となるため、時間が足りないと感じた場合でも、多少強引にでも評価を終了させるべきです。
焦らずに的確に評価を行い、時間の制約に対応しましょう。
また、時間配分を改善するための練習も行うことで、効率的な評価セッションが行えるようになります。
スコアは選考にどれくらい影響するの?
デザイン思考テストが就職活動における選考プロセスに与える影響は、実際には企業によって大きく異なります。
一部の企業では、このテストが選考の中核的な部分を占める可能性がある一方で、他の企業では補足的なデータとして活用されるかもしれません。
しかし、多くの場合、デザイン思考テストは選考対象の一つとして含まれ、特に創造力や問題解決能力、革新的な思考を重視する職種や業界で重視されます。
ただし、他の選考要素も同様に重要であり、総合的なパフォーマンスが最終的な採用の決定において重要なことは覚えておきましょう。
スコアは使いまわせるの?
デザイン思考テストには、企業固有の団体テストと、公式機関が定期的に実施する公開テストの二つの形式が存在します。
公開テストに参加し得たスコアは、その信頼性と公平性から、一部の企業において就職活動の一環として使い回すことが可能です。
これにより、複数の企業への応募において、自らのデザイン思考能力を証明する有力な資料として使いまわすことが可能です。
ただし、各企業の選考基準は異なるため、スコアの活用にあたっては、企業の要求や選考プロセスに適した形で提示することが重要です。
結果が開示されないのはどうして?
公開テストはテスト終了後、通常5日以内に結果が開示されます。
一方、企業固有のテストの場合、結果の開示は企業ごとに異なり、時には結果が開示されないこともあります。
これは、各企業の選考プロセスやポリシーによるもので、受験者は各企業の方針を理解し、それに応じた対応をする必要があります。
このため、テスト受験時は、結果開示に関する企業のポリシーを事前に確認することが望ましいでしょう。
チーム内で意見が衝突した時の対処法
デザイン思考テストでは複数人が限られた時間で話し合うため、意見がぶつかることは珍しくありません。
衝突が起きた時に感情的にならず、相手の意見を最後まで聞く姿勢を持つことがまず大切です。
次に自分の考えを簡潔にまとめ、相手の意見の良い点を認めながら自分の案を伝えることで、対立を和らげやすくなります。
時間が限られている場合は、全員で優先順位を決めるルールを提案するなど、合意形成の方法を示すと議論が進みやすくなります。
自分の案に固執せず、チームとして最善の答えを出す姿勢を見せることが評価にもつながります。
最終的に意見がまとまらない時は、多数決や役割ごとの責任分担を提案して時間内に決定することが重要です。
冷静に話し合いをまとめる力は、発想力と同じくらい選考で高く評価されるポイントとなります。
まとめ
デザイン思考テストは、就活生にとって重要な試験の一つとなっています。
試験内容を聞くと難しそうに感じられるかもしれませんが、対策は日常生活の中でも可能です。
効果的な対策とコツを押さえて、高得点を目指しましょう。
デザイン思考のスキルを身につけ、自身の可能性を広げるためにも、まずは一度デザイン思考テストに挑戦してみてください。