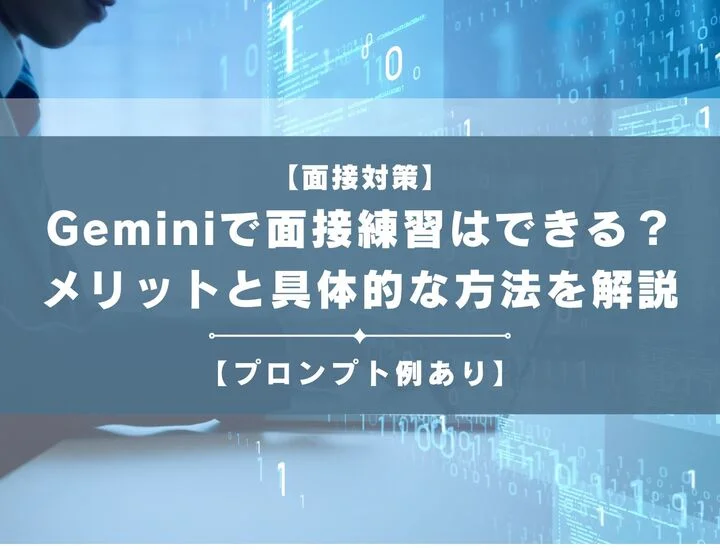はじめに
面接では、最近読んだ本の内容や感想、印象を聞かれることがあります。
普段から読書する習慣があればすぐに読んだ本を思い浮かべられますが、そうでない人にとってはどう答えたら良いのかわからない質問のひとつでしょう。
この記事では、面接の質問に答える際の適切な構成、回答の例文、就活前におすすめな本など、最近読んだ本を聞かれた際の対処に役立つ情報を紹介しています。
面接でされた質問に適切な回答をするためにはどうしたら良いのか、ひとつひとつ見ていきましょう。
面接で「最近読んだ本」を聞かれることはあるの?
面接で「最近読んだ本」について尋ねられることは、実際にあります。
近年、応募者の思想や信条に触れる可能性がある質問は推奨されていませんが、企業によっては応募者の人間性や興味の幅を知るために、この質問をすることがあります。
その人の読んだ本を通して、その人の興味関心のあるものや、考え方の傾向などを知ることに繋がります。
特に、個性を重視する企業や、読書が業務に直結するような職種では、聞かれる可能性があると考えておいた方がよいでしょう。
面接で「最近読んだ本」を聞くことは本来推奨されていない
面接で「最近読んだ本」について尋ねることは、本来は推奨されていません。
その主な理由は、読んでいる本が個人の思想や信条に深く関わる可能性があり、質問の仕方によっては差別につながるリスクがあるためです。
厚生労働省も、採用面接において応募者の適性や能力とは直接関係のない事柄を尋ねるべきではないと明確に指導しています。
このような背景から、多くの企業は、応募者のプライベートな側面や思想に踏み込む可能性のある読書というテーマを直接的に質問することを避ける傾向にあります。
これは、公平な採用活動を推進し、応募者が安心して面接に臨める環境を整えるための配慮と言えます。
企業によって聞かれる可能性がある
面接で頻繁に聞かれる質問とは異なり、「最近読んだ本」に関する質問は、応募者側がつい対策を後回しにしがちな項目かもしれません。
しかし、だからこそ、この質問に対して準備を怠らず、しっかりとした回答を用意しておくことは、他の応募者との間で大きな差別化を図る絶好の機会となります。
質問された際には、単に本のタイトルを挙げるだけでなく、なぜその本を選んだのかという動機、その本から具体的に何を学び、その学びを将来の仕事にどのように活かしていきたいのかまで、具体的なエピソードを交えながら話すことが重要です。
このように深く掘り下げた回答をすることで、面接官に対してあなたの読書に対する熱意や、物事を深く思考する力、そして学びを行動に移す意欲を効果的にアピールすることができます。
【面接時に最近読んだ本を聞かれたら】企業が質問する目的
就活において、最近何の本を読んだのか、どんな感想を抱いたのかなどを聞かれる機会は意外と多いです。
読書習慣の有無などは趣味の範疇に思えますが、実は就活生の人柄や能力を知る上で重要な役割を持ちます。
たくさんある書籍の中からどれを選ぶのか、読んでどんな感想を持つのかはその人の価値観を反映するため、相手について理解するためには無視できません。
また、普段から本を読むような人は学習意欲や知的好奇心が高いと見なされます。
さらに、自分がどのような本を読み、どんな感想を抱いたかを説明できれば、仕事における説明能力も証明できるため、企業にとっても就活生にとっても重要なアピールポイントです。
- 就活生の人となりを知るため
- 読書習慣の有無を知るため
- 説明する力を見るため
就活生の人となりを知るため
どのような本を選んで読むのかは、就活生の価値観や考え方、つまり人となりを探るのに役立ちます。
趣味嗜好が反映されるからこそ、読む本の選択はその人の価値観や考え方を表してくれるものです。
そして、面接でそれを聞けば就活生の考え方や感じ方について一定の指標が得られます。
企業の採用担当者は、このとき読み取った価値観や考え方から、その人材が自社と合うかをチェックしたいのです。
読んだ本が企業の考え方に合うようなものであり、感想もポジティブで肯定的なものであれば企業からの評価も高まります。
逆に選んだ本が企業の思想と程遠かったり、せっかく本自体は企業に合ったものなのに感想が否定的であったりする場合はマッチ度が低いと見なされかねません。
本を選ぶ時点から、どのようなアピールが可能であるかを考えておく必要があります。
読書習慣の有無を知るため
企業は、最近読んだ本の質問からその就活生が普段から本を読むか人なのかどうかを見ています。
普段から読書を習慣付けていれば、このような質問をされてもすらすらと読んだ本について答えられる可能性が高いです。
普段から本を読みなれている人物は、どのようなことを読み取るべきか、要点を掻い摘んで説明するにはどうしたら良いかを知っています。
普段から本を読むようにしている人物ならば、学習の習慣や意欲もあるのではないかという印象を持たせることも可能です。
本を読むのが好きな人は、学習意欲や知的好奇心が高く、もっと多くのことを知りたいという向上心がある人でもある場合が多いためです。
ただし、読んでいる本が娯楽のためのものである場合はあまりそういった評価にならない可能性があるため気を付けましょう。
説明する力を見るため
企業は、本の説明や感想を具体的に話せるかを聞いて、応募してきた就活生に説明能力があるかどうかをチェックしています。
本の内容を掻い摘んで、その本を読んだことのない人にわかりやすく説明するためには高度な説明力が求められるものです。
その本が読者に伝えようとしていることは何か、面白いところはどこか、自分はその本を読んでどう思ったのかなど、読んだ本について説明しなければならないことはたくさんあります。
そこで、就活生がそれらをわかりやすく伝えられるかを見ているのです。
説明能力は、社会のさまざまな場面で求められます。
顧客に製品やサービスについて説明するとき、上司に現在の業務について報告するとき、新しいプロジェクトについてプレゼンするときなど、必要なときに適切な説明能力が発揮できるかを確認されているのです。
【面接時に最近読んだ本を聞かれたら】聞かれたときの答え方
実際に面接で「あなたが最近読んだ本について教えてください」と聞かれた場合、本の内容だけ説明しても回答として相応しくありません。
本を読んで自分がどのような影響を受け、今後どのような変化を周りにもたらすのかにも言及する必要があります。
企業は別に面白い本の内容を共有して欲しいわけではないためです。
紹介する本を読もうと思ったのはなぜか、本の内容や著者の考えから学んだことにも言及し、その本が自分の人生にとって実りあるものであったこと、得たものをこれから活用したいという旨にも触れましょう。
- 最近読んだ本
- 読もうと思ったきっかけ
- その本から得た学び
- 今後にどのように活かすか
最近読んだ本
まず、結論としてどのような本を読んだのか、タイトルを伝えましょう。
「最近読んだ本は〇〇です」と言ったように、一文で簡潔に答えます。
その後であれば、どのような内容だったか掻い摘んで説明すると、その後の学びなど自分の感想につなげやすいです。
しかし、読んだ本がどのような内容であったか長々と説明してしまうと、面接でのアピールではなく本そのものの紹介になってしまうため避けたほうが良いでしょう。
その後に話すべきことへの時間配分も考えて、手短に済ませる必要があります。
就活生に人気の本は面接官も目を通している場合が多いため、長々と説明する必要はありませんが、適当なことを言うと違和感を持たれてしまい、場合によっては読んでいないのではと思われる可能性もあるため注意しましょう。
読もうと思ったきっかけ
続いて、その本を読もうと思ったきっかけは何か、興味関心や日常生活での課題、一種の挫折などから具体的なエピソードを話しましょう。
「先に読んだ友人から○○に関する学びがあると聞き、興味がわいた」「○○についてより深く知りたいと考えた」「自分の欠点を直すにはどう行動したら良いのか知りたかった」など、本の内容に合わせて自分がその本をどうして読みたいと感じたのかを説明します。
「なんとなく」「面白そうだと思ったから」という理由で本を選ぶ人もいるでしょうが、こうした曖昧な回答はあまり歓迎されません。
本を読む際に、明確に目標があるほうが学習意欲が高いと判断されやすいためです。
その本を読もうと決めたときの自分の心理について深掘りしつつ詳しく分析し、どうしてその本を読みたいと感じたのか話しましょう。
その本から得た学び
次に、読んだ本からどのような学びを得たのかを話します。
基本的に、本には読者に対して伝えたいことが設定されており、最後まで読めば何かしらの学びがあるような構成になっているものです。
その一方で、読んだ本から本当に何を学び取ったのかは読んだ人によって異なります。
そのため、本から学んだことは就活生の読解力をアピールするとともに、回答の差別化や自分の人となりのアピールにもなるのです。
ただし、いくら自由度が高い回答とは言え、本来その本が示している内容と大きく乖離する回答をしてしまうと、読解力がない、何も読み取れていないと評価されてしまうため注意しましょう。
その本から実際に読み取れる内容の範囲内で、自分がどう思ったか、何を学んだのかを答えます。
今後にどのように活かすか
最後に、本から得た学びや読んだ経験そのものを今後の人生で社会人としてどのように活かすのかを述べます。
娯楽のための本であれば読んで「面白かった」で済ませて構いませんが、就活で紹介する本はそうではありません。
本を読んだことで自分の内面がどのように変化したのか、それをどう社会に影響させていくのかまで考える必要があります。
「この学びは○○という形で御社の業務でも役立てたいと考えております」のように、具体的にどのような業務に活用できるかも含めて説明できると良いでしょう。
そのため、実際にその企業でどのような業務をこなさなければならないのか、就活生に何が求められているのかは知っておく必要があります。
企業の業務とまったく関係のないことを話すと良い評価は得られないため注意しましょう。
【面接時に最近読んだ本を聞かれたら】回答例を紹介
続いて、実際の本を例にしながら、最近読んだ本について聞かれた場合の回答例を紹介します。
ここに挙げるのはあくまでも一例であるため、実際に答える際は自分の読書体験に基づいた内容を、自分の言葉で伝えることが必要です。
実際に読んでいない本について話しても感想や学んだこと、または内容の深掘りで嘘がバレてしまう可能性が高いでしょう。
また、本当に読んだ本であっても本来の感想とまったく異なることを言ってしまうとあまり意味がありません。
- 道を開く
- 夢をかなえるゾウ
- 坂の上の雲
- 君たちはどう生きるか
- 世界は感情で動く
- 金持ちお父さん・貧乏お父さん
- 嫌われる勇気
- 1分で話せ
- 苦しかったときの話をしようか
- プロジェクトを変える12の知恵
小説・随筆
小説や随筆は、単なる物語として楽しむだけでなく、私たちの人生に大きな影響を与えてくれます。
架空の物語であっても、登場人物の生き方や葛藤、成長の過程に触れることで、現実世界での学びや教訓を得ることができます。
また、作家が文章に込めたメッセージは、読者の心に深く響き、共感を呼び起こします。
私たちは本を通して、自分とは異なる価値観や視点に触れ、視野を広げることができます。
物語に感情移入し、登場人物の喜びや悲しみを追体験する中で、自分自身の内面と向き合うきっかけを得たり、新たな気づきを得たりすることもあるでしょう。
このように、小説や随筆は、単なる娯楽を超え、私たちの心を豊かにし、人生をより深く生きるためのヒントを与えてくれるのです。
君たちはどう生きるか
私が最近読んだのは、吉野源三郎氏の「君たちはどう生きるか」です。
この本は、14歳の少年が身近なトラブルなどについて近しい人のアドバイスをもとに自分なりの答えを探す内容になります。
これを読んだきっかけは、同名の映画を見て原作のメッセージが気になったことです。
映画だけではわからなかったことから、これからの人生を生きるヒントが欲しいと考えて読み始めました。
この本を読んで学んだのは、人生を生きるにあたって大切なのは「目的」だということです。
人生をかけてやりたいことがわかっていれば、自ずとそのとき何をすれば良いかがわかります。
この学びを活かして、御社への入社後も自分が何をしたいかはっきり目的を決め、業務に打ち込みたいと考えております。
夢をかなえるゾウ
私が最近読んだのは、水野敬也氏の「夢をかなえるゾウ」です。
この本は、象の神様から与えられる課題を主人公がこなすことで、考え方や人生を変化させていく物語になります。
この本を読もうと思ったきっかけは、主人公の「自分を変えたい」という気持ちに共感したためです。
自分を変えたいという気持ちは持っているものの、どうやって変えたら良いのか考えあぐねているときにこの本と出会いました。
この本を読んで、自分を変えるためには毎日小さなことから変化させていくのが良いということを学びました。
1つずつ「確かに変化した」を積み重ねることで、最初は小さくとも1週間後、1か月後、1年後には大きな変化になると知ったのです。
これを活かして、御社への入社後も小さな変化や成功の積み重ねを続けて事業の成功につなげたいと考えております。
坂の上の雲
最近読んだ本は「坂の上の雲」です。
この本を読もうと思ったきっかけは、日本の近代化が進む時代に、どのように人々が困難に立ち向かったのかを知りたかったからです。
特に、主人公たちが逆境に立ち向かいながらも理想を追求する姿勢に感銘を受けました。
この本から得た学びは、時代背景が異なっても、目標に向かって努力する姿勢や、周囲の人々と連携して成果を出す重要性です。
また、困難に直面した際にどのように状況を打開するか、冷静な判断力と行動力が求められることも教えられました。
この学びを今後のキャリアに活かしたいと考えています。
具体的には、仕事で困難に直面しても、理想を追求する姿勢を忘れず、周囲と協力しながら目標達成に向けて努力していきます。
自己啓発本
自己啓発本の本は、人生をより良くするための具体的な方法や考え方、成功への道筋を示してくれます。
専門家や成功者の経験に基づいたアドバイスは、漠然とした悩みを解決するヒントを与え、行動を起こすためのモチベーションを高めてくれるでしょう。
具体的な課題から、漠然とした目標まで、自己啓発本は多岐にわたるテーマを扱っています。
読者は自分の現状に合った本を選ぶことで、課題解決のための具体的なステップを学び、実践することができます。
また、自己啓発本は、自分自身の強みや弱みを客観的に見つめ直すきっかけにもなります。
読書を通じて、自分一人では気づけなかった新たな視点や思考法を獲得し、より前向きな気持ちで物事に取り組めるようになるでしょう。
道を開く
私が最近読んだのは、松下幸之助氏の「道を開く」です。
この本は、著者が思う生きるために必要な不変の大原則について書かれた短編随想集となっています。
私がこの本を読もうと思ったのは、社会人としてのスタートダッシュをより良いものにしようと思ったのがきっかけです。
すでに社会人として成功している人がどのような考えで仕事に臨んでいるのかを知ることで、自分が働く上での気付きが欲しいと考えて読み始めました。
この本からは、簡単に大きな成果をあげているように見える人でも、実際には一歩一歩努力を積み重ねているのだということを学びました。
この学びを活用し、御社への入社後も業務の成功に向けて自分なりに着実な努力を重ねていきたいと考えております。
金持ちお父さん・貧乏お父さん
最近読んだ本は「金持ちお父さん・貧乏お父さん」です。
この本を手に取った理由は、将来に向けてお金や資産運用についての知識を深め、より良いキャリア形成を考えたかったからです。
この本では、資産を形成するための考え方や、収入をどのように使うべきかについて具体的なアドバイスが書かれており、とても参考になりました。
特に、労働収入だけに頼るのではなく、資産を活用して長期的な視点で経済的な安定を図ることの重要性を学びました。
今後は、この本で得た知識を活かして、個人としての経済的な計画を立てるだけでなく、仕事においても収益性や長期的な視野を持ってプロジェクトに取り組む姿勢を大切にしたいと思います。
特に、効率的なリソース管理や、新たな価値を生み出す視点を常に意識して行動していきたいと考えています。
嫌われる勇気
私が最近読んだのは、岸見一郎氏と古賀史健氏による「嫌われる勇気」です。
この本は、アドラー心理学の教えをやさしく解説したもので、自分らしく生きるための心持ちについて教えてくれます。
私がこの本を読もうと思ったきっかけは、人から嫌われることを気にして行動できない自分を変えたいと思ったことです。
この本では、人から好かれようと思い、人の期待に応えようとすればするほど他者の言動に振り回されてしまい、ストレスを抱え込みやすい状態になってしまうと解説しています。
そこから私は、自分の人生を自分らしく生きるためには人の言葉を鵜呑みにしすぎないことが大切だと学びました。
御社への入社後も、自分なりの評価軸を持って仕事に臨みたいと考えております。
苦しかったときの話をしようか
最近読んだ本は「苦しかったときの話をしようか」です。
この本を選んだ理由は、社会で働く中でどのように困難に立ち向かうべきか、先人の経験から学びたかったからです。
特に、自分が苦しい状況に置かれた際に、どのように考え行動すれば良いかの指針を求めていました。
この本では、著者が過去に直面した困難な出来事や、それを乗り越えるために取った行動が丁寧に描かれており、とても共感できる部分が多くありました。
困難を避けるのではなく、それを成長の糧とする考え方に心を動かされました。
今後は、この本で得た学びを、どんな状況でも冷静に状況を見極め、自分を成長させるチャンスとして捉える力に活かしたいと思います。
また、周囲と協力し、困難を乗り越える過程を共有することで、チーム全体としての成長にもつなげたいと考えています。
ビジネス書
ビジネス書は、就職活動の面接でアピールしやすいだけでなく、社会人になってからも長く役立つ知識やスキルを身につける上で非常に有用です。
これらの本は、業界の動向や経営戦略、マーケティング、財務、リーダーシップなど、仕事に直結する幅広いテーマを扱っており、読者は専門的な知識を効率よく吸収することができます。
面接においては、単にビジネス書を読んでいるという事実だけでなく、その本から何を学び、どのように仕事に活かしたいかを具体的に話すことで、面接官にあなたの学習意欲や向上心を強く印象づけることができます。
ビジネス書は、常に変化するビジネスの世界に対応し、自身のキャリアを切り開いていくための強力な武器となるでしょう。
1分で話せ
最近読んだ本は「1分で話せ」です。
この本を読もうと思ったきっかけは、プレゼンテーションや会議などで、要点を簡潔に伝える力を磨きたいと考えたからです。
短い時間で相手の心をつかむコミュニケーションスキルに興味を持ち、読んでみることにしました。
この本から学んだことは、どれだけ相手に伝えたい情報が多くても、相手が理解しやすい形で話す工夫が大切だということです。
具体的には、話す内容をシンプルに絞り込むこと、そして結論を最初に述べることで聞き手の関心を引き付ける方法を学びました。
今後は、このスキルを日常的なコミュニケーションだけでなく、仕事の場でも活かしていきたいです。
会議やプレゼンでの発言をより簡潔にし、相手が行動に移しやすいメッセージを伝えられるようになりたいと思います。
世界は感情で動く
私が最近読んだのは、イタリアの経済学者マッテオ・モッテルリーニ氏の「世界は感情で動く」です。
この本には、人の経済活動が直感に基づくものである、という仮説が事例とともに紹介されています。
私がこの本を読んだきっかけは、市場の動きを理解して今後の仕事に活かしたいと考えたことです。
将来的にはマーケティングの仕事がしたいと考えており、その前段階として営業の仕事をこなすため、どのような際に市場が動くのか知りたいと感じました。
この本から学んだのは、マーケティングの現場も人の習性によって動かされているということです。
御社への入社後は、お客様の直感に働きかけるような営業活動を行い、業績を伸ばすところからはじめたいと考えております。
プロジェクトを変える12の知恵
私が最近読んだのは、ITコンサルティング会社の影山明氏による「プロジェクトを変える12の知恵」です。
この本には、業界に縛られずプロジェクトを成功させるためのコツがわかりやすく書かれています。
この本を読もうと思ったのは、サークルでの企画がうまくいかなさそうだったのを変えたいと思ったのがきっかけです。
本を読む前にもいろいろなアプローチを試していましたが、いまいち影響を与えられている実感がなかったためこちらを読み始めました。
この本からは、情報システムに関わるプロジェクトだけでなく、関わったプロジェクトをどう変化させていくと良いのか、どうなったら変化したと言えるのかを学びました。
この経験をもとに、御社への入社後もプロジェクトの要点を押さえ、成功させるための方策を打ち出していきたいと考えております。
【面接時に最近読んだ本を聞かれたら】NG回答の特徴
面接官から「最近読んだ本について教えてください」と聞かれたとき、推奨されないNGな回答も存在します。
たとえば、本は読まないと答えたり、実際には読んでいない本について答えたり、漫画について話すと面接官からの印象は良くありません。
とくに、実際に読んでいない本について話すのは信頼性を大きく損なうためNGです。
基本的には面接前に1冊でも話題にできる漫画以外の本を読んでおき、正直のその感想について話すようにしましょう。
- 本は読まないと伝える
- 実際には読んだことのない本について話す
- 漫画しか読まないと話す
本は読まないと伝える
なるべく避けたほうが良いのは「本は読まない」「最近読んだ本はない」「印象に残った本はない」と伝えることです。
「本は読まない」「最近読んだ本はない」という回答は、その就活生に読書習慣がないという評価を下される原因になってしまいます。
これは、日常的な学びや本という情報源の重要性を知らない人物として評価される原因にもなり、面接官にマイナスな印象をもたれてしまうのです。
また「印象に残った本はない」という回答は、本から学び取る力がないと思われる原因になります。
本を1冊読むのに時間がかかるようであれば早めに読み始め、面接までに読み終えて感想を考える時間を作りましょう。
余裕があれば、企業に合わせて感想を言う本を変えるために何冊か読んでおくのがおすすめです。
実際には読んだことのない本について話す
絶対にやってはいけないのは、実際に読んだことのない本について回答することです。
実際に読んだことのない本を紹介しても、その内容について理解できていないためうまく説明することはできません。
面接官の多くは人事担当であり、就活生に人気の本をリサーチして自分も読んでいるケースが多いです。
内容や感想について対面で深掘りされたときにボロが出てしまい、嘘がバレてしまいます。
そうなるとその回答の信頼が得られなくなるだけでなく、面接全体やあなた自身の信用が失われてしまうのです。
信頼できない人材を採用しようと考える企業はほとんどありません。
些細なことで内定の可能性を逃さないよう、最近読んだ本を聞かれた場合は正直に、実際に読んだ本について答えるようにしましょう。
漫画しか読まないと話す
最近読んだ本の回答としてあまりおすすめできないのが、漫画のタイトルを答えることや「漫画しか読まない」という旨を伝えることです。
もちろん、漫画もエンターテイメントとしては重要な作品であり、そこから学べることもたくさんあります。
しかし、一般的な小説や自己啓発本のような本と比べて、娯楽としての側面が強いです。
面接など正式なビジネスの場所では、娯楽に関わる話はしないという常識が存在します。
面接で読んだ本について聞かれて漫画について答えてしまうと、そういった社会人としての常識を持っていないのでは、という印象を持たれてしまうのです。
そのため、なるべく漫画以外の本も読んでみて、印象に残った本について答える必要があります。
【面接時に最近読んだ本を聞かれたら】普段本を読まない人が面接までに読むべき本のジャンル
面接で「最近読んだ本」を聞かれた際に、自信を持って答えられるように準備することは大切です。
特に普段あまり本を読まない人にとって、どんな本を選べば良いのか迷うこともあるでしょう。
ここでは、面接対策として読むべき本のジャンルについて、ビジネス本、自己啓発本、小説の3つに分けて解説します。
- ビジネス本
- 自己啓発本
- 小説
ビジネス本
ビジネス本は、社会に出る前に役立つ知識やスキルを習得するための最適なジャンルです。
就職活動では、「仕事への意識」や「ビジネスマインド」が問われる場面が多いため、これらの本を読んでおくことで、面接官に好印象を与えることができます。
ビジネス本は、リーダーシップ、コミュニケーション、時間管理など、社会で必要とされるスキルを具体的に学べる内容が豊富です。
また、成功した企業家や経営者の体験談を通じて、仕事に対する考え方や価値観を深めることができます。
たとえば、「ゼロからイチを生み出す」発想法や「失敗を恐れない挑戦心」など、企業が求める人材像に関連する要素を吸収することが可能です。
ビジネス本は、実用的な知識を得るだけでなく、面接官との会話を深める材料としても非常に有益です。
自己啓発本
自己啓発本は、自己成長を促すためのヒントやモチベーションを提供してくれるジャンルです。
特に、自分を変えたい、新たな目標を持ちたいという意識がある場合には、読んでおいて損はありません。
自己啓発本の特徴は、ポジティブな考え方や具体的な行動指針が示されている点にあります。
たとえば、「どんな困難にも負けないマインドセットを作る方法」や「成功者に共通する習慣」といったテーマが多く取り上げられています。
これらは、就活での自己分析や、目標達成のための計画立案に役立つでしょう。
さらに、自己啓発本を読んだ経験は、面接での質問に対する答えとしても活用できます。
たとえば、「この本を読んで、自分に足りない部分を理解し、それを克服するために取り組んだこと」などを具体的に述べれば、主体的に行動できる人材として評価されやすくなります。
小説
小説は、普段本を読む習慣がない人にとっても、比較的親しみやすいジャンルです。
物語を通じて、感情移入しながら学びや教訓を得られるため、読書経験が少ない人にもおすすめです。
小説の魅力は、登場人物の心情や葛藤を追体験できる点にあります。
これにより、他者の考えや感じ方に共感する力を育むことができます。
また、歴史小説や社会問題をテーマにした作品を選べば、広い視野や教養を身に付けることができ、面接での話題としても適しています。
さらに、小説を読むことは文章表現力を養ううえでも役立ちます。
面接官に対して、自分が感銘を受けたシーンやそこから得た教訓を具体的に伝えることで、感受性や思考力の深さをアピールできます。
小説は、物語の楽しさを味わいながらも、内面的な成長を促すツールとして活用できるジャンルと言えます。
【面接時に最近読んだ本を聞かれたら】おすすめの本を紹介
ここからは、就活や面接の前に読んでおくのがおすすめの本について紹介します。
これらの本は、これからの人生や社会生活において大切なことについて学べるほか、就活や面接でも活用できるような内容の本です。
ここから何を学び取るのかは個人の自由ですが、ある程度就活でウケの良い本を読んでおいたほうが、企業が求める人材像への理解なども深まります。
それぞれの本について、著者やあらすじ、特徴などを詳しく見ていきましょう。
- 夢をかなえるゾウ
- 言葉にできるは武器になる
- リーダーの仮面
夢をかなえるゾウ
1冊目は、水野敬也による小説「夢をかなえるゾウ」(飛鳥新社)です。
主人公は普通の会社員ですが、自分を変えたいという願いを持っており、ある日ゾウの姿をした神様に出会います。
そして、人生を変えるための課題を出され、次第に考え方や意識を変えていくという内容です。
小説の体裁ではあるものの、自己啓発本に近く、人生を変えるために必要な行動などが記されています。
項目ごとに分かれているものの、コミカルな物語に沿って読み進められるため、読書が苦手な人でも親しみやすい本です。
これまでに読書経験があまりないという就活生や、自分を変える方法、意識を変えるきっかけについて知りたい、楽しく学びたいという就活生は一度読んでみると良いでしょう。
言葉にできるは武器になる
2冊目は、梅田悟司氏による自己啓発本「言葉にできるは武器になる」 (日本経済新聞出版)です。
この本では、著者が考えるビジネスを成功させるための重要な要素として、コミュニケーションのスキルを挙げています。
ビジネスシーンで実際に使えるコミュニケーション術なども紹介されており、実践的な内容になっているため社会に出てからも直接役立つような内容です。
人の心を動かすような言葉や表現に必要なものは何か、コピーライターとしての立場から解説されており「意志を言葉に込める技術」を伝えています。
社会人としてどのようなコミュニケーションが必要か悩んでいる、営業職として一歩抜きん出たスキルが欲しいといった就活生は、この本を読むのがおすすめです。
リーダーの仮面
3冊目は、安藤広大氏によるビジネス書「リーダーの仮面」(ダイヤモンド社)です。
この本は、所属している組織を成功へ導くリーダーシップの本になります。
組織において、リーダーシップを発揮するためのヒントが多く書かれている本です。
組織内の誤解や錯覚を解決する方法としてリーダーシップの重要性を指摘し、それを発揮するためにはどうしたら良いのかを解説しています。
リーダーシップの本質に迫る、組織全体の成長にフォーカスを当てた内容のビジネス本です。
今後マネジメントの仕事に携わりたいと考えている就活生や、リーダーシップとは何か、自分でも身につけられるものなのか知りたいと考えている就活生は一度読んでおくと良いでしょう。
【面接時に最近読んだ本を聞かれたら】対策する上での読書の効果
面接で「最近読んだ本」について尋ねられることは、単に読書習慣があるかを確認するだけでなく、あなたの人間性や思考力を探る意図があります。
読書は、面接対策をする上で多くのメリットをもたらします。
以下のメリットを意識しながら、読む本を選んだり、読書した後に自分なりに本の内容から得られた情報をもとに考えてみたりしてみてください。
知識・専門性が高まる
読書は、あなたの知識や専門性を飛躍的に高めます。
特に、志望する業界や職種に関連する本を読むことで、専門用語や業界の動向、課題について深く理解できます。
面接官は、あなたがどれだけその分野に関心を持っているか、そして自主的に学習しているかを見ています。
本を読むことは、普通にテキストなどで勉強をするよりも、知識が定着しやすいです。
豊富な知識を持つことで、面接での質問に対しても、表面的な回答ではなく、多様な視点から問題を捉え、論理的かつ説得力のある意見を述べることが可能になります。
これにより、あなたの熱意と真剣さを効果的にアピールできるでしょう。
コミュニケーション能力の向上
読書は、コミュニケーション能力の向上にもつながります。
文章を読むことは、筆者の考えや感情を読み解くトレーニングになります。
これにより、相手の意図を正確に理解する力が養われます。
また、本から学んだ豊かな語彙や表現方法は、自分の考えや感情をより正確に、そして魅力的に伝える助けになります。
面接では、質問の意図を正しく把握し、簡潔かつ明確に自分の意見を述べる力が求められます。
読書を通じて培われた高い言語能力は、面接官に好印象を与え、円滑なコミュニケーションを可能にするでしょう。
しかし、こういったコミュニケーション能力は一朝一夕では身に付きません。
日頃から、本を読む習慣をつけましょう。
他の意見や考え方に触れて視野が広がる
読書は、あなたの視野を大きく広げ、多角的な視点から物事を捉える力を養います。
これは、自分とは異なる文化、価値観、時代背景を持つ人々の物語や考えに触れることで可能になります。
面接の場では、企業が求める人材像や、仕事に対する考え方について深く問われることがありますが、読書を通じて得た広い視野は、そうした質問に対して、自身の考え方や価値観をより深く、そして説得力をもって伝えるための強力な武器となります。
多様な視点から物事を考察できる能力は、入社後もチームでの協力や複雑な問題解決に大いに役立ち、組織全体の成長に貢献できる人材としての価値を高めるでしょう。
【面接時に最近読んだ本を聞かれたら】関連性の高い他の質問
面接で「最近読んだ本」について聞かれる場合、それに関連してさらに踏み込んだ質問をされることがあります。
これらの質問は、あなたがただ本を読んだだけでなく、そこから何を学び、どのように考えているかを探る意図があります。
さらにどのような質問をされるか、具体的に解説します。
以下の内容を参考に、本に関連した質問に対する回答も考えておきましょう。
最近読んだ本で印象に残ったシーンやエピソードはありますか?
この質問は、あなたが本の表層的な内容だけでなく、その核心をどれだけ深く理解しているかを確認するために投げかけられます。
単にストーリーを説明するだけでなく、なぜそのシーンが印象に残ったのか、その出来事が自分にどのような影響を与え、どう感じたのかを具体的に伝えることが求められます。
例えば、登場人物の葛藤や決断から、困難な状況に直面した際の心の持ち方を学んだ、といったように、本の内容とあなた自身の経験や価値観を結びつけて話すことが重要です。
これにより、あなたの思考力や内省する力をアピールできます。
この際、どのようなシーンやエピソードを選ぶかはあまり重要ではありません。
重視されるのは、そのシーンに対する自分の考えをどこまで具体的に話すことができるかです。
おすすめな本やジャンルはありますか?
この質問は、あなたの興味や価値観、そして物事に対する熱意を面接官に直接的に伝える絶好の機会です。
単に本のタイトルやジャンルを挙げるだけでなく、なぜその本やジャンルを勧めるのか、その魅力はどこにあるのかを、あなた自身の言葉で熱意をもって伝えることが非常に大切です。
例えば、特定のジャンルがあなたの自己成長にどのように役立ったのか、具体的な経験を交えて話したり、ある一冊の本があなた自身のキャリア観や人生観を形作るきっかけになったと述べたりすることで、あなたのパーソナリティや価値観を面接官に深く印象づけることができます。
これにより、面接官はあなたがどのような人間であるかを具体的にイメージしやすくなり、あなたの内面をより深く理解してもらえるでしょう。
本を読むことで得たスキルや成果はありますか?
この質問は、読書が単なる趣味ではなく、あなたの成長やスキルアップにどう貢献しているかを証明する機会です。
その本から何を学び、それをどう仕事や生活に活かしたかを具体的に述べることが重要です。
例えば、自己啓発本の内容を実践したことによって生活や自分の気持ちの持ちように変化が起きたなど、読書が具体的な成果につながった経験を話すと、あなたの学びを実践する力や業務改善への意識の高さを強調できます。
本を通して得たスキルや成果は大きなものでなくて構いません。
自分の体験として説得力のあるエピソードを選びましょう。
これにより、あなたの読書習慣が、入社後も会社に貢献できる能力であることを示せるでしょう。
【面接時に最近読んだ本を聞かれたら】面接対策が難しいときは
どうしても面接での回答に詰まってしまうようなら、就活のプロである就活エージェントに相談してみましょう。
「ジョブコミット」であれば、就活におすすめの本の紹介や、読んだ本をどのように紹介したら良いか、面接での話し方に関する的確なアドバイスが受けられます。
就活生の持った感想に対し、企業目線でどのように評価できるかを教えてくれるため、言い換えによってより志望先の企業にコミットした内容に組み替えられる可能性が高いです。
ほかにも、面接対策そのものや企業選び、書類選考など就活の始まりから内定獲得まで包括的にサポートしてくれます。
面接をはじめ就活に悩みがある場合は、二人三脚で手助けしてくれるプロに頼ってみるのがおすすめです。
ジョブコミットへの登録はこちらからどうぞ。
→https://shukatsu-venture.com/lp/6
おわりに
「最近読んだ本」は、就活生の読書習慣や読解力、説明する力などを測るために聞かれる機会が多い質問です。
この質問には、ビジネスでも役立つような内容が書かれた本を答え、自分なりの学びや企業に活かせることを答えると良いでしょう。
逆に、娯楽に偏った回答や学習意欲について疑われるような回答は避けるのが無難です。
就活前には本を読む習慣をつけておき、いざ質問されても困らないような本を読んで印象や感想、学んだことを整理しておきましょう。



_720x550.webp)
_720x550.webp)