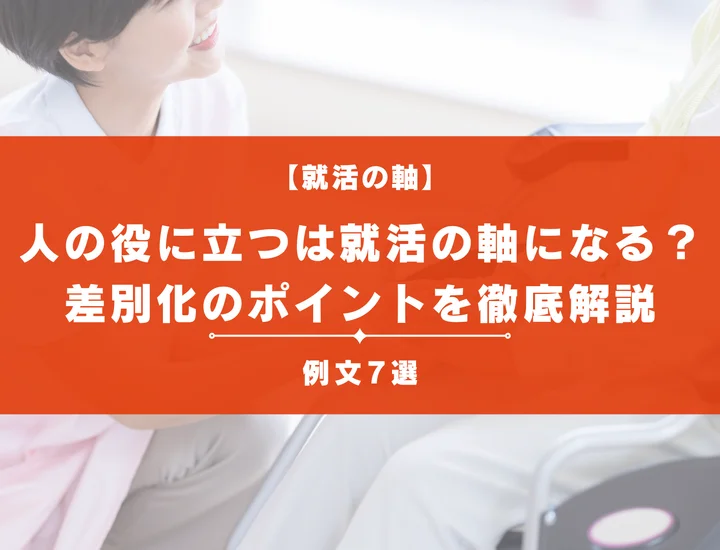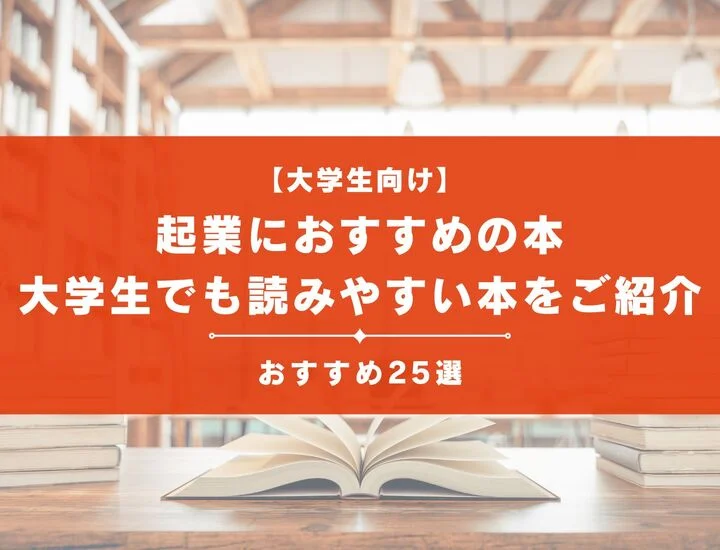はじめに
どういった物事であっても、成功失敗を決める大きな要素になるのが、良い準備をしてきたかどうかです。
もちろん就活の成功も、準備段階である程度決まってしまいます。
就活の準備において、重要な要素を占めるのが自己分析です。
自己分析がしっかりおこなわれていれば、どの企業に応募する場合であっても、比較的内定を得やすくなります。
どの企業に応募する場合でも、自己分析がされていないと、なかなか内定を勝ち取れません。
今回は、就活に向けたより良い自己分析をおこなうための方法、注意点について解説します。
就活の大まかな流れ
まずは、就活の大まかな流れについておさらいしておきましょう。
新卒の就活は、かなりの期間を要するものになります。
内定が出ないと、半年から1年ほどかかることも少なくないほか、最近では大学2~3年生のうちからインターンシップに参加する方が多いです。
そう考えると、大学生活の半分ほどが就活の時期になっていると言っても過言ではないでしょう。
しかし、大まかな流れはインターンシップに参加する・しないにかかわらず、ある程度共通しています。
自己分析
自己分析とは、就活の方向性を決定するための前準備段階です。
ここで決めておくことや知っておくことは、数えきれないほど多くあります。
そのうちのひとつは、自分についてより深く知ることです。
自分は何が得意で、どのような仕事に向いている人材なのでしょうか。
また、自分がどのようなときにモチベーションが上がるか、どのような目的ならやりがいを持って働けるかなどを考える必要もあります。
もうひとつの重要なポイントは、就活の軸を何にするかです。
基本的には、この軸を中心に自己PRを作成していきます。
面接でもエントリーシートでも、この軸からぶれずに自分を表現することが重要です。
しっかり自己分析できていなければ、「私はこのような人間です」と自信を持ってアピールできなくなってしまいます。
業界・企業研究
業界・企業研究とは、自分が興味を持った業界や企業について深くリサーチすることです。
これも就活の準備段階なので、自己分析と並行して同じ時期に進めていきましょう。
業界・企業研究で調べておくことも、多岐にわたります。
そのうちのひとつは、業界の特徴や職種です。
その企業に入ったらどのような仕事をしなければいけないのか、どういった人材が求められているか知る必要があります。
次に、その業界の課題や将来性を調べていきましょう。
その業界は将来性がある業界なのか、失業リスクが低い安定した業界なのかを調べることも、後悔ない就職を実現するためには欠かせません。
業界について調べた後は、その業界内の企業の立ち位置や個性についても学びましょう。
面接では、業界だけでなくその企業を志望する理由が問われるためです。
OB・OG訪問
OB・OG訪問は、必ずしも踏まなくてはならないステップではありません。
OB・OG訪問とは、実際に行きたい企業に就職した大学のOB・OGと会って、話を聞くことを指します。
企業によっては、ホームページなどで積極的にOB・OG訪問できることをアピールしているかもしれません。
しかし、OB・OG訪問に対応してくれる社員にも仕事があります。
毎日OB・OG訪問だけに対応するわけにはいかないため、訪問できる人数はどうしても限られます。
OB・OG訪問できなくても、その企業に就職できなくなるわけではないので、チャンスを得られなかった場合でも気にする必要はありません。
しかし、その企業の内定をもらった方がどのような就活準備をしたか、今どのような仕事をしているかなどを聞ける絶好のチャンスです。
志望度を高めるためにも、気になる企業のOB・OG訪問にはぜひ申し込んでおきましょう。
エントリーシート・履歴書の記入
エントリーシートや履歴書とは、その企業に応募するにあたって、応募者の情報を書き記すための書類です。
以前の就活では履歴書が中心でしたが、最近はWeb上のエントリーシートを提出することにより、企業に応募する意思を示すよう促されることが多くなりました。
もちろん、エントリーシートと履歴書を両方出さなければいけない企業も多くあります。
エントリーシートの内容は、企業ごとにまったく違う場合があるので注意が必要です。
さまざまな質問に答えられるよう、想定される頻出質問に対応できる準備をしておく必要があります。
とくに志望動機やガクチカ、自分の強みといった質問はほとんどの企業で実施されるので、自己分析の結果をもとに良い文章を書けるようにしておきましょう。
筆記試験
多くの場合、エントリーシートの書類選考を通過すると、筆記試験を受けることになります。
筆記試験がない企業もありますが、一定以上の規模の企業ならかなりの確率で筆記試験を受けることになるでしょう。
代表的なものはSPIや玉手箱で、企業によっては同じツールを使うことがあります。
しかし、同じツールでも問題が異なっていることはあるので、簡単にクリアすることはできません。
ある程度問題の傾向は似ているため、過去問や問題集、参考書などを一通りやっておけば高得点を取りやすくなります。
また、筆記試験にはある程度慣れておく必要があるため、本命企業の前に何社か受けておくのがおすすめです。
筆記試験は、応募者が企業で働くのに十分な能力を持っているか、企業の社風に適した性格かを確認するために実施されます。
面接
就活の本番は、最終ステージの面接です。
就活中は、筆記試験と面接がある程度同時進行で進む場合もあります。
また、面接だけでなく、グループディスカッションなどの試験をおこない、応募者のコミュニケーション能力や問題解決能力を見ようとする企業も多いです。
面接は企業が応募者をテストする場ですが、応募者側にとっても企業についてより深く知るきっかけになります。
もし面接で採用担当者が信頼できないと感じたり、説明会で聞いていた話と会社の雰囲気がまったく違うと思ったりしたら、そこで選考を辞退しても構いません。
面接を通じて、その企業が本当に内定を得てから働きたいと思える会社なのか考えてみましょう。
ほとんどの企業で面接は実施されるので、しっかり準備しておくことが大切です。
加えて、面接を受ける際のマナーも身につけておきましょう。
自己分析の目的は?
自己分析をおこなう主な目的は、自分を理解することです。
自分の価値観を知れば、就活の軸を決めやすくなります。
就活はあくまで社会人の入り口で、本当に大変なのは実際に就職してからです。
職場にやりがいを感じられなければ、なかなか仕事が長続きしません。
自分が本当にやる気を持って働ける職場はどのような職場か、どのような仕事なら活躍できるかなどを考えてみましょう。
就活の準備でおこなう自己分析は、就活そのものだけでなく、快適に働ける会社に入るためのものでもあります。
自己分析はいつまでにやればいいの?
自己分析は、いつまでにやれば良いといったように、期限が決まっているわけではありません。
もちろん、エントリーシートの提出時期が始まる前には済ませておく必要があります。
しかし、自己分析は就活の基盤となるもので、繰り返しおこなうのが基本です。
繰り返すほどに深く理解が得られるため、ぜひ定期的に自分を振り返ってみましょう。
また、就活が進むにつれて、価値観が変わることも珍しくありません。
そのため、就活が始まってから、もう一度自己分析をおこなってみるのも良いでしょう。
自己分析をやるメリット5選
ここからは、就活前に自己分析をやっておくメリットを5つご紹介します。
自己分析をおこなう主な目的は自己理解のためですが、実はその後の就職活動を有利に進める実用的な理由も多いです。
就活は能力や学歴、筆記試験の成績もチェックポイントになりますが、そこはなかなか短期間の努力で向上させられるものではありません。
しかし、エントリーシートや面接でのプレゼン力とアピール力は、自己分析の結果次第でほかの学生と差をつけられます。
就活で何から手をつけて良いか迷った際は、まずは自己分析からスタートしてみましょう。
自分の価値観を知れる
自己分析をやることによって、自分の価値観を知り自分に合った企業を選びやすくなります。
毎年、非常に多くの企業が新卒の学生を募集しているので、その中から自分にマッチする企業を見つけるのは簡単ではありません。
少なくとも、自分が心から働きたいと思える企業を見つけなければ、面接で的確に志望動機を述べることはできないでしょう。
また、自分の価値観に合った企業に入るほうが、入社後も仕事をやらされるといった感覚ではなく、自発的に進んでやる感覚で働けます。
どの職場でもそれなりの苦労はありますが、自分の価値観に合いやりがいを持てる仕事であれば、その苦労を乗り越えられる可能性が高いです。
まずは自分の価値観を把握しておき、それに合った企業を見つけましょう。
就活の軸を決定する
次のメリットは、就活の軸を決められることです。
就活の軸は、大まかに分けて2つあります。
自分が本当に軸にしたい「本音の軸」と、面接などで相手に好印象を持ってもらえるよう言い換える「建前の軸」です。
基本的には、まず自己分析で本音の軸を探っていくことになります。
しかし、自分が稼ぎたいと思って仕事をするにしても、面接で「自分はお金がたくさん欲しいです」と言ってしまうわけにもいきません。
好印象を持ってもらえるよう、「活気ある業界で活躍したい」「責任ある仕事に就きたい」などと言い換えるのが無難です。
まずは自分の本音を見つけ、それをエントリーシートや面接でうまく言い換えられるように努める必要があります。
この就活の軸を決める作業は、その後のエントリーシート作成や面接対策をスムーズに進めることにもつながる重要なポイントです。
自己PRが見つかる
自己PRは、採用面接においてほとんどの企業が聞いてくる質問です。
しかし、面接の場で「自由にPRしてください」と言われると、何をアピールして良いか困ってしまう方は珍しくありません。
自己分析をおこなっておくと、自分をアピールするための引き出しが見つかります。
その企業に刺さりやすいアピールポイントが、何かひとつは見つかる可能性が高いでしょう。
もちろん、企業に合ったアピールポイントを書くには、自己分析だけでは不十分です。
どのアピールポイントがベストか探るには、その企業の社風や業界の特徴を知らなければいけません。
自己PRは、就活でも回答が難しい質問のひとつなので、この質問にスムーズに答えられることを目標にして、自己分析や企業研究を進めていくのがおすすめです。
志望動機に繋がる
自己分析は、志望動機を作ることにもつながります。
良い志望動機の文章を作りたいなら、まず自己分析を充実させましょう。
自己分析が志望動機につながるのは、それが自分がどのような企業で働きたいか考える助けになるためです。
求めるのは仕事の内容でしょうか、それとも社会的意義や貢献なのでしょうか。
人によっては仕事の内容などより、職場の人間関係が良くほかの方と良いつながりが築けることのほうが重要かもしれません。
自己分析がおろそかだと、どうしても志望動機が企業中心の内容になってしまいます。
「大企業だから」「やりがいがありそうだから」といった理由だけでは、どうしても採用担当者は応募者の意欲を評価しにくくなってしまいます。
本当にその企業で働きたいという気持ちを見せるには、自己分析ベースの志望動機が不可欠です。
選考対策になる
自己分析は自分の強みや弱み、性格を確認する作業なので、選考でそれらの質問をされたときにうまく回答するための材料になります。
エントリーシートでも、自分自身について聞かれることはあるため、早いうちから自分の強みや弱みを的確に表現できるようになっておくことが重要です。
自分の強みや弱みがわかっていれば、仕事で苦手分野があっても、その苦手をカバーしながら仕事を進めやすくなります。
たとえば、せっかちな方であれば、何か仕事の予定が入ったときに細かくメモをとったり、付箋で次にやるべきことを整理したりすれば、順序立ててあわてず行動できるようになるかもしれません。
このように自分の強みや弱みを知って、選考で説明できるレベルにまで理解を深めておくと、仕事でもその分析を活かせるようになります。
自己分析の方法10選
次に、具体的な自己分析の方法を10パターンご紹介します。
これらの方法は、実際に多くの方が実践している方法ばかりです。
自分についてわかりやすく知るための洗練された方法なので、どう自己分析を進めていけば良いか迷ったときは、これらの方法を取り入れてみましょう。
多くの方法は、1人だけでも実施できるものです。
とくに道具を必要としないものも多いので、時間ができたら気軽におこなえます。
ただし、自己分析はある程度の時間が必要なので、空いたときにやるのではなく、腰を据えてやるのがおすすめです。
自分史
自分史とは、自分が過去にどのようなことをしてきたか、年表のように書き記して振り返る方法のことです。
書いたものをもとに、客観的な視点で自分を見つめなおしてみましょう。
自分史の自分は、もしかしたら常に失敗の連続だったかもしれません。
しかし、それはこれまで何度も失敗から学習を得てきたという証でもあります。
社会人となってから、これまで何度も挫折から復活してきたメンタルの強さが活かされるかもしれません。
逆に、自分が幸運に恵まれ成功してきたと思うのであれば、自分がその幸運を引き寄せられた理由について考えてみましょう。
人脈の広さであったならコミュニケーション能力をアピールできるようになるほか、自分の人柄が成功につながっているなら、人柄そのものをアピールできます。
モチベーショングラフ
モチベーショングラフは、過去に自分がどのようなことをしてきたのか、そのときのできごとが自分の心境にどのような変化をもたらしてきたかを書く自己分析方法です。
過去の自分について書いて振り返るという点では、自分史と似たところがあるといえます。
しかし、モチベーショングラフで重要なのは、自分の心境について書くことです。
たとえば、受験に失敗してしまったなどの経験からでも、人によって考えることは違います。
「次はもっと計画的にやろう」「この程度の失敗は痛くない」と前向きにとらえる方もいますが、悔しさから本気で涙してしまった人も多いでしょう。
そのような心境の変化を探ることで、自分がどのようなときに本気で仕事に向き合えるのか、やりがいを感じて精力的にがんばれるのかなどを把握できます。
マインドマップ
マインドマップとは、自分の思考を具現化していくことです。
自分が普段どのようなことを考えて行動していくのか、地図のようにつながりを作っていきましょう。
マインドマップの利点は、自分の行動の動機がわかること、就活の軸を作りやすくなることです。
マップ上でさまざまな項目とつながっているものは、それだけ自分にとって重要なことであると考えられます。
ただし、マインドマップを作るうえで最初に思いついた事柄が、そのまま就活の軸になるとは限りません。
自己分析において、マインドマップは非常に大きな役割を果たしますが、よりその恩恵を得たいなら作り方や活用方法を学んでおくことが大切です。
やみくもに作り始める前に、まずは正しいやり方について調べることをおすすめします。
ジョハリの窓
ジョハリの窓とは、主観的視点と客観的視点の両方から自分の特性を理解する自己分析方法です。
たとえば、自分が自覚していなかった怒りっぽいという性格が、ほかの多くの人から挙げられるかもしれません。
また、「自分は〇〇だ」と思っていたのに、誰からもその指摘を受けないことも考えられます。
ジョハリの窓は、このように自分と他人の認識の差を知るのに役立つことが大きなメリットです。
ほかの方の意見を聞かなければいけない方法なので、1人では実施できません。
加えて、2〜3人の少人数ではなく、互いに知っている人同士である程度の人数を集めて実施しなければ効果が薄くなってしまいます。
少し手間がかかるのがネックですが、客観的な視点で自己分析を進めたい場合におすすめです。
Will・Can・Mustフレーム
Will・Can・Mustフレームは、就活において自分のキャリアプランや志望業界を考えるための枠組みです。
人それぞれ、できること(Can)と、やりたいこと(Will)があります。
しかし、それは必ずしも一致しているとは限りません。
いくら自分がスポーツが好きで、スポーツに関わる仕事がしたくても、フィジカル面で恵まれていなければ一流の選手にはなれないでしょう。
しかし、WillとCanを結びつけることによって、自分ができることや仕事に活かせることを考えられるようになります。
その後、企業研究を通して自分がやるべきこと(Must)を考えていきましょう。
Will・Can・Mustフレームは、就活生だけでなく、社会人になってからキャリアプランを考える際にも役立つ方法です。
ライフラインチャート
ライフラインチャートとは、過去のできごとと、そのときの気持ちを可視化したものになります。
自分史やモチベーショングラフと似ていますが、こちらのほうがより視覚的にわかりやすい方法といえます。
自分が過去にどのようなできごとで嬉しい気持ちになったか、もしくは悲しい気持ちになったかを考えてみましょう。
ほとんどの人生には良いこともあれば悪いこともあり、これまでずっと上り調子の人生を過ごしてきた方はほとんどいないはずです。
どこかで落ち込んだり挫折を経験したりした際に、どのように立ち直ったか、新しいやりがいを見つけたかを知ることが就活に役立ちます。
自分が楽しめる仕事を見つけるといった目的だけでなく、就活でなかなか内定が得られず落ち込んだときに、気持ちを切り替えるのにも有用です。
Whyで掘り下げる
自分の過去の行動について、ひたすら「Why」を掘り下げていくのも有効な方法です。
この方法はとくに準備やツールがいらず、1人でおこなえるのもメリットといえます。
自分がなぜそのような行動をとったのか考え、しっかりと理解することにより、面接で自信を持って話すことができるようになるのがこの方法の利点です。
たとえば「部活で部長として部員を取りまとめるのに○○をがんばった」と言いたいとき、それをなぜやったのか考えてみましょう。
自分がその方法をベストだと確信したからなのか、もしくは何をやって良いかわからなかったからとりあえず行動してみたからなのかなど、Whyの中身によって、同じ経験であってもアピールポイントが変わってきます。
自己分析ツールを使う
自分史やマインドマップなどの方法がなかなかうまくいかない方は、自己分析ツールを使ってみるのがおすすめです。
ある程度多くの方が使いやすいよう設計されているため、ツールの使用方法を守って分析していくだけで、質の高い自己分析がおこなえます。
その結果をもとに、もう一度改めて自分の過去を振り返ってみるのも良いでしょう。
多くの自己分析ツールは、無料で使えるようになっています。
就活に特化した自己分析ツールを使うと、よりいっそう自分の職業選びや就活の軸作りに役立てられます。
もちろん、これらのツールで得られた結果も、あくまで参考にすぎません。
自分が本当に就きたい職業が決まっているのであれば、その意欲を優先して就職先を考えるのが良いでしょう。
キャリアアドバイザー
自己分析は、必ずしも自分1人でおこなわなければいけないわけではありません。
ほかの人に自分についてどう思うか聞いてみて、その結果を分析する他己分析も、自己分析の一環になります。
そこでおすすめの自己分析方法が、就活のプロである就活エージェントのキャリアアドバイザーに相談してみることです。
どのように自己分析をおこなえば良いか迷った人や、就活において不安に思うことがある場合は、まずはキャリアアドバイザーに相談してみましょう。
また、自分の強みや適性はわかったものの、どの業界が良いか迷っているといった場合も相談できます。
キャリアアドバイザーとの面談では、自己分析だけでなく、業界選びのサポートや面接対策などをおこなうことも可能です。
就活エージェントのキャリアアドバイザーに相談できる詳しい内容は、以下のサイトをご確認ください。
自己分析の注意点
次に、自己分析の注意点を3点ご紹介します。
自己分析は就活における非常に重要な要素ですが、分析が楽しくなってしまい、のめりこみすぎてしまってはいけません。
あくまで自己分析は、就活を有利に進めるための前段階です。
就活に役立つポイントを抽出し、エントリーシートの記入に役立てることも忘れないようにしましょう。
また、自己分析だけでなく、業界・企業研究に割く時間も大切です。
限られた時間を有効に使い、着実に就活の準備を進めていきましょう。
企業からの視点を持つ
自己分析の結果が、独りよがりなものになってはいけません。
応募者を採用するかどうかは、企業が決めることです。
企業がどのような方を採用したいか考え、企業側の視点に立って分析することで、より良い自己分析にすることができます。
自分は志望先の企業にとって、魅力的な人材に映るでしょうか。
現在の自分が、企業にとってあまり魅力的な人材でないと感じるなら、なんらかの方法でカバーする必要があります。
それはこれからの伸びしろかもしれませんし、弱点を補って余りあるだけの長所かもしれません。
企業が採用したくなるようなアピールにつなげるには、自己分析の結果を採用担当者になったつもりで評価してみるのがおすすめです。
自分1人でうまくできない場合は、就活エージェントのキャリアアドバイザーなどに相談してみるのが良いでしょう。
経験を考慮する
自己分析で陥りがちな失敗は、過去の自分の感情だけを振り返ってしまうことです。
しかし実際には、経験に付随した感情が自分にとって重要な役割を果たしています。
その経験から何を学び、その後の自分の成長につながったのかを考えてみましょう。
とくにエントリーシートや面接では、ガクチカを必ずと言っていいほど聞かれます。
ガクチカは学生時代にもっとも力を入れた活動のことであり、ここでは経験を中心に文章を組み立てなければいけません。
その経験が自己形成にどのように影響しているか、仕事でもその経験は活きてくれそうかを考えてみましょう。
仕事と過去の経験を結びつけて説明できれば、採用担当者にも入社後に活躍してくれそうなイメージを持ってもらいやすくなります。
インプットだけで終わらない
就活の自己分析を何のためにやるのかは、内定を得るため、自分に合う仕事に就くためです。
そのためには、企業に効果的にアピールする必要があります。
アピールは、自己分析の結果をアウトプットすることとも言い換え可能です。
自己分析で得たものを自分の意識にインプットするだけではなく、それを具体的な文章や言葉で説明できるようにしておきましょう。
とくにマインドマップでは、責任感などといった単語レベルで自己分析を進めていきます。
しかし就活のアピールでは、単語レベルだけではまったくアピールになりません。
「自分は責任感があります」などの結論に続いて、その理由や補足するエピソードをわかりやすく伝える必要があります。
そのため、自己分析がひと段落したら、アウトプットの作業にも取りかかるようにしましょう。
自己分析を自分でやるのが難しい時には?
自己分析を自分でやるのが難しいと感じたときは、無理に1人だけでおこなう必要はありません。
ほかの方の力を借りながら、効率的に自己分析を進めていきましょう。
就活の準備段階では、業界・企業研究も並行しておこなう必要があるため、行き詰まったり疲れたりしたら、気分転換として企業をリサーチしてみるのもおすすめです。
また、筆記試験の対策を講じるのも良いでしょう。
友達に相談しよう
自己分析を1人でおこなうのが難しいと感じたら、友達に自分の性格や長所について尋ねてみるのがおすすめです。
もしかしたら、自分が気づけなかった部分を指摘してくれるかもしれません。
友達とおこなう自己分析に「ジョハリの窓」がありますが、これはある程度の人数を集めなければできない方法です。
なかなか多くの人が集まる時間を確保できない場合は、近くの友人に自分について尋ねてみることで代用する方法も考えられます。
加えて、他己分析ついでに、就活の情報を交換するのもおすすめです。
先輩に相談しよう
就活を経験した先輩に相談し、自己分析をどのように進めていったのか聞いてみるのも良いでしょう。
とくに自分と同じ業界に進んだ先輩がいれば、その人を頼るのがおすすめです。
なかなか参考になりそうな先輩が近くにいない場合は、OB・OG訪問をするのも良いでしょう。
企業がOB・OG訪問について、積極的に情報を出していない場合でも、問い合わせれば対応してくれることがあります。
OB・OG訪問では、入社後の業務について質問するケースが多いですが、就活について尋ねてもまったく問題ありません。
まとめ
就活において、準備段階をしっかりしておくと、その後の自信につながります。
就職活動の準備とは、自己分析や業界・企業研究のことです。
とくに自己分析は、志望動機作りや就活の軸を決めることに大きく影響するため、重要度が高いポイントになります。
自分史やマインドマップなど、自分1人での作業に限界を感じた場合は、他己分析を取り入れてみるのがおすすめです。
自己分析のやり方に迷ったときや、客観的なアドバイスをもらいたいときなどは、就活エージェントのキャリアアドバイザーに相談してみるのも良いでしょう。