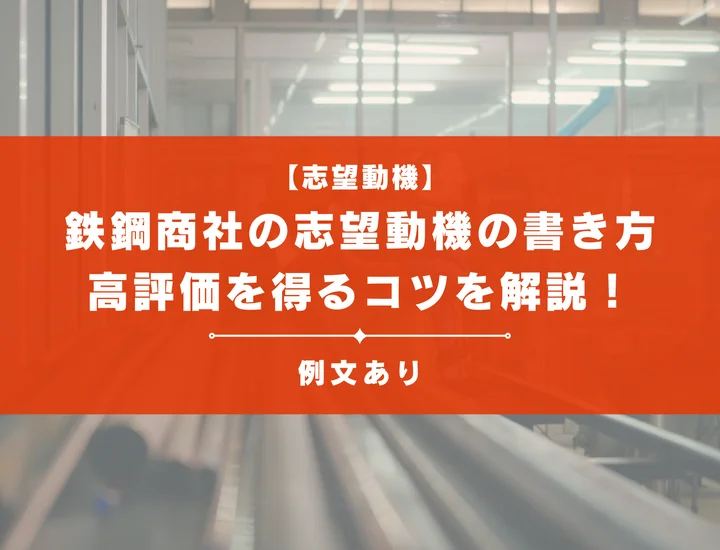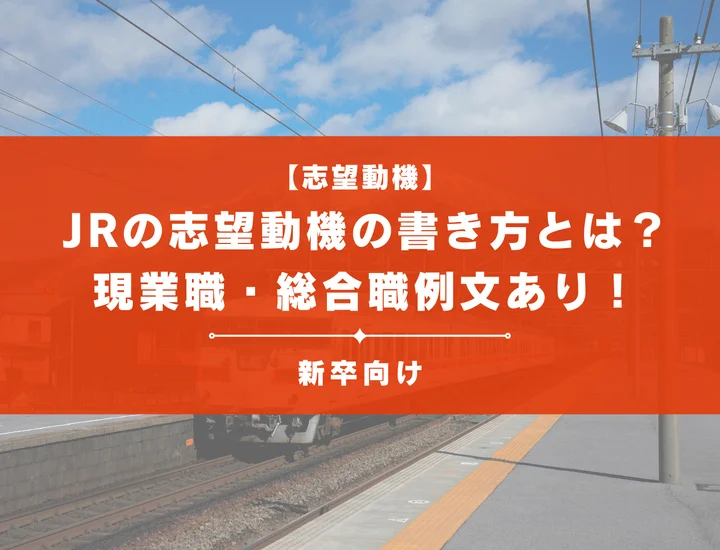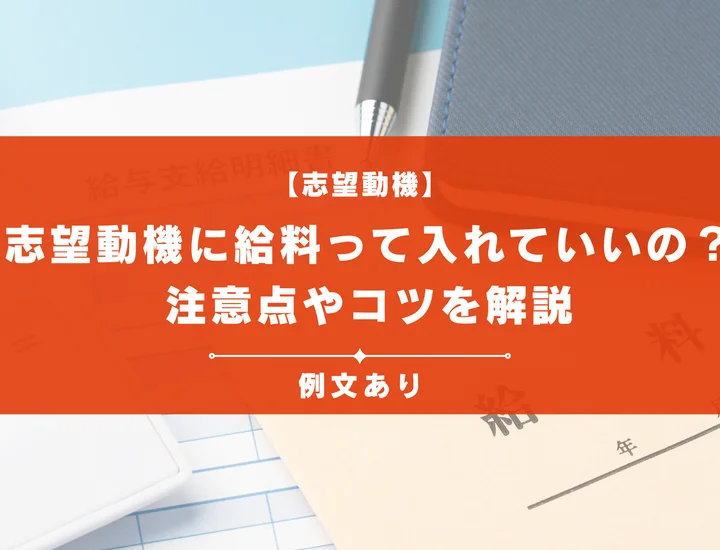- 「御社」と「貴社」の使い分け
- 一般企業以外の呼称
- 志望動機作成のコツ
- 「御社」と「貴社」で頭が混乱している人
- 一般企業以外も視野に入れている人
- 志望動機を基礎から学びたい人
はじめに
就活において「御社」と「貴社」の違いがよくわからず困惑してしまっている方も多いでしょう。
確かに基礎的な部分ではありますが、基礎的だからこそ、誰にも聞けず、結局どちらがどっちなのかわからなくなっている方もいるはずです。
そこで今回は2度と間違えないために「御社」と「貴社」の使い分けについて紹介しつつ、志望動機を作成する際のおすすめの構成などについても解説するため、ぜひ参考にしてください。
志望動機で「御社」と「貴社」をどのように使い分ける?
- 御社
- 貴社
まず、志望動機において「御社」と「貴社」をどのように使い分けるのかについて明確に定義しておきましょう。
この記事でしっかりと区別を押さえておけば、今後迷うこともなくなり、志望動機を作成する際に余計な悩みや雑念が減ってスムーズに作成できるようになるはずです。
御社
「御社」は面接や電話、会社説明会などの際に使う言葉です。
「御社」と「貴社」を両方発音してみると、おそらく言いやすいのは前者でしょう。
したがって「『御社』の方が口で話す際に言いやすいから、話す時は『御社』だ」と覚えておいても良いです。
ただし、面接や電話などで緊張した際に「御社」と「貴社」を混同してしまうこともあるでしょう。
このような場合、どちらが正しかったかについて考えることばかりに頭が回ってしまい、黙り込んでしまうこともありますが、実は「御社」というのも「貴社」というのも、間違えて「御社」と言ってしまったからといって、そこまで重大なミスではありません。
相手も人間ですから「この子は緊張しているんだな」くらいにしか思いません。
敬語がめちゃくちゃで、ESも字が汚い、締切も守らないなど、悪い要素がいくつもある場合はさらに悪い印象を与えることになってしまいますが、しっかりしている就活生に対して、その程度のミスで評価を下げる面接官はあまりいません。
貴社
「貴社」は書面で企業を指す際に使用する敬語として最も適切です。
履歴書、エントリーシート、メールなどの公式な文章では「貴社」を使うようにしましょう。
書面で「貴社」を使う際の注意点としては書面全体の統一感を意識することが挙げられます。
一度「貴社」を使用した場合、同じ書面内で「御社」と混在させないようにすることが大切です。
特に文章において「御社」を使ったからと言ってマイナスな印象を与えるわけではありませんが「貴社」と書いたり「御社」と書いたり、バラバラの場合はマイナスな印象を与えてしまう可能性が高まります。
一度「貴社」と書いたならば、すべての文章において必ず「貴社」と書くようにしましょう。
志望動機で「御社」と「貴社」を使う際の注意点
- 一般企業でない場合の言い方に気を付ける
- 他の言葉と混同しないようにする
- 二重敬語にならないようにする
志望動機で「御社」と「貴社」を使う際の注意点についても紹介します。
以下の3つの注意点を把握しておかないと、マイナスな印象を与えてしまう可能性があるため注意が必要です。
一般企業でない場合の言い方に気を付ける
まず、一般企業でない場合の言い方に気をつけましょう。
病院や学校、店舗など特定の分野においてはそれぞれ「御院」「貴院」「御校」「貴校」「御店」「貴店」といった表現が適しています。
言い方を間違えると、相手の業界や立場への理解が浅いとみなされ、採用担当者に悪い印象を与える可能性があります。
業界や職種に応じた敬語表現を正確に使い分けることは志望動機やあなた自身の信頼性を高めるために欠かせないポイントであるため、必ず正しい表記で書くことを心がけましょう。
他の言葉と混同しないようにする
他の言葉と混同してしまうことはあまりないかもしれませんが、念のため注意が必要です。
「当社」や「弊社」といった書き方は就活において書くことはほとんどありませんが、間違えてこれらの言葉を書いてしまうと、主語が何なのかがわからなくなってしまうことがあります。
相手が主語であるにも関わらず「弊社」などと書いてしまうと、何を言っているのかがわからず「常識が無く、そして文章が読みにくい人物である」と思われてしまう可能性があります。
「御社」と「貴社」を間違えるくらいなら問題ありませんが「弊社」や「当社」などと書いてしまうと、主語が変わってしまうため注意しましょう。
二重敬語にならないようにする
二重敬語になってしまう人も稀にいるため、注意が必要です。
「貴社様」や「御社様」といった使い方は典型的な間違いであるため、気をつけましょう。
面接で緊張して「御社様の事業に感銘を受けました」などと述べてしまうと「常識がない人物なのではないか」と思われてしまいます。
ESも、完成した後は何度も「貴社様」と間違えて書いてしまっていないかについて確認してみてください。
こうした細かい部分にもしっかりと配慮できている人物こそ、内定に最も近い人物です。
志望動機の聞く理由
- 人柄を知るため
- 社風に合うか見極めるため
- 活躍できるか判断するため
続いて、企業が志望動機をなぜ聞いてくるのかについても紹介します。
以下の理由はどのような企業においても当てはまるものであるため、志望動機を読んでその内容が伝わるような書き方を心がけましょう。
人柄を知るため
企業が志望動機を聞く理由の1つに、応募者の人柄を深く理解することが挙げられます。
志望動機にはその人がどのような価値観を持ち、どのような行動をとる人なのかが反映されます。
面接官は応募者が話す志望動機を通じて、その人がどのような価値観を持ち、何を重視して行動しているのかを知りたいと考えています。
この情報は応募者が企業や職種に適しているかを判断するための重要な手掛かりです。
人柄を伝えるためには自分の考え方や行動の動機を探りながら話すことを推奨します。
「社会課題を解決したい」という志望動機を述べるならば、その理由に至る具体的な経験や背景を共有することで、どのような人間性を持っているのかがより分かりやすくなります。
社風に合うか見極めるため
応募者が企業の社風に合うかどうかを見極めるために志望動機を聞かれることも多いです。
企業にはそれぞれ独自の文化や価値観が存在しており、社員がその文化に適応し活躍するためには応募者の性格や価値観が社風と一致していることが重要です。
面接官は志望動機を通じて、応募者が自社の理念や目標に共感しているかを確認し、それが職場での適応力やパフォーマンスにどう影響するかを判断しています。
企業の社風には革新性を重視する場合もあれば、現実的な姿勢を保ちながら着実に成長することを重視する場合もあります。
変化を歓迎する企業ならば柔軟性や挑戦心が求められますし、規律を重視する企業では安定感や計画性が評価されます。
志望動機においては、自分がどのような性格や価値観を持ち、それが企業文化とどのように一致しているのかを具体的に示しましょう。
活躍できるか判断するため
企業が志望動機を質問する理由には、応募者が入社後にどのように活躍できるかを判断したいという意図も含まれています。
志望動機には応募者の熱意や価値観、スキルが凝縮されており、それらが企業の求める人物像に合致しているかを見極める材料となるからです。
また、過去の経験や考え方を通じて、仕事の中で成果を上げられる可能性や成長の見込みを確認することも可能です。
活躍できるかを判断する際、企業は志望動機に含まれる具体的なエピソードに注目します。
これまでの学生生活において、どのように課題を解決し、成果を上げたのかなどが書かれていると、採用担当者は応募者が持つ能力や行動力をイメージしやすくなります。
また、その経験が志望する職務や業務にどのように応用できるかを志望動機で明示しておけば「入社後に即戦力として活躍してくれる」と期待してもらえるはずです。
志望動機作成の際のポイント
- なぜその業界なのかを述べる
- なぜその企業なのかを述べる
- 入社後にどう貢献できるか述べる
続いて、志望動機を作成する際のポイントについても紹介します。
以下のポイントはどのような企業を受ける際にも活用できる内容であるため、ぜひ参考にしてください。
なぜその業界なのかを述べる
志望動機を作成する際はなぜその業界を選んだかを明確に述べることが重要です。
数ある業界の中からその業界を選んだ理由を具体的に説明することで、意志の強さや業界に対する理解の深さが採用担当者に伝わります。
この部分が不明確だと「適当に応募している」という印象を与えてしまい、選考での評価を下げてしまいます。
業界を志望する理由を述べるためには、まず業界研究を徹底することが必要です。
業界の特徴やトレンド、課題などを把握し、自分がどのようにその業界で価値を提供できるかを考えることで、具体性を持った志望動機が出来上がります。
また、自分の経験やスキルと業界との関連性を述べることも重要です。
大学で学んだ専門分野の知識やアルバイトでの経験が、その業界でどう活かせるかを明確にしましょう。
なぜその企業なのかを述べる
志望動機を作成する際は、なぜその企業を選んだのかを明確に述べることも不可欠です。
同じ業界の中にも多数の企業が存在する中で、なぜ特定の企業を選んだのかを具体的に説明することで、企業理解の深さや熱意が伝わります。
この理由が曖昧だと「他社でも良いのではないか」と受け取られ、採用担当者の心に響きません。
その企業を選んだ理由を述べるためには企業研究が欠かせません。
企業の公式サイトやSNS、採用パンフレット、ニュース記事などを活用して、企業の特徴や強みを深く理解しましょう。
その上で、自分がその企業のどの部分に共感したのかを具体的に述べることが重要です。
入社後にどう貢献できるか述べる
企業は活躍してくれる人材を採用したいと考えているため、入社後にどのように貢献できるのかを述べることで、さらに印象が良くなるでしょう。
採用担当者があなたの将来性や即戦力としての可能性を判断する際に重要な材料となるからです。
まず、自分が目指すキャリアや目標を明確にし、その後、企業の業務や目標と結びつけることが大切です。
学生時代にどのような経験をしてきたのか、そしてその経験から培った能力を企業のどのような事業に活かせるのかについて、具体的かつわかりやすく説明することを心がけましょう。
志望動機を作成する際のコツ
- 内定者の志望動機を参考にする
- 他の就活生と差別化をする
- どうしてその企業が良いのかを書き出してみる
続いて、志望動機を作成する際のコツについても紹介します。
先ほど紹介した志望動機を作成する際のポイントと合わせて確認することで、より質の高い志望動機が出来上がるはずです。
内定者の志望動機を参考にする
内定者の志望動機を参考にすれば、よりクオリティの高い志望動機をスムーズに作成できるでしょう。
選考を通過し、内定を得た志望動機であるということは、採用担当者に刺さったポイントが含まれているはずです。
それを参考にすることで、自分がどのような経験や考えをアピールすれば良いかの方向性を見つけやすくなります。
ただし、この方法で注意すべき点は「丸ごとコピー」はしないことです。
あくまで「参考」程度にして、自分なりの志望動機、経験、能力を強調することを心がけましょう。
重要なのは「どのような構成で記述されているか」「どの部分が採用担当者に響いたのか」を分析することです。
他の就活生と差別化をする
志望動機を作成する際には、他の就活生との差別化を意識することも欠かせません。
面接官は多くの応募者と接するため、ありきたりな内容や一般的な表現では印象に残りにくいです。
そのため、志望動機の中で自分ならではの強みや価値観を具体的に述べて、差別化を図りましょう。
他の就活生との差別化をするためには、まず自分の経験やスキルを深掘りすることが重要です。
自分がこれまで取り組んだことや得た学びを整理して、それを志望企業でどう活かせるかを具体的に示すことで、他の応募者との差を際立たせることができます。
また、自分の考え方や行動に至った背景を明確に述べることで、志望理由にさらなる説得力を持たせることも可能です。
どうしてその企業が良いのかを書き出してみる
志望動機を作成する際にはまず「なぜその企業が良いのか」を書き出すことから始めましょう。
これにより、自分がその企業を選んだ理由を整理し、説得力のある志望動機を作る基盤となるのです。
また、この作業を通じて応募する企業の魅力や他の企業と異なる点を明確にすることができ、面接官に強い印象を与える内容を構築しやすくなります。
「なぜその企業が良いのか」を明確にするためには、企業研究を徹底的に行うことが必要です。
企業の公式サイトやSNS、ニュース記事、採用情報などを参考にしながら、企業の特徴や独自性をリストアップしましょう。
企業の使命、社会的な取り組み、社員へのサポート体制、成長戦略などに注目すると、その企業ならではの魅力を見つけやすくなります。
志望動機の構成
- 結論
- 理由
- エピソード
- 貢献
最後に、ここまで紹介してきた内容を踏まえた上で、おすすめの志望動機の構成について紹介します。
この構成はどのような業界でも、どのような企業でも活用できるものであるため、ぜひ覚えておいてください。
結論
志望動機の構成において、結論部分は最も重要です。
まずはあなたがなぜその企業を目指しているのかを一言で述べましょう。
話の趣旨が明確になり、相手がスムーズに内容を理解できるようになるはずです。
結論を述べる際には自分の志望理由を明確にすることが大切です。
一言で、自分が企業に惹かれた理由を具体的に示しましょう。
この部分はあまりだらだらと書きすぎず、その後に続く理由やエピソードに文字数を割けるよう、簡潔に述べることが大切です。
理由
理由の部分では「結論」を支えるための背景や根拠を簡潔に説明することが大切です。
この部分が明確でないと、結論、つまり志望動機が表面的なものだと思われてしまう可能性があります。
理由を述べる際には、自分がその企業や職種を志望するに至った具体的な経緯を含めましょう。
理由の中では企業の理念や事業内容と自分の価値観がどのように一致しているかを示すことを推奨します。
自分の背景と企業の特徴を結びつけることで、説得力が増します。
また、企業研究を通して得た情報を活用し、自分が企業に興味を持った具体的な理由を述べることで、採用担当者に熱意を伝えることもできます。
エピソード
志望動機において最も重要な部分であるエピソードは力を入れてしっかりと書きましょう。
採用担当者があなたの価値観や能力を深く理解するための重要な材料だからです。
また、エピソードが説得力を持つものであればあるほど、他の応募者との差別化を図ることができ、選考を有利に進められる可能性が高まります。
エピソードを述べる際には、自分が過去に取り組んだことや成功体験を具体的に説明し、それが志望理由にどのように結びついているのかを説明することが大切です。
また、具体的な成果や学びを含めることも推奨します。
自分がどのような結果を出せる人物であるのかを説明すると、就職後に貢献してくれると期待してもらえます。
貢献
貢献の部分では自分が入社後にどのように企業に価値を提供するかを明確に述べることが大切です。
あなたを企業に迎え入れることでどのようなメリットがあるのかについて、わかりやすく説明しましょう。
貢献について述べる際にはまず自分の強みやスキルを明確にして、それが企業の目標や業務にどのように還元されるのかを説明することが求められます。
可能な限り、採用担当者にとってイメージしやすい説明を心がけましょう。
就活エージェントに相談する
今回は「御社」と「貴社」の使い分けについて紹介した後に、志望動機のおすすめの構成や、魅力的にアピールするためのポイントなどについて詳しく紹介しました。
「御社」と「貴社」の使い方については理解できたでしょうが、志望動機を作成するにあたってはまだ不安点がある方も多いはずです。
そんな方には弊社が提供している「ジョブコミット」という就活エージェントサービスの利用をおすすめします。
「ジョブコミット」では志望動機や自己PR、ガクチカといった就活で聞かれる可能性が非常に高い項目の添削だけでなく、面接の練習も可能です。
また、おすすめ企業や非公開求人の紹介、業界分析や企業分析シートの配布も行っているため、就活生にとって便利なサービスが豊富です。
以下のリンクから完全無料で登録できるため、気になる方はぜひ利用してみてください。
まとめ
今回は「御社」と「貴社」の使い分けについて説明しつつ、志望動機を作成する際のコツやポイント、構成などについて紹介しました。
「御社」と「貴社」は基礎的な知識ではありますが、間違えることが不安な方もいるかもしれません。
しかし、違いを明確にして、さらに「間違えたとしても、大した問題ではない」と覚えておくことで、心に余裕を持って選考に臨むことができます。
また、本記事で紹介した志望動機を作成する際のコツは、どのような業界や企業を受ける際にも活用できる内容です。
汎用的な知識として、ぜひ参考にしてください。