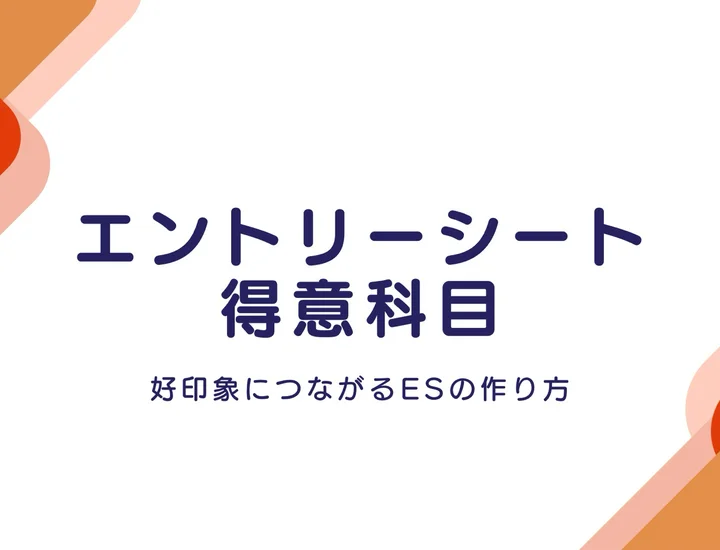明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
- ESで得意科目が聞かれる理由
- 得意科目の選び方
- 得意科目が思いつかない場合の対処法
- 得意科目の回答方法
- ES作成中の就活生
- ESで得意科目を聞かれた人
- 得意科目が思いつかない人
- ES対策を万全にしておきたい人
目次[目次を全て表示する]
ESで聞かれる「得意科目」
企業に提出するESにおいて、「あなたの得意科目はなんですか?」という設問が設けられていることがあります。
この設問に対してどのような回答をすることが正しいのでしょうか。
また企業はどのような意図があって、就活生の得意科目を知ろうとしているのでしょうか。
ESを作成する前に企業の意図や回答のコツ、例文を把握しておくことで好印象につながるESを作成しましょう!
【ESで得意科目を聞かれた】得意科目の選び方
得意科目が1つしかない方の場合は読み飛ばしてもらっても構いませんが、複数ある場合、どのような選び方をすれば良いのでしょうか。
様々な基準が存在しますが、以下の3つ、いずれかを基準として得意科目について回答をすれば、悪い印象を与えることはありません。
ぜひ、それぞれの項目について確認してみてください。
高校の科目で書くべきか、大学の科目で書くべきか
ESで得意科目を求められた時に、高校の科目を書くのか大学の科目を書くのか、迷ってしまう就活生も多いと思います。
結論から述べると、ESに記載する「得意科目」は高校の科目と大学の科目のどちらでも問題はありません。
高校生時代の科目であれば数学や英語、大学生時代の科目であれば心理学や経済学、というように習ってきた科目名を記載するようにしましょう。
ただし、企業によっては指定がある場合もあり、また採用担当側が得意科目から何を知ろうとしているかによって回答内容が異なるため、不安な場合は採用担当に問い合わせてみましょう。
成績が優秀な科目
まずは当然ですが、成績が優秀な科目を選ぶことです。
あなたがどれだけ努力し、成果を上げたかを企業に対して証明する1つの手段になります。
成績が良いということはその科目に対する理解度が高く、努力を惜しまなかったことを示すため、自己管理能力や継続的な努力の姿勢をアピールするための材料にもなります。
大学で高い評価を得た「経済学」や「マーケティング論」を得意科目として挙げることで、学びに対して真剣に取り組んできたことを伝えられるでしょう。
この実績を基に、企業はあなたが自分の目標を達成するために努力し、成果を出すことができる人物だと評価するはずです。
優れた成績は自己管理能力や計画性、問題解決能力を示す要素ともなり得ます。
忙しい授業と課題の中でどのように計画的に学習を進めてきたかを語ることができれば、仕事においてもその能力を発揮できることを伝えられます。
志望職種や業務内容に関連する科目
志望する業界や職種に関連する科目を選ぶと、企業への適性を強調しやすくなります。
企業は就活生が業務にどれだけ適応できるか、どのようなスキルを持っているかを見極めるため、関連性のある科目を挙げることが評価に繋がります。
マーケティング職を志望するならば「統計学」や「経済学」などの科目が良いでしょう。
また、技術職を志望する場合は「物理」や「プログラミング」など、技術的な知識が必要となる科目が有力な選択肢です。
このように、得意科目が志望職種に関連していることをしっかりと伝えることで、あなたの適性を企業にアピールでき、採用される確率を高めることができます。
自己PRしたい強みと関連する科目
自己PRしたい強みと関連する科目を選ぶことも重要です。
自分の強みを引き出すためには、どの科目がその強みを最も強調できるかを考えることが必要です。
プレゼン能力を強調したい場合「国語」や「コミュニケーション論」など、言語表現やコミュニケーション技術を学べる科目を挙げると良いでしょう。
また、チームワークをアピールしたい場合はグループ課題や共同作業を重視した科目を選ぶことが有効です。
「社会学」や「グループワーク」においてチームで協力しながら学んだ経験を交えながら説明しましょう。
強みを最大限に引き出すためには、その強みがどのように学業や経験に結びついているのかを明確にすることが必要です。
得意科目を通じてその強みが発揮されたエピソードを挙げることで、企業に対して強い印象を与えることができます。
【ESで得意科目を聞かれた】得意科目が思いつかない場合の対処法
「得意科目が思いつかないから、この記事を開いている」という人も多いでしょう。
そこでここからは得意科目が思いつかない場合にはどのような対策をすれば良いのかについて詳しく紹介するため、参考にしてください。
自己分析
得意科目が思いつかない場合、まず最初に行うべきことは自己分析です。
過去に学んだ科目や取り組んできたプロジェクト、レポート作成などの経験を振り返り、自分がどの分野に強みを持っているのかを整理することが重要です。
自己分析を通じて、自分がどの科目に対して最も興味や関心を持ち、どの分野で成果を上げたのかを洗い出せます。
成績が良かった科目や、積極的に取り組んだテーマが無いか、考えてみましょう。
過去の試験やレポートを見返し、どの分野で特に自信があったのかを振り返ると、自分の強みが自然と見えてきます。
また、学外活動やプロジェクト活動も自己分析の一環として役立ちます。
サークル活動やインターンシップで学んだスキルや知識が学業と関連している場合、その経験も得意科目の一部として考えられます。
過去の成績や興味関心を振り返る
過去の成績や興味関心を振り返ることも有効な方法です。
自分がどの科目で優れた成果を上げたかを思い出し、その理由を深掘りしてみると、得意科目が自然と浮かび上がることがあります。
まず、成績表やレポートを振り返り、どの科目で良い評価を受けたのかを確認しましょう。
特に高評価を得た科目は自分にとって得意である可能性が高いです。
その際、どの部分で努力したのか、どのようなアプローチを取ったのかを掘り下げることも重要です。
もし、大学で目立った成績を収めていなかった、もしくはアルバイトなどで忙しく、成績が悪かった場合は、高校までの得意科目を思い出してみてください。
国語が得意だったなら「国語力を活かしてコミュニケーションが円滑に取れる」と話せますし、数学が得意なら「論理的思考力を活かして問題解決ができる」などとも話せます。
大学以降の科目が主な主題とはなりますが、どうしても話すことが無い場合は、高校までの科目の話をしても全く問題ありません。
自分の志望する業界に関連する科目を見つける
得意科目が思い浮かばない場合、志望する業界や職種に関連する科目を見つけ、それをアピールする方法があります。
たとえば、営業職を志望する場合、マーケティングや経済学、心理学などの科目が関連性のあるものとして挙げられます。
コミュニケーションに関する授業で得た知識やプレゼンテーションの経験を、営業の仕事に活かせる点として説明すると、説得力が増します。
また、エンジニア職を希望する場合、数学やプログラミングに関する科目を選ぶのが適しています。
特に、問題解決力が求められる業務では、論理的思考を養う授業が役立つことをアピールすると良いでしょう。
このように、成績の良し悪しにかかわらず、自分が受講した科目の中で業界との関連性を探し、それが仕事にどのように活かせるかを考えることが重要です。
【ESで得意科目を聞かれたら?】企業が知りたい4つのポイント
企業は得意科目について聞き、就活生の何を知りたいと思っているのでしょうか。
もちろん企業によって様々な意図が存在しますが、以下の4点は多くの企業に当てはまるものです。
あらかじめ企業の意図を把握しておくことで、効率よく好印象につながる回答を作成することができるため、以下の4点はしっかりと抑えておきましょう。
学業に対する取り組み姿勢
企業が得意科目を質問する際、まず最初に確認しようとしているのは学生が学業に対してどのような取り組みをしているかという姿勢です。
学業に対する真摯な取り組み方は課題解決力や責任感、努力の積み重ねといった職場で求められるスキルにも直結します。
得意科目を「経済学」とするならば、経済に関する知識を深めるためにどれだけ努力したのか、その過程でどのような工夫を重ねたのかを企業は知りたいと考えます。
学業の取り組み方が示すのは、単にその科目に関する知識やスキルだけではなく、問題解決や論理的思考力、さらに与えられた課題に対する責任感や継続的な努力の姿勢です。
「経済学の学びを深めるために、毎日10ページを目安に定期的に勉強し、わからない部分は同じ学部の先輩に質問するようにしていました」など具体的な取り組みを伝えることができれば、企業に対して「学業においても自分の課題に真剣に取り組み、成果を上げている人物だ」と強く印象づけることができます。
業務内容への適性
企業が得意科目を質問するもう1つの目的は、その学生が志望する職種や業務内容にどれほど適しているかを判断するためです。
得意科目は就活生の強みや職務に関連するスキルを示す重要な手がかりとなります。
得意科目が「数学」だとすると、それは分析力や論理的思考力、データ処理能力など、特に技術職やデータ分析の業務に必要なスキルを持っていることを示唆しています。
また「英語」が得意な場合、コミュニケーション能力やグローバルな視野、海外との取引や顧客対応が求められる職務において適性を持っていることが分かるでしょう。
得意科目に関する具体的なエピソードや実績を示し、そのスキルがどのように業務に活かされるのかを具体的に説明することが大切です。
専門性の有無
企業が得意科目を聞く理由の1つとして「その学生の専門性や知識レベルを確認し、即戦力として活躍できるかどうかを見極めるため」も考えられます。
特に、理系や技術系の職種においては、学んだ専門知識をどのように実務に応用するかが重要なポイントです。
得意科目として「物理学」を挙げるとして、その知識がどのように実際の仕事に活かせるのかを企業は知りたいと考えます。
物理学の理論や実験に関する知識をどのように応用し、問題解決に役立てたのかを示すことが求められます。
また、文系の方でも「経済学」や「マーケティング理論」などを得意科目として挙げる場合、その知識をどのように業務に活かすか、論理的思考や分析力がどのように活用されるかを説明することが重要です。
面接での質問材料にするため
ESで記載した得意科目は、書類選考突破後の面接において再度話題に出されることがあります。
それはアイスブレイクとしての話題にされることもあれば、質問として深掘りされることもあります。
そのため、面接の場で「なぜ得意なのか」「どのようなことを意識してきたのか」など様々な角度で話を広げられるように準備しておくことも選考突破のカギとなります。
【ESで得意科目を聞かれた】得意科目の書き方
ESで得意科目について聞かれた際はただ一言「国語」などと書いて終わりではありません。
どのような書き方をすれば良いのかについてポイントを押さえておくことが重要です。
以下の4Stepを理解した上で得意科目について書けば、企業の採用担当者に良い印象を与えることができるでしょう。
Step1:科目名
得意科目をESで回答する際、まずはその科目名を具体的に挙げることが非常に重要です。
曖昧な表現を避け「経営戦略論」や「プログラミング基礎」など、明確な科目名を使うことで、採用担当者に対して学んだ内容のイメージをはっきりと伝えられます。
「経済学」や「ビジネス英語」など、一般的でなく、特定の領域に焦点を当てた科目名を挙げることにより、その分野に対する専門性を強調しましょう。
科目名を具体的に示すことで、自己PRに説得力を持たせ、どれほど深くその科目に取り組んできたのかを示せます。
また、企業側にとっても、得意科目が業務にどのように関連するかが明確になり、就活生がどの分野において強みを持っているのかが一目で理解できるため、伝える能力が高いことも強調できます。
Step2:科目の内容や学んだこと
科目の内容や学んだことを簡潔に説明することも重要です。
専門用語を多用せず、企業担当者が理解しやすい表現を選ぶことで、採用担当者に対してその科目がどのような内容であるのかを、わかりやすく伝えることができます。
「経営戦略論」について述べるならば、授業で学んだ内容やテーマについて簡潔に説明する必要があります。
「経営戦略論では企業の長期的な成長戦略を考えるために、外部環境の分析や内部リソースの評価方法を学びました」など、どのような知識を得たのかを端的に伝えましょう。
このように説明することで、企業がその科目を通じてどのようなスキルや知識が身についたのかが具体的にわかります。
また、専門用語を使い過ぎると企業担当者が理解できない場合もあるため、できるだけ平易な言葉を使い、簡潔に説明することが重要です。
Step3:得意になった理由や背景
得意科目を選ぶ際、その科目を得意とする理由や背景を述べることもおすすめです。
あなたがどれだけその科目に対して興味や関心を持ち、学ぶためにどれほど努力したのかを伝えましょう。
「経済学が得意である理由は、社会の仕組みに深い興味があり、学びを通じて実生活にどう影響を与えるのかを知りたかったからです」といった具体的な背景を述べることで「得意」というだけでなく、その科目に対してどれほど熱心に取り組んできたのかを示すことができます。
企業はその科目に対してどれだけ自発的に学んだか、またその学びをどのように活用したのかに注目します。
背景や努力の過程をしっかり伝え、学業に対する姿勢や主体性をアピールしましょう。
Step4:入社後にどう活かせるか
得意科目を記載する際、その学びを今後どのように業務に活かせるかを具体的に記述することが大切です。
学んだ知識やスキルが実際の仕事にどう応用されるのかを説明することで、企業に対してどれほど自分が実践的なスキルを持っているかをアピールできます。
得意科目が「統計学」ならば「統計学で培った分析力を活かし、マーケット調査やデータ分析に取り組みたい」と述べることで、その科目で学んだ知識が実際の業務にどれほど活用されるかを伝えられます。
その他にも、得意科目が「プログラミング」の場合は「プログラミングのスキルを活かし、システム開発やアプリケーション開発に貢献したい」といった形で、実務に直結するスキルを強調すると良いでしょう。
このように、学んだことを業務にどう活かせるかを具体的に記述することで、企業が求めるスキルと自分の得意科目を関連付けられ、企業に対して自分がどれほど貢献できる人物であるかを示すこともできます。
【ESで得意科目を聞かれた】得意科目を書く際に重要なポイント
ESで得意科目を問われた際には、単に「数学が得意です」「英語が得意です」と答えるだけでは十分ではありません。
企業は就活生の学力そのものを評価するのではなく、その科目に対する姿勢や学びのプロセス、さらにそれを業務にどう活かせるのかを知りたいと考えています。
得意科目を書く際に意識すべきポイントとして、特に「情熱」「根拠」「仕事への応用」の三つが重要になります。
これらの要素を踏まえ、自分の学びを深く掘り下げて伝えることで、企業に対してより強いアピールができるでしょう。
得意科目への情熱
ESに得意科目を記載する際は、単に「得意だ」と伝えるだけではなく、その科目に対する興味や熱意を表現することが大切です。
企業は、就活生が何かに真剣に取り組んできた経験を評価するため、得意科目を学ぶ中でどのような努力をし、どのような工夫を重ねてきたのかを具体的に記述する必要があります。
その科目を好きになったきっかけや、学ぶ中でどのように考え方が変化したのかといったエピソードを交えると、より説得力のある内容になります。
得意である根拠
「得意です」と言うだけでは、その科目に対する習熟度や本当に得意であるかの信憑性が伝わりません。
そのため、学業や実践経験を通じて得た成果を具体的に示し、得意であることの根拠を明確にすることが重要です。
成績が優秀だったのであれば、学内での順位やGPAを示すことができますし、資格試験を取得している場合はその名称やスコアを記載すると説得力が増します。
また、研究やプロジェクト活動でその科目を活かした経験があれば、それを具体的に述べるのも効果的です。
英語が得意な場合であれば、TOEICや英検のスコア、留学経験、英語を活用したプレゼンテーションの経験などを示すことで、企業側も就活生のスキルレベルを正しく理解しやすくなります。
仕事にどう活かせるか
企業が得意科目を尋ねる理由の一つは、就活生がどのようにその知識やスキルを活かして会社に貢献できるのかを知りたいからです。
そのため、得意科目と志望する職種や業務内容を結びつける説明を加えることで、企業に対する意欲を示し、より評価を高めることができます。
マーケティング職を志望する場合、統計学が得意であれば「データ分析を用いて市場の動向を読み解く力を活かし、マーケティング施策の企画に貢献したい」と述べることができます。
また、プログラミングが得意でエンジニア職を志望する場合は、「大学で学んだプログラミングスキルを活かし、より実践的なシステム開発に携わりたい」といった形で企業への貢献を明確に伝えることが効果的です。
【ESで得意科目を聞かれたら?】得意科目を書く際のNGポイント
ESに得意科目を書く際、単に好きな科目や成績の良かった科目を記載するだけでは不十分です。
企業は、応募者が得意科目を通じてどのようなスキルを身につけ、それを業務にどう活かせるのかを見極めようとしています。
そのため、得意科目の選び方や書き方によっては、企業に対して志望動機が曖昧であると受け取られる可能性があります。
ここでは、ESに得意科目を書く際に陥りがちなNGポイントについて解説します。
業種や職種と結び付かない
企業は、応募者が自社の業務に必要なスキルを持っているかどうかを確認したいと考えています。
そのため、ESで得意科目を記載する際には、業種や職種と関連性のある科目を選ぶことが重要です。
たとえば、IT業界を志望する場合、「プログラミング」や「情報処理」などの科目を挙げることで、技術的な適性を示すことができます。
一方で、営業職を志望するにもかかわらず、「美術」や「音楽」を得意科目として記載すると、業務との関連性が薄く、企業に志望動機が伝わりにくくなります。
また、関連性の低い科目を記載することで、「この応募者は業界や職種について十分に理解していないのではないか」と思われる可能性もあります。
特に、企業が求める能力やスキルを考慮せずに得意科目を選んでしまうと、入社後の活躍がイメージしにくくなってしまいます。
何ができるのかが伝わらない
得意科目を単に羅列するだけでは、応募者がどのようなスキルや強みを持っているのかが伝わりません。
たとえば、「数学が得意」とだけ書いた場合、企業は応募者の具体的な能力や適性を判断することができません。
しかし、「数学の中でも確率や統計の分野に強く、データ分析を用いた課題解決を学んだ」と記載すれば、より明確にスキルを伝えることができます。
また、「コミュニケーションが得意」といった抽象的な表現も避けたほうがよいでしょう。
具体的な授業内容や成果を挙げることで、企業に対して説得力のあるアピールができます。
たとえば、「ゼミでディスカッションを重ね、相手の意見を尊重しながら論理的に主張する力を養った」といった具体例を加えることで、強みがより伝わりやすくなります。
具体的に仕事に活かせるかわからない
企業が求めるのは、得意科目が仕事にどう活かせるのかが明確に示されていることです。
たとえば、「英語が得意」と記載するだけでは、企業にとって具体的なイメージが湧きにくくなります。
そのため、「TOEICで○○点を取得し、留学生との交流を通じて実践的な英語力を磨いた」など、具体的な成果を記載すると説得力が増します。
また、理系の学科で学んだ知識を活かしたい場合、「化学が得意」だけでなく、「有機化学の研究に取り組み、新しい合成方法の実験を行った」といった具体的な経験を述べることが効果的です。
こうした説明を加えることで、企業は応募者のスキルがどのように業務に役立つのかをイメージしやすくなります。
企業が採用後の活躍をイメージしやすいよう、学んだことと仕事の関連性をしっかりと示すことが重要です。
【ESで得意科目を聞かれたら?】得意科目の例文
ESに記載する「得意科目」は、自分の強みをアピールできる重要なポイントです。
単に「数学が得意」などと記載するのではなく、具体的なエピソードや学びを交え、希望職種との関連性を明確にすることで、より説得力のある回答になります。
まずは、代表的な得意科目ごとに、企業が評価しやすい例文を紹介します。
その後では文系・理系それぞれの専門科目を用いた例文も紹介しているため、参考にしてみて下さい!
例文1: 数学
私の得意科目は数学です。
数学の問題を解く過程では、論理的思考力や問題解決能力が求められます。
私は幼い頃から数字に触れることが好きで、特に高校時代には微分積分や統計学に興味を持ち、深く学びました。
大学ではデータ分析を用いた課題解決の研究を行い、複雑なデータを整理し、最適な解決策を導き出すことにやりがいを感じました。
こうした経験を通じて、物事を論理的に整理し、多角的な視点から最適な結論を導き出す力を身につけました。
貴社においても、論理的思考力を活かし、データを基にした分析や業務改善に貢献したいと考えています。
例文2: 国語
私の得意科目は国語です。
幼い頃から読書が好きで、多くの文学作品を通じて、言葉の持つ力や表現の奥深さに興味を持つようになりました。
大学では夏目漱石の作品を研究し、言葉の使い方や文章の構成が相手に与える印象について深く学びました。
また、論理的に考えをまとめ、相手に分かりやすく伝える力を養うために、プレゼンテーションやディスカッションにも積極的に取り組んできました。
貴社においても、文章作成やコミュニケーション力を活かし、分かりやすく正確な情報発信に貢献したいと考えています。
例文3: 英語
私の得意科目は英語です。
高校時代に英語スピーチコンテストに参加したことをきっかけに、英語でのコミュニケーションの楽しさを知りました。
大学では1年間の留学を経験し、異文化の中で生活しながら、英語を実践的に活用する機会を得ました。
特に、現地の学生や教授と議論する中で、自分の意見を論理的に伝えるスキルを磨くことができました。
また、帰国後はTOEICで高得点を取得し、ビジネス英語のスキルも強化しました。
貴社では、この語学力と異文化理解力を活かし、グローバルな環境での業務に積極的に挑戦し、海外との架け橋となる役割を果たしたいと考えています。
例文4: 体育
私の得意科目は体育です。
中学・高校とバレーボール部に所属し、キャプテンとしてチームをまとめる経験をしました。
バレーボールは個人技だけでなく、チームワークが不可欠な競技です。
私は、仲間と円滑にコミュニケーションをとり、それぞれの役割を理解しながら目標に向かって努力することの大切さを学びました。
また、試合で負けた際には、原因を分析し、改善策をチームで話し合う習慣を身につけました。
こうした経験から、粘り強く課題に取り組む姿勢や、チームの士気を高める力を培いました。
貴社においても、協調性やリーダーシップを活かし、チーム全体の成果向上に貢献したいと考えています。
【ESで得意科目を聞かれたら?】文系専門の得意科目の例文
続いて、文系専門の科目を得意科目として伝える場合の例文を紹介していきます。
理系専門科目でESを作成したい方は飛ばしても構いませんが、基本的な構成や、押さえなければならないポイントについては、理系の方と共通しています。
時間に余裕があるならば、理系の方も熟読してみてください。
文系の例文1:国際経済論
私の得意科目は国際経済論です。
特に貿易理論や国際金融政策を中心に学びました。
また、為替相場の変動要因を検証する課題に取り組み、実際のデータをもとに経済指標や市場の動向を分析しました。
この分析を通じて、経済現象の裏にある構造的な要因を理解し、さらにプレゼンテーションを行うことで、論理的思考力やデータを分かりやすく伝える能力も高めました。
また、為替や貿易の動向が企業の経済活動にどう影響を与えるかを学び、それを活かす方法を模索する姿勢を大切にしてきました。
このスキルを活かして、今後は企業の海外市場分析や戦略立案に貢献したいと考えています。
マーケットリスクの予測や競争戦略の提案を通じて、企業が国際市場で持続的に成長するために役立てる所存です。
文系の例文2:経営戦略論
私の得意科目は経営戦略論です。
企業の成長戦略や競争優位性に関する理論を学び、それを実際の企業の事例に適用して分析を行いました。
特に、新規事業戦略の立案においては市場調査やSWOT分析を用いて具体的な提案資料を作成し、その結果をプレゼンテーションで発表しました。
この取り組みを通じて、戦略的思考や問題解決能力を大きく向上させることができました。
入社後はこの学びを活かし、マーケティングや事業企画で戦略的に貢献したいと考えています。
特に、新規市場の開拓や競争優位性を築くための戦略立案において、経営戦略論で学んだ知識を応用し、貴社の成長をサポートする所存です。
文系の例文3:法学
私の得意科目は法学です。
契約法や企業法務に関する深い知識を得て、特に契約書の解釈や企業間の法的問題に関して学びました。
実際の判例を分析し、その結果を踏まえて法律的な解釈や対応策を考える能力を身につけ、模擬裁判を通じて交渉力や論理的思考力も鍛え、実際のビジネスシーンでの法的な問題解決に必要なスキルを向上させました。
また、企業の法的リスクや契約関連の重要性を理解し、実践的に活用する方法も学びました。
この経験を活かし、法務関連業務やコンプライアンス管理に貢献する所存です。
企業法務や契約管理の分野でリスクを最小限に抑えつつ、貴社の成長を支える法的アドバイスを提供できるよう努力します。
文系の例文4:社会心理学
私の得意科目は社会心理学です。
人間の行動や判断のメカニズムに関する理論を学び、特に消費者行動を分析する課題に取り組みました。
ゼミではアンケート調査やデータ解析を通じて、消費者の購買行動における心理的要因を分析し、行動経済学の理論を用いた改善提案を行いました。
この経験を通じて、消費者インサイトを得るためのデータ分析力を養いました。
また、社会心理学を得意とする理由は人間の行動が企業活動に与える影響を理解し、実際の市場にどのように適用できるかを常に考えてきたからです。
この分析力を活かし、今後は営業や販促施策に役立てる所存です。
特に、消費者のニーズを正確に把握し、貴社のマーケティング戦略において効果的な施策を提案したいと考えています。
文系の例文5:コミュニケーション論
私の得意科目はコミュニケーション論です。
グループワークでの討論やプレゼン発表を通じて、協調性と発信力を磨きました。
特に印象に残っているのはゼミ内で行ったイベント企画の経験です。
1週間という限られた時間と予算内で実施しなければなりませんでしたが、チームリーダーとしてメンバー一人ひとりの強みを活かしながらタスクを分担し、役割を明確にしました。
イベントは無事に成功し、参加者から高い評価を得ることができました。
この経験を通じて、課題解決力、計画力、そしてチーム運営のスキルを学びました。
この経験は営業職やチーム運営に必要なスキルに直結すると考えています。
入社後はゼミで学んだ協調性や発信力を活かし、クライアントと良好な関係を築きながら、チームの雰囲気も重視し、メンバーを巻き込んで成果を出すためのリーダーシップを発揮したいと考えています。
【ESで得意科目を聞かれたら?】理系専門の得意科目の例文
続いて、理系専門科目を得意科目として伝える場合の例文について紹介します。
ここまで紹介してきた内容を踏まえた上で作成しているため、おさらいとしても参考になるはずです。
もちろん文系の方の参考になるポイントも散りばめられているため、時間に余裕があれば文系の方も熟読してください。
理系の例文1:データサイエンス基礎
私の得意科目はデータサイエンス基礎です。
Pythonを使用したデータ解析や機械学習モデルの構築について学びました。
特に、売上予測モデルの作成に取り組み、実際の企業データを基に予測精度を向上させるために様々な手法を試しました。
この経験を通じて、データを活用した意思決定支援の実務的なスキルを得ることができました。
この科目を得意とする理由は、データを使って問題を解決する過程に強い興味を持ち、課題に対して分析的にアプローチすることに楽しさを感じたからです。
特に予測モデルを使った課題では自分の考えが結果にどれだけ反映されるかを見ることができ、大きなやりがいを感じました。
入社後はデータからインサイトを導き、戦略に結びつける力を発揮し、業務改善や戦略立案に貢献したいと考えています。
理系の例文2:プログラミング基礎
私の得意科目はプログラミング基礎で、C言語とPythonを使用してシステム開発やアルゴリズムの設計を学びました。
また、ゼミではIoTシステムの試作に取り組み、センサー連携やデータ収集のプログラムを担当しました。
実際に手を動かしながら学びプログラムを作成していく中で、論理的思考力や問題解決力が養われました。
プログラミングが得意な理由は、課題解決のために自分でアイデアを実現していく過程に魅力を感じたからです。
自分の考えたコードが実際に動作し、問題を解決した時の達成感は非常に大きく、そのプロセスが面白く、やりがいを感じました。
入社後は新しい技術を用いたシステムやアプリケーション開発において効率的なアルゴリズム設計や実装に携わり、企業の技術革新に貢献する所存です。
理系の例文3:バイオテクノロジー
私の得意科目はバイオテクノロジーです。
特にDNA解析や細胞培養技術を学び、遺伝子組み換え技術を応用した研究に取り組みました。
実験ではデータ分析を通じて新しい実験手法を提案し、論文発表を行い、バイオ分野での実験的なアプローチと理論的な分析の重要性を学びました。
バイオテクノロジーに強い関心を持つ理由は、生命現象を分子レベルで理解し、それを応用して新しい価値を生み出す可能性に魅力を感じたからです。
実験での失敗から学び、結果に基づいて仮説を立て直す過程で、問題解決能力を高めることができました。
入社後は遺伝子編集技術や細胞培養技術の応用を進め、新しい治療法の開発や製品の品質向上に寄与する所存です。
理系の例文4:材料工学
私の得意科目は材料工学です。
新素材の特性評価や加工技術について学び、実験を通じてそのデータを解析しました。
特に卒業研究では強度向上を目的とした新素材開発に取り組み、実際に素材の特性をテストするための装置を用いて実験を行いました。
この実践的な研究を通じて、データ解析能力や実験計画能力を磨きました。
材料工学に強みを感じる理由は、新しい素材を開発し、それが現実の製品にどう影響を与えるかを予測し、改善していく過程に面白さを感じたからです。
特に、新しい素材の性能を評価する実験において、課題に取り組むことで深い学びを得ました。
入社後は素材の強度や耐久性を高める技術を活かして、製品の品質向上やコスト削減に取り組む所存です。
理系の例文5:電気回路設計
私の得意科目は電気回路設計です。
アナログ回路やデジタル回路の設計・解析方法を学び、実験装置を使って回路の動作を確認しました。
特に卒業研究では省エネルギー化を目的とした電源回路の設計に取り組み、効率化とコストの15%削減を実現しました。
実際に回路を設計し、性能をテストする中で、回路設計の知識と実践力を深めることができました。
電気回路設計を得意とする理由は、回路が持つ機能を理解し、その機能を最適化する過程に魅力を感じたからです。
特に省エネルギー化を実現するための設計では環境に優しい技術の重要性を感じました。
入社後は電力消費の効率化を実現するために電源回路の設計に関わり、貴社のコスト削減と環境負荷軽減に寄与する所存です。
【ESで得意科目を聞かれたら?】得意科目を書く際のコツ
ESで得意科目を問われる際、単に好きな科目や成績の良かった科目を羅列するだけでは十分なアピールになりません。
企業は、得意科目を通じて応募者の興味関心や思考特性を知るとともに、それを業務でどのように活かせるのかを見極めようとしています。
そのため、得意科目を効果的に伝えるには、自分の強みや志望動機と関連づけて考えることが重要です。
ここでは、得意科目を書く際の具体的なコツについて解説します。
好きなことと結び付けて考える
ESで得意科目を書く際には、自分の興味のある分野や好きなことと結びつけることで、より説得力のある内容にすることができます。
好きなことに関連する科目は、自発的に学習に取り組んできた可能性が高く、深い知識やスキルを習得していることが多いため、自己PRとしても強い印象を与えることができます。
また、企業は熱意を持って業務に取り組める人材を求めているため、「好きだからこそ深く学び、主体的に行動してきた」というエピソードがあると、入社意欲を伝えやすくなります。
例えば、「マーケティングに興味があり、経済学の中でも消費者行動の研究に力を入れた」といった形で書くと、業務への適性をアピールすることができます。
重要なのは、単に「好きだから得意」ではなく、「好きだからこそ努力し、どのような知識やスキルを得たのか」を明確にすることです。
自分がアピールしたい強みから逆算して考える
ESでは、単に得意科目を伝えるだけでなく、自分がアピールしたい強みと結びつけて記載すると、より効果的な自己PRになります。
例えば、「論理的思考力」をアピールしたい場合は、数学や物理を得意科目として挙げることで、論理的な分析力を培ってきたことを示せます。
また、「プレゼンテーション能力」を強みとするならば、コミュニケーション学や経営学の授業での発表経験を得意科目と関連付けることで、具体的なエピソードを交えて伝えることができます。
このように、まず自分の強みを明確化し、それを裏付ける得意科目を選択することで、ES全体の一貫性が生まれ、説得力のある自己PRが可能になります。
得意科目を単なる科目名として記載するのではなく、それを通じて得たスキルや経験が企業でどのように活かせるのかを考えることが大切です。
企業が求める人物像から逆算して考える
企業ごとに求める人物像やスキルは異なるため、事前に企業研究を行い、それに合致する得意科目を選ぶことが重要です。
例えば、メーカーの開発職を志望する場合は、「材料工学」「化学実験」などの科目を得意科目として挙げることで、業務への適性を示せます。
また、コンサルティング業界では、「経済学」「統計学」などの科目を通じてデータ分析能力や論理的思考力をアピールするとよいでしょう。
企業のホームページや求人情報を確認し、「この企業ではどのようなスキルが求められているのか?」を把握することで、得意科目をより効果的に選ぶことができます。
企業が求めるスキルと自分の得意科目が一致していれば、企業に対して「自分はこの仕事に適している」と伝えることができ、入社後の活躍をイメージしてもらいやすくなります。
面接で会話のきっかけになるように考える
ESに記載した得意科目は、面接で質問される可能性が高いため、会話のきっかけになるような内容を選ぶことも重要です。
例えば、「心理学の授業で消費者心理を学び、マーケティングに応用できると考えた」といった具体的なエピソードを交えることで、面接官の興味を引き、話が広がりやすくなります。
また、珍しい科目を挙げることで、面接官の印象に残ることもあります。
たとえば、「スポーツ科学が得意で、運動生理学を学んだ経験がある」といった内容であれば、ユニークな視点から話を展開できる可能性があります。
ESの内容が面接での会話のきっかけとなり、自己PRの補強につながるように意識して得意科目を選ぶことで、より効果的なアピールが可能になります。
【ESで得意科目を聞かれたら?】得意科目を上手くアピールできる自信が無い時は?
ここまでESで得意科目について聞かれた際のポイントや注意点、文系と理系の例文について詳しく紹介してきました。
しかし、この記事を読んだだけで100点のESを作成できるならば、ここまで多くの就活生の方が困ることはないでしょう。
ESで得意科目についてクリティカルに答えるためにおすすめの対策は、就活エージェントを利用することです。
弊社が提供しているジョブコミットというサービスでは、完全無料でESの添削や面接の練習相手など様々なサービスを提供しています。
ESで得意科目について聞かれた際のアドバイスはもちろん、得意科目が全く思いつかない方の場合は、一緒に得意科目が何かを検討することもできます。
気になる方は以下のリンクから登録してみてください。
まとめ
今回はESにおいて得意科目を聞かれた際のポイントや注意点、文系の方、理系の方に分けた例文などを紹介しました。
全ての企業が聞いてくるわけではない項目ですが、その分、何かしらの意図を持って、重要な質問として聞かれることが多いのが「得意科目」です。
ぜひ本記事のポイントなどを参考に、質の高い回答を用意し、内定をたぐり寄せてください。