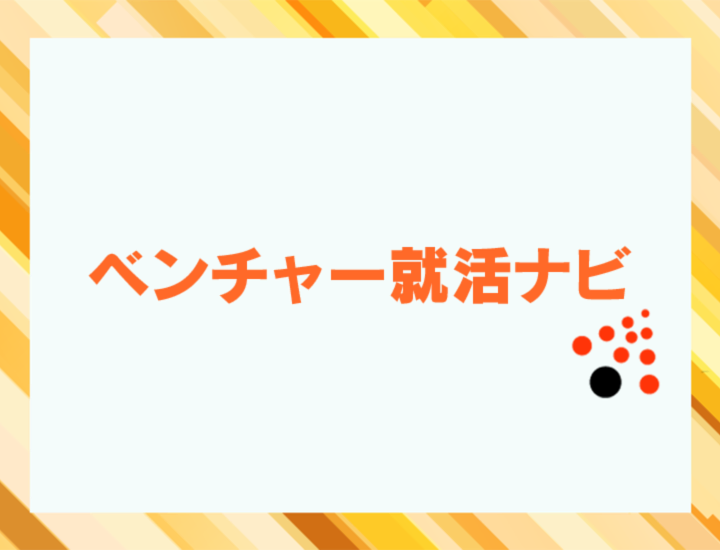明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・志望動機に「ワークライフバランス」はアリ?ナシ?
・ワークライフバランス推進企業を見極めるポイント
・ワークライフバランスを志望動機に入れるときの3つのコツ
・志望動機がワークライフバランスな人
・志望動機の構成が不安な人
・例文を参考に志望動機を作りたい人
目次[目次を全て表示する]
はじめに
働き方改革の広がりや価値観の多様化により、就職活動において企業選びの基準が変わりつつあります。
かつては給与や安定性が優先されていましたが、近年では自分らしい働き方や私生活との両立を重視する傾向が強まっています。
なかでも、ワークライフバランスを大切にしたいと考える学生は年々増加しています。
ただし、働きやすさや私生活への配慮を志望動機として伝える際には注意も必要です。
企業によっては意欲が低いと誤解されるリスクもあるため、伝え方には工夫が求められます。
本記事では、ワークライフバランスを重視する理由の伝え方やそのポイントについて整理していきます。
就活生の中でも働き方や私生活との両立を重視する人が増えている
新卒での就職活動においても、近年は働く環境や制度面に注目する学生が増えています。
残業の少なさや柔軟な勤務体系、在宅勤務の可否など、仕事だけに偏らないバランスを求める傾向は顕著です。
背景には、長時間労働による健康被害やライフイベントとの両立の難しさが問題視されてきたことがあります。
また、インターンやOB訪問を通じて実際の働き方を知る機会が増えたことで、学生自身がより現実的にキャリアを考えるようになってきました。
実際に、企業の採用情報でも「フレックスタイム制度」「時短勤務」「育児・介護支援」など、ワークライフバランスに配慮した制度を打ち出す企業が目立つようになっています。
こうした制度の充実は、働きやすさや定着率の高さにも直結するため、求職者側からも注目されるポイントとなっています。
ワークライフバランスを理由にすることへの不安の声
一方で、ワークライフバランスを志望動機として伝えることに対して不安を感じる学生も少なくありません。
特に、プライベートを優先する姿勢だと受け取られ、仕事への意欲が低いと誤解されるのではないかという懸念があるようです。
実際、多くの就活サイトやキャリアアドバイザーも、伝え方を誤るとマイナスに働く可能性があると指摘しています。
ただ単に働きやすい環境を求めていると受け取られると、採用担当者にとっては志望理由として物足りなく感じられることがあります。
大切なのは、ワークライフバランスの実現を通じてどのように自分が成長し、会社に貢献できるのかを具体的に示すことです。
空いた時間を活用して資格取得を目指す、家族との時間が充実することでより集中力をもって業務に取り組める、といった前向きな目的を添えることで、単なる自己都合ではなく、企業にとってのメリットとして伝えることができます。
志望動機にワークライフバランスはアリ?ナシ?
就職活動を進める中で、ワークライフバランスを志望動機に入れても良いのか、不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、ワークライフバランスを志望理由として伝えることは問題ありません。
実際に、働きやすさや社員の生活を大切にしている企業は年々増えており、その考えに共感して志望するのは自然なことです。
ただし、どのように伝えるかによって、受け取られ方が大きく変わります。
伝え方を間違えると、働く意欲が低いのではないかと思われてしまう可能性があるため、慎重に言葉を選ぶ必要があります。
NGな伝え方:働くことへの意欲が低く見えるケース
ワークライフバランスを理由にする際、気をつけたいのが「仕事よりも自分の都合を優先したいだけ」という印象を与えてしまう伝え方です。
残業はしたくない、とにかく自分の時間を大事にしたいといった言い方では、どうしても消極的な印象になってしまいます。
もちろん、自分の時間を大切にしたいという気持ちは正直で大切なことですが、企業が求めているのは、前向きに働きたいという意欲がある人です。
仕事に対する熱意や、組織に貢献したいという姿勢が見えないままだと、選考で不利になることもあります。
OKな伝え方:自分の価値観・成長意欲・企業とのマッチを交えて話す
一方で、ワークライフバランスを前向きに伝える方法もあります。
健康的に長く働き続けるために、自分の生活と仕事のバランスが取れていることが大切だと考えていますや空いた時間を使って資格取得や自己学習に取り組み、仕事に還元したいといったように、バランスをとることによって自分がどんなふうに成長し、企業にどのように貢献したいかを具体的に伝えると、印象が良くなります。
また、なぜその企業でなら理想の働き方が実現できると思ったのかを話すことも大切です。
制度面や社風に共感したこと、実際に働いている社員の声などをリサーチしておくと、説得力が増します。
ワークライフバランスは、楽をしたいから求めるのではなく、よりよく働き、成長するための土台です。
その前提をしっかりと伝えることができれば、志望動機として十分に通用しますし、むしろ共感してもらえる可能性も高まります。
なぜワークライフバランスを重視しているのかを言語化しよう
志望動機や自己PRで伝えるには、なぜ自分がそう感じているのか、その背景や理由を自分の言葉で説明できることが大切です。
人によってその理由はさまざまですが、特に以下のような考え方を持つ方が多く見られます。
- 健康的に長く働きたい
- 趣味や家族との時間も大切にしたい
- 効率的に成果を出したい
- WLBは「自己研鑽」と「長期的な成長」の土台であると捉える
- 過去の経験と結びつけて深堀りする
健康的に長く働きたい
「健康的に長く働きたい」と感じているケースです。
働く期間は短くて数年、長ければ数十年にも及びます。
その中で、無理を重ねるのではなく、心身ともに安定した状態で働き続けることを重視する人にとって、ワークライフバランスの取れた職場は重要な条件のひとつになります。
趣味や家族との時間も大切にしたい
「趣味や家族との時間も大切にしたい」と考える人もいます。
仕事をがんばる一方で、自分自身の時間や大切な人と過ごす時間を持つことが、日々の生活に潤いや活力を与えてくれます。
こうした時間があるからこそ、前向きな気持ちで仕事に向き合えるという実感を持っている人も多いのではないでしょうか。
効率的に成果を出したい
「効率的に成果を出したい」という視点からワークライフバランスを意識する方もいます。
長時間働くことではなく、限られた時間の中で集中して成果を上げたいと考える場合、働く環境や制度が整っているかどうかは大きなポイントになります。
効率よく働ける環境があるからこそ、より主体的に仕事に取り組めるという考え方です。
WLBは「自己研鑽」と「長期的な成長」の土台であると捉える
現代のビジネス環境では、既存のスキルだけではすぐに時代遅れになってしまいます。
持続的に活躍するためには、業務時間外でのインプット、すなわち自己研鑽が不可欠です。
ワークライフバランスが確保されて初めて、私たちは新しい知識を学んだり、資格取得に取り組んだり、異業種の人と交流したりする「余白」を持つことができます。
この余白こそが、数年後の自分を支える専門性や、より広い視野を育む土壌となります。
WLBは単なる休息ではなく、未来の自分への投資時間を確保し、長期的なキャリア成長を実現するための基盤なのです。
過去の経験と結びつけて深堀りする
「健康」「プライベート」「効率」といった一般的な理由に加えて、あなた自身がワークライフバランスを重視する根源的な動機は、過去の経験の中に隠れているかもしれません。
例えば、かつて体調を崩すほどに、何かに取り組んでいた経験が、健康への意識を高めたのかもしれません。
また、限られた時間で大きな成果を出した成功体験が、効率的な働き方への自信を育んだ可能性もあります。
ご自身の過去を振り返り、何に喜びを感じ、何に苦しみ、何を学んだのかを丁寧に掘り下げることで、よりパーソナルで、説得力のある「ワークライフバランスを重視する理由」が見えてくるはずです。
この自己分析が、あなたらしい働き方を見つけるための羅針盤となるでしょう。
ワークライフバランスの言い換え一覧
- 貴社で長期的にキャリアを築き、貢献し続けたいと考えております。
- 心身ともに健康な状態を維持し、常に高いパフォーマンスを発揮できる環境に魅力を感じています。
- 自己管理を徹底し、持続的に成果を出し続ける働き方を実現したいです。
- メリハリをつけて働き、限られた時間の中で最大限の成果を出すことを重視しています。
- 貴社の生産性を重視する文化の中で、効率的な業務遂行に貢献したいです。
- 業務時間外でも自己研鑽の時間を確保し、得た知識を業務に還元していきたいです。
- 貴社の制度(研修や柔軟な働き方)を活用し、スキルアップすることで、より一層貴社に貢献できる人材になりたいです。
- 育児や介護といったライフステージの変化を経ても、貴社で長く活躍し続けたいと強く願っています。
- 多様な働き方を許容する貴社の環境であれば、どのような状況でも責任を持ってキャリアを継続できると感じました。
企業の取り組み、どう見抜く? ワークライフバランス推進企業を見極めるポイント
「ワークライフバランスを推進しています!」多くの企業がそうアピールしますが、その言葉の裏にある実態は様々です。
制度はあっても形骸化していたり、部署によって状況が大きく異なったりすることも少なくありません。
入社後のミスマッチを防ぎ、「自分らしく働ける」企業を見つけるためには、言葉だけでなく具体的な取り組みや実績、そして社内の雰囲気まで見極める視点が重要です。
ここでは、企業のワークライフバランスへの取り組みの実態を見抜くための具体的なチェックポイントをご紹介します。
- 求人票・採用サイト
- 会社説明会・セミナー
- OB/OG訪問・社員訪問
- 企業の口コミサイト・SNS
- 「働きがい」と「ワークライフバランス」の関係性にも注目する
求人票・採用サイト:具体的な制度と「実績」をチェック
求人票や採用サイトは、企業が発信する公式情報として最初に目にする方が多いでしょう。
ここで注目すべきは、「ワークライフバランス推進」といった抽象的な言葉だけでなく、それを裏付ける具体的な制度が明記されているかです。
例えば、育児休業や介護休業制度はもちろんのこと、時短勤務、フレックスタイム制、テレワーク制度の導入状況、さらには年次有給休暇の取得率や平均残業時間といった客観的なデータです。
特に重要なのは、制度の有無だけでなく、その「実績」が公開されているかどうかです。
高い取得率や具体的な利用事例が示されていれば、制度が形骸化せず実際に活用されている証となります。
企業の誠実な姿勢は、こうした情報の透明性に表れるのです。
「平均残業時間」「有給取得率」「育休復帰率」の3大指標はマストで確認しよう
企業のWLB実態を客観的に把握するために、最低限確認すべき3つの定量データがあります。
第一に「月間平均残業時間」。
これが部署別や全社平均で開示されているか。
第二に「年次有給休暇の平均取得率」。
制度があっても取得しにくい雰囲気がないか。
第三に「育児休業からの復帰率」、特に女性の復帰率が100%に近いかは、長期的なキャリア形成を支える環境かを示す重要な指標です。
これらの数字は、企業が公表する「理想」と、従業員が享受している「現実」とのギャップを測るための、信頼できるバロメーターとなります。
会社説明会・セミナー:担当者の説明と社員の声をヒントにする
会社説明会やセミナーは、企業の雰囲気や担当者の熱意を直接感じ取れる貴重な機会です。
ワークライフバランスに関する企業の取り組みについて、担当者に積極的に質問してみましょう。
その際、制度の説明だけでなく、具体的な運用実態や、社員が制度を利用しやすい風土があるかなどを尋ねると良いでしょう。
言葉を濁したり、曖昧な回答しか得られない場合は注意が必要です。
また、説明会に登壇している若手社員や中堅社員がいれば、その話しぶりや表情、働きがいについて語る内容もヒントになります。
質疑応答の時間だけでなく、説明会全体の雰囲気や、他の参加者からの質問に対する企業の対応からも、その企業の体質や社員への姿勢を垣間見ることができます。
OB/OG訪問・社員訪問:現場の「生の声」を聞く
企業の公式な情報だけでは見えにくい、現場のリアルな声を聞くためには、OB/OG訪問や社員訪問が極めて有効な手段です。
実際にその企業で働く社員から、日々の業務の流れ、平均的な残業時間、休暇の取りやすさ、職場の人間関係やコミュニケーションのあり方など、具体的な情報を得ることができます。
特に、ワークライフバランスを保つ上で、上司や同僚の理解、チーム内の協力体制は不可欠です。
制度があっても、周囲の理解がなければ利用しづらいというケースは少なくありません。
複数の社員に話を聞くことで、個人の意見に偏らない、より客観的な情報を集めることが推奨されます。
率直な意見交換を通じて、自分が入社後にどのような働き方ができるのか具体的にイメージしましょう。
企業の口コミサイト・SNS:多角的な視点を取り入れる
企業の口コミサイトやSNSは、現社員や元社員による匿名性の高い情報が集まるため、公式発表とは異なる側面や、より本音に近い意見を知る手がかりとなります。
良い評価だけでなく、厳しい意見やネガティブな情報にも目を向けることで、企業が抱える課題や改善点が見えてくることもあります。
ただし、これらの情報はあくまで個人の主観に基づくものであり、中には偏った意見や古い情報が含まれている可能性も考慮しなければなりません。
そのため、一つの情報を鵜呑みにするのではなく、複数の口コミを比較したり、他の情報源(求人票、説明会、社員訪問など)で得た情報と照らし合わせたりしながら、総合的に判断する姿勢が重要です。
多角的な視点を持つことで、より実態に近い企業像を把握できるでしょう。
「働きがい」と「ワークライフバランス」の関係性にも注目する
ワークライフバランスは単にプライベートの時間を確保するだけでなく、仕事への「働きがい」と密接に関わっています。
企業が社員の成長やキャリア形成を支援する制度(研修、資格取得支援など)を充実させているか、個人の裁量や挑戦の機会がどれくらいあるかといった点にも注目しましょう。
ワークライフバランスが取れていても、仕事内容にやりがいを感じられなければ、長期的なモチベーション維持は難しいものです。
働きがいを感じながら、心身ともに健康的に働ける環境こそが、真のワークライフバランス推進企業と言えるでしょう。
ワークライフバランスを志望動機に入れるときの3つのコツ
ワークライフバランスを志望動機に盛り込むことは、決して悪いことではありません。
むしろ、働く環境や自分の生活との調和を大切に考えるのは、これからの時代に合った自然な価値観です。
ただし、伝え方によっては仕事への意欲が低いのでは?と受け取られてしまう可能性もあります。
そこで、ワークライフバランスを前向きに伝えるためのコツを3つご紹介します。
- 企業の制度や取り組みに共感していることを伝える
- 仕事内容やキャリアへの意欲もセットで伝える
- 自分の働き方の理想像としてポジティブに語る
企業の制度や取り組みに共感していることを伝える
まずは、企業のどのような取り組みに魅力を感じたのかを具体的に伝えることが大切です。
フレックスタイム制度や在宅勤務制度、育児や介護と両立しやすい社内環境など、企業が実際に取り組んでいる内容に注目しましょう。
その上で、「その制度に共感した」「自分の理想と重なる」といった気持ちを伝えることで、調べたうえでの納得感ある志望理由になります。
仕事内容やキャリアへの意欲もセットで伝える
ワークライフバランスだけを前面に出してしまうと、仕事よりも私生活を優先したいのかな?という印象になりがちです。
そこで、仕事に対する前向きな姿勢や将来のキャリアに関する意欲もあわせて伝えるようにしましょう。
この環境があるからこそ、長期的に専門性を磨いて貢献したいといったように、企業で活躍していく姿を一緒に描くことが大切です。
自分の働き方の理想像としてポジティブに語る
ワークライフバランスを語る際は、「残業したくない」「休みが多いほうがいい」といった消極的な表現ではなく、自分がどんな働き方を目指しているかを前向きに伝えることがポイントです。
心身の健康を保ちながら、集中して成果を出す働き方を大切にしたいや長く働き続けるために、自分らしいリズムで働ける環境を選びたいといったように、自分の価値観として語ると、自然で説得力のある印象になります。
志望動機にワークライフバランスを含めた例文
ここではワークライフバランスを重視した職種別例文を紹介しています。
あなたの志望している職種の例を参考にしてみてください。
一般事務職向けの例文
長期的に安定して働くためには、心身ともに健康でいることが重要だと思っており、貴社のフレックスタイム制度や有給取得推進の取り組みに大きな魅力を感じました。また、業務を正確かつ効率的に進めることが求められる一般事務職だからこそ、日々の生活リズムを整え、自分自身のコンディションを保つことが仕事の質にもつながると考えています。
貴社の職場環境であれば、責任を持って丁寧に業務に取り組みながら、自分の強みであるコツコツとした継続力を活かして貢献できると確信しています。
ITエンジニア職向けの例文
貴社はリモート勤務やフレックスタイム制を導入し、多様な働き方に対応していると知り、その柔軟な制度に大変共感しました。ITエンジニアは、技術的な知識のアップデートが欠かせない職種だと理解しています。プライベートの時間も活用しながら自己研鑽を重ねることで、貴社の開発チームに貢献できる人材になりたいと考えています。
貴社の開発プロジェクトに参加し、技術力を磨きながら、チームの成果にしっかりと寄与していきたいと思っています。
営業職向けの例文
営業職は結果が求められる一方で、精神的なタフさやメリハリのある働き方も重要だと感じており、貴社の働きやすさを支える制度や文化に強く惹かれました。仕事に取り組む時間は全力で集中し、オフの時間ではしっかりとリフレッシュすることで、常にフレッシュな気持ちでお客様と向き合えると考えています。
私自身、人との信頼関係を築くことが得意なので、貴社の営業職としてお客様に寄り添い、長く選ばれる存在を目指していきたいと思っています。
企画職・マーケティング職向け
特に、貴社が社員の創造性とワークライフバランスの両立を重視し、柔軟な働き方を推奨されている点に深く共感いたしました。
大学で〇〇(ゼミやプロジェクト名)を通じて、多様な視点からアイデアを生み出すことの重要性を学びました。
ワークライフバランスの取れた環境であれば、常に新鮮な発想を追求し、市場を動かす企画・マーケティングで貴社の成長に貢献できると確信しております。
総合職向け
貴社が新卒社員の長期的な成長を支援し、ワークライフバランスを考慮した働き方を推進されている点に魅力を感じました。
大学の〇〇(学業や課外活動名)で培った〇〇(強み)を活かし、チームで目標達成を目指す経験を通じて、個人の充実が組織全体のパフォーマンス向上に繋がることを実感しました。
貴社で心身ともに充実した状態で働くことで、貴社の多様な事業領域において、早期に貢献できるよう尽力いたします。
地域に根ざしたサービス業・BtoC向け
貴社が社員の地域貢献活動を支援し、ワークライフバランスを重視されていると伺い、地域に根差した仕事と自身の充実を両立できる環境だと感じました。学生時代の〇〇(ボランティアやアルバイト経験)で培った傾聴力と問題解決能力を活かし、お客様の笑顔を直接見られる仕事に携わりたいと考えています。
貴社で安心して長く働き続け、地域社会の活性化に貢献できるよう、誠心誠意努めてまいります。
志望動機でワークライフバランスを伝えるときの注意点
伝え方を間違えると、志望度が低く見られてしまったり、働く意欲を疑われてしまうこともあるため注意が必要です。
ここでは、ワークライフバランスに言及する際に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
- 福利厚生だけに言及しない
- 他の企業でも通用する内容にしない(志望度が低く見える)
- 働くことへの意欲が低く見える言葉を使わない
- 仕事よりプライベートが大事と取られないように注意
福利厚生だけに言及しない
「有給が取りやすそうだったから」「在宅勤務ができると聞いたから」といったように、制度や福利厚生だけに焦点を当てた志望動機は避けたほうが良いでしょう。
そうした言い方では、企業の理念や事業内容への興味が伝わらず、制度目当てで志望していると受け取られてしまう可能性があります。
企業が整えている制度に共感したのであれば、それを活かしてどんな働き方をしたいのか、どんな風に成長していきたいのか、といった前向きな姿勢とあわせて伝えることが大切です。
他の企業でも通用する内容にしない
志望動機が抽象的すぎると、どの会社でも同じことを言っているのでは?と思われてしまうことがあります。
「ワークライフバランスを重視している会社で働きたいから」というだけでは、企業ごとの魅力や志望理由が伝わりません。
大切なのは、その企業でなければならない理由をセットで伝えることです。
企業の取り組みや考え方に具体的に触れ、「この会社だから実現できる働き方がある」と感じたポイントを盛り込むことで、説得力が高まります。
働くことへの意欲が低く見える言葉を使わない
WLBを重視する理由を語る際、無意識のうちに働く意欲が低いと受け取られかねない言葉を選んでしまうことがあります。
例えば、「無理なく働きたい」「自分の時間を最優先したい」「負担の少ない環境で」といった表現は、困難な仕事から逃げたい、あるいは責任ある立場を避けたいという受動的な姿勢の表れと解釈される危険性があります。
WLBを志望動機に含める場合は、あくまで「高いパフォーマンスを継続的に発揮するため」「長期的に貴社に貢献するため」という、前向きで能動的な文脈で語る必要があります。
言葉の選び方一つで、印象は大きく変わります。
具体的なNGワード
志望動機において、働く意欲を疑われる可能性のある具体的なNGワードには注意が必要です。
代表的なものは「楽そうだから」「残業がない(少ない)から」「休みが多いから」といった、労働条件の良さそのものを志望理由とする直接的な表現です。
これらは、仕事内容への関心よりも、待遇や負荷の低さといった「権利」や「快適さ」を最優先していると受け取られます。
また、「プライベートを充実させたい」という言葉も、それ自体が悪いわけではありませんが、仕事への貢献意欲とセットで語らなければ、「仕事は二の次」という印象を与えかねないため、使い方には配慮が必要です。
仕事よりプライベートが大事と取られないように注意
ワークライフバランスを重視すると言うと、仕事よりプライベートを優先したいのでは?と誤解されてしまうこともあります。
特に新卒の就活生の場合は、社会人としての責任感や働く意欲を見られる場面が多いため、言い回しには気をつけましょう。
しっかりと休みたい、自分の時間を確保したいといった主張だけを強調するのではなく、そのバランスがあるからこそ集中して仕事に取り組める、自分の成長につながる、というような仕事への前向きな姿勢を必ずセットで伝えることがポイントです。
よくある質問Q&A
ワークライフバランスを志望動機に入れるときの、就活生が抱きがちな疑問にお答えします。
Q. 他の志望動機と組み合わせてもいい?
A. はい、むしろ組み合わせることをおすすめします。
ワークライフバランスを大切にしたいという気持ちは、自分の価値観の一部です。
それに加えて、「〇〇業界に興味がある」「〇〇のスキルを活かしたい」「御社の〇〇という事業に魅力を感じた」など、仕事そのものに対する関心や意欲とセットで伝えることで、より説得力のある志望動機になります。
ワークライフバランス単体だと「働きやすさだけを重視している」と見られることもあるため、自分がその企業でどのように貢献したいのかも一緒に伝えるようにしましょう。
Q. ワークライフバランスはどう評価される?
A. 伝え方によって評価は分かれますが、今では十分にありな志望動機です。
実際、多くの企業が「働きやすい環境づくり」や「社員の多様なライフスタイルへの配慮」に力を入れています。
そのため、ワークライフバランスを志望理由に挙げること自体は珍しいことではなくなっています。
ただし、評価されるかどうかは伝え方次第です。
仕事への熱意や、ワークライフバランスのある環境でどう成長したいのかを具体的に伝えられれば、前向きな価値観として好印象を与えることができます。
逆に、プライベートを優先したいという印象だけが残るような言い方はNGです。
Q. 企業に直接聞いてもいいの?
A. はい、聞いて大丈夫です。
むしろ聞き方が大事です。
選考の中で、働き方や制度について企業に質問することは問題ありません。
ただし、「残業はありますか?」「休みは取りやすいですか?」といった権利だけを求めるような聞き方は避けましょう。
「長期的に力を発揮していく上で、働く環境も大切にしたいと考えています。実際に御社では、どのような働き方をされている方が多いですか?」というように、自分の成長や働く意欲と結びつけた形で聞くと、丁寧で前向きな印象になります。
Q. 逆質問でワークライフバランスについて聞くのはアリ?聞き方は?
A. はい、逆質問でワークライフバランスについて尋ねることは問題ありません。ただし、聞き方には配慮が必要です。
単に「休みは取れますか」「残業はありますか」と直接的に聞くと、働く意欲よりも条件面のみを重視している印象を与えかねません。
そうではなく、「社員の皆様が、仕事のやりがいとプライベートの充実をどのように両立されているか、具体的な取り組みや工夫があれば教えていただけますでしょうか」といった形で、企業の制度や文化への関心として尋ねるのが良いでしょう。
また、「貴社で長期的に貢献していきたいと考えており、そのために社員の方々が心身ともに健康に働き続けられる環境について関心があります」と、自身のキャリアプランと絡めて質問するのも有効です。
企業側の取り組みを具体的に知りたいという前向きな姿勢で臨みましょう。
まとめ
ワークライフバランスを志望動機に含めることは、今の時代に合った自然な価値観の表れです。
ただし、楽をしたいや仕事を軽く見ていると誤解されないように、自分なりの働き方の理想像と、仕事への前向きな姿勢をセットで伝えることが大切です。
企業の制度や文化に共感したことを伝えるだけでなく、その環境でどう成長していきたいか、どんな貢献ができるかを具体的に言葉にできれば、きっと説得力のある志望動機になります。
自分らしい働き方を大切にしながら、長く安心して活躍できる場所を見つけてください。
あなたの想いを、丁寧に、誠実に言葉にしていきましょう。