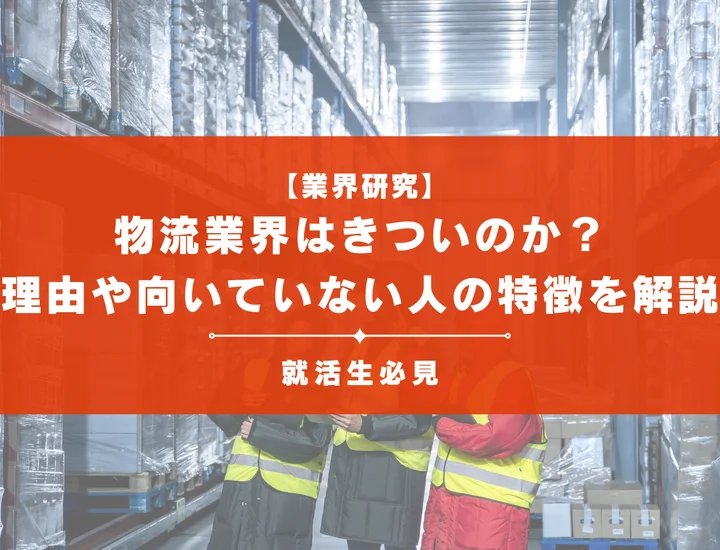明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・長所・短所の見つけ方
・長所・短所をアピールする際の注意点
・魅力的な長所短所の伝え方
・長所・短所について話す際の文章構成
・長所・短所の見つけ方を知りたい人
・自分の短所の言い換え方がわからない人
・長所・短所について話す際の文章構成を知りたい人
・魅力的な長所短所の伝え方を知りたい人
はじめに
就活生の皆さん、長所と短所についての把握と準備は万全でしょうか。
就活において自身の長所と短所を整理して、いつでも簡潔に、また効果的に伝えられるようにしておくことはとても大切です。
もし「自分の長所と短所がよくわからない」「探し方を知りたい」「面接でどうやって伝えたらいいの?」といったお悩みがある方は、ぜひこの記事を参考に、自分の長所と短所をうまく洗い出して、言語化できるようにしてみてください。
魅力的な伝え方も解説していきます。
【長所・短所の見つけ方】長所と短所が分からない人は多い!
就職活動を進める中で、「あなたの長所と短所を教えてください」という質問は、エントリーシート(ES)や面接で頻繁に聞かれる定番中の定番です。
しかし、この問いに対して、自信を持って明確に答えられる人は、意外と少ないかもしれません。
自分自身のことは、客観的に捉えるのが最も難しいからです。
多くの就活生が、「自分の長所って何だろう?」「短所はたくさん思いつくけど、企業にどう伝えればいいんだろう?」といった悩みを抱えています。
これは、決してあなただけが直面する特別な問題ではありません。
日々の生活の中で、自分の行動や性格を深く分析する機会は限られているため、いざ改めて問われると、言葉に詰まってしまうのは自然なことなのです。
しかし、長所と短所を明確に理解することは、就職活動を成功させる上で非常に重要です。
自分の強みを理解していれば、それを最大限に活かせる企業や職種を選ぶことができ、効果的な自己PRにも繋がります。
また、短所を認識していれば、それを改善するための努力をしたり、入社後のミスマッチを防いだりすることも可能になります。
【長所・短所の見つけ方】面接で長所短所を聞かれる理由
面接で「あなたの長所と短所を教えてください」という質問は、就職活動における定番中の定番です。
多くの就活生がこの質問に頭を悩ませますが、企業側がこの質問をするのには、明確な意図があります。
単にあなたの性格を知りたいだけでなく、その背景にあるあなたの能力や思考プロセスを見極めようとしているのです。
自己理解ができているか
企業が長所と短所を尋ねる最大の意図は、応募者が自分自身をどれだけ深く理解しているかを確認するためです。
自己理解は、社会人として成長していく上で非常に重要な基盤となります。
自分の強みを正確に認識していれば、それを仕事でどう活かせるかを具体的にイメージできますし、自分の弱みを把握していれば、それを改善するための努力をしたり、苦手なことを補うための工夫をしたりすることができます。
自己理解が深まっている応募者は、入社後も自律的に学び、成長できる可能性が高いと評価されます。
人柄や性格が会社に合っているか
あなたの長所と短所は、あなたの人柄や性格を如実に表します。
企業は、あなたの性格が自社の企業文化や社風に合致するかどうか、また、配属される可能性のある部署やチームのメンバーと円滑に人間関係を築けるかどうかも重視しています。
どんなに優れた能力を持っていても、企業が求める人物像と大きく異なる人柄では、組織に定着し、長く活躍することは難しいと考えるからです。
あなたの長所が企業の求める特性と一致しているか、短所が業務に大きな支障をきたさないか、といった視点から評価されます。
物事を客観視して感情を切り分けられるか
長所だけでなく、短所を明確に認識し、それを冷静に語れるかどうかは、応募者が物事を客観的に捉え、感情を切り離して分析する能力があるかを見極めるポイントです。
短所を隠そうとしたり、言い訳をしたりするのではなく、「自分のこういう点が短所だと認識しており、改善するためにこのように取り組んでいます」と具体的に説明できる応募者は、自己認識能力が高く、困難な状況にも冷静に対処できると評価されます。
これは、ビジネスにおいて課題を客観的に分析し、解決策を導き出す能力にも繋がると考えられています。
【長所・短所の見つけ方】長所・短所が見つかる自己分析方法
あなたの長所短所はどんなところですかと聞かれた時、即答できる人はそれほど多くないのかもしれません。
日常生活で自分の長所短所を意識する瞬間はほとんどないからです。
面接で聞かれた時に、わかりやすく的確に回答できるよう、事前に準備しておくことが大切です。
長所短所の探し方として、「自己分析を行う」「自分の特徴を書き出す」「好きなこと、苦手なことを書き出す」「自分の頑張った経験を思い出す」「周りの人に聞いてみる」といった方法があります。
一覧表から選ぶ
インターネット上には、長所・短所のリストが掲載されているサイトがたくさんあります。
これらのリストを参考に、自分に当てはまるものを探してみましょう。
リストを見ながら、過去の経験を振り返り、「あの時、私は○○な行動をとった」「あの時、私は○○だと感じた」など、具体的なエピソードを思い浮かべてみましょう。
エピソードが思い浮かべば、その長所・短所はあなたに当てはまる可能性が高いです。
診断ツールを活用する
近年、インターネット上で利用できる自己分析ツールが増えてきました。
これらのツールは、質問に答えるだけで、自分の強みや弱み、価値観、適職などを診断することができます。
客観的なデータに基づいて自己分析を行うことができるため、自分では気づかなかった長所や短所を発見できる可能性があります。
また、ツールによっては、診断結果に基づいたアドバイスや、企業情報などを提供してくれるものもあります。
自分史を書く
自分史とは、文字通り自分自身の歴史を振り返る作業です。
幼少期から現在までの出来事を時系列で書き出し、それぞれの出来事に対して、
・どんな気持ちだったのか
・何を学び、どのように成長したのか
・現在の自分にどんな影響を与えているのか
などを分析していきます。
自分史を作成することで、過去の経験を客観的に見直し、自分自身の長所や短所に気づくことができます。
長所・短所どちらか一方を書き出して言い換える
長所と短所は、表裏一体である場合があります。
そのため、長所を書き出すことで短所が見えてきたり、短所を書き出すことで長所が見えてきたりすることがあります。
例えば、「真面目」という長所は、裏を返せば「融通が利かない」という短所になる可能性があります。
逆に、「優柔不断」という短所は、裏を返せば「慎重」という長所になる可能性があります。
長所と短所をそれぞれ書き出し、言い換えることで、新たな発見があるかもしれません。
マインドマップを書く
マインドマップは、中心となるテーマから放射状にキーワードやイメージを繋げていくことで、思考を整理し、発想を広げるためのツールです。
自己分析にマインドマップを活用する場合、中心に「自分」を置き、そこから「性格」「価値観」「経験」「強み」「弱み」「興味」「将来像」など、様々なテーマを枝分かれさせていきます。
それぞれのテーマについて、思いつくキーワードやイメージをどんどん書き出していきましょう。
関連するキーワードやイメージ同士を線で繋いでいくことで、思考が整理され、自分自身の長所や短所が見えてくるかもしれません。
モチベーショングラフを書く
モチベーショングラフとは、過去から現在までのモチベーションの高低をグラフ化して分析するものです。
横軸に時間を、縦軸にモチベーションのレベルをとり、過去の出来事をプロットしていきます。
モチベーションが高かった出来事、低かった出来事を分析することで、自分のモチベーションの源泉を理解することができます。
モチベーションの源泉を理解することは、自分の長所や短所に気づくきっかけになるかもしれません。
他己分析をする
他己分析とは、友人や家族、先生など、周りの人から見た自分を分析することです。
他己分析では、 自分1人では気づけないような長所や短所、特徴を様々な角度から知ることができます。
他己分析の有名な方法として、ジョハリの窓があります。
自分が知っている自分、自分は気づいていない自分、他人は知っている自分、他人は気づいていない自分の4つに区切ることで、長所や短所を見つけてみましょう。
信頼できる人に、自分について率直な意見を聞いてみましょう。
他己分析の結果を自己分析の結果と照らし合わせることで、より客観的な自己理解に繋がるでしょう。
友人の自己分析結果と比べてみる
自分史やモチベーショングラフ、マインドマップなどで自己分析した結果を、友人の結果と見比べてみると長所や短所を発見することに繋がります。
信頼できる友人に、自己分析の結果を見せてもらい、自分の結果と比べてみましょう。
自分と相手の自己分析結果の共通点や相違点を見比べてみましょう。
まず最初は、自分と相手の似ている部分や共通する部分を見つけてみましょう。
その次にお互いの少し異なる点を見つけてから、最後に大きく異なる点を見つけてみましょう。
異なる点についてはなぜそう考えるのか、なぜそういう行動を取るのかなどについてお互いに意見を交わしてみるのがおすすめです。
自己分析本に従って書き出す
自己分析に関する書籍はたくさん出版されています。
これらの本を参考に、自己分析を進めてみましょう。
本によっては、具体的な質問やワークが用意されているものもあります。
これらの質問やワークに取り組むことで、自分自身の長所や短所を深く掘り下げて考えることができます。
キャリアアドバイザーに相談する
長所や短所を発見し、自分自身を深く理解するためには、専門家を頼るのも一つの手です。
プロのキャリアアドバイザーなら、豊富な知識と経験から長所と短所を的確に見抜き、わかりやすく解説してくれます。
面接での活かし方やエピソードとの結びつけ方なども、個人に合わせたものを一緒に考えてくれるので、身になっていくのが実感できます。
また、長所や短所に限らず、就活において有益な情報も得られるのが、キャリアアドバイザーに頼ることのメリットです。
具体的な情報を得るばかりではなく、就活中に抱いた不安にもプロの視点から向き合い、寄り添ってくれるので、メンタル面での安定にも役立つかもしれません。
自分自身の力で長所や短所を見つけ、理解を深めることに限界を感じたら、就活のプロの力を借りてみましょう。
【長所・短所の見つけ方】「長所・短所」一覧・言い換え例
自己分析を行う際、自分の長所と短所を把握することは非常に重要です。
しかし、いざ書き出そうと思っても、なかなか思いつかない、あるいはどんな言葉で表現すれば良いのかわからないという方もいるかもしれません。
そこで、ここではよくある長所と短所、そして言い換え表現を一覧で紹介します。
これらの例を参考に、自己分析を深めていきましょう。
| 長所 | 短所 |
| 忍耐力がある | 諦めが悪い |
| 好奇心旺盛 | 飽きっぽい |
| 責任感がある | 抱え込みやすい |
| リーダーシップがある | 我が強い |
|
物事に対して慎重に行動する 常に準備を周到にする |
緊張しやすい |
| 調整力がある | 仕切りたがり |
|
集中力がある 探求心が強い |
視野が狭い |
| 几帳面 | 神経質 |
|
計画性がある 責任感が強い 物事を慎重に進行する |
心配性 |
|
行動力がある 物事への対応が早い |
せっかち |
| コミュニケーション力がある | 世話焼き |
| 協調性がある | 流されやすい |
| 観察力がある | 人見知り |
| 努力家 | 没頭しやすい |
|
人の意見に流されにくい 落ち着いて考え行動できる |
マイペース |
| 危機管理能力がある | マイナス思考 |
|
向上心が強い 目標に向かって努力できる |
負けず嫌い |
|
常に効率的に行動する 無駄を省くことが得意 |
面倒くさがり |
|
柔軟性がある 常に配慮ができる |
優柔不断 |
【長所・短所の見つけ方】長所・短所を伝えるコツ
自己分析で見つけた長所・短所は、エントリーシートや面接で効果的に伝える必要があります。
伝える際には、以下のコツを意識しましょう。
表裏一体を意識し矛盾ないように伝える
長所と短所は、表裏一体である場合があります。
例えば、「真面目」という長所は、裏を返せば「融通が利かない」という短所になる可能性があります。
自己PRや面接で長所と短所を伝える際には、矛盾が生じないように注意しましょう。
短所を伝える際には、長所と関連付けながら説明することで、ネガティブな印象を与えることを避け、自己理解の深さをアピールすることができます。
過大・過小評価しない
長所を過大評価したり、短所を過小評価したりすることは避けましょう。
正直かつ客観的に、自分自身を評価することが大切です。
自信を持つことは重要ですが、傲慢な印象を与えないように注意しましょう。
また、短所を隠そうとするのではなく、改善に向けて努力している姿勢を示すことが大切です。
結論から伝える
長所や短所を説明する際は、結論から伝えるようにしましょう。
だらだらと説明するのではなく、最初に結論を述べることで、面接官に分かりやすく伝えることができます。
例えば、「私の長所は、最後まで諦めずにやり抜く力です」のように、最初に結論を述べ、 その後に具体的なエピソードを交えて説明することで、説得力を増すことができます。
具体的なエピソードを話す
長所や短所を説明する際は、抽象的な表現だけではなく、具体的なエピソードを交えて話すようにしましょう。
具体的なエピソードを話すことで、面接官はあなたの長所や短所をより深く理解し、共感しやすくなります。
例えば、「私の長所は、コミュニケーション能力が高いところです」と述べるだけでなく、 アルバイトでお客様とのコミュニケーションを通して、売上を向上させた経験などを話すことで、説得力を増すことができます。
短所は改善策も伝える
短所を伝える際には 改善策も合わせて伝えるようにしましょう。
短所をそのままにしておくのではなく、改善に向けて努力している姿勢を示すことで、面接官に前向きな印象を与えることができます。
例えば、「私の短所は、計画性がないところです」と述べるだけでなく、スケジュール管理を徹底するように 意識している ことや、タスク管理ツールを活用していることなどを伝えることで、改善に向けて努力していることをアピールすることができます。
【長所・短所の見つけ方】長所・短所を伝えるNG例
就職活動の面接では、自己PRやガクチカと並んで、長所と短所を聞かれることが多くあります。
しかし、せっかく自己分析で見つけた長所・短所も、伝え方を間違えると逆効果になってしまうことも。
ここでは、面接で長所・短所を伝える際のNG例を4つ紹介します。
長所・短所を話すだけで終わる
長所や短所を聞かれた際に、ただ単に「私の長所は○○です。短所は△△です。」と答えるだけでは、面接官に何も響きません。
なぜなら、面接官は、あなたの長所・短所を通して、
・あなたの人物像
・仕事への適性
・企業との適合性
・成長可能性
などを見極めようとしているからです。
単に長所・短所を羅列するのではなく、具体的なエピソードを交えながら、なぜそれが長所・短所なのか、仕事にどう活かせるのか、どのように克服しようとしているのかを説明することで、面接官にあなたのことを深く理解してもらうことができます。
「ありません」と答える
長所や短所を聞かれた際に、「特にありません」と答えるのはNGです。
誰でも長所と短所はあります。
「ありません」と答えてしまうと、
・自己分析ができていない
・自分に自信がない
・自己開示ができない
といったネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。
長所は、あなたの強みや能力を示すものです。
短所は、あなたの課題や改善点を示すものです。
どちらも正直に伝えることで、自己理解の深さをアピールすることができます。
たくさん伝える
長所や短所をたくさん伝えようとして、あれもこれもと羅列してしまうのもNGです。
情報が多すぎると、何が言いたいのかが伝わりにくくなってしまいます。
長所・短所はそれぞれ1~2つに絞り、具体的なエピソードを交えながら説明することで、面接官に分かりやすく伝えることができます。
また、長所・短所を絞ることで、自己分析がしっかりとできているという印象を与えることもできます。
仕事に影響しそうな短所を話す
短所を伝える際には、仕事に影響しそうな短所は避けるようにしましょう。
例えば、「集中力がない」「時間にルーズ」「協調性がない」といった短所は、仕事をする上で支障をきたす可能性があります。
短所を伝える場合は、仕事への影響が少なく、かつ改善可能なものを選びましょう。
そして、短所を克服するために、どのように努力しているのかを具体的に説明することで、前向きな姿勢をアピールすることができます。
【長所・短所の見つけ方】面接で聞かれたときの回答例
面接で長所や短所について聞かれた際に、効果的に伝えるための回答例を紹介します。
面接で長所・短所を答える際に、教科書的な内容にならないように注意しましょう。
企業の面接担当者には、マニュアル通りの回答はそれと見破られてしまうことが多いものです。
本来の人柄が伝わらなければ、企業も自社に合った人物かどうかを判断することができません。
一般に言われている長所や短所を、できるだけ具体的な経験やエピソードに落とし込み、自分なりに表現していくことを考えてみましょう。
長所:「計画性がある」
目標を達成するために、事前に綿密な計画を立て、スケジュール管理を徹底することを心がけています。
大学時代、私はサークル活動でイベント企画を担当しました。
限られた予算と時間の中で、イベントを成功させるためには、計画性と実行力が不可欠でした。
そこで、私はまずイベントの目的を明確にし、そこから逆算して必要なタスクとスケジュールを洗い出し、ガントチャートを作成しました。
計画通りに実行することで、イベントは大成功を収め、参加者からも「企画がしっかりしていて楽しかった」「運営がスムーズで安心して楽しめた」といった高い評価を得ることができました。
この経験を通して、計画性の重要性を改めて認識し、どんな仕事にも活かせる強みだと感じています。
御社でも、この計画性を活かし、目標達成に向けて積極的に行動することで、組織に貢献したいと考えています。
短所:「心配性」
物事を慎重に進めることはできますが、時にそれが過剰になり、決断を遅らせてしまうことがあります。
以前、アルバイトで接客をしていた時、お客様からのクレーム対応に戸惑い、適切な対応が遅れてしまったことがありました。
その結果、お客様に不快な思いをさせてしまい、深く反省しました。
この経験から、私は「70%の確信があれば行動する」というルールを自分に課しました。
もちろん、重要な決断を下す際には、事前に十分な情報収集と分析を行い、リスクヘッジを怠りません。
しかし、過去の経験にとらわれ、過度に心配しすぎるのではなく、状況に応じて柔軟に対応できるよう、意識的に行動するようにしています。
まだ完璧とは言えませんが、日々改善を心がけています。
【長所・短所の見つけ方】エージェントに相談しよう
就活で困ったことがあれば、就活エージェントに相談してみることと良いでしょう。
就活に関して総合的にアドバイスをしてくれるだけでなく、就活に関する不安や疑問を話すことにより解決することができます。
それに加えてES添削や本番を意識することができる模擬面接をしてもらうことができます。
まとめ
長所と短所は面接でも問われることが多い、就活における最頻出項目の一つです。
長所が秀でているだけではなかなか評価されないことも多く、短所と絡めた一貫性のあるアピールが大切になります。
長所は具体的なエピソード、短所はいかにマイナスの印象をプラスに変えられるかが重要です。
これまでにお伝えした長所短所の見つけ方、注意点、魅力的な伝え方のポイントを押さえ、万全の状態で就活が行えるよう、しっかり準備していきましょう。