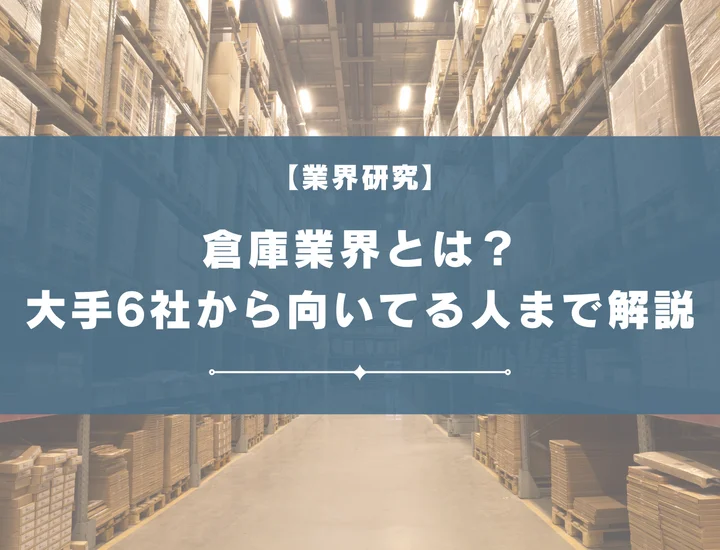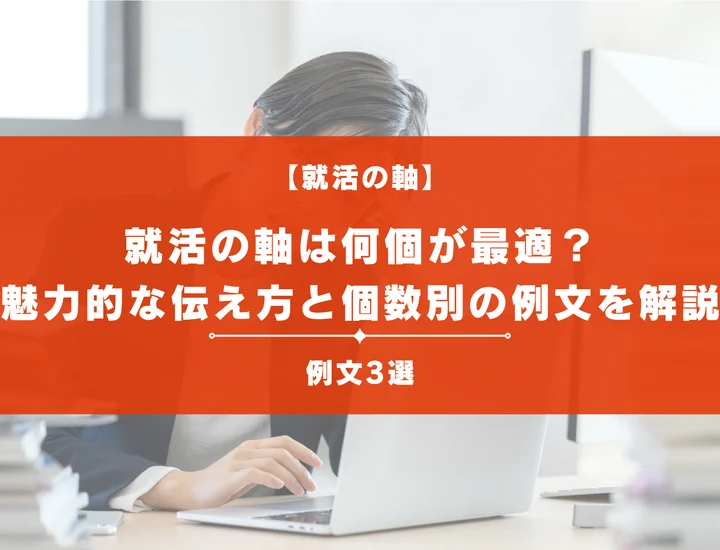はじめに
転職活動の際、職務経歴書の提出を求められることがあります。
しかし、職務経歴書は何のために必要なのか、履歴書との違いは何なのか、などの疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、職務経歴書を書く際のコツをご紹介します。
書き方がわからない方はぜひ参考にしてみてください。
【職務経歴書のコツ】なぜ企業は職務経歴書の提出を求めるのか
職務経歴書は、ただ自分の経歴を並べ立てればいいというものではありません。
採用を目指すのであれば、自分は企業が求める人材に近いのだということをアピールする必要があります。
そこで、書き方のコツをつかむために、まず初めに企業側の意図を把握しましょう。
企業が職務経歴書の提出を求める主な目的は、「対象外の人を外すこと」「経験職種と募集職種が合っているかを判断すること」「最低限の情報を得ること」の3つです。
続いて、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
対象外の人を外すため
目的の1つとして挙げられるのは、対象外の人を外すことです。
求人を出した企業は、募集人数より多い応募者をふるいにかける必要があります。
そのために面接などの選考が行われますが、多くの応募者を相手にするとなると、非常に時間と手間がかかる作業です。
明らかに求めている人材からかけ離れた応募者に対し面接を実施することは、人事担当者にとって大きな負担になるでしょう。
そのため、面接の前段階として職務経歴書を提出させ、企業にまったく合っていないような人を外します。
面接をしてみないとわからないことは多いですが、書類による選別を行うことによって、面接の手間を省くことができるのです。
求める人材像から大きく外れると判断されかねない経歴書を作成するのは、避けるべきでしょう。
経験職種と募集職種が合っているかを判断するため
次に企業が注目して見ると思われるポイントは、職種です。
職務経歴書に書かれている過去の職種と、企業の募集している職種との相性も、採用するべきかどうかを判断する基準の1つとなっています。
たとえば前職が募集されている職種と相性の良いものであれば、ある程度のノウハウを持ち合わせている可能性が高く、企業は教育のためにかかるコストなどを節約できると考えるでしょう。
一方で、職種が合っていなければ働かせるのにふさわしくないと判断され、その時点で落とされてしまうこともあります。
加えて、職種を事前に知っておくことで、企業側が面接で見るべきポイントを絞ることができるのです。
自身の経歴が募集職種と合っているかどうかを良く見極め、応募する必要があります。
最低限の情報を得るため
前述した2つは、応募者をふるい落とすためという側面が強い要素でした。
企業のもう1つの目的は、最低限の情報を得ることです。
職務経歴書には、学歴や職歴など志望者に関する基本的な情報が記載されています。
もちろん企業が求めている人材に適しているかどうかを判断するには、経歴書上の情報だけでは足りません。
しかし、さらなる情報を得るために面接を行うにあたっての前提知識として、それらの基本データが役立つのです。
1つ前の項目でも述べたように、企業側も面接に先立って応募者のどこを見るかを絞る必要があります。
事前に応募者について知り、質問を準備するための材料として、職務経歴書は企業にとって重要なものです。
作成する際には、これらの意図を意識するようにしましょう。
【職務経歴書のコツ】履歴書と何が違うのか
同じく面接の前に提出を求められるものとして、履歴書があります。
一見、履歴書も職務経歴書も自身の経歴について記載する書類であり、大きな違いはないような印象を受けますが、この2つの違いは何でしょうか。
履歴書とは、学歴や職歴など志望者本人に関する基本的なデータについて記載し、自分の情報を提供することが目的の書類です。
ゆえに、履歴書を通して自身の強みなどをアピールすることは難しいといえます。
一方職務経歴書は、自分の情報に加えて過去に担ってきた役割や経験、スキルと共に、自己PRを記載する書類です。
企業は職務経歴書を読むことで、志望者の強みを判断します。
したがって、採用者にとって魅力的に見えるような自身の経験についてアピールする必要があるでしょう。
【職務経歴書のコツ】企業は職務経歴書で何をみているのか
ここまでは、企業が職務経歴書を通して何を知ろうとしているのかということについて、ご説明してきました。
次に、企業が職務経歴書のどこに注目しているのかを把握しましょう。
重要なのは、応募者が持っている経験やスキル、意欲だけでなく、書類としての完成度も重視されるポイントであるということです。
職務経歴書1枚をとっても、作成した者の性格や美意識がよく表れるものであり、採用者はそこに注目しています。
それでは、注意するべきポイントについて解説していきます。
書類作成の丁寧さ
まず前提として、企業が重視するポイントの1つは書類が丁寧に作成されているかという点です。
人事担当者はフォーマットにこだわっていませんが、書類をどれだけ丁寧に作成してきたかを見ています。
このような事務的な作業には、普段の性格が反映されやすいからです。
たとえば用紙の端が折れ曲がっていたり、汚れがついていたりしたら、大雑把でいい加減な性格であるという印象を与えてしまいます。
入社した後の仕事も適当にこなすタイプだと判断され、選考に悪い影響を及ぼしかねません。
書類の内容ではなく、その前段階が原因で落とされてしまうのは非常にもったいないことです。
用紙の綺麗さや写真の身だしなみなど細かいところまで気を配り、丁寧に職務経歴書を作成することを心がけましょう。
書類の見やすさ
書類を丁寧に作るという大前提をクリアしたら、次に注意するべきはそのレイアウトです。
企業に提出する書類の作成においては、企業の人事担当者に見てもらえるような、見る気にさせるレイアウトで作成することが非常に重要になります。
先ほども述べたように、職務経歴書は企業に対して自身をアピールするための書類でもあります。
したがって、自分だけが読めればいいわけではありません。
汚い字やごちゃごちゃとして読みづらい配置で書いてしまうと、重要な情報がうまく伝わらなくなってしまいます。
それどころか、目を通してもらえない恐れもあるでしょう。
ですから、読みやすい字で書くことはもちろん、見やすくわかりやすいレイアウトで作成することが求められるのです。
求める経験やスキルを持っているか
書類としての体裁を整えた後は、採用されるためにどのような内容にするべきかを考えなければなりません。
人事担当者は、企業が求める経験やスキルを志望者が持っているかどうかを見ています。
企業には理想とする人材像があるため、できるだけそれに近い人材を採用したいと考えているはずです。
人柄や態度は面接を通して実際に接してみないとわかりませんが、経験やスキルといった情報は面接でなくても職務経歴書から読み取ることができます。
求めているものとあまりにも乖離したスキルを持っている人を採用したとしても持て余してしまうでしょうから、それを回避するためにも職務経歴書を見て判断する必要があります。
つまり、職務経歴書は採用者にとって重要な選考基準となり得るのです。
職務経歴書を書く際は事前に企業の理想像を把握しておき、それに近いという印象を与えることを目指しましょう。
どんな強みがあるか
人事担当者は、どんな強みがあるかというポイントにも注目します。
応募者の持つ強みがその企業の業務に役立つものである場合、人材としての魅力が一気に高まるからです。
職務経歴書では、自身の学歴や職歴といった情報のほかに、過去に担ってきた役割や経験、スキルについて記載することができます。
企業はそれらの情報を通して、志望者にどのような強みがあるかを理解しようとしているのです。
どのような人材が求められているのかを把握したうえで、それに合致するような強みがあれば、積極的にアピールすることが望ましいでしょう。
また強みがわかったら、それに関する質問を採用面接で投げかけてくる可能性があります。
職務経歴書でアピールした自身の強みについて、口頭でも説明できるようにしっかりと分析をしておきましょう。
意欲や向上心があるか
企業は、応募者の経歴や能力だけではなく、志望意欲や向上心がしっかりとあるかどうかも採用基準に含めています。
過去の経歴ももちろん大事ですが、前提として気持ちの面は仕事をやるうえでマストになってくる要素です。
意欲が高く向上心のある人材は、就職した後もスキルアップを図って努力し、会社側にも利益をもたらし得ると考えられます。
一方で、向上心がない従業員は日常的な業務をこなすことはできても、企業の成長につながるような働きはできないでしょう。
また、チームでの業務などにおいては士気が低下し、生産性が落ちることも考えられます。
企業にとって魅力的なのは前者の人材であるので、職務経歴書を作成する際にも、やる気があることをアピールするように心がけましょう。
過去にどんな経験があるか
過去の経験は、人事担当者が最も注目するポイントであるともいえます。
職務経歴書において最も重要な要素は、過去の具体的な経験を踏まえた自己PRです。
企業は、志望者が過去にどのような姿勢で業務に取り組み、その結果どのような成果を上げたかを知りたいと思っています。
強みや意欲に関するアピールは、それらを活かした成功体験がないと少し説得力に欠けると思われかねません。
自己PRを行うにあたっては、過去の具体的な経験の工夫や取り組みを踏まえつつ書くことが重要になるのです。
過去の経験について書く際は、自身がアピールしたいポイントと関連付けることを意識すると共に、最終的にどのような成果につながったのかという結果まで記すようにしましょう。
【職務経歴書のコツ】作成前の準備は何をしたらよいか
ここまで、職務経歴書を作成する際に注意しなければならないポイントについて、ご説明してきました。
次は、職務経歴書を作成する具体的な手順やコツを解説していきます。
まずは、作成前の準備についてです。
前の項目でも述べたように、企業が求めている人材や自身のアピールポイントについては入念な分析が必要となります。
作成の前段階として、企業の募集要項の理解と経歴の整理は、時間をかけて丁寧に行うことを心がけましょう。
企業の募集要項を理解する
まず、自己PRの軸を定めるために、企業が理想とする人材像について理解することは最優先です。
自身の強みについて考えたときに、複数のアピールポイントが思い浮かぶ方も多いかもしれません。
しかし、それらすべてについて説明しようとすると1つ1つの印象が薄まり、かえって思い通りのアピールができなくなる恐れがあります。
したがって、自己PRの軸となる軸を1つ選び、それについて深く掘り下げることで自身を印象づけやすくなるのです。
アピールポイントは、やはり企業の理想としているものに近い強みを選ぶことが望ましいです。
募集要項には「どのような人材を求めているか」ということが必ず記載されているので、深く読み込んで企業理解につなげましょう。
公式HPなどに載っている企業理念とあわせて読むと、さらに理解を深められるかもしれません。
経歴の整理をする
自己PRの軸が定まった後は、経歴の整理をすることが重要です。
自身の強みを企業に対して効果的にアピールするためには、具体的な経験と紐づけて説明する必要があります。
しかし、強みを活かしたエピソードがすぐには思いつかないという方もいらっしゃるかと思います。
そこで、経歴の細分化を行うことにより、自身の過去について深く見つめ直してみましょう。
細分化によって見えてきた小さな取り組みなどに、アピールしたい強みや意欲が表れていることがあるかもしれません。
自身の経歴について掘り下げることは、具体的な自己PRの作成につながるといえます。
以上の2つの準備を行うことで、自己PRのベースを強化し、人事担当者の目を惹きつける職務経歴書を目指しましょう。
【職務経歴書のコツ】職務経歴書作成のコツ
職務経歴書を書く際に気を配るべきポイントと、行うべき準備については十分ご理解いただけたかと思います。
ここからは、いよいよ具体的な書き方についてのご説明です。
相手に読んでもらうことが前提の書類であるので、伝えたいことをだらだらと書き連ねるだけでは、良いものになりません。
文書としての見やすさ、内容のわかりやすさを意識することが重要です。
ここでは読みやすく、主張を十分に伝えることができる職務経歴書作成のコツを4つご紹介していきます。
読みやすさにこだわる
1つ目のコツは、読みやすさにこだわって作成することです。
文書は読みづらいというだけで、読み手側の興味を一気に削いでしまう恐れがあります。
職務経歴書は選考に関わる重要な書類であり、きちんと読んでもらえなければ意味がありません。
企業の人事担当者に見てもらうことを考えて、読みやすくなるように心がけましょう。
具体的には、レイアウトや文字の大きさ、丁寧さなどの細かい部分にまで気を遣うことが読みやすさにつながります。
また、このような作業には性格が反映されるものであり、人事担当者は文書としての完成度にも注目しているかもしれません。
細部にまで気を配ることによって、丁寧で細やかな仕事ができる人材であるということをアピールしましょう。
適当な分量で書く
2つ目のコツは、適当な分量で書くことです。
まず、決められた分量は最低限超えるように心がけましょう。
規定の字数に達していなかったり聞かれたことに答えていなかったりした場合、志望意欲に欠けるとみなされてしまう恐れがあります。
また、指示をよく読んでいないと判断され、能力面でもマイナスの評価を受けてしまうかもしれないので注意しましょう。
一方で、字数が多すぎても採用者に良い印象を与えることはできません。
冗長な文章は読みづらいうえに、主張が伝わりづらくなります。
加えて、文章を的確にまとめる能力がないと思われる可能性が高いです。
主張したいことを絞り無駄な表現を削って、適正だと考えられる字数の範囲内に収めることを心がけましょう。
経験だけでなく工夫したことも書く
次のコツは、経験だけでなく工夫したことも書くということです。
企業が職務経歴書を通して判断しようとしているのは、単純な経歴ではありません。
応募者が思う自身の強みを、具体的な経験の中でどのように活かすことができたかについて、伝えなければならないのです。
そのためには単に自分の過去の経験を書くだけでなく、過去の経験の中でどのように自分が工夫を凝らして業務を遂行してきたのか、具体的に書くことが大切になります。
準備段階で行った経歴の細分化をもとに、自身の強みを活かすことができたといえる自発的な行動について、書くようにしましょう。
また、志望先の業務にも活かせるような内容の工夫について述べられると、より良い印象を与えることができます。
自己PRではできること、やりたいことを明確にする
最後にご紹介するコツは、自己PRでは入社後にできること、やりたいことを明確にすることです。
ここまで、企業にとって有益となる自身の能力や強みをアピールするべきだと何度か述べてきたように、自己PRを作成する際に「できること」を主張するのはもちろん大切です。
しかし、あわせて企業に入社した後に自分が「やりたいこと」を明確にして伝えておくことで、人事担当者も応募者の働く姿がイメージしやすくなります。
したがって、過去の経験とその際に発揮した自身の強みを説明すると共に、今後その強みを活かして何を成したいのかについても具体的に述べましょう。
そのためには、志望先の業務について詳しく把握しておく必要もあります。
準備段階で行った企業分析と絡めることで、意欲のアピールにもつながるでしょう。
【職務経歴書のコツ】エージェントに相談しよう
職務経歴書の作成に関するご説明は以上になりますが、これらに基づいて文章を作っても、良し悪しについて自分で判断することは難しいかと思います。
そこで、転職エージェントに職務経歴書を添削してもらうことがおすすめです。
第三者に読んでもらうと自分にはない視点からの指摘を受けることができ、文章の質の向上につながります。
また、エージェントは職務経歴書の添削のほかにも、転職先の紹介など有益なサポートを行っているので、ぜひ利用してみましょう。
利用したい方は、下記のURLからアクセスしてください。
まとめ
職務経歴書は、応募者の経歴だけでなく自己PRを記載できる書類です。
企業が求めているものに近い自身の強みを探し、それを活かして成果を上げることができたといえる、具体的な経験と共にアピールしましょう。
そのためには、入念な企業分析と経歴の細分化を行う必要があります。
また、人事担当者が読むことを念頭に置いて、読みやすいレイアウトや文字で、適当な分量に収めて書くことも重要です。
エージェントによる添削サービスなども利用しながら何度か書き直し、より良い文章を目指してみてください。