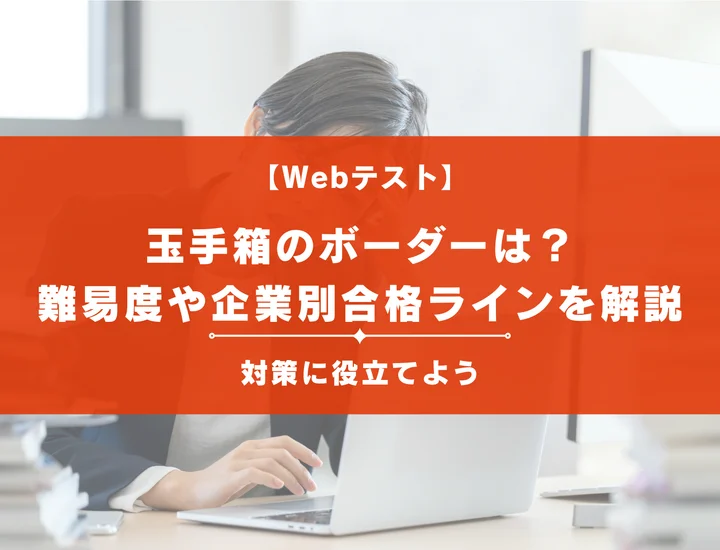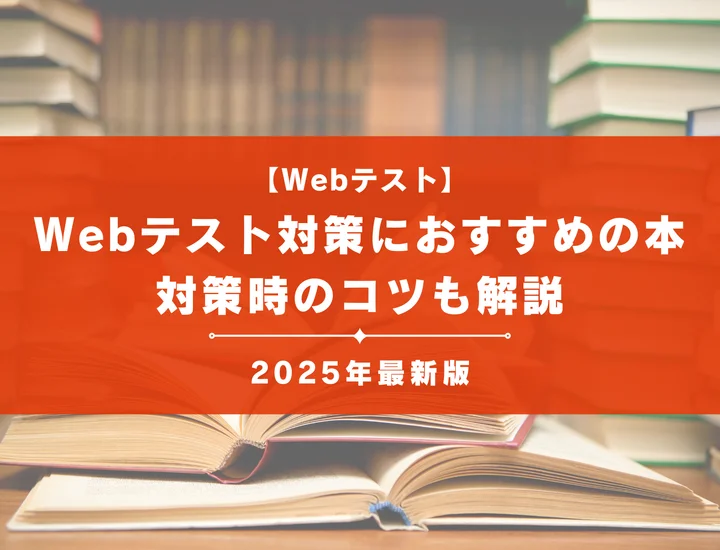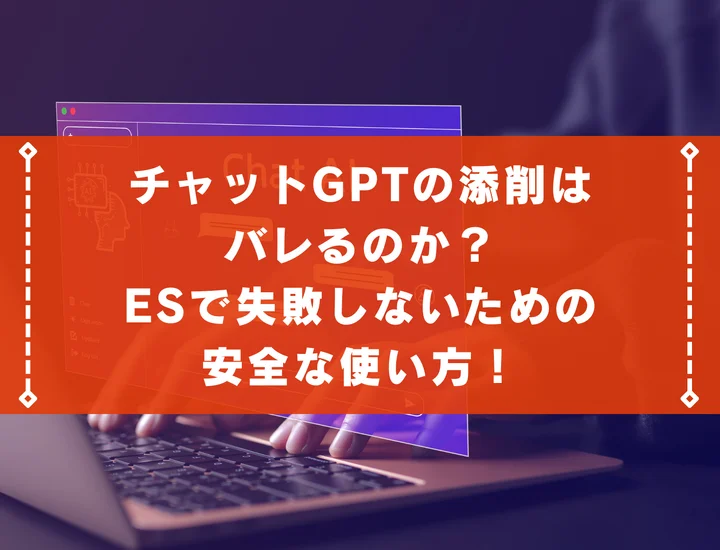明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・WEBテストの対策方法
・WEBテストの形式・種類
・WEBテストの見分け方
・WEBテストの対策を始めた人
・WEBテストの見分け方を知りたい人
・WEBテスト効率的な対策スケジュールを知りたい人
近年は就職試験の筆記試験を、WEBテストで実施する企業が多くあります。WEBテストの通過率を上げるためには、どのような対策をすれば良いのでしょうか。
今回はWEBテスト対策や効率的な進め方について解説するので、ぜひ参考になさってください。
【WEBテスト対策】Webテストの対策はするべき?
これからWEBテストを受けるにあたり、事前に対策する必要があるのか疑問に思っている人もいるでしょう。
一般的な企業の選考であれば、中学高校までに習った範囲で済みそうなため、わざわざ対策するのは面倒だと感じる人は多いです。
しかし、WEBテストを受けるのであれば事前準備は必ずするべき行為です。
WEBテストは近年では多くの企業の選考に設けられており、とくに難関企業の場合比較的高いボーダーとなっています。
なお、確かに中学高校までの知識で解けるようになっている場合が多いですが、大学受験の試験問題とは傾向が違うため注意が必要です。
テストの時間は限られているため、短時間で効率的に進めていくためにも解き方を身につけなければならず、WEBテスト用の勉強は必須です。
【WEBテスト対策】そもそもWebテストとは
WEBテストとは、近年の選考フローで多くの企業が取り入れているテストです。
その名の通り、パソコンやスマートフォンを使ってWEB上で受験します。
自宅など、場所を問わず受験できる場合もあれば会場が指定されている場合もあり、企業によってどのように受けるか異なるため案内の確認が必要です。
なお、テストの形式は複数存在し、評価される分野も異なります。
そのため、志望先の企業が何を導入していても対応できるよう、それぞれの形式に適応する準備をおこなう必要があるのです。
難易度
一般的なWEBテストの難易度は、そこまで高く設定されているわけではありません。
基本的に、中学レベルの知識で解ける比較的簡単な問題が多いです。
ただし、WEBテストには提供している企業を含めさまざまな種類、形式が存在します。
そのため形式によって難易度の差があり、難関企業ほど難しいテストを導入しているのです。
また、出題方法に癖があるため、初見でスラスラ解ける人は多くありません。
時間内に何問正答できるかが合否を分けるため、対策しないと難しいと感じる人がほとんどです。
実施時期
WEBテストの実施時期は、主にエントリーシートの提出と同時であることが多いです。
つまり、企業にエントリーすると同時に受験して結果を企業に送らなければならないのです。
これは、WEBテストが企業にとって最低ラインとなるスキルを有している就活生をふるい分ける機能を持っていることに由来します。
ただし、企業によっては一次面接後や入社前に課すところもあり、一概にはいえません。
志望先の企業がどのタイミングでテストを実施するかは、企業からの案内を逐一確認する必要があります。
【Webテスト対策】Webテストを攻略するポイント
就職活動の選考では、Webテストが序盤に課されることが多く、突破できるかどうかで面接に進めるかが決まります。
ここでは、Webテストを攻略するための具体的なポイントを4つ紹介します。
志望企業の出題傾向を把握する
WebテストにはSPIや玉手箱、TG-WEBなど複数の形式があり、それぞれ出題範囲や特徴が異なります。
そのため、志望企業がどの形式を導入しているかを事前に把握しておくことが重要です。
企業の採用ページや就活サイト、先輩の体験談を参考にすることで、よく出題される分野や難易度の目安を知ることができます。
出題傾向を理解したうえで学習を進めれば、志望企業の選考に向けて効率的に得点力を高めることができ、無駄な対策を避けられます。
まずは志望先の情報を調べ、自分に必要な対策範囲を明確にしましょう。
できる限り早めに対策を始める
Webテストは制限時間が短く、テストごとに独特な問題形式が多いため、基礎学力だけで対応するのは難しいケースも少なくありません。
個々の学力レベルによって必要な学習時間は変わりますが、早めに取り組むことで余裕をもって対策できます。
特に数学や論理問題に不安がある人は、慣れるまで時間がかかる場合が多いため、就活開始の段階から少しずつ練習しておくのがおすすめです。
試験直前に慌てて対策するより、日常的に問題を解いておき、Webテストに慣れることで、スムーズに得点力を伸ばせます。
時間配分を意識する
Webテストで高得点を取るためには、限られた時間で効率的に解答する力が欠かせません。
Webテストでは、基本的に「1問にかけられる時間」が非常に短く、考え込みすぎると最後まで到達できないことも多くあります。
そのため、普段から模擬問題を解く際に時間を計り、1問にかける上限時間を意識して練習しておくと、本番で焦らず取り組めます。
また、難しい問題に時間を取られすぎず、解ける問題を優先して得点を積み重ねることが重要です。
このように時間配分を意識した問題演習を習慣化すれば、安定して高得点を狙えるようになるでしょう。
苦手分野を重点的に対策する
Webテストでは幅広い範囲から出題されるため、苦手分野を放置すると得点の大きなロスにつながります。
全体的にバランスよく点を取れるようにするには、自分の弱点を早めに把握し、集中的に対策して克服することが重要です。
例えば、推論問題が苦手な人は何度も問題を経験して解き方の傾向を掴む、計算スピードが遅い人は計算ドリルを繰り返す、文章理解が苦手な人は読解問題を増やすなど、ピンポイントで対策を行いましょう。
苦手を放置せずに取り組むことで、総合的な得点力が底上げされ、安定して合格ラインを超えやすくなります。
【WEBテスト対策】WEBテスト効率的な対策スケジュール
WEBテストの効率的な対策スケジュールを紹介します。
1.WEBテストの目的を把握する
2.WEBテストの形式・種類を知る
3.WEBテストの対策ツールを知る
4.勉強をする
5.WEBテストを受ける準備をする
就職試験で出されるWEBテストは1種類だけではないので、結構時間がかかるものです。
半日~1日時間ができた休日に、テストについてしっかり下調べしておくことをおすすめします。
1.WEBテストの目的を把握する
まずは、WEBテストが実施される目的を知ることが大切です。
テストが何のために行われるか・合格ラインはどれぐらいか・いつ何回受験しなければならないのか、といったことを把握しておきましょう。
多くの企業を受験する場合、SPIなどのWEBテストは、毎日のように受ける時期があってもおかしくありません。
しかし、就職試験時以外あまり受ける機会がないのも事実です。
ほとんどの方にとってなじみが薄いものなので、事前にしっかり基礎的なものを学んでおきましょう。
2.WEBテストの形式・種類を知る
続いて、WEBテストの形式・種類を学んでおくことも大切です。
WEBテストは1種類だけでなくさまざまな種類があり、企業によって選ぶ試験が異なります。
同じ名前の試験でも、企業によって出題範囲や難易度が違うことも多いです。
例えば英語力を重視する企業だと、他の企業が実施するWEBテストに加え、英語のWEBテストを追加することがあります。
自分の苦手科目・問題をしっかり対策できるよう、テストの種類を知っておくことが効率化のポイントです。
3.WEBテストの対策ツールを知る
続いて、WEBテストの対策ツールをチェックしておきましょう。
WEBテスト対策の方法は1つだけではなく、さまざまな学び方があります。
主な対策ツールは、参考書や問題集・アプリです。
しかし、人によって自分に合った勉強法は異なるでしょう。
どの方法が自分にとってやりやすいか、見極めてから勉強を始めるのがコツです。
まずはアプリをダウンロードしたり、書店で参考書や問題集を手に取って中身を確認したりして自分に合ったツールを探しましょう。
4.勉強をする
WEBテストの目的や種類・対策ツールについて十分予習をしてから、勉強を進めていきます。
人によって勉強スタイルは違うので、自分に合った方法で進めましょう。
先に問題集を解いてみて、苦手分野を見つける方が点数を伸ばしやすい人も多いです。
しかしWEBテストを初めて受ける人は、まず参考書でどのような問題が出るか解説を読み、学んでから試験を受けるスタイルがやりやすい場合も多いでしょう。
アプリを使い、スキマ時間に少しずつ問題を解いていく方法もおすすめです。
5.WEBテストを受ける準備をする
最後に、WEB テストを受けるための準備をしておきましょう。
WEBテストを受けるには、インターネット環境や音声関係の周辺機器などを充実させておく必要があります。
WEBテストの受験に必要なIDなどがあれば、その情報も紛失しないようにしておかなければいけません。
また、テストが立て込む時期はスケジュール管理も必要になります。
テストは時間のある時に自宅で受けられますが、志望する企業のテストをいつでも自分の希望する日時に受けられるように準備しておくことが大切です。
【WEBテスト対策】WEBテストの形式・種類
次に、WEBテストの形式や種類をチェックしていきましょう。
どのテストも実施される目的は同じで、近い問題が出題されることも多いです。
しかしそれぞれ独自の特徴もあるので、どの種類も1度は模擬テストを受けておくことをおすすめします。
①SPI
SPIは言語系・非言語系・性格診断からなるWEBテストで、多くの企業が採用している有名なテストでもあります。
英語を重視する企業では、SPIの英語試験も一緒に実施されることも多いです。
そのため対策本などもたくさん出ており、事前の練習をするツールには困らないでしょう。
SPIについてより詳しく知りたい方・対策したい方は、これらの記事もぜひ参考になさってください。
②玉手箱
玉手箱は能力テスト・性格テストがどちらも出題されるWEBテストです。
能力テストは言語・計数・英語といった分野があります。
SPIと同様に、多くの企業で実施している有名なテストです。
玉手箱の方がSPIより難しい・時間が短いと感じ苦戦する就活生が多く、難しくてあまり解けなかった場合でも周りも点数が良くない可能性が高いので、悲観する必要はありません。
③TG-Web
TG-Webも、多くの企業が採用しているWEBテストです。
特徴としては従来型・新型と2タイプの試験があることや、SPIなど他のWEBテストと形式が異なる問題が多いことが挙げられます。
またTG-Webは非常に難易度が高いテストですが、大企業が採用しているケースが多く問題が難しいにもかかわらず、合格ボーダーラインが高く設定されている可能性があるのです。
④GAB
GABは、総合職の適性を確かめるために言語・計数系の問題が出題されるWEBテストです。パーソナリティ検査も実施されます。
GABは、企業側に成績に基づいた職務適性などが伝えられることが特徴です。
論理的思考力を試される問題が多く、事前に対策をしておくようにしましょう。
またGABは電卓の使用が認められているので、解答時間短縮のために電卓を準備しておくことが大切です。
⑤CAB
CABは能力検査・性格検査が実施されるWEBテストで、プログラマー・エンジニアといった職業の適性を見るために実施されることが多いです。
そのため、IT系の企業などで実施されることが多いでしょう。
能力検査では四則演算・法則性・暗号などの問題が出題される傾向が強く、暗号など他の試験では出題されないこともある問題を、しっかり対策しておく必要があります。
【WEBテスト対策】WEBテストの見分け方
WEBテストがSPIか玉手箱か、それとも別のテストか見分ける方法について解説します。
テストを開いた瞬間にどのテストか把握しておけば、どのような問題が出題されるか予測し心構えができます。
ぜひ、見分け方を覚えておきましょう。
URLのドメインで見分ける
WEBテストを見分ける最も簡単な方法は、URLのドメインを確認することです。
ドメインとはネットワークやコンピュータを識別するもので、ネットワーク上の住所を示すものと言い換えることもできます。
例えば、Googleで何かを検索すると、検索結果のページには何を検索しても「google.com」というドメインが含まれるでしょう。
しかしYahoo!で検索すると、検索結果ページには「search/yahoo.co.jp」というドメインが含まれます。
このように、アドレスを見てドメインを特定できれば今から受けるテストが何か判別できるのです。
ある程度WEBテストに慣れてくると、最初の注意事項やはじめの問題も見たことがあるものが多くなり、ドメインを見なくても問題が予測しやすくなります。
・SPI:「http://arorua.net/」
・玉手箱:「e-exam」・「nsvs」・「tsvs」を含むアドレス
・TG-Web:「http://assessment.c-personal.com/」・「http://assessment.e-gitest.com/」・「https://www.c-personal.com/」
【WEBテスト対策】WEBテスト対策ツール
次に、代表的なWEBテスト対策ツールを紹介します。
これからWEBテスト対策を進めたい人は、ぜひ参考になさってください。
こちらの記事でも、詳しくWEBテストの効率的な勉強法を紹介しています。
ぜひこちらも読んでおくことをおすすめします。
参考書・問題集
参考書・問題集は手軽に入手できるおすすめ対策ツールですが、さまざまな本が出ているのでどの本を買えば良いか迷う方も多いでしょう。
就活生から評判が良い、おすすめの参考書は以下の2つです。
・『これが本当のWebテストだ!』
・『2025最新版 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集』
しかし、WEBテストはいくつも種類がありますので、特定のテスト形式に合わせて対策しておきたい場合は、ぜひそのテスト専用の参考書・問題集を使いましょう。
こちらの記事では、さらに詳しくWEBテストの参考書・問題集を紹介しています。
アプリ
近年は紙ベースの参考書・問題集だけでなく、アプリでもWEBテストの対策ができるようになっています。
特におすすめのアプリは、「SPI言語・非言語 就活問題集 -適性検査SPI3対応」・「SPI言語|しっかり解説の資格試験問題集」・「SPI言語・非言語 一問一答"」です。
アプリは短時間でもスマホがあれば勉強ができ、成績管理・弱点分野なども把握しやすい特徴があります。
参考書・問題集とうまく組み合わせると、さらに効率的な勉強ができるでしょう。
Webテスト偏差値診断
ベンチャー就活ナビの「Webテスト偏差値診断」は、幅広いテスト形式に対応して、総合的にあなたの解答力を鍛えられるサービスです。
会員登録をするだけで、完全無料で回数制限なく利用可能なため、「自分の実力を試したい」「苦手分野を明確にしたい」という思いがある方におすすめです。
興味がある方は、以下のボタンからぜひ学習に役立ててみてください。
【WEBテスト対策】WEBテストの対策方法
次に、WEBテストの対策方法を解説します。
WEBテストは考える時間がなく、次々と答えなければいけません。
効率よく対策をして、満足できる点数を取れるようにしましょう。
能力検査編
まずは、WEBテストの能力検査に対する対策から見ていきましょう。
能力検査を突破するためには、決められた時間内で効率的に、どんどん問題を解けるよう訓練する必要があります。
そのため、一つの問題集をやり込む、動画コンテンツを活用する、解けなかった問題を振り返る、受験の回数を重ねるなどの対策が必要です。
それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。
一つの問題集をやり込む
能力検査に効率的に対策をおこなうためには、1冊の問題集を繰り返し解き、やり込む必要があります。
さまざまな出版社から構成の異なる問題集が販売されているため、自分に合った問題集を選び、それを完全にマスターすることが重要です。
WEBテストは出題される問題数が多く、決められた時間内にどんどん問題を解いて正答を引き出していく必要があります。
1冊の問題集に掲載されている同じ種類の問題を繰り返し解くことで、出題される問題パターンを把握でき、解答スピードも向上する可能性が高いです。
とはいえ自分に合わない問題集を購入しても練習に身が入らず、うまく訓練できません。
過去の問題集の口コミを確認する、先輩からどのような問題集が良かったかなどの情報を集めて、自分に合った問題集を探して取り掛かりましょう。
公式を丸暗記する
特に非言語分野の問題を難しく感じる人も多いですが、数学の公式や解法を覚えておくだけで、格段に解答スピードが速くなります。
仕事算や速度算、損益算といった典型的な分野は、公式や解き方を丸暗記しておくと、考える時間を大幅に短縮できるのです。
丸暗記というと応用が利かないように思われがちですが、むしろ基礎の公式を覚えることで複雑な応用問題にも対応しやすくなります。
制限時間が短いWebテストでは「解法を覚えているかどうか」が得点力を左右するため、繰り返し学習して公式を定着させておくことが合格への近道となります。
動画コンテンツを活用する
能力検査の対策には、動画が役に立つ場合もあります。
なかには、本を読むだけでは解法の理解が難しい問題や、これまでに解いたことがない新しい問題タイプに遭遇する場合も少なくありません。
そのような場合は、YouTubeなどの動画プラットフォームで解説動画を探しましょう。
動画では視覚的に解き方を解説しているため、参考書のなかで文字の解説だけを読むよりも効率的に理解を深めることができます。
とくに、構造的把握能力の検査などでは解説動画が役に立つ場面が多いです。
一つ動画を見れば複数の関連動画をおすすめしてもらえるため、理解するまで動画を探せるでしょう。
ただしYouTubeなどで動画を探す際は、関係のない動画に目移りしないよう気をつけなければなりません。
解けなかった問題を振り返る
本番中に解けない問題に固執するのは良くありませんが、練習では解けなかった問題こそ振り返って解き直す必要があります。
解けなかった問題をそのまま放置すると、本番で再びその問題が出たときにその分の得点を捨てることになりかねません。
一問でも多くの問題を解き、得点に繋げるべきWEBテストでこれは大きな痛手です。
そのため、間違えた問題や解けなかった問題は覚えておき、しっかり解き直すことが大切になります。
本命の企業のWEBテストで解けない問題が出てから後悔しても遅いため、なるべく苦手だと感じた分野にもしっかり取り組んで対策しておくことが重要なのです。
表面だけなぞっても似た問題が出たときに対応しきれなくなるため、しっかり解き方を理解できるまで繰り返し解きましょう。
受験の回数を重ねる
何よりもWEBテスト対策になるのは、本番のテストを繰り返し受験し回数を重ねることです。
これは、受験時の雰囲気や出題の形式に慣れるだけでなく、問題そのものを解きやすくなっていく対策になります。
WEBテストは、基本的に特定の問題群からランダムに出題される仕組みです。
そのため、実際の受験回数を重ねるほど過去に解いた問題に出会いやすくなり、練習にかける時間の削減に繋がります。
就活では、WEBテスト以外にもさまざまな選考の対策をおこなわなければなりません。
書類選考と同時に実施されるWEBテストに練習時間を割き過ぎて、そのあとの面接対策が疎かになってしまっては意味がないでしょう。
そのため、効率良く問題に慣れ、過去問を復習しながら他の選考の対策をおこなっていくためには、本命でない企業のWEBテストもどんどん受ける必要があります。
性格検査編
続いて、WEBテストにおける性格検査の対策について見ていきましょう。
性格検査に正確に答えられるようにするには、自己分析や企業研究が欠かせません。
自分がどのような人材なのか、そして企業がどのような人材を欲しているのかわかっていないと、思うような結果は残せないでしょう。
それぞれの対策について、より詳しく見ていきましょう。
自己分析
性格検査でマイナス評価を受けにくくするためには、自己分析が大切です。
企業が性格検査を実施するのは、応募者の性格と企業が求める人物像に大きなズレがないか確認する目的があります。
そのため、自分の性格と社風・求める人物像が合わない場合は、同業他社の別の企業を受けることでWEBテストの通過率を上げることも可能です。
テスト対策だけでなく入社してからの働きやすい会社を選ぶことにもつながるので、しっかり自己分析を進めておきましょう。
企業の特徴を捉えよう
企業の特徴を捉え、社風や働き方などの特徴を理解しておくことも大切です。
企業が求める人物像に、ある程度寄せた回答をしやすくなります。
嘘をつくのは良くありませんが、「違う」と答えると社風と合わないと評価されそうな設問を、「どちらかといえば違う」に回答するといった対策はできるでしょう。
また自分の性格の一部が社風と合わないと知っていれば、面接で性格の話題になってもフォローができます。
「こういう弱点はありますが、こうしたことに注意して仕事をしたい」など言い方で、その性格が大きな問題にならないことを伝えてください。
【WEBテスト対策】WEBテストの受験前の準備
最後に、WEBテストの受験前の準備について説明します。
会場に行かなくても大丈夫なWEBテストですが、ちょっとしたミスで受けられなくなったり、解答が送信できなくなったりすると非常にもったいないです。
重要事項をしっかり確認しておきましょう。
受験日を確認する
根本的に受験日を間違えてしまうと不合格になってしまうので、受験日をしっかり確認しておくことが重要です。
多くの企業が、WEBテストを実施する時期が近いため、複数の企業のテストを同じ日に受けるといったケースが出てきてもおかしくありません。
どの企業のテストを何時に受けるか、各企業のURLはどれかなど整理しておきましょう。
テストに関する案内のメールは、フォルダを作るなどしてわけておくのがおすすめです。
また、部屋でテストを受けている時間に邪魔が入らないよう対策しておきましょう。
問題を解く感覚を取り戻しておく
WEBテストについて、すでにさまざまな過去問を解いてきている人もいるでしょう。
そんな人は安心しきっているかもしれませんが、必ず事前に問題を解く感覚を取り戻しておいてください。
なぜなら、以前はスムーズに書けたのに、本番ではうまく書けなくなってしまっていることも珍しくないからです。
特に問題を解く練習をしてから時間が経過していればいるほど、その感覚は忘れかけているおそれがあります。
だからこそ、本番直前にもう一度その感覚を掴んでおいてください。
ちなみに、普段からできる対策方法として、いつも自然に目にすることになるニュースから数字が出てきた時に、それが何を意味しているのかを考えるクセもつけておくと良いでしょう。
これが適性検査の準備としてもっともおすすめです。
パソコン受験に慣れておく
WEBテストは文字通り、WEB上でおこなわれるテストになります。
つまり、誰もが必然的にパソコンを使って受験することになるのです。
そうなると、パソコンの基本的な操作ができるようになっておく必要があります。
例えば、テスト内容によっては、特徴的な回答方法が出てくることもあるでしょう。
そんな時に、何もわからずに挑んでしまうと、本当は答えられたはずの問題が解けなかったという事態に陥るおそれがあります。
だからこそ、本番で問題なく実力を出せるように、パソコン上での適性検査をきちんと体験して、操作に慣れておかなければいけません。
そうすれば、いざという時に焦ることなく、常に冷静な状態で受験に臨めるはずです。
テスト形式を確認する
WEBテストの案内にテストのURLが載っていれば、そのドメインでどのテストが出題されるか事前に確認できます。
テスト形式や所要時間などを確認し、どのような問題が出題されるか想定しておくようにしてください。
今まで自分が見たことのないURLの場合、ドメインを確認して事前に模擬テストを受けておくのがおすすめです。
初めての形式では、時間配分などがわからなかったり、何を問われているか確認するのに時間がかかったりして苦労することがあります。
そのため、経験済みの形式より成績が落ちてしまう可能性が高いです。
電卓を準備する
GABなどのテストでは、電卓の使用が認められています。
電卓を使える場合、大きな数字の計算をする必要があるなど手計算だと時間がかかる問題が出題される可能性が高いでしょう。
計算問題で時間をかけすぎると他の問題で時間が足りなくなるので、電卓を使ってしっかり時間の節約をしておきたいところです。
すぐ使えるように、受験前に電卓を手元に用意しておきましょう。
慣れているならスマートフォンの電卓機能でも構いませんが、より早く問題を解くために使いやすい電卓を1個購入しておくことをおすすめします。
通信環境を整える
多くの方は、WEBテストを自宅のインターネット回線を利用して受けることになるはずです。
そのため、通信環境が悪いと読み込みができなかったり、解答に時間がかかったりして損することも考えられます。
自宅のパソコンのマウス・キーボード・ヘッドフォンなどを、使いやすいものに変えて、使い慣れておくことも大切です。
ルーターの調子が悪いといった理由で回線切れになってしまう可能性が高いなら、学校など別の場所でWEBテストを受けることも検討しましょう。
テストセンターの場合は事前に性格検査を受験する
テストセンターとは、適性検査であるSPIにおける受験方法の一種です。
リクルートマネジメントソリューションズが会場に準備してあるパソコンを使って、受験する形になります。
また、基本的にテストセンターでの検査は、能力検査のみです。
そのため、拘束時間もかなり短めになっており、厳密には35分で終了します。
さらに1問ごとにも制限時間があるため、スピーディーに検査が進むのが特徴です。
性格検査については自宅で受講しなければいけませんので、勘違いしないようにしましょう。
ちなみに性格検査は、制限時間が30分になっています。
いずれにしても短めだといえるので、ゆっくりと考えて問題を解いている時間は、あまりないといえるでしょう。
【WEBテスト対策】困ったときの対処法
WEBテストを受ける際には、場合によってさまざまなトラブルが発生することも出てくるかもしれません。
そんな時には、どのように対処すれば良いのでしょうか。
これから3つのパターンを紹介しますので、同じような状況に遭った時は、ぜひこの内容を参考にした上で対処してみてください。
そうすれば、少しでもなんとかなる可能性が出てきます。
パソコンがフリーズしてしまった
WEBテストはパソコンを通じておこなうことになるため、状況によっては突然フリーズしてしまうケースもあるでしょう。
フリーズの原因にも色々ありますが、特によくあるのが連続クリックをしてしまうことです。
なかなか画面が切り替わらないことでついクリックをたくさんしてしまう人もいますが、不必要にクリックしすぎることによって画面が固まり、余計に前へ進まなくなってしまうおそれがあります。
そのため、余計なことはせず落ち着いて行動することが重要です。
もしどうしてもフリーズしてしまった場合は、一旦ヘルプデスクに問い合わせてみてください。連絡先は受験予約完了メールに書かれているはずですので、そこから問い合わせるだけでOKです。
時間内に回答ができなかった
WEBテストの問題は、それぞれ時間が定められているため、ゆっくり考えすぎると次に進んでしまいます。
そのため、回答する前に終わってしまうことも少なくありません。
だからこそ、普段からスピードも意識して問題を解く練習をしておいた方が良いでしょう。
もちろん、どこまで練習していたとしても、本番当日でうまくいかなくなることがあります。
そんな状況になってしまったとしても、落ち着いて次の問題を解くようにしてください。
人によってはすべての問題を解きたいと思うかもしれませんが、よほど自信がない場合は解けるものだけを優先的に取り組む方が、最終的に高い得点になる可能性があります。
受験期間を過ぎてしまった
WEBテストを本当は受けるつもりだったのに、うっかり受験期間を過ぎてから気づいてしまうケースもあるでしょう。
この場合は、残念ながら先攻対象外になってしまうと思っておいた方が良いです。
どうしても諦めがつかない場合は、ダメもとで企業に連絡を入れてみるのも良いかもしれません。
ただし、そこまでしても結果は変わらないことがほとんどなので、あまり過度な期待をしてはいけません。
とはいえ、状況次第では必ずしもお断りされるとは限らないのも事実です。
例えば、謝罪内容によっては再受験のチャンスが得られる可能性もあります。
そのため、何もせずに諦めてしまうくらいなら、少しの可能性にかけてみるのも良いでしょう。
【WEBテスト対策】対策が難しいと感じたら
WEBテストについて、人によってはなかなかうまく対策できずに、頭を抱えてしまうことがあるかもしれません。
そんな人にこそおすすめなのが、就活エージェントを利用する方法です。
就活エージェントでは、あなたの進捗状況に合わせて、就活のプロであるキャリアアドバイザーからアドバイスを受けられるのが大きなポイントです。
もちろんWEBテストに関する対策や相談も、就活エージェントを通じて行うことができます。
興味がある人は、ぜひ以下のボタンから実際に試してみてください。
まとめ
WEBテストにはSPI・玉手箱などさまざまな形式があり、問題に慣れておくことで正答率を高めたり解答にかける時間を減らしたりできる問題も多いです。
そのため、事前に参考書や問題集・アプリなどをやっておくとテストの通過率が上がります。
WEBテストを少しでも多く通過し、面接のチャンスを多く得ることが内定への近道です。
エントリーシートの準備を進めたり面接の練習をしたりすることも重要ですが、WEBテストの対策も怠らないようにしましょう。