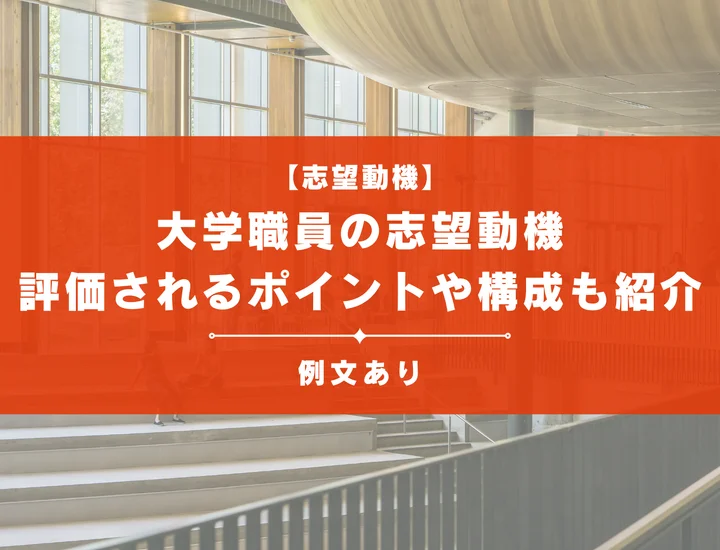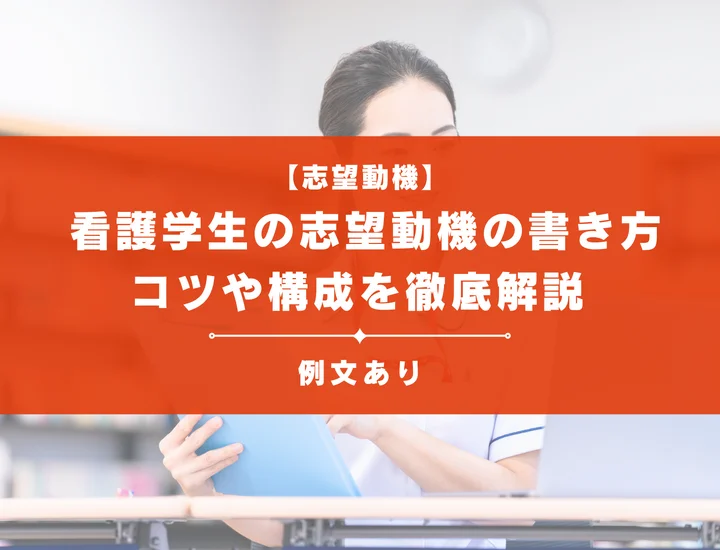- 大学職員の仕事内容
- 評価される志望動機を作成する方法
- 内容別の志望動機例文
- 大学職員に興味のある人
- 志望動機作成に困っている人
- 例文を参考にして志望動機を作成したい人
NEW!大学職員特化の志望動機AIツールで簡単に1分で作成
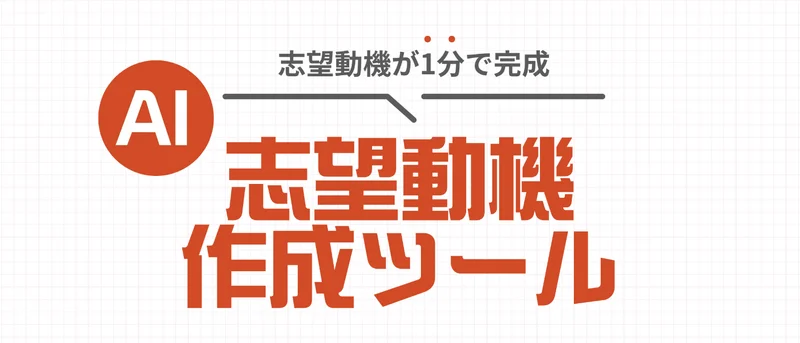
7つの質問で自分だけの志望動機を作成!
今すぐ作成(無料)
私は、教育を通じて社会に貢献できる大学職員という仕事に魅力を感じ、志望いたしました。特に貴学は、学生一人ひとりの主体性を尊重し、学びや成長を多角的に支援する姿勢に共感しています。社会の基盤を支える教育機関の一員として、学生の挑戦や成長を裏方から支えることにやりがいを感じています。
現在は営業のアルバイトを通じて、相手の立場で考える力や、丁寧かつ的確な対応力を培ってきました。これらの経験を活かし、事務職として学生や教職員のニーズに寄り添いながら、円滑な大学運営に貢献していきたいと考えています。
NEW!志望動機AIツールで簡単に1分で作成
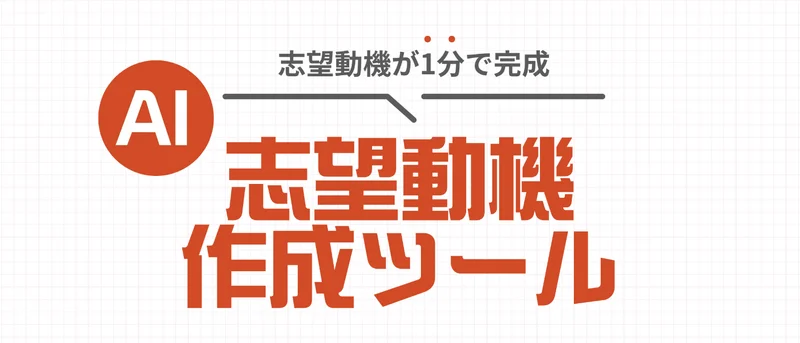
7つの質問で自分だけの志望動機を作成!
今すぐ作成(無料)
私は、教育を通じて社会に貢献できる大学職員という仕事に魅力を感じ、志望いたしました。特に貴学は、学生一人ひとりの主体性を尊重し、学びや成長を多角的に支援する姿勢に共感しています。社会の基盤を支える教育機関の一員として、学生の挑戦や成長を裏方から支えることにやりがいを感じています。
現在は営業のアルバイトを通じて、相手の立場で考える力や、丁寧かつ的確な対応力を培ってきました。これらの経験を活かし、事務職として学生や教職員のニーズに寄り添いながら、円滑な大学運営に貢献していきたいと考えています。
はじめに
大学職員という職種は、安定性や社会貢献性、教育・研究を支えるというやりがいから、近年ますます人気が高まっています。
その一方で、求人数に対して志望者数が多く、競争率は高くなる傾向があります。
そうした中で、採用担当者の目に留まるには、表面的な志望理由ではなく、その大学の理念や役割、職員としての職務内容を深く理解した上での志望動機が求められます。
この記事では、大学職員を志望する際に志望動機がなぜ重要なのか、採用側の視点も交えながら詳しく解説していきます。
志望動機が聞かれる理由
- 人柄や価値観が職場に合うかを見極めるため
- 本気度・熱意を測るため
- 入職後の活躍や定着を見越しているため
まず志望動機を聞かれる理由について考えてみましょう。
この理由はどのような企業でも、どのような大学を受ける場合にでも当てはまる要素です。
あなたが大学職員だけでなく、一般企業なども視野に入れている場合でも活用できる考え方であるため、ぜひ覚えておいてください。
人柄や価値観が職場に合うかを見極めるため
採用担当者が最初に注目するのは応募者の人柄・価値観です。
大学職員の仕事は学生や教職員とのコミュニケーションが多岐にわたるため、どのような価値観を持っているかが重要なポイントとなります。
大学の雰囲気や職場のチームワークに適合する人材であるかどうかを判断するため、志望時から応募者の考え方や行動の傾向を探ろうとします。
学生のサポートに対する情熱や責任感、他者との調和を重視する姿勢などが伝わると、大学の環境に適応する力があると判断してもらえることでしょう。
本気度・熱意を測るため
採用担当者が志望動機を聞く理由の1つに、応募者の入社意欲度を確認する目的があります。
大学職員の採用には多くの時間や費用がかかるため、採用した人材が早期に辞退したり退職したりすることは避けたいと考えています。
志望動機には応募者がどれほどその職場に魅力を感じ、具体的にどのような貢献を目指しているのかが反映されます。
志望動機において大学職員という仕事に対する深い理解が示されていると、安定性や福利厚生だけを理由に志望しているのではなく、本当にその職場に興味を持っていると判断してもらえます。
大学事務の仕事内容について具体的に触れ、学生支援や教育環境の整備にどのように携わりたいかについて述べることを心がけましょう。
入職後の活躍や定着を見越しているため
志望動機を聞くもう1つの理由は、応募者が入社後にどれだけ活躍できる可能性を秘めているかを確認するためです。
大学職員の業務は多岐にわたりますが、特に重要なのは学生や教職員との円滑なコミュニケーション、問題解決能力、そして主体的な行動力です。
志望動機ではこれらの能力がどのような経験を通じて培われたかを具体的に示すことが求められます。
志望動機では結果よりもその過程に注目することが大切です。
どのような課題に直面してそれをどのように乗り越えたかを詳細に説明することで、あなたの問題解決能力や思考の柔軟性も伝わります。
また、経験を通して学んだことがどのような職場で再現可能かを明確にすることも重要です。
業務改善への取り組みやチームワークの強化に自信があることを述べれば、採用担当者に前向きな印象を与えられるでしょう。
大学職員の主な業務内容
- 学生支援
- 研究支援
- 事務
- イベント企画・運営
- 入試・広報業務
- 総務・経理
大学職員の業務は、単なる「事務仕事」にとどまりません。
大学という教育・研究機関を支えるために、多岐にわたる分野で専門性と総合力が求められます。
学生対応、教員支援、学外との連携、経理・法務など、多面的な役割を担っており、組織全体の運営に欠かせない存在です。以下では、主な業務内容を分野ごとに詳しく解説します。
自分が就職した後、どのような仕事を任されるのかについてイメージしておくためにも確認してください。
学生支援
学生支援は大学職員の業務の中でも学生との直接的な関わりが多い、重要な役割です。
学生の入学から卒業、さらには就職に至るまでの様々な過程をサポートします。
履修登録や成績管理のサポート、奨学金の案内、キャリア支援センターでの就職活動のアドバイスなど多岐にわたるサポートを行います。
学生一人ひとりが抱える課題や目的に応じて柔軟に対応する力が必要です。
新入生が大学生活に適応できるようにガイダンスを企画し、履修相談や生活面のアドバイスを行うことも重要な仕事の1つです。
このような業務はただの手続きの案内だけでなく、学生の不安や疑問に寄り添う姿勢が求められます。
特に留学生や障害を持つ学生への対応ではより個別のサポートが求められるため、専門的な知識や柔軟な対応力も必要となります。
研究支援
研究支援は大学で行われる研究活動を円滑に進めるための重要な役割を担っています。
研究者が専門分野の研究に集中できるよう、様々な場面でのサポートを行うのが主な仕事です。
具体的には研究資金の調達支援や助成金の申請書類作成、研究費の予算管理、研究成果の発信などが含まれます。
助成金の申請では書類の作成や提出期限の管理、必要なデータの収集などを行います。
助成金の審査では内容の正確さや論理的な構成が重視されるため、細部にわたる確認作業が欠かせません。
また、研究費の管理では予算の適切な配分を行い、不正使用を防ぐための監査も求められます。
これにより研究活動が透明性を持ちながら進められるように支援するのです。
研究成果の発信も研究支援の一環であり、学内外の研究者や社会に向けて成果を広めるための活動を行います。
これにより研究者の成果が多くの人々に届き、大学の評価や社会的貢献度も向上します。
事務
事務は大学職員の業務の中核を担う分野で、大学全体の運営を支える役割を果たしています。
この業務には予算書や決算書の作成、施設や備品の管理、学内規定の作成、人事異動の手続きなどが含まれます。
これらの業務を通じて大学の日常業務が滞りなく進むようにサポートするのが仕事です。
予算書や決算書の作成では大学全体の収入と支出を正確に把握し、適切に計上する必要があります。
この業務ではミスが許されないため、細かいデータの確認や分析能力が必須です。
また、施設や備品の管理では学生や教職員が快適に過ごせる環境を整えるための維持管理を行います。
設備の老朽化やトラブルが発生した際には迅速に対応し、問題解決を図ります。
さらに、学内規定の作成や人事異動の手続きも重要な業務です。
規定の作成では大学の方針や法令を踏まえた上で適切な内容を整備する必要があります。
事務業務では正確性や迅速な対応力が求められる一方、幅広い業務内容に対応する柔軟性も必要です。
大学全体を支える役割として、責任感と計画性が欠かせません。
イベントの企画・運営
イベントの企画・運営は大学の魅力を発信し、学生や外部関係者との交流を促進するための重要な業務です。
入学式や卒業式、学園祭などの内部イベントから、オープンキャンパスや新学説明会など外部向けイベントまで幅広く担当します。
これらのイベントを成功させるためには、計画性と調整力が重要です。
オープンキャンパスでは高校生や保護者に大学の魅力を伝えるためのプログラムを企画する必要があります。
参加者が興味を持つ内容を考え、学内ツアーや模擬授業、在学生との座談会などを組み入れます。
また、イベント当日にはスタッフやボランティアとの連携を図り、スムーズな運営を実現することも大切です。
そして、内部イベントでは学生や教職員が主体的に参加できる環境を整えることが重要です。
卒業式では会場の設営やタイムスケジュールの調整、ゲスト対応などの業務を調整する必要があります。
イベントの企画・運営では計画通りに進まない場合でも代替案を用意し、円滑な運営を目指すことが求められるでしょう。
入試・広報業務
入試業務は、試験の準備、出願受付、成績処理、合格発表などが中心で、ミスの許されない正確さとスピードが求められます。
一方で、広報業務では、大学の魅力を外部に発信し、受験生や保護者に対しての情報提供、パンフレット制作、SNS・Web管理、メディア対応などを行います。
この分野では、ブランディングやマーケティング的な視点が求められ、大学の「顔」としての意識が必要です。
大学間競争が激化する中で、戦略的な情報発信の重要性は年々増しています。
総務・経理
総務部門では、人事労務管理、規程整備、学内ガバナンス、文書・備品管理、法務対応などを担当します。
一方、経理では予算編成、決算処理、会計監査対応、補助金・助成金の管理など、お金の流れを支える重要な役割を担います。
いずれも、制度や法律に関する正確な理解と運用が求められ、大学の安定的な運営の根幹を担っています。
民間企業での経理・人事経験があれば活かしやすい分野でもあります。
大学職員に向いている人
- 語学やITスキルがある人
- コミュニケーション能力が高い人
- 事務処理やスケジュール管理が得意な人
- 柔軟な対応力・協調性がある人
- 教育や地域への貢献意識がある人
続いて、大学職員に向いている人の特徴についても説明します。
以下の項目が多く当てはまる人は大学職員に向いている可能性が高いため、自信を持って選考に臨んで良いでしょう。
一方、当てはまる項目が少ない場合は、他の職種も検討するか、就活本番までに少しでも近づけるよう努力してみてください。
語学やITスキルがある人
グローバル化が進む現代の大学では、英語をはじめとした語学力や、情報処理能力の高い人材が強く求められています。
国際交流部門では、海外の大学との連携、留学生の受け入れ、英語での文書作成・対応が日常業務です。
TOEICや英検のスコアが求められるケースもあります。
また、学内では基幹システムやクラウドサービス、学生向けポータルなどの運用・保守も欠かせず、業務のIT化が進む中でExcelの関数レベルは当然、AccessやSQL、業務フロー設計の理解もあると重宝されます。
特にコロナ禍以降は、オンライン授業の支援やハイブリッドイベントの技術サポートなど、ITスキルの高い人材の存在感がさらに増しています。
コミュニケーション力がある人
大学職員は学生、教員、保護者、さらには地域社会の関係者とも接する機会が多い仕事です。
したがって、円滑な業務遂行のためには高いコミュニケーション力が欠かせません。
学生に対しては履修登録や奨学金制度、就職活動などについて適切に案内する必要があります。
一方で教員には研究支援や授業運営に関する情報提供を行います。
これらの場面では相手のニーズを的確に把握し、それに基づいた情報を提供する能力が求められます。
特に学生支援の場面では学生の悩みを引き出し、それに寄り添う姿勢が重要です。
進路相談では学生が自分の考えを話しやすい雰囲気を作りつつ、適切なアドバイスを提供することが求められます。
また、保護者からの問い合わせに対応する際には丁寧かつ誠実な対応が欠かせません。
こうした一つひとつのやり取りが大学全体の信頼度向上につながります。
細かい作業が得意な人
大学職員の業務には細かい作業が数多く含まれます。
履修手続きや奨学金の申請書類の確認、規定の改定、研究費の精算などが挙げられます。
これらの業務はいずれも正確性が求められるものであり、ミスが生じた場合には学生や教員に大きな不利益を与える可能性があります。
したがって、正確かつ丁寧に作業を進められる人が適しているのです。
これらの業務では細かいデータを扱うことが多いため、デジタルツールを活用する能力も求められます。
学生の成績データを管理するための表計算ソフトや専用システムを使いこなせなければなりません。
このような細かい作業を確実にこなすことで、大学全体の運営を円滑に進める役割を担うのが大学職員です。
スケジュール管理が上手な人
大学職員の業務は多岐にわたるため、スケジュール管理能力が非常に重要です。
1日の業務スケジュールを立てるだけでなく、長期的な計画を見据えて仕事を進める能力が求められます。
オープンキャンパスの準備を例に挙げると、数ヶ月前から企画を進め、当日に向けて細かい作業を順次進める必要があります。
このような業務を滞りなく進めるためには優れたスケジュール管理能力が欠かせません。
さらに、多くの人と協力しながら進める業務も多いため、相手の予定を考慮しながら調整を行う力も求められます。
教員や外部業者とのミーティングを設定する際には全員の都合を踏まえてスケジュールを組む必要があります。
これにより、業務が効率的に進むだけでなく、関係者との信頼関係も深まるのです。
また、突発的な業務が発生した場合にも柔軟にスケジュールを見直す力が必要です。
計画が変更された場合でも冷静に優先順位を見極め、限られた時間内で最適な対応を行う姿勢が求められます。
面倒見がいい人
大学職員は学生が快適に大学生活を送れるように環境を整える仕事です。
学生との接点が多いため、面倒見の良さが特に求められます。
履修手続きに迷う学生に対して丁寧に説明を行ったり、進路について相談を受けたりする場面は頻繁にあります。
これらの業務では学生の話をよく聞き、相手の立場に立った対応が必要です。
また、留学生や障害を持つ学生に対しては特にきめ細やかなサポートが求められます。
文化や言語の違いによる困難に寄り添い、生活面や学業面でのアドバイスを行う必要があるのです。
さらに、大学に来ることが難しい学生や悩みを抱える学生に対しては特別な支援制度を提案することなどもあります。
このような対応を通じて、学生が安心して学びを続けられる環境を提供することこそが大学職員の使命です。
大学職員を志望する際の注意点
- 異動がある可能性がある
- 就職倍率が高い可能性がある
- 少子化により競争が激化している
ここまで、大学職員の主な役割や向いている人の特徴などについて説明しました。
大学職員として働くことに興味を持ち、やる気が高まっている方も多いことでしょう。
しかし、大学職員として働くにあたってはデメリットや注意すべきポイントがいくつかあります。
ぜひ、以下の3点を踏まえた上で、自分が本当に大学職員を目指すのか検討してみてください。
異動がある可能性がある
大学職員を目指す際には異動の可能性について理解しておくことが重要です。
大学職員の業務範囲は広く、大学本部だけでなく、付属の幼稚園や初等部、中等部、高等部などに配属されるケースもあります。
また、キャンパスが複数存在する大学の場合、県外や遠方のキャンパスへの異動を求められることも多いです。
こうした異動は職員のキャリア形成の一環として行われる場合が多く、場合によっては拒否できないこともあります。
したがって、地元に留まりたい場合や、同居しているパートナーがいる場合など、異動があると生活や人生設計に影響が出る方は、あらかじめ自分が受ける大学に異動の可能性があるかについて調べておきましょう。
就職倍率が高い可能性がある
大学職員は非常に人気のある職業であるため、就職倍率が高い傾向があります。
働きやすい環境が整備されていることや、安定した雇用形態がその理由として挙げられます。
こうした魅力的な職場であるため、求人に対する応募者の数が多く、就職倍率が非常に高い大学も多いのです。
また、大学職員の離職率が比較的低く欠員が少ないことも倍率の高さに影響しています。
このような環境では志望動機や自己PRで他の応募者との差別化を図る必要があります。
大学職員としてどのように貢献できるかを具体的に示し、自分の強みを大学の業務にどう活かすかを具体例を交えて述べることが大切です。
また、学生支援や研究支援など大学職員の業務内容について深く理解していることを示すことも重要です。
倍率が高い大学を受ける場合は他の大学も視野に入れる、もしくは他の職種も検討するなど、落選した場合の第2、第3の選択肢を考えておきましょう。
少子化により競争が激化している
少子化による競争が激化していることも注意点の1つです。
生まれてくる子供の数が減少しているため、大学に入学する学生の数も減少傾向にあります。
このような中で大学職員として大学に貢献するためには大学の魅力をアピールするプロモーション能力が求められます。
つまり、大学の強みを社会に発信できる能力を持つ人材が求められているのです。
一昔前は「大学全入時代」と言われ、ほとんどの学生が大学に進学することが一般的でしたが、近年では学歴を重視しない企業も増えており、大学に進学しない若者が増えています。
そのような時代の中でも大学に入学するメリットを発信できる人材であることが、今後ますます重要になっていくでしょう。
評価される志望動機を作成するコツ
- 内定者の志望動機を参考にする
- 他の就活生と差別化をする
- なぜその業界を選んだのかを伝える
- なぜその大学が良いのかを伝える
続いて、評価される志望動機を作成するためのコツについても紹介します。
以下のコツを4つ踏まえた上で作成すれば、より質の高い志望動機が出来上がることでしょう。
ぜひ、それぞれのポイントを参考にしてみてください。
内定者の志望動機を参考にする
志望動機を作成する際は内定者の志望動機を参考にすることを推奨します。
内定者の志望動機ということは、つまり「合格点を与えられた文章」ということであり、何かしら参考になる部分が必ずあります。
特に大学職員のような職種では具体的な経験やエピソードを通じて自分がどのように貢献できるか明確に伝えることが求められるため、どのようにエピソードを話しているのかについて、注力しながら読んでみましょう。
これにより、あなたが目指している大学がどのような人物を求めているのか、どのような人物なら活躍しやすいのかなどのイメージがつきやすくなります。
近年では内定を獲得したエントリーシートが公開されているサービスも多いため、ぜひ、いくつかのサイトを活用して内定者の志望動機を確認してみてください。
他の就活生と差別化をする
他の就活生と差別化を図ることは採用担当者に自分を強く印象付けるために欠かせない対策です。
多くの応募者が同じような内容やエピソードを述べる中で、どうすれば自分だけが持つ独自性を伝えるかを考える必要があります。
そのためにはただ経験を羅列するだけでなく、その経験を通して得た教訓や価値観を具体的に掘り下げることが重要です。
アルバイトやボランティア活動、授業、インターン、サークルなどにおいて課題をどのように捉え、それを解決するためにどのような工夫をしたのかを伝えることで説得力が増します。
差別化をする際にはなぜそのような行動を取ったのかという部分は特に強調すると良いでしょう。
応募者がどのように考え、どのような価値観を持って行動したのかは、採用担当者が重視するポイントです。
また、自分の行動で得られた結果を述べるだけでなく、それがどのように大学職員としての業務に結びつくかを具体的に示すことで、他の応募者にさらに差をつけることができます。
なぜその業界を選んだのかを伝える
「なぜその業界を選んだのか」について伝えることも非常に重要な要素の1つです。
大学職員を目指す場合、なぜ大学職員という業界を選んだのか、その理由を明確に述べる必要があります。
教育や学生支援に対する強い関心や、自分の経験が大学運営に役立つと考えていることを具体的に示しましょう。
この理由を述べる際には「教育に興味があるから」「人と関わるのが好きだから」といった漠然とした表現ではなく、自分の経験や考え方と結びつけることが大切です。
学生時代に部活動やボランティアで後輩を指導した経験などを挙げて、それが教育や支援の分野で働く動機となったなどと説明すると説得力が増します。
また、教育業界の現状や課題についてリサーチを行い、それに対して自分がどのように貢献できるかを具体的に述べることで、さらに深い理解を示すことができるでしょう。
なぜその大学が良いのかを伝える
なぜその大学が良いのかについて伝えることも、非常に重要な要素の1つです。
採用担当者は応募者がその大学についてどれほど理解しているのか、またその大学でどのように貢献できるかを見極めようとします。
そのため、志望する大学の特徴や魅力を十分に調査し、それが自分の価値観や目指すキャリアにどのように結びついているのかを明確に伝える必要があります。
その大学が力を入れていることを調べ、その取り組みに自分の経験やスキルがどのように役立つかを述べると良いでしょう。
また、大学の理念やビジョンに共感したエピソードを盛り込むことで、自分がその大学にふさわしい人物であることをアピールできます。
さらに、志望する大学の課題や可能性についても触れると、より深い理解を示せます。
少子化による学生確保の難しさなどを挙げ、その課題に対して自分がどのように貢献できるかを具体的に述べるなど、工夫を凝らしましょう。
志望動機の構成
- 結論
- 根拠
- 今後の展望
志望動機の構成を理解しておけば、大学職員の選考を受ける時だけでなく、一般企業を受ける時にも活用できます。
この構成はどのような企業を受ける場合でも、どのような職種を目指す場合でも汎用的に活用できるものです。
ぜひこの記事でマスターして、どのような選考を受ける場合でもスムーズに志望動機を作成できるようにしましょう。
結論
冒頭部分ではなぜその大学や職種を志望しているのかを明確かつ簡潔に述べることが重要です。
採用担当者に最初の一文で興味を持ってもらうためには、具体性と説得力を持たせる必要があります。
ただし、この部分では過剰に長い説明を避け、簡潔で分かりやすい表現を心がけることが大切です。
志望理由が長すぎると、本題に入る前に相手が集中力を失ってしまう可能性があるからです。
自分がその大学で働きたい理由を、一言で理解させることがポイントです。
根拠
志望動機の中核をなす部分である根拠では、冒頭の結論を支える具体的な理由やエピソードを述べる必要があります。
この部分では自分の経験やスキルが志望する大学や職種にどのように関連しているかを具体的に示しましょう。
ただ「計画力があります」「チームワークを大切にしてきました」などと主張するだけでは不十分です。
これらを裏付ける具体的な行動や成果を提示することで、採用担当者に納得してもらうことが求められます。
例えば、学生時代に行ったプロジェクトの進行管理や目標達成の経験を挙げ、それがどのように計画力や問題解決能力など自分のアピールポイントの向上につながったのかを述べましょう。
また、チームでの活動によって自分がどの役割を果たしたのかを具体的に説明し、その経験を活かして大学ではどのように貢献できるのかを述べることも大切です。
この部分では自分の経験が志望する大学の業務内容や価値観とどのように一致しているかを具体的に示す必要があります。
誰が読んでも理解できるような、客観的かつ定量的な説明を用いて、分かりやすく表現しましょう。
今後の展望
志望動機の締めくくりとなる「今後の展望」では自分がその大学でどのように成長し、どのように貢献していきたいのかを具体的に述べる必要があります。
ここでは志望する大学での働き方やキャリアを明確に示し、採用後にどの役割を果たすことを目指しているのかを伝えることが重要です。
ただし、あまりにも大きすぎる目標や抽象的な表現は避け、自分のスキルや経験に基づいた現実的なビジョンを示すように心がけましょう。
また、この部分では自分の成長だけでなく、大学の成長に寄与する姿勢を示すことが重要です。
志望する大学のビジョンや課題について触れ、それに対して自分がどのように具体的に貢献できるかを述べることで、採用担当者に「この人はうちの研究をしっかり行っており、やる気が高く、貢献してくれる人物だ」と思ってもらえるはずです。
内容別の志望動機例文
ここまで紹介した内容を踏まえた上で、内容別の志望動機例文を紹介します。
以下の4つの例文を参考に、自分の志望動機に最も近いものを基にして作成してください。
地域に貢献したい
母校に恩返しがしたい
理念に共感をした
スキルを活かしたい
就活エージェントに相談する
ここまで、大学職員を目指す方向けに志望動機の作成方法や大学職員として働く上での注意点、おすすめの志望動機の構成例文などについて紹介してきました。
しかし、この記事を読んだだけで100点の志望動機を作成できるほど就職活動は簡単ではありません。
そこで、おすすめの対策は就活エージェントに相談することです。
弊社が提供している「ジョブコミット」というサービスでは自己PRや志望動機、ガクチカの添削を行うだけでなく、面接の練習相手やグループディスカッション、Webテスト対策のサポートなども行っています。
いずれのサービスも無料で利用できるため、気になる方はぜひ以下のリンクから登録してみてください。
まとめ
今回は大学職員を目指している方向けに志望動機の構成や例文、大学職員の業務内容や就職に当たっての注意点などについて詳しく紹介しました。
大学職員は多くの学生のサポートを行う、やりがいがある仕事であるため、倍率は高いです。
しかし、福利厚生なども充実していますし「やりがい」と「安定性」の両方を実現できる魅力的な仕事の1つであるため、ぜひ本記事で紹介した内容を踏まえた上で質の高い志望動機を提出し、内定を勝ち取ってください。