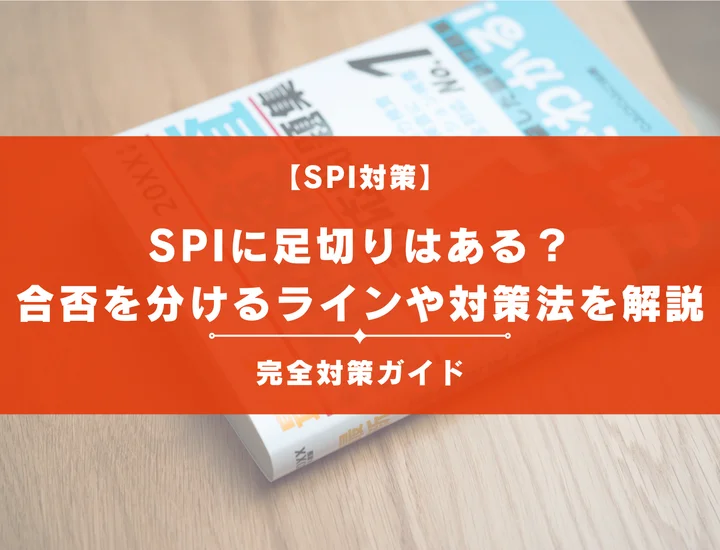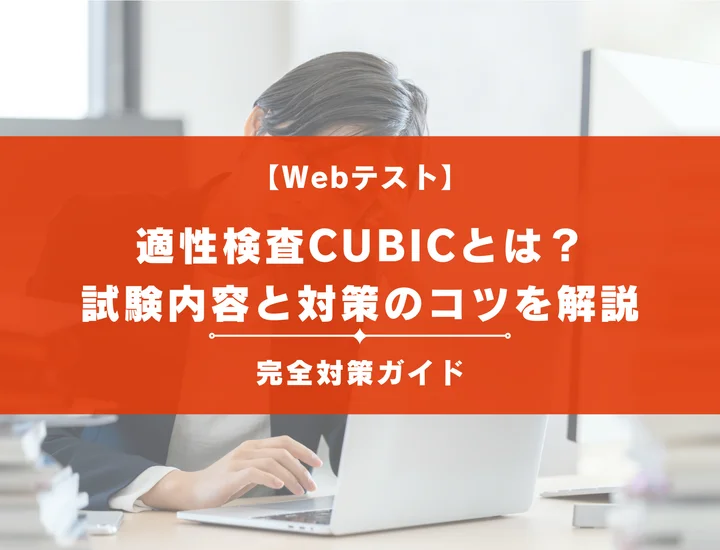明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
- シンクタンク業界の特徴
- シンクタンク業界の仕事内容
- シンクタンク業界に向いている人
- シンクタンク業界に興味のある人
- シンクタンク業界の業界研究がしたい人
- シンクタンク業界をより詳しく知りたい人
目次[目次を全て表示する]
シンクタンク業界とは
シンクタンク業界は政治や経済、社会、科学技術など様々な分野に関わる課題や問題に対して、政治提言や解決策を提示する研究機関のことであり、非常に重要な役割を担っています。
今回は大手企業7社の比較から仕事内容などについて詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
まずはシンクタンク業界のビジネスモデルや平均年収、就職難易度やコンサルとの違いなどについて詳しく紹介します。
基礎を理解して、シンクタンク業界がどのようなものであるか、理解を深めていきましょう。
・シンクタンクとは
・ビジネスモデル
・平均年収
・就職難易度
・シンクタンクとコンサルの違いは?
シンクタンクとは
シンクタンクとは政治や経済、社会問題、科学技術など幅広い分野にわたって専門的な調査研究を実施し、課題解決のための政策提言や具体的な解決策を提出する研究機関のことです。
官公庁や地方自治体、企業からの依頼を受けて業務を行いますが、時には自主的に研究を行い、社会に向けて情報を発信する場合もあります。
また、シンクタンクでは経済予測や市場動向、政策分析などを高度な専門知識を持つ研究員が分析し、客観的で信頼性の高い情報提供を行っているのも特徴です。
ビジネスモデル
シンクタンク業界のビジネスモデルは主にクライアントである観光地や地方自治体、民間企業などから案件を受注し、調査分析を行い、その成果物として報告書や政策提言書を納品することで対価を得る、というものです。
受注した案件ごとに契約が発生し、プロジェクト単位で仕事が進められることが特徴と言えます。
具体的な成果物としては経済予測、市場調査、社会調査、政策分析などが挙げられます。
また、定期的にレポートや情報提供を行い、継続的に契約を結ぶケースも多いです。
提供する情報や提言がクライアントの意思決定に大きく影響を与えるため、調査の質や情報の正確性、分析力の高さが評価されます。
平均年収
シンクタンク業界の平均年収は約635万円で、日本全体の平均年収である460万円を大きく上回る水準となっています。
シンクタンク業界の年収が高い理由は、業務の特性上、高度な専門性や豊富な知識、スキルが求められるからです。
調査・分析の仕事は高い専門知識と分析能力が必要であり、学歴や専門性を有した人物が多く求められます。
特に大手シンクタンクの場合は業績が安定しており、福利厚生や昇給制度も充実しているため、長く勤務すれば高い年収を得ることが可能です。
就職難易度
シンクタンク業界の就職難易度は非常に高いと言われています。
特に大手シンクタンクでは採用基準が非常に厳しく、学歴、専門的なスキル、分析力、論理的思考力など多様で高度な能力が求められるからです。
実際、主要なシンクタンクでは有名大学や大学院出身の学生が多く採用されており、大学で専門的な研究を行った人や、特定分野において深い知識を持つ人が選ばれる傾向にあります。
就活においては筆記試験、論文試験、面接のハードルも高いことが多く、入念な対策が求められます。
学生時代にあまり何かの分野に集中して学習をしたことがない方や、学歴に自信がない方は、しっかりと対策をしなければ内定を得ることは難しいでしょう。
シンクタンクとコンサルの違いは?
ここまでの説明で、シンクタンクとコンサルの違いがよくわからないと思っている人も多いでしょう。
そこで、2つの違いを説明します。
まず1つ目の違いは「顧客」です。
シンクタンクの主な顧客は企業も含まれるものの、観光地や地方自治体などの公的機関の方が多く、政策や公共性の高い課題を扱います。
コンサルは皆さんご存知のとおり「民間企業」がメインの顧客です。
2つ目の違いは提供する「商材の内容」です。
シンクタンクの主な商材は情報で、調査分析に基づく専門的な知識や客観的データを提供します。
一方、コンサルはコンサルティングファーム「人材」が商材であり、コンサルタント自身が企業の現場に入り込んで、具体的な課題解決や業務改善の役割を担います。
シンクタンク業界の種類
シンクタンク業界の種類についても詳しく紹介します。
大きく分けて「政府系シンクタンク」と「民間系シンクタンク」が存在し、それぞれクライアントとなる企業や機関などが異なります。
どのような業務を行っているのかについても詳しく紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
・政府系シンクタンク
・民間系シンクタンク
政府系シンクタンク
政府系シンクタンクとは国や地方自治体などの公的機関が直接設立している、または運営している研究機関のことです。
主な目的は行政の政策立案や実施をサポートするための調査分析を行うことで、研究内容は政治、経済、社会、科学技術、環境問題など多岐にわたります。
政府系シンクタンクの特徴は公的な視点から中立的かつ客観的な立場で研究を行い、政策判断に必要なデータや提言を提供することです。
また、行政と密接に連携しているため、政策形成に直接的な影響を及ぼすことも多く、社会全体に与えるインパクトが非常に大きいのも特徴であると言えるでしょう。
- 経済社会総合研究所(内閣府)
- 財務総合政策研究所(財務省)
- 防衛研究所(防衛省)
民間系シンクタンク
民間系シンクタンクは主に民間企業や財団法人、業界団体などによって設立・運営されている研究機関です。
公的な研究機関と異なり、営利目的で設立されている場合が多く、ビジネスの視点から具体的かつ実践的な課題解決に取り組んでいる点が大きな違いであると言えます。
民間企業が抱える経営戦略や市場調査、新規事業開発のための調査分析を中心に、企業の意思決定に必要な情報を提供します。
また、顧客は民間企業が中心となるため、迅速かつ実務的なアウトプットが求められる現場に近いところで働きたいと考える人にとって、魅力的な環境と言えるでしょう。
- 野村総合研究所(NRI)
- 三菱総合研究所(MRI)
- 日本総合研究所(JRI)
シンクタンク業界の大手企業7選
続いて、シンクタンク業界の大手企業を7つ紹介します。
中にはシンクタンク業界についてまだ業界研究が進んでいない方でも、名前を聞いたことがあるような大手企業もいくつか存在します。
それぞれどのような業務を行っているのか、何を強みとしているのかなどについて詳しく紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
・野村総合研究所(NRI)
・三菱総合研究所(MRI)
・日本総合研究所(JRI)
・みずほリサーチ&テクノロジーズ(MHRT)
・三菱UFJリサーチ&コンサルティン(MURC)
・大和総研(DIR)
・NTTデータ経営研究所
野村総合研究所(NRI)
野村総合研究所は野村證券から独立・分社化した2つの会社を源流とする、日本最大規模のシンクタンクです。
コンサルティングサービスとITソリューションサービスの2つの事業をメインとしています。
とりわけ、金融分野のITソリューションに力を入れているのが特徴です。
国内の大企業や観光庁などの顧客に対して、コンサルティングサービスやシステムインテグレーションを提供しています。
特に国内において予測分析・政策提言などによって問題発見から解決策を導く「ナビゲーション」と、その解決策を業務改革やシステムの設計・構築・運用によって実現する「ソリューション」の2軸に強みがあるのが大きな特徴であると言えます。
国内のコンサル会社としては随一の知名度と人気を誇る企業であると言えるでしょう。
三菱総合研究所(MRI)
三菱総合研究所は経済や企業の経営政策、公共、科学技術分野などの広い領域でシンクタンク系コンサルタントとしての役割を担っています。
総合力が魅力であり、医療や福祉、環境、情報通信はもちろんのこと、様々な分野のプロフェッショナル人材が課題を解決するため、非常に多くの顧客から高い評価を得ています。
連結子会社であり、ITソリューション分野を担う「三菱総研DCS」にも1,000人を超える情報処理技術者試験等合格者が在籍しているなど、人材の多さも大きな強みです。
日本総合研究所(JRI)
日本総合研究所は三井住友ファイナンシャルグループの総合情報サービス会社です。
シンクタンクはもちろん、コンサルティング、システムインテグレーションの3つの業務・事業を展開しているのが特徴であると言えます。
金融機関系のシンクタンクとして主に金融ビジネスに関する分析や研究をメインとしており、ITソリューション事業においてはグループ各社の情報システム企画・構築を担っています。
みずほリサーチ&テクノロジーズ(MHRT)
みずほリサーチ&テクノロジーズは幅広い調査や分析能力を備え、解決に向けた提言力やコンサルティング力、先端的なデジタルテクノロジーに関する知見やシステム設計力・実装力を強みとしています。
「いかなる時代にあっても変わることのない価値を創造し、お客さま、経済・社会に〈豊かな実り〉を提供する、かけがえのない存在であり続ける」ことを基本理念としており従来の金融の枠を超え、顧客の未来を共に考え、実現していくパートナーとなることを目的としている企業です。
経済社会を読み解くリサーチ力、半世紀以上にわたる政策立案・戦略策定支援の歴史を持つコンサルティング力と先端技術試験とIT実装力を結集して、社会や顧客の課題を解決することを目指している企業です。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC)
三菱UFJリサーチ&コンサルティングはコンサルティング、グローバル系サポート、政策提言、研究、提言、経済調査などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングです。
コンサルタントや研究員などのプロフェッショナルに囲まれた環境で、若手から多様な案件に数多く携われることが魅力と言えます。
また「コンサルティング&シンクタンク」という事業構造のもと、既存の枠組みにとらわれず、実行力の高いアプローチを行っているのが特徴です。
三菱UFJファイナンシャルグループに属する利点を活かして、年間約2,000件のプロジェクトを手掛けるなど、シンクタンク業界の中でも特に案件を安定的に獲得できている企業と言えます。
大和総研(DIR)
大和証券はリサーチ・コンサルティング・システム分野のスペシャリストが連携して、様々な顧客のニーズに応えてきた実績が特徴です。
シンクタンクとしての調査分析をもとに、質・量ともに充実した情報を発信しています。
また、大和証券グループ各社におけるシステムの先導役として、高品質で信頼性の高いシステムサービスを提供し、各社のビジネスを本格化させているのも特徴の1つです。
大和証券の公式サイトは採用ページが非常に充実しており「読むだけで業界・企業研究が進む」と言えるほどボリュームがありますから、時間があれば大和証券を目指していない方もぜひ一度チェックしてみてください。
NTTデータ経営研究所
NTTデータ経営研究所はITの知見を強みとした企業の戦略立案、組織経営改革、新規事業開発支援、さらには中央省庁、地方自治体の政策提言といった社会インフラ構築へ貢献しています。
政府や観光庁には社会課題に対して省庁を横断した政策提言を行い、官民一体でのバリューチェーン・エンジニアリングを行っています。
また、企業のビジネス・デジタルビジネス化を支援するビジネスプロデュースなども行っており、特にIoTやAIには力を入れているのも特徴です。
現場を熟知した提言を提示するビジネス事業開発推進と、社会政策を踏まえた具体的な事業開発に向けてコンサルティングの実施なども行っています。
シンクタンク業界の現状・課題
続いて、シンクタンク業界の現状や課題などについても詳しく紹介します。
現状について理解しておけば、面接で業界について聞かれた際にスムーズに答えられますし、自分がどのように貢献できるのかについて、自己PRでアピールできるようにもなります。
ぜひ、それぞれのポイントをしっかりと確認しておいてください。
・競争の激化
・需要の増加
・サービスの多様化
競争の激化
シンクタンク業界では現在、コンサルティングファームやIT企業、大学など従来とは異なる業界からの新規参入が相次ぎ、市場競争が激しくなっています。
特に近年ではデータ分析技術の発展やAI技術の高度化により、IT企業がビッグデータを活用した調査・分析サービスを提供し、シンクタンクの伝統的な領域に割って入ってきているのです。
また、コンサルファームも高い分析能力や迅速な対応力を武器に、観光地や企業向けの政策立案支援に積極的に参加しています。
このように多様なプレイヤーがライバルとして登場しているため、案件獲得の競争はますます激化していると言えます、
需要の増加
近年、社会情勢の複雑化やグローバル化の加速、技術革新が急速に進展する中で、シンクタンク業界に対する需要は増加傾向にあります。
特に、国際経済や環境問題、感染症など社会課題が広範化かつ複雑化するにつれて、専門的な知見に基づく調査分析や政策提言を求めるニーズが高まりつつあります。
また、企業においても競争環境が激しくなるにつれて、市場予測やリスク分析、新規事業開発支援など、客観的かつ信頼性の高い情報への需要が高まっているのも見逃せません。
さらに、デジタル化やAI活用など、先進的な技術を取り入れた調査分析を求める声も高まっており、これらの高度化したニーズに応えられるシンクタンクへの依頼が増えています。
サービスの多様化
シンクタンク業界では従来の調査研究や政策提言といったサービスに加えて、近年は提供するサービスが多様化しているのが特徴です。
企業や官公庁のニーズに応えるために、経営コンサルティングやITソリューションの提供、人材育成や教育研修サービスといった新たな領域に事業を拡大しています。
つまり「コンサル系の企業がシンクタンクに進出している」一方で「シンクタンクの企業も、コンサル業界に進出している」と言えるでしょう。
顧客が抱える課題や対応が複雑化していることや、迅速かつ実務的な成果を求めるニーズの高まり、つまりコンサル業界の重要性の高まりなどが理由として挙げられます。
シンクタンク業界の今後の動向
続いて、シンクタンク業界の今後の動向についても詳しく紹介します。
以下の3つは今後のシンクタンク業界について考える上で非常に重要な項目の1つであり、あなたのキャリアプランを考えるにあたっても重要な要素となってくるものの1つです。
ぜひ、シンクタンク業界が今後どのように進んでいくのかについて、理解を深めていきましょう。
・デジタル技術の活用
・専門性の多様化
・新たなビジネスモデルの模索
デジタル技術の活用
シンクタンク業界の今後の動向として最も注目されているのが、デジタル技術の活用です。
AI、ビッグデータ、IoT技術の活用が進むことが予想されています。
特にAIを活用してデータ分析の予測精度を向上させたり、膨大な情報を瞬時に処理できるビッグデータ技術の活用が重要です。
また、IoTによりリアルタイムに取得可能な大量のセンサーデータを分析することで、より精度の高い市場予測や政策提言も可能となりました。
従来のアナログ的な調査方法に加えて、こうした技術を積極的に取り入れることによって、調査研究の迅速化・高度化が実現され、企業や官公庁の意思決定プロセスに貢献できる可能性が高まっているのです。
専門性の多様化
シンクタンク業界では社会の課題が複雑化・多様化する中で、専門性をさらに広げていくことが求められています。
特に、気候変動に代表される環境問題やサイバーセキュリティ、地政学的リスク、感染症対策など、新たに社会的関心が高まっている分野への専門的な対応が重要視されています。
従来の経済や政策の分野に限らず、科学技術や環境、デジタルセキュリティなど幅広い分野における高度な知見が求められており、専門性の高い研究員の確保や外部機関との連携強化は不可欠です。
新たなビジネスモデルの模索
今後のシンクタンク業界では従来の受託研究やコンサルティングだけでなく、新たなビジネスモデルの模索が一層盛んになるでしょう。
調査や分析、データそのものを顧客に提供するサービスや、データ・情報を統合的に提供するプラットフォームの運営、専門知識を持つ人材を育成し、顧客企業に派遣・紹介する事業などが考えられます。
これらの新しいビジネスモデルを導入することで、顧客のニーズにより迅速かつ柔軟に対応できるようになり、収益の多様化にもつながるでしょう。
シンクタンク業界の職種・仕事内容
続いて、シンクタンク業界の職種や仕事内容などについて詳しく紹介します。
大きく分けて3つの職種が存在しており、それぞれがどのような業務を行うのかについて理解を深めておけば、企業研究もよりスムーズに就活対策が進むはずです。
ぜひ、それぞれの業務内容や自分がどの仕事をこなしたいかについて考えながら確認してみてください。
・研究・リサーチ
・コンサルティング
・ITソリューション
研究・リサーチ
シンクタンク業界の研究・リサーチ職は社会的・経済的・科学技術課題に対して、最新のデータや情報を収集し、これを詳細に分析するのが仕事です。
政府機関や民間企業などから依頼されたテーマに基づいて、市場動向や社会情勢、政策効果などに関するデータを集めて、統計的手法や定性的な分析を用いて、客観的な結論を導き出します。
また、過去の事例や類似ケースを調査して課題解決のための新たな視点を提供したり、将来のトレンド予測を行ったりすることもあります。
高い専門性と深い知識、分析力、論理的思考力が必要な職種です。
コンサルティング
コンサルティング業は顧客が抱える課題に対して具体的な解決策や戦略を提案することが主な仕事です。
経営戦略、事業戦略、組織改革など幅広い分野に対して、クライアントが抱える問題を詳細に分析し、実行可能で説得力のある解決方法を提示します。
シンクタンクのコンサルティングは調査や分析で得られた客観的なデータや情報を根拠に、経営者や担当者に対して提言や助言を行う点が特徴です。
特に、公共政策や社会インフラ整備に関連する案件では政策立案や制度改革に向けた具体的なアドバイスを提供し、実際に政策が動き出すまで伴走することもあります。
課題発見力・問題解決力に加えて、円滑にコミュニケーションを取れる能力も重要です。
ITソリューション
シンクタンク業界のITソリューション職は調査研究やコンサルティング業務を支える情報システムやIT環境の開発・構築を担当しています。
調査業務で扱う大量のデータを効率的に管理・分析できるシステムの開発や、AIやビッグデータ解析ツールなど先端技術を駆使した高度な分析環境の構築を行うのが仕事です。
また、クライアント向けにデータ可視化ツールや分析結果を迅速に提供するプラットフォームの構築など、デジタル技術を活用した新たなソリューションの提案・導入も重要な業務です。
技術的な専門性だけでなく、調査研究やコンサルティング業務への深い理解が求められ、シンクタンク業務に最適なシステムを設計する能力が求められます。
シンクタンク業界で働く魅力・やりがい
続いて、シンクタンク業界で働く魅力・やりがいについて詳しく紹介します。
魅力とやりがいについて理解を深めておけば、就活の軸や志望動機の回答のクオリティを高められるだけでなく、就活全体のモチベーションも高まるでしょう。
就活は気が重くなりがちなものであるため、少しでもモチベーションを保って進めるためにも、ぜひそれぞれ参考にしてみてください。
・多様な分野の知識が身につく
・社会的影響力が大きい
・幅広いキャリアを歩める
多様な分野の知識が身に就く
シンクタンク業界で働く最も大きな魅力の1つは、多様な分野の知識を幅広く習得できることです。
シンクタンクが扱うテーマは経済・金融だけでなく、環境・エネルギー、IT、医療、社会福祉など社会全般にわたり、多岐に及びます。
1つの分野に特化するだけでなく、異なる業界や専門領域を横断的に研究・分析することも珍しくありません。
そのため、自分が専門としている分野以外でも、プロジェクトを通じて知見を得られることが多いです。
社会的影響力が大きい
社会的な影響力の大きさも、シンクタンク業界で働くやりがいの1つです。
シンクタンクは観光庁や大企業の政策立案や意思決定に深く関与する機会が多いため、自分が携わった調査や提言が実際の社会政策や企業の戦略として実行されることが多いです。
自分の仕事が社会全体に対して直接的に影響を与えることになり、大きな達成感とやりがいを感じられるでしょう。
また、シンクタンクの調査分析には中立性と信頼性が求められるため、社会の様々な課題に対して中立的な立場で取り組み、広く社会に役立つことを実感できます。
幅広いキャリアを歩める
将来的に幅広いキャリアパスが開かれている点も、シンクタンク業界の魅力と言えます。
シンクタンクの業務は専門的な調査・分析スキルや政策立案能力、論理的思考力、コミュニケーション能力など、様々な能力を総合的に高めることが可能です。
想像にたやすいように、これらのスキルは他の業界でも非常に評価が高く、将来的に政府機関、国際機関、コンサルティングファーム、企業の経営戦略部門など、幅広い分野へのキャリアチェンジ・ステップアップを可能にします。
シンクタンク業界に向いている人の特徴
続いて、シンクタンク業界に向いている人の特徴についても紹介します。
以下の3つの項目のうち、自分はいくつ当てはまっているかについて考えてみてください。
当てはまっている場合は自信を持って、2個や3個当てはまっている場合は自信を持ってシンクタンク業界を目指しても良いでしょう。
1つ、もしくは0個の場合は、他の業界も選択肢に入れるか、それぞれ就活を進めながら少しでも近づけるように取り組んでいってください。
・学習意欲がある人
・論理的思考力がある人
・コミュニケーション力がある人
学習意欲がある人
シンクタンク業界に向いている人の特徴として、まず学習意欲が高いことが挙げられます。
シンクタンクでの仕事は、ここまでの説明を読んでわかるように、専門性の高い知識が求められるだけでなく、経済・社会・環境・技術など幅広い分野に対する最新情報を追い続ける必要があります。
特に現代社会は変化が激しく、新しい課題が次々と登場するため、自ら積極的に情報収集し、学び続けられる姿勢が重要です。
業務内容はプロジェクトごとに異なり、新しいテーマに触れる機会が多くなるため、自分の専門領域だけでなく、関連分野・新しい分野に対しても興味を持ち、知識やスキルを吸収できる人に向いていると言えるでしょう。
論理的思考力がある人
もう1つ重要な要素として、論理的思考力が高いことが挙げられます。
シンクタンクの仕事は複雑で高度な社会課題や企業の経営課題を扱うため、問題の本質を的確に把握し、解決策を論理的に導き出す能力が求められます。
また、調査や分析を行う上でも、集めた膨大なデータや情報を管理・整理し、客観的かつ合理的な結論を導き出すために、論理的思考力は必須のスキルです。
さらに、クライアントに調査結果や提言を説明する際には自分の考えや分析、データに基づく結果を説得力をもって説明することが大切です。
そのため、物事を整理して考える習慣や、原因と結果の関係性を理解し、筋道を立てて説明できる能力が求められると言えるでしょう。
コミュニケーション力がある人
コミュニケーション能力が高いことはシンクタンク業界において必須の要素です。
シンクタンクの仕事は個人で完結するものではなく、ほとんどの場合、チーム単位で取り組むため、円滑なコミュニケーションが求められます。
自分が調査・分析して導き出した解決策をチームのメンバーに伝え、チームとしての結論を出す際には、自分の考えを相手に理解してもらうことが不可欠です。
また、官公庁や企業などのクライアントに対してプレゼンテーションや提案を行う際にも、自分たちの調査結果や提言をわかりやすく端的に伝える能力が求められます。
専門的な内容を相手の知識量に合わせて簡潔かつ明確に伝え、相手の意見や疑問を的確に理解し、双方向のコミュニケーションをとれる人物が求められるのです。
シンクタンク業界に行くためにすべきこと
続いて、シンクタンク業界の内定を獲得するためにはどのような対策をしなければならないのかについても詳しく紹介します。
以下の4つの対策はシンクタンク業界はもちろん、どのような業界を目指す方にとっても就活において非常に重要な対策であるため、ぜひ可能であれば3つすべてに力を入れて取り組んでみてください。
・業界・企業研究をする
・インターンシップに参加する
・OB/OG訪問をする
業界・企業研究をする
まず行うべきは業界・企業研究です。
シンクタンクといっても、官公庁を主なクライアントとして政策提言を中心に行う企業もあれば、民間企業を対象にコンサルティングや市場調査を得意とする企業もあります。
また、金融機関系や商社系など、母体企業の特性が色濃く反映されることも多く、それぞれ社風や働き方が異なります。
そのため、シンクタンク業界全体の理解を深めた上で、自分がどのような分野や業務に興味があるかを明確にしましょう。
また、企業ごとの得意分野や実績、主要な案件などを調べることで、その企業の強みや特徴をより理解しやすくなります。
インターンシップに参加する
就活対策として最もおすすめなものの1つが、インターンの参加です。
実際の調査業務やコンサルティング業務を体験できるため、企業や業界の理解を深められます。
また、インターネットや説明会では得られない、その会社の雰囲気や仕事内容の細かい部分について直接知ることも可能です。
さらに、現役の研究員やコンサルタントと交流できるため、求められるスキルや働き方について具体的に理解できますし、自分がその環境に馴染んで働いていけるかどうかも検討できます。
インターン経験は志望動機を面接で活かせる場合も多くあり、インターンに参加した人が選考で優遇されることもあるため、ぜひ参加しましょう。
OB/OG訪問をする
OB/OG訪問も、ぜひ行っておきたい対策の1つです。
実際に現場で働く社員から、具体的な仕事内容や社風、求められるスキル、業界の課題など、インターネットや説明会だけでは得られない貴重な情報を聞くことができます。
また、入社後のギャップ、働きがいや業務についてもリアルな声を直接聞けるため、自分が本当にその企業にマッチしているかどうかの判断材料も得られます。
まず公式サイトなどで情報をまとめ、不明点や生の声を聞きたい点をメモして、OB/OG訪問に取り組みましょう。
適職診断ツールを用いよう
ここまでシンクタンク業界について詳しく紹介してきましたが、自分が本当にその業界に向いているのか、自分が就職したとしてどんな強みを活かせるのかわからないという方も多いでしょう。
そこでおすすめなのは、適職診断ツールを活用することです。
弊社が提供している診断ツールでは、52個の質問にLINEで答えるだけで、あなたの強みや向いている業界・職種などが明確になります。
完全無料で利用できるため、気になる方は以下のリンクから登録してみてください。
就活エージェントに相談しよう
「シンクタンク業界が自分に合っているのか不安」、「シンクタンク業界に行くには何をすべきなのかわからない」という悩みは多くの就活生が抱えています。
そんなときは、就活のプロに相談してみてはいかがですか?
どのような準備をすれば良いかの的確なアドバイスや、書類・一次選考免除の特別選考ルートへの案内も可能です。
気になった方は、ぜひ下のリンクからチェックしてみてください!
おわり
この記事ではシンクタンク業界について詳しく紹介しつつ、どのような仕事があるのか、どのような魅力があり、どのような人が向いているかなどについて詳しく紹介しました。
シンクタンク業界は非常に重要な役割を担っており、責任が重大ではありますが、その分、やりがいも感じられる仕事です。
ぜひ、この記事で魅力を感じた方はそれぞれの対策を入念に行い、理想の企業への就職を叶えてください。