明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・面接で「最近、気になるニュースは?」と聞かれる理由
・医療業界のトレンド・ニュース
・ニュースについて述べる際の構成と例文
・医療業界を目指している人
・ニュースを普段はチェックしない人
・面接の対策を入念に行いたい人
はじめに
医療業界を志望している方の中で、医療業界の最近の動向や知識が不足していて心配!そんな学生さんもいらっしゃるかと思います。
最近のニュースを知っておくことで面接や選考時に正しい知識で臨むことができますし、根拠のある志望動機を作成することもできるかと思います。
そこで今回は「最近のニュースについて聞かれる理由」「どのようにニュースの題材を選べば良いか」などについて詳しく紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
【医療業界の最近のニュース】就活で最近気になるニュースはよく聞かれるの?
結論として、就活で最近気になるニュースについてはよく聞かれます。
医療業界の面接も例外ではなく、ニュースの動向をチェックしているか、うまく答えられるかなどを確認されることが多いです。
志望動機や自己PRのように100%聞かれる質問ではありませんが、それでも面接の中では聞かれる可能性が高い項目と言えます。
ぜひ本記事を活用して、うまく答えられるようになっておきましょう。
【医療業界の最近のニュース】就活で最近のニュースが聞かれる理由
就活において、最近のニュースについて聞かれる理由は何なのでしょうか。
理由を知ることで、納得できるのはもちろんのこと、より面接官の意図に沿った回答を提供できるようになります。
相手が何を知りたいと考えているのか理解した上で、回答を作成しましょう。
情報感度の高さを知るため
面接官が最近のニュースについて質問してくる理由の1つとして、候補者が社会の動向や業界のトレンドにどれだけ敏感かを確認することが挙げられます。
ビジネスの世界では日々新しい情報が飛び交い、それに応じた迅速な対応が求められます。
そのため、企業は入社後に情報を的確に収集し、活用できる人材を求めているのです。
ニュースを常にチェックしているかどうかは知識量だけでなく、候補者の情報収集力や問題意識の高さを示す指標ともなります。
学生の価値観や考え方を知るため
面接官がニュースについて尋ねるもう1つの理由として、候補者の価値観や思考プロセスを知ることが挙げられます。
社会の出来事に対してどのような意見を持ち、それをどのように整理するのかを確認することで、その人の人となりや仕事への適性を判断しようとしています。
同じニュースを題材にしても、人によって着目するポイントや解釈は千差万別です。
面接官はこうした違いを通じて、候補者がどのような価値観を持ち、どのような視点で物事を考えるのかを把握しようとしているのです。
木下恵利

自分の志望する企業にマッチした人材がどんな価値観なのかあらかじめ知っておくと有利に選考を進められるよ。
イレギュラーな質問への対応力を知るため
候補者の対応力を確認する目的で、こうしたイレギュラーな質問をしてくる面接官もいます。
志望動機や自己PRと異なり、100%聞かれる質問ではないため、準備をしてこない就活生もいます。
準備をしてこなかった質問への回答にはその人の本質や、いわゆる「素」の部分が出ることが多いため、質問する面接官が多いのです。
就職後の仕事において、想定外の事態に対処する場面は少なからずあります。
特にクライアント対応やプロジェクトの進行は計画通りに進まないことが日常茶飯事です。
そのため、面接官はイレギュラーな質問を通じて判断力や対応力を確認しています。
木下恵利

イレギュラーなことが起きても冷静に対応するのがポイント。模擬面接で万全に対策しよう。
【医療業界の最近のニュース】就活で聞かれる最近のニュースの選び方
就活で聞かれる最近のニュースについて、どのように選べば良いのかについて詳しく紹介します。
どのような媒体を活用し、いつの時期のニュースを選び、どのように意見を付け加えれば良いのかについて詳しく紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
①信頼できる情報源を利用する
最も大切なことは、信頼できる情報源を活用することです。
情報の正確性が担保されているニュースをもとに選ぶことで、面接官に対して説得力のある受け答えができます。
新聞、テレビ、ラジオ、書籍、Webサイト、ニュースアプリなどが代表的な情報源です。
特に日経新聞や朝日新聞、NHKなどの大手メディアは事実確認を徹底しているため、信頼性が高い情報を提供しています。
一方、SNSや個人ブログで発信されたニュースは事実が保証されていなかったり、誤った情報が含まれていたりする可能性があるため、注意が必要です。
信頼性の低い情報元を選ぶと「誤情報やデマが多いこの時代に、精査できないのは問題だな...」と思われてしまう可能性があるため、必ず、以下で紹介する媒体を活用するようにしてください。
新聞
新聞は最も詳細で信頼性の高い情報源の1つであるため、就活で話すニュースを選ぶ際には非常におすすめです。
新聞社は取材を通じて正確な情報を提供することを使命としており、誤報を防ぐためのチェック体制が整っています。
新聞をメインに情報収集をすれば、インターネット上の不確かな情報よりも信頼性が高く、企業の面接官に対しても説得力のある話ができるでしょう。
新聞の中でも、日経新聞が特におすすめで、経済、企業、各業界の動向を詳しく報じており、ビジネスパーソン向けの分析記事も充実しています。
電子版もあり、スマートフォンやパソコンで手軽に最新のニュースをチェックできるため、忙しい皆さんでも効率的に情報収集が可能です。
テレビ
テレビのニュース番組は映像を通して視覚的に情報を得られるため、ニュースの内容がより分かりやすいというメリットがあります。
特に、災害や国際情勢などの現場の映像が含まれるニュースは文字だけでは伝わりにくい情報を直感的に理解することが可能です。
特にNHKは客観的な報道を特徴としており、政治・経済・国際情勢についてバランスの取れた情報を得ることができます。
テレビのニュースはリアルタイムで流れるため、最新の話題を短時間で把握することも可能です。
普段あまり活字を読む習慣がない方は、まずテレビから情報を仕入れてみてください。
ラジオ
ラジオは移動中や作業中でもニュースを聞けるため、忙しい方にとって非常に便利な情報源です。
特に通学やアルバイトの行き帰りの時間を有効活用しながら、時事問題についての理解を深められます。
特にNHKラジオは政治・経済・国際ニュースを網羅しており、信頼性が高いです。
もちろん、民放のラジオでも経済や社会問題を専門家が解説することがあるため、お気に入りの局があれば、そちらを活用しても構いません。
さらに、スマートフォンアプリ「radiko」を活用すれば、リアルタイムの放送だけでなく、過去の放送を聞くこともできるため、自分の好きなタイミングで情報を仕入れられるのもメリットです。
書籍
書籍は特定のニュースや社会問題についてより深く学ぶ際におすすめな情報源です。
新聞やテレビのニュースが最新情報を素早く得るのに適していますが、背景や歴史的な経緯を詳しく知りたい場合には書籍を活用することを推奨します。
経済やビジネスについての理解を深めたい方は「日経文庫シリーズ」などを活用すると良いでしょう。
また、医療やテクノロジー分野については信頼できる専門家が執筆した解説書を読めば、より専門的な知識を深めることができるはずです。
ただし、書籍は発行時点の情報が元になっているため、なるべく最近、可能であれば1年以内に出版されたものを選ぶようにしましょう。
Webサイト
Webサイトは最新のニュースを素早くチェックできる非常に便利な情報源の1つです。
新聞やテレビと異なり、インターネットにアクセスすればいつでも最新の情報を入手できるため、忙しい方にとって欠かせないツールであると言えます。
ただし、インターネット上には誤情報やフェイクニュースも多いため、情報の出典をしっかり確認することが重要です。
特に、SNSで話題になっているニュースや個人ブログだけに掲載されているニュースはデマである可能性があるため、必ず公式のニュースサイトで確認するように心がけてください。
いくら面接官の興味を惹くようなニュースであったとしても、正しくなければ意味がありません。
ニュースアプリ
ニュースアプリはスマートフォンで手軽に最新のニュースをチェックできるため、就活生の方に非常に便利なツールです。
基本的に無料で利用でき、プッシュ通知を設定すれば重要なニュースをリアルタイムで受け取れます。
特におすすめのニュースアプリは「SmartNews」と「NewsPicks」です。
SmartNewsは3000以上のメディアの記事を集約しており、政治・経済・国際ニュースなど幅広くカバーしています。
NewsPicksも経済・ビジネス分野を中心に様々なニュースを配信しており、業界の専門家や経営者のコメントを読むことができるため、ニュースへの理解を深めるのに役立ちます。
②1年以内のニュースに絞る
就活で話題にするニュースは1年以内の、最新のものであることが望ましいです。
古いニュースでは「情報感度が低い」と思われる可能性があります。
また、その話題に続報があり、すでに新事実が発覚していたり、新しい技術が発明されていたりして「古い」もしくは「誤った知識」として認識されていることもあるでしょう。
特に、経済・政治・テクノロジーなどの分野を選ぶ場合、情報が日々変化しているため、最新の情報を取り上げることが重要です。
医療業界を目指す方は最新の医療技術の進展や新型感染症対策の動向などのニュースを選ぶと、業界への関心が高いことを示せるでしょう。
③自分が感じたことを加える
ニュースを選ぶ際にはただ事実を述べるだけでなく、自分がそのニュースに対してどのように感じたのか、どのような意見を持ったのかを加えることも心がけてください。
面接官は候補者がニュースをどのように解釈し、そこから何を学び、自分の考えを持っているかを見極めようとしています。
そのため、ニュースを話す際には「なぜそのニュースに関心を持ったのか」「このニュースは自分の志望業界や将来の仕事にどう関係するのか」などを整理しておくと良いでしょう。
ただニュースをまとめるだけなら誰にでもできますし、候補者らしさが伝わってこないため、面接官は「オリジナルの意見をぶつけてほしい」と願っています。
【医療業界の最近のニュース】 最新のニュースを聞かれた時の答え方
続いて、最近のニュースについて聞かれた時の答え方についても紹介します。
この答え方とはつまり回答のおすすめの構成のことです。
医療業界のニュースについて答えるときはもちろんのこと、別の業界のニュースについて話すときにも活用できる構成と言えます。
医療業界を志望している方はもちろんのこと、他の業界を併願している方も、ぜひこの記事で頭の中に叩き込んでしまってください。
ニュースの概要を伝える
面接でニュースを話す際は、まずその概要を簡潔に説明することが大切です。
聞き手がそのニュースを知らない可能性もあるため、誰でも理解できるように噛み砕いて伝えることを意識しましょう。
具体的には「いつ・どこで・何が起きたのか」を明確にすることで、話の軸がブレずに伝わります。
「今年○月に○○という新たな規制が導入されました。」
といったように、要点を押さえながら話すと聞き手も非常に理解しやすくなるはずです。
また、余計な情報を詰め込みすぎると要点がぼやけてしまうため、最も重要なポイントを選んで話すことを心がけてください。
興味を抱いた理由を伝える
次に、なぜそのニュースを選んだのか、自分の関心とどのように結びついているのかを伝えてください。
面接官はそのニュースの内容を知りたいのではなく、候補者がどのような視点を持っているのかを確認したいと考えています。
そこで「なぜこのニュースが気になったのか」を明確にすることで、より説得力のある話し方が可能です。
医療業界を目指す人の場合、
「医療のDXが進むというニュースに興味を持ちました。これからの医療現場ではIT技術が不可欠だと感じたからです。」
といった形で、自分の志望業界や価値観と結びつけて話すと、印象に残りやすくなります。
ただし、表面的な理由だけでなく、自分自身の経験や考えと関連付けることが大切です。
自分の考え・意見を伝える
最後に、そのニュースについて自分の意見を述べて話を締めるようにしましょう。
ただ概要を説明するだけでは「ニュースを知っているだけ」という印象を与えてしまいます。
そのニュースをどう捉え、どう考えたかを伝え、思考力や分析力をアピールしましょう。
「医療DXの推進は業界全体としてプラスの影響があると思いますが、高齢者やデジタルに不慣れな人への対応が課題だと感じました」のように、自分なりの視点を加えると、より深みのある回答になります。
面接官はあなたの思考プロセスや論理的な考え方を見ているため、単なる感想を述べるのではなく「なぜそう思ったのか」を明確にすると説得力が増すでしょう。
【医療業界の最近のニュース】 医療業界の最近のニュースの例
医療業界の最近のニュースとその回答の例文を紹介します。
先ほど紹介したおすすめの構成になぞらえて作成しているため、どのように回答すれば良いかイメージが湧くはずです。
特に「自分がどのように感じたか」について答えることがポイントであるため、最後の部分に、特に注目して読んでみてください。
透析腎がん発症の仕組み解明 近位尿細管の増殖起点 国立センターなど
子育て世帯に応援手当 1人2万円来春支給 こども家庭庁
再生医療細胞点滴に試薬 提供計画に不適合 厚労省に報告 院長体感面での工夫 東京
がん5年生存率部位で格差 悪性リンパ腫などで改善傾向 国立センター
生活保護2.5%引き下げ案了承 全額支給案も併記 厚労省専門委
【医療業界の最近のニュース】医療業界の現状
医療業界の現状について、理解を深めておきましょう。
最近、医療業界ではどのようなことが課題であり、どのような対策などが取られているのかについて理解しておくことで、面接でより深い回答ができるようになります。
ニュースだけでなく、最近の医療業界について意見を問われることもあるため、ぜひ確認しておいてください。
高齢化と医療需要の増加
日本では高齢化が急速に進行しており、それに伴い、医療サービスの需要も年々増加しています。
総務省の統計によると、65歳以上の高齢者の割合はすでに全人口の3割近くを占めており、今後も増加が続く見込みです。
高齢者は慢性的に疾患を抱えることが多く、糖尿病や高血圧、認知症といった疾患への対応が求められています。
そのため、病院や介護施設の負担が増え、医療費の増大も大きな社会問題となっているのです。
このような背景から医療の効率化が求められており、遠隔医療やAIを活用した診断支援システムなどの導入も進んでいます。
オンライン診療の拡充により、通院が困難な高齢者でも医療サービスを受けやすくなるメリットが期待されています。
医療従事者の不足
日本の医療業界では医師、看護師、介護職員など医療従事者の不足が深刻な課題となっています。
特に地方の医療機関では都市部と比べて人材が集まりにくく、病院や診療所の運営が厳しくなっているのです。
医師の働き方改革も進められていますが、長時間労働が常態化している現場も多く、離職率の高さが問題視されています。
また、新型コロナウイルスの流行時には医療従事者の負担がさらに増大し、一部の病院で通常の診療が困難になるという事態も発生しました。
こうした状況に対応するために、外国人医療従事者の受け入れ拡大やAI、ロボット技術の活用による業務負担の軽減が模索されていますが、根本的に解決には至っておらず、まだまだ人材不足は続くと考えられています。
医療制度とアクセス
日本の医療制度は国民皆保険制度を基盤としており、全ての国民が平等に医療サービスを受けられるように設計されています。
この制度により誰もが比較的安価な負担で医療を受けることができる一方で、財政的な持続可能性が課題です。
また、都市部と地方では医療へのアクセスに格差があり、特に過疎地域では医師や病院の数が不足していることが問題視されており、この解決策として遠隔医療の導入が進んでいます。
今後、デジタル技術を活用した医療サービスの普及とともに、医療の質とアクセスの向上をどのように実現していくかが重要な課題となっています。
【医療業界の最近のニュース】就活生が知っておくべき医療業界の職種
続いて、医療業界の主な職種についても紹介します。
いずれも名前は聞いたことがあるかもしれませんが、自分が目指している職種以外はどのような業務を行うのか、明確になっていない方も多いはずです。
しかし、医療業界は皆さんご存知の通り、それぞれの職種がお互いに協力しながら仕事をこなすため、理解しておくとよりスムーズに就活や仕事が進みます。
就活の対策のためにも、就職後にスムーズに働くためにも、参考にしてください。
看護師
看護師は患者の健康管理や治療の補助を行う医療従事者です。
病院や診療所、介護施設など幅広い現場で働き、医師の指示に従って点滴、採血、投薬といった医療処置を行うのが主な仕事であると言えるでしょう。
また、入院患者の身の回りの世話や手術後の回復支援なども担当し、患者が安心して治療を受けられるようにサポートすることも求められます。
患者や家族への精神的なケアも重要な1つです。
近年では高齢化に伴う在宅医療の需要が高まりつつあり、訪問看護の分野でも活躍の場が広がっています。
感染症対策や救急医療など、特定の分野に特化することで専門性やキャリアの選択肢を広げることも可能でしょう。
薬剤師
薬剤師は医薬品の専門家として患者に最適な薬を提供して、その安全な使用を支える役割になります。
病院や調剤薬局、ドラッグストアなどで働き、処方箋に基づく薬の調合や患者への服薬指導などを行うのが仕事です。
また、薬の効果や副作用についても説明し、患者が正しく服用できるようサポートすることも求められます。
病院では医師や看護師と連携し、患者ごとに合わせた薬剤管理を行い、製薬企業や研究機関では新薬の開発や品質管理にも寄与します。
近年では地域の健康相談窓口としての役割も求められ、在宅医療において訪問薬剤指導を行う機会も多いです。
薬の専門知識を活かし、患者の健康を支える重要な職種であると言えるでしょう。
理学療法士
身体機能が低下した患者に対してリハビリテーションを行い、運動機能の回復を支援する専門職です。
病院やリハビリ施設、介護施設などで働き、患者の身体状態を様々な要因から評価した上で、ストレッチや筋力トレーニング、歩行訓練などの運動療法を実施するのが仕事です。
特に高齢者や脳卒中の後遺症などがある患者に対するリハビリの需要が高まりつつあり、日常生活動作の維持・向上を目的としたサポートも求められています。
また、スポーツ分野ではアスリートの怪我の回復をサポートするのも仕事の1つです。
患者一人ひとりの状態に応じた適切な治療計画を立て、機能回復を目指すことで、生活の質を向上する、やりがいのある職種です。
作業療法士
作業療法士は病気や障害によって日常生活に支障をきたしている患者に対して、自立した生活が送れるように支援する専門職の1つです。
病院やリハビリの施設、福祉施設などで働き、食事や着替え、家事、仕事などの動作訓練を行います。
特に、脳卒中や認知症の患者、精神疾患を抱える人々へのサポートが重要とされており、それぞれの生活環境に応じたリハビリプログラムを考案・提供するのが仕事です。
身体的なリハビリに加え、認知機能の回復や社会復帰を目指した訓練を行うことも多くあります。
また、福祉の分野では障害を持つ子供への療育支援にも携わることがあり、幅広い領域で活躍できる職種です。
診療放射線技師
診療放射線技師はX線、CT、MRIなどの医療機器を操作し、医師が診断を行うための画像を提供する専門職です。
病院やクリニックで働き、骨折や内臓の異常を発見するための画像診断などを行います。
近年ではがんの早期発見を目的としたPET検査や放射線を用いた治療にも関与することが多いです。
放射線を使うため、安全管理に関する特に専門的な知識が求められ、正確な技術と高度な判断力が必要とされる職種です。
また、検査時には患者と直接コミュニケーションを取る機会が豊富であるため、不安を和らげるための優しい言葉遣いや対応力なども重要になります。
継続的な学習が必要な分野であるため、就職後も学び続けることに抵抗がない人に向いていると言えるでしょう。
管理栄養士
管理栄養士は患者の健康維持や病気の予防・回復を目的として、適切な栄養管理を行う専門職です。
病院や介護施設はもちろん、学校や企業の社員食堂などで働くことも多く、個々の健康状態に合わせた食事メニューを作成するのが仕事です。
特に、糖尿病や高血圧などの生活習慣病を持つ患者に対しては医師と連携しながら栄養指導を行うことが求められます。
また、スポーツの分野でアスリートの体調管理を支える役割を担うことも多いです。
さらに、近年では地域の健康増進のために自治体と協力して食育活動を推進する機会も増えています。
食事は健康の基盤となるため、栄養の専門知識を活かし、多くの人の生活を支えられるやりがいのある仕事であると言えるでしょう。
【医療業界の最近のニュース】ニュースを伝える時に気を付けるべき注意点
ニュースを伝える時に気をつけなければならない注意点についても紹介します。
以下の2点を意識せずに回答をしてしまうと、自分では完璧だと思っていても、気付かぬうちにマイナスな印象を与えてしまっている可能性があります。
ぜひ、以下の2点を意識した上で、質の高い回答を用意できるように意識してください。
相手にも理解できるように説明する
ニュースを伝える際は聞き手が内容を正しく理解できるよう、わかりやすい言葉を選ぶことを心掛けてください。
医療業界のニュースは特に専門用語が多く使われるため、そのまま伝えてしまうと相手に伝わりにくくなってしまいます。
「ゲノム医療」などの用語を使う場合は、その言葉の意味を簡単に説明した上で話すと、理解しやすくなるでしょう。
また、1つの情報を長々と説明するのではなく、要点を整理して簡潔に伝えることも大切です。
具体的な例を交えながら話すと、相手も内容をイメージしやすくなるでしょう。
断片的な情報だけで語らない
ニュースは表面的な情報だけで終わらせず、できる限り正確で深みのある内容を心がけることも大切です。
特に医療業界のニュースは専門性が高いため、不確かな情報を話してしまうと誤解を招くおそれもありますし、情報の取捨選択ができない人物であると判断される可能性が高いでしょう。
例えば「新しいワクチンが開発された」というニュースについて話す場合、それがどのような病気に対するもので、どの段階まで開発が進んでいるのか理解していないと、質問された時に対応できなくなってしまいます。
また、ニュースの一部だけを取り上げて話すと、意図しない誤解を生むこともあります。
そのため、必ずニュースの背景を調べて、複数の情報を確認することが重要です。
【医療業界の最近のニュース】医療業界の最近のニュースを見つけるのにおすすめのサイトとアプリ
ニュースを見つけるにあたって、医療業界の最近のニュースを見つけるにあたっておすすめのサイトやアプリを紹介します。
いずれも信頼性が非常に高く、正しい情報を発信しており、そして専門家の意見なども掲載されていることが多い媒体です。
いずれも隙間時間で情報収集ができる点が魅力であるため、気になるものがあればぜひ活用してみてください。
NewsPicks
NewsPicksは政治や経済、社会情勢、海外の情報など幅広いニュースを集約しているサイトの1つです。
医療業界に関するニュースも非常に豊富であり、最新の医療技術や製薬業界、医療政策に関する記事を手軽に読むことも可能です。
また、専門家や経営者、医療関係者がコメントを寄せる機能もあるため、ただニュースを読むだけでなく、業界の専門家の視点を交えた深い考察を得ることもできます。
また、アプリ版も提供されており、隙間時間にスマートフォンで有料ニュースをチェックすることも可能で、シンプルなデザインで操作性も良いため、就活の情報収集に最適なツールの1つであると言えるでしょう。
日経ビジネスオンライン
日経ビジネスオンラインは経済や企業経営、社会問題に関する専門性の高い記事を提供しています。
もちろん、医療業界に関するニュースも多く掲載されており、新たな医療技術の開発、病院経営の課題、政府の医療政策など、実務的な視点からの分析記事も豊富です。
特に医療業界の最新トレンドを知る上で、製薬会社の戦略や病院経営の動向などを詳しく解説している点が特徴です。
専門的な記事が多いため、最初は少し難しく感じることもありますが、業界研究を深めるために有益なサイトの1つであると言えるでしょう。
また、企業の経営戦略や医療業界の将来の展望について考察が掲載されていることも多いため、面接で深い議論をする際の参考にもなります。
SmartNews
SmartNewsは3000以上の提携メディアから厳選された記事を配信しているニュースアプリです。
業界ナンバーワンの提携数を誇り、新聞社や専門メディアの記事をまとめて読むことができます。
医療分野のニュースも幅広くカバーされており、新型コロナウイルスやワクチンに関する最新情報、医療制度の変更、病院の経営状況など、就活生が知っておくべき話題を閲覧できます。
また、カテゴリは細かく分かれているため、医療、ビジネス、政治など、関心のある分野のニュースを効率的に集めることも可能です。
アプリには通信環境が悪い状況でも記事を読むことができるオフライン機能もあり、移動中でも快適に情報収集ができます。
【医療業界の最近のニュース】最新ニュースの回答に行き詰まったらどうする?
ここまで医療業界のニュースについて聞かれた際にうまく答えるためのポイントや、ニュースの選び方などについて詳しく紹介してきました。
しかし、まだ「うまく答えられるだろうか」と不安に思っている方は多いでしょう。
そんな方におすすめなのは、就活エージェントを活用することです。
就活のプロに自分の回答を聞いてもらえば、どのような点にまだ改善の余地があるのか、どのような点は自信を持って良いのかが明確になります。
弊社が提供している「ジョブコミット」では面接練習はもちろん、ESの添削やおすすめ企業、非公開求人の紹介なども行っているため、気になる方はぜひ以下のリンクから登録してみてください。
まとめ
今回は医療業界を目指している方向けに、最近の気になるニュースについて面接で聞かれた際の対策について詳しく紹介しました。
最近の気になるニュースについては面接で聞かれることが多く、全く対策していないとうまく答えることができません。
そこで、この記事を参考に情報収集により力を入れ、面接で聞かれた際、自信を持って答えられるようになっておくことが重要です。
ぜひ、この記事を参考にして、しっかりと対策を行っておいてください。




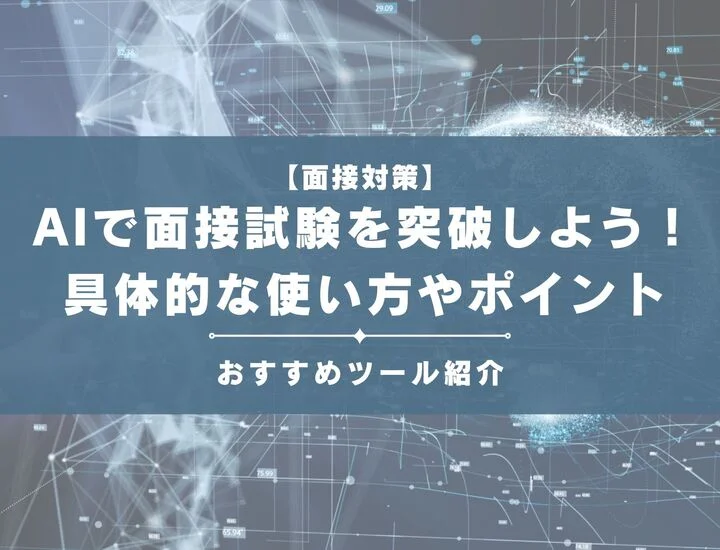







木下恵利
業界に関するニュースや経済動向について的確に話せる人は「自社への関心が高い」と判断されることが多いです。