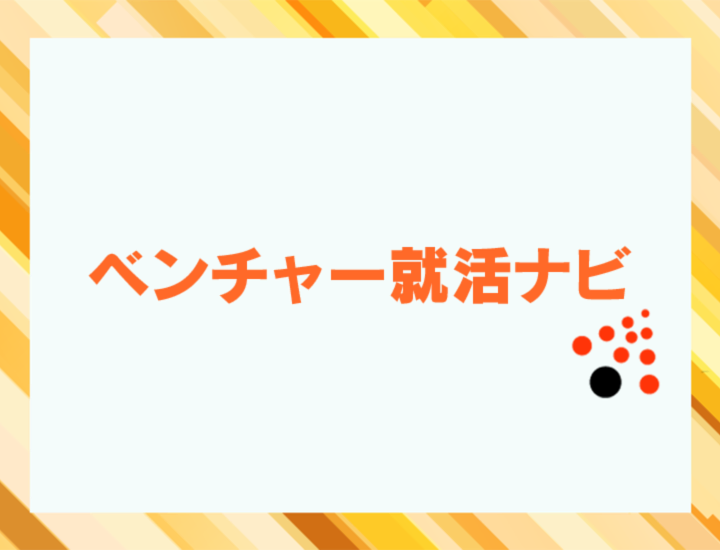明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・調整力をアピールする自己PRのポイント
・自己PRのおすすめ構成
・調整力をアピールする際の例文
・調整力をアピールする自己PRのポイントを知りたい人
・自己PRのおすすめ構成を知りたい人
・自分の自己PRに不安がある人
はじめに

就活をする際に必要となるのが自己PRです。
各企業の面接官に対して、自分がどのような人間であるのかをアピールするためのものです。
自己分析を行ったうえで、ご自身の強みが調整力であると判明したとします。
しかし、これまで自己PRをしてきていない場合、いきなり書くといってもどうしたらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は自己PRで調整力をアピールするための書き方やその際の注意点についてご紹介いたします。
【自己PRで調整力をアピールするには】企業が求める調整力とは
まず調整力とは、かなり範囲が広い能力です。
最も重要なのは、その強みに対して企業側はどのような部分を求めているのかを理解することです。
たとえば、企業で業務を遂行する中で、社内の部署間や他社との連携は不可欠となってきます。
お互いの都合を主張した場合に、意見がぶつかってしまうこともあるでしょう。
スケジュールがかみ合わず、納期に影響が出てしまうこともあります。
そのような業務上の問題発生時に、調整力を発揮することによって円滑にしっかりとした結果が出ることを企業は望んでいるのです。
この調整力はクライアントとの意見の調整はもちろん、組織内の意見の調整においても重要となります。
また、人間関係も同様です。
人間は生まれも育ちも違います。
価値観や考え方にも違いがあり、それによって業務に支障が出てしまうこともあります。
そんなときも調整力で意見をうまくまとめて円滑にまとめ上げることが理想的です。
そのことを強く意識したうえで自己PRを作成しなくてはなりません。
【自己PRで調整力をアピールするには】調整力をアピールできる!
調整力は就活においてアピールできるポイントです。
調整力は聞き上手の人であれば、アピールできるポイントであるため比較的アピールしやすいです。
しかし調整力をアピールする人が一定数いるため、周りと差別化をすることが大切です。
差別化をする方法として経験の違いから差別化をする方法やキャッチコピーのようなものを作る方法などがあります。
ベンチャー企業でもアピールできる
ベンチャー企業でも自己PRで調整力をアピールすることができます。
ベンチャー企業は新しい商品やサービスを提供する企業のことであるため、仕事が不安定なことがあるようです。
そんな時に調整力がある人は、不安定な仕事に対して自分や他の人を適応させることができ、大いに力を発揮します。
それだけでなく、しっかりと計画性を持ち、様々なことを調整することができる人材が重宝されます。
【自己PRで調整力をアピールするには】企業が調整力を求める理由
ビジネスの場面で求められる調整力とはどのような能力なのかを説明しました。
では、企業はなぜビジネスにおいて調整力を求めるのでしょうか。
ここから調整力のメリットについて説明するとともに企業が調整力を求める理由を解説していきます。
問題を円滑に解決できる
調整力をもっていると、仮に問題が起こったとしても問題に関わる人に不満を抱かせることなく問題を解決に導くことができます。
立場が高くなると、権力を使って強引に問題を解決することもできなくはありませんが、そのような方法をとっても一時的な解決にしかなりません。
力技での解決は様々な人に不満を抱かせる結果に繋がり、さらなる問題の発端になります。
場合によっては関係する企業全体に不信感を抱かれてしまい、信用を失ってしまうこともあり得るのです。
しかし、調整力のある人が問題解決にあたると利害の対立を最小限に押さえて問題が起こっている関係者全てとコミュニケーションをとって円滑に問題を解決することができます。
スムーズに仕事ができる
調整力をもっていると、様々な業務を担当したとしてもスムーズに仕事を進められることが多いです。
調整力のある人は、全体を俯瞰してみることができるためどのようなところに課題があるかを把握することができます。
事前に起こりそうな問題を把握することができるため、先回りしてトラブルを回避することができます。
企業に調整力のある人がいると、問題発生時に対応する時間やそのほかの無駄なやりとりに咲く時間が減るので、仕事の効率化を測ることができるのです。
仕事の効率化ができれば、プロジェクトが停滞するということもなく全員がスムーズに仕事を進めることができます。
まとめると、調整力のある人を雇うことによって社員が最大限のパフォーマンスを常にすることができるため、仕事の効率化につながるのです。
リーダーシップがある
調整力のある人は、リーダーシップも兼ね備えています。
先ほど述べたように調整力がある人は、利害の対立を最小限におさえ問題を円滑に解決することができたり、全員がスムーズに仕事ができるようにすることができます。
このような能力を活かしながら仕事をしていると、他人からの信頼を得ることができます。
他の社員からの信頼を得ることができると、調整力のある人の方針についてきて仕事をしてくれる人が増えてきます。
社員の様々な意見がある中で、それらの意見をまとめた上で意見の対立を防ぎ、まとめることができるのが調整力だと言えます。
リーダーシップを活かしていくためには、より主体的な調整力が必要になります。
自分から課題を解決したり、意見の対立をおさえたり主体的に仕事をしていくことが求められます。
利害の対立を避けられる
企業では、他者との取引をする上で必ず利害の対立が起こってしまうものです。
調整力のある人は、なぜ利害の対立が起こってしまっているのかを瞬時に把握して両者それぞれの意見を聞き入れながら解決策を講じることができます。
あるいは両者の意見をまとめて新たな両者が合意するような意見を作ることもできます。
調整力があれば、様々な状況を客観的に把握することができるため、利害の対立が起こりそうな場面を想定してそれを未然に防ぐこともできるのです。
このように調整力のある人は、様々な意見や経営状況などを全て考慮した上で全員が納得できるような形へと調整して、最終的なゴールに導いてくれます。
そのような意味で企業は調整力のある人を必要としているのです。
リスクに気づくことができる
調整力があると、様々な状況を考慮することができるため、リスクの把握がしやすくなります。
取引を行うにあたって、それに伴うリスクにいち早く気づくことができます。
そのため、企業に損害が出ないようにリスクを避けることができるのです。
企業は安定して利益を上げるためにできるだけリスクは避けたいものです。
しかし、気づかないリスクというものもある程度存在します。
調整力のある人はそのような気づかないリスクにも気づくことができます。
目標や目的がブレない
調整力がある人が企業にいると、目標や目的を他の社員に示して成功に導くことができます。
調整力がある人は様々な社内の状況を考慮して目標や目的に対して、正しい取り組みができているかを確認して方向性を示してくれます。
間違った方向を向いていれば正しい方向にする力を持ち合わせています。
目的や目標をブラさずに導いてくれるため、調整力のある人材を企業は求めているのです。
【自己PRで調整力をアピールするには】調整力をアピールする際の構成方法
続いて、調整力をアピールする際の構成方法についても紹介します。
この構成はPREP法と呼ばれるものであり、調整力だけでなくどのような能力をアピールする際にも活用できるものです。
ぜひそれぞれのポイントを踏まえた上でマスターして、企業が求めている人物に近いことをアピールしましょう。
PREP法
PREP法は「Point(結論)」「Reason(根拠)」「Example(具体例)」「Point(再結論)」の4つの要素で構成され、論理的かつ簡潔に自分の強みを伝えるためのフレームワークです。
まず、最初に結論を明確に述べることで聞き手の関心を引き、次にその根拠を補足することで説得力を高めます。
具体例を挙げることで話に現実味を持たせ、最後に再び結論を述べて印象を強く残す構成です。
では、それぞれの項目を見てみましょう。
まずは最初に自分のアピールポイントを明確に述べましょう。 調整力をアピールする場合、ここで「私の強みは調整力です」と端的に述べることで、話の全体像を伝えられます。 この段階では具体的な理由やエピソードは述べず、聞き手が最初に「調整力」というキーワードを把握できるようにします。 また「この強みを活かして、これまで多くの困難を解決してきました」と一言付け加えることで、これから話す内容への期待感を高めることが可能です。 結論部分では簡潔さが求められるため、過剰な説明は避け、聞き手が「調整力」というテーマに集中できる表現を意識することが重要です。
根拠では調整力がなぜ自分の強みであるのか、その理由を説明します。 例えば「私はグループでの活動や課題解決において、常に全員が納得できる方向性を模索してきました」といった形で、自分の取り組み方や意識を具体的に述べます。 この部分では自分が調整力を活用する場面で意識している行動や考え方を伝えることが大切です。 「対立している意見を公平に捉え、それぞれの意見の良い点を組み合わせることで解決策を見つけました」など、日常的な行動や姿勢を交えると、より説得力のある説明になります。 このように、根拠を明確に示すことで、調整力という強みが「単に自分で強みと思っているだけ」ではなく「具体的な行動に裏付けられたものである」ことを伝えることができます。
具体例では自分の強みを裏付けるための実際のエピソードを述べましょう。 例えば「大学の部活動で部長として活動する中、メンバー間で目標がばらばらだったため、プロジェクトが停滞していました。 そこで私は個別にメンバーと話し合い、それぞれの意見をヒアリングしながら共通の目標を設定しました。 その結果、チーム全体の意識が統一され、最終的に大会で優勝することができました」といった形で、具体的な行動や結果を詳細に述べます。 この部分では課題、行動、結果の流れを明確にすることが重要です。 調整力を活かしてどのように行動し、どのような成果を得たのかを具体的に伝えることで、聞き手が話をイメージしやすくなり、説得力も高まります。
再結論の部分では最初の結論を再度強調し、自分の強みを締めくくります。 「このように、調整力を活かしてチーム全体をまとめ、成果を上げてきた経験があります。 貴社においても、多様なメンバーが関わるプロジェクトで調整力を発揮し、円滑なコミュニケーションと目標達成に貢献していきたいと考えています」と述べることで、入社後のビジョンと結びつけます。 この再結論部分では自分の強みが企業にどのような利益をもたらすかを明確に伝えることがポイントです。 最初に述べた結論を繰り返すことで、話全体がまとまり、聞き手に強い印象を残せる構成になります。
STAR法
STAR法は「Situation(状況)」「Task(課題)」「Action(行動)」「Result(結果)」の4つのステップを用いて、論理的かつ具体的に自己PRやエピソードを構成するためのフレームワークです。
自分の行動がどのように課題を解決し、どのような結果をもたらしたかを分かりやすく伝えるのに役立ちます。
特に、調整力のような抽象的な能力をアピールする際にはSTAR法を用いることで話に説得力を持たせることが可能です。
具体的な状況から課題、そしてその解決に至る行動と成果を順序立てて説明することで、聞き手に自分の能力や実績をわかりやすくアピール可能です。
「シチュエーション」では自分が経験した具体的な状況を説明します。 調整力をアピールする場合、この段階で「ゼミの研究プロジェクトで、メンバー間の意見が大きく分かれ、研究の方向性が定まらない状況に直面しました」といった形で、何が起こっていたのかを明確に述べることが重要です。 この説明は聞き手が状況をイメージしやすいように、簡潔でありながら詳細にする必要があります。 また、課題の複雑さや状況の深刻さを伝えることで、その後の行動の意義や価値を強調する土台を作ることができます。 この部分がしっかりしていると、聞き手がエピソードに興味を持ち、話の内容を深く理解しやすくなります。
「課題」では状況で直面した問題や解決すべき課題について説明します。 例えば「方向性のずれが原因で、研究の進行が大幅に遅れ、チーム全体の士気も低下していました」と述べることで、具体的にどのような困難が存在していたのかを伝えましょう。 この部分では問題を述べるだけでなく、その問題が「どのように影響を及ぼしていたのか」を詳しく説明することが求められます。 課題が明確であればあるほど、次の「行動」で述べる解決策や取り組みの重要性が際立ちます。 「意見の対立」や「ゼミの研究テーマを変更せざるを得なくなった」といった具体的な課題を例に挙げると良いです。
「取り組み」では課題を解決するために自分が行った具体的な行動を説明します。 例えば「私は全員が納得できる解決策を見つけるため、まずメンバー一人ひとりと個別に面談を行い、それぞれの意見や主張の背景を理解しました。 その後、全員が共通の目標を共有できるよう、合意形成のためのミーティングを開催しました」といった形で、どのように調整力を発揮したのかを具体的に述べましょう。 この部分では自分の行動のプロセスを順序立てて説明することが重要です。 また、自分がどのように問題解決に貢献したのかを明確にすることで、聞き手に自分の能力や行動力をしっかりと伝えることができます。
「結果」では自分の行動がどのような成果をもたらしたのかを説明します。 調整力をアピールする場合「メンバー全員が新しい方向性に納得し、プロジェクトの進行がスムーズになりました。 そして、学内コンペティションで優勝することができ、チーム全体の達成感と結束力も高まりました」などと述べると良いです。 この部分では具体的な数値や成果、他の人からのフィードバックなどを交え、話の説得力が増すようにしましょう。 また、成果は必ずしも100%の成功体験である必要はありません。 失敗していたとしても、そこから学んだことを就職後に活かせると話せるならば、問題ありません。 いずれにせよ「結果」部分はエピソード全体を締めくくる重要な要素であり、話の印象を大きく左右します。
【自己PRで調整力をアピールするには】調整力をアピールする際のポイント
自己PRで調整力をアピールする際に注意すべきポイントとして2つあげられます。
自己PRの目的は面接官に伝えることですが、どれだけアピールをしても正しく伝わらなければ意味がありません。
今回あげたポイントというのは面接官に正しく伝えるためであり、わかりやすく伝えるためのものです。
深く考えずに作るとついつい抜けてしまいがちな部分でもあります。
どちらも重要なポイントですので、ぜひ参考にしてみてください。
調整力の内容を明示する
調整力という能力はわかりやすいようで、そうでもないという不思議なものです。
実際に異なる意見をまとめたりと調整をする場合には、いくつかの能力が必要だといえます。
たとえば、意見が食い違っている関係者に寄り添って話を聞ける能力や、ぶつかった意見に対して折衷案を生み出せる能力も必要でしょう。
交渉力も調整するうえでは不可欠です。
具体的に説明することでよりわかりやすく伝わります。
調整力の表現に関しては内容をしっかり明示しましょう。
どれ1つだけに的を絞ってもかまいませんし、複数の内容をまんべんなくアピールするのもいいでしょう。
重要な部分はその内容が明示されているかどうかです。
この人が入社することによって、会社としてどのようなメリットがあるのか想像しやすくなれば、アピールする意味がよりたしかなものとなるでしょう。
状況をしっかり説明する
調整力とはエピソードにおいて、結果としてうまくまとめられる能力を指すでしょう。
しかし、それでは本当にその能力があるのかいまいちわかりません。
調整力の重要なポイントとなるのは、どういった状況でどのようにして最終的に調整できたのかという部分なのです。
そして結果的に円滑にまとまったという結果のことを企業が知りたい調整力といえるでしょう。
状況をしっかりと説明して、それをまとめ上げたエピソードが必要になります。
エピソードは具体的であればあるほど、強みであると伝わります。
もちろん説明が長くなってしまっては中だるみしてしまう恐れもあるでしょう。
無駄な部分は削ぎ落とす必要があります。
しかし、できるだけ背景も交えつつ状況を説明したうえで、さらにどのようにまとめ上げたのかという部分を明確に伝えましょう。
状況をしっかりと説明することでわかりやすくなる反面、エピソード自体が弱いと逆効果になってしまうかもしれません。
誰でも調整できるわけではない状況が理想です。
何が課題となり、どういったところが難しかったのかを効果的に伝えましょう。
業務にどう活かしていくか
入社後に自分の調整力をどのように活かし、企業に貢献できるかをアピールしましょう。
社会人に必要な調整力とは、自らが率先して行動を起こせる主体性です。
状況をくわしく説明できたら、その経験が業務でどのように活かせるかを伝えましょう。
たとえば、多くの人を巻き込んで物事を進めた経験のことを調整力と説明した場合です。
入社後、社内外の相互理解を深め全員が納得できるよう調整をし、プロジェクトを遂行する際に自分のスキルを発揮し、企業に貢献できるとアピールできます。
企業の仕事は個人の力では成立しないことばかりです。
どのような場面で発揮された調整力を、企業のどのような場面で発揮できるかを明確に説明できるようにしましょう。
【自己PRで調整力をアピールするには】アピール時のコツ
ここまでは自己PRにおいて調整力を別の言葉に言い換えた際の例や、調整力をアピールする際のポイントについて詳しく紹介してきました。
続いては自己PRで調整力をアピールする際のコツについても詳しく紹介していきます。
自己PRで調整力をアピールする際に下記の3つを意識しておくことで、より企業に良い印象をアピールできることでしょう。
内定した人のESを参考にする
自己PRで調整力をアピールする際のコツとして、内定した人のESを参考にするということが挙げられます。
実際に内定を得られた人のESは必ず参考になる部分があり、あなたが実際に作成した自己PRと比べてみて足りない部分は何かと判断しやすいことでしょう。
先輩のESが見たい方におすすめのツールは「イールック」で、業界ごとのES対策はもちろんのこと、これまで内定を獲得してきた人のESを細かく確認することができます。
大手、ベンチャーなど企業の規模や職種などにも合わせて、絞って条件検索できるのも魅力的なポイントです。
また、もちろん料金は無料なので、アルバイトをする余裕のない就活生にも優しいサービスです。
差別化を意識する
調整力をアピールする就活生は少なくないので、差別化を意識することも非常に重要なポイントとなってきます。
多くの就活生は企業に対して感じている魅力やアピールポイントについて話しますが、できれば自分の経験を積極的に盛り込むようにしていきましょう。
これにより、あなたの唯一無二である経験を述べることができ、他の就活生とは違う印象を与えられる可能性が高まります。
実際に調整力を活かした経験があるならば、それをアピールしつつ、その経験をどのように活かして就職後も活躍できるのかについて述べるようにしましょう。
これにより、企業の採用担当者もあなたが活躍してくれる人材であると考え、採用したくなるかもしれません。
結論から述べる
結論から述べるということも非常に重要なポイントなので、忘れないようにしましょう。
自己PRを作成する際、まずは自分の長所が何であるのかを一言目に述べることが重要です。
これにより企業の採用担当者はあなたの自己PRが何なのか、どのような話が展開されていくのかを念頭において読んでいくことができます。
就活のシーズンになると企業の採用担当者は無数の自己PRや志望動機を読むことになり、隅から隅まで全てを読むということは難しいです。
そこで結論から述べられている文章を提示することで、集中力が切れることなく、あなたがどのような魅力を持っているのかが最後まで伝わりやすい文章になることでしょう。
【自己PRで調整力をアピールするには】「調整力」は言い換えるべき?
調整力という言葉はわかりやすい反面、実際にどのような能力であるのか具体的な部分についてはわかりにくい面があります。
意見をまとめ上げて円滑にすすめられることを総合的にまとめた言葉が調整力というわけです。
自己PRでそのまま使用すること自体は問題ないものの、他の志願者がその言い回しを選択することは容易に想像できるでしょう。
ほかの志願者と同じ言い回しをすれば、アピールが薄くなってしまう恐れもあります。
別の言い回しにするほうが無難かもしれません。
たとえば「チームワークや協調性を大切にする」や「妥協点を見つけるためのアイデア力がある」という言い回しだと、調整力よりも具体性があるのでわかりやすくなります。
【自己PRで調整力をアピールするには】調整力の言い換え例
続いて、調整力を言い換える際にはどのような表現が当てはまるのかについても紹介します。
もちろん「調整力」とそのままアピールしても悪い印象を与えるわけではないのですが、あなたの強みを言語化してみると、より近い表現方法が見つかるかもしれません。
いずれも企業の採用担当者に良い印象を与えやすい能力であるため、確認して、よりあなたの能力をアピールしやすい表現があれば活用してみてください。
チームワーク
調整力をチームワークとして言い換えることで、協調性や仲間意識を持ちながら仕事を進める能力を強調できます。
例えば、周囲を巻き込んでお互いに助け合う環境を作ることで、生産性の向上や職場の雰囲気の改善につなげられることをアピールできます。
特に、異なる背景やスキルを持つメンバーがいるチームで調整力を発揮して全員が同じ目標に向かえるようサポートしたような経験があれば、説得力のあるエピソードになるでしょう。
チームワークを通じて、個人の成果だけでなく、チーム全体としての成功を重視する姿勢を伝えることで、集団の中で輝ける人材であることをアピールできます。
交渉力
調整力を交渉力として言い換えると、対外的なやり取りでのスキルをアピールすることが可能です。
特に、取引先やクライアントとの交渉で意見の相違を解消し、関係性を改善した経験を持つ場合に有効です。
例えば、価格交渉や契約条件の調整を通じて、双方が納得できる結果を導き出した経験をエピソードとして述べることで、実務的な能力の高さを強調できます。
交渉力としてアピールする際には、結果を述べるだけでなく、プロセスや具体的な工夫についても詳しく説明することで、面接官に自分の能力を具体的にイメージしてもらうことができます。
リーダーシップ
調整力をリーダーシップとして言い換えると、チームをまとめる力や、目標達成に向けた行動力をアピールできます。
特に、リーダーとして適切な指示を出し、メンバー全員の意見を反映させながら組織をまとめた経験がある場合におすすめです。
リーダーシップをアピールして、課題解決やチームの目標達成を実現したエピソードを具体的に述べることで、周囲への影響力を伝えることができます。
相手もあなたが入社後も同様にリーダーシップを発揮し、チームや組織全体に貢献する姿をイメージしやすくなるでしょう。
傾聴力
調整力を傾聴力として言い換えることで、周囲の意見をしっかりと聞き、それを取りまとめる能力をアピールできます。
特に、チーム内で異なる意見が飛び交う状況や、個々のメンバーの不安や要望を把握して解決に導いた経験があれば、それを傾聴力として具体的に説明すると効果的です。
また、塾講師など、誰かの相談に乗ることがあるアルバイトをしていた人もアピールしやすい能力です。
「相手の立場に立って話を聞き、全員が納得できる結論を導き出した」などといったエピソードを述べることで、協調性や問題解決能力を面接官に伝えることもできます。
傾聴力を強調することで、入社後の職場環境の改善や、チームメンバーとの円滑なコミュニケーションを期待してもらえるでしょう。
【自己PRで調整力をアピールするには】調整力をアピールする際の注意点
「私には調整力があります」と単に伝えるだけでは、まったくアピールにならないことはここまで読んで理解できたでしょう。
具体的な調整力についてのエピソードを伝える際、気をつけなければならないポイントがいくつかあります。
自分のアピールしたい調整力を理解してもらえるようなエピソードが必要です。
面接官に「調整力が備わっているな」と感じてもらうため、以下に注意してください。
せっかく考えた自己PRも面接官にとって、印象の悪いものとならないようにしましょう。
ネガティブなエピソードは避ける
調整力をアピールするうえで、ネガティブなエピソードはNGです。
失敗した経験を伝えると、調整力があるとは言い難いエピソードになり、面接官への印象は良くないでしょう。
特別な経験や華々しい実績だけが良いエピソードではありません。
経験を通して自分がどのように考え行動したかをあらわし、調整力をアピールしましょう。
どうしてもネガティブなエピソードになってしまいそうであれば、どのような学びがあったかを盛り込みます。
たとえば、サークルで学園祭のイベントに出店をした際の経験を話すとしましょう。
まず、自分が取った手段として「当日まで全員で打ち合わせをする機会はあまり取れなかったが、サークル全体の意見を取り入れつつ学園祭の実行委員会との橋渡しに努めた」ことを述べます。
まとめとして「惜しくも、売り上げ目標はわずかに届かなかったが、この経験を通じ、コミュニケーションの量ではなく質を重要視するようになった」というように失敗だけでなく学びとセットで伝えましょう。
自己主張が弱いと思われないようにする
調整力を伝えるうえでもっとも気をつけるべきことは、どのようなことにでも同調をする性格だと思われないようにすることです。
調整力があることを「周りの意見に流されやすく意志が弱いのでは」と捉えられるかもしれません。
周りの意見を取り入れてまとめ、円滑に物事を進められるとアピールしましょう。
また、単に「場の雰囲気を悪くしたくない、ことを荒立ててややこしくしたくない」という考えでそのようにしていると捉えられることもあります。
その場合は、どういった理由で行動をしたのか、十分理解して行っていることを伝えます。
自分に備わっている調整力は、周囲を動かす力であるとアピールすれば、面接官にも調整力がありそうだと伝わるでしょう。
その場しのぎのエピソードは使わない
調整力を自己PRとして話そうと考えたとき、偶然うまく調整できたエピソードもあったでしょう。
しかし、それがどれだけ優れた経験でも、そのエピソードを使うべきではありません。
偶発的に解決したことは、その場を逃れるために取った行動であるように感じ、調整力とは言えないからです。
調整力とは、起きている課題に対して、どういった理由で対処したかと、本質的な問題解決ができたことをエピソードにしましょう。
実際に自己PRで話すエピソードにするためには、既知の問題は再度発生させないことを第一に考え、自主性をもって体制や制度を変更したり、新しいルールを作ったりして周りの協力を仰ぎながら防ごうとした経験などを伝えると良いでしょう。
「調整力」を細分化し言い換える
「調整力」という言葉は、非常に汎用的で抽象度が高い表現です。
このため、自己PRとして用いる際には、具体的なスキルや行動に細分化し、それぞれを分かりやすい言葉で言い換えることが重要です。
調整力は単なる「人と人の間を取り持つ能力」ではなく、複数の要素が組み合わさったスキルの総称です。
そのため、これを効果的に伝えるには、自分が発揮している調整力の具体的な内容を整理し、採用担当者がイメージしやすい言葉に落とし込むことが大切です。
【自己PRで調整力をアピールするには】自己PRの書き方を紹介
はじめて自己PRを書く場合には、いきなり書き始めるとまとまらなくなってしまう傾向にあります。
もともと文章力がある方であれば難しくない話かもしれませんが、なかなか自分自身のことをアピールするのは難しいでしょう。
面接官の方に対して伝えなければいけません。
点を押さえてわかりやすく簡潔にまとめる必要があります。
そのためには以下の構成で作るといいでしょう。
2.発揮したエピソード
3.課題
4.解決策
5.結果
6.会社にどう貢献できるか
まずはわかりやすく調整力という強みがあることを宣言します。
そのうえで、状況説明をしっかりとし、強みを活かせたエピソードにつなげます。
課題や解決策も明確にしましょう。
そして最終的に、最も重要な部分となる会社に対してその強みを活かしてどう貢献できるのか、という部分で締めとなります。
特にエピソードの部分が大切です。
調整力があることをわかってもらえるように、内容を明示することも必要です。
【自己PRで調整力をアピールするには】経験別例文
構成や注意点などがわかったとしても、はじめてであれば思うように書くことが難しいでしょう。
強みをアピールしなければならないので、就活生の方にとっては神経質になってしまう部分でもあるはずです。
そこでこれまでご紹介したポイントを踏まえて、3つの例文をご用意しました。
こちらを参考にご自身のエピソードを照らしあわせれば、自己PRを書けるでしょう。
例文があることで文章が作りやすくなる面もあるかと思います。 ぜひベースにして組み立ててはいかがでしょうか。
部活動(運動部)
高校時代はバレー部に所属していましたが、その当時私たちの学年と1つ下の学年であまり仲がいい状態ではありませんでした。
バレーはチームプレーで成り立っているスポーツです。
仲違いしている状態で結果はついてきません。
そこでまずは仲が悪い原因を確かめました。
チームメイトなどの話をたどっていくと、特定のメンバー間でのいざこざが原因だとわかったのです。
そこで思い切って、当事者同士での話し合いの場を設けることにしました。
原因になった先輩風を吹かせて無茶な要求をした同級生メンバーには、後輩の身になって考えるように説得し、心からの謝罪をするように促したのです。
後輩に対しても、謝罪を受けた以上は最低限の礼儀は守って接するように伝えました。
この出来事をきっかけに学年間でのわだかまりがなくなり、その翌年の県大会ではベスト4という過去最大の成績を収めることができたのです。
貴社に入社した際には、チームワークや協調性を大切にするという強みを活かして、部署間で意見がぶつかった際も落とし所を見つけて円滑に業務を遂行いたします。
この例文では、具体的なエピソードによって協調性やチームワークを大切にできると伝えています。
特に感情的なトラブルの場合には調整の難易度は高くなるのです。
それでも最終的にはチームワークを大切にし、確執をなくしたという結果を手に入れているので、面接官の方にも伝わりやすいでしょう。
部活動(文化部)
大学の吹奏楽部に所属していた際、部長と副部長の考え方が食い違い、吹奏楽部の全員が同じ目標を持てていないという状況が続いていました。
そこでパートリーダーである私は部長、副部長の意見だけでなく全員の意見を聞き、整理する中で「大会で入賞したいという考えを持っている」という共通点を見つけ、考えを統合するべく話し合いを行いました。
この結果、お互いの意見を反映した効率的な練習メニュー作りに成功したことで、双方のわだかまりが徐々に解けていき、協力し合える体制ができました。
それにより春の大会では見事金賞を受賞することができました。
この強みを生かして、貴社に入社した後もチーム内での仲介役として、チームの関係性を保ち生産性をよくできるように勤めていこうと考えています。
学園祭
大学の文化祭の実行委員会で歌フェスティバルの責任者として活動していましたが、お互いの企画に無関心で誰が何の仕事をやっているのかを理解できていないという状況でした。
そこでみんなで仕事や意見を共有しながら活動をしたいと考え、自分の担当でない企画にも声をかけたり、全体での話し合いを重ねました。
これらから私は担当外の仕事でも良し悪しを言い合える環境を整えました。
また話し合いでは毎回話すグループを変えることで、だんだん全体の結束力、一体感を作ることができました。
結果、前年比1.5倍の観客数を達成しております。
貴社で働く上でも主体的にチームのために動くことで貢献したいです。
サークル
大学生のころ、映画サークルで映画を自主制作していました。
当時長編映画を撮影していた際に、川辺でのシーンにおいて川に入水させたい監督陣と入りたくない役者の間でトラブルが発生したのです。
脚本では入水するとまでは言及されていなかったものの、監督や脚本のイメージでは入水が不可欠という主張でした。
しかし、その当時まだ肌寒い3月の撮影ということもあり、役者としてはできることなら避けたいという主張だったのです。
撮影時間も限られているため、カメラマンだった私は双方の意見をまとめることにしたのです。
入水することで役者が万が一体調を崩してしまったら、まだ残っている撮影が完了できなくなると監督に説明しました。
役者には実際に入水するのではなく、カット割りやアングルなどで入水しているようにすることを提案しました。
勢いの必要なシーンでもあり、その案で監督人からも役者からもOKが出たので、映画は無事完成にこぎつけられたのです。
貴社に入社したあかつきには、このアイデア力を最大限発揮してクライアントなどと意見が食い違ったとしても、アイデアをもって妥協点を見つけます。
この例文のポイントは、双方を説得したうえで妥協点に落ち着いたという部分です。
立場の違いなどによってお互いの主張がぶつかることはよくあることです。
そこで妥協点を見つけることによって、トラブルを防いでプロジェクトや業務を遂行できるとアピールしましょう。
アルバイト
大学生時代、アルバイトをしていたファミレスでアルバイトリーダーに任命されていました。
年末年始の時期になると、どうしてもアルバイトの出勤率は下がります。
誰もが友人や知人と過ごしたり、自宅でゆっくりしたりしたいのでシフトには入りたがりません。
ある日、急な病欠により、その人数では到底さばききれない可能性があると判明しました。
しかしそれではお店の営業に支障が出てしまいます。
みんなの事情を聞きながら、人数が足りない日は入れる人を探して、出勤してもらえるようお願いしました。
余裕のある日には、変わって出勤してくれた人に休んでもらうなどバランスを意識してきました。
その結果年末年始であるにもかかわらず2年連続、最大人数の8人で営業することが可能となったのです。
この例文ですが、全員の都合をしっかりとヒアリングしたうえで、スケジュールに合わせていることが評価に値するでしょう。
ただお願いをすることで出勤してもらうというだけでなく、無理を聞いてくれたことに対して対価をしっかりと付与しています。
調整力を端的に示すことが可能でしょう。
ボランティア
私は大学1年生から地域のボランティア団体に所属し、そこでボランディア参加者の増加を目標に行動しました。
情報を広めることで新しい参加者を増やしていきましたが、それだけでは組織が安定する人数の確保には程遠かったため、参加者の定着率を上げることに注力しました。
まず、途中辞退をしてしまった人から、理由を聞きどこに課題があるかを把握し、その声を基に改善策練っていきました。
理由として、すでに仲が良い人同士でコミュニティが出来上がっており、ボランティア先に知人がいない場合、参加を継続しにくいといったものが多く挙がりました。
そこで参加者に対して経歴や学部、趣味等のアンケートを取り、共通点のある人同士でグループを作り、初めての人同士でも馴染みやすい空気感を作っていきました。
組織内での親密な仲が広まり、昨年40%の定着率を今年は70%まで引き上げる事に成功しました。
このように、課題に対してチームで取り組める環境を作る調整力を活かし、入社後も様々なプロジェクトに積極的に取り組んでいきたいと考えています。
ボランティア活動の中で、「人員不足」という課題に対して自分のアイデアを使い、チーム全体で課題を解決できるような基盤・環境を作ったエピソードを述べています。
これは、チームの状況を把握し、調整できる能力であると言えます。
インターン
この強みは、大学3年生の際に参加したインターンシップで活かされました。
私は新商品の企画立案をするチームの一員として、プロジェクトを進めていました。
しかし、プロジェクトを進めるにあたり、チーム内で意見が対立し、議論が停滞するという課題がありました。
この課題を解決させるために、私はまず、全員の意見を整理し、それぞれのメリットとデメリットを可視化することに取り組みました。
そして、対立している意見の中から双方の良い部分を抽出し、新たな提案として提示することで、全員が納得できる形にまとめました。
また、その後の進行をスムーズにするため、作業の役割分担を明確化し、進捗管理も行いました。
結果として、チーム全員が納得する新商品の企画を期限内に完成させることができ、最終プレゼンでは高い評価をいただくことができました。
貴社に入社した際も、この調整力を活かし、チームの力を最大化させることで貴社の目標達成に貢献していきたいと考えています。
ゼミ
この強みは、大学のゼミ活動で卒業研究のテーマを決定する際に活かされました。
私たちのゼミでは、研究テーマをグループで選定する必要がありましたが、議論が紛糾し、メンバー全員が納得するテーマを見つけることができないという課題がありました。
この課題を解決するために、私はまず、各メンバーの意見や希望を丁寧にヒアリングし、それぞれの意見がどのような背景や目的を持っているのかを整理しました。
その上で、共通する要素を探し出し、全員が納得できるテーマの候補を提案しました。
また、決定後の研究進行をスムーズにするため、計画表を作成し、各メンバーの役割分担を明確にしました。
結果として、メンバー全員が満足するテーマで研究を進めることができ、ゼミ内での成果発表では教授陣からも高い評価をいただくことができました。
貴社に入社した際には、この調整力を活かし、プロジェクトチーム内での意見を取りまとめ、目標達成に向けたスムーズな進行を支える存在になりたいと考えています。
留学
この強みは、大学時代のカナダ留学中に行われたグループプロジェクトで発揮されました。
このプロジェクトでは、異なる国籍や文化を持つメンバーで共同作業を行いましたが、文化や価値観の違いから、意見がまとまらず、作業が停滞するという課題がありました。
この課題を解決するために、私はまず、各メンバーが抱える意見や懸念をしっかりと傾聴し、それらを一つひとつ整理しました。
その後、共通するゴールを明確にし、それに基づいた役割分担を提案しました。
また、進行状況を管理するためのスケジュールを作成し、チーム全員が主体的に作業に取り組める環境を整えました。
結果として、全員の意見を反映した内容でプロジェクトを完成させることができ、最終発表では教授から高い評価を受けることができました。
貴社に入社した際も、異なるバックグラウンドを持つ人々との連携を円滑に進めることで、チームとしての成果を最大化し、貴社の成長に貢献したいと考えています。
【自己PRで調整力をアピールするには】志望職種別例文
続いては自己PRで調整力をアピールする際におすすめの例文を、志望する職種ごとに紹介していきます。
あなたが就職したいと思っている職種の中で最も近いものを選び、参考にしてみてください。
実際に自分の作成した自己PRと見比べることで、何が足りないのか、何が優れているのかが分かりやすいかもしれません。
事務職
営業職
接客・販売職
エンジニア職
企画職
この強みは、大学のゼミ活動で学内イベントの企画を担当した際に発揮されました。
私たちのゼミでは、新入生向けのオリエンテーションイベントを企画していましたが、企画を進めるにあたり、エンタメ性を重視する意見と実用性を優先する意見が対立し、全員の意見がまとまらないという課題がありました。
この課題を解決するために、私はまず全員の意見をヒアリングし、各意見の背景にある目的や期待を整理しました
た。
その後、両者の意見を反映できるプログラム案を提案しました。
たとえば、エンタメ要素を前半に取り入れ、後半には新入生が実用的な情報を得られるセッションを設ける構成にしました。
この案に対して全員が納得し、スムーズに準備を進めることができました。
結果として、新入生からは「楽しさと実用性が両立したイベントで役立った」と高い評価をいただきました。
貴社に入社した際も、この調整力を活かして、多様なステークホルダーの意見をまとめながら、効果的な企画を提案し、プロジェクトの成功に貢献したいと考えています。
【自己PRで調整力をアピールするには】完成度を高めるために
様々な例文を確認し、自己 PR を作成し終わった人もいることでしょう。
しかし、時間に余裕があるならば是非行って欲しい対策がいくつかあります。
以下の3つを行うことでより質の高い自己 PR を作成できるので、是非行ってみてください。
声に出して読んでみる
どれだけ自分では完璧な自己 PR を作成できたと思っていたとしても、意外と文脈がおかしかったり、誤字脱字があったりする場合もあります。
しかし、黙読しているだけではなかなかおかしな点に気づけないことが多いです。
そこでおすすめなのが、声に出して一つ一つの文章をゆっくり読んでみることです。
これにより「結論」「理由」「エピソード」「学んだこと」「今後にどのように活かすか」「再度結論」それぞれの繋がりがおかしくないかについて確認することができます。
また、誤字脱字をしていないと自信がある人ほど、意外と間違えていることがあるので、ゆっくり読んでみてください。
誤字脱字が多いと、注意散漫な人材であるとみなされてしまい、就職した後もミスが多い人であると思われてしまう可能性があります。
完成した後、少し時間を置いてからゆっくり、声に出して読んでみましょう。
他の人に添削してもらう
自分一人だけで確認していると、どうしても客観的な視点で確認することはできません。
可能な限り、「これは自分が書いたものではなく、他人が書いたものだ」という考えを持ちながら読むことで、ある程度、客観的に見ることができます。
しかし、数時間自分が書いた文章とにらめっこするよりも、数人の友人に一度読んでもらう方がよっぽど効率的であると言えます。
特に、就活に取り組んでいる友人がいるならば、お互いの自己 PR を確認し、悪いところと良いところを指摘し合うのも良いでしょう。
同じ業界を受けた先輩がいるならば、添削してもらうのも選択肢の一つです。
可能な限り多くの人に確認してもらい、特にエピソードの部分で分かりにくいところがないか質問してみましょう。
就活エージェントに相談してみよう
確かに、友人や先輩に確認してもらうのは非常に有効な選択肢の一つですし、時間に余裕があるならば積極的に行いたいところです。
しかし、最も根本的な解決方法として就活のプロに相談することが挙げられます。
お金がかかるところもありますが、ジョブコミットの場合は完全無料で自己 PR はもちろんのこと、志望動機やガクチカの添削を行ってくれる上に、面接対策まで行ってくれます。
毎年、何人もの就活生を成功させる企業へ送り込んでいる優秀なスタッフが徹底的にサポートしてくれるので、信頼性が高いと言えるでしょう。
もし興味がある人は、下記のリンクから登録してみてください。
まとめ
調整力というのは仕事をするうえで必ず求められる能力です。
実際にその能力が備わっていると判断されるためには、具体的に明示しなければなりません。
今回ご紹介した内容は、どれも自己PRをするうえで欠かせないでしょう。
構成にも気をつけつつ文章を作っていくことで、問題ない自己PRが作成できるかと思います。
あとはそれを実際に伝える練習も必要です。 採用されるために、調整力をちゃんとアピールしましょう。