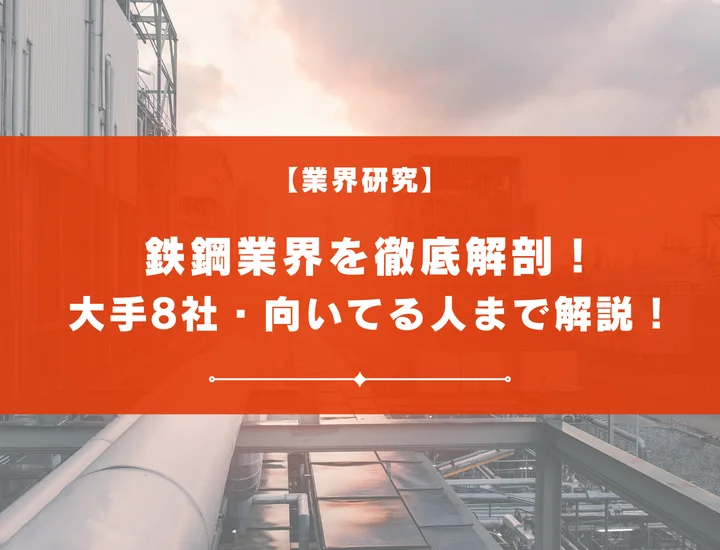明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・就活は平均で何社落ちるのか
・落ちた際の切り替え方法
・就活を成功させるコツ
・就活が思うように進んでいない人
・自分と周りとの立ち位置を比較したい人
・就活対策をしたい人
これから就活を始めようという人も、すでに就活真っ最中でいくつか合否の連絡が来ているという人も、就活の中でいったい何社の選考に落ちるのが普通なのかは気になるところでしょう。
連続してお祈りメールを受け取っていれば、自分はこのまま内定をもらえないのではないかと不安になるかもしれません。
今回は、就活市場全体の平均から、就活生の平均エントリー数や、不採用になった数などを紹介します。
内定を勝ち取るために大切な考え方や、対策の方法にも触れていますので、興味をお持ちの方はぜひ参考にしてみてください。
目次[目次を全て表示する]
【就活は平均何社落ちる?】全体を知ろう!
就活中、一社も落ちることなく応募した企業すべてから内定をもらったという人は、まずいないでしょう。
一般的には、不採用の連絡をもらうことの方が多いです。
とはいえ、あまりに内定がもらえないと不安になることもありますし、その不安が次の選考に響いてはもったいないです。
まずは、就活市場全体の傾向を見ていきましょう。
平均15社
リクルート就職未来研究所の調査によると、就活生は平均で15社の選考に落ちているということがわかっています。
エントリーシートなどの書類を提出し、選考にエントリーした企業数の平均は17社です。
その中で内定、もしくは内々定が出た企業数の平均が2社となっています。
多くの人が、エントリーしたうちのほとんどの企業に落ちていることがわかります。
もちろん、これらはあくまでも平均値です。
「平均よりもたくさん落ちているから自分はダメ」「平均よりも少ないから大丈夫」などと一喜一憂せず、次のアクションについて冷静に考えることをおすすめします。
エントリーシートは平均30社
多くの企業から不採用通知を受け取っているということは、それだけ多くの企業に応募しているということでもあります。
プレエントリーを含め、就活生が何らかのアクションを起こした企業数の平均を調べてみると、おおよそ30社、またはそれ以上とされています。
そのうち、次の選考に進めるのは約半数です。
これは、大手から中小企業まで含めた場合の数字ですが、エントリーシートを提出して受かる確率は40〜50%だと企業側も明かしています。
多くの就活生が、エントリーシートで落ちてしまう経験をたくさんしているとも言えるでしょう。
【就活は平均何社落ちる?】どのフェーズで落ちることが多い?
では一般的に、就活ではどのフェーズで不採用になってしまうことが多いのでしょうか?
まずはそれぞれのフェーズに関する、落ちる人の割合をここで詳しく紹介します。
これから就活を始めようと考えている人は、このデータをもとにどんな対策をすれば良いのかを、しっかり考えるようにしてみてください。
そうすれば、少しでも落ちてしまう確率を下げることができるでしょう。
ESまで:約50%
まず就活の際には、いきなり面接からスタートしないケースも珍しくありません。
つまり、最初はエントリーシートを出して書類選考を受けることもよくあります。
もちろん書類選考の段階から就活はスタートしているため、この段階で落ちてしまう人も出てくるでしょう。
一般的に書類選考で落ちる人は、平均で50%といわれているため、2人に1人は落ちるものだと認識しておいてください。
特に人気の高い企業や有名な大企業になってくると、その分競争率も高くなることが想像できるため、よりいっそう通過するハードルは高くなることが予想できます。
だからこそ、エントリーシートはきちんと企業とのマッチ度をアピールできるように、入念に考えて書かなければいけないのです。
グルディスは企業による
志望する企業によっては、エントリーシートによる書類選考や面接以外にも、グループディスカッションを求めてくるケースがあります。
特に大きな企業ほどグループディスカッションを経験することになるため、あらかじめ対策は必要不可欠だと思っておいた方が良いでしょう。
また、グループディスカッションは企業によって選考基準が大きく変わってくるのが特徴です。
そのため、厳密に何%の人が落ちているのかまでは計れません。
なお、グループディスカッションは全員が通過することもあるため、誰か1人が必ず落とされるとも限らないのがポイントです。
だからこそ、あらかじめグループディスカッションに関する動画を色々見ながら、対策するようにしてください。
ちなみに、こちらに対策方法を載せた記事があるので、気になる人は合わせて要チェックです。
テスト系:約40%
就活は場合によって、テストを受けさせられることもあります。
なお、ここでいうテストとは、一般的に玉手箱やSPIのようなものを指すため、あらかじめこちらも対策しておく方が無難です。
ちなみに、どのようなテストなのかというと、簡単にいえば知的能力や性格適正を測定するためのテストになっています。
例えば、言語問題や計数問題、英語問題など、その人の基礎学力や論理的思考力を計る内容です。
事前に過去問に挑戦しておけば本番でも良い結果が出しやすくなるため、忘れないようにしましょう。
本格的に対策したい人は、以下の記事もぜひチェックしてみてください。
一次面接:約40%
書類選考やテストなどを終えて、ようやく一次面接に進むことも少なくありません。
この段階では、全体の40%ほどの人が落ちてしまう傾向にあります。
一次面接ではエントリーシートに沿って、もっとも基本的な質問をされることが多いので、あらかじめ何を言われてもスムーズに答えられるようにしておく必要があるでしょう。
特にここで注目されるのは、どちらかというと就活生の面接態度です。
例えば、きちんと人の目を見てコミュニケーションが取れているのか?背筋を伸ばして話せているのか?など、細かいところまで見られてしまいます。
だからこそ、常に良い印象を残せるように、マナーを守って対応できるようにしておかなければいけません。
二次面接:約45%
一次面接を終えたあとは、さらに二次面接に進むことになります。
最初から正社員として入社する場合は当然のようにあるものなので、一次面接を通過したからといって安心してはいけません。
ここでは平均的に45%ほどの人が、不採用通知をもらいます。
そのため、このフェーズでも2人に1人は落ちてしまうものだと思っておきましょう。
この二次面接では、一次面接とは異なりさまざまな質問をして、就活生がどのような人材なのかを深掘りしていくのがメインです。
そのため、場合によっては想像もしていないようなことを聞かれるパターンもあります。
だからこそ、事前に自己分析や企業研究をきちんとしておいた方が良いでしょう。
最終面接:約50%
二次面接のあとは、いよいよ最終面接に臨むことになります。
このタイミングでは、その企業の社長や役員といった人と直接会話をすることになるでしょう。
会社の経営陣が、本当に活躍しそうな人材なのかどうかをその目で確かめるのが目的なので、いかに自分が役立つ人材になれるのかどうかを、うまくアピールしなければいけません。
ここでも2人に1人は落ちることが多いため、最終面接に来たからといって気を抜かないようにしてください。
その経営陣がどのような人なのかを、事前に調べておくとスムーズにコミュニケーションが取りやすくなるので、できることなら会社HPやSNSをチェックしておくのがおすすめです。
【就活は平均何社落ちる?】就活生に伝えたいこと
「周りの人はどれくらい落ちているのか」「自分は本当に受かるのか」と、不安になることもあるでしょう。
そんな不安がつきものの就活を乗り切るために、知っておいてほしいことを以下にまとめます。
就活に対する考え方を少し変えるだけでモチベーションを上げることもできるため、ぜひ押さえておくようにしてください。
落ちるのは当たり前であるということ
福利厚生が充実している会社や有名な企業は、当然ながら希望者も多く、競争率が高くなります。
多くの人が受ける企業であれば、旧帝大生がたくさんいることが予想されます。
また、仕事において必要な能力に秀でている人がいる可能性も高いため、内定を得るのは容易ではありません。
面接やグループディスカッションなどの選考に進んだ際、「東大と京大しかいなかった」ということが多々あり得るのが大手企業の選考です。
同時に、企業側もできるだけ優秀な就活生を採用したいと思っているので、落ちてしまうのも仕方がないことなのです。
また、最終的に就職するのは一社なので、「志望度の高い企業のうち一社から内定をもらえればいいのだ」ということを意識して今後の選考に臨むことが重要と言えるでしょう。
気持ちの切り替えが大切
本命の企業で不採用になってしまうと、一気に落ち込んでしまって何も手がつけられない状態になる人も少なくありません。
もちろん本気で臨んだからこそ、その分ショックも大きくなってしまうと思います。
しかし、落ちてしまった事実は変えることができませんし、それだけで就活をやめるわけにもいかないでしょう。
だからこそ、気持ちをすぐに切り替えることも大切です。
自分のことをもっと理解してくれる、相性の良い企業が必ず他にもあると自分に言い聞かせて、次に進むようにしてください。
また、一度好きなことをして気分をリフレッシュすることで、再挑戦するモチベーションも上がる可能性があるので、決して諦めないでください。
就活は企業と学生のマッチング
就活は、あくまでも企業と学生のマッチングの場であることを忘れないようにしましょう。
企業の採用担当者は、就活生と企業がマッチするかどうか、自社が欲している能力があるかどうかをチェックしています。
同時に、就活生自身も、今受けている会社が自分に合っているかどうかをしっかりと判断していくことが大切です。
就活の中で、自己分析と業界研究や企業研究が必要だと言われるのは、ここで必要になるためです。
企業の求める人物像と自分自身の特性をよく見極めて、後悔のない決断をするようにしてください。
PDCAを行う
就活中、選考に落ちてしまうことは特に問題がない、ごく当たり前のことだと先に説明しました。
しかし、お祈りメールを受け取ってそのまま次の選考を受けるだけでは、次も落ちてしまう可能性が高いと言えます。
そのため、なぜ今回落ちてしまったのかをチェックし、対策していくことが重要です。
そこで活用したいのが「PDCAサイクル」です。
以下に、その内容を具体的に説明します。
Check:評価
まず、なぜ今回の選考に落ちてしまったのかを分析・評価しましょう。
筆記試験でつまずいてしまったのか、面接で緊張してうまく話せなかったのか、事前の準備不足で質問に答えられなかったのか、どこに原因があるかはっきりさせることが大切です。
特に面接で落ちてしまった場合、うまく話せなかった原因が何なのかを突き詰めて考えることが重要です。
できる限り細かく分析して、気づいたことはノートやスマホのメモアプリなどに書き留めておきましょう。
Action:改善
次に、評価(Check)の中で出た、選考に落ちてしまった原因を改善・解消するための具体的な方法を検討します。
筆記試験でわからない問題があったのであれば、筆記試験の勉強をする計画を立てます。
面接の中でうまく答えられない質問があったなら、あらためて自己分析や企業研究など行い、きちんと答えられるように対策することが必要です。
学校の勉強と同じで、失敗や間違いを潰していくつもりで取り組みましょう。
Plan:計画
改善策を書き出せたら、具体的なプランを立てていきましょう。
たとえば面接対策の場合、「授業のない火曜2限の時間を面接練習の時間にする」「木曜4限のゼミが終わったあとに就活友達と面接対策をする」などと、具体的にスケジュールを決めてしまうのがおすすめです。
もちろん、大学の勉強も並行して行わなければなりません。
単位を落としてしまわないよう、無理のない計画を立てることを忘れないようにしてください。
Do:実行
選考に落ちてしまった原因を突き止め、改善策を立ててその計画までできたら、あとは実行するのみです。
ここが最も大変な段階ですが、くじけずに計画通り行うことで、自信にもつながります。
続けられるかどうか不安な場合は、就活仲間や家族と一緒に協力してもらうと良いでしょう。
やり切ることで、自分自身をレベルアップさせることが可能です。
準備を徹底する
面接や筆記試験に臨む際、事前準備が必要です。
筆記試験であれば、事前に勉強しておくことで落ち着いて試験に臨めますし、類似問題が出たときには悩まず回答できるため、試験時間にゆとりもできます。
また、面接を控えている方なら、よく聞かれる質問に対する回答を考えておくと良いでしょう。
特に志望動機や自分の長所・短所、将来の展望などは聞かれることが多いので、きちんと回答できるよう、準備しておくことをおすすめします。
また髪型や服装など身だしなみのチェックも、面接の事前準備として必要不可欠です。
ここが甘いと、面接官から「だらしない人」「準備ができない人」だと判断され、最終的に落ちてしまう可能性があるので注意しましょう。
【就活は平均何社落ちる?】就活生必須のストレス対策5選
就活中は忙しいうえにメンタルにかかる負荷も多く、なかには体調を崩してしまう方も少なくありません。
しかし、体調不良で貴重な時間を失ってしまうのはもったいないことです。
また、ストレスが溜まると普段のパフォーマンスも下がってしまいます。
ここでは、就活生に必須のストレス対策法を5つご紹介します。
①本を読む
読書は、ストレス解消におすすめの方法です。
イギリスのサセックス大学の研究によると、6分間の読書でストレスレベルを68%も軽減できることがわかっています。
読書と聞くと、小説を読んだ方が良いのか悩むかもしれませんが、ビジネス書などを読んで新しいことを学ぶのも効果的です。
雑誌や絵本、漫画などもストレス解消につながるので、ジャンルを選ばず自分の好きな本を読みましょう。
また、普段の生活の中で複数のことを同時にこなさなければならない場面が多い学生は、読書のみに集中できる環境を整えることをおすすめします。
シングルタスクにすることで、脳への負荷が取り除かれ、より効率良くリラックスできます。
コーヒーや紅茶を飲みながら、ゆったりとした気持ちで自分の好きな本を読みましょう。
②仲の良い友達と話す
やらなければいけないことが多い就活生にとって、友達とカフェに行ったり飲みに行ったりすることは、一見時間の無駄に思えるかもしれません。
しかし、仲の良い友達と他愛のない会話を楽しみリフレッシュすることも大切です。
就活であった失敗談を聞いて笑ったり、逆に成功した方法があれば共有したりすれば、有意義な時間を過ごせます。
「エントリーシートがなかなか通らない」「面接で毎回緊張しすぎてうまく話せない」など、悩み相談ができるのも友達だからこそです。
また、友達の悩みを聞くことで、「戦っているのは自分だけではない」と再確認することもできます。
行き詰まったときは、就活仲間と近況報告し合いながらストレスを発散させると良いでしょう。
③自分の思いをノートに書く
ストレスは、抱え込んでばかりいると気分も良くありませんし、体調にも影響してきます。
何かしらの形でアウトプットすることができれば、胸のうちにあるモヤモヤを解消することができます。
イライラすることや不満があったら、ノートにそれを書き出してみましょう。
やり方は、そのとき思ったことをひたすら書き出していくだけです。
手書きのノートがない場合、スマホやPCに打ち込んでください。
書き出していくうちに、少し気持ちがスッキリしていることに気づくでしょう。
また、悩みごとを書き出していくうちに、頭の中が整理されて、解決策が浮かぶ場合もあります。
ノートに書き出すことはストレス発散になるほか、自分の考えをまとめることもできるため一石二鳥です。
④運動をする
体を動かし汗を流すことは、気分転換にもなりつつ、ストレスを軽減してくれる効果が高いので、就活中の方には習慣化してほしいことのひとつです。
運動をすると、心に安らぎをもたらすセロトニンというホルモンが分泌され、荒れていた気持ちが徐々に落ち着くようになります。
また、ストレス源から離れて運動に集中する時間を持つことで、イライラも軽減されます。
気持ちが安定するのと同時に、運動は体のバランスも整えてくれるので、健康第一の就活において必須の行動と言えるでしょう。
しっかりと汗を流せば、その日の夜はぐっすりと眠れ、また翌日から活動的に過ごすことができるようにもなります。
「あまり運動が得意ではない」という人は、15分くらいの軽い運動でも効果があるのでぜひ試してみてください。
⑤睡眠時間を確保する
ストレス解消と同時に、ストレス耐性を高めてくれるのが「睡眠」です。
「起きたとき、前日のイライラが少し収まっていた」という経験を持っている方は多いでしょう。
十分な睡眠を取ることによって自律神経のバランスが整い、イライラしにくくなります。
逆に、睡眠不足の状態になると、集中力が低下し、イライラしやすくなります。
また、免疫力も低下するため、体調を崩してしまうことも珍しくありません。
一度この負のスパイラルに陥ると、抜け出すまでにはかなりの時間を要するので、1日でも早く抜け出すようにしたいところです。
毎日忙しいと、どうしても睡眠を削ってしまいがちですが、夜遅くなってしまった翌日は早めに布団へ入るなど、意識して睡眠を確保するようにしてみましょう。
【就活は平均何社落ちる?】内定を取るために今からやってほしいこと3選
ここまでの内容を振り返り、次こそ内定を取るためにまずどんなアクションを起こせば良いか、考えてみましょう。
やるべきことはたくさんありますが、その中でも今すぐ実行してほしいポイントを3つに絞りました。
まずは、以下のことから手をつけていきましょう。
①落ちた試験の振り返り
就活での失敗を成功につなげるためには、PDCAサイクルを回すことが必要だと先に述べました。
「Do(実行)」の結果として選考に落ちてしまった今、まずすべきことは失敗の振り返り、すなわち「Check」(評価)です。
時間が経つほどに選考を受けたときの記憶も薄れていってしまうので、なるべく早めに取りかかることが大切です。
そして、受かるために必要な改善点を徹底的に洗い出し、できる限りの準備を進めていきましょう。
②次の準備を徹底する
先ほども軽く触れましたが、失敗の原因と次の対策が考えられたら、次の選考に向けて準備しましょう。
自己分析はもちろん、企業研究や業界研究も一から行います。
焦る気持ちはわかりますが、時間をかけて徹底的に行いましょう。
面接練習が必要だと判断したなら、周囲の協力も得て練習を重ね、しっかりと準備を進めていきます。
地道な作業ですが、それこそが就活で内定を勝ち取るための近道です。
一つひとつの積み重ねが自信につながります。
③生活習慣の見直し
先に紹介した「ストレス対策5選」を参考に、生活習慣を見直してみましょう。
もしかしたら、今回の失敗も心や体に疲れが溜まっているために、本来の力を発揮できなかっただけなのかもしれません。
やるべきことに追われてパンクしてしまう前に、定期的にストレスを発散し、ストレスとうまく付き合っていくことで、就活準備の効率アップも目指せます。
もちろん、紹介した方法をすべて実践する必要はありません。
自分に合ったストレス対策を行いましょう。
④会話でキャッチボールをすることを意識する
面接では、その人の学歴やガクチカだけで判断されるわけではありません。
つまり、コミュニケーション力も必ず問われます。
だからこそ、相手からの質問に対してスムーズに返答できるようになっておかないといけないのです。
コミュニケーション能力が低いと判断されるとそれだけで落ちる原因になることもあるため、普段から人としっかりコミュニケーションを取るようにしてみてください。
うまく会話のキャッチボールができるようになれば、必ず面接でも活かされるはずです。
相手は友達でも良いですし、家族や他の知り合いに協力してもらってもまったく問題ありません。
⑤身だしなみと面接マナーを確認する
内定を確実に取りたいなら、大前提として身だしなみや面接マナーのことも、きちんと理解しておくことが必要です。
なぜなら、社会人としてもっとも基本となる部分になるからです。
どんなに良い自己PRができたとしても、マナーを守れていないことが相手に伝わってしまうと、結局落ちてしまう原因になります。
もちろん最終面接どころか、二次面接にすらたどり着けない可能性が高いため、周りの人からアドバイスをもらいながら、常に失礼のないように気をつけるようにしましょう。
そうすれば、余計な理由で不採用になることはありません。
就活エージェントに頼ろう!
就活を自分1人の力だけで進めるのは難しいものです。
ノウハウを持っている就活エージェントに頼ることが、内定獲得への近道になります。
専任のアドバイザーが、エントリーシートの添削や模擬面接などをしてくれます。
モチベーションを保てるほか、無駄なく準備ができるのが魅力です。
就活の悩みについても、プロの視点からアドバイスをくれるため、安心して相談できます。
利用はもちろん無料なので、気になる方はぜひこちらのサイトにアクセスしてみてください。
まとめ
多くの時間を費やして準備し臨んだ選考でも、落ちてしまうことはよくあります。
特に大きな企業や条件の良い会社であればあるほど、採用人数よりも圧倒的に多い就活生が応募しているため、「50社受けたけどダメだった」というケースも少なくありません。
しかし、最終的には入るのはたった一社なので、過度に落ち込むことはありません。
選考に落ちるのは非常につらいことですが、本記事の内容を参考にし、ストレスとうまく付き合いながら今回の失敗を次につなげましょう。