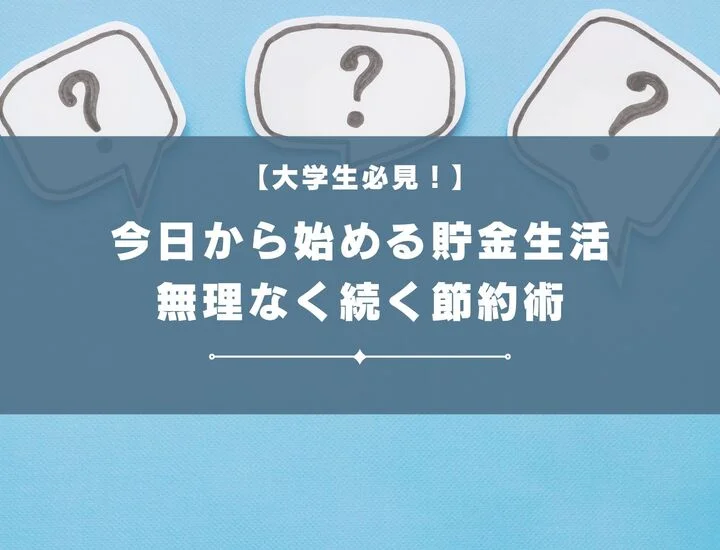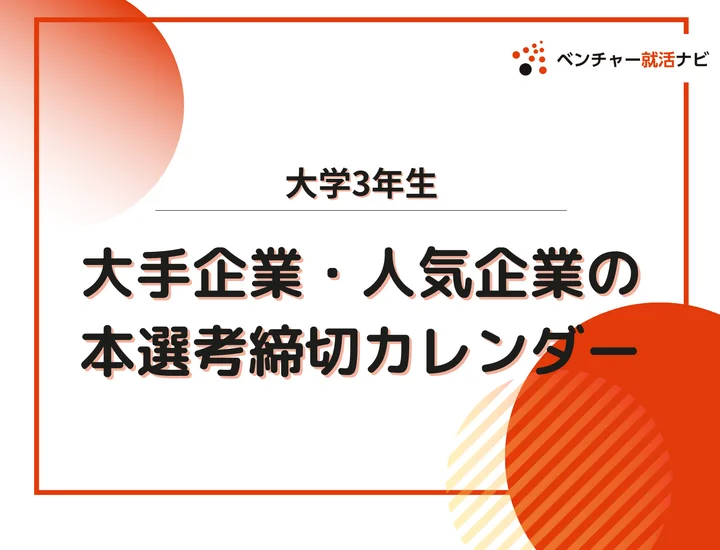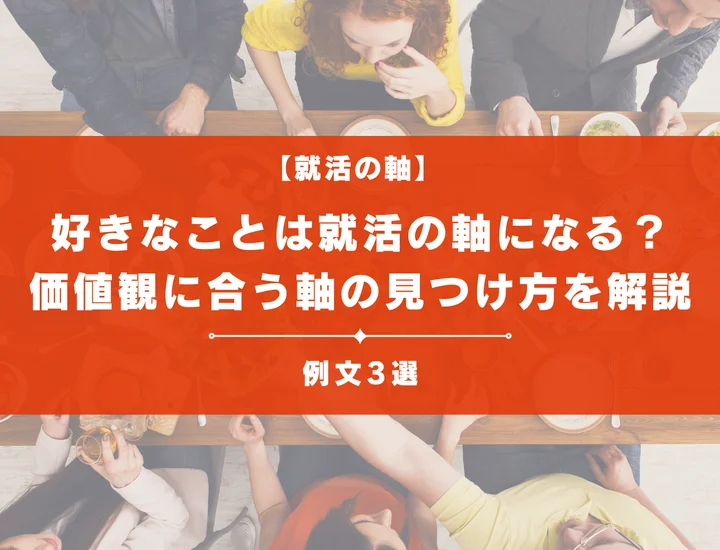・ESは「ですます調」「である調」どちらが正しいのか
・ESの語尾について
・ESの語尾に迷っている人
・そもそもどんな構成がいいのかわからない人
・評価されるESを作成したい人
就活をはじめてESを作成しようと思ったときに、まずは書き方に悩む学生は多いと思います。
特に、敬語で書くべきかなどの口調に関する部分は、分かりにくく悩むところでしょう。
今回はこれらの「ですます調」と「である調」のどちらが良いのかについて解説していきます。
お互いのメリット、デメリットについても解説しますので、ぜひ最後まで読んでください。
就活をしていると時間に追われる日々でしょう・・!
そんな中ES添削を依頼したくても添削に時間を取られタイムロスになってしまいます。
そこで就活のプロが監修「ES添削 by Ai」がおすすめです!
LINEと登録でES添削が約10秒、完全無料の使い放題です!
ぜひこちらの添削ツールを使用して効率良く就活を行なってください。
目次[目次を全て表示する]
ESは「ですます調」「である調」どちらが正しい?
どちらが正しいのかといった部分であれば、結果的にはどちらを使っても問題はありません。
「ですます調」を用いることで、相手に丁寧な印象を与えることができるため、ESを見ていただくのが目上の人で敬意を表したいと考え、ですます調を使います。
一方で「である調」は書いている内容に説得力を与える効果があります。
このため、自身の主張を強く訴えたいと考える方は、である調を使います。
これらの口調によって、例え同じような内容であったとしても、ESから受ける印象は異なってきます。
どちらが正解といったわけではなく、自身の考えている目的や伝えたい内容に合わせて使い分けるのが良いでしょう。
語尾は統一させよう
どちらの口調も正しいので、どちらを使っても問題ありません。
ただし、語尾は一貫して統一して使うことが重要です。
語尾がバラバラだと文章にまとまりがなく見えてしまいます。
これでは、読み手にとっても読みにくい文章で、伝えたいこともうまく伝わらない可能性があります。
このため、どちらの口調を選ぶかは問題ではありませんが、使う口調は統一してください。
迷ってしまったら「ですます調」にしよう
エントリーシートの作成において、「ですます調」と「である調」のどちらを使用すべきか迷う就活生は多くいます。
結論として、どちらを選択しても問題ありませんが、判断に迷った場合は「ですます調」を用いることを推奨します。
その理由として、まず「ですます調」は一般的に広く使用されており、採用担当者にとって自然で違和感のない文体であることが挙げられます。
特に、対人関係を重視する職種や、協調性やコミュニケーション能力を求められる企業においては、丁寧な印象を与えやすい「ですます調」の方が適しているといえるでしょう。
さらに、社会人としての基本的なビジネスマナーを備えていることを示すうえでも、「ですます調」は好印象につながる表現です。
一方で、「である調」は論理的で説得力のある文章を構成するのに適していますが、場合によっては高圧的な印象を与えてしまう可能性があります。
また、敬語表現との相性が良くないため、企業への敬意を示す場面では「ですます調」を使用する方が無難です。
そのため、特別な理由がない限り、迷った際は「ですます調」を選択し、統一感のある文章を作成されることをおすすめします。
【例文で比較しよう】「ですます調」と「である調」の例文
私は、計画的に物事を進めることを得意としております。
大学では、ゼミ活動のプロジェクトリーダーとしてチームをまとめ、期限内に成果物を完成させるためにスケジュール管理を徹底いたしました。
特に、チームメンバーが効率的に作業を進められるよう、役割分担を明確にし、定期的な進捗確認を実施いたしました。
その結果、ゼミ内のプレゼンテーションにおいて最優秀賞を受賞することができました。
この経験を活かし、貴社の業務においても計画的にタスクを進め、チームの成果向上に貢献してまいります。
私は計画的に物事を進めることを得意とする。
大学では、ゼミ活動のプロジェクトリーダーを務め、期限内に成果物を完成させるためにスケジュール管理を徹底した。
チームメンバーが効率的に作業を進められるよう、役割分担を明確にし、定期的な進捗確認を行った。
その結果、ゼミ内のプレゼンテーションにおいて最優秀賞を受賞した。
この経験を活かし、貴社の業務においても計画的にタスクを進め、チームの成果向上に貢献したいと考えている。
「ですます調」は、より丁寧で柔らかい印象を与えるため、企業の採用担当者にとって読みやすい文章となる。
一方、「である調」は簡潔かつ論理的な表現が可能なため、説得力が増す特徴がある。
しかし、「である調」は断定的な表現が多くなりがちであるため、場合によっては強い印象を与えてしまうことがある。
一方で、エンジニアやコンサルティング業務、研究職など、論理的な思考が求められる職種においては、「である調」も適切な選択肢となる。
ただし、どの文体を選択する場合でも、一つのエントリーシート内で統一感を持たせることが最も重要である。
結論として、迷った場合は「ですます調」に統一し、企業や職種によって適切に使い分けることを意識されるのが望ましい。
ですます調のメリット・デメリット
「ですます調」は、敬語表現を含むため、柔らかく丁寧な印象を与えやすいことが特徴です。
そのため、多くの就活生が選択する文体であり、無難な選択肢といえます。
しかし、メリットだけでなくデメリットも存在するため、適切に使い分けることが重要となります。
メリット
「ですます調」は、相手に対して礼儀正しい印象を与えやすいです。
エントリーシートは採用担当者が読むものであり、初対面の相手に対しては丁寧な表現を用いるのが基本となります。
「ですます調」を用いることで、社会人としてのマナーを備えていることを示せる点は大きな利点です。
また、この文体の読みやすさにもつながります。
敬語表現を含むため、文章が穏やかで柔らかい印象になり、採用担当者がスムーズに内容を理解しやすくなります。
特に多くのエントリーシートを読む担当者にとって、親しみやすく、負担なく読める文章は好まれる傾向があります。
さらに、「ですます調」は、ビジネスシーンにおいても広く使われるため、社会に出たときの実務的な文書作成能力を示すことができます。
この点は、特に営業職や接客業など、顧客対応が求められる職種では評価されやすいでしょう。
デメリット
「ですます調」は、語尾のバリエーションが少なくなりがちです。
そのため、「〜です。」「〜ます。」が繰り返されることで単調な文章になりやすく、読んでいて退屈な印象を与える可能性があります。
文章のリズムを工夫しないと、ありきたりな表現に終始し、個性が伝わりにくくなるのは欠点といえます。
また、この文体は敬語表現が多くなるため、文章全体の文字数が増えてしまう傾向があります。
エントリーシートには文字数制限があることが多く、限られたスペースの中で多くの情報を伝える必要があります。
そのため、冗長になりがちな「ですます調」は、簡潔に要点を伝えたい場合には不向きとなることもあります。
さらに、敬語の使い方に注意が必要であり、間違った敬語表現を使うと逆にマイナスの印象を与えてしまいます。
「ご教授ください」ではなく「ご教示ください」が正しいなど、細かな敬語の使い分けを誤ると、社会人としての基本的な言葉遣いが身についていないと判断される可能性があります。
である調のメリット・デメリット
「である調」は、主張を明確にし、論理的な文章を構成するのに適した文体です。
特に、コンサルティング業界や研究職、ジャーナリズムなどの業界では、簡潔かつ説得力のある表現が求められるため、この文体が好まれることがあります。
しかし、「ですます調」に比べると、堅苦しい印象を与えることもあり、使い方には注意が必要となります。
メリット
「である調」の最大の利点は、文章に説得力を持たせられる点です。
断定的な表現が多くなるため、自信に満ちた力強い印象を与えることができます。
特に、論理的な思考力や分析力をアピールする際には、的確な表現を用いることで、内容に一貫性と信憑性を持たせることができます。
また、「である調」は、敬語表現が少なく、文章が簡潔になるため、少ない文字数で情報を伝えるのに適しています。
エントリーシートの文字数制限が厳しい場合には、無駄を省いた表現が求められるため、「である調」の方が適していることも多いです。
さらに、語尾のバリエーションが豊富であるため、文章が単調になりにくく、読みやすい流れを作りやすくなります。
特に、長文を書く際には、文末表現を工夫しながら、リズムよく読み進められるように調整しやすい点がメリットです。
デメリット
「である調」は、ビジネス文書としては適しているものの、対人関係を重視する場面では堅苦しい印象を与えがちです。
特に、採用担当者が応募者の人柄を重視している場合には、柔らかさが欠けることで親しみを感じにくくなる可能性があります。
そのため、営業職や接客業など、人と接する機会が多い職種を志望する場合には、適していないこともデメリットとして挙げられます。
また、断定的な表現が多いため、文章によっては上から目線の印象を与えてしまうことがあります。
「私はこの分野において十分な知識を有している」と書いた場合、自信に満ちた表現になる一方で、採用担当者には高圧的に映る可能性につながります。
そのため、適度に謙虚な表現を交える工夫が必要です。
さらに、「である調」は敬語との相性が悪く、企業に対する敬意を示しにくいという問題です。
エントリーシートでは、企業への敬意を示すことが重要であるため、企業に対する敬語表現が使いづらい「である調」は、場面によってはふさわしくないと判断されることも頭に入れておきましょう。
ESで企業が評価しているポイント
ですますで書くことのメリット・デメリットがわかったところで、そもそもESを通して企業は何を評価しているのかを見ておきましょう。
相手の評価ポイントを知っておくことで、どのように書くべきか、どんなことを書くべきかが見えてきます。
今回は3点紹介しているので、これを踏まえたうえでESの作成に取り掛かりましょう。
企業にマッチしているかどうか
まず1点目は、企業へのマッチ度です。
ESでは志望動機、自己PR、ガクチカなどが聞かれ、自分の考え方や強みを文面上でアピールします。
そのうえで、企業が求める人物像にどれだけマッチしているかを判断されます。
まずは企業のホームページや説明会でどんな人材を求めているのか、どんな人材が活躍しているのかを把握したうえで、自分もそのような能力があり貢献できることをアピールしましょう。
志望度の高さ
次に志望度の高さです。
これはESに限らず、すべての選考過程で見られることではありますが、はじめである書類選考でも十分に志望度の高さは見られています。
志望動機や自己PRで熱意をどれだけ伝えられるか、また企業を選んだ理由が明確になっているかといった部分で志望度の高さは判断されます。
文章を構成した後は、何度も読み返し、抽象的な表現に対しては「これはなぜ?」という疑問を繰り返すことで、より深掘りをした内容にしていきましょう。
論理的思考能力
最後に「論理的思考能力」が挙げられます。
これは主に文章の書き方、伝え方で判断されます。
結論ファーストでいかに伝わりやすく、かつ内容は深く文章を構成できているかを見て、論理的に考えを持ち、それを相手に表現することができるかどうかを評価しています。
ESを書き出す前にしておくべきこと
ここまで「ですます調」「である調」それぞれのメリットや企業の評価ポイントを紹介してきましたが、ESを書き出す前に準備しておくべきことについても解説しておきます。
ESは企業と接点を初めて持つ部分であり、第一印象を決める重要なものとなります。
そのため書き出す前に万全な準備をしてから、作成することも選考突破のカギとなります。
自己分析を徹底しよう
就職活動において欠かせないのが「自己分析」です。
自己分析は様々な方法がありますが、自分の強みや働くうえでの軸を明確にする目的があります。
自己分析を丁寧に行っていないと、いざESを書き出すときや面接の際に自信を持った回答ができず、企業に好印象を与えることも難しくなります。
より詳しく自己分析について知りたい方は以下の記事を参考にしてみて下さい!
業界・企業分析をしておこう
業界分析と企業分析も重要な準備と言えます。
特に志望動機を述べるうえで、なぜその業界を志望するのか、そしてその業界の中でなぜその企業を選んだのかを明確に持っておくことで、熱意を伝えられるだけでなく、説得力のある文章を作ることができます。
より詳しい分析方法を知りたい人は、業界分析、企業分析それぞれ以下の記事を参考にしてみて下さい。
ESを書く際のコツ
様々なポイントで企業が評価をするESですが、書く際のコツがあります。
これは、どの企業のESいおいても意識するべきポイントであるため、ESを書き出す前にあらかじめ頭に入れておきましょう。
アピールしたいことを絞る
1つの質問に対してアピールしたいことは1つ、というように伝えたい内容を絞った文章を構成しましょう。
例えば自己PRなどで、自分の強みを複数挙げて文章を作ってしまう就活生は多くいますが、アピールしたいことが増えるほど相手には伝わりにくくなり、印象は下がります。
そのため、何を一番に伝えたいのか考えたうえで内容を一つに絞りましょう。
エピソードの具体性を上げる
志望動機、自己PR、ガクチカなど頻出質問では、過去のエピソードを記載する場面があります。
その際にエピソードをより具体的なものを挙げていると、説得性があり、内容も分かりやすくなります。
ただ詳しく書くという意味ではなく、簡潔にまとめながら具体的な場面を抽出して記載しましょう。
伝わりやすい文章で書く
就職活動という場面において、伝わりやすさはとても重要です。
どんなに良い内容やアピールすることがあっても、伝わらなければ意味がなく、特に書類ではそれが顕著に現れます。
結論ファースト、文末の表現を揃える、誤字脱字を防ぐ、具体的なエピソードを用いるなどを意識することで、文面上でも十分に相手に自分がどんな人物なのかを伝えるESを作ることができます。
ESの頻出質問/例文
ESにおいて頻出質問といえる、志望動機、自己PR、ガクチカについてどんな内容を書くものかを紹介しつつ、その例文を見ていきましょう。
この3つは、どの企業でも聞かれる内容であるため、あらかじめ用意しておくことがおすすめです。
志望動機
まずは志望動機です。
その名の通り、なぜ企業を志望するかについて述べます。
結論ファーストの構成で書くため、「私が御社を志望する理由は○○です」という書き出しが一般的です。
例文を見てみましょう。
私が御社を志望する理由は、掲げているミッションに強く共感したからです。
私は長期インターンにおいて常に新たな取り組みに挑戦してきました。
例えば、既存の運用していた広告メディアに加えて別の方法で顧客リストを増やす方法を模索し、新たなSNS運用を新規プロジェクトとして立ち上げました。
そんな主体性ある姿勢は御社がミッションとして掲げる「挑戦し続ける意味」に重なり、入社後は貢献していきたいと考えています。
私は、貴社の製品開発に携わり、多くの人々の生活を豊かにすることに貢献したいと考えている。
大学では材料工学を専攻し、特に環境負荷の少ない新素材の研究に取り組んできた。
その過程で、持続可能な技術の開発が企業の競争力向上に寄与することを実感した。
貴社は、革新的な製品開発を通じて業界をリードしており、環境配慮型の技術開発にも積極的に取り組んでいる。
私は、これまで培ってきた知識と研究経験を活かし、貴社の開発プロジェクトに貢献したいと考えている。
特に、研究開発部門において、新素材の実用化に向けた研究に携わり、より多くの人々の暮らしを支える製品の開発に尽力したい。
自己PR
次に自己PRです。
自分の強みについて述べます。
結論ファーストの構成で書くため、「私の強みは○○です」という書き出しに続けて、それが活かされたまたは培われたエピソードを付随させるのが一般的です。
例文を見てみましょう。
私の強みはコミュニケーション能力です。
サークル活動で幹事長を務めていた際に、チームをまとめるうえでコミュニケーション能力が求められました。
練習期間に中々参加者が集まらなかった際に、一人一人と会話をすることでなぜ練習に参加しないのかを聞き出し、練習場所や方法を改善していきました。すると段々とヒトが集まるようになり、チームとしての団結力も向上していきました。
今後は、社内外で関わる人たちとよい関係を構築していくために、このコミュニケーション能力を活かしていきたいと考えています。
私は、課題解決に向けて粘り強く取り組むことを強みとしている。
大学ではデータ分析を専門とし、統計学を活用したマーケティング調査の研究を行ってきた。
研究過程では、大量のデータを適切に処理し、そこから有益な情報を導き出すことの重要性を学んだ。
特に、複雑なデータを整理し、分かりやすく伝えるスキルを磨いてきた。
加えて、ゼミではチームのリーダーとして、メンバーの意見をまとめ、研究の方向性を決定する役割を担った。
その経験を通じて、チームワークの大切さを学び、円滑なコミュニケーションの重要性を認識した。
貴社においても、データ分析のスキルと協調性を活かし、戦略的な意思決定を支援できる人材として貢献したいと考えている。
ガクチカ
次にガクチカです。
自分が学生時代に力を入れたことについて述べます。
結論ファーストの構成で書くため、「私は学生生活において○○に力を入れてきました」という書き出しに続けて、苦労したこと、そしてそれをどう乗り越えたのかというエピソードを付随させるのが一般的です。
例文を見てみましょう。
サークル活動において、新入生の歓迎に力を入れました。
自分たちの今ある魅力を伝えるのではなく、どんなサークルであったら入りたいかのニーズを聞き出すことで、興味を引き付けていくことを頑張りました。
今後は、相手の考えや思いを尊重することの大切さを学び、今後もクライアントとの関係構築に活かしていきたいと考えています。
私は、大学のサッカーサークルに所属し、副キャプテンとしてチームの強化に尽力した。
入部当初、チームは個々の能力が高いにもかかわらず、組織的なプレーが不足していた。
そのため、私はチームメンバーと話し合い、練習メニューを見直すことを提案した。
特に、戦術理解を深めるために試合映像の分析を行い、具体的な戦略を共有する機会を設けた。
その結果、チームの連携が向上し、地方大会で優勝するという成果を収めた。
この経験を通じて、組織の課題を分析し、改善策を講じることの重要性を学んだ。
貴社においても、チームワークを重視しながら、自ら課題を見つけ、解決策を提案できる人材として貢献したいと考えている。
ESは内容が1番重要!
ESの作成では、語尾や誤字脱字に注意を払うことも重要ですが、一番大切なことは限られた文章の中で何を伝えられるかといった点です。
自身の魅力を最大限に引き出し、相手に理解してもらうことが重要です。
ESは企業の担当者に最初に自分を評価してもらう非常に大切な文章です。
作成に迷った際には、就活エージェントに相談してみましょう。
ジョブコミットでは、経験豊富なアドバイザーがあなたを専属でサポートしてくれます。
まずは、無料でのカウンセリングからはじまり、あなたの方向性のジャッジをしてくれます。
豊富な経験に裏付けられたアドバイスで、面接対策を行い、あなたが納得いくまで無料で就活相談をすることも可能です。
まずは、以下のサイトを確認し、無料の会員登録からはじめて見ましょう。
まとめ
ESの作成は就活の入り口でもあります。
ですます調、である調どちらを選択しても間違いではありません。
大切になってくるのは、自身の方向性に対する考え方です。
ここがブレると進むべき方向がわからなくなってしまいます。
自分の考えをしっかりと持ち、表現することがES作成では重要になります。