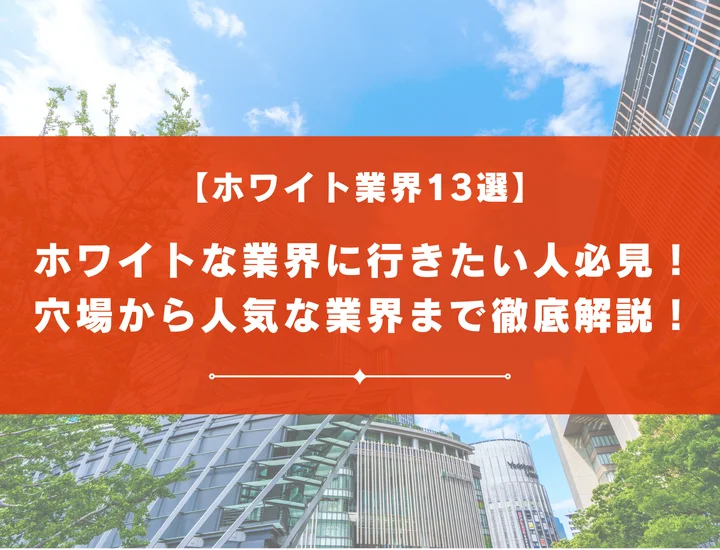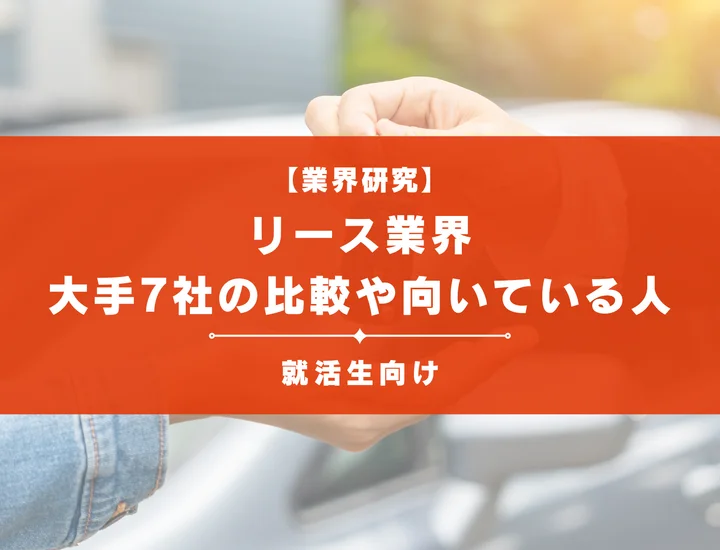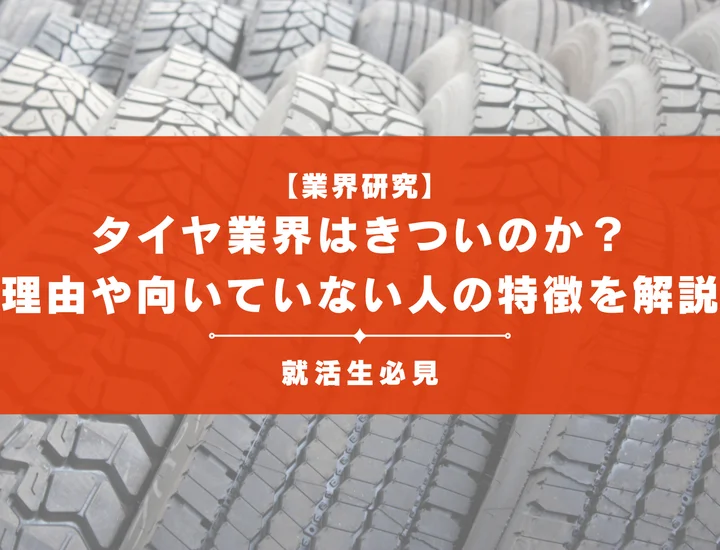目次[目次を全て表示する]
向いている業界・就活の軸がわかる!
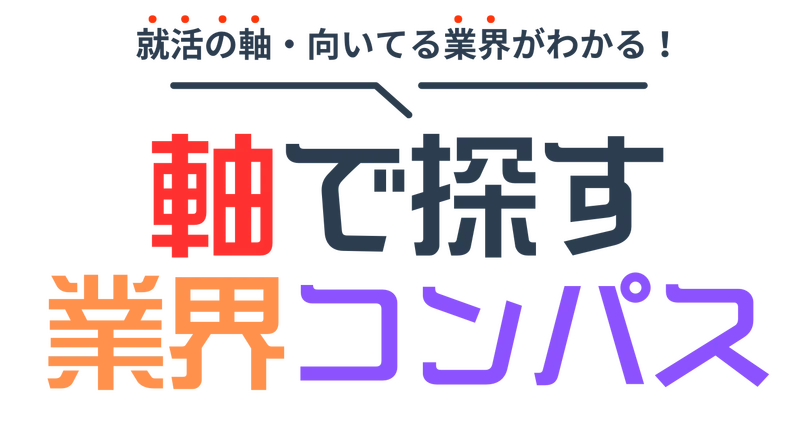
ホワイトな業界に行きたいけど、どの業界に向いているかわからない人は多いと思います。
しかし業界選びは就活において非常に重要になってきます。
そこでおすすめなのが、「軸で探す業界コンパス」です。
20問の質問に答えるだけで全45業界からあなたに合った3業界と、就活の軸3つがわかります。
こちらは完全無料のため、ぜひご利用してみてください。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
- ホワイト業界の特徴とは
- ホワイトな業界に向いている人の特徴
- ホワイトな業界のメリット
- ホワイト業界の特徴について知りたい人
- ホワイトな業界に向いている人の特徴を知りたい人
- ホワイトな業界のメリットについて知りたい人
就職活動で志望する企業を選ぶ際、その企業が「ブラック企業」か「ホワイト企業」かについて注意深く調べる方は多いでしょう。
しかし、実際は企業単位ではなく業界単位でも「ブラック業界」「ホワイト業界」と呼ばれる分類があり、労働環境の傾向が異なります。
そのため、ホワイトな職場で働きたいのであれば、業界選びの段階でホワイトかどうかを考慮することが大切です。
今回はホワイト業界について、その特徴や向いている方、業界の具体例、メリット・デメリットなどを解説します。
【ホワイトな業界とは?】ホワイト業界の特徴
まずは、ホワイト業界がどのような特徴を持つ業界なのかについて確認しておきましょう。
「ホワイト」という言葉に関しては「ブラック」に対比するものとして、漠然と良いイメージを持っている方は多いかもしれません。
しかし、業界選びで後悔しないためには、その具体的な特徴をしっかり把握し、自身のワークスタイルや理想に合うかどうかを判断することが大切です。
今回は、ホワイト業界に共通していることが多い特徴を7つピックアップし、それぞれについて詳しく解説します。
- 給与が高い
- 年間休日が多い
- 福利厚生が充実している
- 新規参入が難しい
- 社会に必要不可欠な存在
- 経済状況に左右されない
- BtoBのビジネスモデル
- 新卒の離職率が低い
- 残業時間が少ない
給与が高い
働いて得られる収入の金額は、生活の質や将来設計に大きな影響を与える重要なポイントです。
給与だけが仕事のすべてではありませんが、給与が高く安定した収入が確保できることはホワイト業界の特徴の1つといえるでしょう。
現在の日本の平均給与は約440万円であり、一般的には平均年収500万円以上の企業がホワイト企業と呼ばれます。
収入の水準は業界ごとにある程度決まっていますが、成果や年収によって金額が上がる業界とそうでない業界があるので、しっかり業界研究をして確認しておくことが大切です。
年間休日が多い
年間休日が多ければ、趣味や休息に使える時間が多くなり、ワークライフバランスの取れたゆとりのある生活ができるようになります。
働きすぎて健康を害してしまっては元も子もないので、年間休日の多さはホワイトかどうかを判断する重要なポイントだといえるでしょう。
現在の日本の平均年間休日日数は115日であり、一般的には年間休日120日以上の企業をホワイト企業と呼びます。
これは毎週末の休みにくわえて、GWやお盆、年末年始といった時期にしっかり休みが取れる場合の年間休日日数です。
福利厚生が充実している
従業員のことを考えた福利厚生や各種制度が充実していることも、ホワイト業界の特徴です。
福利厚生の具体例としては、住宅手当、託児施設の用意、資格取得支援、家賃補助などが挙げられます。
適切な給与の水準も、金銭的な支援が受けられる住宅手当・家賃補助があるかどうかによって変わってくるでしょう。
託児施設の有無も子どもを持つ場合の働きやすさに大きく関わってくるので、自身のライフスタイルに合った制度が整っているかどうかはあらかじめ確認しておくことが大切です。
新規参入が難しい
ここからは、「こういった特徴を持つ業界がホワイトになりやすい」事例についての解説となります。
参入障壁が低く、新たな事業者が増えやすい業界では、価格競争が起こって利益が分配されてしまいます。
そのため、高い給与を始めとするホワイトな特徴を維持することが困難です。
一方、高い専門性や技術が必要な業界、参入の際に大きなコストやリスクが伴う業界は新規参入が少なく、安定した利益が確保できます。
結果として、新規参入が難しい業界は、ホワイト業界となっているケースが少なくありません。
社会に必要不可欠な存在
人々の生活に深く根ざしており社会に必要不可欠な存在となっている業界は、常に安定した高い需要があるので、業界自体が大きく低迷したりなくなったりする心配がありません。
そのため、給与の高さや年間休日の多さといったホワイトな特徴を維持しやすくなります。
具体例としては、ガス・水・電気といった生活に欠かせないインフラ関連の業界が挙げられるでしょう。
また、こういったインフラに関わる企業は元々国営だったケースが多いので、潤沢な資金があるケースが多く見られます。
経済状況に影響されない
今現在安定性の高い業界や、ホワイトな特徴を持つ業界であっても、経済状況次第では大きな変化を余儀なくされる可能性があります。
経済状況は国内だけでなく世界的な情勢、需要の動向を受けて変化するので、その動きを見極めるのは困難です。
景気低迷などの影響を受けて業界の利益が減少した場合は、人員や給与の削減が必要になるケースもあるでしょう。
そのため、安定性の高いホワイトな業界に就職を目指すのであれば、経済状況の影響を受けにくい業界を選ぶのがおすすめです。
BtoBのビジネスモデル
BtoBとは、企業が顧客に製品やサービスを提供するBtoCとは異なり、ほかの企業との間で取引をおこなうビジネスモデルのことです。
BtoBは企業を顧客にするので取引で動く金額が大きく、一度関係性が構築できれば継続的かつ大規模な利益が確保できます。
そのため、BtoB中心の業界はBtoC中心の業界に比べて安定性が高く、ホワイト業界になりやすいといわれています。
BtoBをメインにする業界は一般消費者視点だと認知度が低いケースが多いので、しっかり業界研究をおこない、情報を集めておきましょう。
新卒の離職率が低い
ホワイト企業の特徴として、新卒の離職率が低いことが挙げられます。
新卒離職率が低い企業では職場環境やサポート体制が整っているため、新入社員が安心して仕事に取り組み、成長できる体制が整っています。
多くのホワイト企業では新入社員向けの研修プログラムやメンター制度が充実しており、業務の基本から段階的に学びながら成長できるのです。
加えて、配属後も定期的な面談が行われ、成長に応じたフィードバックを受けられるため、困難に直面した際にも適切なサポートが受けられ、孤立することなく仕事を続けられるのが特徴です。
また、離職率が低い企業はキャリアパスが明確であることが多く、社員が将来の目標を立てやすい環境が整っています。
これにより「長く働き続けたい」という意欲が高まりやすく、企業に対する帰属意識も深まるのです。
残業時間が少ない
残業時間が少ないのも、ホワイト企業の特徴です。
効率的な業務プロセスが整備されているため、社員が定時で業務を終えやすい環境が整っています。
上司や管理職が積極的にスケジュール管理を行い、無理のない範囲で業務を進められるように配慮されています。
また、計画的な業務分担や明確な進捗管理が行われており、無駄な残業の発生を防ぐための対策も徹底されています。
そして、ホワイト企業の多くでは働き方改革の一環としてテレワークやフレックスタイム制を導入し、社員が自分のライフスタイルに合わせて働くことができる柔軟な制度も万全です。
【ホワイトな業界とは?】ホワイトな業界13選
次は、ここまで解説してきた特徴に当てはまるホワイト業界の具体例をご紹介します。
今回は、ホワイト業界の代表例として、インフラ業界、食品業界、たばこ業界、種苗業界、医薬品業界、鉱業業界、電子部品・電子機器業界、石油・石炭業界、私立大学職員、海運業界をピックアップしました。
これらはいずれも社会において重要なポジションを担う業界ですが、普段生活しているなかではあまり聞き覚えのない名前もあるかもしれません。
もし知らない業界があった場合は、この記事をきっかけにどのような仕事をしている業界なのかを調べてみると良いでしょう。
今回ご紹介する業界についてより詳しく知りたい方は、以下のリンク先を参考に業界研究をおこない、さらに深堀りして情報を集めてみてください。
- インフラ業界
- 食品業界
- たばこ業界
- 種苗業界
- 医薬品業界
- 鉱業業界
- 電子部品・電子機器業界
- 石油・石炭業界
- 私立大学職員
- 海運業界
- 化学業界
- クレジットカード業界
- リース業界
- ゲーム業界
インフラ業界
インフラ業界とは、生活の基盤として必要不可欠なインフラストラクチャー(infrastructure)を整備・管理する業界です。
インフラの具体例としては、電気、ガス、水道、通信、交通などが挙げられます。
これらのインフラを管理する主体は国、地方自治体、民間企業などさまざまですが、いずれの場合も社会における重要度が高く、不要になることはありません。
また、社会構造や各地域と密接に結びついた関係性が構築されているので、新規の参入障壁と、業界全体の生産性も高くなっています。
インフラ業界は安定性が非常に高く、経済状況にも左右されにくいので、代表的なホワイト業界として知られています。
インフラ業界についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのページも参考にしてください。
- 東京電力ホールディングス
- 東京ガス
- JR東日本
食品業界
食品業界とは、人々の生活に不可欠な食品の加工や販売を担う多様な業種を含む業界です。
具体例としては、農家に代表される第一次産業、加工や製造を担う食品メーカー、商社・卸業者などが挙げられます。
ただし、就職活動において食品業界を志望するという場合は、第一次産業を除いたメーカーや商社などを指すケースが多いでしょう。
食品業界もインフラ業界と同様に社会における重要度が高く、需要がなくなることはありません。
また、新しく事業を立ち上げるためには加工・製造をおこなう工場の建設や、従業員の確保が必要なのでコストが高く、新規参入障壁も高めです。
一方、就活生に人気の業界なので、全体的に倍率は高い傾向にあります。
また、食品業界のホワイト企業についてはこちらの記事に詳しく記載しています。
是非参考にしてみてください。
ホワイト企業ナビ:【食品業界のホワイト企業30選】企業の探し方や給料ランキング!
- アサヒグループHD
- キリンHD
- 味の素
たばこ業界
日本では、JT(日本たばこ産業株式会社)のみが国からたばこの販売を許可されています。
そのためたばこ業界は国内における市場競争が発生せず、新規参入がないホワイト業界となっているのです。
近年日本ではたばこに対する規制が強まり、喫煙者を取り巻く環境も大きく変化してきました。
しかし、世界第三位の売上を誇るJTのたばこ事業は海外を主な収入源としているので、現在でも安定した利益を上げています。
また、従来の紙巻きたばこだけでなく、電子たばこや加熱式たばこの開発・販売もおこなっているので、将来的にも高い安定性が期待できます。
主な収入源はたばこ事業ですが、加工食品事業や医薬品事業も展開しているので、意外なところでJTの製品に触れている方も多いでしょう。
- 日本たばこ産業
- フィリップ・モリス・ジャパン合同会社
- ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
種苗業界
種苗業界とは、花や野菜といった植物の新しい品種を開発し、その種や苗を販売する業界です。
あまり就活生には馴染みがない業界かもしれませんが、種苗業界も高い安定性を持つホワイトな業界として知られています。
野菜や穀物の生産に関わる種苗業界は、食品業界と同様に人々の生活に不可欠な存在であり、需要がなくなる心配はありません。
そのため、経済状況に左右されることがめったになく、常に安定した利益を上げられるのです。
また、基本的に農家や種苗量販店などの事業者を対象として種や苗を販売するBtoBのビジネスモデルなので、利益の規模が大きく安定しています。
国内で需要が減った際は、海外に販路を広げることも可能なので、将来的な安定性も期待できる業界だといえるでしょう。
- タキイ種苗
- サカタのタネ
- カネコ種苗
医薬品業界
医薬品業界は、病院や薬局で使用・処方される医薬品の開発や製造、販売をおこなう業界です。
製薬業界とほぼ同義の業界として扱われる場合も多く、具体的な業種としては、製薬メーカーなどが該当します。
医薬品の開発や製造には国からの認証が必要になるので、新しく医薬品業界に参入するのは容易ではありません。
そのため医薬品業界は、潤沢な資本がある限られた企業によって構成されている、比較的競合の少ない安定したホワイト業界となっているのです。
具体的な業務としては、研究開発職、生産技術職、MR(営業)、管理薬剤師、薬事部門などが挙げられます。
どの企業も入社難易度は高めなので、医薬品業界を志望するのであればなるべく早い段階から業界や企業の情報を集め、対策を考えておくと良いでしょう。
- 武田薬品工業株式会社
- アステラス製薬株式会社
- 第一三共株式会社
鉱業業界
鉱業業界とは、鉱物資源の採掘、精錬、加工などをおこなう業界です。
鉱物資源はさまざまな機械や電子部品、薬品などさまざまな形態で社会に流通していますが、その最上流にあたる部分を担う業界だといえるでしょう。
普段生活しているだけでは名前を聞く機会が少なく、就活生の知名度もあまり高くはありませんが、鉱業業界も安定性が高くホワイトな業界の1つです。
鉱物資源は社会にとってなくてはならないものであり、その需要がなくなることはありません。
鉱物資源が採掘できる場所は限られているので参入の障壁も高く、業界全体の動向が安定しています。
また、先述のとおり就活生からの知名度も高くないので、ホワイト業界への就職を目指すのであれば狙い目の穴場な業界といえるでしょう。
- INPEX
- 石油資源開発
- 日本鉱業
電子部品・電子機器業界
電子部品・電子機器業界は、さまざまな機器・装置に使用される電子部品の開発・製造をおこなう業界です。
IT化が進んだ情報化社会の現代では、至るところに電子機器が使われており、今後もその需要が伸びていくと予想されています。
そのため電子機器の製造に大きく関わる電子部品・電子機器業界も安定感が高く、今後の発展も期待できる有力なホワイト業界です。
また、日本の電子部品・電子機器関連企業は技術力が高く、世界中で需要があるため、グローバル展開やさらなる成長も期待できます。
社会における重要度が高い一方、BtoBのビジネスモデルがメインであり、就活生の認知度はあまり高くありません。
そのため、競争率がそこまで高くならない、ホワイト業界のなかでも穴場の業界といえるでしょう。
- 村田製作所
- ニデック
- 京セラ
石油・石炭業界
石油・石炭業界は、燃料や原料として重要性が高い石油や石炭の精製、加工をおこなう業界です。
身近なところでは、道路を舗装しているアスファルトにも石油や石炭が使われています。
燃料としての側面を見ると、近年は電気を中心に新たな形態の燃料・動力が普及してきたため、以前に比べて石油・石炭の需要は減少しています。
それでもなお、社会において必要不可欠な存在であり、海外需要も高まると予想されているので、今後も安定感が期待できる業界だといえるでしょう。
また、事業を始めるためには高い技術力と莫大なコストが要求されるため、まったく新しい企業が新規参入してくるケースはほとんどありません。
こういった特徴から、石油・石炭業界は経済状況に左右されず安定した利益を上げられるので、ホワイト業界の1つとして数えられています。
- ENEOSホールディングス
- 出光興産
- コスモエネルギーHD
私立大学職員
私立大学職員は、私立大学で学生や教員をサポートするための仕事をおこなう職業です。
その業務内容は事務系と技術系に大別され、事務系の場合は学生支援や研究支援、総務、人事、財務などさまざまな側面から大学の運営を支えていくことになります。
一方で技術系は、電気、建築、機会、土木といった専門分野での採用がおこなわれ、教育や研究を技術面からサポートするのが主な仕事です。
私立大学職員は国公立大学の職員よりも年収が高く、休みも取りやすいためホワイトな業界だといわれています。
また、有名私立大学であれば基本的になくなることはないので、安定性の高さも期待できるでしょう。
ただし、日本には600を超える私立大学があり、それぞれ経営状況や給与の水準が異なるので、個別に情報を集めることが大切です。
- 早稲田大学
- 明治大学
- 関西学院大学
海運業界
海運業界とは、海路を用いた物資の輸送や船舶の取引をおこなっている業界です。
海上輸送は国内を対象とした内航海運と海外を対象にした外航海運に分けられ、タンカーやコンテナ船といった船舶を用いて適切な輸送がおこなわれます。
四方を海に囲まれている日本ではとくに海路の重要性が高く、貿易量の大半は海運が担っているのが現状です。
そのため、海運業界は社会にとって不可欠な存在であり、将来的にも安定した需要が見込めます。
自社で物資を輸送するだけでなく、船舶をリースして収入を得ている企業もあり、それぞれが連携して安定した収入を上げているのが特徴です。
また、国から認可を得なければ事業が始められないので新規参入のハードルが高く、競争が激化したり、業界の構造が大きく変化したりする心配がありません。
海運業界についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのページも参考にしてください。
- 日本郵船
- 商船三井
- 川崎汽船
化学業界
化学業界は化学製品の研究開発、製造、販売を行う分野で、幅広い業界と関わりを持つ重要な産業です。
石油化学、医薬品、化粧品、食品添加物、高機能素材など、多岐にわたる製品が開発されており、自動車や電子機器、建設業界など多くの産業を支えています。
また、研究開発が活発で、最先端の技術を駆使した新しい素材や製品を生み出すことが求められるため、技術革新のスピードが速い点も特徴です。
安定性が高く、長期的なキャリアを築きやすいため、就活生の方々から人気を集めています。
- 三菱ケミカルホールディングス
- 富士フイルムホールディングス
- 住友化学
クレジットカード業界
クレジットカード業界は皆さんご存知の通り、消費者が現金を使わずに決済できる、クレジットカードに関連するサービスを提供する業界です。
カードの発行、決済ネットワークの構築、ポイントサービスの運営、加盟店の管理など、幅広い業務が行われています。
また、キャッシュレス決済の普及に伴い、市場規模は拡大を続けており、フィンテックの発展とも密接に関わっています。
安定したビジネスモデルがあり、継続的な収益が見込める点が特徴です。
また、銀行、カード会社、通信系、流通系など、様々な企業がクレジットカード事業を展開しているため、自分の興味や強みに合った企業を選ぶこともできます。
- 三井住友カード
- JCB
- 三菱UFJニコス
リース業界
リース業界は企業や個人に対して、機械設備や車両、情報機器などを一定期間貸し出すサービスを提供する業界です。
購入せずに利用できるため、コストを抑えて設備を導入できる点が強みであり、法人向けのビジネスが中心となっています。
工場の機械、オフィス機器、医療機器など、高額な設備を必要とする企業にとって、リースは有効な資金調達手段の1つと言えるでしょう。
この業界の特徴としては、常に需要があるため、景気の変動に左右されにくい点が挙げられます。
リース契約は特に長期にわたるものが多いため、安定した収益を上げやすく、経済の影響を受けにくいビジネスモデルです。
- オリックス
- 三菱HCキャピタル
- 三井住友ファイナンス&リース
ゲーム業界
ゲーム業界はビデオゲーム、コンピューターゲーム、スマホゲームなど、様々な形態のゲームを制作・販売・配信する業界です。
近年ではeスポーツの発展やVR・AR技術の進化、クラウドゲームの登場により、市場規模がさらに拡大しています。
国内だけでなく、海外市場でも日本のゲームコンテンツは高い評価を受けており、グローバル展開を視野に入れたビジネスモデルも主流です。
プログラマー、デザイナー、マーケティング担当など、多様な職種が存在し、自分のスキルや興味に応じてキャリアを選べます。
- スクウェア・エニックス・ホールディングス
- バンダイナムコエンターテイメント
- 任天堂
【ホワイトな業界とは?】穴場な隠れホワイト業界
上記であげた優良な環境は、必ずしも知名度の高い業界や企業だけにあるわけではありません。
世間的には目立たなくても、特定の分野で強みを持ち、社員にとって非常に働きやすい「隠れホワイト業界」が存在します。
ここでは、そうした魅力的な穴場業界をいくつかご紹介します。
- 特定分野の専門商社
- ガス業界(都市ガス・LPガス)
- 独立行政法人
特定分野の専門商社
特定分野の専門商社は、ある特定の商材や業界に特化して事業を展開する企業です。
総合商社と比較すると知名度は低いものの、その専門性を武器に安定した経営基盤を築いている企業が少なくありません。
特定の分野で高いシェアを誇り、既存の顧客との強固な関係性を構築しているため、過度な新規開拓営業や価格競争に陥ることが少なく、安定した収益を確保しやすいのが特徴です。
そのため、社員への還元も手厚く、給与水準が高い傾向にあります。
また、取引先や業務内容がある程度固定されていることから、突発的な業務が発生しにくく、残業時間が少ないなど、ワークライフバランスを保ちやすい労働環境が整っている点も大きな魅力と言えるでしょう。
BtoBビジネスが中心で学生からの知名度が低いことも、隠れた優良企業が多い理由の一つです。
ガス業界(都市ガス・LPガス)
ガス業界は、私たちの生活に不可欠なエネルギーを供給するという社会インフラを担う極めて公共性の高い事業です。
景気の変動による影響を受けにくく、常に一定の需要が見込めるため、経営が非常に安定しています。
特に大手都市ガス会社は、法律によって供給エリアが定められているため、安定した収益基盤を持っています。
こうした事業の安定性は、社員の雇用や給与にも反映され、長期的に安心して働ける環境につながっています。
また、法令遵守意識が高く、安全を最優先する企業文化が根付いているため、労働時間や休日取得など、労務管理が徹底されている傾向にあります。
福利厚生も手厚い企業が多く、社員が心身ともに健康で長く働き続けられるような制度が整っている点も、ホワイト業界と言われる所以です。
独立行政法人
独立行政法人は、国が所管する行政サービスの一部を担う法人であり、公共性の高い事業を行っています。
非営利の組織であるため、民間企業のような過度な利益追求や厳しいノルマは基本的にありません。
そのため、職員は安定した環境の中で、社会貢献性の高い業務にじっくりと取り組むことができます。
給与や福利厚生は国家公務員に準じた体系となっていることが多く、手厚い住宅手当や各種休暇制度などが整備されています。
また、年間休日がしっかりと確保されており、残業時間も少ない傾向にあるため、プライベートの時間を大切にしながら働くことが可能です。
雇用の安定性も非常に高く、長期的なキャリアプランを描きやすいのが大きな魅力です。
安定した組織で、ワークライフバランスを重視しつつ、社会に貢献したいと考える人にとって、魅力的な選択肢と言えるでしょう。
【ホワイトな業界とは?】価値観リスト
どんな働き方をしたいかは、業界選びの軸になる重要な視点です。
ホワイトな業界といっても、全員にとって理想的とは限りません。
あなたが大切にしたい価値観は何でしょうか?安定性、自由度、社会貢献性、柔軟な働き方などたくさんあると思います。
それぞれの価値観に合ったホワイトな業界を見つけるために、まずは以下のリストから自分の考え方に近い項目をチェックしてみましょう。
業界選びの第一歩が、きっと見えてくるはずです。
下記の表から、自分に当てはまる価値観を探してみてください。
以下のホワイトな業界を探す際の意識すべき価値観リストを見てみましょう。
- 価値観 | 具体的な考え方・好み | 合いそうなホワイト業界(例)
- 安定志向 | 景気に左右されず長く働きたい | インフラ・医薬品・たばこ業界
- 社会貢献性 | 社会の役に立っている実感を得たい | 教育(大学職員)・医療・食品
- プライベート重視 | 土日祝休み・残業少なめがいい | クレジットカード・リース業界
- 自由・柔軟性 | 自分の裁量で働きたい、働き方に多様性がほしい | ゲーム業界・IT企業・一部ベンチャー
- チーム志向 | 協力して物事を進めたい、仲間と成し遂げるのが好き | 海運・メーカー・教育業界
- クリエイティブ性 | 何かを作る、企画することにやりがいを感じる | ゲーム・広告・エンタメ系
- 専門性・技術志向 | 一生モノのスキルを身につけたい | 電子部品・化学・医薬品業界
- スピード感・変化志向 | 刺激がある環境で成長したい | IT業界・一部スタートアップ
- 決まったルールで働きたい | 手順やマニュアルに沿って安心して働きたい | インフラ・金融・公務的な業務が多い業界
【ホワイトな業界とは?】ホワイト業界おすすめランキング
一般的に「ホワイト」と呼ばれる業界は、働きがいがあり、従業員の定着率が高く、ワークライフバランスを実現しやすい環境が整っていることが多いです。
しかし、何をもってホワイトとするかは個人の価値観によって異なります。
そこで今回は、働きやすさを測る代表的な軸をいくつか設定し、それぞれの軸において特に「ホワイト」と言えるおすすめの業界をランキング形式でご紹介します。
ご自身のキャリアにおいて何を重視したいか、どの軸が最も気になるかを考えながら、あなたに最適な業界を見つけるヒントにしてください。
離職率の低さ
頻繁な転職を望まず、一つの会社でじっくりと腰を据えてキャリアを築きたい、安定した生活基盤を重視したいと考える方にとっては、特に注目すべきポイントと言えるでしょう。
離職率が低いとされる業界は、総じて従業員の定着率が高く、長期的に安定した働き方が実現しやすい傾向にあります。
近年人気のワークライフバランスが優れているという特徴もあります。
安定を求める人必見です。
インフラ業界
(電力・ガス・水道など)私たちの生活に不可欠なエネルギーや水を供給するという極めて公共性の高い事業を担っています。
インフラ業界は景気変動の影響を受けにくく、事業基盤が非常に安定しているため、倒産リスクが低く、安心して長く働き続けることができます。
安定志向の方には最適な業界の一つです。
医薬品業界
人々の健康や生命に直結する医薬品を研究・開発・製造・販売する業界です。高度な専門性が求められると同時に、社会への貢献度も非常に高く、仕事に対する誇りや強いやりがいを感じやすいことが特徴です。
これが従業員の満足度につながり、結果として離職率の低さに結びついています。
食品業界
「食」という、人間が生きていく上で欠かせない生活必需品を扱っています。そのため、景気の波に関わらず需要が常に安定しており、業界全体として安定性が高いのが魅力です。
長期的な視点でキャリアプランを考えやすく、安定した環境で着実に成長していきたい方に適しています。
有給休暇取得率
企業が従業員の休息やプライベートな時間を尊重し、心身の健康維持を重視している文化の表れとも言えます。
仕事だけでなく、趣味や家族との時間、自己啓発など、プライベートも充実させたい、メリハリのある働き方をしたいと考える方にとって、有給休暇の取得しやすさは非常に重要な要素です。
自動車業界
大手メーカーを中心に、福利厚生制度が充実している企業が多い傾向にあります。
例えば、ホンダでは有給休暇の取得率が94.8%(※情報源に基づく)と非常に高い水準にあり、これは会社として有給休暇の取得を奨励し、従業員が気兼ねなく休暇を取れるような風土が根付いていることを示しています。
IT業界
比較的新しい業界であり、柔軟な働き方が浸透している企業が多いのが特徴です。
リモートワークやフレックスタイム制度の導入が進んでおり、時間や場所に縛られない働き方が可能です。
このような環境は、従業員が自身の裁量で仕事のスケジュールを調整しやすく、結果的に有給休暇も取得しやすい文化につながっています。
電子部品・電子機器業界
技術革新が求められる一方で、従業員の働きやすさにも配慮する企業が見られます。
例えば、富士電機では、有給休暇はもちろんのこと、育児休暇などの各種休暇制度の取得率が非常に高く、制度が形骸化せず、従業員のライフステージの変化に合わせた働き方を支援する体制が整っていることがうかがえます。
女性管理職の比率
ダイバーシティ&インクルージョン(多様性の受容と活用)を経営戦略として重視し、女性が長期的にキャリアを形成していくための制度(育児支援、研修制度など)が整っている企業が多い傾向にあります。
性別による有利不利なく、自身の能力で勝負したい、管理職を目指したいと考える女性にとって、重要な指標となるでしょう。
IT業界
実力主義の風土が比較的強く、性別よりもスキルや成果が重視される傾向があります。
SCSKなどの企業では、ダイバーシティ経営を積極的に推進し、女性管理職の育成・登用に力を入れています。
柔軟な働き方が可能な点も、女性がキャリアを継続しやすい要因の一つです。
電子部品・電子機器業界
技術系の職種が多いイメージもありますが、近年は女性活躍推進に積極的に取り組む企業が増えています。
日立ハイテクのように、女性従業員のキャリアパスを明確にし、昇進を後押しするための研修プログラムやメンター制度などを整備している例が見られます。
食品業界
もともと商品開発やマーケティング、品質管理など、女性従業員が活躍する場が多い業界です。
全体的に女性従業員の比率が高いことから、女性管理職への登用に対しても積極的な企業が多く、ロールモデルとなる女性管理職も比較的見つけやすい環境と言えます。
文系向け
「ホワイト」な環境で、人と深く関わる仕事や、組織を円滑に動かす役割を担いたいと考える文系出身者におすすめの業界をご紹介します。
海運業界
世界経済の動脈ともいえる国際物流を担う、スケールの大きな業界です。
グローバルな舞台で活躍する機会が多く、語学力や異文化理解力、交渉力といった文系的な素養が活かせます。
例えば、日本郵船は平均年収が1,000万円を超え(※情報源に基づく)、平均勤続年数も長いことから、非常に高い安定性と待遇の良さを兼ね備えています。
クレジットカード業界
キャッシュレス社会の進展とともに、その重要性を増している金融関連業界です。
営業、マーケティング、企画、顧客サポートなど、多様な職種で文系出身者が活躍しています。
金融知識を身につけながら、堅実なキャリアを築いていくことが可能です。
教育業界(大学職員)
大学運営を支える事務系の仕事が中心となります。
学生支援、広報、研究支援、国際交流、総務・人事など、業務内容は多岐にわたりますが、比較的ワークライフバランスが取りやすく、安定した雇用環境の中で長期的に働きやすいのが特徴です。
教育という社会貢献性の高い分野で、落ち着いた環境で働きたい方に向いています。
理系向け
研究職や開発職、技術職として、専門性を深めながら活躍できる場が豊富な業界をご紹介します。
食品業界
新商品の研究開発、品質管理、生産技術、醸造技術など、理系の専門知識が不可欠な職種が数多く存在します。
例えば、味の素では研究・開発職のポストが豊富にあり、食を通じて人々の健康や豊かな生活に貢献できるやりがいがあります。
また、平均年収も高い水準(※情報源に基づく)にあり、待遇面でも魅力的な業界です。
医薬品業界
新薬の創薬研究、臨床開発、品質管理、製造プロセス開発など、高度な専門性が求められる職種の宝庫です。
人々の命を救う、健康を守るという非常に社会貢献性の高い仕事であり、強い使命感を持って働くことができます。
専門性を活かして社会に貢献したい理系出身者にとって、大きなやりがいが得られるでしょう。
電子部品・電子機器業界
半導体、センサー、通信機器、精密機器など、常に最先端の技術開発が求められるダイナミックな業界です。
自身の研究や開発が、新しい製品や技術として世の中に出ていく過程に携わることができ、知的な探求心を満たしながらスキルアップを図ることが可能です。
技術革新に貢献したいという意欲のある方におすすめです。
女性向け
これらのライフステージの変化に柔軟に対応できる制度(産休・育休、時短勤務、在宅勤務など)が整っており、かつ、それらの制度を利用しやすい企業文化・環境がある業界を選ぶことが、長期的なキャリア形成の鍵となります。
キャリアを諦めることなく、自分らしい働き方を続けたい女性におすすめの業界をご紹介します。
IT業界
リモートワークやフレックスタイム、時短勤務といった柔軟な働き方を積極的に導入している企業が多いのが大きな特徴です。
これにより、育児や介護など、個々の事情に合わせて働き方を調整しやすく、仕事と家庭の両立を図りやすい環境が整っています。
スキルさえあれば、場所や時間に比較的縛られずに活躍できる可能性があります。
電子部品・電子機器業界
近年、女性活躍推進に力を入れる企業が増加しており、育児支援制度(企業内保育所の設置、育児短時間勤務制度の充実など)が手厚く整備されている傾向にあります。
また、前述の通り、女性管理職の登用も進んでおり、キャリアアップを目指す女性にとっても働きがいのある環境が整いつつあります。
食品業界
もともと女性従業員の比率が高いこともあり、ライフイベントに対する理解が得られやすい風土があると言われています。
産休・育休からの復職率も高く、時短勤務などを活用しながら、ライフステージの変化に応じて働き方を選びやすい環境が期待できます。
商品開発やマーケティングなど、女性ならではの視点が活かせる職種も多いです
【ホワイトな業界とは?】ホワイト傾向の職種
続いて、ホワイトな傾向にある職種についても紹介します。
もちろん、以下の職種なら全て100%ホワイトな環境で働けるというわけではありませんが「過酷な環境で働かされる可能性は低い」と言える職種です。
できるだけホワイトな環境で働きたいと思っている方は、ぜひ以下の職種を選択肢に入れてみてください。
- 受付
- 事務
- 品質管理
受付
受付の仕事は来客対応や電話対応、社内の案内業務などを担当する職種です。
企業の「顔」として訪問者を迎え、丁寧な接客や円滑なコミュニケーションが求められます。
また、来客者の手続きを行ったり、会議室の予約を管理したりすることもあり、社内外の人と関わる機会が多いのも特徴です。
受付業務は基本的に定時で終わることが多く、突発的な残業が発生しにくい点が魅力の1つです。
また、業務内容が基本的にルーティン化されているため、仕事の進め方が明確である点も魅力であると言えるでしょう。
事務
事務職は書類作成やデータ入力、電話対応、備品管理など、企業の業務を円滑に進めるためのサポートを行う職種です。
一般事務、営業事務、人事事務、経理事務など、担当する業務によって内容は異なりますが、基本的にはデスクワークが中心となります。
また、業務の進行管理や社内の調整業務を担うこともあり、組織の運営を支える役割を果たしているのも特徴の1つです。
事務職の魅力は業務が比較的安定しており、過度な残業が発生しにくい点です。
特に、大手企業や公的機関ではワークライフバランスを重視した働き方が推奨されており、育休・産休などの制度も整っています。
品質管理
品質管理は製品やサービスの品質を維持・向上させるための業務を担当する職種です。
製造業では製品の検査や不良品のチェック、品質基準の策定などを行い、企業のブランド価値を守る役割を担います。
また、サービス業やIT業界でも品質管理の仕事があり、顧客満足度を高めるための対策・改善策を考えたり、業務プロセスの見直しを行ったりすることが求められます。
この職種はトラブルが発生しないように事前に対策を立てる業務が中心となるため、納期に追われることが比較的少なく、安定した働き方ができる点が魅力です。
また、専門知識や分析力を活かす場面も多く、経験を積むことでスキルアップしやすい点も魅力であると言えるでしょう。
【ホワイトな業界とは?】ホワイトな業界に向いている人の特徴
次は、ホワイトな業界に向いている人の特徴について解説します。
先述のとおり、ホワイト業界は高い給与、多い年間休日数、充実した福利厚生などの特徴を持ち、基本的に働きやすい環境が整っています。
そのため、業界の雰囲気や働き方と相性の良い方であれば充実した社会人生活が送れるでしょう。
今回はホワイト業界に向いている人の特徴として、以下の3つをピックアップしました。
自身のライフスタイルや社会人の理想がどれかに当てはまる方は、ホワイト業界を中心に就職活動を進めてみても良いかもしれません。
- ワークライフバランスを求めている人
- 安定的に稼ぎたい人
- 決められたことに従うことが得意な人
ワークライフバランスを求めている人
年間の休日数が多く福利厚生も充実しているホワイト業界は、ワークライフバランスを重視している人にとくにおすすめです。
希望どおりの有給休暇が取得しやすく残業時間も少ないので、無理なくプライベートと仕事を両立させられるでしょう。
また、子どもの病気や学校行事に対応するための休暇取得、食事を作るための定時退勤などが必要となる子育て中の人も、ホワイト業界であれば無理なく仕事を続けられます。
すでに働いている家族や知人、OB・OGの意見を参考に、どの程度のワークライフバランスが適切かを考えてみると良いでしょう。
安定的に稼ぎたい人
ホワイト業界は給与の高さも特徴の1つですが、それ以上に優れた安定性が大きな魅力となっています。
生活に必要不可欠なインフラ系を筆頭に業界全体の安定度が高いので、給与がいきなり減ったり、リストラされたりする可能性は低めです。
新規参入が少ない業界であれば、業界内の立ち位置や勢力図が大きく変化する心配もありません。
そのため、経済・景気の動向に振り回されず安定して稼ぎたい方や、将来の目標のために堅実に資金を貯めたい方はホワイトと業界との相性が良いでしょう。
決められたことに従うことが得意な人
ここまで触れてこなかったホワイト業界の特徴の1つとして、コンプライアンスに厳しい業界・企業が多いことが挙げられます。
これはつまり、社会・業界・企業が定める倫理やルールの遵守が求められるということです。
ホワイト業界の企業では、仕事に関する厳格なルールや手順があらかじめ決まっており、それに従って業務をおこなうことを求められるケースが少なくありません。
そのため、決められた規律やルールに従って仕事をするのが得意な人はホワイト業界との相性が良く、安心して働けるでしょう。
【ホワイトな業界とは?】ホワイトな業界に向いていない人の特徴
ここまでは、主にホワイト業界の魅力的な面について解説してきました。
ただし、物事にはかならず良い面と悪い面があり、一面的な印象だけを見ていては全体像はわかりません。
一見すると誰にとっても理想的な職場のようなホワイト業界ですが、人によっては働きづらさや居心地の悪さを感じてしまう場合もあるでしょう。
今回はホワイト業界に向いていない人の特徴として、以下の3つをピックアップしました。
しっかり自分のことを理解したうえで、本当にホワイト業界を目指すべきかどうかを考えてみてください。
- 成長環境を望んでいる人
- 成果を出して稼ぎたい人
- 変化を求める人
成長環境を望んでいる人
ホワイト業界は安定性が高い一方で、組織としてのシステムやルール、業務の手順は厳格に決まっている企業が多く見られます。
ベンチャー企業や新規参入が多い業界の企業に比べると年功序列の構造も強く残っており、若手が裁量権を持って働くことは難しいでしょう。
社会人として働き始めた当初は、決められた仕事をただこなすだけになるケースも少なくありません。
若いうちから経験を積めるような環境は少ないので、成長スピードは緩やかです。
そのため、積極的に成長したいと考える意欲の高い方には、あまり向いていないでしょう。
成果を出して稼ぎたい人
給与水準が高めで安定しているのが魅力のホワイト業界ですが、その金額は大きく下がる心配がない一方で、大きく上がることもめったにありません。
インセンティブ制度を採用している企業のように、仕事の成果に応じて給与が大きく増えるケースは基本的にないと考えて良いでしょう。
そのためバリバリ働いてその分稼ぎたいと考えている方は、ホワイト業界にはあまり向いていていません。
頑張っても収入が増えないので、仕事にやりがいを見いだせなくなってしまう可能性もあるでしょう。
変化を求める人
コンプライアンスを重視し、決められた仕事をこなすことが多いホワイト業界は、安定性が高い一方で変化が少ない業界です。
そのため、割り当てられたものだけでなくさまざまな業務にチャレンジしてみたい方や、新しい事業を始めてみたいと考える方にはあまり向いていないかもしれません。
また、ホワイト業界の傾向として新規参入が少なく経済状況の影響も受けにくいので、刺激が少ないと感じる方もいるでしょう。
安定性と変化は両立が難しいポイントなので、自身がどちらを重視するタイプなのかをしっかり把握しておくと良いでしょう。
【ホワイトな業界とは?】ホワイトな業界に行くメリットとは
次は、ここまで解説してきた業界の特徴や傾向を考慮し、就職先としてホワイトな業界を志望する具体的なメリットについて考えていきましょう。
ホワイト業界は漠然と良いイメージを持たれることが多いですが、その具体的なメリットを尋ねられると返答に困る方も多いかもしれません。
業界の選択は就職活動やその先の社会人としての人生を左右する重要なポイントなので、可能な限り選ぶ基準を明確化しておくことが大切です。
今回は、ホワイト業界で働くメリットとして以下の3つをピックアップしました。
- プライベートを確保しやすい
- ストレスなく働ける
- 制度が充実している
プライベートを確保しやすい
年間の休日数が多く、福利厚生も充実しているケースが多いホワイト業界は、プライベートの時間を確保しやすいのが大きなメリットです。
定期的に旅行に行きたい方や、夜はしっかり自分の時間を楽しみたい方でも、ホワイト業界であれば無理せず働けるでしょう。
また、産休や育休といった制度も整っているので、子育てをしながら仕事を続けやすいのもホワイト業界の大きな魅力です。
理想のワークライフバランスは人によって異なるので、自己分析で自分がどの程度のプライベートを確保したいのか把握しておくと良いでしょう。
ストレスなく働ける
ホワイト業界の企業は多くの場合、コンプライアンスを重視し、ハラスメントなどの迷惑行為にも厳正に対処しています。
そのため職場の雰囲気が良く、ストレスを感じずに仕事ができるケースが多いでしょう。
また、競争の激しい業界やベンチャー企業と異なりノルマが設定されていない場合もあるので、仕事をするうえで過度なプレッシャーを感じる心配もありません。
企業によってはカウンセリングなどのメンタルケアも充実しているので、心身の健康を保ちながら仕事ができます。
制度が充実している
ホワイト業界の企業では、従業員の仕事と暮らしを支えるための制度が多く導入されています。
とくに働き方やライフスタイルが多様化している昨今においては、自分に合わせた働き方が可能なことは大きなメリットになるでしょう。
リモートワークやフルフレックス制度が導入されている場合は、自分のライフスタイルやプライバシーを維持しながら、時間を効率的に使った勤務が可能です。
家賃補助や住宅手当は金銭的な恩恵が大きい制度であり、給与が同じ場合でも貯蓄や子育て資金に回すための余裕が生まれやすくなります。
ホワイトな業界に行くデメリットとは
次は、ホワイト業界で働くデメリットについても確認しておきましょう。
基本的にポジティブな側面が多いホワイト業界ですが、良い面だけを見て就職を決めてしまうのは要注意です。
どのような業界・企業にも良い側面と悪い側面があり、一面的な見方だけでは自身との相性や、就職するべきかどうかは判断できません。
悪い面にもしっかり目を向け、そこで働く自分を想像してから業界を選ぶと良いでしょう。
今回は、ホワイト業界で働くデメリットとして、以下の3つをピックアップしました。
- 主体的に動かなくなってしまう
- スキルなどが身につかない
- 業務に飽きる可能性がある
主体的に動かなくなってしまう
ホワイト業界は安定性が高く、コンプライアンスを重視するため規律もしっかりしています。
そのため、新人の研修制度や業務のマニュアルも整っており、決まったルールに従って仕事をすることが求められるケースが多いでしょう。
しかし、そういった環境で仕事を続けていると、新たな課題やチャンスを見つけようと積極的に動く機会が減り、いわゆる指示待ち人間になってしまう可能性があります。
主体的に動く感覚が鈍ると、予期せぬ事態への対応や新しい分野へのチャレンジが苦手になってしまうので、注意が必要です。
スキルなどが身につかない
ホワイト業界の仕事は社会に深く根ざした必要性の高いものであるケースが多く、新規参入のハードルも高めです。
そのため、新たな事業を展開したり、競争力を強化したりすることなく安定した一定の利益を見込めます。
これは働く個人のレベルでも同様であり、成果によるインセンティブが少ないので、収入を増やすために新しいスキルの習得が必要ありません。
そのため、ほかの業界に比べると仕事を続けていてもスキルが身につかず、成長性も低くなってしまう可能性があるでしょう。
業務に飽きる可能性がある
ここまで何度か触れてきたように、ホワイト業界の仕事では主体的に動いて変化を起こすよりも、決められたマニュアルに従うことが求められます。
業界全体が安定しているので、毎日の仕事が似たような業務の繰り返しに感じられてしまうケースも少なくありません。
そういった環境で仕事を続けていると、仕事そのものに飽きてしまったり、やりがいを見失ったりしてしまう可能性があるでしょう。
とくに、社会人として積極的にバリバリ働きたいと考える方は、大きなギャップを感じるかもしれません。
【ホワイトな業界とは?】「 ホワイト業界=安泰」ではない?知っておくべき落とし穴
一見すると理想的に思えるホワイト業界の環境にも、見過ごされがちな課題やリスク、いわゆる「落とし穴」が存在します。
入社してから「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、その言葉の裏に潜む可能性を理解しておくことが大切です。
- 会社はホワイトでも「部署ガチャ」で環境は変わる
- 成長の機会が少なく、市場価値が上がりにくい可能性がある
- 「ホワイト業界=自分に合う業界」とは限らない
ここでは、ホワイト業界を目指す際に知っておくべき注意点について解説します。
会社はホワイトでも「部署ガチャ」で環境は変わる
企業全体の評判が「ホワイト」であっても、全ての社員が同じように快適な環境で働いているとは限りません。
いわゆる「部署ガチャ」によって、労働環境が大きく左右される可能性があるためです。
例えば、全社的な平均残業時間は少なくても、特定の部署、特に花形部署や新規事業部門、トラブル対応を担う部署などでは、業務が集中し、恒常的に長時間労働が発生しているケースは少なくありません。
また、配属先の人間関係、特に直属の上司との相性も働きやすさを決める重要な要素です。
企業の文化がオープンで風通しが良くても、部署によっては旧態依然とした価値観が根強く残っていることもあります。
会社選びの際には、企業全体の評判だけでなく、OB・OG訪問などを通じて、部署ごとの実情や文化について、より解像度の高い情報を得ることが、入社後のミスマッチを防ぐ鍵となるでしょう。
成長の機会が少なく、市場価値が上がりにくい可能性がある
安定していて働きやすい環境は、裏を返せば、変化や挑戦の機会が少ない環境である可能性も秘めています。
ホワイト業界の企業は、既存の安定した事業モデルに依存していることが多く、若いうちから裁量権の大きい仕事や困難な課題に取り組む機会が比較的少ない傾向にあります。
ルーティンワークが中心で、日々穏やかに過ごせる半面、厳しい競争環境で得られるようなスキルや経験を積むことが難しく、自己成長のスピードが鈍化してしまう恐れがあるのです。
その結果、数年後に転職を考えた際に、同世代の他業界のビジネスパーソンと比較して、自身の市場価値が上がっていない、あるいはアピールできる実績が乏しいという事態に直面しかねません。
将来的なキャリアの選択肢を広げるためには、働きやすい環境に安住するだけでなく、主体的にスキルアップや資格取得に励む姿勢が重要になります。
「ホワイト業界=自分に合う業界」とは限らない
就活を始めたばかりの頃、つい「有名企業」や「ホワイト業界=正解」と思ってしまいがちだと思います。
ですが、どれだけ条件が良くても自分にとって合わない仕事だったら、毎日がつらく感じてしまうかもしれません。
・安定志向でルールに沿って働きたい人が、自由な発想やスピード感を求められるゲーム業界に入ったら?
・自分の意見を出したいタイプの人が、年功序列で上下関係の強い企業に入ったら?
どちらもホワイトな業界・企業かもしれませんが、働きやすさは人それぞれです。
だからこそホワイトかどうか?だけじゃなくて、自分に合っているかどうかを大切にしてみてください。
こちらでは自分にあう業界がわからない方に業界診断ツールを紹介します。
ぜひご利用ください。
【ホワイトな業界とは?】ホワイトな業界・企業か確かめる方法
続いて、ホワイトな業界や企業かどうかを確かめる方法について紹介します。
口コミを活用する、またはOBOG訪問をすることが代表的な方法ですが、口コミの場合は「OpenWork」と「エンゲージ」というサービスがおすすめです。
それぞれのサービスの特徴についても詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 口コミを活用する
- OB/OG訪問をする
口コミを活用する
ホワイトな業界や企業を見極めるためには、実際に働いた人の口コミを参考にすることが最もおすすめです。
求人情報や企業の公式サイトでは良い面ばかりが強調されがちなため、現場の実情を知るためには社員のリアルな声をチェックすることが重要です。
口コミには労働環境、実際の残業の実態、職場の雰囲気、福利厚生の充実度などが詳しく書かれていることが多く、企業選びの判断材料として活用できます。
ただし、口コミはあくまで個人の意見であり、全てを鵜呑みにするのは危険です。
部署や職種によって環境が異なる場合があるため、複数の口コミを比較して実態を把握するようにしましょう。
- OpenWork
- エンゲージ
OpenWork
OpenWorkは国内最大級の社員口コミ数を誇る情報プラットフォームで、企業の働きやすさや職場環境を知るために非常に役立つサービスであると言えます。
給与水準、ワークライフバランス、成長環境、企業文化など、様々な項目で評価があり、企業ごとのスコアを比較することも可能です。
特に、実際に働いている社員や元社員の評価が点数化されているため、客観的に企業を分析しやすいのが特徴と言えます。
また、企業の強みや課題についての具体的なコメントが多く掲載されており、求人票や公式サイトでは分からない情報を得ることもできます。
エンゲージ
エンゲージは日本最大級の社員口コミサイトで、22万社以上の企業の口コミが掲載されている、非常に大きな媒体です。
正社員だけでなく、アルバイトや契約社員の口コミも掲載されているため、幅広い視点から企業の実態を知ることができます。
特に、中小企業やベンチャー企業などの情報も豊富に掲載されており、大手企業以外の選択肢を考える際にも役立ちます。
また、エンゲージは職場環境、福利厚生、成長の機会などについての詳細なコメントが多いため、企業の良い点と悪い点の両方を知ることができるのも魅力の1つです。
OB/OG訪問をする
OB/OG訪問は実際に企業で働いている社員と直接話すことができる貴重な機会であり、インターネットだけでは得られないリアルな情報を知ることができます。
特に、社内の雰囲気、職場環境、人間関係など、口コミサイトでは分かりにくい部分について詳しく聞けるのがメリットです。
業界の実情やキャリアパス、社内の雰囲気などについても聞けるため、就職活動の方向性を決める上でも役立つでしょう。
また、的確に質問ができれば企業研究が深まりますし「意欲のある人物」というアピールができるため、少しかもしれませんが、内定が近づく可能性もあります。
ホワイト企業に行くためには?
続いて、ホワイト企業に就職するためにはどのような対策をしなければならないのかについても詳しく紹介します。
ただ「楽で、休みが多くて、給料が高い」という利益を「享受するだけ」の姿勢では、就活は成功しません。
自分に合っており、自分が価値を提供できる企業がどのようなものなのかを判断することが必須です。
以下の3つの対策を入念に行えば、福利厚生などがしっかりしている、ホワイト企業への就職を叶えられることでしょう。
- 自己分析をする
- 業界・企業研究をする
- インターンシップに参加する
- 適職診断ツールを用いる
自己分析をする
まず自己分析を徹底することが重要です。
自己分析は自分自身の強みや価値観、キャリアで重視する要素を理解するためのプロセスであり、就職活動の土台とも言えるものです。
ホワイトな企業では働きやすい環境が整っている反面、企業ごとに求められるスキルや人物像が異なるため、自分に合った企業を見つけるための自己理解が不可欠です。
どのような状況で力を発揮しやすいか、どのような働き方が自分に向いているのかを明確にすることで、ホワイトな企業の中でも自分に適した職種や企業を見極めやすくなります。
自己分析を行う際には過去の成功体験やチャレンジした経験、さらに自分がモチベーションを感じる状況を具体的に振り返ると良いでしょう。
また、自分の価値観や大切にしているもの、例えば、成長環境や働きがい、ワークライフバランスなどを整理しておくことで、企業選びの指針が定まります。
業界・企業研究をする
ホワイトな企業に進むためには業界や企業についての理解を深めることが欠かせません。
業界・企業研究を行うことで、どのような職場が働きやすいか判断でき、そして福利厚生や労働環境が整った企業を見つけることができます。
業界研究では業界全体の平均年収や残業時間、離職率など、具体的なデータを参考にし、ホワイトな企業の条件に合致するかどうかを見極めましょう。
また、企業研究を行う際にはその企業が持つビジネスモデルや成長戦略、業界内での競争ポジションについても理解を深めると、入社後の自分の役割や働き方が具体的に想像できるようになります。
企業の公式サイトや採用ページ、さらにはOB・OG訪問や口コミサイトなどの情報を活用して、企業の文化や社員の働き方についてのリアルな情報を収集することも大切です。
インターンシップに参加する
ホワイト企業を目指す際には、インターンシップに参加することもおすすめです。
インターンシップで実際の業務に触れることで企業文化や働きやすさを直に体験できるため、企業の雰囲気を肌で感じる機会になります。
インターンシップを通じて社員同士のコミュニケーションの取り方や働きやすさが重視されているかを確認でき、自分に合った職場環境であるかを判断する材料が得られます。
実際の業務に関わることで仕事の達成感ややりがいを体験し、自分の「働きやすさ」の基準を見つけることもできます。
インターンシップ中は業務内容に加え、職場の人間関係や上司・同僚との距離感なども注視することが大切です。
特にホワイトな企業では社員が互いにサポートし合う文化が根付いているため、インターンシップ期間中に確認し、自分が「働きやすそうだ」と思えるかどうかを考えましょう。
適職診断ツールを用いる
適職診断ツールを用いることで、自分が向いている業界や企業がどのようなものであるのかについても判断できます。
自分で分析するのも悪いことではありませんが、どうしても主観的な要素が入り込んでしまいます。
そこで適職診断ツールを用いて、客観的に判断してみましょう。
弊社が提供しているツールを利用すれば、LINEで52個の質問に答えるだけと、数分であなたの強みや向いている業界が判断できます。
完全無料で利用できるため、気になる方はぜひ以下のリンクから登録してみてください。
【ホワイトな業界とは?】エージェントに相談しよう
「自身にはどのような業界が合うのかわからない」「業界研究の方法がわからない」といった悩みは、多くの就活生が抱えています。
また、就職活動ではES作成や面接対策などしなければいけないことも多いので、自己分析や業界研究の時間が確保できない方もいるでしょう。
そういった場合は、就職のプロであるエージェントに相談するのがおすすめです。
適切な就活対策に関するアドバイスや、書類・一次選考が免除される特別選考ルートへの案内も可能なので、気になった方はぜひこちらのリンクからチェックしてみてください。
おわり
ホワイト業界とは、高い給与や充実した福利厚生を兼ね備えた働きやすい業界であり、新規参入が少なくBtoBのビジネスを展開している分野に多く見られます。
具体例としては、インフラ業界、食品業界、たばこ業界などが挙げられるでしょう。
しかしホワイト業界には、仕事の変化が少なく、スキルが身につきにくいといったデメリットも存在します。
人によって向き不向きが分かれやすいので、まずはしっかりと自己分析と業界研究をおこない、自身に合っているかどうかを慎重に判断することが大切です。