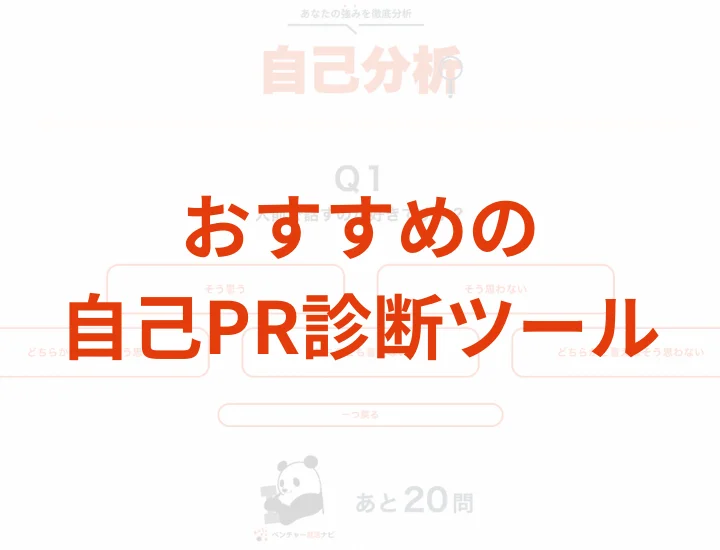明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート
・面接官が面接が苦手な人をどう思っているのか
・面接が苦手な人の克服方法
・面接が苦手な人
・面接で失敗したくない人
・面接が苦手な原因が分かっていない人
はじめに
面接が得意な人ばかりではありませんし、むしろ苦手な人が多いでしょう。
しかし、面接が苦手だからといって具体的な対策を避け続けていると、いくら質の高いESを作成しても意味がありません。
そこで本記事ではなぜ面接が苦手なのかについて深掘りし、それぞれの原因別に対策を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
【面接が苦手】面接が苦手だと内定に繋がらない?
結論として、面接が苦手だと内定に繋がらないというわけではありません。
しかし、対策せず、面接が苦手なまま「放置」してしまっていれば、内定を獲得することはなかなか難しいでしょう。
面接が苦手でも、何が苦手なのか自分と向き合い、適切な対策をすることができれば内定を獲得することはできます。
これまで弊社の就活エージェントを利用して内定を獲得した人のほとんどはもともと面接が苦手でした。
しかし、以下で紹介する対策を徹底的に行った結果、内定を獲得できた方がほとんどです。
ぜひ諦めずにしっかりと対策を行い、内定を獲得してください。
【面接が苦手】面接が苦手な人の面接官の評価とは?
続いて、面接が苦手な人に対する面接官の評価について紹介します。
特に緊張しやすい人や、コミュニケーションが少し苦手な人が多いでしょうから、以下の2つに焦点を当てて説明します。
- 緊張しやすい人
- コミュニケーションが少し苦手な人
緊張しやすい人
面接で緊張してしまうことは誰にでも起こり得る自然な反応です。
緊張自体を気にしすぎる必要はありませんが、それが面接の流れに影響を与える場合、面接官はその原因と背景を冷静に見ています。
面接官が注目するのは緊張そのものではなく、その状況下でどのように対応し、自己表現を試みているかという点です。
面接で緊張すると、話すスピードが速くなったり、言葉が詰まったりすることがあります。
このような場合でも、面接官は「緊張しながらも誠実に質問に答えようとしている」と評価することが多いです。
自分自身の緊張を隠そうとせず、むしろ「少し緊張していますが、落ち着いてお話しできるよう努めます」と一言伝えることで、面接官に前向きな印象を与えることもできます。
面接官が緊張しやすい人に対して最も評価するのは「緊張しながらも一生懸命伝えようとする姿勢」や「誠実さ」です。
そのため、緊張を完全に克服することよりも、その状況で最大限の努力を見せることが大切です。
コミュニケーションが少し苦手な人
面接での受け答えに不安を感じる場合でも、自分の伝えたいことを整理し、的確に伝える努力をすることが重要です。
面接官は話の流れや言葉遣いよりも「自分の考えを伝えようとする姿勢」に注目しています。
そのため、多少言葉に詰まったり、表現が簡素になってしまっても、伝えようとする意欲が評価されます。
例えば、質問に対する答えがまとまらなかった場合でも「少し考える時間をいただいてもよろしいでしょうか」と伝えることで、自分のペースを取り戻せるでしょう。
また、コミュニケーションが苦手と感じる人が意識したいポイントの1つは「要点を絞る」ことです。
話を短くまとめることで、伝えたい内容をより簡潔に伝えることが可能です。
例えば「なぜその企業を選んだのか」という質問に対して、自分の経験や価値観に基づく具体例を1つ挙げるだけでも、十分に説得力が生まれます。
【面接が苦手】面接が苦手な人の原因は?
続いて、面接が苦手な人の原因について考えてみましょう。
代表的な原因は以下の7つが考えられます。
自分がどれに当てはまるのか、考えてみてください。
また、この次の見出しでは原因別の克服方法についても紹介しています。
- 緊張しい人である
- 面接練習不足である
- コミュニケーション能力不足である
- 完璧主義になっている
- 面接で失敗した経験がある
- 面接で落ちることを恐れている
- 自分をアピールすることが苦手
1.緊張しい人である
緊張しやすい人が、人生において重要な場面の1つである面接に苦手意識を持つのは当然のことです。
しかし、緊張そのものが悪いわけではありません。
むしろ、適度な緊張は集中力を高める効果があります。
緊張しやすい理由は自分の評価を気にしすぎるあまり、失敗への不安が大きくなっていることが多いです。
面接中に言葉が詰まったり、思考が混乱したりすると「自分はダメだ」と感じてしまうかもしれません。
緊張を克服するためには事前準備を徹底し、自分が話す内容に自信を持つことが重要です。
また、模擬面接を繰り返すことで、面接の雰囲気や流れに慣れることができ、実際の面接でも落ち着いて話せるようになります。
緊張しやすい人ほど「緊張を前向きなエネルギーに変える意識」が大切です。
2.練習不足である
面接練習が不足している場合、面接に対する苦手意識が強くなることは当然です。
準備不足は自信の欠如につながり「どんな質問が来るかわからない」という不安を引き起こします。
特に初めての面接では形式や雰囲気が分からず、戸惑ってしまうことが多いです。
面接練習を行う際には模擬面接を積極的に活用することが効果的です。
例えば、大学のキャリアセンターで実施される練習や、友人とロールプレイを行うことで、面接の流れや質問への対応を体感できます。
また、練習時には自分の回答を録音して客観的に振り返ることで、改善点を把握しましょう。
練習不足を解消するには質問例をリストアップし、想定回答を用意することが重要です。
3.コミュニケーション能力不足である
面接ではコミュニケーション能力が重要な評価ポイントになります。
そのため、普段から会話が苦手な人や、自分の意見をうまく伝えられない人は面接に対して苦手意識を抱きがちです。
しかし、コミュニケーション能力は練習次第で改善できるスキルです。
面接官が見るのは「完璧に話せるか」ではなく、自分の考えを真摯に伝えようとする姿勢です。
コミュニケーション能力を磨くためには普段から他者との会話を増やし、自分の意見を整理して話す練習をすることを推奨します。
例えば、友人や家族に面接で話す内容を伝えてフィードバックをもらうことで、自信をつけることができます。
また、話すだけがコミュニケーションではありません。
相手の話をしっかり聞き、的確に応答することもコミュニケーション力向上の鍵です。
4.完璧主義すぎる
完璧主義な人は余計なプレッシャーを感じ、苦手意識が強まります。
「失敗してはいけない」「全ての質問に完璧に答えなければならない」と考えすぎると、緊張感が高まり、実際のパフォーマンスが低下することがあります。
このような状態では本来の自分をアピールする余裕がなくなり、結果として自己表現がうまくできなくなってしまいます。
完璧主義を克服するには「面接はあくまで自己表現の場であり、失敗することもある」と前向きに捉える姿勢が重要です。
面接官は答えの内容以上に、どのような姿勢で質問に向き合っているかを見ています。
分からない質問をされたときに「完璧に答えられないから、もう終わりだ」と諦めるのはもってのほかです。
わからない質問でも「それは〇〇という意味でしょうか?」「申し訳ありません。勉強不足でその用語を存じ上げていないのですが、どういった意味でしょうか?」など、誠実に答えましょう。
5.面接で失敗した経験がある
面接で失敗した経験があると、それがトラウマとなり、次の面接に対して苦手意識を持つことがあります。
失敗を繰り返すことへの恐れが自信を失わせ、面接全体にネガティブな影響を及ぼすからです。
しかし、失敗は次へのステップであり、そこから学びを得ることが重要です。
失敗を振り返る際には何が原因だったのかを冷静に分析し、具体的な改善策を考えましょう。
例えば、面接で話がまとまらなかった場合、回答を簡潔に整理する練習をすることで、次回の面接ではスムーズに話せるようになります。
また、緊張で言葉が詰まった場合は模擬面接を繰り返すことで、本番での対応力を高めることもできます。
面接の失敗は次の機会で同じミスを繰り返さないための貴重な経験と捉えるべきです。
成功体験に変えるために、前向きな姿勢で取り組むことが、自信を取り戻す第一歩となります。
6.面接で落ちることを過度に恐れている
面接で落ちることへの恐怖は多くの就活生が抱える共通の悩みです。
「この面接に落ちたらどうしよう」という考えばかりが先行すると、自分の考えを十分に伝えられなくなり、本来の力を発揮するのが難しくなります。
この恐れを克服するには、失敗を過度に意識しないことが重要です。
落ちることを恐れる気持ちは準備不足や自信の欠如から来る場合が多いです。
事前に企業研究や模擬面接を徹底的に行い、質問に対する回答を準備することで、自信をつけることができます。
また「面接は合否を決定する場でもあるが、自分を知ってもらう機会でもある」と考えると、気持ちが軽くなります。
そして「落ちたとしても、得た経験は次に活かせる」など前向きな考え方を持つことで、プレッシャーを軽減できるでしょう。
7.自己アピールが苦手
自分をアピールすることが苦手だと、面接が難しいと感じる原因になります。
「自分には目立った強みがない」と思い込んでしまうことで、堂々と話すことができなくなるからです。
アピールが苦手な場合、自分の経験を具体的に振り返り、それをどう活かしてきたのかを整理すること、つまり自己分析から始めましょう。
例えば、大学でのグループプロジェクトやアルバイト経験を通じて培ったスキルを見直し、それが志望する企業でどのように役立つかを考えることで、具体的なアピール内容が見えてきます。
また、模擬面接を繰り返し行うことで、自分をアピールする練習を重ねると、自信がついてきます。
最初はうまく話せなくても、回数を重ねることで徐々に話し方や表現が洗練されていくはずです。
【面接が苦手】苦手な原因別の克服方法
続いて、先ほど紹介した「面接が苦手な原因」別の克服方法について紹介します。
あなたがなぜ面接が苦手であるのかを言語化できたら、続いてその原因を根本的に解決するフェーズに入りましょう。
以下の対策をしっかりと行えば、面接に対する苦手意識が薄れ、本番では胸を張って臨めるようになるはずです。
1.緊張しやすい人の克服方法
多くの企業の人と話せる機会だと考える
面接を「評価される場」と捉えると、緊張感が増し、自分の言葉でうまく伝えられないことがあります。
しかし、視点を変えて「企業の人と直接話せる貴重な機会」と考えることで、緊張を和らげることが可能です。
面接は企業と自分が互いを理解し合う場であり、一方的に評価されるだけではなく、自分の疑問や興味を伝える場でもあります。
そのように考えることで、必要以上に構えず、リラックスして臨むことが可能になります。
また、面接の場を通じて、企業の価値観や仕事の進め方を直接聞けることは就職活動において貴重な情報源となります。
「評価される場」ではなく「対話を楽しむ場」として面接を考えることで、自然なコミュニケーションが可能になるでしょう。
「落ちても、命を取られるわけではない」と考えて、できるだけ気楽に臨みましょう。
緊張していることを面接時に伝える
面接で緊張しているときは無理に隠そうとせず、その気持ちを素直に伝えることで緊張が緩和できることもあります。
「少し緊張しています」と一言話せば、相手も配慮してくれますし、むしろ「そんなにうちに入社したいのか」とやる気を評価されることでしょう。
「緊張していますが、一生懸命お話しします」など、前向きな姿勢を示す言葉を加えると、より良い印象を与えられます。
また、緊張を伝えることは自分自身を落ち着かせる効果もあります。
自分の緊張を客観的に認識し、それを言葉にすることで、焦りを軽減し、冷静さを取り戻しやすくなるのです。
その結果、質問に対して的確に答えたり、自分の考えを整理して伝えることができるようになります。
2.コミュニケーション能力不足の人の克服方法
質問の意図を汲み取ることを意識する
コミュニケーション能力不足を克服するためには、面接官が質問を通じて何を知りたいのか、その意図を汲み取ることが重要です。
質問の意図を理解せずに表面的な回答をしてしまうと、面接官が求める情報を提供できず、結果として良い印象を与えることが難しくなります。
面接官が投げかける質問にはその学生の価値観やスキル、経験、職場での適応力を確認する意図が含まれています。
そのため、ただ質問に答えるだけでなく「この質問を通じて何を評価しようとしているのか」を意識することが大切です。
質問の意図を汲み取るためには事前に面接でよく聞かれる質問をリストアップし、それぞれの質問が何を評価するためのものかを考える練習が効果的です。
例えば「あなたの強みは何ですか?」という質問では自分が職場でどのように活躍できるかを具体的に伝える必要があります。
また、面接中に質問の意図が分からない場合でも、焦らず「確認なのですが、〇〇についてお話しすれば良いでしょうか?理解力が足りず、申し訳ありません」などと確認する姿勢を示せば、安心して回答できますし、相手も誠実さを評価してくれます。
ただし、この場合「何を言っているのかわからないよ」という言い方ではなく「自分の理解力が足りず、申し訳ない」という姿勢を示しましょう。
表情や姿勢を意識する
コミュニケーションには言葉だけでなく、表情や姿勢といった非言語的な要素も重要な役割を果たします。
面接中に自分の意見をうまく言葉にできなくても、明るい表情や誠実な態度が相手に好印象を与えることがあります。
逆に、不安そうな表情やうつむきがちな姿勢はコミュニケーションへの意欲が低いと受け取られる可能性があるため、注意が必要です。
まず、表情を意識することで、自分の考えや熱意をより明確に伝えられます。
笑顔を忘れずに、相手の目を見て話すことで、面接官との信頼関係が築きやすくなるでしょう。
特に、相手が質問を投げかけている間も頷き、アイコンタクトを通じてしっかり聞いていることを示すと、相手に安心感を与えることができます。
3.完璧主義すぎる人の克服方法
言葉が出なくても良いことを理解する言葉に詰まっても問題ないことを理解する
面接で完璧を求めすぎると、想定外の質問に対して言葉に詰まった際「失敗した」と感じてしまうことが多々あります。
しかし、面接官は答えそのものよりも「質問に対してどう向き合うか」という「姿勢」を重視しています。
したがって、言葉に詰まること自体が即座に評価を下げる原因にはなりません。
むしろ、冷静に対応する姿勢や正直に考えを伝える態度が好印象を与えることも多いです。
言葉に詰まったときは焦らずに「少し考える時間をいただけますか」と落ち着いて伝えることで時間をもらえますし、真剣に取り組んでいることも伝わります。
全ての回答に完璧に答える必要はないことを意識して「自分らしく話す」ことを優先することで、過度なプレッシャーから解放されます。
聞き返しても良いことを理解する
完璧主義の人は面接官の質問に即座に答えなければならないと考えがちです。
その結果、質問の内容を誤解したまま回答してしまう場合や、焦りから十分な答えが出せない場合があります。
しかし、質問を聞き返すことはマイナスの評価にはなりません。
むしろ、質問の意図をしっかり理解しようとする姿勢は面接官に誠実で慎重な印象を与えます。
質問が聞き取れなかった場合や、内容が曖昧に感じた場合には「もう一度お聞きしてもよろしいでしょうか?」と丁寧に聞き返しましょう。
質問を聞き返すことは自分が相手の意図を正確に把握しようと努力している証拠です。
この姿勢は仕事の場面でも「相手の要望を正確に理解しようとする能力」があることをアピールすることにもつながります。
曖昧な指示をそのまま受け取るのではなく、疑問を解消するために質問する姿勢は職場でも高く評価されるものです。
4.面接で失敗経験がある人の克服方法
失敗経験があるほうが良いことがある失敗した面接を徹底的に振り返る
面接で失敗を経験した場合、それをただの忘れたい出来事として終わらせるのではなく、自分を成長させるための最高のフィードバックと捉えることが大切です。
失敗から学ぶにはまず何が問題だったのかを具体的に振り返ることが必要です。
例えば「自分の回答が質問の意図とずれていた」「緊張しすぎて思うように話せなかった」「表情や姿勢が適切でなかった」など、失敗の原因を洗い出します。
この振り返りを行う際にはただ主観的に考えるだけでなく、模擬面接をしていた友人やキャリアセンターのアドバイザーなど、第三者の視点を取り入れると効果的です。
また、面接でのやり取りをメモに残しておくと、後で具体的にどの部分が課題だったのかが明確になります。
例えば「質問に対して結論から答えず、面接官に再度質問されてしまった」といった具体例を記録し、それをどう改善するかを考えることが重要です。
振り返りができたら、改善策を練り、次回の面接でどのように活かすかを計画しましょう。
面接ごとに求められていることが違うと理解する
面接が失敗に終わった原因の1つに、企業や職種ごとに求められる要素を十分に理解できていなかったことが挙げられます。
面接はどの企業でも同じように進むわけではなく、各企業の採用基準や評価ポイントは異なります。
そのため、自分の失敗を振り返る際にはその企業が何を求めていたのかを分析する必要があります。
例えば、ある企業ではチームでの協調性が重視される一方、別の企業ではリーダーシップが評価の中心となる場合があります。
自分が受けた企業の業界や職種を再度研究し、それに基づいた適切なアピールができていたかを確認しましょう。
もしその企業の価値観や目標を事前に理解していなかった場合、次回以降は企業研究を徹底し、自分の経験をその企業が求めるものと結びつけて話す練習を行うことが必要です。
5.面接で落ちることを過度に恐れている人の克服方法
面接官との相性が悪いことがあることを理解する
面接において落ちることを過度に恐れてしまう原因の1つは自分が全ての結果を左右していると考えてしまうことにあります。
しかし、面接は必ずしも自分の能力や準備不足だけが結果に影響するわけではありません。
面接官も人間であり、それぞれの価値観や考え方、受け取り方が異なるため、相性が影響を及ぼす場合があります。
そのため、面接がうまくいかなかったときは相性の問題だった可能性を考え、必要以上に自分を責めないことが重要です。
次のチャンスに向けて切り替えましょう。
一度の面接が全てではないため、面接官との会話を通じて得られた学びや反省点を次に活かす姿勢が必要です。
仕方がなく落ちてしまうこともあることを知る
面接で落ちることを恐れる人の多くは「全ての面接に受からなければならない」というプレッシャーを抱えてしまいがちです。
しかし、現実的にはどんなに準備をしても、全ての面接に合格することはありません。
企業側が求める人物像やタイミング、競争率など、自分ではコントロールできない要素も多いため、全てを自分の責任と捉える必要はないのです。
まず、面接では「選ばれなかったこと」が必ずしも能力の欠如を意味するわけではないことを理解することが重要です。
企業ごとに求める人材像は異なり、自分の強みや性格が必ずしもその企業に合わない場合もあります。
この場合、自分に合った企業を探すための1つのステップと捉え、前向きに次の挑戦に備えることが大切です。
6.自分をアピールすることが苦手な人の克服方法
周囲の人と協力の重要性を伝える
自分をアピールすることが苦手ならば、自分だけでなく周囲との関係性やチームでの役割を通じて自分の価値を伝える方法が有効です。
「自分が、自分が」と自分の功績ばかりを強調するのではなく「仲間があってこその自分」という視点で話を構成することで、謙虚さと協調性を同時にアピールできます。
特に、チームで成果を出した経験や、仲間がどのようにサポートしてくれたかを具体的に述べると、話に奥行きが生まれます。
例えば、チームで取り組んだプロジェクトを例に挙げる場合、自分がどのような役割を果たし、結果としてチーム全体にどのような影響を与えたのかを説明することが大切です。
このとき、仲間の協力やサポートを適切に取り入れることで「自己主張が強すぎない人物」としての印象を与えます。
さらに、仲間のサポートをどう活かして目標を達成したかを語ることで、感謝の気持ちや他者を尊重する姿勢も示せます。
企業に貢献できることを伝える
面接官が面接を通じて知りたいのは「この人が企業でどのように貢献してくれるのか」という点です。
そのため、自分が企業に対して提供できる価値や具体的なスキルを伝えることが、面接成功の鍵になります。
自分をアピールするのが苦手な場合でも、焦点を「自分の成果」ではなく「自分が企業に提供できること」に絞ると、話しやすくなるでしょう。
自分がこれまでに培ってきたスキルや経験を基に、どのように企業の課題解決に貢献できるかを説明します。
例えば、アルバイトやサークル活動で得たスキルを引き合いに出し、それが企業でどのように役立つかを話すと、説得力が増すはずです。
「自分は○○が得意なので、それを活かして貴社の業務改善に貢献したいと考えています」といった具体例を挙げることで、面接官に明確なイメージを与えられます。
7.練習不足な人の克服方法
面接練習を行う
面接の苦手意識を克服するには、まず徹底的な練習を行うことが重要です。
特に練習不足が原因で自信を持てない場合、実践に近い形での練習を繰り返すことで自信を育てることができます。
面接練習は友人や先輩、キャリアセンターのスタッフなど、様々な人と行うことがおすすめです。
異なる視点からのアドバイスを受けることで、自分では気づかない弱点や改善点を見つけられるからです。
練習の際には模擬面接の環境を可能な限り本番に近づけることが効果的です。
服装を整え、敬語の使い方や話し方を意識し、緊張感を持って臨むことで、実際の面接時の雰囲気に慣れることができます。
さらに、録画や録音をして後で自分の話し方や表情、姿勢を確認することも有益です。
自分の話し方や内容を客観的に振り返ることで、より具体的な改善点が見えてきます。
就活エージェントを使う
就活エージェントを活用することは最も抜本的かつおすすめの対策と言えます。
どのような悩みを抱えている人にもおすすめできる対策であるため、練習不足な人以外もぜひ参考にしてください。
就活エージェントは就活のプロが「無料で」面接対策を何度も行ってくれる非常にありがたいサービスであり、弊社が提供している「ジョブコミット」というサービスでも、面接連中が可能です。
あなたがなぜ面接で落とされてしまうのか様々な原因を企業側の目線から分析するため、原因が明確になっていない場合でも活用してほしいサービスです。
以下のリンクから無料で利用できるため、気になる方は登録してみてください。
面接が苦手】面接でよく聞かれる質問4選
面接でよく聞かれる質問を4つ紹介します。
これらの質問は100%聞かれると思っておいた方が良く、エントリーシートでも聞かれる可能性が高いため、質の高い回答を用意しておく必要があります。
特に、面接の際はエントリーシートに書いた項目をさらに深掘りして尋ねられる可能性が高いため、面接本番前に読み返し、以下の4つの項目を掘り下げておくことを推奨します。
自己紹介
自己紹介では文字通り、自分の紹介を行います。
大学名や学部・学科を伝えるだけでなく、自分の強みなどを一言添えて簡単に説明することを推奨します。
面接官はあなたがどのような人物なのかを短時間で把握しようと思って、この自己紹介を求めているからです。
また、志望動機・自己PR・ガクチカなどの中から、何か一言話すようにすると良いでしょう。
「継続力がある」「企業の理念に共感した」「学生時代は部活に力を入れた」など、一言を伝えることで面接官に印象を残しやすくなります。
また、時間に余裕がありそうであれば、それらに付随したエピソードなどについて話すと、より説得力が増すでしょう。
志望動機
志望動機では、なぜその企業を選んだのかを具体的に伝えることが大切です。
面接官は応募者の価値観やキャリアの方向性が自社と合っているかを判断するために、この質問を重視しています。
ただ「業界に興味がある」「企業理念に共感した」と述べるだけでは他の応募者と差別化できません。
そこで、説得力を持たせるために、企業の特徴を踏まえた理由を述べることが重要です。
その企業が提供するサービスの強みや独自性に魅力を感じたこと、成長環境が整っていること、特定の事業に関心を持ったことなどを話してください。
また、自分の経験やスキルがどのように活かせるのかを説明することで、入社後の活躍をイメージさせることもできます。
自己PR
自己PRではどのように活躍できるのかを示すことが大切です。
ただ強みを述べて終わるのではなく、その強みを発揮した具体的な経験などを交えて説明すれば、説得力が増します。
面接官は応募者の能力が自社で活かせるかを判断するために、わかりやすいエピソードを求めています。
どのような状況で強みが発揮されたのかを説明し、どのような成果につながったのかを示すことが重要です。
また、成功体験を話して終わるのではなく、困難を乗り越えた経験なども交えれば、より印象に残りやすくなるでしょう。
さらに、強みを発揮する過程でどのような工夫をしたのかまで述べられれば、より具体性が増します。
ガクチカ
ガクチカでは学生時代に力を入れたことをエピソードを交えて説明することが大切です。
面接官は応募者がガクチカを通じてどのような力を身につけたのか、そして入社後にどのように活かせるのかを知りたいと考えています。
そこで、ただ取り組んだ内容を淡々と述べるのではなく、どのような課題に直面し、どのように工夫して乗り越えたのかを具体的に伝えることを心がけてください。
状況や課題を意識することで伝わりやすくなります。
また、成果だけでなく、その過程でどのような努力をしたのかを伝えれば、面接官にあなたの成長のプロセスが伝わりやすくなることでしょう。
【面接が苦手】面接で役に立つテンプレートを紹介!
続いて、面接で活用できる回答のテンプレートについて紹介します。
このテンプレートは自己PR、志望動機、ガクチカなど、どのような内容にも活用しやすいPREP法という構成です。
もちろん質問内容に応じて多少変える必要はありますが、基本的には以下のような構成で作成しておけば、よほどおかしな回答が出来上がることはありません。
- 結論
- 理由
- エピソード
- 学び
- 入社後にどう活かすか
結論
面接で質問をされた際の回答では最初に結論を述べることが最も重要です。
結論を冒頭で伝えることで、面接官は話の方向性を明確に把握できます。
例えば「私が学生時代に力を入れたことは〇〇です」や「私の強みは〇〇です」といった簡潔な表現を用いることで、何を伝えたいのかを最初に明示することが可能です。
この手法は自己PRでも志望動機でもガクチカでも共通して有効です。
結論を最初に述べることで、聞き手は内容を整理しながら聞くことができ、話全体の理解が深まります。
話の冒頭で結論を明示しない場合、聞き手は内容を理解するのに余計な労力を要し、アピールの効果が薄れてしまいます。
そのため、話の軸を明確にする結論の提示は不可欠です。
理由
結論を述べた後にはその結論を裏付ける理由を明確に伝えることが必要です。
理由を述べることで、結論の妥当性や説得力を高められます。
例えば、自己PRで「私の強みは〇〇です」と述べた場合、その理由として「この強みを培った背景」や「強みを発揮する場面」を具体的に挙げると良いでしょう。
この理由付けによって、面接官は結論が「ただの個人的な主張」ではなく、現実に基づいていると認識します。
理由は論理的かつ簡潔に伝えることが求められますが、具体性が欠けると説得力が減少します。
したがって、結論と理由を密接に結びつけて話すことが大切です。
エピソード
理由を述べた後はそれを補強する具体的なエピソードを挙げることで、面接官に強い印象を与えることができます。
エピソードを通じて、あなたがどのような行動を取り、どのように課題に取り組んだのかを具体的に伝えましょう。
例えば「私は大学で〇〇のプロジェクトに参加し、〇〇という課題に取り組みました」という形式で話すと、面接官はあなたの人柄や行動力をイメージしやすくなります。
エピソードはリアリティが重要です。
具体的な数字や事例を盛り込み、面接官に「その場にいたかのような感覚」を与えると、より効果的なアピールが可能です。
学び
エピソードを述べた後にはそこから得た学びを伝えることで、面接官にあなたの成長を示します。
この学びを話す際にはエピソードと直接結びつけて話すことが大切です。
「この経験を通じて、私は〇〇を学びました」と具体的に述べることで、あなたがどのように成長したかが面接官に伝わります。
また、学びを話す際には仕事に直結するスキルや考え方を強調すると良いでしょう。
学びの部分は面接全体の中で最も重要な要素であり、面接官があなたを評価する際の基準にもなるため、深掘りして伝えることを心がけてください。
入社後にどう活かすか
最後に、得た学びを入社後にどのように活かすかを具体的に伝えることで面接官にあなたが企業にどのように貢献できるかを示しましょう。
「私はこの経験で身につけた〇〇を貴社の〇〇の分野で活かし、貢献していく所存です」と述べることで、面接官はあなたの入社後の働き方をイメージしやすくなります。
学びと入社後の活用法が一貫していると、あなたの志望動機や仕事への適性も自然と伝わります。
この部分は面接官が最も注目するポイントの1つであり、企業とのマッチ度を示す絶好の機会です。
そのため、企業研究を十分に行い、具体的かつ説得力のある回答を準備することが求められます。
【面接が苦手】良く聞かれる質問の回答例文を見よう!
続いて、面接においてよく聞かれる質問の回答例文を紹介します。
自己紹介・志望動機・自己PR・ガクチカの4つに分けて紹介するため、パターン別に参考にしてみてください。
自己紹介
まずは自己紹介です。
自己紹介の場合、自分の強みを加える、学業について一言加える、趣味について一言加えるなど、大きく分けて5つのパターンが存在します。
それぞれどのように話すのかについて、参考にしてみてください。
自分の強みを一言加える場合
状況に応じた対応力を強みとしています。
大学では学業と並行して飲食店でアルバイトに取り組み、お客様に寄り添った対応を心がけました。
店舗が混雑した際には状況に応じた動きを意識し、スタッフと連携を取りながら業務を円滑に進めました。
この経験を通じて、周囲と協力しながら臨機応変に対応する力の重要性を学びました。
入社後も変化の多い環境の中で柔軟に対応し、チームの成果に貢献する所存です。
本日はこのような経験を活かしながら、自分の言葉で説明できるように心がけます。
よろしくお願いいたします。
学業を一言加える場合
経済学を専攻し、データ分析を用いた研究に取り組み、論理的思考力を磨いてきました。
ゼミでは小売業の売上向上をテーマに、データをもとにした購買行動の分析を行いました。
特に、店舗ごとの売上データをもとに来店時間や商品カテゴリの関連性を検証し、販売促進の効果的な施策を提案しました。
研究を進める中で、仮説を立てて検証するプロセスの重要性を学びました。
入社後は数値をもとにした提案を行い、貴社の成長に貢献する所存です。
本日はこれまでの経験を活かしながら、自分の考えをわかりやすくお伝えできればと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
趣味を一言加える場合
趣味として登山に取り組んでおり、普段から体力向上に努めています。
先日、仲間とともに日本各地の山に挑戦した際、途中で天候が悪化し、予定通りのルートを進むことが難しくなりました。
しかし、話し合いながら状況を分析し、安全を確保しつつ目的地点に到達する方法を模索しました。
この経験を通じて、困難な状況でも冷静に対処し、目標達成に向けて努力し続ける力を身につけました。
本日は自分の好きなことを続ける中で学んだことを活かしながら、お話しできればと考えています。
よろしくお願いいたします。
留学経験を一言加える場合
留学経験を通じて、様々な環境への適応力を養いました。
大学2年次に半年間アメリカに留学し、現地の学生と共同でプロジェクトに取り組んだことが印象に残っています。
言語の壁や文化の違いに戸惑うこともありましたが、積極的にコミュニケーションを取ることでチームの一員として信頼を得ることができました。
この経験を通じて、未知の環境でも自ら動き、周囲と協力する大切さを学びました。
本日はこのような経験を活かしながら、お話しできればと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
キャッチコピーを一言加える場合
「挑戦し続けること」をモットーにしております。
大学では学業と並行してフルマラソンに挑戦しました。
長距離走は得意ではありませんでしたが、計画を立て、継続的にトレーニングを積むことで4時間を切るタイムを達成しました。
途中でペースが落ちそうになった際も、自分を鼓舞しながら最後まで走り抜いた経験が自信につながりました。
この経験から、困難に直面しても諦めずに努力を続ける力を養うことができました。
本日は自分の大切にしている価値観や経験をお伝えしながら、お話しできればと考えています。
よろしくお願いいたします。
志望動機
代表的な業界を5つ選び、志望動機の例文を作成しました。
どのように回答しているのか、どのような点を強調しているのかを意識しながら、ぜひあなたが目指している業界以外の例文も参考にしてみてください。
金融業界
大学のゼミで中小企業の資金調達について調査し、金融機関のサポートが企業の成長に直結することを学びました。
その経験を通じて、企業を支える仕事に携わりたいと考えるようになりました。
御社は幅広い金融サービスを提供しながら、中小企業向けの融資アドバイザリー業務に強みを持っており、私が目指すキャリアに最適な環境です。
入社後はそれぞれの企業の課題を的確に把握し、最適な資金調達の提案を行うことで、日本経済の発展に貢献できればと考えています。
IT業界
大学で情報工学を専攻し、データ分析を活用した課題解決に取り組んできました。
ゼミではAIを用いた需要予測モデルの開発に携わり、データを活用することで業務効率を大幅に向上できることを学びました。
御社は最新技術を活用したソリューション提供に強みを持ち、社会課題の解決に取り組んでいる点に魅力を感じています。
入社後は技術の知識を活かしながらクライアントの課題を解決する提案を行い、御社のさらなる業績向上に貢献する所存です。
コンサルティング業界
大学のゼミでは実際の企業の事例をもとに成長戦略を立案し、収益向上のための施策を提案するプロジェクトに取り組みました。
データを分析しながら論理的に成長を考える面白さを実感し、経営支援に携わる仕事に興味を持ちました。
御社は戦略策定から実行支援まで幅広く企業の成長をサポートしており、学んできたことを活かせる環境であると考えています。
入社後は論理的思考力を活かし、クライアントの課題を的確に分析し、最適な戦略を立案することで、御社のさらなる成長に貢献する所存です。
不動産業界
大学で地方都市の再開発プロジェクトについて調査し、適切な不動産投資が地域経済に与える影響を学びました。
また、実際に再開発が進んでいるエリアを訪問し、現地の課題をヒアリングする機会もあり、不動産が人々の生活に与える影響の大きさを実感しました。
御社は大規模な開発案件を手掛けるだけでなく、地域に根ざした不動産活用にも力を入れており、私のキャリア志向と一致しています。
入社後はまちづくりの視点を持ちながら、不動産を活用した提案を行い、より良い都市環境の創出に貢献する所存です。
人材業界
ゼミの専攻は心理学で、モチベーション向上の要因について調査し、環境や働き方が個人の成長に大きく影響を与えることを学びました。
また、アルバイト先では新人の教育を担当し、心理学の知見を活かして指導方法を工夫する中で、人の成長を支援することのやりがいを実感しました。
御社は企業の人材戦略を支援する幅広いサービスを提供しており、人と企業の成長をつなぐ仕事ができる環境が整っていると感じています。
入社後は相手の強みを引き出す視点を活かし、企業と求職者の最適なマッチングを実現し、多くの人々を目指す企業へと導きたいと考えています。
自己PR
自己PRは多くの就活生がアピールしやすい能力を5つ選び、それを主題として例文を作成しました。
あなたがアピールしたいと思っている能力以外の例文も、それぞれ参考になるはずなので、ぜひ5つの例文を読み、感覚を掴んでください。
継続力
英語のスピーキング力向上を目指し、毎日30分の音読と週1回のオンライン英会話に取り組みました。
最初は簡単な会話もできず、自信をなくすこともありましたが、諦めずに学習を続けました。
実践的な場面でスピーキングを鍛えるため、外国人観光客のボランティアガイドにも挑戦しました。
最初はうまく話せず苦戦しましたが、繰り返し経験を積むことで、徐々に相手の反応を見ながら話せるようになりました。
この経験から、粘り強く物事を継続する力をさらに高めることができました。
入社後は未経験の業務にも積極的に取り組み、新しい知識やスキルを習得し続けながら、様々な業務を担当できる人物として貢献する所存です。
協調性
大学ではゼミのグループ研究でリーダーを務め、地域活性化をテーマにした研究に取り組みました。
当初、観光資源の活用と地元住民の生活向上のどちらを優先すべきかで意見が分かれましたが、双方の意見を尊重しながら、観光資源の活用が地元住民の生活向上につながる仕組みを考え、全員が納得できる結論を導き出しました。
この経験を通じて、意見をまとめる力に自信を持ちました。
入社後はまず自らの業務を完璧にこなせるよう努力し、数年後には皆の意見を尊重し、チームをまとめ、最大の成果を生み出せるリーダーとして貢献したいと考えています。
責任感
大学時代、飲食店のアルバイトでシフトリーダーを任され、店舗運営の一端を担いました。
重要な繁忙期には全体の動きを把握しながら適切な指示を出し、オーダーの優先順位を判断してホールとキッチンの連携を強化することで、スムーズな提供を実現しました。
急な欠勤も多くありましたが、率先してフォローし、他のスタッフと協力して営業を円滑に進めました。
店長からは「社員になってほしいほどだ」と評価され、新人教育の担当も任されました。
入社後は一つひとつの業務に責任を持ち、周囲と協力しながら成果を上げ、信頼される存在となる所存です。
傾聴力
大学ではボランティアサークルに所属し、特に地域の高齢者向けの交流ボランティアに参加しました。
活動を通じて、相手の話をしっかりと聞き、適切に応対することが信頼関係の構築につながることを学びました。
特に、ある方から「家族以外に話を聞いてくれる人がいない」と言われたことがあり、気持ちに寄り添いながら丁寧に話を聞くことを心がけました。
その結果、少しずつ心を開いてくださり「次はいつ来るの?」「毎日来てほしい」とまで言っていただけるようになりました。
入社後も、相手の意見を丁寧に聞き、適切な対応を取り、信頼関係を構築しながら業務を進める所存です。
チャレンジ精神
大学時代、プログラミングに挑戦し、独学で学習を進めながらアプリ開発を行いました。
当初はエラーが多く、挫折しそうになりましたが、オンラインの教材や理系の友人などのアドバイスを得ながら、粘り強く学習を続けました。
また、学生向けのハッカソンにも参加し、チームでアプリを開発した際は限られた時間の中で試行錯誤を重ねながら完成させ、プレゼンテーションで高い評価を受けました。
入社後はプログラミングスキルを活かしつつ、新しい言語も積極的に学びながら、プログラミングだけでなく様々な業務を担当できるオールラウンドな人物として貢献する所存です。
ガクチカ
多くの方が学生時代に経験したであろう5つの経験別に、ガクチカ例文を作成しました。
時間に余裕がない方は、自分がアピールしようと思っている経験だけ読んでいただいて構いませんが、余裕がある方はぜひ、他の例文も熟読してコツを掴んでください。
アルバイト
スタッフ間の連携を強化しようと、ホールとキッチンの間で注文状況をリアルタイムに共有する仕組みを整え、提供までの時間短縮を実現しました。
また、お客様への声かけを徹底し、待ち時間のストレスを軽減するよう努めた結果、店舗の回転率が向上し、売上も前年比15%向上しました。
この経験から、問題を発見し、チームで解決に向けて行動する力を養いました。
入社後は顧客の要望や業務プロセスを詳細に分析し、より良いサービスや業務改善案を提案することで、御社のさらなる業績向上に貢献できればと考えています。
部活動
入学当初は筋力不足、そしてフォームが悪く、思うようなタイムが出せませんでした。
そこで、先輩やコーチのアドバイスをもとに、筋トレとフォーム改善に毎日取り組みました。
また、動画を活用して自分の走りを分析し、無駄な動きを減らすことを意識した結果、半年で自己ベストを1秒以上更新し、地区大会では2位に入賞できました。
この経験から、目標達成に向けて計画を立て、継続的に努力する能力を身につけました。
入社後はデータを分析し、業務プロセスの改善策を提案することで、よりスムーズに業務に取り組める環境づくりを行い、貢献できればと考えています。
留学
英語力を向上させ、異文化への理解を深めるため、半年間アメリカへ留学しました。
当初は英語でのコミュニケーションに苦戦し、意思疎通がスムーズに行えない場面も多くありました。
しかし、事前に議論内容を整理し、的確に意見を伝える練習を重ねた結果、英語力が向上し、相手の考えを深く理解できるようになりました。
この経験を通じて、課題解決のために主体的に行動し、協力する力を身につけました。
入社後は相手の意図を正確に理解することを意識し、英語力と文化理解力を活かしながら、適切な提案を行うことで、営業職として貢献できればと考えています。
研究
消費者の購買行動をデータ分析して、売上向上の要因を探りました。
大手企業の販売データを基に価格設定や広告戦略が消費者心理に与える影響を分析しましたが、データの扱いが難しく、当初は適切な分析手法を見つけるのに苦労しました。
そこで、専門書を読み込み、教授に相談しながら試行錯誤を重ねた結果、データの傾向を捉え、実際の企業戦略に応用できる提案を行いました。
この経験から、論理的に物事を分析し、根拠に基づいた提案を行う力を養うことができました。
入社後はデータ分析のスキルを活かし、顧客のニーズを的確に捉えた戦略立案を行うコンサルタントとして貢献する所存です。
ボランティア活動
特に、子供向けの学習支援に力を入れ、担当生徒の学習意欲を高めることを目指しました。
勉強に苦手意識を持ち、授業についていけない子が多かったため、教えるだけでなく、生徒の関心を引き出す工夫をしました。
ゲーム感覚で問題を解く方法を取り入れたり、目標を一緒に設定したりすることで、学習の楽しさを伝えました。
その結果、生徒が積極的に学ぶ姿勢を見せるようになり、成績も向上しました。
この経験から、相手に合わせて対応する力と、やる気を引き出す工夫の大切さを学びました。
入社後はまず自分の役割を全うできるようになり、その後、モチベーションを引き出せるリーダーとして貢献できればと考えています。
【面接が苦手】面接での回答を作成するコツ
面接で質の高い回答を用意するためにはどのような点を意識すれば良いのかについて詳しく紹介します。
以下の3点を意識しておけば、あなたの面接の回答のクオリティが高まり、面接官も納得してくれるようになることでしょう。
ぜひ参考にしてみてください。
自己分析を徹底する
面接の回答を作成する上で、最も重要なのは自己分析を徹底することです。
自己分析を行うことで、自分の価値観が明確になり、企業にどのように貢献できるのか具体的に伝えられるようになります。
自分の得意なことや、過去に努力して成果を上げた経験を振り返り、面接で話すべきエピソードを整理しましょう。
また、その経験が自分にとってなぜ重要だったのかを深掘りすれば、自分の考え方や行動の傾向を把握することも可能です。
さらに、自己分析を通じて、自分がどのような環境で力を発揮できるのかを知ることも大切です。
チームで協力することが得意なのか、それとも個人でじっくり取り組む方が向いているのかを理解することで、自分に合った企業・職種を選ぶ判断材料になります。
企業分析を行う
企業分析を行うことも、面接でより良い回答をする上で欠かせません。
求める人物像を把握すれば、自分がどのように貢献できるかを明確に伝えられるからです。
採用ページなどを確認し、企業理念、ビジョン、事業内容を把握すれば、どのような価値観を大切にしているのかが明確になります。
また、企業がどのような人物を求めているのかを理解すれば、面接の際に自分の経験をどのように結びつけるかも見えてきます。
また、企業分析を行うことで、志望動機の説得力を高めることも可能です。
企業は自社についてしっかり調べているモチベーションの高い人材を採用したいと考えているため、ぜひ企業分析を徹底し、求める人物像に沿ったアピールをしましょう。
ツールを使ってみる
面接の回答をスムーズに作成するために、ツールを活用するのもおすすめの方法です。
AIを活用した面接対策ツールを使えば、実際の面接をシミュレーションしながら、適切な回答を作成できます。
よく聞かれる質問に対する回答を想定してくれるツールや、自分の話し方の癖を分析し、改善点を指摘してくれるツールもあります。
これらを活用すれば、より完成度の高い回答を準備することができ、本番の面接でも落ち着いて対応できるようになるでしょう。
以下の3記事ではガクチカ、自己PR、志望動機作成ツールについて紹介しているので、参考にしてみてください。
ガクチカ
自己PR
志望動機
まとめ
面接が苦手な方のために、なぜ面接が苦手なのかを言語化できるよう理由を分析した後、それぞれの原因別にどのような対策をすれば良いのかについて紹介しました。
面接は苦手な人の方が多いですが、残念ながらほとんどの企業において、選考では避けて通れない関門です。
ぜひ本記事で紹介した内容を踏まえ、苦手を克服し、本番では心に余裕を持って臨めるようになっておきましょう。